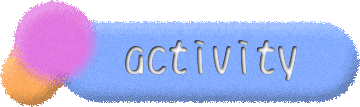
| ボランティア活動 |
|
| 「輝く未来へ!アイヌ民族」に参加して | 3年 W.Y |
|
去る三月三日、豊島区民センター文化ホールにおいて、「輝く未来へ!アイヌ民族」と題されたイベントが行なわれました。 このイベントは、北海道の先住民族であるアイヌに対する理解を、彼らの伝統芸能を通じて深めていこうという趣旨から、豊島区在住の社会人有志の方々が中心となって企画されました。そして、やるからには広く呼びかけた方がいいということで、同じ豊島区に所在する大学である立教大学、中でもボランティアに取り組んでいる団体であるYMCAに実行委員会への協力を依頼してきました。 当初私は、「YMCAを代表して彼らの話を聞きに行く」程度の軽い気持ちでした。しかし、結局、このイベントに実行委員会事務局メンバーとして参加し、企画立案段階から本番当日まで携わることとなってしまいました。 「なってしまった」などと書くと、悪いことのように読めますが、そうではありません。むしろ、色々な意味で良い勉強になったと思います。アイヌ民族に対する差別の歴史や彼らの置かれている現状といった知識面についてもさることながら、企画立案や人を集めることの難しさ、あるいは各方面との折衝といった、一つのイベントを立ち上げ、それを成功させるための実務的な事柄も学ぶことができ、良かったです。 私は法学部に在学しているのですが、今までは法律学一辺倒であったのが、このイベントをきっかけにして政治学の領域、殊に社会的弱者に対する差別の問題に関心が広がり、現在、それに関連したゼミに所属し、もっと深くアイヌの問題について学びたいと思っています。 因みに、一八八八(明治二一)年、アイヌ民族に読み書きを教える初めての学校「愛隣学校」を現在の登別市に創設したのは、立教大学設立の母体である聖公会のイギリス人宣教師ジョン=バチェラーでした。そして、彼の教え子のうち何人かは当時の立教大学神学部に入学し、卒業後キリスト教の伝道師として活躍されたそうです。些細なことですが、何か「見えざる力」のようなものを感じます。 また、このイベントを通じて、他大学の学生の方々と交流を持つことができたことも大きな収穫でした。個人的な意見ですが、今の立教YMCAは、あまり学外の団体、あるいは個人とは積極的に関わろうとしていないように思います。これはこの団体の短所でもあり、長所でもあるといえます。しかし、これからは内側ばかりではなく、外にも目を向けていかなければならない時代です。外部の人々と連携することにより、YMCAの活動の幅を広げていけたらと考えています。 |
|