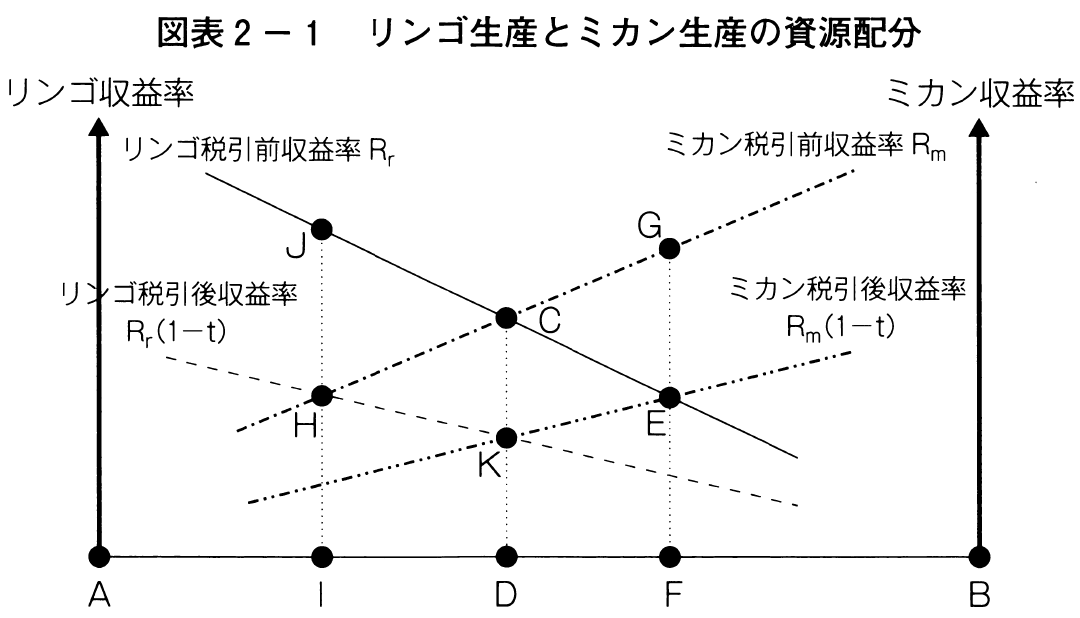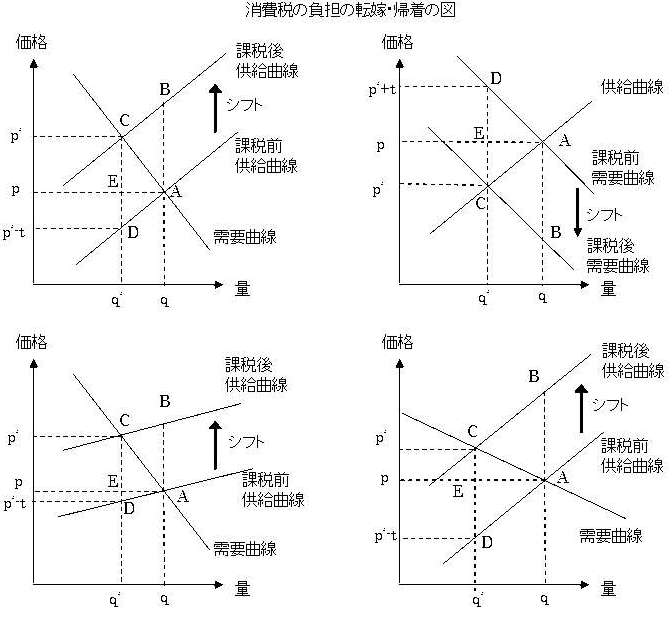����
2023youtube�b �e�N�x�Ő������b �Œ����\�b ���{�̓��v�b ���Œ�2025(�p)| �������v �p�b �����W����R7 | �����ƒm �p | �������S�� | �������Z���v����865 | �p���t���̍u�`�m�[�g�ŋ��ȏ��w�d�Ŗ@�T���x��⊮���Ă����B
�u[���]�`�`�v�Ƃ��������͎����ł������Ƃ͌���Ȃ��B(�]�k ��͐l�̂��߂Ȃ炸�Ɣ�vs.�O���[�v�w�K)
�d�Ŗ@�͂����ׂ��ɖ𗧂�(�Ƃ����̂͗������ɃA�s�[�����Ȃ��悤��)�B�i�@�����ł̕s�l�C(�I���Ȗ�8�Ȗڒ�6��)�B
�w���w�����w�ԈӋ`�́H(�S�����d�Ŏ����ƂɂȂ�킯�ł͂Ȃ� / �p�ɂɉ��肳���)
(1)�S�����Q�����҂ɂȂ�@���@�d�ł̌�����_�����b(�Ђ��Ă͐����ւ̈ӎ���)�B
(2)�l�I���{�̌���@���@�T�O����łȂ������̑���Œm��d�ʼn���e�N�j�b�N(���ۂɎg�����ł͂Ȃ�)�B
�{�u�`�͔���E����@�ډ��ɍS�炸�L���̕��j�B�ǂ��炩�Ƃ����ƕ��K�����B
���O�l�ܘZ������\���O�l�ܘZ������\���O�l�ܘZ������\���O�l�ܘZ������\���O�l�ܘZ������\
���ȏ��F��������Ғ��w�d�Ŗ@�T���x(4�ŁA�L��t�A2021) ����(�������)
���q�G�w�d�Ŗ@�x(24�ŁA�O�����A2021)(�P���Ƃ��Ă͍Ō�̉���)
���q�G��Ғ��w�P�[�X�u�b�N�d�Ŗ@�x(6�ŁA�O�����A2023)(�u��121.01�v���̓P�[�X�u�b�N�Ƃ̑Ή�)
�������E����nj[�w�d�Ŗ@����Z�@�x(6�ŁA�L��t�A2023)
����nj[�w�d�Ŗ@�����x(3�ŁA�L��t�A2023)
�����p���w�X�^���_�[�h�����Ŗ@�x(4�ŁA�O�����A2024)
�n�ӓO��w�X�^���_�[�h�@�l�Ŗ@�x(3�ŁA�O�����A2023)
�����p���E���R�R���w�X�^���_�[�h����Ŗ@�x(2�ŁA�O�����A2022)
���������ҁw�d�Ŕ���S�I�x(7�ŁA�L��t�A2021)
����nj[�E�{��T�q�w���ۑd�Ŗ@�x(4�ŁA������w�o�ʼn�A2019)
�ȏ�A�i�@�����őd�Ŗ@��I������҂Ɋ��߂�{�B�ȉ��A���发�A���ǖ{���B
���q�G���w�Ŗ@�����x(7�ŁA�L��t�A2016)
�O�؋`��Ғ��w�悭�킩��Ŗ@�����x(19�ŁA�L��t�A2025)
�����p���w�v���b�v�d�Ŗ@�x(4�ŁA�O�����A2021)
��ȏ͔@�E����M�q�w�d�Ŗ@�x(���{�]�_�ЁA2020)(link��ɒ�������)
��ȏ͔@�w�z�[�������E�{�[�����E���Ĕ���������ېł����̂��x(�����o�ώЁA2020)
��ȏ͔@�w�Ȃ������Њ�Ƃւ̉ېł͂܂܂Ȃ�Ȃ��̂��x(�����o�ώЁA2023)
�}���L���[(�����p�V����)�w�}���L���[�o�ϊw �T�~�N���ҁE�U�}�N���ҁx(���m�o�ϐV���)
�X�e�B�O���b�c(�����j�Y�E��)�w�����o�ϊw�@�㉺�x(���m�o�ϐV���)
�V���x��(�c���j��ѓc����)�w�@�ƌo�ϊw�x(���{�o�ϐV���o�ŎЁA2010)
�ő�u�{ (�����ŕ��ł���)�b������ �킪���̐Ő��̊T�v
�w�����Ŗ@�Z�@�@�@�ߕҁx(�V���{�@�K)�G�w�Ŗ��Z�@�@�@�ߕҁx(���傤����)
�����Ŗ@ �����Ŗ@�{�s�� �����Ŗ@�{�s�K�� �@�l�Ŗ@ �� �� �����Ŗ@ �� �� ����Ŗ@ �� �� �n���Ŗ@ �� �� �d�œ��ʑ[�u�@ �� �� ���Œʑ��@ �� �� ���Œ����@ �� �� �d�ŏ����{����@ ��
���̑��F��� | �d�ŏ��ꗗ | �Љ�ۏዦ�� | ��������ꗗ | �ʒB(�����Ŗ@��{�ʒB���̖@�߉��ߒʒB�̑��A�u���O�Љ�ɑ��镶���v��u���^��������v��������) | ���Œ��^�b�N�X�A���T�[ | �a�p�|��
1. �d�Ŗ@�̈ʒu�t��
1.1. �d�ł̊T�O�Ƃ��̗��j�I�w�i
1.2. ���@�Ƃ��Ă̑d�Ŗ@�Ǝ���@�Ƃ��Ă̑d�Ŗ@
1.3. �@�I���͂ƌo�ϕ��͂̓����\�\�d�Ő���Ƒd�Ŗ@
1.4. ���_�Ǝ����̗Z���ƁA�֘A�@����̓����I�l�@�̕K�v��
1.5. �܂Ƃ߁\�\�ېŖ��̓��F�Ƃ��Ă̑�����
���@�⏤�@�̍u�`�ƁA�����Ƃ̃Y��������B���Z�����Ƌ�C��R�̔�gct��F�����ɂ����Ė��@��͂Ƃ�����������͌��菳�F������ƕs���ɂȂ邱�Ƃ�����(4.2.3.5.)�B
2. �d�ł��߂��闧�@�E�s��
2.1. ���㍑�ƂƑd�Ő��x
2.1.1. ���㍑�Ƃɂ�����d��
2.1.1.1. ���{��`�o�ϑ̐��Ƒd��
2.1.1.2. �������ƂƑd��
2.1.1.3. �f���N���V�[�E�u���v�v�E�d��
1 �������̂��߂̎������B������(public goods)cu�c�c�T�^�͍��h�B�@�g�}�g�̏���ȂǂƂ̈Ⴂ�ɂ��āB
����(nonrivalrous)�F����������Ȃ��̂ŗ��p����l�������Ă��lj��I��p��������Ȃ��B
��r����(nonexcludable)�F���p����l����ߏo�����Ƃ�����ł���B
�@��
�������(free ride)���̔����B�s��̎��s�@���@���{�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
(���������{�̎��s�����邩������Ȃ��B�@���Ƃ����Ăm�o�n�E��c���g�D�ɔC�����邩�H)
2 (�����E�x��)�ĕ��z
�@���Ƃ���ҋ~�ς����Ȃ��Ƃ���A�Ďu�ƁE�@���{�ݓ��ɗ��邱�ƂƂȂ낤(�����́c��)�B
�@���������݂̌��@ 25���́u���N�ŕ����I�ȍŒ���x�̐����v��ۏႹ��Ƃ���B���ɗ���ȁA�Ƃ����N�w�E���l���f�͋c�_�̑Ώۂ��肤�邪�A���Ȃ��Ƃ����݂̂Ƃ�����{�l�͂��̂悤�ȉ��l���f�����Ă��Ȃ��B
�@�ނ��A�������͐G��Ȃ��B���@25���̓v���O�����K��B���@29���F���L���Y���Ƃْ̋�������B
�@�ĕ��z�͑d�łłȂ��Љ�ۏ�(social security�����ی��N����)���S���@�\�ł���A�Ƃ������������܌�������B[���]�������������͖��Ӗ����낤�B�d�łɂ���Љ�ۏ�ɂ���A���{�����s���Ă���Bcv
�@��ʘ_�Ƃ��������͎�҂̂���(�ĕ��z�̌����Ƃ���)�ł���B���Ł���҂����߂͕K�R�ł͂Ȃ��v����B
�@cf.�n�����(poverty trap)�c�n������̒E�p�̍���B�Œ���̐���������t����Ƃ���Ǝ҂̘J���ӗ~���j�Q�����(�ŗ�100%�Ɠ��������߁B���{��A�k�Ќ�̓��d�ɂ���Ў҂̐����ۏ�v�ł����ʂ�����)�B���Ƃ����ċ��t�����̂�����Bcf.�x�[�V�b�N�C���J���E���̏�����cw
3 �i�C�����c�i�C�ߔM���A���������㏸���A�ݐi�����Ő��̉��ŐŊz�������A�i�C��؊��A���������������A�ݐi�Ő��̉��ŐŊz������A�Ƃ��������i�C����(built-in stabilizer)�@�\������Bcf.��쑾�Y=����q��=�����呢�u�l�����ېł̎������艻�����v2024�N11���^24A-03�i�ʊ�375���jcx
4 ��������̈��i�c�Y�f�œ���bads tax��A�����x���p���ɂ��d�ŗD���[�u���T�^�B
�d�ł��ۂ����Ƃ̐���������
���v���E�Ή����c���ƌ_�����w�i�Ƃ��A�s�������Ƃ���闘�v�̑Ή��ƌ���l�����B���h���̌��������l������̗��O�͔ے肵����A����������������������̗��O�ƏՓ˂��鋰��B
�`�����E�]�����E�\�͐��c���Ƃ͓��R�ɉېŌ�������(���ГI���Ǝv�z)�A�����͓��R�ɔ[�ŋ`�����A�Ƃ���l�����B���Ƃ͍����̗��ւ̂��߂ɑ��݂���Ƃ������O�ƏՓ˂��鋰��Bdh
2.1.2. ���{�̑d�Ő��x�̌���
2.1.2.1. ���łƒn���Łi�n���ő��_�j�@�}�\2-1�@���ƒn���̐Ŏ��\��
COLUMN2-1 �n�����^�ŁE�n����t�ł́u�Łv���H
2.1.2.2. ���̐Ŏ��\���@�}�\2-2��ʉ�v�Ŏ����ځ@�}�\2-3�Γ��Ώo�\��
2.1.2.3. �Γ��\���\�\�u�d�ō��Ɓv�̌���
�Γ��̌��ˑ��������������߂��v���C�}���[�o�����X(primary balance�F��b�I�������x)�̋ύt(�ł��������)���I�c ���݂̎����ŁA����܂ł̎؋��̌��������ȊO�̎x�o�͘d����悤�ɂ��悤�i����̎؋��͉ߋ��̎؋��̕ԍς����ɂƂǂ߂�j�Ƃ������ƁB2.1.3. �ېŌ��̖@�I�\���Ƃ��Ă̑d�Ŗ@
2.1.3.1. ���Ƃ̉ېŌ��Ƃ��̖@�I����
�O���N�\�����E�Ŕ�����21�N10��29�����W63��8��1881�ŕS�I7��74(��COLUMN8-4)2.1.3.2. �c��̉ېŏ��F�Ƒd�Ŗ@���̈ʒu�t��
2.1.3.3. ���{�̑d�Ŗ@�̑̌n�Ɠ���
2.2. �d�Ŗ@�̒藧�ߒ�
2.2.1. ���@��̌���
���@14���F�����戵�����@���d�Ō�����`���@30���F�[�ŋ`��
���@83���F���������`�E��������S��`�@�������@�ɑ���������B
���@84���F�d�Ŗ@����`
���@94���F���������`
2.2.1.1. �d�Ŗ@����`
2.2.1.1.a �ېŗv���@����`
���@84���u���炽�ɑd�ł��ۂ��A���͌��s�̑d�ł�ύX����ɂ́A�@�����͖@���̒�߂�����ɂ�邱�Ƃ�K�v�Ƃ���B�v�c�c���@31��(�ߌY�@���`)�u���l���A�@���̒�߂�葱�ɂ��Ȃ���A���̐����Ⴕ���͎��R��D�͂�A���͂��̑��̌Y�����Ȃ����Ȃ��B�v�ƑΔ�
���������c��͍����ɂ�霓�ӓI�ېł�h�����߂Ɍ��ꂽ�B�@2�̎v�z�I��b�F�����`�E���R��`�B
(�Ԑ�) �����`�@���ېőΏێ҂̓��ӁB��\�Ȃ����ĉېłȂ��@(cf. Boston Tea Party����)dq
[���]�����ɂ͎Q�����̂Ȃ��҂ɉېł��邱�Ƃ�����(�����N�A�O���l��)�B�y�ېőΏێ҂̓��Ӂz�y����ȕ��S�z�͊ѓO����ĂȂ��B�s�����ȉېł��ۂ��A�Ƃ����ʂ̍l���v�f�ŕ⊮����������Ȃ��Ɛ�Ȃ͎v���B
���p���F�Q�����̂Ȃ��@�l�ɉېł��邱�Ƃ͈ጛ���H(cf.�n���c��)
�Œ莑�Y�Ŗ��`�l�ېŎ�`�����E�ő唻���a30�N3��23�����W9��3��336��dr�c�cX��A�ɏ��a26�N2��5���ɓy�n�̏��L�������n(10���A�ړ]�o�L)��������B�n���Ŗ@343���y��359����1��1�����݂̓y�n���L�҂Ƃ��ēo�^����Ă���҂�[�ŋ`���҂Ƃ��Ă��邱�Ƃ͌��@�Ɉᔽ���Ȃ��B
�ϔC���@(���@�{���s���{�ɈϔC���邱�Ƃ�������邩)����̓I�E�ʓI�łȂ���Ȃ�Ȃ��B
��ʓI�E�����I�ϔC�͈ጛ�E�����Bcf.�����p���u�d�Ŗ@���ɂ�閽�߂ւ̈ϔC�̎i�@�����̂�����\�\����ƕ]���v�w�d�Ŗ@����`�̑����I�����x11��(�t�B�i���V�����E���r���[129��)mz
| 5�Ł�123.02�H�c�s�������N�ی��Ŏ����E��䍂�H�c�x�����a57�N7��23���s�W33��7��1616��(6��18��) ���@84���̒n���ŁE�n���ŏ���`�Ɋւ��A�ېő��z�̒�ߕ��ɂ��ď��Ŋ���K�肳��Ă��Ȃ����߁A�ېŗv������`�ᔽ�Ɣ��f�B |
| 6�Ł�111.01����s�������N�ی���᎖���E�ő唻����18�N3��1�����W60��2��587��7��2df �������N�ی����̕ی����������O�ɖ��炩�ɂ���Ă��Ȃ����Ƃ͌��@84���ᔽ���ɂ��āA�������N�ی����ɂ��Ή���������(�u�����t�Ƃ��Ē��������v)�̂Łu���@84���̋K�肪�����ɓK�p����邱�Ƃ͂Ȃ��v(�A���������N�ی��ł̏ꍇ�ɂ́u�K�p�����v�Ƃ��q�ׂĂ���A�`���I)�B �������u�d�ňȊO�̌��ۂł����Ă��A���ے����̋����̓x�����Ȃǂ̓_�ɂ����đd�łɗގ����鐫����L������̂ɂ��ẮA���@84������|���y�ԁv�B |
| 6�Ł�112.02�葱�v���K��̈ϔC�̉� �����g�����o�^�Ƌ��Ōy������(�؍X�Ö؍ގ���)�E������������7�N11��28���s�W46��10=11��1046�� �@�o�^�Ƌ��ł̌y�����d�œ��ʑ[�u�@�ɒ�߂��Ă���A���̂��߂̎葱�v���i�m���̏ؖ����j���d���@�{�s�K��29���ɒ�߂��Ă����B�ŋ�������ĉߑ�ɔ[�t���Ă��܂����Ƃ��āA�[�ŎҁEX���s�������𗝗R�ɍ��z�̕Ԋ҂𐿋��B �@��R�F�m���̏ؖ����̓Y�t���葱�v���Ƃ��邱�Ƃ��@�̐��߂ւ̈ϔC�̒�߂���́A�ǂݎ�邱�Ƃ��ł��Ȃ��A�Ƃ���X�̐�����F�e�B�i�ېŒ��̒ʒm�̓K�@���Ɋւ��Ă͔F�߂Ă���j �@��R�F���̍T�i�����p�B�u���߈ȉ��̖@�߂ɈϔC���邱�Ƃ��������̂́c�d�Ŗ@����`�̖{���Ȃ�Ȃ����̂Ɍ�������̂Ƃ���˂Ȃ�Ȃ��B�v�u�������Ɏ葱�I�ȉېŗv�����߂�̂ł���A�葱�I�Ȏ������ېŗv���Ƃ��邱�Ǝ��͖̂@���ŋK�肵�A���̏�ʼnېŗv���ƂȂ�葱�̍זڂ߈ȉ��ɈϔC����Α����v�u���鎖�����ېŗv���Ƃ��Ēlj�����̂��ǂ����ɂ��Ė@���ɖ����̋K�肪�Ȃ��ꍇ�A�ʏ�͂��̎����͉ېŗv���ł͂Ȃ��Ɖ��߂��ׂ����̂ł���B�v�u�葱�I�������葱�I������L����ɂƂǂ߁A������ېŗv���Ƃ��Ȃ����@������c�v cf.�o�^�Ƌ��Ők�Г��᎖���E��㍂������12�N10��24�����^1068��171�� �@�n�k�̓���ɂ��o�^�Ƌ��ŖƏ��ɂ��āB����@�ɂ��ؖ����̓Y�t�Ƃ����葱���ӂ��A�ʏ�ʂ�[�߂Ă��܂����ŋ��ɂ��A�[�Ŏ҂͕s�������ԊҐ������𐿋��B �@��R�F�s�������ԊҐ��������ɂ��Ă͔F�e�B�i�ېŒ��̒ʒm�̓K�@���Ɋւ��Ă͔F�߂Ă���j �@��R�F����������A�������p�B�@�c���߈ȉ��ւ̈ϔC�́u��̓I�E�ʓI�ϔC�Ɍ�����̂ł���A��ʓI�E�����I�ϔC�͋�����Ȃ��v / �o�L�葱�ł͈��̏��ʂ̓Y�t��\�肵�Ă���A�����āA�ȗ߂͎葱�I�����̒�߂����u���Ȃ��̂��ʏ�B�u����@37��1���̑呠�ȗ߂ւ̈ϔC�́A��ʓI�E�����I�ɈϔC���������̂ł́v�Ȃ��B cf.�h�C�c�،������E�����n������27�N5��28���Ŗ��i����265������12671�E������������27�N12��2���Ŗ��i����265������12763�c�X�g�b�N�A���[�h�͈ꎞ�����E���n�����ł͂Ȃ����^�����ł���t�^��̂̓h�C�c�@�l�ł�����{�@�l�ł͂Ȃ������`���͂Ȃ��Ƃ��ꂽ����B�d�ŏ����{����@12���̈ϔC�����{�s�K��9����2�ɂ��͏o���̒�o�͑d�ŏ��̉��b���邽�߂̎葱�v���ł͂Ȃ��B |
2.2.1.1.b �ېŗv�����m��`
���R��`����̗v���@���@�\���\��(�܂��͖@�I���萫)�̊m���ېŌ��ʂ��\���ł��Ȃ���A������ޏk�����A�Ƃ��������B
���ȏ��I����������������l�@
(1)�d�Ŗ@�K���s���m���Ɩ{���Ɏ�����ޏk����̂��H
(2)������ޏk���邱�Ƃ̉��������̂��H
(1)�Ɋւ��z�������锽�_�\�\�����I�o�ϐl�͑S�Ẵ��X�N��D�荞��Ŏ�����̍s�������锤�ł���B�d�ŕ��S���s���m�ł����Ă��A���̃��X�N��D�荞��ō����I�o�ϐl�͍s�����锤�ł���c�c���H(cf. Knight�ɂ�郊�X�Nrisk�ƕs�m����uncertainty�Ƃ̋��)
�����̐l�����X�N����(risk averse)�@���@����ޏk�B
�ނ����ۂ̂Ƃ���K�肪�������̗̈�͏��Ȃ��炸����B�K������R�X�g���n���ɂł��Ȃ��Bdt
(2)�Ɋւ��A����͑��������悢�̂��H�c�c�����I����͎Љ������(welfare)����Ɏ�����(��F�ь�20��ۗL����`���Ɠ�5kg��ۗL����a���Ƃ̊Ԃ̎��)�B������ޏk����A�Љ�ɔ����������̌������Ȃ��Ȃ�B
�s�m��T�O�̋��e��bk�@(cf. rule vs. standard if) (cf.��COLUMN5-1�������)
�s�m��T�O���Q��ނɋ�ʁc�c�d�ōs�����Ɏ��R�ٗʂ�^���邩�ۂ��B���߂ɂ���Ė��m���ł��邩�ۂ��B
1�@���Y�K��̏I�ǖړI�≿�l�T�O����e�Ƃ���s�m��T�O(��:�u���v��K�v�̂���Ƃ��v)
2�@���ԖړI�Ȃ����o���T�O����e�Ƃ���s�m��T�O(��:������ЋK��ł̐ŕ��S���u�s���Ɍ���������v)
2.2.1.1.c ���@���̌���
�@���Œ�߂�ꂽ�ʂ�ېł��Ȃ���Ȃ炸�A�ېœ��ǂɂ͉ېł��d�������茸�Ƃ����肷���ٗ����F�߂��Ȃ��B�d�Ō�����`�̉����ŗ����B�a��(��3.2.4.5.)�⋦��͖����Ƃ������O(cf. ��s��)�Ɍ��т�(���A�����F��Ɋւ���a���͂��肤��Ƃ����c�_������)�Bcf.�����p���u�d�Ŗ@����`�Ƒd�Ō�����`�v���q�G�ҁw�d�Ŗ@�̊�{���x55�Łi�L��t�A2007�j
�M�`��(���͋֔���)(��3.1.4.)�ƏՓ˂���\��du
2.2.1.1.d �K���葱(due process)�̕ۏ�
�[�Ŏ҂��@�I�ɑ����]�n���m�ۂ���Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�d�ő��א��x(��3.2.)�̏[���B6�Ł�232.01�G�����ݓ|���s�������ԊҐ��������E�Ŕ����a49�N3��8�����W28��2��186��(cf.4.4.2.)
| �����n���ߘa3(�s�E)29��(���p)�E���������ߘa5�N6��30���ߘa5(�s�R)3��(���p)�E�Ŕ��ߘa6�N5��7���ߘa5(�s�c)334��(���p)(���J��C�j(�[�Ŏґ㗝�l)�E�Ŗ@�w590��125-142�ŁA���F���l�u�F�\�����F��������i�@�l�Ŗ@127��1���j�ɂ����Ď��O�̈ӌ��q�葱�͕K�v�Ƃ���Ȃ��Ƃ��ꂽ�����v�V�E������Watch�d�Ŗ@No.185 (2024.7.5)�A�R�c�N�j�u�F�\���̏��F�̎�������ɑ��鎖�O�̖h��̋@��̕t�^�ƌ��@31���v�V�E������Watch���@No.234 (2024.8.2)�A������ƁE�W�����X�g1610���d����6�N40-41��) |
| �Ŕ�����26�N12��12���W��248��165�ŕS�I6��99de�c�c���z�X����̑��z�X���̏ꍇ�A���ؐŁi��2.3.2.4.a�j�Ȃ�(�ō��ق̑d�Ŕ���Łu�t���v��p�������炭�B��̗�)(��28�������Œ�61��2���őΏ�)�B ���l�ɍt�����l�������Ɩڂ����(�A���t���Ƃ͌����ĂȂ�)��Ƃ��ď[���Ɋւ����Ŕ��ߘa3�N6��22�����W75��7��3124��fr(��ȏ͔@�u�ؔ[�����ɂ�����z�����̂����A��̌��z���ی���ɂ��z�����ɑ��݂��Ȃ��������ƂƂȂ�N�x���̏Z���łɏ[������Ă��������́A���̔N�x���̏Z���łɖ@��[�������v����鏑�W���[�i�������ԍ�HJ100129)(����̂Ō�ł悢)�B |
2.2.1.1.e �k�y���@�̋֎~
| 6�Ł�115.01�y�n���n�������v�ʎZ�ے莖���E�ňꏬ������23�N9��22�����W65��6��2756�ŕS�I7��3dx(�œ�����23�N9��30���W��237��519�ł����|�����⑫�ӌ����[�����Ă���jdz ����16�N3��26�����@�A4��1���{�s�B���N1��1���Ȍ�̓y�n���n�ɂ��đ��������v�ʎZ(����69��)�s�B ������(�����œ�)�ƈႢ���Ԑ�(�����œ�)�ɂ��Ċ��ԏI���O(�����łȂ�12��31���ȑO)�Ȃ��k�y�ې��̖��͐����Ȃ��A�Ƃ����������l�����Ȃ��ł͂Ȃ����A�����܂ł̂��Ƃ͂ǂ̍ٔ����������Ă��Ȃ��B���@39��(�k�y�����֎~)�̂悤�Ȗ����̋K��͂Ȃ����A���@84���͗\���\���E�@�I���萫���ۏႵ�Ă���ƍl�����Ă���B���������_�Ƃ��Ă͕���16�N�����ɂ��k�y�ېł�e�F(�������f)�B (1)���@29��1��(���Y���ۏ�)�Ɋւ����ő唻���a53�N7��12�����W32��5��946�ŕS�I���@7��I-99gj(�_�n�����Ή��ύX�͔_�n�������������̂̐N�Q�ł͂Ȃ�����)�Ɉˋ����Ă���(���Y���̓��e�ɑ��鎖��I�Ȑ���̋������/������Ȃ��͈̖͂��Ƃ��Ę_����)���ƁA�y�� (2)�哈�i��(����121.01)�Ɍ��y���Ă��Ȃ�����(�����R�͑哈�i�ׂɌ��y���Ă������A�哈�i�ׂ̌��@14��1���̖��Ɩ{���̌��@29��1���̖��͈Ⴄ�ƍō��ق͍l�����̂ł��낤)���|�C���g�B ���\��u�d�Ŗ@����`�Ɓw�k�y���@�x�v�w�d�Ŗ@����`�̑����I�����x61�ł͖���B�k�y���@�őd�ʼn����ׂ����ƂƁA�ٔ��������ߘ_�őd�ʼn����ׂ����ƂƁA�ǂ��炪�d�Ŗ@����`�ɓK���I���H���T��26��(���J���j)�u�k�y���@�̖���d�Ŗ@����`�Ɗ֘A�t���Ę_����ׂ��ł͂Ȃ��v�B ��㍂�����a52�N8��30������878��57��(���R�_�˒n�����a52�N2��24����23��3��572��)�c�c�y�n�ۗL�łɊւ���K��̎{�s���͏��a48�N7��1���ł���̂ɏ��a44�N1��1���Ȍ�Ɏ擾���ĕۗL����y�n�ɂ����K�p����Ƃ������Ƃ͈ጛ�ł͂Ȃ��B �k�y���ւ�����Ƃ������ꐶ�N����ގ����E�������ߔe�x�����a48�N10��31����19��13��220�Łc���i�ł̉ېőΏۂɌf�����Ă��Ȃ���������ނɂ��Ĕ[�t���ꂽ�Ŋz�̊ҕt��h�����Ƃ���@������F�߂Ȃ��Bdw |
2.2.1.1.f �d�Ŗ@�̉��ߌ���
��141.01�z�X�e�X��V�v�Z���Ԏ����E�Ŕ�����22�N3��2�����W64��2��420�ŕS�I7��13(��3.1.1.3.)�Ŕ�����27�N7��17������2279��16��gk�c�c�o�L��̕\�蕔�̏��L�җ��Ɂu�厚���v�ȂǂƋL�ڂ���Ă���y�n�ɂ��A�n���Ŗ@343��2����i�̗ސ��K�p�ɂ��A���Y�y�n�̏��݂���n��̏Z���ɂ��g�D����Ă��鎩����͒�����Y�y�n�̌Œ莑�Y�ł̔[�ŋ`���҂ɓ����邩(����)(cf.��3.1.1.2.)
2.2.1.2. �d�Ō�����`
2.2.1.2.a �������S����
�����I�����E�����I�����̋�ʂɗ��Ӂi4.1.1.2.�ŏڏq�jCOLUMN2-2 �哈�i���Ə����Ŗ@����
| ��6�Ł�121.01�d�ŗ��@�̈ጛ�R����@�哈�i��(�T�����[�}���ŋ��i��)�E�ő唻���a60�N3��27�����W39��2��247�ŕS�I7��1di ���_�F����(��w����)������dj����鋋�^�����ɂ��Ď��z�o��T��dk��F�߂Ȃ����̋K��̈ጛ���H �⑫�F�i�ׂ��N���ɂ����悤�ɂ��邽�߁A�������^�����T��(�T�Z�I�o��T���ƈʒu�Â�����)�͂��Ȃ�[�Ŏ҂ɊÂ��v����Ă���B�܂�A���ۂ̌o����^�����T���z�����邱�Ƃ͖w�ǂȂ�(���A�{���ł͎��z�o��̕����傫���ƌ����͎咣dl)�B(cf.���ԋ��^����) �����@���d�ł̒�`�E�@�\(2.2.2.�Q��) ���u�����E�o�ρE�Љ�����̍����S�ʂ���̑����I�Ȑ������f��K�v�Ƃ���v�u�ɂ߂Đ��Z�p�I�Ȕ��f��K�v�Ƃ���v ���u�������s�����v�ł��邱�Ƃ��u���炩�v�łȂ�����A���@�{�̔��f�Ɍ��o�����Ȃ��Bdn �����^�����҂̎��z�T��(�I�𐧂��܂�)�̎��s��̍���@���@��ʂ́u�ړI�͐�������L����vdm ���ړI�Ƃ̊֘A�ɂ����č�������L���邩�@�c�c���^�����҂́u�K�v�o��̊z����ʂɁc���^�����T���̊z��������̂ƔF�߂邱�Ƃ͍���v (�A���ɓ����ȕ⑫�ӌ��ɗ��Ӂc�c���z�o�������^�����T�����������ꍇ�A�ጛ�Ƃ���)�B �[�ŎҔs�i�ł�����̂̏��a62�����ւ̐����I�Ӌ`������57����2����x�o�T���̑n�݁B(��24����)��4.2.6.3. |
���@(����14��1��)�ᔽ�̑i�ׂ͖w�ǐ˂����Ă���B
�S���t���y�{�ݗ��p�Ŏ����E�Ŕ����a50�N2��6������760��30�Łc�c�S���t�����ɉېł��邱�Ƃ͈ጛ�ł͂Ȃ��B
�@���p�F���[�����ŁA�g�щ��y�Đ��@��(iPod��)�Ȃǂ�n�݂���Ƃ��āA����͍������H
�ޗnj������ό��ŏ�᎖��(���厛����)�E�ޗǒn�����a43�N7��17���s�W19��7��1221�Łc�c���厛�̓��ꗿ���ɉېł��邱�Ƃ͐M���̎��R�i���@20���j���Ɉᔽ���Ȃ��B
�@���p�F�@���c�̂�ƐłƂ��邱�Ƃ͈ጛ�̖�����N���邩�H�i�����ĒN�������K�i��L���邩�H�c�c�[�Ŏ҂ɊÂ����x�ɂ��đi�ׂƂȂ邱�Ƃ͋ɂ߂ċH�B���{�̌��@�i�ׂ̂�����̖��̈�j
�ǂԂ낭�ٔ��E�Ŕ��������N12��14���Y�W43��13��841��
��̖Ƌ������������E�Ŕ�����4�N12��15�����W46��9��2829�ŁA�Ŕ�����10�N7��16������1652��52�Łc��Ŗ@9��1���A10��11���͌��@22��1���Ɉᔽ���Ȃ��B�ł��ጛ���f�ɋ߂Â������̂̈�Ƃ�����B�ጛ�Ƃ���Ȃ���̘_���\���̃|�C���g�́H
�@���p�F�o���҂ɉېł��邱�Ƃ͈ڏZ�̎��R(���@22��)�Ɉᔽ���邩�H
�����s�������N�ی���᎖���E�����n������24�N5��23����23(�s�E)625������n������379��10�Łc�c�������N�ی��ł̎��Y���z�̊�b���y�n�E�Ɖ��Ɍ��肳��Ă��邱�Ƃ͑d�Ō�����`�ɏƂ炵���@14��1���ᔽ�ł͂Ȃ��B
������(�Ǖw�T��)�������c�����n���ߘa3�N5��27���ߘa��(�s�E)236���A�œ�����7�N12��15���Ŏ�214��765�ŕ���7(�s�c)163���Bcf.�����F���u�Ƒ��̂�����Ƒd�Łv���q�G�āw����d�Ŗ@�u��2�Ƒ��E�Љ�x3��(���{�]�_�ЁA2017)
�����s��s����᎖���E������������15�N1��30������1814��44�Łc���_�͒n���Ŗ@�ᔽ�����A���s�݂̂ɉېł��邱�Ƃ͒n���Ŗ@�ᔽ�łȂ��B���̌�a��(?)�B���@���f�͂Ȃ��Bdp
�k�y�K�p��2.2.1.1.e ��115.01
����̐����ړI�̂��߂ɁA�Ӑ}�I�ɍ��ʓI�ȑd�Ŗ@������邱�Ƃ��������Ȃ��B�ጛ���f�͖ő��ɂȂ���ɁA���������i�ׂő��_�Ƃ��邱�Ƃ����(��O:�喴�c�s��2.2.1.3.a)�B����ł����@�_�Ƃ��āA�����̖�舽���͍��ʓI�����̍����I���R�̗L���̖����c�_����]�n�͂��낤�B
2.2.1.2.b �����戵����
| �����n���ߘa2�N10��9������30(�s�E)338���F�e�c�s�X�n�_�n�̑����Ŗ@��̕]���ɂ��āu�]���ʒB�ɂ�����ʂ̎���v����Ƃ��Ĕ[�Ŏ҂̐�����F�e��������B�u�]���ʒB�ɂ�����ʂ̎���̑����Ȃ�����C�����J�n���ɂ����铖�Y�s���Y�̋q�ϓI�Ȍ������l�Ƃ��Ă̓K���Ȏ�����������̂ł͂Ȃ��Ɛ��F����v�B�u�������C�{���y�n���n�ɓ]�p����̂ɁC�]���ʒB�S�O�|�Q��Q�S�|�S�̒�߂��z�肷����x�����������n������i���z��@��̓��H�܂ŒʘH���J�݂���̂ɕK�v�Ȕ�p���܂ށB�j��v����悤�ȏꍇ�ɂ́C�]���ʒB�ɂ�����ʂ̎������v�B |
| 6�Ł�441.01�����̕]�����@�@�}���V�����]������(�^���}�������ƌĂ�邱�Ƃ����邪�W�����̓^���}���ł͂Ȃ�)�E�Ŕ��ߘa4�N4��19�����W76��4��411��ds�i���R���������ߘa2�N6��24���ߘa��(�s�R)239���A���X�R�����n���ߘa���N8��27������1583��40�ŕ���29(�s�E)539���j�i�A�؏���E�W�����X�g1555��139�ŁA��ȏ͔@�E�����@�G��159��2��230�Łj(��COLUMN7-1�y�n�̕]��) �@�����A�}���V�����̒ʒB�]���z�͔������ቿ�z��1/4���ł������B�푊���l����6���~�̍��Y�������Ď��ɂ����ł������Ƃ���A�푊���l����10���~���؋����Ė�14���~(�ʒB�]���z�͖�4���~)�̃}���V�������w�����A���S�����B�����Ŕ[�łɍۂ��A�}���V������4���~�A�؋���10���~�A�����}�C�i�X6���~�ŁA���X�L���Ă����ϋɍ��Y(6���~)��ł������A�����ł̕��S��������悤�Ƃ����B ���|�F�u�d�Ŗ@��̈�ʌ����Ƃ��Ă̕��������́A�d�Ŗ@�̓K�p�Ɋւ��A���l�̏ɂ�����͓̂��l�Ɏ�舵���邱�Ƃ�v��������̂Ɖ������B�����āA�]���ʒB�͑������Y�̉��z�̕]���̈�ʓI�ȕ��@���߂����̂ł���A�ېŒ�������ɏ]���ĉ��I�ɕ]�����s���Ă��邱�Ƃ͌��m�̎����ł��邩��A�ېŒ����A����̎҂̑������Y�̉��z�ɂ��Ă̂ݕ]���ʒB�m���Y�]����{�ʒB��7.1.11�n�̒�߂���@�ɂ��]���������z�����鉿�z�ɂ����̂Ƃ��邱�Ƃ́A���Ƃ����Y���z���q�ϓI�Ȍ������l�Ƃ��Ă̎���������Ȃ��Ƃ��Ă��A�����I�ȗ��R���Ȃ�����A��L�̕��������Ɉᔽ������̂Ƃ��Ĉ�@�Ƃ����ׂ��ł���B�����Ƃ��A��L�ɏq�ׂ��Ƃ���ɏƂ点�A�����ł̉ېʼn��i�ɎZ���������Y�̉��z�ɂ��āA�]���ʒB�̒�߂���@�ɂ����I�ȕ]�����s�����Ƃ������I�ȑd�ŕ��S�̌����ɔ�����Ƃ����ׂ��������ꍇ�ɂ́A�����I�ȗ��R������ƔF�߂��邩��A���Y���Y�̉��z��]���ʒB�̒�߂���@�ɂ��]���������z�����鉿�z�ɂ����̂Ƃ��邱�Ƃ���L�̕��������Ɉᔽ������̂ł͂Ȃ��Ɖ�����̂������ł���B�v �ޗ�F�}���V�����삯���ݎ擾�����E�����n������4�N3��11������1416��73�ŁB �ޗ�F������������5�N3��15���s�W44��3��213�ŕS�I4��78(���R�����n������4�N7��29���s�W43��6=7��999��)�c�c�������Y�̕]���������ȉ��ł����̑����l�ƈقȂ�]�����@�ɂ��ꍇ�͈�@�ƂȂ肤�邪�A���̎��Ă͔푊���l���؋������ēy�n���w����������ł���A�����ŕ��S�y���ړI�ł���̂ŁA���Y�]����{�ʒB�ɂ�炸�擾���z���Ȃĕ]�����邱�Ƃ͋������Ƃ�������i�T��4��29�łɁu�Œ莑�Y�Łv�Ƃ��邪�A�����Ŗ@�Ɋւ��鎖�Ăł��邱�Ƃɗ��Ӂj�B �ޗ�F�����n������5�N2��16�����^845��240�ŕ���28(�s�E)92���E������������5�N12��21������5(�s�R)35�� ������3�N�������@�c�c���a63�N12�������ɂ�鋌�d��69����4�́A�����J�n�O3�N�ȓ��Ɏ擾�����y�n�������̕]���z�͎擾���z���ȂĂ���Ƃ��Ă����B���̋K��́u���@�ᔽ(���Y���̐N�Q)�̋^�����ɂ߂ċ����v(���n������7�N10��17���s�W46��10=11��942��)�ƕ]����A����8�N�ɔp�~���ꂽ(�̂���㍂������10�N4��14����45��6��1112�łŒn�ٔ����͎�����ꂽ)�B �����戵�����ƌŒ莑�Y�łƂ̊W�ł͎��̔��Ⴊ�d�v�i�����A���|�͕K�����������戵�����ɏd�_�������Ă͂��Ȃ��B�j�c�c�ԕԒc�n�����E�Ŕ�����25�N7��12�����W67��6��1255�ŕS�I7��98go(���n�~�E�W�����X�g1465��91�ŁA���E�@������67��12��221�ŁA���앐�u�E��������90��5��132��)�c�c(�A)�o�^���i������������Έ�@�B(�C)�o�^���i���Œ莑�Y�]����i�ʒB�ł͂Ȃ��B�n���Ŗ@388��1���������ɖ@���ɋ߂����͂��F�߂���j�ɂ��]��������Ύ����������ĂȂ��Ă���@�B(�E)���ʂȎ���Ȃ�����]����ɂ��]���͎����������ĂȂ��Ɛ��F�����B(�G)�o�^���i���@�]����ɂ��]�������鎞��(�C)�Ƃ��Ĉ�@�A�A(�E)�̐��F���y�����������鎞��(�A)�Ƃ��Ĉ�@�B �� ���쎖���E�Ŕ�����15�N6��26�����W57��6��723�ŕ���10(�s�R)41���S�I7��97ht�c�c�u�y�n�ېő䒠���ɓo�^���ꂽ���i�����ۊ����ɂ����铖�Y�y�n�̋q�ϓI�Ȍ������l������C���Y���i�̌���͈�@�v�B����͑O�L(�A)�ɑ�������B���̔��Ⴉ��́A����������肳������A�o�^���i���Œ莑�Y�]����ɂ��]���������Ă��Ă���@�ƂȂ�Ȃ����A�s�����ł������B�O�L(�C)�ɂ���@�ƂȂ邱�Ƃ����炩�ɂȂ����B cf.���ւ��\��}���V�������^�����E������������27�N12��17����62��8��1404�ŕS�I7��86�c�c���ւ��O�̃}���V�����̕����̔������ቿ�z���ʒB�]���z���Ⴍ���ւ���̃}���V�����̕����̔������ቿ�z���ʒB�]���z��荂����������B�}���V�������ւ��������ɑ��^���Ȃ��ꂽ�ꍇ�̑��^���̎��������ېŒ��咣�z�i�ʒB�]���z�j�������Ă��邩�����ƂȂ����B(���_�͐������p)�c�c�����ő��^�łƍ��Y�]����{�ʒB�Ƃ̊W�ɂ��Ă��Ŕ�����22�N7��16���W��234��263��do�i�Вc�����Ö@�l���Ј��ގЎ��̏o���̕��߂����̑ΏۂY�@�l�̈ꕔ�̍��Y�Ɍ��肷��|��芼�Œ�߂Ă���ꍇ�ɂ����āA���^�ł̉ېłɓ����蓖�Y�@�l�̍��Y�S�̂���b�Ƃ��ē��Y�o����]�����邱�Ƃɍ�����������Ɣ��f��������Bcf.����G���u���������Ö@�l�o�������̕]���v�_��T�V�E���c�F�h�җ�w���@�w�̊g����x337-352�Łj�����p����邱�Ƃ������B���̎��A�Óc�C�I�E�{�����F�⑫�ӌ��͉ېł̌������̊m�ۂƂ����ϓ_���d�����Ă����B���̗���ɉ����āA�}���V�����̑��^�łɊւ���]���Ɋւ��铌���n������25�N12��13���Ŏ�263������12354�������戵�������d�����Ă������A���̍T�i�R�E������������27�N12��17������2282��22�ł͊����ĕ����戵�����Ɋւ����R�̔���������Ă����i���Y�]����{�ʒB�ɐ��F����F�߂�X���ɑ����͔��c��ȏ͔@�E�W�����X�g1506��119-122�Łj�B |
| �I�I�m�����E�����n���ߘa6�N1��18���ߘa3(�s�E)22��(�F�e)(�d�K�E�Ō�235��93-98�ŁA�R�������q�E�d�ői��17��73-96��{�[�Ŏґ��㗝�l}�A�����O�E�d�ői��17��173-210�ŁA�⊪���]�u�����łɂ��ĂȂ��ꂽ�X�����������������ᔽ�ł���Ɣ��f���ꂽ�����v�V�E������Watch�d�Ŗ@No.193 2025.3.28)�E���������ߘa6�N8��28���ߘa6(�s�R)36�����p(�g���Y2025�N4��4���d�Ŕ��ጤ����A�q���q���E�W�����X�g1610���d����6�N156-157��) �@�����@�{���푊���l�d�̖{�������ɂ�茴����i�����`�E�����a�B�ǂ�����d�̎q�B�d�̍Ȃf���{�������̑����l�ł��邪�����ł͂Ȃ��j���擾�������Y�i���Ёo�]���ʒB178�p����I�I�m�Ёo�d����\������B�Ȃf���č����p�̊����o��Ж@2��17�����n���������B�]���ʒB168:�������̂Ȃ������p�j�̕]���ɂ��āB �@����26�N1��16�� �{���푊���l�d���I�I�m�����p�E���{��g��O��Ƃ���閧�ێ��_����o�C�^���l�b�g�Ђƒ��������B �@����26�N5��29�� �d�ƃo�C�^���l�b�g�Ђ��I�I�m�����n�Ɍ������{����{���ӂ���������B63��0408���~(10��5068�~/��)�B �@����26�N6��11�� �d���S�B �@����26�N7��8�� �{�������l��̈�Y�������c�B �@�@�����O ���v6�����B�d��2��1400���B�f��1��3000���B�`��3600���B�a��3600���B�`�̕v��200���B�`�̎q��600���B���W�҂����v1��7600���B �@�@������ �f��1��0700���擾�B�`��5350���擾�B�a��5350���擾�B�m���炭�@�葊�����ʂ�n �@�@�f���o�C�^���l�b�g�ЂɃI�I�m��6���������n����O��ŁA�`�E�a���e�X8950�����f��9��4035��8600�~(10��5068�~/��)�ŏ��n����B �@����26�N7��14�� �{����{���ӂɉ����Ăf���o�C�^���l�b�g�Ђ�6������63��0408���~(10��5068�~/���c�u�{�����p���i�v)�ŏ��n�����B �@����27�N2��27�� �{�������l�炪�I�I�m��1��������8186�~�i�]���ʒB180:�ގ��Ǝ�䏀���z�j�i8186�~�~2��1400����1��7518��0400�~�j�̑O��ő����ł̐\���������B �@����30�N8��7�� �����s����������k�Ŗ��������]���ʒB6�Ɋ�Â��������1��������8��0373�~�i�u�{���Z��z�v�j�i��������Ђj�o�l�f�e�`�r���쐬�����Z����̕��ϒl17��2000���~�Ɋ�Â��j�̑O��ōX���������������B�m�y�n�̕]�����͏ȗ��n ���_1:�{������������]���ʒB6�ɂ��]�����邱�Ƃ̓K�� ���_2:�����s�������]���ʒB6�Ɋ�Â��]�������{�����������̉��z�̓K�� ���_3:�ߏ��\�����Z�ł̕��ۂɂ��č��Œʑ��@65��4���m��:5��1���n�ɋK�肷��u�����ȗ��R�v�̑��� �@��R���|�@�u���ٔ����́A�����s�������{�����������ɂ��A�]���ʒB�P�W�O�̒�߂���@�ɂ��]���z�i�ގ��Ǝ�䏀���z�j�ƈقȂ鉿�z���Z�o���Č�����ɑ��Ė{���e�X�����������s�������Ƃ͈�@�ł���i���_�i�P�j�j�A������̎�ʓI�����͔F�e���ׂ����̂Ɣ��f����B�v �@�u�A�@�����Ŗ@�Q�Q���́A�������ɂ��擾�������Y�̉��z�Y���Y�̎擾�̎��ɂ����鎞���ɂ��Ƃ��邪�A�����ɂ��������Ƃ͓��Y���Y�̋q�ϓI�Ȍ������l���������̂Ɖ������B�����āA�]���ʒB�́A��L�̈Ӗ��ɂ����鎞���̕]�����@���߂����̂ł��邪�A�㋉�s���@�ւ������s���@�ւ̐E�������̍s�g���w�����邽�߂ɔ������ʒB�ɂ������A���ꂪ�����ɑ����ڂ̖@�I���͂�L����Ƃ����ׂ������͌�������Ȃ��B��������ƁA�����ł̉ېʼn��i�ɎZ���������Y�̉��z�́A���Y���Y�̎擾�̎��ɂ�����q�ϓI�Ȍ������l�Ƃ��Ă̎���������Ȃ�����A�����Ɉᔽ������̂ł͂Ȃ��A���̂��Ƃ́A���Y���z���]���ʒB�̒�߂���@�i�]���ʒB�̂����]���ʒB�U�ȊO�̒�߂Ɋ�Â��������Y�]���Ɋւ���ʏ�̕��@�������B�ȉ������B�j�ɂ��]���������z�����邩�ۂ��ɂ���Ă͍��E����Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���B�v �@�u�C�@�����A�d�Ŗ@��̈�ʌ����Ƃ��Ă̕��������́A�d�Ŗ@�̓K�p�Ɋւ��A���l�̏ɂ�����͓̂��l�Ɏ�舵���邱�Ƃ�v��������̂Ɖ������B�����āA�]���ʒB�͑������Y�̉��z�̕]���̈�ʓI�ȕ��@���߂����̂ł���A�ېŒ�������ɏ]���ĉ��I�ɕ]�����s���Ă��邱�Ƃ͌��m�̎����ł��邩��A�ېŒ����A����̎҂̑������Y�̉��z�ɂ��Ă̂ݕ]���ʒB�̒�߂���@�ɂ��]���������z�����鉿�z�ɂ����̂Ƃ��邱�Ƃ́A���Ƃ����Y���z���q�ϓI�Ȍ������l�Ƃ��Ă̎���������Ȃ��Ƃ��Ă��A�����I�ȗ��R���Ȃ�����A��L�̕��������Ɉᔽ������̂Ƃ��Ĉ�@�Ƃ����ׂ��ł���B�����Ƃ��A��L�ɏq�ׂ��Ƃ���ɏƂ点�A�����ł̉ېʼn��i�ɎZ���������Y�̉��z�ɂ��āA�]���ʒB�̒�߂���@�ɂ����I�ȕ]�����s�����Ƃ������I�ȑd�ŕ��S�̌����ɔ�����Ƃ����ׂ��������ꍇ�ɂ́A�����I�ȗ��R������ƔF�߂��邩��A���Y���Y�̉��z��]���ʒB�̒�߂���@�ɂ��]���������z�����鉿�z�ɂ����̂Ƃ��邱�Ƃ���L�̕��������Ɉᔽ������̂ł͂Ȃ��Ɖ�����̂������ł���B �@ �@�u�����J�n����ɑ������Y�̈ꕔ�����z�Ŕ��p���邱�Ƃ��ł����Ƃ��Ă��A���̎����ɒ��ڂ��đ����ېł����Ȃ���Α��̔[�Ŏ҂Ƃ̊Ԃőd�ŕ��S�Ɋʼn߂���s�ύt������Ƃ͕K�������f�����Ȃ��B�v �@�u�{�������J�n�ɂ���Ė{�����������̔���������߂�\�������������Ƃ�����������i���Q�O�j�̂ł����āA�{����{���ӂ��{�������̌���{�������l��Ƃ̊Ԃł��̂܂ܑ������邩�ۂ����́A�{�������J�n���ɂ����Ă͕s�����ȏł������Ƃ��킴��Ȃ��B�Ȃ��A��L�̓_�ɉ����A�{����{���ӂ����n�\�艿�i���ɂ��Ė{���푊���l�y�уo�C�^���l�b�g�Ђ�@�I�ɍS��������̂ł͂Ȃ��Ƃ��Ă����_��{���푊���l�ɂ����ăI�I�m�Њ����̑S�������܂Ƃߖ��͔����W�߂邱�Ƃ��O������Ƃ���Ă����_�i�O���i�R�j�E�j�ȂǂɊӂ݂�A���n�\�艿�i�ɂ��{�����������̔���������𑊑����Y�Ɠ������邱�Ƃ�����ł���B�v �@�u�{���ɂ����ē��i�̎���͂Ȃ����̂Ƃ����ق��͂Ȃ�����A�{�����������̉��z�ɂ��Ă͖{���ʒB�]���z�ɂ���ĕ]�����ׂ��ł���A�]���ʒB�U��K�p���Ė{���Z��z��p���Ė{������������]�������{���e�X���������́A�ō��ٗߘa�S�N�����̎��������f�g�g�݂ɏƂ炵�A���������Ƃ����ϓ_�����@�ł���B�v �@��R���|�@�u���ʓI�ɁA���I�]���ɂ��������l�ƕ]���ʒB�P�W�O�ɒ�߂�ގ��Ǝ�䏀���z�Ƃ̂������̒��x���������Ɣ��肳�ꂽ�ꍇ�ɂ����Ă��ς��Ȃ��̂ł����āA�{�����������ɂ��āA���n�\�艿�i�i�P�O���T�O�U�W�~�j�Ɩ{���Z��z�i�W���O�R�V�R�~�j����r�I�߂��A����炪�{���ʒB�]���z�i�W�P�W�U�~�j�Ƒ傫�����������Ă��邩��Ƃ����āA�X�������̎��_�ɂ����̂ڂ��āA���n�\�艿�i���������l�f�������̂ł���Ƃ��āA�]���ʒB�̒�߂���@�ɂ����I�ȕ]�����s�����Ƃ������I�ȑd�ŕ��S�̌����ɔ�����Ƃ����ׂ�����i���i�̎���j�����݂��Ă����Ƃ������Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��B�v �@�u�]���ʒB�U�̓K�p�ɓ�����A��L�������̗L���������ɔ��f���邽�߂ɂ́A���̑����Č����܂߁A�������̂Ȃ��������̑��s�ꐫ�̂Ȃ��������Y�̑S�Ăɂ��āA���I�]�����s���ׂ��ł����āA�����I�ȗ��R���Ȃ��̂ɁA����̑������Y�݂̂ɂ��Đ��I�]�����s���A�������ɂ��ĉېŏ������s�����Ƃ́A���������ɔ�����v�B �@�u��L�ō��ٔ����m�_�n���告�������E�Ŕ����a61�N12��5����33��8��2149�Łn�́A�c�c�����_�����������Ă��Ȃ��ꍇ�Ƃ͖��炩�ɏ��قɂ���v�B �@�u�ō��ٗߘa�S�N�����́A�]���ʒB�U�̓K�p�̗L���ɓ�����A�푊���l���A�����ł̕��S���������͖Ƃꂳ����s�ׂ��������Ƃ��l�����Ă���Ƃ���A�c�c�{���푊���l���͔�T�i�l�炪�A�����ł̕��S�������A���͖Ƃꂳ����s�ׂ������ƔF�߂邱�Ƃ��ł��Ȃ��ȏ�A�{���푊���l���͔�T�i�l��̍s�ׂɒ��ڂ����ꍇ�ɁA���̔[�Ŏ҂Ƃ̊W�ŕs�����ł���Ɣ��f����]�n�͂Ȃ��B�v |
��122.01�X�R�b�`���C�g����(��2.2.4.1.)
2.2.1.2.c ���ߓK�p�̎w�j�Ƃ��Ă̌������S�����H
�h�C�c�ɂ��̂悤�ȋc�_�����邪���{�ł͎x������Ă��Ȃ��B2.2.1.3. ���������`
�_�ސ쌧�Վ������ƐŎ����E�Ŕ�����25�N3��21�����W67��3��438�ŕS�I7��7gw�c�_�ސ쌧�̗Վ������Ɛŏ��i�@�l�Ŗ@��̌������̌J�z�ɂ��ېŏ������Ȃ��Ƃ��ꂽ�������ېőΏۂƂ���n���Łj����@�ł���Ƃ��āA�����U�����Ԃ��[�t�����S�z19���~�]��̕Ԋ҂����ɋ��ߔF�e���ꂽ����B���@92�E94���Q�ƁB�n�������c�̂ɂ͌��@��ېŎ��匠������B
�Ő��E����������n�������ɂ��A���̂悤�Ȓ����Z�����l������B
���e�n���̎���ɑ��������ߍׂ��ȐŐ����\�z�ł���B
���d�ŋ���(���ł̓��[)���Ő��E������������(�d�G�v���△�ʂȍ����x�o�����ɂ����Ȃ铙)�B
������ɐŐ��������ƁA��X�̐Ő����ł��ĐŐ������G������B
���Z�ޒn��ɂ���Ē������ŕ��S���قȂ邱�ƂɂȂ�s�����g��̋���B
�����n��Z���ɑd�ŕ��S��]�ł��悤�Ƃ����d�ŗA�o�̋���B
����ւ̋���(�ŗ���������)����Ґ؎̂Ă�����B
�i�����O���s��(����)������ł̒n���ʼn����咣�������Ƃɂ��Ē����Z���܂��x���E�s�x�����l���Ăق����BCf.�y����N�u�u����ł̒n���ʼn��v���Ȃ炱���l����v2012.4.9�j
2.2.1.3.a �n���ł̉ېō���
�喴�c�s�d�C�ői���E�����n�����a55�N6��5����26��9��1572�ŕS�I7��8�c�n���Ŗ@�ɂ����̗p�r�ɋ������d�C�܂��̓K�X����ېłƂ���Ă����Ƃ���A�喴�c�s�͎s�ŏ��ɂ��d�C�K�X�ł��ۂ������̂ɐŎ��s���������Ă��܂��Ă���A���i�퍐�j�ɂ��ېŌ��̐N�Q�ł���Ƃ��č��Ɣ����@1��1���Ɋ�Â����Q�����𐿋���������(�������p)�B��111.01����s�������N�ی���᎖���E�ő唻����18�N3��1�����W60��2��587�ŕS�I7��2
�n���Ŗ@�Řg���͂߂��Ă���(�g�@�E�����@)�B
�n���ł̕��ے����͒n���ŏ��ɍ����t�����˂Ȃ�Ȃ��c�c�n���ŏ���`�B
2.2.1.3.b �n���Ŗ@�ɂ�鎩��ېŌ��̐���
2.2.1.3.c �֗^�̖@���`
��s�ӂ邳�Ɣ[�Ŏ����E�ŎO�����ߘa2�N6��30�����W74��4��800��hx�c������b�̕s�w��̈�@�E������F�߂�����B2.2.2. �u�d�Łv�̖@�I��`
�u���Ƃ��A���ʂ̋��t�ɑ��锽���t�Ƃ��Ăł͂Ȃ��A�����T�[�r�X����邽�߂̎����B����ړI�ŁA�@���̒�߂Ɋ�Â��Ď��l�ɉۂ�����K���t�vcy(�A)�d�ł����v��(�������B�ړI)
�@�����E�ȗ����ƈقȂ�B�������B�ȊO�̖ړI(�Ⴆ�Ί�)�ł����Ă��A�������B�����ړI�̈�Ƃ��Ă���A�d�łł���Bcf.�E�l�}�~�ł͐ł��H
(�C)�d�ł���Ή���
�@�e��g�p���E�萔���E���������Ƌ�ʁB��v�ҕ��S�I���i�̋����łƂ̋��E�͞B���B��111.01����s�������N�ی���᎖���E�ő唻����18�N3��1�����W60��2��587�ŕS�I7��2(��2.2.1.1.a)
(�E)�d�ł���ʐ�
�@���S���ƁA��ʁB�������A��v�ҕ��S���I���i�̋����ł�����B���H������������ł̕����ړI�ʼn����̎g�r�������ʍ��������]�܂����Ƃ����̂������w�̒���Bdb
�@�܂��A����̎҂݂̂ɑd�ł��ۂ�����(������_�������ې�)�͋�����Ȃ��Bcf.���l�s�̔n���ŁBdc
(�G)�d�ł����͐�(������)
�@���̎��Ǝ����ȂǂƈقȂ�(cf.�Ζ�)�B�ېőΏێ҂̓��ӂȂ����ĉېłł���Bcf.��s�Ł�COLUMN2-2�@cf.�K�[���W�[�������E�Ŕ�����21�N12��3�����W63��10��2283��(��COLUMN8-7)
(�I)���K���t�@(���[dd�͑����łȂǂŗ�O�I)
�@���[�ɂ́A�[�Ŏ҂̎��R�������I�����z�����Q������x���Ⴂ�A�Ƃ��������b�g������B
COLUMN2-3 �u�d�Łv�̖{���I�v�f�́u�������v���H
2.2.3. �d�Ő����̌���
COLUMN2-4 �o�ϊw�I�m���̗L�p���\�\�َ��̐�(implicit tax)��f�ނ�
2.2.4. �d�Ŗ@�̑��`��
2.2.4.1. �d�Ŗ@�̖@��
(a)���@(b)�@��
(c)���߁i���߁F�����Ŗ@�{�s�߁A�ȗ߁F�����Ŗ@�{�s�K���j
(d)�����c��F����78��2��2���B�Œ莑�Y�]����ɂ��Ă͒�����`���B
���{�s�Z�b�����E�Ŕ�����21�N6��5���W��231��57��is(���{�[��E�W�����X�g1427��169��)�c�c�s�X�����_�n�̑�n���ݕ]���i�_�n�͒Ⴍ�]������邪��n�ɓ]�p�ł���y�n�͍��l�Ŕ���ꂤ��̂ő�n���݂ɕ]�����邱�Ɓj�ɂ��A�s�X�����Ƃ��Ă̎��Ԃ�L���ĂȂ��Ƃ��Ďs���̎咣��˂������R�ɑ��A���R��j�����A�s�X�����_�n�̉��i��K�ɎZ�肷�邱�Ƃ̂ł��Ȃ����ʂ̎���̑��ۂɂ��č��߂�������B�Ȃ��l�����E�d��H25�A58-59�ł͌��ւ��\��}���V�������^�����E�Ŕ�����25�N7��12�����W67��6��1255��(��2.2.1.2.b)�ɂ��āB
(e)���E�K��
(f)���ۖ@���i�d�ŏ�j�c�c���@98��2���F���@����၄�@������������
(g)����
(h)�ʒB(�@�߉��ߒʒB)�c�@���ł͂Ȃ����@�I�Ɂu���v�ł��Ȃ��B�ߏ��\�����Z�Łu�����̗��R�v�̘_�_���B�댹(�^�L�Q��)�����E�Ŕ��ߘa2�N3��24������2467��3�ł͌�q(��4.2.3.5.)
| 6�Ł�130.01�s�����@�@�p�`���R���V�펖���E�Ŕ����a33�N3��28�����W12��4��624�ŕS�I7��6ek ���a26�N�ʒB�����ɂ��p�`���R���V�킪���i�ł̉ېőΏۂ̈�ł���V�Y��Ɋ܂܂��Ƃ��ĉېł��n�܂������Ƃɂ��A�ېŏ����͓K�@�Ƃ��ꂽ�B �����ʒB�ې�(�ʒB���ېł̍����Ƃ��邱��)�̐���͔�ł���B ���O�_�c�@�K�͂̑n��(���@)�Ɣ���(����)�Ƃ̈Ⴂ�B �p�`���R��ېłƂ������K�@(�s�����@�c�ɘa�ʒB�Ƃ̊W��M�`��(��3.1.4.)�Ƃ̊W)(��140.01�d�Ŗ@�̖@�� ���q�G�_��)���������Ă������H ���ɉߋ��̔N�x�ɂ��Ă��ېŏ�����łƂ��Ƃ�����H�k�y�K�p��������Ȃ��A�ƂȂ邩�Hel|em|en|eo �a�J��O�u���Y�]���Ɋւ�����q���Ƃ��̓W�J�v���Ō��_�W86��79-91�ŁA����85�ł́u�ٔ������ʂ̎����ɂ����Ĕ[�Ŏ҂��~�ς��悤�Ƃ���Ƃ��ɂ́A���̓_�m�s�����@�̐�����F�߂�ƁA�ʒB�����ł͂Ȃ��@�߉�����v����_�n�́A���̕��@�Ɣ�ׂČ��ʂ���������v�Əq�ׂāA�s���@�w�i�d�Ŗ@�������j�┻��E�ٔ���ōs�����@�̋c�_���[�܂�Ȃ������o�܂𐄑����Ă���B |
| 6�Ł�122.01�X�R�b�`���C�g�����E��㍂�����a44�N9��30�����ٖ��W22��5��682�ŕS�I7��9ea ���Ŋւ�20���A�_�ːŊւ���30���ʼnېł��Ă����Ƃ���A�u30���̊ł��ۂ���̂������ł��邯��ǂ��v�A�u�Ŋ֊Ӎ�������c�̌��c�ɂ��A�S������I�ɖ{�����i�Ɠ���̕��i�ɑ��Ă�20���̐ŗ��ɂ��ł��ۂ��邱�ƂƂȂ�A�݂���Ԃ��Ȃ�̊��Ԍp�����Ă����̂ł��邩��v�A�u���߂���10���̌��x�ɂ����Ė@���Ɋ�Â��Ȃ���@�ȉہE���ŏ����ɓ���v�B |
2.2.4.2. �ېŗv��
(a)�[�ŋ`���ҁc�c�����Ŗ@��̌����[�t�`���ҁA����Ŗ@��́u���Ǝҁv���c�c�[�ŋ`���҂ƒS�Ŏ҂Ƃ̋�ʁ@�i��[�ŋ`���F���h�ЊC��ی����݉�Ў����E�Ŕ��������N7��14������1327��21�ŕS�I7��24mv�j(b)�ېŕ����c�c�u�����v��
(c)�ېŕ����̋A���c�c�����Ŗ@12��
(d)�ېŕW���c�c�u�����̋��z�v��
(e)�ŗ��c�c�����Ŗ@89��1����
2.3. �d�Ŗ@�̎����ߒ�
2.3.1. �d�Ŗ@���W�̓���
�Ŕ����a35�N3��31�����W14��4��663�ōs������S�I�T-7��11�c�c�ؔ[�����ɂ����Ė��@177���̓K�p���m��B�Ŗ��������A�o�L�̌�㞂��咣���鐳���ȗ��v��L�����O�҂ɊY�����Ȃ��Ƃ�������B��������������B�u���o�Ϗ�̎���̈��S��ۏႷ�邽�߂ɐ݂���ꂽ���@�ꎵ�����̋K��́A����@�ɂ��_�n���������ɂ́A���̓K�p�����Ȃ��v�Ƃ����ő唻���a28�N2��18�����W7��2��157�łƑԓx���قȂ�B
6�Ł�232.01�G�����ݓ|���s�������ԊҐ��������E�Ŕ����a49�N3��8�����W28��2��186�ł͌�q(��4.4.2.)
�R����2-5�@�u���̂̌����v�Ƃ��Ă̍��W���ƌ��͊W��
cf.�����p���u�w�d�ō��x�_�f�`�v���q�G�Ғ��w�d�Ŗ@�̔��W�x3��2.3.2. �d�ōs���ߒ�
2.3.2.1. �T��
2.3.2.2. �d�Ŋm��葱
2.3.2.2.a. �����I�ȑd�Ŋm��葱
�\���[������(�Œ�16��1��1��)�����ۉې�����(2���B�n���Ŗ@1��1��7���ł͕��ʒ���)�m��\��(����120��)�ɂ������F�\�����x��ih�ɂ�铮�@�t���̐v
| ���R���L�F���q��D�������E�Ŕ����a60�N4��23�����W39��3��850�ŕS�I7��109it�c�u�@�l�Ŗ@��O�Z����F�\���ɂ�����@�l�łɂ��čX��������ꍇ�ɂ͍X���ʒm���ɍX���̗��R�L���ׂ����̂Ƃ��Ă���̂́A�@���A�F�\�����x���̗p���A�F�\���ɂ����鏊���̌v�Z�ɂ��ẮA���ꂪ�@��̒���g�D�ɂ�鐳���ȋL�ڂɊ�Â����̂ł���ȏ�A���̒���̋L�ڂ����čX������邱�Ƃ��Ȃ����Ƃ�[�Ŏ҂ɕۏႵ����|�ɂ��݁A�X���������̔��f�̐T�d�A��������S�ۂ��Ă��̜��ӂ�}������ƂƂ��ɁA�X���̗��R����ɒm�点�ĕs���\���Ă̕X��^�����|�ɏo�����̂Ƃ����ׂ��ł���A�������āA���돑�ނ̋L�ڎ��̂�۔F���čX��������ꍇ�ɂ����čX���ʒm���ɕ��L���ׂ����R�Ƃ��ẮA�P�ɍX���ɂ����銨��ȖڂƂ��̋��z�����������ł͂Ȃ��A���̂悤�ȍX��������������L�ڈȏ�ɐM�ߗ͂̂��鎑����E�����邱�Ƃɂ�ċ�̓I�ɖ������邱�Ƃ�v����v(���L�a�����E�Ŕ����a38�N5��31�����W17��4��617��kh)�B �u���돑�ނ̋L�ڎ��̂�۔F���邱�ƂȂ��ɍX��������ꍇ�ɂ����ẮA�E�̍X���͔[�Ŏ҂ɂ�钠��̋L�ڂ����̂ł͂Ȃ�����A�X���ʒm���L�ڂ̍X���̗��R���A���̂悤�ȍX�������������ɂ��Ē���L�ڈȏ�ɐM�ߗ͂̂��鎑����E��������̂łȂ��Ƃ��Ă��A�X���̍�����O�L�̍X���������̜��ӗ}���y�ѕs���\���Ă̕X�Ƃ������R���L���x�̎�|�ړI���[��������x�ɋ�̓I�ɖ���������̂ł������A�@�̗v������X�����R�̕��L�Ƃ��Č�����Ƃ���͂Ȃ��v(���R���L�͕�25�ȍ~�͐���킸���{����Ă��邱�Ƃɗ��ӁB���F�\���̋L���E����ۑ��`���g��(�Œ�74����14�A����232��))�B |
| ���ŕs���R�����ߘa5�N12��15���ٌ��E�ٌ�����W133�W�Q�Łc�c����Ŏd���Ŋz�T���۔F�̗��R���L�ɕs��������Ƃ��ꂽ����(�k���L�u���R��������Ȃ���I�v) |
���^�����E���q�������l�X�ȂƂ���������[�t���p������B
�Ŕ����a45�N12��24�����W24��13��2243�ŕS�I7��114kr(��4.8.3.����)�c�c�����́u�[�ŋ`���͉E�̏����̎x���̎��������A���̐����Ɠ����ɓ��ʂ̎葱��v���Ȃ��Ŕ[�t���ׂ��Ŋz���m�肷��v�B�u�����ɂ�鏊���ł̐Ŋz�́A�O�q�̂Ƃ���A����Ύ����I�Ɋm�肷��̂ł��āA�E�̔[�ł̍��m�ɂ��m�肳�����̂ł͂Ȃ��B���Ȃ킿�A���̔[�ł̍��m�́A�X���܂��͌���̂��Ƃ��ېŏ������鐫����L���Ȃ��v�B�u�����ɂ�鏊���łɂ��Ă̔[�ł̍��m�́A�ېŏ����ł͂Ȃ����������ł��āA�x���҂̔[�ŋ`���̑��ہE�͈͉͂E�����̑O���肽��ɂ����Ȃ�����A�x���҂ɂ����Ă���ɑ���s���\���Ă������A�܂��͕s���\���Ă����Ă��ꂪ�r�˂��ꂽ�Ƃ��Ă��A�҂̌���[�ŋ`���̑��ہE�͈͂ɂ͂����Ȃ�e�����y�ڂ�������̂ł͂Ȃ��B�v
�����f�Վ����E�Ŕ�����4�N2��18�����W46��2��77�ŕS�I7��115lb�c�c�u�����łƐ\�������łƂ̊e�d�ō��̊Ԃɂ͓��ꐫ���Ȃ��A�����ł̔[�łɊւ��ẮA���Ɩ@���W��L����͎̂x���҂݂̂ŁA�҂Ƃ̊Ԃɂ͒��ڂ̖@���W���Ȃ����̂Ƃ���Ă��邱�Ƃ��炷��A�O�L�����Ŋz�̍T���̋K��́A�\���ɂ��[�t���ׂ��Ŋz�̌v�Z�ɓ�����A�Z�o�����Ŋz����E�����̋K��Ɋ�Â��������ׂ����̂Ƃ���Ă��鏊���ł̊z���T�����邱�ƂƂ��A����ɂ�茹�����x�Ƃ̒�����}���|�̂��̂Ɖ������̂ł���A�E�Ŋz�̌v�Z�ɓ�����A�����ł̒����E�[�t�ɂ�����ߕs���̐��Z���s�����Ƃ́A�����Ŗ@�̗\�肷��Ƃ���ł͂Ȃ��B�v(��COLUMN4-3�N�����������ی�����d�ېŎ���)
2.3.2.2.b. ��O�I�ȑd�Ŋm��葱
(�A)�ߏ��\���̏ꍇ�@�C���\��(���Œʑ��@(�Œ�)19��)(�C)�ߑ�\���̏ꍇ�@�X���̐���(�Œ�23��1���c�c5�N�ȓ��Ɋ��ԉ���)
�X���̐����E�s�������ԊҐ����E���Ɣ����Ƃ̊W�ɂ���
���쒩�C�����E�Ŕ����a39�N10��22�����W18��8��1762�ŕS�I7��104nu�c�u�m��\�����̋L�ړ��e�̉ߌ�̐����ɂ��ẮA���̍��낪�q�ϓI�ɖ������d��ł����āA�O�L�����Ŗ@�̒�߂����@�ȊO�ɂ��̐����������Ȃ��Ȃ�A�[�ŋ`���҂̗��v�����Q����ƔF�߂�����i�̎������ꍇ�łȂ���A���_�̂悤�ɖ@��̕��@�ɂ��Ȃ��ŋL�ړ��e�̍�����咣���邱�Ƃ́A������Ȃ��v�B�X���̐����̌����I�r�����B
�Ⓚ�q�Ɏ����E�Ŕ�����22�N6��3�����W64��4��1010�ŕS�I7��121ig�c�c�u�n���Ŗ@�́C�Œ莑�Y�]���R���ψ���ɐR����\���o�邱�Ƃ��ł��鎖���ɂ��ĕs��������Œ莑�Y�œ��̔[�Ŏ҂́C���ψ���ɑ���R���̐\�o�y�т��̌���ɑ��������̑i���ɂ���Ă̂ݑ������Ƃ��ł���|���K�肷�邪�C���K��́C�Œ莑�Y�ېő䒠�ɓo�^���ꂽ���i���̂̏C�������߂�葱�Ɋւ�����̂ł����āi�S�R�T���P���Q�Ɓj�C���Y���i�̌��肪�������̐E����̖@�I�`���Ɉ�w���Ă��ꂽ�ꍇ�ɂ����鍑�Ɣ����ӔC��ے肷�鍪���ƂȂ���̂ł͂Ȃ��B�c�c�s����������@�ł��邱�Ƃ𗝗R�Ƃ��č��Ɣ�������������ɂ��ẮC���炩���ߓ��Y�s�������ɂ��Ď�������͖����m�F�̔����Ȃ���Ȃ�Ȃ����̂ł͂Ȃ��v(��3.2.2.1.�R�������O�u��`)my iv
(�E)����I�Ȏ����W�̕ϓ��ɂ��\���Ŋz���ߑ�ƂȂ����ꍇ�@2�����ȓ��ɍX���̐���(�Œ�23��2���Bcf.70��1��)kl
(�G)�Ŗ������̍s���s�ׂɂ��Ŋz�m��@�\����(�K����)�Ȃ��ꍇ���X���E����(�Œ�24���E25��)�B�[�Ŏ҂��s���ł���Εs���\���ĂցB
2.3.2.2.c. ���⌟����
2.3.2.3. �����葱
51���}�\2-4�@�Ŋz�m��E�����葱�̗���i�\���[�ŕ����̏ꍇ�j�Q�ƁB�@��[�����܂łɎ����I�[�t���Ȃ��ꍇ�����������ցB���ɂ������Ȃ�����ؔ[�����ցBmm
��[�ŋ`��
| CFJ������Ў����E�����n���ߘa4�N5��17���ߘa2(�s�E)370��(���p)�c�c���Œ����@39���u���̖Ə��v�̈Ӌ` ���|�@�u�����@�̒�߂��[�ŋ`�����x�́A�傽��[�ŋ`�����\�����͌���Ⴕ���͍X�����ɂ���̓I�Ɋm�肵�����Ƃ�O��Ƃ��āA���̊m�肵���Ŋz�ɂ��{���̔[�ŋ`���҂̍��Y�ɑ��đؔ[���������s���Ă��Ȃ��������ׂ��z�ɕs������ƔF�߂���ꍇ�ɂ����āA�`���I�ɂ͑�O�҂ɍ��Y���A�����Ă��Ă��A�����I�ɂ͑ؔ[�҂ɂ��̍��Y���A�����Ă���ƔF�߂Ă������������Ȃ��悤�ȂƂ��́A�`���I�Ȍ����̋A�����̂�۔F���邱�ƂȂ��A���̌`���I�Ɍ������A�����Ă���҂ɑ��ĕ�[�I�ɔ[�ŋ`���S�����邱�Ƃɂ��A�d�Œ����Ɖېł̌����̊m�ۂ�}�邱�Ƃ����̎�|�Ƃ�����̂ł���i�ō��ُ��a�S�W�N�i�s�c�j��P�P�Q�����T�O�N�W���Q�V����@�씻���E���W�Q�X���V���P�Q�Q�U�ŎQ�Ɓj�B �C�@�����āA�����@�R�X���́A�ؔ[�҂��s�����������n���̏����̑�������[�ŋ`���҂Ƃ��Ă���Ƃ���A����́A�ؔ[�҂��s���������n���̏������A�d�ō��̈����ĂƂȂ�ؔ[�҂̐ϋɍ��Y��������������̂ł���ƂƂ��ɁA���̑�����Ɉ���I�Ɍo�ϓI���v����������̂ł��邱�ƂɊӂ݁A���̂悤�Ȗ������n���̑�����ɂ��ẮA���ꂾ���ŁA�ʏ�ł���Ζ{���̔[�ŋ`���҂ł���ؔ[�҂Ɠ���̔[�ŏ�̐ӔC�킹�Ă������������Ȃ��悤�ȓ��ʂȊW�ɂ���Ƃ����邱�Ƃ���A�����̎҂ɑ�[�ŋ`�����ۂ����ƂƂ������̂Ɖ������i�ō��ٕ����P�U�N�i�s�q�j��Q�V�T�����P�W�N�P���P�X����ꏬ�@�씻���E���W�U�O���P���U�T�Łm�S�I7��25�n�Q�Ɓj�B���̂悤�ȓ����̎�|���炷��A�����ɂ����u���̖Ə��v�́A���@�T�P�X������̍��̖Ə��Ɍ�������̂ł͂Ȃ��A�_��ɂ����̖Ə����A�ؔ[�҂����̈ӎv�ɂ�肻�̗L�������Ή��Ȃ����ł�����s�ׂ��L���܂����̂Ɖ����ׂ��ł���B�v |
| ���ŕs���R�����ߘa6�N9��25���ٌ��E�ٌ�����136�W�Q��(�k���L�u�łŃ�������ǂ�����i��14��j�`�������Ȃ�ĕ����ĂȂ���I�`�v)�c�c�������������ɂ́A����l��������ׂ��������Y��̕��S�ł���R�������l�̎ؒn���Ƃ����u�����Ɋւ��d�v�ƔF�߂��鎖���v�̋L�ڂ��R��Ă���Ƃ������r���F�߂��A���������ׂ����r������Ƃ�������B |
2.3.2.4. ���ѐ�
2.3.2.4.a ���ؐ�(�Œ�60��)mu
�Ŕ�����26�N12��12���W��248��165�ŕS�I6��99(��2.2.1.1.d�K���葱)�����n������28�N1��15������26(�s�E)664���c���Œʑ��@60��4���ɂ�葊���Ŗ@34��1���̑����łɂ͉��ؐł��܂܂��B�@��[������A�{���̔[�ŋ`���҂������P�\���Ă������Ԃƌ������A�є[�t�`���̔[�ō��m����܂ł̊��Ԃ��܂߂āA���ؐł���������B
2.3.2.4.b ���q��(�Œ�64��)
�G���Ɍ����A�����̒x�����Q���i�����ؐŁj�Ɩ����̖@�藘���i�����q�Łj�B���q�ł̔N7.3�����Œ�58�����ҕt���Z���̔N7.3��)�B���݂͓�������(�d���@93���A95��)
2.3.2.4.c ���Z��(�Œ�65�`68��)
[1]�ߏ��\�����Z��(�Œ�65��)[2]���\�����Z��(�Œ�66��)
[3]�s�[�t���Z��(�Œ�67��)
[4]�d���Z��(�Œ�68��)
���������E�Ŕ����a33�N4��30�����W12��6��938��nv�c癒E�Ƃɑ���Y���ƒǒ��ł͌��@39��(��d�����֎~)�Ɉᔽ���Ȃ��B
���ŕs���R�����ߘa5�N12��4���ٌ��E�ٌ�����W133�W�Q�Łc�c�H�������\�����Ă��Ȃ�����(�S��������������Ŏ��̎����̔��s��Y�꒠��ɋL�ڂ��Y��Ă���)���Ƃɂ��ĉB�������ɓ����炸���Œʑ��@68��1��(�d���Z��)�̕��ۗv�������Ȃ��Ƃ�������Bcf.�k���L�u�B������͂Ȃ������̂Ɂc�v
COLUMN2-6 ���Z�Ő��x�Ƒd�Ŗ@�̎����ߒ�
�����p���u�ߏ��\�����Z�ł�Ə�����w�����ȗ��R�x�Ɋւ����l�@�\�\IMPACT���肪����Ƃ��āv�����Ő�����2��91���X�g�b�N�E�I�v�V�������Z�Ŏ����E�Ŕ�����18�N10��24�����W60��8��3128��(��4.2.6.2.�t�����W�E�x�l�t�B�b�g)
�q��@���[�X���Ɠ����g�������E�Ŕ�����27�N6��12�����W69��4��1121�ŕS�I7��22(��4.2.5.�s���Y����)
2.3.3. �d�ōs���ߒ��ɌW����
2.3.3.1. �d�ōs���g�D�̍\��
2.3.3.1.a ���̑d�ōs���g�D
2.3.3.1.b �n�������c�̂̑d�ōs���g�D
2.3.3.2. �ŗ��m���x
�ŗ��m�@52���ɂ��Ɩ��Ɛ�F�����ł��ʖځ@(cf.�ŗ��m�@51��ʒm�ٌ�m���x�ɂ��ā�km)cf.�ٌ�m�@72���ɂ��Ɩ��Ɛ�i��ٍs�ׂ̋֎~�j�ɂ́u��V��ړI�v�u�ƂƂ���v�Ƃ������肪����B
3. �d�Ŗ@�̎����Ɩ@���Ƃ̖���
3.1. �d�Ŗ@�̉���
3.1.1. �d�Ŗ@�߂̉���
3.1.1.1. �@�߉��߂Ƃ������
3.1.1.2. ���������̊�{
�����`�I���ʂ����R��`�I���ʁB�Ŕ�����27�N7��17������2279��16�Łi��2.2.1.1.f�j3.1.1.3. �ō��ق̑ԓx
| 6�Ł�141.01�z�X�e�X��V�v�Z���Ԏ����E�Ŕ�����22�N3��2�����W64��2��420�ŕS�I7��13ns(��2.2.1.1.f.) ���ŗ�322���u5000�~�ɓ��Y�x�����z�̌v�Z���Ԃ̓������悶�Čv�Z�������z�v�͊e�z�X�g�E�z�X�e�X(���^�����ł͂Ȃ����Ə������ғ�)�̎��ۂ̏o�Γ���(�K�v�o��T�Z�T���̊ϓ_����)���Ӗ������P���ȓ����ł���B �K��̎�|�ƕ������l�������B ���ߕ��@�ɂ��āB���J���j�u�d�Ŗ@�̉��ߌ����̘_���Ƃ��Ắw�d�Ŗ@����`�x�\�\���۔�r�̊ϓ_����v�������E���J���j�ҁw�d�Ŗ@����`�̑����I�����x271��(�L��t�A2021)�A�����p���u�ō��ٔ���Ɍ���d�Ŗ@�K�̉��ߎ�@�v�R�{�h�O�E�����v�ҁw�@���߂̕��@�_ ���̏����ƓW�]�x341��(�L��t�A2021) |
| �K�C�A�b�N�X�����E�Ŕ�����18�N6��19���W��220��439��ad�c�u�y������ł́C�{���C�y����R���Ƃ��鎩���Ԃ̗��p�҂����H�����̎�v�҂ł��邱�Ƃ���C���H�Ɋւ����p�ɏ[�Ă邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Čy���̈������ېł̑ΏۂƂ�����̂ł������Ƃ���C�{���e�K��m�n���Ŗ@700����3��3�����n�́C�y���ȊO�́w�Y�����f�Ƃ��̑��̕��Ƃ̍������x�ł����Ă������Ԃ̓��R�@�ւ̔R���Ƃ������̂ɂ��ẮC���̔̔������y������ł̉ېł̑ΏۂƂ��邱�Ƃɂ���Đŕ��S�̌�����}�낤�Ƃ������̂ł���B���̂悤�Ȗ{���e�K��̎�|�₻�̕����ɏƂ点�C�{���e�K��ɂ����w�Y�����f�Ƃ��̑��̕��Ƃ̍������x�Ƃ́C�Y�����f���听���Ƃ��鍬�����Ɍ��炸�C�L���Y�����f�Ƃ��̑��̕����Ƃ����������������������̂Ɖ�����̂������ł���B�v |
�t�n�[�t�^�b�N�X�v��������(�{�V�ی��_��ی����T������)�E�Ŕ�����24�N1��13�����W66��1��1��(��4.2.9.�ꎞ����)
| �Ŕ�����27�N7��17������26(�s�q)190���W��250��29��(���Y��E�W�����X�g1487��10-11�ŁA��핐����E�W�����X�g1492���d����27�N201-202��)�c�c�o�L��̕\�蕔�̏��L�җ��Ɂu�厚���v�ȂǂƋL�ڂ���Ă���y�n�ɂ��C�n���Ŗ@343��2����i�̗ސ��K�p�ɂ��C���Y�y�n�̏��݂���n��̏Z���ɂ��g�D����Ă��鎩����͒�����Y�y�n�̌Œ莑�Y�ł̔[�ŋ`���҂ɓ�����Ƃ������R�̔��f�Ɉ�@������Ƃ��ꂽ���� |
| �t�[�W���[�X�R�[�|���[�V���������E�Ŕ�����28�N12��19�����W70��8��2177�Łc�u�n���Ŗ@�{�s�ߕ����U���̂P�V��Q���̋����Z��Ɋւ��Ē�߂�ꂽ�ː��v���m100�ȏ�n���[�����邩�ۂ��̔��f�ɂ����Ă��C�ʒi�̒�߂��Ȃ�����C�P���̋����Z���P�ʂƂ��ׂ��ł���v�B |
3.1.1.4. �T�O�̊g���Ək��
| ���[�V���O�J�[���i�Ŏ����E�Ŕ�����9�N11��11���W��186��15��ae�c�c�����𑖂�Ȃ������p������(FJ1600)�����i�Ŗ@�́u���^������p�l�֎����ԁv�ɊY������Ƃ��ĕ��i�ł��ۂ������āB�ō��ٞH���u�l�̈ړ��Ƃ�����p�ړI�̂��߂Ɏg�p�������̂ł��邱�Ƃɕς��͂ȁv���B(����s�M�E�����������Έӌ�����)�B |
| �Ŕ�����16�N12��16�����W58��9��2458�ŕS�I7��94cz(��6.2.4.2.b) �����(�t�����l��)���d���Ŋz�T���̗v���́u���떔�͐��������c�c��ۑ����Ȃ��ꍇ�v(����30��7���E����)�ɂ��A�K���ɒ��Ȃ����Ƃ́u�ۑ����Ȃ��v�ɓ�����B �ޗ���Ŕ�����16�N12��20������1889��42��da�ő��ɒj���Έӌ�����B |
�Ŕ�����17�N3��10�����W59��2��379�ŕS�I7��110(��6.2.4.2.b)�c����s���̐F�\�����F��������͓K�@�B
3.1.1.5. �ސ�����
| �T�����E�������X�y�n���؎����E�Ŕ����a45�N10��23�����W24��11��1617�ŕS�I5��37af �ؒn���ݒ�(����́u���Y�̏��n�v�Ƃ͌���������)�ɔ����u�������v�ł��A�u���L�҂����Y�y�n�̎g�p���v���i�v�I�Ɏ藣�����ʂƂȂ�ꍇ�ɁA���̑Ή��Ƃ��čX�n���i�̂���߂č��������ɓ�������z���x������Ƃ����悤�Ȃ��́v�ɂ��Ắu���n�����ɓ�������̂��ސ���������v�B�Ȃ����Ă̌��_�Ƃ��Ă͕s���Y���������Ȃ̂ŗސ����߂��Ă��Ȃ��B �⑫�F�d�Ŗ@��ސ����߂��邱�Ƃ͋�����Ȃ��ƌ����邱�Ƃ��������A�Ŕ����a45�N10��23���ł́u�ސ����߁v�Ɩ��L���Ă���B�����A�u�ސ����߁v�Ɩ��L���Ă��Ȃ����ސ����߂��������炭�B��̍ō��ّd�Ŕ���Ƃ��ēs���Ŋҕt���Z���N�Z�������E�Ŕ�����20�N10��24�����W62��9��2424��gi������B |
| 4�Ł�161.02(6��73��)�����Y�ƐM�p���Ɏ����E�Ŕ����a48�N11��16�����W27��10��1333�ŕS�I6��92hd ���n�S���Ƃ��Ă̕s���Y�擾���s���Y�擾��(�u���ʐłɑ����A�s���Y�̈ړ]�̎������̂ɒ��ڂ��ĉۂ�����v)�̉ېőΏۂƂȂ�Ƃ��A��ېŋK��̗ސ��K�p���ے肵���B |
3.1.2. �d�Ŗ@�Ǝ��@
3.1.2.1. �ؗp�T�O
�ŗL�T�O�F���̖@����ł͗p�����ĂȂ��d�Ŗ@���Ǝ��ɗp���Ă���T�O(��:�����A���Y)�ؗp�T�O�F���̖@����ŗp�����Ă���Ӗ����e���^�����Ă���T�O(��:����A�z���)hc
3.1.2.2. �ؗp�T�O�̉���
������F�ؗp�T�O���ؗp���̖@����ɂ�����̂Ɠ����Ӌ`�ɉ��߂��ׂ��A�Ƃ���̂��ʐ��B�A���u���v�z���v�T�O�����@��K�@�Ȕz���Ɍ��肳��Ȃ�������ɗ���(6�Ł�221.02�����Z�����E�Ŕ����a35�N10��7�����W14��12��2420�ŕS�I5��36��4.2.2.1.)
5�Ł�162.02(6��80��)���ƌo�ϊ�����Ў����E�Ŕ����a36�N10��27�����W15��9��2357�ŕS�I5��16ar�c�o���҂��B�ꂽ���Ǝ҂Ƃ��Ď��ƂɎQ�������̗��v�̕��z����ӎv��L�����A���K����Ђɗ��p�������̑Ή��Ƃ��ė���������ӎv�����Ă����ɉ߂����A���̂��Ƃ��A�������F��̎���̂��Ƃɋq�ϓI�ɂ��F�߂���ꍇ�́A���Ǝ҂Əo���҂Ƃ̌_��́A�����Ŗ@��P���Q����R���ɂ����u�����g���_��т���ɏ�����_��v�ɂ�����Ȃ��B
�������u�z��ҍT���v�i���E�Ŕ�����9�N9��9����44��6��1009�ŕS�I7��50av�c�@�����Ɍ���B
�}�{�T���ɂ����u�e���v�E�Ŕ�����3�N10��17����38��5��911��ax�c���@��̐e���Ɍ���B
�Z���F6�Ł�142.01���x�m�����E�Ŕ�����23�N2��18������2111��3�ŕS�I7��14(��3.1.3.4.)
�@�l�E�f���E�F�A�BLPS�����E�Ŕ�����27�N7��17�����W69��5��1253�ŕS�I7��23(��4.2.5.�s���Y�����A8.2.1.2.c)
�ِ�
�Ɨ����F�d�ł̒����m�ۖ��͌������S�̊ϓ_����A�ؗp�T�O�ł����Ă��d�Ŗ@�Ǝ��ɉ��߂��ׂ��ł���B
�ړI�K�����F�K�������d�ł̒����m�ۂɎ�������߂��D�悷��킯�ł͂Ȃ����A�ؗp�T�O�ł����Ă��d�Ŗ@�̖ړI�ɓK���I�ȉ��߂����ׂ��ł���B(�h�C�c�ŗL�͂ł�����{�ł��x���҂����邪�[���肵�Ȃ�)
��������ʐ��Ƃ͂����A������̘_�҂��ʈӂɉ����ׂ����Ƃ��d�Ŗ@�K�̖������͂��̎�|���疾�炩�ȏꍇ�͕ʘ_�Ƃ��Ă���A������ƓƗ����E�ړI�K�����Ƃ̈Ⴂ��������`�I�ɑ�����ׂ��łȂ��B
3.1.2.3. �ؗp�T�O�̏C��
����60��1���u���^�v�T�O�̏C���F6�Ł�222.08�l��������p�n�����E�Ŕ����a63�N7��19������1290��56�ŕS�I7��44(��4.2.3.6.�d�ő����̈��p��)�B3.1.2.4. ���@����Ƒd�Ŗ@
| �ŕ��S�Ɋւ��������c5�Ł�163.01(6�łȂ�)����ю����E�Ŕ��������N9��14�������W��157��555�ŕS�I5��18he �����ɍۂ��Ă����Y���^�ɏ��n�����ېł��ۂ����邱��(cf.4.2.3.3. ��222.02���É���t���Y���^����)��m��Ȃ������̂ō��떳��(���͍������ł��邪)�ł���Ǝ咣��������B �@���|�u���@���َ��I�ɕ\������Ă���Ƃ��ł����Ă��A���ꂪ�@���s�ׂ̓��e�ƂȂ邱�Ƃ�W������̂ł͂Ȃ��v�B�َ��I�\���i ߄t߁j�߶�� �@�{���ł́u���Ȃɉېł���Ȃ����ƂR�̑O��Ƃ��A���A���̎|��َ��I�ɂ͕\�����Ă����v�B (�ނ��ٔ���𑽐����n���ƍ��떳�����F�߂��鎖��ƔF�߂��Ă��Ȃ����Ⴊ���邱�Ƃɗ��ӁB) cf.�@��[������̍���咣�F6�Ł�250.02�N���J�O���[�v������㍐�R�����E�Ŕ�����30�N9��25�����W72��4��317�ŕS�I7��116(��4.8.3.����) |
6�Ł�225.01�y�n�����擾�����E�É��n������8�N7��18���s�W47��7=8��632��(��4.2.9.�ꎞ����)
| ���s�����y�n�r�������E��㍂������14�N7��25�����^1106��97�ŕS�I6��106 �`����w����Y�y�n���擾��������ő����ł̐\�����������a���擾�������咣���ʌ������ła���i�i�������������p��������j�B���@144���u�����̌��͂́A���̋N�Z���ɂ����̂ڂ�B�v�ɂ��ʌ��������Œ�23��2��1���u�����v�ɓ�����Ƃ��Ăw���X���̐������������A�˂���ꂽ�B �����O�ɉ��p�����葊���J�n��ɔ������m�肵���ꍇ�͐Œ�23��2��1���u�����v�ɓ�����ł��낤�B �����O�Ɏ�����������������ɉ��p���������ꍇ�ɂ��Ė{�����̎˒��O���H(���ŕs���R��������14�N10��2���ٌ��E�ٌ�����W64�W1��(���ŕs���R��������19�N11��1���ٌ��E�ٌ�����W74�W1�ł����|)�͍X���̐�����F�߂Ă���B�A����~��������ے肵�Ă͂��Ȃ��B���R�͕]���̌��z�B�a�J��O�E�Ŗ����ጤ��120��54�ł͕]���z���Ƃ��鏈���ɋ^���悷�B cf.���ˋM�V�u�d�Ŗ@�Ƒk�y���\�ٔ���E�ٌ���̕��͂���\�v������w�@�ȑ�w�@���[���r���[7��28-54��2012.9���Q��) |
| ��㍂������14�N12��26�����^1134��216�ŕS�I5��17 (�����@110���A���s��Ж@839��)�c�u�ېŊW�ɂ����Ă��A�������������̌��͂͑k�y���Ȃ��v�u�{�������ɂ���Đ��Z�����y�т݂Ȃ��z�����������������Ƃ͔ے�ł��Ȃ��v |
3.1.3. �d�ʼn���̔۔F
3.1.3.1. �ߐŁE�E�ŁE�d�ʼn��
6�Ł�143.01���q�G�u�d�Ŗ@�Ǝ��@�\�\�ؗp�T�O�y�ёd�ʼn���ɂ��āv�̗p��@�ߐ�(tax saving, Steuerersparung):�d�Ŗ@�K���\�肵�Ă���Ƃ���ɏ]���Đŕ��S������������B���@�B
�E��(tax evasion, Steuerhinterziehung):�ېŗv���̏[���̎�����铽���Đŕ��S������������B��@�B
�d�ʼn��(tax avoidance, Steuerumgehung):�u�����I�܂��͐����ȗ��R���Ȃ��̂ɁA�ʏ�p�����Ȃ��@�`����I�����邱�Ƃɂ���āA�ʏ�p������@�`���ɑΉ�����ŕ��S�̌y���܂��͔r����}��s�ׁv�i��P�ތ^�j�A�u�d�Ō��ƋK��̎�|�E�ړI�ɔ�����ɂ�������炸�A���@��̌`���\���𗘗p���āA���Ȃ̎����������[������悤�Ɏd�g�݁A�����Đŕ��S�̌y���܂��͔r����}��s�ׁv�i��Q�ތ^�j�i���q�G�d�Ŗ@24��134�Łjhg
cf. �^�b�N�X�E�V�F���^�[(tax shelter�d�ʼn�����i):���x�ɕ��G�Ȉ�A�̌_���g�ݍ��킹�đd�ŕ��S�̌y����}��d�g��(scheme/structure�Ƃ��Ă��)�B
�d�ʼn���̗�@�@(�����Ŗ@33��1�����ʏ������Ȃ��ꍇ�́u���n�v�̉��)
�`�a�Ԃ̏��n�̗�b�b�c�Ԃŏ��n����������
�`�@�@�@�@�@�a�@�b�@�b�@�@�@�@�@�c�@�@(���E)
���@���y�n���n�@�b�@���@���n�㌠�ݒ�@(�n�ど)
���K�x�����@10�@�b�@���K�Z�����@10�@�@(�����q)
3.1.3.2. �d�ʼn���ւ̑Ή�
�d�ʼn��(�s��)�̔۔F�c�c�d�ʼn�����������ꍇ�ɁA�����҂��p�����@�`����d�Ŗ@��͖������A�ʏ�p������@�`���ɑΉ�����ېŗv�����[�����ꂽ���̂Ƃ��Ď�舵�������ʓI�۔F�K���Ɋ�Â��Ĕ۔F���邱�Ƃ͂ł���B(����33��1�����ʏ��A�d�œ��ʑ[�u�@41����4��2����g�������̕s���Y�����ɌW�鑹�v�ʎZ���̓���)
����ʓI�Ȕ۔F�K��A�Ⴆ�Γ�����Ђ̍s�v�Z�۔F�K��(�@�l�Ŗ@132��(��COLUMN5-1)���c�ނ��ېŒ����s�i���鎖��͒������Ȃ�)��hi�ɂ��Ă͕s�m��T�O(��2.2.1.1.b)���Q��
��1��330.01�������Y������Ў����E�Ŕ����a33�N5��29�����W12��8��1254��
���t�[�����E�Ŕ�����28�N2��29�����W70��2��242�ŕS�I7��64eboh�AIDCF�����E�Ŕ�����28�N2��29�����W70��2��470�Łc�c�@�l�Ŗ@132����2�ɂ��āu���p�v�������Ȃ��B
| PGM�v���p�e�B�[�Y������Ў����E�����n���ߘa6�N9��27���ߘa3(�s�E)181���F�e(�T�i) �ɓ����u=���c�M�s�u�@�l�Ŗ@132����2�̓K�p���ے肳�ꂽ�����v(���������Ж@��������)�A�����C��E�Ŗ����ጤ��202��1-9�ŁA���c�M�s�E�d�Ō���903��212-266�ŁA�n�ӓO��E�@�w����98��1��47-70��(�������ӌ���)�A�����S���E�d�Ŕ��ጤ����2025�N6��20���B �n�ӓO��E�@�w����98��1��49�ł���} �@�@�@�@�@�@�@�@���������� �@�@�@�@�@�@�@�@��PGMHD �� �@�@�@�@�@�@�@�@���������� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��100.0% �@�@�@�@�@�@�@�@���������� �@�@�@�@�@�@�@�@�� PGP�@�� �@�@�@�@�@�@�@�@���������� �@�@������������������������������������������ �@�@��100.0%�@�@�@�@�@�@��100.0%�@�@�@�@�@�@��99.99% �����������@�@�@�@�@�����������@�@�@�@�@���������� ��PGPAH6���\�\�\�\����PGMP4 ���\�\�\�\���� ���� �� �����������{�������P�����������{�������Q���������� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����{�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���������������������������b���� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�@�@�@���@�@�@�@�@�@���b�Q �@�@�@�@�@�@���������������������������������������� �@�@�@�@�@�@��100.0%���@100.0%���@�@�@100.0%���@�@�� �@�@�@�@�@�@���@������������������������������������ �@�@�@�@�@�@���@������CC����PGMP3 �������{�S���t���� �@�@�@�@�@�@���@������������������������������������ �@�@�@�@�@�@���������������������������������������� �@�����@�{�������P�Ɩ{�������Q���@�l�Ŗ@2��12����8�̓K�i�����ɓ�����O����@�l�Ŗ@57��2���y��81����9��2��2����K�p���{�������P�̒��O�̌������z57���](�{���������������z)�������̘A���������z�Ƃ݂Ȃ�����29�N3�����̘A�����ƔN�x�̘A���m��\�����������͂����B�������Ŗ������́A�@�l�Ŗ@132����2�̋K��ɂ��{���������������z�������̘A���������z�Ƃ݂Ȃ����Ƃ�F�߂Ȃ��O��Ŗ@�l�ōX���������������B �@���_�@�{���e�������@�l�Ŗ@�P�R�Q���̂Q�ɂ����u�@�l�ł̕��S��s���Ɍ��������錋�ʂƂȂ�ƔF�߂�����́v�i�s�����v���j�ɊY�����邩�ۂ� �@���|�@�u�O���[�v�ɂ����ẮA�o�c��@�Ɋׂ�Ȃǂ����S���t��^�c�@�l�����ċK�͂��g�傳���A�����̃S���t���{���ŏW���Ǘ����A�S���t�p�i�����ꊇ�w������Ȃǂ��ăX�P�[�������b�g��Nj�����ƂƂ��ɁA�����ɂ�葝��������q��Ђ̐��������ɂ��팸���邱�Ƃɂ��A�o�c�̍������E��������Nj�����Ƃ����r�W�l�X���f���i�{���r�W�l�X���f���j�̉��A���Ƃ��c��ł���B�v�u�O���[�v�́A�{���r�W�l�X���f���Ɋ�Â��A�{���e�����̂P�O�N�ȏ�O����A�����ɂ���Ăo�Q�O�̎q��Ђ̐���������x������s�x�A�O���[�v���ł̋z���������J��Ԃ��A�ŏI�I�ɂ͌����ɂ����̉�Ђ��z�����������邱�Ƃɂ���āA�S���t��ۗ̕L�@�\�������ɏW���A�o�Q�O�̎q��Ђ̐����팸���邽�߂̍������J��Ԃ��Ă����B���̂悤�ȍ����ɓ�����A�S���t�ꎖ�Ƃ��c��ł��Ȃ��@�l�������̑ΏۂƂȂ����ق��A�����ɔ����Ĕ퍇���@�l���獇���@�l�֖������������z�������p����Ȃ������������������B�v �@�u�g�D�ĕҐ��́A���̌`�Ԃ���@�����G�����l�ł��邽�߁A����𗘗p����I���ȑd�ʼn���s�ׂ��s���₷���A�d�ʼn���̎�i�Ƃ��ė��p����邨���ꂪ���邱�Ƃ���A�@�l�Ŗ@�P�R�Q���̂Q�́A�ŕ��S�̌������ێ����邽�߁A�g�D�ĕҐ��ɂ����Ė@�l�ł̕��S��s���Ɍ��������錋�ʂƂȂ�ƔF�߂���s�ז��͌v�Z���s��ꂽ�ꍇ�ɁA����𐳏�ȍs�ז��͌v�Z�Ɉ��������Ė@�l�ł̍X�����͌�����s��������Ŗ������ɔF�߂����̂Ɖ�����A�g�D�ĕҐ��ɌW��d�ʼn�����I�ɖh�~����K��Ƃ��Đ݂���ꂽ���̂ł���B���̂悤�ȓ����̎�|�y�іړI���炷��A�����ɂ����u�@�l�ł̕��S��s���Ɍ��������錋�ʂƂȂ�ƔF�߂�����́v�Ƃ́A�@�l�̍s�ז��͌v�Z���g�D�ĕҐŐ��ɌW��e�K���d�ʼn���̎�i�Ƃ��ė��p���邱�Ƃɂ��@�l�ł̕��S��������������̂ł��邱�Ƃ������Ɖ����ׂ��ł���A���̗��p�̗L���̔��f�ɓ������ẮA�@���Y�@�l�̍s�ז��͌v�Z���A�ʏ�͑z�肳��Ȃ��g�D�ĕҐ��̎菇����@�Ɋ�Â�����A���ԂƂ͘��������`������o�����肷��ȂǁA�s���R�Ȃ��̂ł��邩�ǂ����A�A�ŕ��S�̌����ȊO�ɂ��̂悤�ȍs�ז��͌v�Z���s�����Ƃ̍����I�ȗ��R�ƂȂ鎖�ƖړI���̑��̎��R�����݂��邩�ǂ������̎�����l��������ŁA���Y�s�ז��͌v�Z���A�g�D�ĕҐ��𗘗p���Đŕ��S�����������邱�Ƃ��Ӑ}�������̂ł����āA�g�D�ĕҐŐ��ɌW��e�K��̖{���̎�|�y�іړI�����E����ԗl�ł��̓K�p������̖��͖Ƃ����̂ƔF�߂��邩�ۂ��Ƃ����ϓ_���画�f����̂������ł���i�ō��ٕ����Q�W�N�������Q�Ɓj�B�v�u�@�K�i�������s��ꂽ���ʁA�������������z�������p����A�d�ŕ��S����������ꍇ������Ƃ����̂́A�g�D�ĕҐ��Ő����\�肵�Ă�����̂ł��邱�Ɓi�ނ���A�K�i�����̏ꍇ�ɏ��n���v�̌v����J�艄�ׂď]�O�̉ېŊW���p�������邱�Ƃ́A�g�D�ĕҐŐ��̎�|���̂��̂ł���B��L�R�Q�Ɓj�A�A���v�ݏo���A���������ɑ��ĊҌ����邱�Ƃ����ɂ̖ړI�Ƃ��銔����Ђɂ����āA���K�͈ȏ�̎��������ɓ�����A�Ŗ���̉e����S���l�����Ȃ����Ƃ͍l����i�b�U�S�Q�Ɓj�A�ނ���A������l�������Ȃ��Ŏ�����s���A������̐ӔC��Njy����鎖�Ԃ��������˂Ȃ��̂ł����āA������Ђ����Ƃ̖ړI�ɉ����Ď�X�̌o�ϊ����𐋍s����ɓ�����A�Ɩ��̊Ǘ��E���s��A�����㖔�͐Ŗ��㓙�̗l�X�Ȋϓ_����A���v���ő剻��������@��@�߂̋��e����͈͓��Ŏ��R�ɑI�����邱�Ƃ��ł���Ɖ�����邱�Ƃ��炷��ƁA�s�ׁE�v�Z�̕s���R�����S���F�߂��Ȃ��ꍇ��A���̂悤�ȍs�ׁE�v�Z���s�����Ƃ̍����I�ȗ��R�ƂȂ鎖�ƖړI�����\���ɑ��݂���ƔF�߂���ꍇ�ɂ́A���̎�����l������܂ł��Ȃ��A�g�D�ĕҐŐ��ɌW��e�K���d�ʼn���̎�i�Ƃ��ė��p�������̂Ƃ������Ƃ͂ł����A�s�����v���ɊY������Ɣ��f���邱�Ƃ͍���ł���v�B�u������Ђ������I�Ȏ��ƖړI�̂���g�D�ĕҐ����s���ɓ�����A�ʏ�͑z�肳��Ȃ��菇����@�ł͂Ȃ��A���ԂƘ��������`������o������̂ł��Ȃ��A�s���R���̑S���F�߂��Ȃ������̎菇����@�̒�����ł��ŕ��S�̏��Ȃ����̂��̂����Ƃ��Ă��A���̂��Ƃ��璼���ɑg�D�ĕҐŐ��ɌW��e�K���d�ʼn���̎�i�Ƃ��ė��p�������̂Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��i�Ⴆ�A�����p����関�����������z�́A�����̎����ɂ���č��ق������邪�i�T�V���Q���A�R���A�T�V���̂Q���Q�Ɓj�A���������邩�͊�{�I�ɓ����҂̎��R�ł���A�����ɂ������I�Ȏ��ƖړI������ꍇ�ɂ́A�Ŗ���̌��ʂ��ő�ƂȂ鎞��������߂č��������s�����Ƃ��Ă��A���̂��Ƃ��璼���ɕs�����v���ɊY������Ɣ��f���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ɖ������B�j�B�v �@�u��ƃO���[�v���̓K�i�����̂����A�x�z�W������ɂ����Ȃ��ꍇ�i�x�z�W�K�i�����j�ɂ́A��L�v���ɉ����āA�]�Ǝ҈��p�v���y�ю��ƌp���v�����K�v�Ƃ���Ă���A�������ƓK�i�����ɂ��ẮA�X�ɋ������Ɨv�����K�v�Ƃ���Ă��邪�A���S�x�z�W�K�i�����ɂ��ẮA���@�Q���P�Q���̂W�C�̕�����A�����]�Ǝ҈��p�v���y�ю��ƌp���v�����̂�����ɂ��Ă��K�v�Ƃ���Ă��Ȃ��B�v�u�g�D�ĕҐŐ��ɌW��@�l�Ŗ@�T�V���Q�����̎�|�y�іړI�́A�g�D�ĕҐ��ɂ�莑�Y���ړ]����O��Ōo�ώ��ԂɎ����I�ȕύX���Ȃ��ꍇ�ɂ́A���̏��n���v�̌v����J�艄�ׂď]�O�̉ېŊW���p��������Ƃ������̂ł���A�o�ώ��ԂɎ����I�ȕύX���Ȃ����ۂ��f����Ȃǂ̂��߂ɁA�@�l�Ŗ@�Q���P�Q���̂W�y�т�������@�l�Ŗ@�{�s�߂S���̂R���ɂ����āA�K�i�����Ɣ��肷�邽�߂̋�̓I�ȗv������߂��Ă���v�B �@�u�퍐�́A�u�ړ]���Y���ɑ���x�z���p�����Ă���ꍇ�v�Ƃ��ẮA���Y�ړ]���Y���̉ʂ����@�\�̖ʂɒ��ڂ���Ȃ�A�퍇���@�l�ɂ����ē��Y�ړ]���Y����p���ĉc��ł������Ƃ������@�l�Ɉړ]���A���̎��Ƃ�������ɍ����@�l�ɂ����Ĉ��������c�܂�邱�Ƃ��z�肳��Ă���ȂǂƂ��āA�@�l�Ŗ@�T�V���Q�����́A���S�x�z�W�K�i�����̏ꍇ���܂߂āA�����ɂ�鎖�Ƃ̈ړ]�y�э�����̎��Ƃ̌p����O��Ƃ��āA�퍇���@�l�̗L���関�����������z�̍����@�l�ւ̈��p����F�߂����̂Ɖ����ׂ��ł���A�܂��A�퍇���@�l���u���Ɓv���c��ł������ۂ��́A���i�̎���Ȃ�����A�@�l�Ŗ@�{�s�K���R���P���P���̔����ɂ��ׂ��ł���Ƃ��āA���̂悤�Ȋϓ_����s�����v���̊Y�����f���ׂ��ł���|�咣����B�m���s�n�������Ȃ���A�d�Ŗ@����`�̌����ɏƂ炷�ƁA�d�Ŗ@�K�݂͂���ɋK��̕����𗣂�ĉ��߂�����g���K�p�����肷�ׂ��ł͂Ȃ��i�m�����Y�ƐM�p���Ɏ���>�E�Ŕ����a48�N11��16�����W27��10��1333�Łn�A�m�z�X�e�X��V�v�Z���Ԏ����E�Ŕ�����22�N3��2�����W64��2��420�Łn���Q�Ɓj�B�v�u���S�x�z�W�K�i�����̏ꍇ�ɂ����āA�u�����ɂ�鎖�Ƃ̈ړ]�y�э�����̎��Ƃ̌p���m�v�H�n���@�l�Ŗ@�T�V���Q�����̓K�p�́u�O��v�ƂȂ��Ă���Ƃ��A�u�����ɂ�鎖�Ƃ̈ړ]�y�э�����̎��Ƃ̌p���v���Ȃ����S�x�z�W�K�i�����ɏ�L�K���K�p���邱�Ƃ͂��̖{���̎�|�y�іړI�ɔ�����ȂǂƉ����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�v |
�۔F�K�肪�Ȃ��ꍇ�ɂ��۔F���F�߂��邩�ۂ��B�\�\�۔F�K��Ȃ��۔F��F�߂Ȃ��Ƃ���ƁA�d�ʼn�����s�Ȃ����҂ƒʏ�̖@�`����I�������ʂ̔[�Ŏ҂Ƃ̊Ԃŕs����(��q)�������Ă��܂����Ƃ����O�����B���A�ʐ��͔F�߂Ȃ��B�ō��ق̔��f�͂Ȃ��A�����R�̍ٔ���͕�����Ă���A�Ɛ��������B���A�ߔN�̍ٔ����(�ېŒ���)�A�۔F�K��Ȃ��۔F�͔F�߂��Ȃ��A�Ƃ������Ƃ�O��Ƃ��Ă����B���̑O��̉��A�ʂ̗��R�t���ɂ��۔F����̂Ɠ��l�̌��ʂ�������邩�A�ɋc�_�̏œ_�͈ڂ����B
�s�����ɂ��āc�c�d�ʼn�����s�Ȃ���҂͍������҂Ɍ����A�d�ŕ��S�̌����Ȕz���Ƃ����v���Ɉ�w������Ƃ������O�B�X�ɁA�ٌ�m�����d�ʼn���ɋ��ނ��Ƃ͎���(���])�̖��ʌ������A�Ƃ����ᔻ������B�A���A�d�Ŗ@�̕s���Ăȗ̈�ɐ������������炵�Ă�����Ƃ����Ӗ��őd�ʼn���ɂ͐ϋɓI�Ӌ`������Bcf.�n�Ӓq�V�u�d�ʼn���̌o�ϊw�F�s�����_��Ƃ��Ă̑d�Ŗ@�v�t�B�i���V�����E���r���[69��153��
�����p���w�X�^���_�[�h�����Ŗ@�x4��521�ňȉ�(�O�����A2024)�̗p��@
�d�ʼn��۔F�_1.0�F�۔F�K��Ȃ��۔F�͋�����Ȃ��B
�d�ʼn��۔F�_2.0�F�d�ʼn���̔۔F�ɋ߂����ʁi�����ېŒ����i�j�������炷�\���B
(�d�ʼn��۔F�_3.0�FBEPS��AGAAR�̐���A�@�l132����2�Ɋւ���u���x�̗��p�v�T�O�̐��A�Ő�[�̋c�_�͗����I�Ȃ̂Ŋw�������x���ł͗����ł��Ȃ��Ă��\��Ȃ��B)
�d�ʼn��۔F�_2.0�F�۔F�K��Ȃ��۔F�͔F�߂��Ȃ��Ƃ̑O��ł��A�[�Ŏ҂̑d�ŕ��S�y���̎��݂���������Ƃ͌���Ȃ��B
(1) �_��E�@���\���̐^�������[�Ŏ҂̎咣����ʂ�ł���Ƃ͌���Ȃ��B
(2) �d�Ŗ@�K�̉��߂��[�Ŏ҂ɓs���̗ǂ����Ƃ���ł͂Ȃ��B
(1)�@�����F��E���@��̖@���\���ɂ��u�۔F�v�\�\�[�Ŏ҂��咣����@���\��(��Ɍ_��)�̐^�������ے肳��A�d�ʼn�����������Ȃ��ꍇ�̂��ƁB�_�ٔ����ɂ���ĔF�߂��Ă��Ȃ��̂ŁA�d�ʼn�����۔F�����̂ł͂Ȃ��A���������d�ʼn�����������Ă��Ȃ��A�Ƃ��������B���ʓI�ɑd�ʼn����۔F���邱�Ƃɗގ����邪�A�ʏ팾����Ƃ���̑d�ʼn���̔۔F�Ƃ͈قȂ�̂ŁA���ʂ��́u�۔F�v�ŕ\�������B(��6�Ł�143.02���ݔ��������E������������11�N6��21�����ٖ�52��1��26�Łc�c�A�������F��E���@��̖@���\���ɂ��u�۔F�v��F�߂Ȃ���������)
(2)�@�ېŌ��ƋK��̌�������\�\�o�Ƃ����v�������Ήېł����Ƃ���Ƃ����K�肪����Ƃ���A����[�Ŏ҂��m���ɂo�Ƃ����v�������Ă��邪�A�d�Ŗ@�̓K�p�ɓ�����A���Y�ېŌ��ƋK��̎�|�E�ړI�ɏƂ炵��������Ă͂��Ȃ����p�Ƃ����v�����������Ă��Ȃ��ƉېŌ��Ƃ̉��b��^���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��A�Ȃǂ̉��߂����邱�Ƃɂ��A�[�Ŏ҂̑d�ŕ��S�y���̎��݂�ׂ����ƁB�d�Ŗ@�K�̉��߂̈�ԗl�ł���A�۔F�K��Ȃ��۔F�ł͂Ȃ��A�Ɛ��������B(��6�Ł�143.03�O���Ŋz�T���]�T�g�肻�ȋ�s�����E�Ŕ�����17�N12��19�����W59��10��2964��)
(2)�̑��̗�
6�Ł�143.04�p���c�B�[�i����(�t�B�������[�X����)�E�Ŕ�����18�N1��24�����W60��1��252��(���R��(1)�����F��E���@��̖@���\���ɂ��u�۔F�v�̗�Ɨ���������Ƃ���A�ō��ق͗��R��(2)�ېŌ��ƋK��̌�����߂ɕς���)
5�Ł�322.05(6��403��)�I�E�u���V���z�[���f�B���O�����E�Ŕ�����18�N1��24����53��10��2946��
������Ƃ������F��Ƃ�����ʘ_�Ƃ��Ę_���邱�Ƃɂ��܂�Ӗ��͂Ȃ��B���ƂȂ��Ă����̓I�ȋK��⎖���W�ⓖ���҂̎咣�̍I�قɍ��E�����B
�����s�ׂ̐����ƍ��킹�āA���̕\���쐬(�A�����̕\�͐�ȓƎ��B����ł͂Ȃ�)�B
| �ٔ��ߒ� | �� | �@�I���� |
| ���`�������F�� | ������B���A�U�̈�ӂ��������_���؋��Ƃ��Ē�o����A�ȂǁB | �E���i�w�}���T�̏��x�w�`�F�C�X�x�j |
| �^�ӂ̔F��(���_�����) | �_�ɏ����Ă���ʂ�̐^�ӂ�L���Ă���ƔF�߂��邩�ۂ��B�Ⴆ�A���L�����b���牳�Ɉڂ��Ƃ����^�ӂ����������ۂ��B�d�ŕ��S�y����_�����_��̐^�ӂ�ے肷�邱�Ƃ͈�ʘ_�Ƃ��Ă͍���B | �^�ӂ��Ȃ���������s���B�d�ʼn��s�����B�E�ł��͌��E���B���q�͒E�łƉ����B |
| �^�ӂƈقȂ�_����� | �`�Ƃ����_��(��:����)��^�ɈӐ}���Ă��邱�Ƃ��F�߂��Ă��A������O�I�Ȃ���ٔ��������̐^�ӂɑ������@����̌��ʂ�F�߂��A�a�Ƃ����@���\��(��:�ݎ�)��F�肷�邱�Ƃ��J���@�E����ҕی�@���݂ł��肤��̂ŁA�d�Ŗ@���݂ł����肤��̂ł�(�٘_����)�Bblog | �����E�łƌĂԎ҂͋��炭���Ȃ��B���@��̖@���\���ɂ��d�ʼn�����������Ȃ������B |
| �d�Ŗ@�K�̉��� | ���@��̖@���\���Ƃ��Ă͂`�Ƃ����_��ł��邱�Ƃ��ے�ł��Ȃ��ꍇ�A�d�Ŗ@��Ǝ��ɖ@���\�����č\�����邱�Ƃ͓��{*�ł͋�����Ȃ��B | �۔F�K��Ȃ��۔F�͔F�߂��Ȃ��B�������**or�۔F�K��őΏ��B |
**Cf.��164.03 Gregory, 293 US 465 (1935)�c����@���̃A�����J�ł́A�����I�۔F�K�肪�Ȃ��Ƃ��A�K��̎�|�����Ă��A���ƖړI���Ȃ�����ɂ��đd�ʼn����ׂ��Ⴊ����B([���]�p�Ăŋ������Ȃ���{�ł������H�A�Ɛq�˂���ƁA���������č���B)
(1)�̎����F��E���@��̖@���\���ɂ��u�۔F�v�̉ۂɊւ��āB
|
�����s���Ƃ��ꂽ��6�Ł�422.01�����؏����^�����E���É���������10�N12��25����46��6��3041�ŕS�I7��81kp ���a60�N�A������q�ւ̕s���Y���^�̌����؏����쐬�B����5�N�A���L���ړ]�o�L�B���L���ړ]�o�L������ƐŖ����ɏ�`���̂ŁA�ېł�����(����7�N)��҂��ĒE�ł�}�낤�Ƃ����B �����́A�s���Y�̏��n�����a60�N�ł͂Ȃ�����5�N�ɂȂ��ꂽ�ƔF�肵���B �y�E�ŖړI�����珊�L���ړ]�̐^�ӂ��F�肳��Ȃ�������z�Ɨ������Ă͂Ȃ�Ȃ��B�E�ł̈Ӑ}�����邩�炱���A���@��̐^�ӂƂ��āA���a60�N�ɏ��n����Ƃ����ӎv������Ƃ��������ɌX�����Ƃ����肤��(cf.6�Ł�143.04�p���c�B�[�i����(�t�B�������[�X����)�E�Ŕ�����18�N1��24�����W60��1��252��)�B�{���ł͗l�X�ȏ؋��ɏƂ炵�ď��a60�N�����̏��L���ړ]�̐^�ӂ��Ȃ��ƔF�肷�邱�Ƃ��\�ł������A�Ƃ������Ƃł��낤�B �]�k:���F��v�m�̃Z�~�i�[�Ŏ������Ƃ��邪�A����͋����Ƃ��H |
|
�_����߂����ߎ�ƂȂ�����5�Ł�165.01(6�łȂ�)�ۍg�ѓc�����E�����������a55�N5��29���s�W31��5��1278�� �y�n�������̈ړ]�����n�S���ł����ď��n�������������Ȃ����A���̑㕨�ٍ��ł����ď��n�������������邩�A������ꂽ��B �u�����F��v�ɂ��ېł̈Ⴂ�A�Ƃ����邱�Ƃ����邪�A���`�̎����F��ł͂Ȃ��A��̕\�ł́u�^�ӂ̔F��(���_�����)�v�̖��B�u�����F��v�̍L���ɒ��ӁB ��R�͏��n�S�ۂł���ƔF�߂㕨�ٍς�O��Ƃ����ېŏ����������ł͂Ȃ��Ƃ������A��R�͑㕨�ٍςł���ƔF�߂��B |
|
�����s�ׂłȂ��Ƃ��ꂽ��6�Ł�143.02���ݔ��������E������������11�N6��21������1685��33�ŕS�I7��18lk (�ޗ�F�ݎ����E������������14�N3��30����49��6��1808��) �w�͖{���y�n�i�`�E�a�E�b�j�����L���Ă����Ƃ���A�n�グ������ł������o�u�����A�c��悩�甄�p�������B�w�͂قړ����̓y�n�����A�����o��E������d�����Ƃ��ł���悢�A�Ƃ����B�����ŁA�w���c���ɖ{���y�n��7���~�i���y�@�̕s�������z�ł������j�Ŕ��p���A�قړ����̋ߗדy�n�i�d�y�n�Ƃ���j��4���~�ōw�����A���E�c���Ƃ���3���~�̌�t�����B�����w�E�c��悪�_�ʏ�ō̗p�����@�`���́A�e�ʂ����ݔ����{�������ςł������i�{���y�n�Ɋւ�����n�������z��7���~�j�B �x�Ŗ������́A�{���y�n�Ɋւ�����n�����̌v�Z�ɓ�����A7���~�̉��l�̂���擾�y�n�i�d�y�n�j�y��3���~�̍������擾�����̂ł��邩��A�{���y�n�̏��n�ɌW��������z��10���~�ł���Ƃ��āA�X�����������s�Ȃ����B�����x�̗̍p�����@�`���́A�s����̂̕⑫���t�����ł���A�Ƃ������̂ł������B �w�@�@�@�@�@�@�@�@�@�c�@�@�b�@�w�@�@�@�@�@�@�@�@�@�c�@�@ �����V���~�i���p�j�@�@�@�@�b�@�����i�����j �@�i���p�j�y�n�S���~�����@�b�@�@�i�����j�y�n�V���~���� �@�@�@�@�i�����R���~�j�@�@�b�@�@�@�@�i�⑫���R���~�j ��R�@�������p�@�⑫���t�����ƔF��B �T�i�R�@�T�i�F�e�A����������A�����F�e(�m��) �@���ݔ����̖@�`���́u���n�����ɑ���ŕ��S�̌y����}�邽�߂ł��������Ƃ��A�D�ɐ��F�ł���v�B �@�m���Ɍ����Ƃ����_��ތ^�̕����u���̂ɂ��K�����Ă��蒼�B�ł���v���A�u���n�����ɑ���ŕ��S�̌y����}��Ƃ����l������A���I���Ȗʂ̂�������ł���v���ݔ����́u�@�`�����̗p���邱�Ƃ�������Ȃ��Ƃ��ׂ������͂Ȃ��v�B �@�u�����ҊԂ̐^�̍��ӂ��c�⑫���t�����_��̍��ӂł���̂ɁA������B�����āv���ݔ����Ƃ��āu���������Ƃ����ꍇ�ł���c�B�����ꂽ�^�̍��Ӂv�ł�������u��O��Ƃ����ېł��s����ׂ��v�B�������A�{���ł͉B�����铮�@�ɖR�����A�u�{������ɂ����č̗p���ꂽ�E�����_��̖@�`���������̂��̂ł���Ƃ��邱�Ƃ͍���v�B �@�u�d�Ŗ@����`�̉��ɂ����ẮA�@���̍����Ȃ��ɁA�����҂̑I�������@�`����ʏ�p������@�`���Ɉ��������A����ɑΉ�����ېŗv�����[�����ꂽ���̂Ƃ��Ď戵���������ېŒ��ɔF�߂��āv�Ȃ��B �@�����Ŗ@59���i�݂Ȃ����n�j(�ېŌJ�����4.2.3.5.)�����邪�A�{���ł́u�������Ⴂ�Ή��ɂ����n�ɓ�����Ȃ��ȏ�A���̌y�����ꂽ�����ɑΉ�����ېŕ��S�͌�ɌJ�艄�ׂ��邱�Ƃ�@�����̂��\�肵�Ă���v�Bhj [���ӁI]�d�Ŗ@�w�҂͑��ݔ����������d�v�����邪�A�ېŒ��s�i�����ł͂Ȃ��B�i�@�������ɂ����đ��ݔ������������Ă͂Ȃ�Ȃ����A�����ɏA���Ă���́y���ݔ������������邩��_��̐^�����͍ٔ����ɔF�߂Ă��炦�锤�z�Ɗy�ώ��ł��Ȃ��B ������������19�N10��30����54��9��2120�Łc�c�C�ӑg����ʂ��ē����������n�v�i�Ɣ[�Ŏґ����咣������́j���A�����g���_���ɂ����闘�v�̕��z(�G����)�Ƃ��ꂽ��B�c���G���E�W�����X�g1394��122�ł͔��|�ɔ��B |
3.1.3.3. �@�߉��߂̌��E
| 6�Ł�143.03�O�ōT���]�T�g�肻�ȋ�s�����E�Ŕ�����17�N12��19�����W59��10��2964�ŕS�I7��19js(�g������E�����1937��184��) �����E���_�c�c�N�b�N�����@�l�b�Ё������@�l�a�Ђ̗Z���_��Ƃ������ƂɁA�����w�Ђ����`�݂�������B�b�Ђ��w�Ёi�̃V���K�|�[���x�X�j�ɗa�����A�y�тw�Ёi�̃V���K�|�[���x�X�j���a�ЂɗZ������A�Ƃ����@�`���B �@�w�Ђ͂a�Ђ������葽���b�ЂɎx�����̂ő��ł���B���A�@�l�Ŗ@69���O���Ŋz�T���ŁA�w�Ђɂ��]�T�g������Ƃ���ƁA�O���Œ��ł��ꂽ�������̐Ŋz�͓��{�Ŕ[�߂�ׂ��Ŋz����T�������B���ǁA�O���Ŋz�T���ɗ]�T�g������ꍇ�A�w�Ђ��O���Ŕ[�߂��Ŋz�̕��������{�ł̐Ŋz������̂ŁA�w�ЂɂƂ���15�̊O���Ŋz�͎����I�ɕ��S�ƂȂ�Ȃ��B�w�Ђ͂��̗]�T�g���a�ЁE�b�Ђɔ������Ƃ������Ƃł���B �@����������ł͌��Ǔ��{�̐Ŏ���15���邱�ƂƂȂ��Ă��܂��B�����ŁA���̂悤�ɂ킴�ƊO���Ŕ[�ł����Ƃ����`���𐮂����ꍇ�ɂ܂ŁA�O���Ŋz�T�����x�ŋ~�ς���ׂ��ł͂Ȃ��̂ł͂Ȃ����A�Ƃ��������ƂȂ����B�Ⴆ�A�w���{������Ƃ͕ʂ�1000�̍��O�����Ă���A�O����200�̉ېł��A���{�̐ŗ���30���ł���Ƃ���ƁA���Ŋz�����݂�300�ł���A300�|200��100�̗]�T�g�����邱�ƂƂȂ�B�{������̌��ʁA���O������1000����1004�ɂ��������Ȃ��i�{������ł�100�̗��q�����A96�̗��q�x�o�ł��邽�߁j�A���Ŋz��300����301.2�ɂ��������Ȃ����A�O���Ŋz�T���z��200����215�ƂȂ�A���{�ւ̔[�Ŋz��100����301.2�|215��86.2�Ɍ�������c�܂�N�b�N�����̌����Ŋz15�̖w�ǁi13.8�j�����{�ł̊O�ōT���Ɏg����B �@������A����13�N�����E�@�l�Ŗ@69���y�і@�l�Ŗ@�{�s��141��4���ɂ��A���̂悤�Ȉُ�Ȏ���͊O���Ŋz�T���̓K�p�Ώۂ��珜�O����邱�Ƃ����������ꂽ�i�n�ݓI�K��H�m�F�I�K��H�j�B �w����݁@�@�b�@�@�w����݂���ꍇ �@�@�@�@�@�@�b �P�T�a�Ё@�@�b�@�P�T�a�Ё\�\�\�\���w���x�X�c�c�w�� �@���b�@�@�@�b�@�@���@�@���q�W�T�@�@�b�@�@�@�P�T�� �@��b�@�@�@�b�@�@��@�@�@�@�@�@�@�@�b���q�@�@�O�b �@���b���q�@�b�@�@���@�@�@�@�@�@�@�@�b�X�U�@�@�œ��{ �@�����W�T�@�b�@�@���@�@�@�@�@�@�@�@���@�@�@�@�T �@�b�Ё@�@�@�b�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�Ё@�@�@�@�� ���R�@���̂悤�ɂ��Č������������Ă����B�i���R�ł͂Ȃ��ō��ٔ��|����̔����B�����E��ȁj �u(1)�@�{������̌o�ϓI�ړI�́C�b�Ћy�тa�ЂɂƂ��ẮC�b�Ђ���a�Ђւ��Ⴂ�R�X�g�Ŏ������ړ������邽�߁C�w����邱�Ƃɂ��C���̊O���Ŋz�T���̗]�T�g�𗘗p���ăN�b�N�����ɂ����錹��ł̕��S���y�����邱�Ƃɂ���C��㍐�l�ɂƂ��ẮC�O���Ŋz�T���̗]�T�g����C�����邱�Ƃɂ���̂ł���B���̂悤�Ȍo�ϓI�ړI�Ɋ�Â��ē����҂̑I�������@���W���^���̖@���W�ł͂Ȃ��Ƃ��āC�{������������s���ł���Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B �@(2)�@�w�́C���Z�@�ւ̋Ɩ��̈�Ƃ��āC�a�Ђւ̓����̑����I�R�X�g��ቺ���������Ƃ����b�Ђ̈Ӑ}��F��������ŁC����̊O���Ŋz�T���̗]�T�g�𗘗p���āC���R�X�g�̒Ⴂ���Z����C���̑Ή��������s�������̂Ɖ����邱�Ƃ��ł��C���ꂪ���ƖړI�̂Ȃ��s���R�Ȏ���ł���ƒf���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B���������āC�{��������O���Ŋz�T���̐��x�𗔗p�������̂ł���Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B�v ���|�@�@�ō��ق͎��̂悤�ɔ������Č����̐��������p�����B �u�{������́C�S�̂Ƃ��Ă݂�C�{���͊O���@�l�����S���ׂ��O���@�l�łɂ��ĉ䂪���̋�s�ł����㍐�l���Ή��Ĉ����C���̕��S�����Ȃ̊O���Ŋz�T���̗]�T�g�𗘗p���č����Ŕ[�t���ׂ��@�l�Ŋz�����炷���Ƃɂ���ĖƂ�C�ŏI�I�ɗ��v�悤�Ƃ�����̂ł���Ƃ������Ƃ��ł���B����́C�䂪�����O���Ŋz�T�����x�����̖{���̎�|�ړI���璘������E����ԗl�ŗ��p���Ĕ[�ł�Ƃ�C�䂪���ɂ����Ĕ[�t�����ׂ��@�l�Ŋz��������������C���̖Ƃꂽ�Ŋz�������Ƃ��闘�v������W�҂����邽�߂ɁC������̂ɂ���Ă͊O���@�l�łS����Α����������邾���ł���Ƃ����{������������čs���Ƃ��������ł����āC�䂪���Ђ��Ă͉䂪���̔[�Ŏ҂̕��S�̉��Ɏ���W�҂̗��v��}����̂Ƃ����ق��Ȃ��B��������ƁC�{������Ɋ�Â��Đ����������ɑ���O���@�l�ł�@�l�Ŗ@�U�X���̒�߂�O���Ŋz�T���̑ΏۂƂ��邱�Ƃ́C�O���Ŋz�T�����x�����p������̂ł����C����ɂ́C�ŕ��S�̌��������Q������̂Ƃ��ċ�����Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���B�v �����@�i��3.1.3.3.�j���R��(1)�́A�����F��E���@��̖@���\���ɂ��u�۔F�v�i�����́A�����s�ׂł���Ƃ������R�ɂ��u�۔F�v�j�ɑΉ����A (2)�́A�ېŌ��ƋK��̌�������̍����Ƃ��āA�{���̉I��I�Ȏ�������ƖړI�̂Ȃ�����ł��邩��@�l�Ŗ@69���͓K�p����Ȃ��A�Ɖېœ��ǂ��咣���Ă������ƂɑΉ�����B�����A�ō��ٔ����́A����I�ȗ��R�ʼn��ł������̂�������ɂ����i����������������Ă��邱�Ƃ͔���ł͂Ȃ��B�j�B���Č���łƂɂ������_�����o�����A�Ƃ������Ă��܂��B�{�����̎˒��ɂ��Ă͕s�����i�ō��ق́A�����点�Ȃ��悤�ɂ���앶�������Ă��Ă���(?)[���]��|���肪����q�ׂ��Ă������A�t�ɂ����Ǝ�|����ƂȂ肻���Ȃ��̂����炸����ׂČ���I�ȗ��R�t�����킴�ƞB���ɂ��Ă���悤�ɂ������Ă��܂��B�j�B �@�Ȃ��A���ƖړI�]�X�Ƃ��������́A�A�����J��5�Ł�164.03�O���S���[����(Gregory v. Helvering, 293 U.S. 465 (1935))�̌���jt�����n�ɂ������̂ł��邪�A[���]���{�Ő����Ȏ��ƖړI�̌������Ó�����̂��́A�܂��悭������Ȃ��B���R�́u���ƖړI�v�Ƃ�������I�ɗp�������A�{�����ł������Ȏ��ƖړI�̌������ӎ��������̂悤�ȋL�q������ɂ͂���i�ǂ̕������͊e���ŒT���āj�B�A�����J�ɂ�����d�ʼn���̔۔F�͐���@�i�d�Ŗ@�Ȃǁj�̔w��ɂ���R�����E���[�ɂ��Ƃ���Ă��邪�i�A�����@��̐�������ł͂Ȃ��A�d�Ŗ@�̉��߁j�A���{�ɃR�����E���[�̊T�O�͂Ȃ��B���{�ɒu��������ƁA�d�Ŗ@�̔w����@�̈�ʌ����������āA���ꂪ�d�ŕ��S�y���̎��݂�ׂ����Ƃɂ���p����A�Ƃ������_�ƂȂ낤���H �@�̈�ʌ����̈�ł����������p�_��{�����͎�������ł���̂��ۂ��Hju �@�{�������u���p�v�Ƃ������p�����̂ŁA���̌�A���t�[�����E�Ŕ�����28�N2��29�����W70��2��242��(��3.1.3.2.)�ł��@�l�Ŗ@132����2(�g�D�ĕ҂Ɋւ���۔F�K��)�̓K�p�Ɋւ��u���p�v�Ƃ������p����悤�ɂȂ����i���u���p�v�̈Ӗ��ɂ��Ă͊w���㗝����������Ă���B��w�@���x���Ȃ̂ō��͕�����Ȃ��Ă悢�j�B �@�肻�ȋ�s�k����a��s�l�����E�Ŕ�����17�N12��19��(�ېŌ��ƋK��̌�����߂Ƃ������q�G���͓��Ă͂܂�Ȃ��Ƃ���_�҂�����)�ƎO��Z�F��s�k���Z�F��s�l�����E��㍂������14�N6��14������49��6��1843�Ŕ���1816��30�Ŕ��^1099��182��(�����i)(�ېŌ��ƋK��̌�����߂Ƃ������q�G���͓��Ă͂܂�₷��)�Ƃ̈Ⴂ�ɂ��āA�c�������u�d�Ŗ@��̌�����߂Ɨ��p�\�\�g�D�[���~���̋c�_�}�����Q�Ƃ��āv�Ō�228��27-31�ŁA���J���j�u�d�Ŗ@����`�͂����Ȃ�ԗl�őd�Ŗ@���߂�g�Â��Ă��邩�\�\�u�c�_�v�̍\������̃A�v���[�`�v�@������97��6��70-75�ŁB |
| �����F��E���@��̖@���\���ƌ�����߂̕���(�O�ōT���̎���ł͂Ȃ�) 6�Ł�143.04�p���c�B�[�i����(�t�B�������[�X����)�E�Ŕ�����18�N1��24�����W60��1��252�ŕS�I7��20kf(��ȏ͔@�E�@��125��10��2363��) �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�z���_���� $6000�� ���������K�̗���@�@�@�@�@�c�Ё@���������������������@�e�� �������f��̌����̗���@�@�����@������������������(����/�z��) �d�d�����ҁ@�@�@�@�@�@�@�ۄ����@�f���z�����@�@�@���� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ 100�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����f �@�@�@�@�@�@�f��s�@�@���x�����f�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�f������ �@�@�@�@�@�@�@�ۏ@�@�~��������@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�愫���� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�z�����z�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���������@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�L���� �@�@�@100���~ �ؓ����ԍρ@�������@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������ �@�@�@�������������������@�����@�@�@�@�@�f�揊�L���@�@���� �d��s 64���~ �{���ؓ����@�a�g���@���������������������b�� �@�@�@�������������������@�����F�@�������������������� �@�@�@�@�@�@�萔���������������F�@86���~ �f���� �@�@�@�g�،��@�S���~�@�@�o�����F �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@26���~�����������p���� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�w��g���� �����E���_�@�����w�͂a�g���ɎQ���B�a�g���i�{���g���j�͂b�Ёi�W�F�l�V�X�j����e�Ёi�b�o�h�h�j����̉f����w�����A�c�Ёi�h�e�c�j�ɉf��z������i�X�ɂc�Ђ��e�Ђɔz������j�B�a�g���͂d��s�i�I�����_��s�j����؋����A100���~��ԍς��Ȃ���Ȃ�Ȃ����A�c�Ђ��a�g���Ɏx�����ׂ��f��z�����̑Ή��Ƃ��Ă�100���~�x�����ɂ��Ăf��s���ۏ��Ă���̂ŁA�a�g���͖w�ǖ����X�N�ł���B�a�g���́A�f�悪�q�b�g����Δz���_��Ɋ�Â����v�����邪�A�f��t�B�����̏��L�҂Ƃ����������p�������S����B�������p��̕��S�������a�g���̑g�����ɂƂ��Ă̐Ŗ���̃����b�g�ƂȂ�B�f��͑ϗp�N�����Z�����ߌ������p��傫���Ȃ�B(���͗��@�őΏ�)jw ���R�@�u���@��̐^�̈ӎv�́A�e�Ђɂ����Ă͖{���f��Ɋւ��錠���̍���������ۗL�����܂܂Ŏ������B��}�邱�Ƃɂ��v��B�u�w�̏o�����́c�{���f��̋��s�ɑ���Z�����s�������̂ł����āA�{���g���Ȃ������̑g�����ł���w�́A�{������ɂ��{���f��Ɋւ��鏊�L�����̑��̌�����^���擾�������̂ł͂ȁv���B(�ō��ٔ���������̈��p) ���|�@�u�{���g���́A�{�������_��ɂ��{���f��Ɋւ��鏊�L�����̑��̌������擾�����Ƃ��Ă��v�u�{���f��́c�{���g�������Ƃ̗p�ɋ�����������̂Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ�����A�@�l�Ŗ@�c31��1���ɂ����������p���Y�ɂ�����Ƃ͔F�߂��Ȃ��B�v �����@���R�́u�^�̈ӎv�́v���@3.1.3.2.�̒��́u�^�ӂ̔F��i���_����߁j�v�̕����ŏ����B �^��F�d�ʼn�����Ӑ}���Ă��邩�炱���A�^�ӂƂ��Ă͉f��̏��L�����擾����ӎv�����������ł́H �ʉ��߁F�^�ӂƂ��ď��L���擾�̈ӎv�������Ă��A�ٔ���������I�Ɂy�^�ӂƈقȂ�_����߁z�������B�i3.1.3.2.�̐����͂܂���������ĂȂ��B�ٔ��������̂悤�ȉ���I�ȔF������锤���Ȃ��Ƃ����_�҂��炷��A�����܂Łu�^�ӂ̔F��i���_����߁j�v�ł̏����Ƃ������ƂɂȂ�B�j �@������ɂ��挴�R�́A�d�Ŗ@�̓K�p�̖��Ƃ��ď��������̂ł͂Ȃ��B�����܂Ŏ��@��̖��Ƃ��ď����B �@���R�̍l�����ɂ��ꍇ�ɁA�[�Ŏ҂̎��݂͒E�łƂ��ČY���ӔC���̂��A�Ƃ����_�_������B �@�ō��ق́A�u�擾�����Ƃ��Ă��v�Ƃ����\�������Ă���̂ŁA���̔��f���瓦���Ă���ma�B���@��̔F�肪�ǂ��ł���A�u�d�Ŗ@�K�̉��߁v�̗̈�Ŕ[�Ŏ҂̊�ׂ݂͒��Ƃ��Ă���B �@�q��@��D���𗘗p�������Ăł͔[�Ŏґ����i�Ŋm�肵�Ă���B �@NBB�q��@���[�X�����E���É���������17�N10��27���Ŏ�255������10180(�㍐���Ȃ��܂܊m��) �@�D�����[�X�����E���É���������19�N3��8������18(�s�R)1���Ŏ�257������10647�E�Ō�����20�N3��27������19(�s�q)185���Ŏ�258������10933�s��(���J�h��Y�����c�k�i�u�C�O���Ƒ̂̉ېŏ�̈����v���q�G�ҁw�d�Ŗ@�̔��W�x639�ŁA�L��t�A2010)�c�c�P�C�}����LPS(limited partnership)�����{�̐Ŗ@��g���ɓ�����̂�(�����g���ɓ�����Ȃ��̂�)�A�ېŒ��̂����G�����ł͂Ȃ��A�s���Y�����ł���B |
3.1.3.4. �[�Ŏ҂��d�ʼn��ړI�Ǝ����F��
|
6�Ł�142.01���x�m�����E�Ŕ�����23�N2��18���W��236��71�ŕS�I7��14jf ���x�m�n�Ǝҕv�w�����j�w�ɃI�����_�@�l(���x�m���x�z)�̎���(1653���~�]�����O���Y)�^�B�w�͍��`�ݏZ�ł�����{�̑��^�ʼnېł̗v���̈�ł���u�Z���v(���@22���F�����̖{��)�����{�ɂȂ��Ǝ咣�����B�w�́A���^�����N�ɂ����āA���`�ɑ؍݂��Ă������Ԃ̕��������i���`�F65.8���A���{26.2���j�B ��R�@�u�q�ϓI�����v�Ɋ�Â��ďZ���肷��B�u���Z�ӎv�v�́u��[�I�ȍl���v�f�v�B ��R�@�u�q�ϓI�����v�y�сu���Z�ӎv�𑍍����Ĕ��f����v�c�q�ϓI�����Ƌ��Z�ӎv������̊W�B �ō��ف@�u�q�ϓI�ɐ����̖{��������̂�������Ă��邩�ۂ��ɂ���Č����ׂ����̂ł���A��ϓI�ɑ��^�ʼn���̖ړI���������Ƃ��Ă��A�q�ϓI�Ȑ����̎��̂����ł�����̂ł͂Ȃ��v�B�c�u���Z�ӎv�v�̈ʒu�t���ɂ��Č��y���ĂȂ����̂́A���@�w���̂�����ϐ��ł͂Ȃ��q�ϐ����̂������̂Ǝ~�߂��Ă���B �@���䗾�����E�ő唻���a29�N10��20�����W8��10��1907�ł��Ŕ����a35�N3��22�����W14��4��551�ł����菊�Ƃ��Ă���B�ǂ�����I���Ɋւ���Z���̔���ɂ��Ă̔���ł���B�Z���̔����͉��̂��߂̏Z�����肩�ɂ���ĕς���A�Ƃ����l���������@�w���ŗL�͂̂悤�ł���i�����A�ؗp�T�O�̖��Ƃ��čl���Ă��A�d�Ŗ@�̓K�p�ɂ����ď]���̔���̊�ɏ]��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ͌�����Ȃ��j���A�{����R�E��R�E�ō��قƂ��A�����ŁE���^�œƎ��̏Z���������l���悤�Ƃ͂��Ă��Ȃ��悤�ł���B �@cf.�Z���Ɋւ���Guglielmo Maisto ed., Residence of Individuals under Tax Treaties and EC Law (EC and International Tax Law Series, Vol. 6, IBFD 2010)�G�쓇���X�u���@�̌n�ɂ�����w�Z���x�K��̒n�ʁv�@��58��8��1121�ŎQ�ƁB �@�Ȃ��A2000�N�O��Ɋ���̍��ő����ŁE���^�ł̉ېőΏێ҂͈̔͂��g�[����@�������Ȃ���Ă���B���{�ł͕���11�N�����ɂ��A����12�N4��1���ȍ~�̑����E���^�ɂ��āA5�N�����O�ɏZ����L���ċ��Z���Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��A���̋K�肪�݂���ꂽ�B�������Ŗ@1��3�A1����4�B �@����͑����Ŗ@�̑��^�łɊւ��鎖��ł��邪�A�����Ŗ@�Ɋւ��Ċ������n�����ېʼn������Ƃ��ă��j�}�b�g�����E������������20�N2��28�����^1278��163�œ�������Bjg |
3.1.3.5. �����I�Ή��̕K�v��
5�Ł�322.05(6��403��)�I�E�u���V���z�[���f�B���O�����E�Ŕ�����18�N1��24����53��10��2946��3.1.4. �M�`��(���@1��2��)
3.1.4.1. �d�Ŗ@�߂̉��߂Ɋւ���[�Ŏ҂̐M���ی�
3.1.4.2. �M�`���̓K�p�v��
|
6�Ł�144.01��ޔ̔��ƎҐF�\�������E�Ŕ����a62�N10��30������1262��91�ŕS�I7��17hm �w�͂`(���Z���`��)�����ޔ̔��Ƃ�����������p���ʼn^�c���A�F�\��(�`�͏��F����Ă������w�͖��葱��)�Ő\�������B��ŐF�\���̌��͂�Ŗ������͔۔F�ł��邩�H �M�`���̎l�v���c�c(1)���I�����̕\���A(2)�M�����čs���A(3)�\���ɔ�����s�ׁA(4)�[�Ŏґ��ɋA�ӎ��R���Ȃ��B ��ʘ_�Ƃ��ĐŖ��ł��M�`��(�֔����̖@���Ƃ�����)�̓K�p�\�����F�߂��Ă���B�����Ẳ����Ƃ��ĐM�`����F�߂����Ă�(���炭)�Ȃ��Bhn |
|
5�Ł�166.02(6��106��)�����w�@�����E�����������a41�N6��6���s�W17��6��607�� �Ŗ������������w�ɑ�����Ɋ�Â��Œ莑�Y�ł��ېłƂ���|�̒ʒm�������B��������ɂw���w�Z�@�l���łȂ����ߔ�ېŗv���ɊY�����Ȃ����Ƃ����������B�k�y���ĉېł��邱�Ƃ̓K�ۂ₢���ɁB ��R�@�M�`���܂��͋֔����̖@���̓K�p��F�߁A�w���i�B �T�i�R�@�T�i�F�e�E����������i�w�s�i�j�@�u�֔����̖@���Ƃ́c���Ȃ̌���(�\��)�ɂ�����l�����Ă��鎖������M���������҂́A���̌�M�Ɋ�Â��A���̎�����O��Ƃ����s���i�n�ʁA���Q�W��ύX�j�������l�ɑ��A����Ɩ��������������咣���邱�Ƃ��ւ�����A�Ƃ���v���̂ł���B�u��ʂɁA�֔����̓K�p�����\���Ƃ́A�����̕\���ł��邱�Ƃ�v���A�P�Ȃ�ӌ��������͈ӌ��̕\���ł͑��肸�A�܂��A�֔����̓K�p��F�߂����@�Ȍ��ʂ���ꍇ�ɂ́A���̓K�p��j�p������Ɖ�����Ă���v�B �@�u�E�ʒm�ɂ�����A��M�̂䂦�ɂw�����i�̍s���������Ƃ����̂ł��Ȃ��v�B�u�g�D�ύX�����Ȃ������̂ł����āA�����A�w�͂��̌����[�߁A���S���ď]���ǂ���̊w�Z�o�c�𑱂����Ƃ����ɂ����Ȃ��v�B [���]�Ŕ����a62�N10��30���͐M�`����4�v�������������A�����������a41�N6��6����5�ڂ̗v��(��@�Ȍ��ʂ��������Ȃ�)�������Ă���B�d�ł��ۂ��ׂ��Ȃ̂ɉۂ��Ȃ��Ƃ���ΑS�āu��@�Ȍ��ʁv�ɂȂ邩����͋֔����͓K�p���ꂦ�Ȃ��A�Ƃ������ƂɂȂ邩�A�w������ϋl�߂��Ă��Ȃ��B �@�Ȃ��A1�ڂ̗v���Ɋւ��u�����̕\���v�łȂ�������Ȃ��Ə�����Ă��邪�A�Ŕ����a62�N10��30���ɂ́u�����̕\���v�łȂ���Ȃ�Ȃ��Ƃ͏�����ĂȂ��B�u�����̕\���v�ł͂Ȃ��\��(�ӌ��ɂƂǂ܂�ꍇ�Ȃ�)�ŐM�`���E�֔������K�p����Ȃ��̂��ɂ��āA�w������ϋl�߂��Ă��Ȃ������B�^�L�Q�������E�Ŕ��ߘa2�N3��24������2467��3��(��4.2.3.5.�݂Ȃ����n)�F�ꍎ��⑫�ӌ����A�ʒB���M�`���̋N������u�\���v�ɓ�����Əq�ׂ��B |
��ېł̎�����Ԃ��ςݏオ�鎖�ɂ��A�M�`����A��ېł����Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ邩�H(��2.2.4.1.h�ʒB)
���@���̌���(��2.2.1.1.c)�Ƃْ̋��W
[���]�`���I�ɂ����āA�@�̐��������߂�m��Ȃ������[�Ŏ҂ɂ��ĕی삵�Ȃ��Ă悢�A�Ɠ˂��������Ƃ��l�����Ȃ��ł͂Ȃ��B�������A�����ŁA�ېœ��ǂ̌�����M�����҂����̌����ɏ]���Ĉ��̍�ׁE�s��ׂ��Ȃ��Ă����Ƃ���Ɓi�Ⴆ�Ώ����T���E�����Z��������ƐM���Ċ�hk����Ȃǂ����ꍇ�j�A�M�`���E�֔�����F�߂Ȃ���Δ[�Ŏ҂̗\���\�����i�`���I�ɂ͂Ƃ�����������́j�Q�����B
3.1.4.3. ���Z���ɂ�����u�����ȗ��R�v
�X�g�b�N�E�I�v�V�������Z�Ŏ����E�Ŕ�����18�N10��24�����W60��8��3128��(��4.2.6.2.�t�����W�E�x�l�t�B�b�g)6�Ł�225.03�q��@���[�X���Ɠ����g�������E�Ŕ�����27�N6��12�����W69��4��1121��(��4.2.5.�s���Y����)
3.2. �d�ő��א��x
3.2.1. �Ӌ`
3.2.2. ���łɊւ���s���\���葱
3.2.2.1. �R�������O�u��`�̌���
75���}�\3-1 ���łɊւ���s���\���葱�̗����@�Q��
�s�i�@8��1���{���̎��R�I����`�̗�O�Ƃ��āA�����Ȃ�i�ׂ��N���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
���Ă͐Ŗ��������ɑ��ًc�\�������Ă���A�s������������ŕs���R�������R������������A�Ƃ�����i�K�ł��������A�ًc�\���i���͌�����������Ŗ��������ɑ����Ē����̐���)���ȗ��ł���悤�ɂȂ����B
�����Ȃ�i�ׂ��N�ł��Ȃ��Ƃ͂����A���Ɣ������������邱�Ƃ��ł���ꍇ������B�Ⓚ�q�Ɏ����E�Ŕ�����22�N6��3�����W64��4��1010��(��2.3.2.2.b��O�I�ȑd�Ŋm��葱)
3.2.2.2. �i�ג�N�O�̕s���\���葱
3.2.2.3. �Ē����̐����葱
3.2.2.4. �R�������葱
�ٔ��Ƃ͐F�X�Ⴄ�c�c���Ȏ咣�����A���_��`�I�^�p�A�٘_��`�s�K�p(�Œ�97��1��)�A���f�̓���(�Œ�98��4��)�A�ېŒ����̏o�i�s��(�Œ�102��1��)3.2.3. �n���łɊւ���s���\���葱
�Ŕ��ߘa���N7��16�����W73��3��211�ŕS�I7��99bb(�c���[�V�E�W�����X�g1539��10��)�c�Œ莑�Y�]���R���ψ���ɂ��R���̉ߒ��Ŏ咣���Ȃ��������R������i�ׂɂ����Ď咣���邱�Ƃ͋������B3.2.4. �d�ői��
3.2.4.1. �i�חތ^�Ǝ葱
��������`(�s�i10��2��)�c�c�ٌ��̓K�ۂ𑈂��̂ł͂Ȃ��ېŒ��̏����̓K�@��@�𑈂��B�[�Ŏ�(�㗝�l�E�ٌ�m�{�⍲�l�E�ŗ��m)vs.��(�w��㗝�l�͏ז�����������)(�ȑO�͐Ŗ��������퍐������)
3.2.4.2. �i�ו��Ə������R�̍��ւ�
�w���ł����_��`�����������A����(�Ŕ����a49�N4��18����20��11��175��bd�c�u�{���R���ٌ����E���������z���\�����鏊�_���^�����̋��z��V���ɔF�肵�Ă�����l���̂����R�����������p�������Ƃɂ́A���_�̈�@������Ƃ͂����Ȃ��v�B�u�{�����菈������i�ׂ̑i�ו��́A�E���������z�ɑ���ېł̈�@��ʂł���A���_���^�����̋��z���A�E���������z���\��������̂ł���v�B)�����z��`�@���������R�̍��ւ��͓��Ŋz���ł����i��ʂ��K����o��`(���@�Ɍ�ꂽ�U���h����@�łȂ����)�͈͓̔��ʼn\�Bcf.��6�Ł�231.03�����s���c��n���������E�����n�����a48�N6��28���s�W24��6��7��511��(��4.3.3.��@�Ȏx�o)
|
�Ŕ����a56�N7��14�����W35��5��901�ŕS�I7��120bf �s���Y�擾���z6000���~�A�̔����z7000���~�̑O��łx���X�������B���R�̒lj��R�قƂ��Ĕ̔����z9450���~�Ƃ��A�擾���z���w�咣�ʂ��7600���~�ł���Ƃ��Ă����n�v1000���~�̉ېŏ����Ɉ�@���͂Ȃ��Ǝ咣�B �ō��فu�x�ɖ{���lj��咣�̒�o�������Ă��A�E�X�������𑈂��ɂ��폈���҂���w�Ɋi�ʂ̕s���v��^������̂ł͂Ȃ��v�B (���R���L�Ƃ̊W�Ŏ���̈��������c�u��ʓI�ɐF�\�����ɂ��\���ɂ��Ă����X�������̎���i�ׂɂ����čX���̗��R�Ƃ͈قȂ邢���Ȃ鎖�������咣���邱�Ƃ��ł���Ɖ����ׂ����ǂ����͂Ƃ������v) ���R���L�Ɋւ��āc�Ŕ�����23�N6��7�����W65��4��2081�ŕS�I�s���T-8��117(�ꋉ���z�m�Ƌ���������������������)�D�y�s�̌��z�m���Ƌ����������ꂽ�s�������̍ۂɏ\���ȗ��R��������Ȃ��������Ƃ�s���Ƃ��ċN�����A�u���R���\��������Ă��Ȃ������v�Ƃ��ď�����������������i�ߐ{�O���A�������q���Έӌ�����j �^�C�L�����s�����E�����n������22�N3��5���Ŏ�260������11392����19�N(�s�R)754��(��5.2.2.1.a)(�^�C�֘A��Ђ̊z�ʔ��s�����̈����ɔ��������Ƃ̍��z�̎v���v�����\������Ƃ�������)�͑��_��`���̗p���Ă���悤�ɓǂ߂�B |
3.2.4.3.. �咣�ӔC�E�ؖ�(����)�ӔC�̕��zdv
3.2.4.4. �i���̗��v
|
�܂��炸�⎖���E�Ŕ����a42�N9��19�����W21��7��1828�ŕS�I7��119ew �u��1���X�������͑�2���X�������ɂ���Ď�������C��3���X�������́C��1���X�������Ƃ͕ʌɂȂ��ꂽ�V���ȍs�������ł���v �c���R���L�ɕs���̂����1���X���������2���X�������Ŏ���������ő�3���X�������̎����I���e�͑�1���X�������Ɠ����Ƃ����������A�T�^��Ƃ��������������A���z�čX�������Ɋւ��A�w���Ŏx���̍������������i�������E�Ɨ����E�lj����Ƃ��j�ɑ�������z�����i���Ő��E��̐��Ƃ��j�ň�сB ���z�čX�������Ɋւ��ꕔ�����(�čX���͑����Ȃ��B�����X���𑈂�)���Ƃ���6�Ł�223.01�ٌ�m�ږ◿�����E�Ŕ����a56�N4��24�����W35��3��672�ŕS�I7��38(��4.2.6.1.���^����) |
3.2.4.5. �a��
��2.2.1.1.c ���@���̌��� �Ƃْ̋��W(������̘a���͂���)3.2.4.6. ���v�ې�
�Ŕ����a39�N11��13����11��2��312��bi���@84���ᔽ�ł͂Ȃ��B������������6�N3��30���s�W45��3��857�ŕS�I7��111�c�����Ŗ@156��(�@�l�Ŗ@131��)���v�ېłɂ��āu�����̎��z�Ƃ̊W�Ō����Ȑ�������L����K�v�͂Ȃ��A���z�ېłɑ�������ɂӂ��킵���Ƃ���������x�̐��v�̍������ő����v�B���z���̗��ؐӔC�ɂ��āu���������ڎ����ɂ���Ď����y�ьo��̎��z���咣�E�����邱�Ƃ́A�퍐�̍R�قɑ���P�Ȃ锽�ł͂Ȃ��A���炪�咣�E�ؖ��ӔC���Ƃ���̍čR�قł���A�������A���̍čR�قɂ����Ă͒P�Ɏ������͌o��̎��z�̈ꕔ���͑S�����咣�ؖ����邾���ł͑��肸�A�����y�ьo��̎��z�����ׂĎ咣�E�ؖ����邱�Ƃ�v����v�B lo
cf.�ߘa6�N�x ���@�̊T�v
3.3. �d�Ŗ@���Ƒd�ő��ׂ̌���
3.3.1. �d�Ŗ@���Ɩ@���Ƃ̖���
3.3.1.1. �d�Ŗ@���Ɩ@����
3.3.1.2. �d�ő��ׂɂ�����@����
COLUMN3-1 ���ۓI�d�ő��ׂ̓���
3.3.2. �@�������Ƃɋ��߂������
COLUMN3-2 �^�b�N�X�E�v���j���O
10�N�O��1000���~�ɂ���600���~�ׂ̖�(�ň�����) �� ���������5�����Ăǂ������Ӗ��H�N5��(�Ŗ���)�ŔN�����^�p�� ���{�~1.05�~1.05�~�c�~1.05 �� 1.05��10���1.629
�t�ɁA1.6��1/10����v�Z�������ꍇ�@�u1.6^0.1=�v�ŃO�O�� �� 1.0481������N����5���B
�h�������̂ё��Ɂu����a���Ȃ�100�N��1024�{�v�Ɗ��߂� �� 1024^0.01��1.0718 �N��7%�̎���̘b
4. �l�̏����ېŁ\�����łƏZ����
4.1. �����T�O�Ə����Ŗ@�̍\��
4.1.1. �����T�O
4.1.1.1. �����I�����T�O�E��I�����T�O
�S�ŗ�(ability to pay, Leistungsfähigkeit)�T�O�ɂ��āc�c�d�łS����\�́A�Ƃ��������x�̞B���ȈӖ��ł���A�_�ɂ͎g���ɂ����}�W�b�N�E���[�h�ł���Bec��F�u��Â̏���ɂ͒S�ŗ͂��Ȃ��B�v�u���̏���ɂ͒S�ŗ͂�����B�v�����ł͐����ɂȂ�Ȃ��B�S�ŗ͂�����A�S�ŗ͂��Ȃ��A�Ƃ������_�Ō��_������Ă���A�Ȃ������l���邩�̗��R�̕����厖�B
�S�ŗ͂̊�Ƃ��āA�����E����E���Y(���Y)��������������B
�^�b�N�X�E�~�b�N�X�c�c���ނɗ���ƕ��Q���傫���̂ŁA�����ł����łȂ����Y�ŁE����ł��g�ݍ��킹�o�����X�̂Ƃꂽ�Ő����\�z���ׂ��ł���Ƃ����l�����Bed
�擾�^(�����^)�����T�O(acquisition (accrual) type concept of income)
�����I�����T�O(limited income)�c����������E�����I�������Ƃ������B���B�Ŏx�z�I(���B�ŃL���s�^���E�Q�C���ېł͗�O�I)�B���ޏ�����(scheduler system)�Ɛe�a�I�B
��I�����T�O(global income)�c����������{�����Y�����ƒ�`�B�����Y�������Ƃ������B��3���̃V�����c�E�w�C�O�E�T�C�����Y(Schanz, Haig, Simons)�̏����T�O�Ƃ������B���ĂŎx�z�I�B����������(global system)�Ɛe�a�I�B
4.1.1.2. �擾�^(�����^)�����T�O�ɑ���ᔻ(����^�����T�O)
�ꉞ�̒m���Ƃ��āc�c�����I����(�����̌o�ϗ͂�����҂ɓ����̉ېł����ׂ�)�������I����(�قȂ�o�ϗ͂�����҂ɂ��̈قȂ�ɉ��������ق�݂����ېł����ׂ�)���̓�̌����T�O��m���Ă����ׂ��ł͂��邪�A���ꂾ���ł͓����������Ȃ����Ƃ������B�����Ȃāu���l�v�u�قȂ�v�ƕ]�����H�܂�o�ϗ͂�}��ۂɉ�X�͉��ɒ��ڂ��ׂ����H�l�����͓��̐��ɉ������ېł�����������Hee
�i[���]�����ɂ��āu�����v(�`���I)�Ɓu�t���v(�����I)���g��������l���������{�u�ł͍t�����g��Ȃ��j
��F�`��1000�̏����A100�����B�a��100�̏����A100�����B�`�Ƃa�Ƃ͓��l�̏��B
��F�b��1000�̏����A1000�����B�c��1000�̏����A100�����B�b�Ƃc�Ƃ͓��l�̏��B
����(equity)�ƒ�����(neutrality)�E������(efficiency)
(a) �s�����Ƃ͌���Ȃ����ʓI�E���I�戵
�@�ł̂Ȃ����E�ɂ����āA�Ƃ��Ɏ��v��10%�̂w�E�x�Ƃ�����̓����悪����Ƃ���(�T���̃����S�E�~�J�����w�E�x�Ɉ�ʉ�)�B�w���̗��q�ɐŗ�50���ʼnېł��A�x���̗��q�ɉېł��Ȃ��Ƃ���B�w�̐ň�����v����5%�A�x�̐ň�����v����10%�B
�@�w�֓������Ă����҂̈ꕔ���x�ւ̓����ɐU��ւ���B���v����(diminishing returns)ef�̖@����O��Ƃ���ƁA�w�̎��v�����㏸���A�x�̎��v������������B�ŏI�I�ɁA�w�̐ň�����v���Ƃx�̐ň�����v���������ɂȂ�܂��A�w����x�ւ̐U��ւ����s�Ȃ���B�Ⴆ�A�ň�����v��7��eg�Ȃǂ܂Œ��������B
�@������̏�Ԃ��ύt(equilibrium)�Ƃ����B
�@�x�ɂ��Ė��ړI�ɂ͉ېł���Ă��Ȃ��ɂ�������炸�A�����ߒ����o�Ăx�̐ň��O���v����10%����7%�Ȃǂɒቺ���Ă��邱�Ƃ��A�Öق̐�(implicit tax)���ۂ����Ă���Ƃ����B
�@���ʓI�E���I�ȉېł́A�K���������ʓI�ɂ��s�����Ƃ͌���Ȃ��B
�@50%�̉ېł���ƒm��Ȃ��犸���Ăw�ɓ��������҂�����I�ɋ~��(��ېłƂ���)�ƁA�p���Ăw��s���ɗD�����邱�ƂƂȂ�B�x�ɓ��������҂Ɏ���I�ɉېł���ƁA�p���Ăx��s���ɗ�����邱�ƂƂȂ�B
�@���p��F�����N���������ɂ��āc�c���ړI�Ȑŗ���50%�ł���A�T�����[�}���͂��̏�����100%���ېłɕ����A���c�Ǝ҂͂��̏�����60%���ېłɕ����A�Ƃ������E�����z����B�T�����[�}���̏����ɂ�����ŗ���50%�ł���A���c�Ǝ҂̏����ɂ�����ŗ���30%�ł���A�Ƃ����̂Ɠ������Ƃł���B�A�ƌ`�Ԃɂ��č��ʓI�E���I�Ȉ����ł����B�������A�T�����[�}�������c�Ǝ҂����R�ɑI�ׂ�̂��������ʓI�ɂ͕s�����łȂ��c�c�Ƃ����邩�H
���A�ƌ`�Ԃ̑I�����A�w���E�x���̑I���Ɠ����悤�ɁA�X���[�Y�ɂł���Ƃ͌���Ȃ��B�A�ƌ`�ԑI�������C(friction)���������A�s�������͎c��B
���ڍs(transition)�̖��c�c�lj��I�ȗ�Ƃ��āA������ˑR�T�����[�}���̐ŗ���30%�ɉ�����ꂽ�Ƃ���B�s��ɂ����钲����ʂ��ăT�����[�}�����������ň��O�������㏸���Ă����Ƃ��ɁA�ˑR���x���ς��ƁA���c�Ǝ҂��T�����[�}���ɂȂ낤�Ƃ��鎟�̒����̊ԁA���ɃT�����[�}���ł������҂����Ȃڂ�(windfall)��B(���ӁF���x�ύX����ɂ��Ȃڂ��������炷�Ƃ͌���Ȃ��B���x�ύX���\�z����Ă���ꍇ�ȂǁB)
���E�ƑI���̎��R(cf.��22��)�́A�w�E�x�̓����ƈقȂ�A�ł݂̂ɂ���Č��܂�Ȃ��B
�s��ŏ�Ɋ����ɒ��������Ƃ͌�����Ȃ��B���A�s�����͌������قǂł͂Ȃ��A�Ƃ����̂���ʂ̐^���B
(b) ���A�����
�I�������R�ɂł��A�ڍs�̖����N���A�����Ȃ�A�s�������͂Ȃ��Ȃ邩������Ȃ����A����ł����ʓI�E���I�Ȏ戵�ɉ����s�s��������̂��H
�c�c���I�ȉېł����d(deadweight loss: ���d�����Ƃ�����)�������炷�A�܂�A������������炷�̂������B (�w�z�[�������E�{�[�����E���Ĕ���������ېł����̂��x54�ł��)
�@�}�́A�`-�a�Ԃ̎���(�Ⴆ�Δ_�n)�́A�����S�ƃ~�J���Ƃ̔z����\���Ă���B�`�ɋ߂��_�n�̓����S�ɓK�����v���������a�ɋߕt���قǎ��v�����Ⴍ�Ȃ�B�a�ɋ߂��_�n�̓~�J���ɓK�����v���������`�ɋߕt���قǎ��v�����Ⴍ�Ȃ�B���ł̐��E�ł͏�̉E������Ȑ��Ə�̍�������Ȑ��̌�_�ł���b�_���ύt�_�ł���A�`-�c�Ԃ̔_�n�Ń����S���A�c-�a�Ԃ̔_�n�Ń~�J���Y���邱�Ƃ��œK�Ȏ����z���ł���B�ˑR�A�~�J���������ېł����ƂȂ�ƁA�~�J���̐ň�����v���Ȑ��͉��̉E������Ȑ��ɂȂ�B�V���ȋύt�_�͂d�X�ƂȂ�B�c-�e�Ԃ̔_�n�́A���ł̐��E�ł̓~�J���̕������v���������������A�~�J�������̔��I�Ȑł����������ƁA�~�J���̐ň��O���v��胊���S�̐ň��O���v���̕��������̂ŁA�c-�e�Ԃ̔_�n�̓~�J�����烊���S�ɐU��ւ����A�`-�e�Ԃ̔_�n�������S�Ɋ��蓖�Ă��A�e-�a�Ԃ̔_�n���~�J���Ɋ��蓖�Ă���B�Ȃ��A���̏ꍇ�A�f-�d�̉E��̕���(�~�J���̐ň��O���v���Ȑ��Ɛň�����v���Ȑ��̊�)�͐Ŏ��ɂȂ�A���������ҋ~�ς̂��߂Ɏg����̂ŁA���ʂɂ͂Ȃ�Ȃ��B���ʂɂȂ�͎̂O�p�`�b�f�d�̕����ł���A���̕��������I�ȉېłɂ�萢�̒���������Ă��܂��B���̕��������I�ȉېł̎Љ�I�ȃR�X�g�ł���A���d�Ƃ����B�~�J�����ېł��ꂸ�����S�����ېł����ꍇ�̎��d�͎O�p�`�b�i�g�̕����ł���B�����S�ƃ~�J���������悤�ɉېł����Ȃ�ύt�_�͂j�_�ł���A�����z�����c�܂Ȃ��B
���ʓI�E���I�Ȏ戵����ɔ�����������炷�Ƃ͌���Ȃ��B
��F�Ɛg�j�ɉېł��A�Ɛg���ɉېł��Ȃ��A�Ƃ���B���]�����s�\�Ȃ�(���͉\����)�A�����z���ɉe�����Ȃ�(�v�w���̃J�b�v���͕ʘ_)�B�������������ɂ͉e�����Ȃ��B
�ނ����̔��I�戵�͔�����������炷�̂ŁA���Ɣ�����Ƃ͂قړ��`�Ŏg����B
�������́A���Ɖ��Ƃ̑I���ɒ��ڂ��邩�𖾂炩�ɂ�����ŏ��߂ĈӖ������Bcf.����I�������Ƃ����T�O�ɂ��đ���nj[�u�@�l�ł̉ېŒP�ʁ\������ЂƘA���[�Ő��x���߂���ߔN�̋c�_��f�ނƂ��ā\�v�d�Ŗ@����25��62��(1997)
��F�Ɛg�j�̒����ɉېł��A�Ɛg���ɉېł��Ȃ��B �� �J���ӗ~�����Ƃ��������(��COLUMN4-2�l�I���{)�B
���̔�����́A�u�j�v�ɉېł������ʂł͂Ȃ��A�u�����v�ɉېł������ʂł���B(�v�w���͕ʘ_)
�����I�ȉېłƂ́c�c�ꊇ��(lump-sum tax) ���l����(a poll tax, capitation)
��F���������ɂ��ېł��ƈ�l��l�̐Ŋz���قȂ邪�A�l�X�̍s���͕ω����Ȃ��B
�[�Ŏ҂̍s���Ɩ��W�ɒ��������ł������I�ȑd�� (cf.�g����ej) �ǂ��d�ł��͕ʘ_
(c) �����ƒ�����(������)�Ƃ̊W
�����ƌ������Ƃ��g���[�h�I�t(trade off)�̊W�c�c���z���ɂ��悤�Ƃ���ƁA�ېł���鑤�̓����C�������A���z�̑Ώۂł���o�ϓI�p�C�̑傫�����̂��̂��������Ȃ�(�܂������ɂȂ�)�B
�Ȃ��A�����Ƃ����Ƃ��A���ʂ̕����Ƌ@��̕�������ʂ���邱�Ƃ��������A��ʂ��ʂ��̂�����B
�{�u�Ō����͂��܂舵�킸���������������Ƃ������B������_����̂͂܂�����B
(d)���~(�����x�点��)�Ƒ�������Ƃ̔�r
�������݉��l(discounted present value)�����K�̎��ԓI���l(time value of money)�ɗ���
�`�i���������l�j�Ƃa�i���~���ė��N�����l�j�Ƃ̔�r
�������蒙�~(��ŏ����)�Ƃ����I�������I�����T�O�͕s�����E���I�ɕs���Ɉ����Ă���
������^(�x�o�^)�����T�O(consumption (expenditure) type concept of income)�c����݂̂ɉېł��ׂ��Ƃ���l�����B�x�o��(expenditure tax)�Ɛe�a�I�B
expensing(�S�z�����T��)�����F���~���ɉېł����A���q��̎�(���)�ɉېł���B(��COLUMN5-5���������Z���Ǝ��Y��)
yield exemption(���v��ې�)�����F���~���ɉېł��邪�A���q��̎�(���)�ɉېł��Ȃ��B
�����ې�vs.����ېŁc�o�ϊw�ҁF���q�ې�vs.��ې� | �J�F���ڐ�vs.�ԐڐŁ@(��COLUMN6-6��I�����T�O�Ə���ېł̍��ق͈ӊO�Ə������H)
���q��ېł̘_���c�o�ϊw�ҁF����E���~�̒����� | �J�F�����������q�����Ȃǂɉېł�������{����(capital flight)�ň�w���{�o�ς��ꂵ���Ȃ鋰��B
cf.�k���������I������(dual income taxation)�c���������y�і@�l�̏����ɂ��Čy�߂̔��ŗ�(flat rate)�A�J�������ɗݐi�ŗ�(progressive rate)�B
COLUMN4-1��I�����T�O�͐������Ȃ��H
����ېŘ_��(���q��ېŘ_��)�ւ̔��_���F����ېłɂ�����(�]�Ɂ�COLUMN4-2�l�I���{)�B�����̐��̔�r�̈Ӌ`�̏������B
���F�������ȊO�̍l���v�f�c��I�����T�O�̒�`���͈ꌩ������O�̎��̂悤�Ɍ����邩������Ȃ����A�����x�̍ĕ��z�Ƃ��������I�Ӑ}�������������̂ł���(��F�r���E�Q�C�c�̂悤�ȕx���Ƃ��Ȃ��̏�����������ł�������ŕ��S�������ŗǂ��ł����H)�B
�����T�O�_�ɐ����͂Ȃ��A���l���f�̖��ł���Ƃ����̂����ȏ��I����(�w�E�ł͍X�ɓ˂����c�_������Ă���eq)�B)
�ߔN�͏���������Ƃ����N�w(���l���f)����œK�ېŘ_(optimal taxation theory)�������c�c���̐Ŏ������{�ɂƂ��ĕK�v�ł��邱�Ƃ�^��(�_����ΏۂƂ��Ȃ��O��)�Ƃ��A�ǂ������d�ŕ��S�z���Ȃ�����ɔz���������������܂�Q���Ȃ��ōςނ�(�ΘJ�ӗ~��j�Q���Ȃ��ōςނ�)���l����B
4.1.2. �����Ŗ@�̍\��
4.1.2.1. �킪�������ł̓���
4.1.2.2. �����Ŋz�̌v�Z�̏���(����21��)
�}�\4-1 �����Ŗ@�ɂ�����Ŋz�Z��̗��� �Q��
(a)�������z�|�K�v�o��������z�@(�������ނɗ���)
(b)�������z�|�����T�����ېŏ������z�@(���v�ʎZ�A�������̌J�߂��E�J�z���ɗ���)
(c)�ېŏ������z�~�ŗ��|�Ŋz�T�����[�Ŋz
�������͐}�\4-1�������ł��Ȃ��Ă������̂œx�X�U��Ԃ��āI
4.1.2.3. �ېŕW��(����22��)
����22��2��2����33��3��2��(�������n����)�A34��(�ꎞ����)�����z�ېłɂȂ�B
4.1.2.4. �e�폊�����z�̌v�Z�F��������(����23�`35��)�A�������z(36��)�A�K�v�o��(37��)
4.1.2.5. �ېŏ������z�̌v�Z�F���v�ʎZ(����69��)�A�������̌J�z����(70��)�A�����T��(72�`87��)
4.1.2.6. �Ŋz�̌v�Z�F���ߗݐi�ŗ�(����89��)
|
|
89���̐Ŋz�v�Z��A����92�E95���ɍ��v������Ŋz�T��(��4.2.2.2.�z���T���A��8.3.1.�O�ōT��)�B
4.1.3. �ېŒP�ʁF���ߗݐi�ŗ����ł̏��������̗U��
4.1.3.1. �ېŒP�ʂ̌^
| �l�P�ʎ�` | �����P�ʎ�`(�v�w�P�ʁE�Ƒ��P��)le |
| �@���Z����`�^���Z������`(�ϓ��E�s�ϓ�) �@�P��ŗ��\���x�^�����ŗ��\���x |
4.1.3.2. �I���h�}���E�e���v���̖@��(Oldman & Temple)
�`�Ɛg1�l���a�Љ҂����b���҂����c�Ɛg2�l�`���a�c�c������
�a���b�c�c��Ǝ�w/�v�̉Ǝ����ɂ���A������(imputed income��4.3.4.)
�b���c�c�c�K�̗͂��v(economy of size)(�c��2�l���������ĂȂ��ꍇ)
4.1.3.3. ���̕]��
| 6�Ł�212.03����i���E�ő唻���a36�N9��6�����W15��8��2047�ŕS�I7��30bj �@(���^�����{���Ə�����62��4800�~�̔��z)�{(�z������43��2200�~)�c���^�E���Ə����͍Ȃ������̌��L��A�z�������ɂ͂Ȃ��A�Ƃ����z��B�T�^�I�ȓ��(�v�w���Z����)�Ƃ͈قȂ�B �@(�]�k�F�������̍��Y���^(���`�̍��Y���^)�ɂ����ĕv�̓��L���Y���銔�����琶�����z�������͍��Y���^�̑ΏۂƂȂ炸�A�v�̋��^�������ɂ��Ă͍Ȃ̓����̌�������Ƃ������Ƃō��Y���^�ɂ����ċ��^�������������Ƃ���~���ɂ��ĊT�ːܔ������B�]���āA�v���e���犔�����̎��Y�^���Ă��炤�Ȃǂ�����v�̗������ɍ��Y���^�Ŏ����Ă�����Ȃ�����ŁA�v���e����w����o���Ă�����Ė@�w���E�@�ȑ�w�@�ɒʂ킹�Ă�������Ȃǂ̏ꍇ�̕v�̋��^�������͕v�̗������ɍ��Y���^�̑ΏۂƂȂ�Ƃ�������(�v�̐e���e�ɂǂ̂悤�Ȍ`�ő��^���邩�̑I�����ɂ���)�����݂���B�ܘ_�v�w�t�̏ꍇ�����l�B) �@���|�@�u�����Ŗ@���A���v����ɂ���v�w�̏����̌v�Z�ɂ��āA���@���Z����ꍀ�ɂ�邢�����ʎY��`�Ɉˋ����Ă�����̂ł���Ƃ��Ă��A�����������@��l���Ɉᔽ������̂Ƃ����Ȃ����Ƃ́A�O�L�̂Ƃ���ł��邩��A�����Ŗ@���܂��ጛ�Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B�v �@�ō��ق͌l�P�ʎ�`���ጛ�ł͂Ȃ��Əq�ׂ������Ȃ̂ŁA���{�̌��@�E���@�̋K����O��Ƃ��ē���m���m����̗p�����ꍇ�Ɉጛ�ƂȂ邩�ɂ��Ă͉����q�ׂĂȂ��B�������A����m���m�悪�ጛ�ƂȂ�\���͒Ⴂ�ł��낤�B �@���Ɍ����̎咣��F�߂�Ƃ�����A�Ȃ̏������ނ͋��^�����E���Ə����ł悢�̂��A�Ƃ�������������B �@cf.�v�w���Y�_���E�����n�����a63�N5��16������1281��87�ŕS�I6��29(��4.5.1.2.) |
4.1.3.4. �ېŒP�ʂ��߂��鐳���̕s����
��搧�x�̖��_�c�cC��D���K�̗͂��v�����bB��C�������̌�(�A������)�������Z�����u�����ɑ��锱��(or�ې�)�v(marriage penalty)���Ő��̍�����������j�Q�����Bfs
[���]�Ǝ����̋A���������ېőΏۂɎ�荞�܂Ȃ��������ېŒP�ʂ̖��ɐ����͂Ȃ��B
4.2. ��������(����23���`35��)
4.2.1. ���q����(23��)
����23���u���q�����Ƃ́A���Ѝy�їa�����̗��q�c�c���тɍ����^�p�M���A���Ѝ����M���y�ь�����Ѝ��^�p�����M���̎��v�̕��z�c�c�ɌW�鏊���������B�Q�@���q�����̋��z�́A���̔N���̗��q���̎������z�Ƃ���B�v
����181��(�����`��)�u���Z�҂ɑ������ɂ����đ��\�O���ꍀ�i���q�����j�ɋK�肷�闘�q���c���͑��\�l���ꍀ�i�z�������j�ɋK�肷��z�����c�̎x��������҂́A���̎x���̍ہA���̗��q�����͔z�����ɂ��ď����ł����A���̒����̓��̑����錎�̗����\���܂łɁA��������ɔ[�t���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�Q�@�z�����c�ɂ��ẮA�x���̊m�肵���������N���o�߂������܂łɂ��̎x��������Ȃ��ꍇ�ɂ́A���̈�N���o�߂������ɂ����Ă��̎x�����������̂Ƃ݂Ȃ��āA�O���̋K���K�p����B�v
����182��(�����Ŋz)�u�O���̋K��ɂ�蒥�����ׂ������ł̊z�́A���̊e���̋敪�ɉ������Y�e���Ɍf������z�Ƃ���B
��@���q���@���̋��z�ɕS���̏\�܂̐ŗ����悶�Čv�Z�������z
��@�z�����@���̋��z�ɕS���̓�\�̐ŗ����悶�Čv�Z�������z�v
�d�œ��ʑ[�u�@3��(���q�����̕����ېœ�)�u���Z�Җ��͍P�v�I�{�݂�L����Z�҂��c�����ɂ����Ďx������ׂ������Ŗ@���\�O���ꍀ�ɋK�肷�闘�q���m1-4���́u�s�K�p���q�v�������B�u��ʗ��q���v�Ƃ����B�n�c�ɂ��ẮA���@���\����y�ё攪�\�����тɑ�S�Z�\���̋K��ɂ�����炸�A���̏����Ƌ敪���A���̎x������ׂ����z�ɑ��S���̏\�܂̐ŗ���K�p���ď����ł��ۂ���B�v[1-4�����A2-4����]
����ݎ،_��F���@587���u����ݎ́A�����҂̈������ށA�i���y�ѐ��ʂ̓������������ĕԊ҂����邱�Ƃ�đ����������K���̑��̕�����邱�Ƃɂ���āA���̌��͂���B�v
�������_��F���@666���u���҂��_��ɂ������������邱�Ƃ��ł���ꍇ�ɂ́A���҂́A������ꂽ���Ǝ�ށA�i���y�ѐ��ʂ̓������������ĕԊ҂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�Q�@��ܕS��\���y�ё�ܕS��\����̋K��́A�O���ɋK�肷��ꍇ�ɂ��ď��p����B
�R�@��ܕS��\����y�ё�O���̋K��́A�a�����͒����ɌW��_��ɂ����K����������ꍇ�ɂ��ď��p����B�v
�u���q�v�Ƃ������t�őz�N�������̈�ʂł͂Ȃ��a�����̗��q�����S�B
���K�������_��(���@666��)�c�c5�Ł�221.01(6��163��)���a���Ǝ����E�����������a39�N12��9���s�W15��12��2307�ŕS�I5��35gf
6�Ł�221.01�u�a���v�̈Ӌ`�@�V����s�f�b�g�A�T���v�V�����_���E�����n������17�N7��1������16(�s�E)13��(�T�i�R������������17�N12��21������17(�s�R)198��
�f�b�g�A�T���v�V���������E������������18�N8��17����54��2��523�ŕS�I7��36(���R�����n������18�N1��24����54��2��531��)
��m�Z�����g���Ǝ����E�����������a41�N4��28�����^194��147��(�K���������K�������_��ł��邩�ɍS�D�����A�a���̌o�ϓI�����ɒ��ڂ���Ƃ���)(cf.�����p���u���q�����ɂ�����u�a�����q�v�̈Ӌ`�Ɣ͈́v�_�˖@�w�G��41��1��61-88��1991�N)
���K����ݎ��_��(���@587��)�̏ꍇ�A�G����(���͎��Ə���)�ł��邱�Ƃɗ��ӁB
�K�v�o��̍T�������x��\�肳��Ă��Ȃ��B(����23��2��)
�⑫�F����a���̂悤�Ɂu�Ԋ҂̎������߁v���������_��Ə���ݎ،_��Ƃ̈Ⴂ�́H
�Ő�������u�Ő��̔��{�I�������ɂ��Ă̓��\�v���a61�N10��55-56�Łi�Ő�������̓��\�i�Œ����\�j�ɂ��Ă͓��{�d�Ō��������HP���֗��j
���ŕ��@�\�\���Z�@�ւ����q�����ɊY������������x�����ۂ��������A�����Č����ɂ�������������B�ꗥ�����ې�(��4.8.3.)�Ƃ����B���s�ʂŕ֗��ł��锽�ʁA�X�̔[�Ŏ҂̌o�Ϗ�Ԃf�ł��Ȃ�(���z�����ҁE���z�����҂ɂ��čl�@����)�Ƃ������_������B(�@�ȑ�w�@����5�Ł�221.02�Ő���������Z���ψ���u���Z�����ېł̈�̉��ɂ��Ă̊�{�I�l�����v(����16�N6��15��)���Q��)
cf.�o�ŎЂ����錴�e�������������(����204���ȉ�)���ېŊW�͊������Ȃ��B
4.2.2. �z������(����24��)
4.2.2.1. ��`
����24��(�z������)�u�z�������Ƃ́A�@�l�c�c�����[1]��]���̔z���i�c�c���{��]���̊z�̌����ɔ������́c�c�������B�j�A[2]���v�̔z���c�c�A[3]��]���̕��z�c�c�A[4]�����M���y�ѓ����@�l�c�c�̋��K�̕��z�c�c�A[5]��������c�c���тɓ����M���c�c�y�ѓ����v�،����s�M���̎��v�̕��z�c�c�ɌW�鏊���������B�Q�@�z�������̋��z�́A���̔N���̔z�����̎������z�Ƃ���B�������A�������̑��z���������ׂ����{���擾���邽�߂ɗv�������̗��q�c�c�ł��̔N���Ɏx�������́c�c���T���������z�Ƃ���B�v
25��(�z�����Ƃ݂Ȃ����z�m�u�w���݂Ȃ��z���ƌĂԁn)�u�@�l�c�c�̊��哙�����Y�@�l�̎��Ɍf���鎖�R�ɂ����K���̑��̎��Y�̌�t�����ꍇ�ɂ����āA���̋��K�̊z�y�ы��K�ȊO�̎��Y�̉��z�c�c�����Y�@�l�́m�@�l�Ŗ@2���n�\�Z���ɋK�肷�鎑�{�����̊z�c�c�̂������̌�t�̊���ƂȂ����Y�@�l�̊������͏o���ɑΉ����镔���̋��z����Ƃ��́A���̖@���̋K��̓K�p�ɂ��ẮA���̒����镔���̋��z�ɌW����K���̑��̎��Y�́A�O���ꍀ�ɋK�肷��[1]��]���̔z���A[2]���v�̔z���A[3]��]���̕��z����[4]���K�̕��z�Ƃ݂Ȃ��B
��@���Y�@�l�̍����c�c
��@���Y�@�l�̕����^�����c�c
�O�@���Y�@�l�̊������z�c�c
�l�@���Y�@�l�̎��{�̕��߂��c�c���͓��Y�@�l�̉��U�ɂ��c�]���Y�̕��z
�܁@���Y�@�l�̎��Ȃ̊������͏o���̎擾�c�c
�Z�@���Y�@�l�̏o���̏��p�c�c�A���Y�@�l�̏o���̕��߂��A���Y�@�l����̎Ј����̑��̏o���҂̑ގЎႵ���͒E�ނɂ�鎝���̕��߂����͓��Y�@�l�̊����Ⴕ���͏o���Y�@�l���擾���邱�ƂȂ����ł����邱�ƁB
���@���Y�@�l�̑g�D�ύX�c�c�v�m2�E3�����n
�݂Ȃ��z���͓���̂�(�Ⴆ��)�w�������x���ł͕�����Ȃ��Ă��悢���A�Ⴆ��25��1��4����i�u���Y�@�l�̉��U�ɂ��c�]���Y�̕��z�v�̗�c�c�w���Ƃx�������ꂼ��200�~���o�����A�y��Ђ�ݗ����A���Y900�~�A����500�~�A���{��400�~�ŃX�^�[�g�B�y��Ђ̉c�Ƃ����܂������A���Y��1100�~�܂ő������Ƃ���(����500�~�A���{��400�~�̂܂�)�B�����ły��Ђ����U����ƁA���ԍό�600�~���c��̂ŁA�w���Ƃx�������ꂼ��300�~�����A100�~(��300�|200)�ɂ��Ĕz�������ƌ��Ȃ����Bgg
��㍂������24�N2��16����58��11��3876��(���ˋM�V�E�W�����X�g1461��127��)�c�]�ƈ�������̍��̑㕨�ٍςƂ��ĉ�Ђ����Ȋ������擾���邱�Ƃ��݂Ȃ��z���ɓ�����Ƃ�������B�����ł��u���Y�̌�t�v�ɓ�����B�]�ƈ�������͏����Вc��4�v�������Ă��g���ł���B
6�Ł�322.05���ۋ��ƊǗ�������Ў����E�Ŕ��ߘa3�N3��11�����W75��3��418��
| 6�Ł�221.02 �����Z�����E�Ŕ����a35�N10��7�����W14��12��2420�ŕS�I5��36kg �����E���_�@���告���Z���(���Z�K���̒E�@)������D�ҋ����z������(�����u���v�̔z���v)�ɊY�����邩(�����Ďx���҂ł�������������`������)�H �@�Ⴆ�`�E�a�E�b��3�l���o�����Ċ��告���Z��Ђ�ݗ����A����D�ҋ������ƁA�c�E�d�E�e����s�ɗa�����A�a�����q������ʂ��ׂĂ݂悤�B �@�o���@�@�@�@�b�@�@�@�@�@�@�@�@�b�@�@�@�@�@�@�@�@�b����D�ҋ� �`�\�\�������@�b�@�`�@�@�@�����@�b�@�`�@�@�@�����@�b�@�`���\�\���� �a�\�\���Z��@�b�@�a�@�@�@�Z��@�b�@�a�@�@�@�Z��@�b�@�a���\�\�Z�� �b�\�\����@�b�@�b���\�\��@�b�@�b�\�\����@�b�@�b���\�\� �@�@�@�@�Ќ݁@�b�@�@�ؓ��@�Ќ݁@�b�@�@�ԍρ@�Ќ݁@�b�@�@�@�@�@�Ќ� �@�@�@�@�@�@�@�b�@�@�@�@�@�@�@�@�b�@�@�@�@�@�@�@�@�b �@�a���@�@�@�@�b�@�@�@�@�@�@�@�@�b�@�@�@�@�@�@�@�@�b�a�����q �c�\�\����@�@�b�@�c�@�@�@��@�@�b�@�c�@�@�@��@�@�b�@�c���\�\�� �d�\�\���s�@�@�b�@�d�@�@�@�s�@�@�b�@�d�@�@�@�s�@�@�b�@�d���\�\�s �e�\�\���@�@�@�b�@�e���\�\�@�@�@�b�@�e�\�\���@�@�@�b�@�e���\�\ �@�@�@�@�@�@�@�b�@�@�ؓ��@�@�@�@�b�@�@�ԍρ@�@�@�@�b�@�@�@�@�@ �T�i�R�����@�u���v�̔z���Ƃ͏��@�c�̋K�肷�闘�v�̔z���v���w���B(�ؗp�T�O��3.1.2.2.) �����㍐���R�@�u��Ђ��A����ɑ��Ă��̏o���ɑ���Ή��v�Ƃ��Ďx�������ꍇ�́u��ɗ��v�̔z���v�ł���A�u���@�Ɉᔽ���ĂȂ��ꂽ���ۂ��́v�W�Ȃ��B�u���v����ɂ��ƂÂ��Ȃ��ʼn�Ђ�����ɑ����̊��傽��n�ʂɂ����āv�x�����ꍇ�́A(�����̗�O������)�u���ׂė��v�̔z���ł���v�B �ō��ٔ��|(�㍐���p)�@�㍐���R�Ɉꕔ���Ӂ\�\�u�����Ŗ@���܂��A���v�z���̊T�O�Ƃ��āA���@�̑O��Ƃ��闘�v�z���̊ϔO�Ɠ���ϔO���̗p���Ă���v�B���@��s�K�@�ȑ��z���⊔�啽�������ᔽ�̔z�������u�����Ŗ@��̗��v�z���̂����Ɋ܂܂��v�B �@�������u�{���̊���D�ҋ��Ȃ���̂́A���v�v�Z�㗘�v�̗L���ɂ�����炸�x��������̂ł��芔���z�̏o���ɑ��闘�v���Ƃ��Ďx��������̂Ƃ݂̂͒f��v�ł��Ȃ��B �l�@ �ېœ��ǂ̏㍐���R�Ə㍐�R�����Ƃ̌��_�̍��ɒ��ځBcf.�����24-1(��]���̔z���A���v�̔z�����͏�]���̕��z�Ɋ܂܂�����)�y��24-2(�z�����Ɋ܂܂�Ȃ�����) �@�u�z���v�͎ؗp�T�O�_�ł����Η�ɋ������邪�A�y���@�ɂ�����̂Ɠ����Ӗ��ʼn��߂��ׂ��z(�����)���y���@��K�@�Ȕz���Ɍ��肳���z�ɒ��������ł͂Ȃ��A�Ƃ����������Ș_���\��������B(�Ȃ��A���z���Ɋւ��锻���͑��v�v�Z��̗��v�Ɋ�Â��Ȃ��̂ł��邩�疵�����Ă���悤�Ɏv����B�������Ă��Ȃ��Ƃ��������͕s�\�ł͂Ȃ����A[���]�M���������̂ł��낤) �@�t�̌��_�̂悤�Ɍ�����6�Ł�323.02�������������E�ő唻���a43�N11��13�����W22��12��2449��(��5.3.3.1.)�ƃZ�b�g�ŕ��K���ׂ��B �@[���W]��18������́u��]���̔z���v�́A�{����(�u���v�̔z���v)�̎˒��O�ł��낤�Ƃ���������������͗D���ł���悤�Ɍ�����B�w�������x���ł̓t�H���[���Ȃ��Ă悢�Bcf.�O���@�l�X�s���I�t�����i�^�C�RTyco�����j�E�����n������21�N11��12�����^1324��134�ŁA�J�i�_�@�l�q��Њ��������z�������E������������17�N1��26���Ŏ�255������9911��kq�B |
4.2.2.2. �ېŕ��@�Ɣz���T��
����92��(�z���T��)�u���Z�҂���]���̔z���c�c�A���v�̔z���c�c�A��]���̕��z�c�c�A���K�̕��z�c�c���͏،������M���̎��v�̕��z�c�c�ɌW��z�������c�c��L����ꍇ�ɂ́A���̋��Z�҂̂��̔N���̏����Ŋz�c�c����A���̊e���Ɍf����ꍇ�̋敪�ɉ������Y�e���ɒ�߂���z���T������B��@���̔N���̉ېő��������z���疜�~�ȉ��ł���ꍇ�@���Ɍf����z�������̋敪�ɉ������ꂼ�ꎟ�ɒ�߂���z�̍��v�z
�@�C�@��]���̔z���A���v�̔z���A��]���̕��z�y�ы��K�̕��z�c�c�ɌW��z�������@���Y�z�������̋��z�ɕS���̏\���悶�Čv�Z�������z
�@���@�،������M���̎��v�̕��z�ɌW��z�������@���Y�z�������̋��z�ɕS���̌܂��悶�Čv�Z�������z
��@���̔N���̉ېő��������z���疜�~���A���A���Y�ېő��������z����،������M���̎��v�̕��z�ɌW��z�������̋��z���T���������z���疜�~�ȉ��ł���ꍇ�@���Ɍf����z�������̋敪�ɉ������ꂼ�ꎟ�ɒ�߂���z�̍��v�z
�@�C�@��]���̔z�����ɌW��z�������@���Y�z�������̋��z�ɕS���̏\���悶�Čv�Z�������z
�@���@�،������M���̎��v�̕��z�ɌW��z�������@���Y�z�������̋��z�̂����A���Y�ېő��������z����疜�~���T���������z�ɑ���������z�ɂ��Ă͕S���̓�E�܂��A���̑��̋��z�ɂ��Ă͕S���̌܂����ꂼ��悶�Čv�Z�������z�̍��v�z
�O�@�O�Ɍf����ꍇ�ȊO�̏ꍇ�@���Ɍf����z�������̋敪�ɉ������ꂼ�ꎟ�ɒ�߂���z�̍��v�z
�@�C�@��]���̔z�����ɌW��z�������@���Y�z�������̋��z�̂����A���Y�ېő��������z����疜�~�ƃ��Ɍf����z�������̋��z�Ƃ̍��v�z���T���������z�ɒB����܂ł̋��z�ɂ��Ă͕S���̌܂��A���̑��̋��z�ɂ��Ă͕S���̏\�����ꂼ��悶�Čv�Z�������z�̍��v�z
�@���@�،������M���̎��v�̕��z�ɌW��z�������@���Y�z�������̋��z�ɕS���̓�E�܂��悶�Čv�Z�������z�v�m2�E3�����n
(�^�b�N�X�A���T�[No.1250�z������������Ƃ�(�z���T��)�̐}��������₷��)
�����擾�̂��߂̕��ɌW�����q���T���ł���(����24��2��)(�Ⴆ�Ί����擾�̂���1000���~���؋����z������180���~����藘�q100���~���x�������ꍇ�̔z��������180�|100��80(���~))���A���v�ʎZ�s��(����69��1��)�B�����Ƃ��đ����ېł̑Ώۂł���\���[�ł��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�Ȃ��F���������ꍇ�A�\���s�v�̏ꍇ������(��4.2.2.3.)�B
����92��1�����Ŋz�T�����A�@�l�łƂ���d�ېł̒����̂��߂ɔF�߂���B
(���ɔz���z��10%�������T����������H�c�c(1100�|14)�~33���|153.6��204.78(���~))
����92���͔z���T���Ƃ��邾���ŏ����T�����Ŋz�T����������ɂ������A�����T�����Ŋz�T�����Ō��ʂ��S�R�Ⴄ�̂ŁA�T���������T���̈Ӗ����Ŋz�T���̈Ӗ�����Ɋm�F����Ȃ����Ăق����B
4.2.2.3. ��ꊔ�����̓���
���Z�����ꌳ���̕����I�����B������A�����ېłɋ߂��B�z���ɂ��đd��8����4�A8����5�F�\�������ېŐ��x�E�\���s�v���x�B
�����n������29�N12��6���Ŏ�267������13096����28(�s�E)10���E�T�i�R������������30�N5��17���Ŏ�268������13153����29(�s�R)386���c�c��ꊔ�����̔z�����ɌW��\�������ېł̓���(�d��8����4)����ۂ̑I����������ہA����1���u�m��\�������o�����Ƃ��v�̉��߂Ƃ��āA�X���̐������ɂ���Ď���I�ɑI�����������Ƃ͂ł��Ȃ��Ƃ�������B�c���G���E�W�����X�g1543��130�ł͔��|���B
�������n�v�Ɋւ���\�������ېŁE����������x�ɂ��đd��37����10�E37����11��3�B
�y�ۑ[�u(����20�N��������32�A33�A43�A45��)�̕���25�N���p�~��ɓ��{��ISA�iNISA�F�j�[�T�Ɣ�������jiw��26�N�ɓ�������(�d���@9����8�A37����14�A����22�N��������52���A64��)�B���݁A���NISA�A�݂���NISA������(�W���j�ANISA��2023�N12�����ɏI��)�B
����25�N�x�Ő��������y�ۑ[�u���p�~�����̂ō��E�n���ō��킹10������20���ցB���Ѝ��n�����ېŁB������ЍE��ꊔ�����ɂ��A���q�E�z���E���n���v���ꌳ�����ĉېł��A�ꗥ�����ېł̑Ώۂ���O��20���̐\�������ېł̑ΏۂƂ����v�ʎZ���\�ɂ���(���Z�����ꌳ���ɋߕt��)�B��ʌ��Ѝ�(���q�͈ꗥ�����ېł̂܂�)�E���ꊔ���̏��n�����ېł̈ꌳ���Bcf.��5���n�v�Ő������̂���܂�
4.2.3. ���n����(33��)
4.2.3.1. ��`
����33��(���n����)�u���n�����Ƃ́A���Y�̏��n�i�������͍\�z���̏��L��ړI�Ƃ���n�㌠���͒��،��̐ݒ肻�̑��_��ɂ�葼�l�ɓy�n���Ԏg�p������s�ׂŐ��߂Œ�߂���̂��܂ށB�ȉ����̏��ɂ����ē����B�j�ɂ�鏊���������B�Q�@���Ɍf���鏊���́A���n�����Ɋ܂܂�Ȃ����̂Ƃ���B
�@��@���ȉ����Y�c�c�̏��n���̑��c����ړI�Ƃ��Čp���I�ɍs�Ȃ��鎑�Y�̏��n�ɂ�鏊��
�@��@�O���ɊY��������̂̂ق��A�R�т̔��̖��͏��n�ɂ�鏊��
�R�@���n�����̋��z�́A���̊e���Ɍf���鏊���ɂ��A���ꂼ�ꂻ�̔N���̓��Y�����ɌW�����������z�������Y�����̊���ƂȂ����Y�̎擾��y�т��̎��Y�̏��n�ɗv������p�̊z�̍��v�z���T�����A���̎c�z�̍��v�z�i�c�c�u���n�v�v�Ƃ����B�j������n�����̓��ʍT���z���T���������z�Ƃ���B
�@��@���Y�̏��n�c�c�ł��̎��Y�̎擾�̓��Ȍ��ܔN�ȓ��ɂ��ꂽ���̂ɂ�鏊���c�c�m�Z�����n�����n
�@��@���Y�̏��n�ɂ�鏊���őO���Ɍf���鏊���ȊO�̂��́m�������n�����n
�S�@�O���ɋK�肷����n���������ʍT���z�́A�\���~�i���n�v���\���~�ɖ����Ȃ��ꍇ�ɂ́A���Y���n�v�j�Ƃ���B�v�m5�����n
����38��(���n�����̋��z�̌v�Z��T�������擾��)�u���n�����̋��z�̌v�Z��T�����鎑�Y�̎擾��́A�ʒi�̒�߂�������̂������A�������Y�̎擾�ɗv�������z���тɐݔ���y�щ��ǔ�̊z�̍��v�z�Ƃ���B
�Q�@���n�����̊���ƂȂ鎑�Y���Ɖ����̑��g�p���͊��Ԃ̌o�߂ɂ�茸�����鎑�Y�ł���ꍇ�ɂ́A�O���ɋK�肷�鎑�Y�̎擾��́A�����ɋK�肷�鍇�v�z�ɑ���������z����A���̎擾�̓�������n�̓��܂ł̊��Ԃ̂������̊e���Ɍf������Ԃ̋敪�ɉ������Y�e���Ɍf������z�̍��v�z���T���������z�Ƃ���B
�@��@���̎��Y���s���Y�����A���Ə����A�R�я������͎G�������ׂ��Ɩ��̗p�ɋ�����Ă������ԁ@��l�\����ꍀ�i�������p���Y�̏��p��̌v�Z�y�т��̏��p�̕��@�j�̋K��ɂ�蓖�Y���ԓ��̓��̑�����e�N���̕s���Y�����̋��z�A���Ə����̋��z�A�R�я����̋��z���͎G�����̋��z�̌v�Z���K�v�o��ɎZ������邻�̎��Y�̏��p��̊z�̗ݐϊz�v�m���n�m�������p��5.2.3.3.b.�n
�����33-1�u���n�����̊���ƂȂ鎑�Y�Ƃ́A�@��33���2���e���ɋK�肷�鎑�Y�y�����K���ȊO�̈�̎��Y�������A���Y���Y�ɂ́A�؉ƌ����͍s�������̋��A�F�A�����ē��ɂ�蔭������������̌������܂܂��B�v
���Y���ŗL�T�O�̓T�^��Bcf.6�Ł�222.03�T�����[�}���E�}�C�J�[�i�ׁE�Ŕ�����2�N3��23������1354��59�Ł�4.6.3.���v�ʎZ
���K�����Y�Ɋ܂܂�Ȃ����ƂɈ٘_�͂Ȃ����A���K�������O����ʒB�ɂ͈٘_�̗]�n����B
| �������E(���R�����n������20�N11��28���Ŏ�258������11089����20(�s�E)281��)������������21�N5��20���Ŏ�259������11203����21(�s�R)5���S�I7��37 ���Y�ɂ��āc�c���̈ړ]�́u�b�~�n�̈ړ]�ɏ�������̂Ƃ������Ƃ͂ł����C���Y�]��e�ς��b�~�n�̗��p������Ɨ��C�������ĉ��~�n�Ɉړ]���邱�Ƃ���߂�ꂽ���̂ł͂Ȃ��v�B�u�w�]��e�ϗ��p���x�Ȃ���̂́C�y�n���L�����畣������~�n���p���\�i�o�ϓI���v�j�ł����āC�~�n���p���Ɨ���ēƗ��ɏ����\�ȍ��Y���Ƃ������Ƃ͍���ł���B�v ���n�ɂ��āc�c�u�w�]��e�ϗ��p���x�̌������͘A�S���z���v���x�ɓ��ӂ���ꍇ�̌_��̌_����e�ɂ��̂ł���C�܂��C���̓��ӂɌW��Ή��͕s���Y�𑼐l�Ɏg�p�����邱�Ƃ̑Ή��Ƃ������ƂɂȂ邩��C���ӂɌW��Ή������R�ɏ��n�����ɊY��������̂Ɖ����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B���̓_�́C�s���Y�𑼐l�Ɏg�p�����邱�Ƃ̑Ή��Ƃ��Ă̒��،��Ɋւ��鏊���ɂ��Ă݂Ă����炩�ł���B���Ȃ킿�C�`���L�y�n���a���������L�ړI�Œ����C�a�����̒n��Ɍ��z�����������ؒn���t���łb�ɔ��p�����ꍇ�C���p���i���̎ؒn���������͂a�̗L�����ؒn���̏��n�ɂ�鏊���Ƃ������ƂɂȂ邪�C�`�̍s�ׂ͂a�ւ̎ؒn���u�ݒ�v�ł����āC���R�ɏ��n�����̑ΏۂƂȂ�ؒn���́u���n�i�ړ]�j�v�ƂȂ���̂ł͂Ȃ�����C�`���擾���闘�p���v�̑Ή�����n��́C�@�߂ɕʒi�̒�߂��Ȃ�����C�s���Y�����ɊY��������̂Ƃ����ق��Ȃ��i���̏ꍇ�C�a���ؒn�������Ȃ̎��Y�Ɍv�サ���Ƃ��Ă��C�`�ɂ����Ď��Y���n�ɂ�鏊���������Ă�����̂ł͂Ȃ��B�j�B�v �u�{���e�y�n�̎��Y�̒l���ɂ�蒷���Ԃɂ킽���Ē~�ς��ꂽ�����̈ꕔ���ꎞ�I�Ɏ��������Ƃ������ʂ�����C�����I�ɂ͓y�n�̌��{���l�̗��o�Ƃ��ď��n�����Ɖ����ׂ��ł���|�́v�[�Ŏґ��̎咣�ɑ��āu�����Ŗ@�y�ѓ��{�s�߂́C�s���Y�����Ə��n�����Ƃ̎����_�݂̂ł́C���҂̋敪������ł���Ƃ��납��C���߂ɂ����ċ�̓I�Ȕ��f���݂������̂ł���C���̂悤�Ȏ�|���炷��C�����̏��L��ړI�Ƃ��đ��l�ɓy�n���Ԏg�p������s�ׂł����Ă��C���߂Œ�߂��ɊY�����Ȃ���C���n�����ɂ͊Y�����Ȃ��Ƃ����ׂ��ł����āC���Y��ɂ��s���Y�����ɊY������ꍇ�ɁC�X�Ɏ����_�������ď��n�����͈̔͂��g�傷�邱�Ƃ�\�肷����̂ł͂Ȃ��B�����āC�{���n�����̐ݒ�͓��{�s�߂V�X���P���ɗ��ꂽ���̓��e�̒n�����̐ݒ�ɂ͊Y�����Ȃ�����C�{���_��ɂ��擾����闘�v�����n�����Ɖ����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�v (���n�ɂ���4.2.3.3.�A6�Ł�222.01�|�{�Ǝ����E�Ŕ����a43�N10��31����14��12��1442�ŁA6�Ł�222.02���É���t���Y���^�����E�Ŕ����a50�N5��27�����W29��5��641�ł�) |
| �؉ƌ��́u���Y�v�ɓ�����Ƃ�����Ƃ��āA�������n�ɂ��������������E�����n�����a51�N2��17����22��3��791��(�����������a52�N6��27����23��6��1202�łňێ�)�A�����ɂ����ł����؉ƌ��̑Ή��ɂ����s�n�����a56�N7��17����27��11��2150��(�m��)�B���q�G�d�Ŗ@24��270�ł͎؉ƌ������Y�Ɋ܂߂邱�Ƃɏ��ɓI�B |
| ���@9��1��5���ɂ��Ăł��邪���n�����̒�`�ɂ����s�@33��1���A���ɗގ�����K�肪���ꂽ���a34�N�@����79���E���ߑ�85���ɂ�������̎��ĂƂ������n�����a44�N1��28������570��40��(��㍂�����a45�N4��6���Ŏ�59��586�łňێ�)������B |
| �����n���ߘa5�N3��9���ߘa2(�s�E)323���ꕔ��70��11��1255�Ŕ��^1528��159�Ŋ��p�A�ꕔ�p��(���c���q�E�W�����X�g1593��10�ŁA�����S���E�W�����X�g1597���d����5�N180-181��)�c�t�F���[���������Ŗ@38��2���������u�Ɖ����̑��g�p���͊��Ԃ̌o�߂ɂ�茸�����鎑�Y�v�ɓ�����Ƃ�������B������Ȃ���Ƃ��ăX�g���f�B�E�o���E�X�̃o�C�I�������������邱�Ƃ������B�������p�ɂ��ď��@49���A�������p���Y�ɂ��ď��@2��1��19���A����6���e���B�ב֍����v�͎G�����ɓ�����Ɣ��f�����B���Œ��͊O���ʉ݂����n�����̊���ƂȂ�u���Y�v�ɓ�����Ȃ��Ƃ���������̂��Ă���i�ی�2-21�ێ�3-10�ېR5-13�ߘa4�N10��7���u�G�����͈̔͂̎戵���Ɋւ��鏊���Ŋ�{�ʒB�̉���v�j�B�^��Ƃ��Đ�u���z�ʉ݁i�Í��ʉ݁A�Í����Y�j�̏��n�ɂ�鏊���̏��n�����Y�����v�Ŗ@�w581��3-32��(2019)�B |
| �L���،������Y�ɓ�����Ȃ��Ȃ�� (���R�����n������27�N3��12����62��7��1307��)������������27�N10��14����62��7��1296�ŕS�I7��43(�����p��=�~�엳�ETKC�Ō����25��4��122��) ����33��1�u���̋K�肷����n�����̊���ƂȂ�u���Y�v�ɂ́C��ʂɂ��̌o�ϓI���l���F�߂��Ď���̑ΏۂƂ���C�����v��������悤�ȑS�Ă̎��Y���܂܂�邪�C���̈���ŁC��L�̑����v�����Ȃ����́C���Ȃ킿�C�Љ������͂��������\�����S���Ȃ��悤�Ȗ����l�Ȃ��̂ɂ��ẮC�����̋K�肷����n�����̊���ƂȂ�w���Y�x�ɂ͓�����Ȃ��v�B�u�����̌o�ϓI���l�����v���y�ы��v������b�Ƃ�����̂ł���ȏ�C���̏��n�̎��_�ɂ����āC�����̌������@�I�ɂ͏��ł��Ă��Ȃ������Ƃ��Ă��C��ʓI�Ɏ��v���y�ы��v���������ɍs�g������]�n�������Ă����ꍇ�ɂ́C��ɂ����̌����������ɍs�g������悤�ɂȂ�W�R��������Ȃǂ̓��i�̎���F�߂��Ȃ�����C���v���⋤�v������b�Ƃ��銔���Ƃ��Ă̌o�ϓI���l��r�����C���͂�C�����v����悤�Ȑ�����L������n�����̊���ƂȂ�u���Y�v�ɂ͊Y�����Ȃ��v�B �����l�������̗ޗ�Ƃ��������������T���۔F�����E��t�n������18�N9��19����54��3��771��(������������18�N12��27����54��3��760�łňێ�)(�ėR�ԁE�W�����X�g1350��110��)�c�u�����̏����v�_(��q��������������27�N10��14���ł͎g���Ȃ��_��)�B ���É��n������17�N7��27�����^1204��136��(���É���������17�N12��21���Ŏ�255������10249�ňێ�)�c�a����������S���t������ɂ����n������ے� |
| �É��n������25�N5��10���Ŏ�263������12213���p�E������������25�N10��10���s���Ŏ�263������12305���p�m��(�א쌒�E�d�ői��17��149-172��)�c�c�ŗ��m�Ɩ��̉c�ƌ����n�̑Ή������n�����łȂ��G�����ł���Ƃ��ꂽ����B |
| ��d�����@�F6�Ł�222.04��V�]�s��n�R�����n�����E���R�n������3�N4��18����37��12��2205�ŕS�I7��42�i������������6�N3��15���Ŏ�200��1067�łňێ��j �@���|�@��n�����ɂ���Đ��������v�̕����͎��Ə���(���͎��Ƃɓ�����Ȃ���ΎG����)�A���̑��̕����͏��n�����B�������A�̔��ړI�ȊO�Œ����ԕۗL���Ă���A��n�����Ɏ��|�������ꍇ�A�u���̓y�n���̏��n�ɂ�鏊���ɂ́A�E���H��������O�ɐ��ݓI�ɐ����Ă������Y�̉��l�̑����v�ɑ���������������������܂܂�Ă���B�����ŁA���̂悤�ȏꍇ�ɂ́A�E���H�ɒ��肷��܂ł̎��Y�̉��l�̕����ɑ������鏊�������n�����Ƃ��A���̑��̕��������Ə����܂��͎G�����Ƃ���̂������ł���B�v �@�u���n�����Ǝ��Ə����Ƃɋ敪���ׂ����R�́A�c�c�Վ��I�A�����I�ɔ������鏊���ł��邽�߁A���Ə����ɔ�r���ĒS�ŗ̗͂����n�����Ƃ��ׂ��������������x�܂܂�Ă���A��������Ə����Ƃ��ĉېł���̂͐ŕ��S�̌�������������ł���v �@�l�@�@�{���œ�d�����@�̍̔ێ��̂͑��_�ƂȂ��ĂȂ��B�܂����Ə����Y�������i�����咣�ɂ��Α�n�����ɂ�鑝�������j���Z�o���Ďc�z�����n�����Ƃ��邩�A�{���̂悤�ɂ܂����n�����Y�������i�������n�����͌y�ۂ����j���Z�o���Ďc�z�����Ə����Ƃ��邩�A�Ƃ����A���n�����Ǝ��Ə����Ƃ̋敪���@�ɂ��āA�c�_�̗]�n���c��B���|�̒ʂ�ł���ƁA��n������̒n�������i�y�n�o�u���Ȃǁj���������Ə����ł���Ƃ���Ă��܂��B |
4.2.3.2. �ېŕ��@
���n���������������z�|�擾��|���ʍT���z(50���~)(����33��3�E4��)���������z��6�Ł�143.02���ݔ��������E������������11�N6��21������1685��33��(��3.1.3.2.)�B�����Ƃ��Ĕ������i�B��O�Ƃ��āA�݂Ȃ����n(����59��1��)�K�p���͏��n���Y�̎����B
�Z�����n�����E����33��3��1���A�������n�����E��2���̋�ʁc�c�������[�u(averaging system)�̈��B
�����Ԃ������ˌ���(bunching effect)�����邵�C���t���ɂ�閼�ړI����(�����I�ȖL������Ȃ����l�ゾ���̗���)�������Ȃ��Ă��܂��̂ŋ~�ς���B[���]�ނ��������[�u�Ƃ��Ă͑e������̂Ōܕ���������ɉ��߂�ׂ��ł��낤�B
�Ŕ����a47�N12��26�����W26��10��2083�ŕS�I7��41bq�ɂ��Β��������ٍ��̏ꍇ�ł����n�����͈ꎞ�Ɏ����������̂Ƃ��ĉېł��邱�Ƃ������ł���B���݂�����132�������[�������Ă���B
4.2.3.3. ���n�̈Ӌ`
�T�����E�������X�y�n���؎����E�Ŕ����a45�N10��23�����W24��11��1617��(��3.1.1.5.�ސ�����)�D�y�n������31�N3��27���Ŏ�269������13259����28(�s�E)31��(����p�q�E�W�����X�g1545��111��2020.5�A���J���j�E�d�ŗ�1�N188��)�c�푊���l�o�̖@�葊���l�͂w�i�����j�y�тp��ł������B����5�N11��18���A�o�͂w�Ɉ�Y�̑S�Ă𑊑�������|�̌����؏��⌾���쐬�����i�o�̎��S�N�����͕s���j�B�w�͔_�n1�`�_�n8�i�u���{���e�_�n�v�Ƃ����j�𑊑������B�w�͑d�œ��ʑ[�u�@�i����7�N�����O�j70����6��1���Ɋ�Â��u�[�ŗP�\�̓K�p�������_�n���̖����v��Y�t���[�ŗP�\�z��4778���~�ƋL�ڂ����\������6�N12��9���ɒ�o�����B����6�N�ɂw�͂p�炩��◯�����E�����i���݂͈◯���N�Q�z�̐����j�����B�n�Ŗ������́A�w�̑����Ŋz��4237��440�~�A�P�\�Ŋz��4134��4800�~�Ƃ���X�������������B����10�N�A�_�n3�y�є_�n4�ɁA���ɓ������z����ړI�œ]�p���i�_�n�@4���j�����A�s�i�w�̒��j�j���L���`�̖{���{�݂����z���ꂽ�i�u�{���]�p�v�Ƃ����j�i�w�̎�����4636.875���āB4636.875��6224.375��7.45���j�B����13�N�A�w�͂p��Ƒi��̘a���������i�u�{���a���v�Ƃ����j�B���{���e�y�n�̂p��̋��L�����ƁA�_�n9�̂w�̋��L�����Ƃ����������i�u�{�������v�Ƃ����j�B�w�͂p��ɖ{�������̐��Z�����x�������B�{���a���ɂ��w����p���8848.75���āi8848.75��62224.375��14.22���j�̔_�n���ړ]�����i7.45���{14.22����20���j�B�ȏ�̎����̉��A�{���]�p�y�і{���������d��70����6��1��1���u���n���v�ɊY������B
���n���X���b�v����ɂ��āA���É��n������29�N6��29���Ŏ�267������13028����28(�s�E)78���͏��n�Y������F�ߏ��n�����̔�����F�߂����A�T�i�R���É���������29�N12��14���Ŏ�267������13099����29(�s�R)74���͊���i��������j�_��ł���ƔF�ߏ��n�Y������ے肵�����̐�����F�e�����B
�����33-2(���n�S���ɌW�鎑�Y�̈ړ])�@���҂��A���ٍ̕ς̒S�ۂƂ��Ă��̗L���鎑�Y�����n�����ꍇ�ɂ����āA���̌_�Ɏ��̂��ׂĂ̎����𖾂炩�ɂ��Ă���A���A���Y���n�����S�ۂ݂̂�ړI�Ƃ��Č`���I�ɂ��ꂽ���̂ł���|�̍��ҋy�э��҂̘A���ɌW��\�������o�����Ƃ��́A���Y���n�͂Ȃ��������̂Ƃ���B���̏ꍇ�ɂ����āA���̌セ�̗v���̂����ꂩ�������Ɏ������Ƃ����͍��s���s�̂��߂��ٍ̕ςɏ[�Ă�ꂽ�Ƃ��́A�����̎����̐��������ɂ����ď��n�����������̂Ƃ���B
(1)���Y�S�ۂɌW�鎑�Y�����҂��]���ǂ���g�p���v���邱�ƁB
(2)�ʏ�x�����ƔF�߂��铖�Y���ɌW�闘�q���͂���ɑ�������g�p���̎x���Ɋւ����߂����邱�ƁB
(��)�`����A���ߏ����t���n���͍Ĕ����̗\��Ƃ���Ă�����̂ł����Ă��A��L�̂悤�ȗv����������Ă�����̂́A���n�S�ۂɊY������B
| 6�Ł�222.02 ���É���t���Y���^�����E�Ŕ����a50�N5��27�����W29��5��641�ŕS�I7��45nf �����E���_�@�������s���Y���w(�v)����v(��)�Ɉړ]�B���̎����n�����ېł����邩�H ��R�����@�Ԏӗ��x���̎�|������ېŁB(���S���������B��R�̈ԐЗ��͌뎚) �T�i���R�@�Ԏӗ��Ƃ������̂͌��(����)�B���Y���^�ł�����n�����͔������Ȃ��B(�ԐЗ��̎x�����Ă��ŋ��͂�����Ȃ������Y���^�Ƃ��Ď�Α��^�ł��ېł���邩������Ȃ�����{���y�n�A�����̏��n���ԐЗ��Ƃ��Ă���A�Ƃv�̑㗝�l������������Ɋ�Â��ė]�v�Ȏ����������炵���B�����Ƃ��č��Y���^�ɑ��^�ł͉ۂ����Ȃ��B�ˑ����9-8)(�]�k:�}�{�Ƒ��^�łɊւ��đ����21��3-3�`21��3-6) �T�i�R�����@�Ԏӗ��ł����Y���^�ł����̗��s�ł���A�w�͍�����̉���Ƃ����o�ϓI���v������̂ŁA���n�����͔�������B �㍐���R�@�㕨�ٍ��ɂ����镔���ɂ����n��������������̂͂Ƃ������A���Y���^�ɓ����镔���ɂ����n�����͔������Ȃ��B�u���^�҂����̂���[���Y���^]�ɂ�艽��o�ϓI���v��������̂ł͂Ȃ��v�@���Y���^�́u���^�_��̐����ɂ�閳���ł̌����ړ]�c�ƑS������ł���v(��q�̏���59��(�݂Ȃ����n)�͌l�ɑ��鑡�^��K�p�͈͂Ɋ܂߂Ă��Ȃ����Ƃɗ���) �ō��ٔ��|�@�u���n�v�T�O�ɂ��āu�����Ŗ@33��1���ɂ����w���Y�̏��n�x�Ƃ́A�L���������킸���Y���ړ]�����邢�����̍s���������v�B �@�u���^�҂́c�c���^�`���̏��łƂ����o�ϓI���v�������v �l�@ �㕨�ٍς̏ꍇ�͏��n�������������邱�Ƃɂ��Ăw����e�F���Ă���B �ō��ق��A���Y�u�ړ]�v�́u�L����������v�Ȃ��ƌ����Ă���̂ɁA�Ȃ��u�o�ϓI���v�v�Ƃ����L�����Ɍ��y���Ă���̂��A�_���̉^�т����R�Ƃ��Ȃ����݂��c��B�ō��ٔ����Ƃ����ǂ��l�Ԃ��������͂ł��邩��d���Ȃ��B�ŁA���ǁu�o�ϓI���v�v�Ƃ����L�����͕K�{���ۂ��H�K�{�ł͂Ȃ��Ɖ����ׂ��B �w��(���q�G):�u���@768���̍��Y���^�v���敪�c�u�v�w���ʍ��Y�̐��Z�v�u�����ɂ�鑹�Q�̔����v�u������̕}�{�v �u�v�w���ʍ��Y�̐��Z�̈Ӗ��ō��Y�����^���ꂽ�ꍇ�́A���̎��������L���Y�̕����ł����āA���Y�̏��n�ɂ͓�����Ȃ��Ɖ������B�v (�Ԏӗ��Ȃ���n�ɂ����適��R�E�T�i�R�B�Ȃ��{���̕s���Y�͂w�v������ɍw�����ꂽ���̂ł��邪�u�w�����L���Y�ł������v�Ƃx�͎咣���Ă���B) �@�Ⴆ�`�E�a�̋��L�ł��邪�`�P�Ɩ��`�̎��Y�ɂ��āA��������A�����ɂ��Ė��`���`����a�ɕς���Ă��A�@�I�����ɂ����Ă`����a�ւ̏��n�͂Ȃ�(�ړ]�͂Ȃ�)�A�ƍl������B�����33-1��7(��f) �@�Ĕ��_(���q���ᔻ)�F�E�c�[���E�����p���u���Y���^�Ƒd�ł��߂�����v�@�w����357��64�Łc�c���������ł́u�v�w���ʍ��Y�̐��Z�v�u�����ɂ�鑹�Q�̔����v�u������̕}�{�v���ꂼ��̊z��������Ƌ�ʂ��Ȃ��B(��Ȃ��������o�������������Ɍ����č��Y���^�ł����������������Ȃ��̂ő����I��点�����Ƃ����C����������)ks �@�āX���_�F�R�̎�|��������Ƌ�ʂ����������Ⴊ���݂���A�u�v�w���ʍ��Y�̐��Z�v�����ɂ����n�����������Ƃ��Ĉ����Ă悢�̂ł͂Ȃ����H �@�āX�X���_�F�Ŕ�����7�N1��24���Ŏ�208��3�ł̌��R������������6�N6��15���Ŏ�201��519�ł��u�v���`�̎��Y�`���ɑ���Ȃ̍v�������݉�����܂ł̊ԁA�Ȃ��v���`�̍��Y�ɑ��Ȃ�炩�̐��ݓI�Ȏ�����L����Ƃ��Ă��A����͖���������������܂��Ă��Ȃ����ۓI�Ȍ����Ƃ����ׂ����̂ł���i�E���Y�`���̑ԗl�ɂ͎�X�l�X�Ȃ��̂����肤�邵�A�v�w�̍��Y�͒ʏ핡���̂��̂��琬����̂ł��邩��A�����̂��ׂĂɂ��Ĉꗥ�ɍȂ��̈�̋��L������L����Ƃ݂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�j�A�����̍��Y���^�葱������ď��߂ċ�̓I�Ȍ����Ƃ��Ċm�肷����̂ł���B���������āA���Y���^���P�ɉE���ݓI���������݉������A����𐳎��ɋA�������邾���̎葱�Ƃ͂����Ȃ��̂ł����āA���Y���^�ɂ���ď��߂ĕv���`�̍��Y�ɑ���Ȃ̏��L�����͋��L��������������Ƃ��킴��Ȃ�����A�����Ɏ��Y�̏��n�Ɩڂ�������������v(���L�n�̕����Ƃ͈Ⴄ�Ƃ����_��)�Ɣ������Ă���̂Ŕ��Ⴊ���q�����̗p����\���͂Ȃ��Bkt �v�ɂƂ��Ă̎��Y�̎擾��Ə����38-6�@(cf.���q�����ƒʒB�̒ʂ�ɂȂ邩�H) cf.�D�y��������24�N1��19����59��4��1091�Łi���R�D�y�n������23�N5��16����59��4��1070�Łj�c�����ɔ������Y���^�����@768��3���̎�|�ɔ����ĕs�����ɉߑ�ł���Ƃ��āA���Q�s����i���@424���A�Œ�42���j�̑ΏۂƂȂ�Ƃ�������(����ƗY�E�W�����X�g1464��132-135��2014.3)�i[���]�����i�Ȃ�ǁA�������̏����Ԃ�͍ȑ��ɊÂ�����悤�Ɋ�����j�B |
�����33-1��4(���Y���^�ɂ�鎑�Y�̈ړ]) ���@��768���s���Y���^�t�c�c�̋K��ɂ����Y�̕��^�Ƃ��Ď��Y�̈ړ]���������ꍇ�ɂ́A���̕��^�������҂́A���̕��^���������ɂ��������̎��̉��z�ɂ�蓖�Y���Y�����n�������ƂƂȂ�B
(��) 1�@���Y���^�ɂ�鎑�Y�̈ړ]�́A���Y���^�`���̏����Ƃ����o�ϓI���v��Ή��Ƃ�����n�ł���A���^�ł͂Ȃ�����A�@��59���1���s�݂Ȃ����n�ېŁt�̋K��͓K�p����Ȃ��B
2�@���Y���^�ɂ��擾�������Y�̎擾��ɂ��ẮA38�|6�Q�� �mcf.���^�y�n��̏��n�����n
�����33-1��7(���L�n�̕���) �l�����̎҂Ɠy�n�����L���Ă���ꍇ�ɂ����āA���̋��L�ɌW���̓y�n�ɂ��Ă��̎����ɉ����錻���������������Ƃ��ɂ́A���̕����ɂ��y�n�̏��n�͂Ȃ��������̂Ƃ��Ď�舵���B�m(��)���n
�����38-6(���^���Y�̎擾��)�@���@��768���s���Y���^�t�c�c�̋K��ɂ����Y�̕��^�ɂ��擾�������Y�́A���̎擾�����҂����̕��^�������ɂ��������̎��̉��z�ɂ��擾�������ƂƂȂ����Ƃɗ��ӂ���B
| ���^�y�n��̏��n�����E�����n������3�N2��28���s�W42��2��341�Ŋm��S�I4��44 �����@�g(���v)���w(����)�@�{���y�n�����Y���^�Ƃ��ď��n�B�g�̏��n�������z�͖�2.3���~(�P�Ǝ�����i�B�ʑi�Ŋm��)�B�قǂȂ��w�͖{���y�n���b�y�n�ƈ�̂Ŗ�3.5���~�ŏ��n�B�x�Ŗ������́A�w�̎擾���z����2.3���~�ł���Ƃ̑O��ŁA���z��1.2���~�̏����z����X�������B�אڒn�ƈ�̂Ŏ�����ꂽ�����P�Ǝ�����i�������l�����B �����@�����F�e(�w���i)�B�u�擾�҂́A���Y���^�������Ƃ����o�ϓI���v�����ł����㏞�Ƃ��ē��Y���Y���擾�������ƂƂȂ�v�B �@�u�w���ł�����b�y�n�ƈ�̂Ƃ��ė��p���邢�͏������邱�Ƃ����̑O��Ƃ���Ă������̂Ɛ��F����v�B �@�u���������A���鎞�_�ɂ�����y�n���̎��Y�̋q�ϓI�ȉ��z�Ƃ������̂́A�Ӓ蓙�ɂ���ď�Ɉ�`�I�ɓ��肳���Ƃ��������������̂ł͂Ȃ��A������x�̕����������͈͓��̉��z�Ƃ��ĊϔO�����ׂ����̂ł���v �l�@�@���Y���^���̕��^��(�Ⴆ�Εv)�ɂƂ��Ă̏��n�������z�Ǝ�̎�(�Ⴆ��)�ɂƂ��Ă̎擾��Ƃ���v���邱�Ƃ����x��z�肳��Ă���Ƃ͂����A�ېŏ����͕ʁX�ɂȂ���i�葱�����ʁX�ɂȂ邽�߉ېŘR�����������B�{���ł͌��ʂƂ��Ė�1.2���~���ېŘR���������Ă���B�g�Ƃw�ŕs�����I�ȉېł��Ȃ���Ă��邪�A��������ۂ��x�I���t���͂Ȃ��B���������A��d�ېł����������邪�A����ł͒v�����Ȃ�(?)�B �@�Ƃ���Łu�w���ł�����b�y�n�ƈ�̂Ƃ��ė��p���邢�͏������邱�Ƃ����̑O��v�Ƃ�����������{�����͂g�Ƃw�ɂƂ��Ė{���y�n�̎����͈�v����(�����ϔO����ɂ����Ȃ�)�Ƃ����O����̂��Ă���悤�ɓlj��ł������ŁA�Ŕ��ߘa2�N3��24���W��263��63��(��4.2.3.5.)�͏��n�l�Ə���l�Ƃœ���̎��Y�̎������قȂ肤�邱�Ƃ�O��Ƃ��Ă���悤�ɓlj��ł���B |
�����33-6(�؉Ɛl���闧�ޗ�)�@�؉Ɛl�����ݎ̖ړI�Ƃ���Ă���Ɖ��̗��ނ��ɍۂ��邢���闧�ޗ��̂����A�؉ƌ��̏��ł̑Ή��̊z�ɑ������镔���̋��z�́A�ߑ�95���s���n�����̎������z�Ƃ����⏞�����t�ɋK�肷����n�����ɌW��������z�ɊY������B
(��)�@��L�ɊY�����Ȃ����ޗ��ɂ��ẮA34�|1��(7)�Q��
�����34-1(�ꎞ�����̗Ꭶ) (7) �؉Ɛl�����ݎ̖ړI�Ƃ���Ă���Ɖ��̗��ނ��ɍۂ��邢���闧�ޗ��i���̗��ނ��ɔ����Ɩ��̋x�~���ɂ�茸�����邱�ƂƂȂ�؉Ɛl�̎������z���͋Ɩ��̋x�~���Ԓ��Ɏg�p�l�Ɏx�������^���؉Ɛl�̊e�폊���̋��z�̌v�Z��K�v�o��ɎZ���������z���U���邽�߂̋��z�y�їߑ�95���s���n�����̎������z�Ƃ����⏞�����t�ɋK�肷����n�����ɌW��������z�ɊY�����镔���̋��z�������B�j
(��) 1�@�������z���͕K�v�o��ɎZ���������z���U���邽�߂̋��z�́A���̋Ɩ��ɌW��e�폊���̋��z�̌v�Z�㑍�������z�ɎZ�������B
�@2�@�ߑ�95���ɋK�肷����n�����ɌW��������z�ɊY�����闧�ޗ��ɂ��ẮA33�|6�Q��
���ŗ�95���i���n�����̎������z�Ƃ����⏞�����j�u�_��c�c�Ɋ�Â��A���͎��Y�̏��Łi���l�̌������܂ށB�c�j�����Ƃł��̏��łɑ���⏞��čs�Ȃ����̂̐��s�ɂ����n�����̊���ƂȂ�ׂ����Y�����ł��������Ɓi�ؒn���̐ݒ肻�̑����Y���Y�ɂ��ĕ�����ݒ肵���͍����������邱�Ƃɂ�艿�l�������������Ƃ������B�j�ɔ����A���̏��łɂ��ꎞ�Ɏ�⏞�����̑�����ɗނ�����̂̊z�́A���n�����ɌW��������z�Ƃ���B�v
4.2.3.4. �擾��͈̔�(����33��3���E38��)
| 6�Ł�222.05 �x�����q�t����p�����E�Ŕ�����4�N7��14�����W46��5��492�ŕS�I7��46mt �����E���_�@3000���~�؋����ď��a46�N4��16���ɕs���Y�w���B���N6��6�����Z�J�n�B���a53�E54�N�ɏ��n�B���Z�p�s���Y�擾�̂��߂��ؓ������q���擾��Ɋ܂܂�邩�A�܂܂��Ƃ��Ăǂ͈̔͂��H ��R���|(�����n�����a60�N5��30��)�@�u�g�p���l�����Ɏx�z����ړI�̂��߂̎ؓ������q�̎x���́A���Y�̒l���Ƃ͉���֘A����L���Ȃ�����A���n�����̌v�Z�ɂ����Ĕ�p�Ƃ��čT�������Ȃ��v�B �@�u���̕��́A���Ɏ��Y�̎���ɂ��g�p�̗��v(������A������)�ɉېł���鐧�x���Ƃ���Ƃ���A���̏����ɂ��Ă̔�p�Ƃ��čT������邱�ƂƂȂ�v ��R���|(�����������a61�N3��31��)gl�@�ؓ������q���擾��Ɍ����Ƃ��Ċ܂܂��B�������A���Z�̗p�ɋ����ꂽ���_�Ȍ�A�������͎g�p���������_�Ȍ�A�u���Y�̈ێ��E�Ǘ��Ƃ����ړI�̂��߂̔�p�v�ւƐ������ω�����A�܂����g�p�u���Ԃ̋A�����v�Ɠ����ƌ��Ȃ�����v�B�擾��ɎZ�����Ȃ������́A�A������(��4.3.4.)���ېł���Ȃ����ƂƐ����I�ł���B �ō��ٔ��|�@�Ǝ��̂��߂̎ؓ������q�Ɠ������u������Ȃ����Ǝ���ɂ����Ȃ��v�̂Ŏ擾��Ɋ܂߂Ȃ��̂������B �@�������A���Z�̗p�ɋ�����ȑO�̊��Ԃł����Ă����q�x�����]�V�Ȃ������Ƃ���A�u�ؓ����̗��q�̂����A���Z�̂��ߓ��Y�s���Y�̎g�p���J�n����܂ł̊��ԂɑΉ���������́A���Y�s���Y�����̎擾�ɌW��p�r�ɋ������ŕK�v�ȏ�����p�Ƃ������Ƃ��ł��v�A�u���Y�s���Y���擾���邽�߂��t����p�ɓ�����v�B �l�@�@���_�Ƃ��ẮA�{���ō��ٔ��|����R���|���A���Z�O�̊��ԂɑΉ����闘�q�͎擾��Ɋ܂܂�A���Z��̊��ԂɑΉ����闘�q�͎擾��Ɋ܂܂�Ȃ��Ƃ����_�ɂ����ċ��ʂ��Ă���(�����̎g�p�ɒ��ڂ��邩�A�g�p�\���ɒ��ڂ��邩�A�Ƃ������ق͂���)�B�������_���\���͈قȂ�A�����Ɨ�O���t�]���Ă���B�S�I����͍ō��ٔ��|��ᔻ���A��R���|�������]�����Ă���B �@�Ȃ��A�ؓ������q�́A�Ǝ��̂��߂ł��ꎖ�Ƃ̂��߂ł���A���q���S�҂̏����Y�����������炷���ł���Ƙ_������(����nj[�E�@�w����365��123�ňȉ��B�Ȃ��A������Ƃ����đS�ď����Ŗ@��T����F�߂�ׂ��Ƃ������Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��B��ېŏ����ɑΉ�����ؓ������q�̍T����F�߂���d�ōْ���(tax arbitrage)���\�ƂȂ��Ă��܂�����ł���B��͂��R���|�̘_���ɋ߂�)�B �@�g�p�J�n�O�̊��ԂɑΉ����闘�q���u�t����p�v�ɓ�����Ƃ���_�����ō��ٔ��|�ŏ[���ɂ͘_�����Ă��Ȃ��悤�Ɍ����邪�A���̓_�͂����������_�ƂȂ��Ă��Ȃ������Ƃ��l������B |
�����38-8(�擾��ɎZ������ؓ����̗��q��)�u�Œ莑�Y�̎擾�̂��߂Ɏ���ꂽ�����̗��q�c�c�̂����A���̎����̎ؓ���̓����瓖�Y�Œ莑�Y�̎g�p�J�n�̓��i���Y�Œ莑�Y�̎擾��A���Y�Œ莑�Y���g�p���Ȃ��ŏ��n�����ꍇ�ɂ����ẮA���Y���n�̓��B�c�c�j�܂ł̊��ԂɑΉ����镔���̋��z�́A�Ɩ��̗p�ɋ�����鎑�Y�ɌW����̂ŁA37�|27����37�|28�ɂ�蓖�Y�Ɩ��ɌW��e�폊���̋��z�̌v�Z��K�v�o��ɎZ�����ꂽ���̂������A���Y�Œ莑�Y�̎擾��͎擾���z�ɎZ������B�v�m��2���y��(��)���n
| �����擾�̈ꎞ�����v�㎞���Ǝ擾�� �����n������4�N3��10����39��1��139�Ŋm��S�I5��50 �����@�w���S���`����S�Z�a���`�̓y�n��1960�N���ɑ��^���ꂽ�B�w��1970�N�Ɏ擾���������p���a�̑����l�b�ɏ��L���ړ]�o�L�����߂Ē�i�����B�w���i��1983�N�Ɋm�肵���B�`�̑��̑����l�c���w�Ɉ◯�����E���������A�w�͂c��1983�N�ɑ㕨�ٍςƂ��Ė{���y�n�����n�����B�w��1983�N�̏��n�����̌v�Z�ɂ����莞���擾�����m�莞�̎������擾��ɎZ�����悤�Ƃ����B �@S35.5�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@S45.10�@�@�@�@�@S58.12��S58.12 ���������������������������������������������������������������������̌o�� �a���`�y�n�`���w���^�@�@�w�������p�@�@���������m�聕�w���c�㕨�ٍ� ���|�@�u�y�n�̎����擾�ɂ�闘���́A�����Ŗ@��A�ꎞ�����Ƃ��ď����ł̉ېł̑ΏۂƂȂ�A���̏ꍇ�̎������z�́A���Y�y�n�̏��L���擾�����ł����������p���̓��Y�y�n�̉��z�ł���Ɖ����ׂ��ł���(���@36��1���A2��)�B��������ƁA���Y�y�n�̎������p���܂ł̒l���v�́A�E�ꎞ�����ɌW��������z�Ƃ��ď����ł̉ېł̑ΏۂƂ���邱�ƂɂȂ邩��A�����擾�����y�n�����n�����ꍇ�̂��̏��n�����ɑ���ېł͉E�������p���ȍ~�̓��Y�y�n�̒l���v�ɑ��čs�������ƂɂȂ�A���������āA�E���n�����̌v�Z��A�����擾��̊z�́A�E�ꎞ�����ɌW��������z���Ȃ킿�������p���̓��Y�y�n�̉��z�ɂ���ׂ����ƂƂȂ�B�v cf.�Ŕ����a61�N3��17�����W40��2��420��ba�c�c���Ŏ����ɂ��Ē�~�������E���p�������̗p(�_�n�̔����Ɋ�Â����m���ɑ��鏊�L���ړ]���\�����͐������̏��Ŏ������Ԃ��o�߂��Ă����̌�ɉE�_�n����_�n�������ꍇ�ɂ́A����ɏ��L�����ړ]���A��_�n����ɂ��ꂽ�����̉��p�͌��͂��Ȃ��B) �l�@�@���@144���̑k�y���ɏƂ炷�Ǝ������p���ł͂Ȃ��������N�Z���Ɉꎞ��������������ƌ����Ȃ����Ȃ����A���܂�Ɏ��ԁinot���́j���炩������Ă��邽�߂������E�ٔ���ŋN�Z�������̗p����邱�Ƃ͂Ȃ��B�����������Ƃ����l�����͂��肦�Ȃ��ł͂Ȃ�(���i��)���A���@��A�����������Ɍ��͂���������Ƃ͌�����Ƃ�����_������B�{�����̎������p�����́A6�Ł�225.01�y�n�����擾�����E�É��n������8�N7��18���s�W47��7=8��632�ŕS�I7��15(��4.2.9.�ꎞ����)�ł��̗p����Ă��邪�A�������p�������Ó�����͎̂����擾�ɂ��đ������Ȃ��ꍇ�Ɍ�����ׂ��ł͂Ȃ����Ƃ��l�����A�����擾�̐��ۂɂ��đ���������ꍇ�͂w�̎咣�̒ʂ������m�莞����Ƃ��ׂ��ł��낤�B�����m�莞���̕���6�Ł�232.03���������z���������E�Ŕ����a53�N2��24�����W32��1��43��(��4.4.3.�Ǘ��x�z�)�̌����_(�����̌��_�ł͂Ȃ�)�Ƃ������I�ł���B ���s�����y�n�r�������E��㍂������14�N7��25����49��5��1617��(��3.1.2.4.) �����������������������������������������������������������������̌o�� �@��L�@�@�@�@�@�����@�@���������@�@�������p �@�������������Ƒ������ǂ�����(�H)�F���ŕs���R��������19�N11��1���ٌ��E�ٌ�����W74�W1��(��3.1.2.4.)(�ޗ����ŕs���R��������14�N10��2���ٌ��E�ٌ�����W64�W1��)�c�c�擾���������と�����J�n���擾�������p�Ƃ������n��ŁA�y�n�𑊑������҂������擾���p�҂ɔs�i���y�n��D��ꂽ���߁A�y�n����̑O��̑����ł̌v�Z�����ł���Ǝ咣�����B�R�����́A��~�������i���p�����j���ێ����i�܂莞�����������͍̗p���Ă��Ȃ��j�A�����J�n���_�œy�n���������Y���珜����鎖�ɂ͂Ȃ�Ȃ��Ƃ��A�]���z���Ƃ��A���ʂƂ��Ĕ[�Ŏ҂��~�����B�a�J��O�E�Ŗ����ጤ��120��54�ł͕]���z���Ƃ��鏈���ɋ^��ł���Ƃ��A�[�Ŏ҂��~���Ȃ瑊�����Y���珜���ׂ��ł���Əq�ׂ�B�[�Ŏ҂��~���_���\���Ƃ��ẮA[1]�]�������z����A[2]�������Y���珜�O����A[3]���T���A�Ƃ��������̂����邪�A�������_�������(������[�Ŏ҂��~��Ȃ��Ƃ������_���o���Ă��悢��������Ȃ������ł��邵�A����ł͌��@29��1���̍��Y���ۏ�Ɉᔽ���邩������Ȃ�)�B �����������������������������������������������������������������̌o�� �@��L�@�@�@�@���������@�@�����@�@�@�@�������p �@�����n������4�N3��10���̎擾��̔��f�͏���38��1���̕����ɏƂ炵�����͂����A���n�v�ɂ��ĉېŘR�ꂪ�����鋰�ꂪ���邪�A�������������O�����l�l�ɒ��ڂ�����ł̓�d�ېŖh�~���d���������̂Ɨ����ł���B���̎p���́A6�Ł�222.06�S���t��������^����(�E�R����)�E�Ŕ�����17�N2��1���W��216��279��(��4.2.3.6.)�A6�Ł�211.04�N�����������ی�����d�ېŎ����E�Ŕ�����22�N7��6�����W64��5��1277��(��4.2.10.)�Ƃ����ʂ��Ă���B �@�]�k:�ْ��w�z�[�������E�{�[�����E���Ĕ���������ېł����̂��x�͓����n������4�N3��10���̎擾��̍l�����ɑ���^�₩��o�����Ă���B |
| �y�n���Nj挈�ϋ������E�Ŕ�����18�N4��20���W��220��141��nc �y�n���ǖ@�Ɋ�Â����ϋ�����ю{�݂̋��͋����z�̍��v���A�_�n���n�ɂ�������n��p�Ɋ܂܂�邩�ɓ�����u��ʓI�A���ۓI�ɓ��Y���Y�����n���邽�߂ɓ��Y��p���K�v�ł��邩�ǂ����ɂ���Ĕ��f����̂ł͂Ȃ��v�u�����ɍs��ꂽ���Y�̏��n��O��Ƃ����A�q�ϓI�Ɍ��Ă��̏��n���������邽�߂ɓ��Y��p���K�v�ł��������ǂ����ɂ���Ĕ��f���ׂ��v�Ƃ�������B �@�O�ҁE��҂Ƃ��u�K�v�v�Ƃ������p���Ă��邪�A�T���\�����A�O�҂́u��ʓI�E���ۓI�c�K�v�v�Ȕ�p�������肹���A��҂̂悤�Ɂu�����c�̏��n�v�ɂƂ��Ă̕K�v���ɒ��ڂ��������A���Ə����Ɋւ���K�v�o��(37��1��)�Ɋւ��ʏ�̔�p�Ɍ��肳��Ă��Ȃ����ƂƂ̋ύt���Ƃ��A�Ɨ����ł��悤���B |
4.2.3.5. �������z�ېŁE���Z�ېŁE�݂Ȃ����n(��59��)
����59���i���^���̏ꍇ�̏��n�������̓���m�u�w���݂Ȃ����n�n�Ƃ����j�u���Ɍf���鎖�R�ɂ�苏�Z�҂̗L����R�сc�c���͏��n�����̊���ƂȂ鎑�Y�̈ړ]�������ꍇ�ɂ́A���̎҂̎R�я����̋��z�A���n�����̋��z���͎G�����̋��z�̌v�Z�ɂ��ẮA���̎��R�����������ɁA���̎��ɂ����鉿�z�ɑ���������z�ɂ��A�����̎��Y�����n���������̂Ƃ݂Ȃ��B�@��@���^(�@�l�ɑ�����̂Ɍ���B)���͑���(���菳�F�ɌW����̂Ɍ���B)�Ⴕ���͈②(�@�l�ɑ�����̋y�ьl�ɑ����②�̂������菳�F�ɌW����̂Ɍ���B)
�@��@�������Ⴂ���z�̑Ή��Ƃ��Đ��߂Œ�߂�z�ɂ����n(�@�l�ɑ�����̂Ɍ���B)�m���ŗ�169���F�����̔��������n
�Q �@���Z�҂��O���ɋK�肷�鎑�Y���l�ɑ�������2���ɋK�肷��Ή��̊z�ɂ����n�����ꍇ�ɂ����āA���Y�Ή��̊z�����Y���Y�̏��n�ɌW��R�я����̋��z�A���n�����̋��z���͎G�����̋��z�̌v�Z��T�������K�v�o��͎擾��y�я��n�ɗv������p�̊z�̍��v�z�ɖ����Ȃ��Ƃ��́A���̕s���z���A���̎R�я����̋��z�A���n�����̋��z���͎G�����̋��z�̌v�Z��A�Ȃ������̂Ƃ݂Ȃ��B�v
����60���i���^���ɂ��擾�������Y�̎擾��j�u���Z�҂����Ɍf���鎖�R�ɂ��擾�����O���ꍀ�ɋK�肷�鎑�Y�����n�����ꍇ�ɂ����鎖�Ə����̋��z�A�R�я����̋��z�A���n�����̋��z���͎G�����̋��z�̌v�Z�ɂ��ẮA���̎҂�����������������L���Ă������̂Ƃ݂Ȃ��B
�@��@���^�A����(���菳�F�ɌW����̂������B)���͈②(��②�̂������菳�F�ɌW����̂������B)
�@��@�O���̋K��ɊY��������n
�m2�E3�����c�z��ҋ��Z���W�n
�S�@���Z�҂��O���1����1���Ɍf���鑊�����͈②�ɂ��擾�������Y�����n�����ꍇ�ɂ����鎖�Ə����̋��z�A�R�я����̋��z�A���n�����̋��z���͎G�����̋��z�̌v�Z�ɂ��ẮA���̎҂����Y���Y�����̎擾�̎��ɂ����鉿�z�ɑ���������z�ɂ��擾�������̂Ƃ݂Ȃ��B�v
�d���@39���i�������Y�ɌW����n�����̉ېł̓���j�u�������͈②�c�c�ɂ����Y�̎擾�c�c�������l�œ��Y�������͈②�ɂ����@�̋K��ɂ�鑊���Ŋz��������̂��A�c�c�\�����c�c�̒�o�����c�c�̗����Ȍ�O�N���o�߂�����܂ł̊Ԃɓ��Y�����Ŋz�ɌW��ېʼn��i�c�c�̌v�Z�̊�b�ɎZ�����ꂽ���Y�̏��n�c�c�������ꍇ�ɂ�������n�����ɌW�鏊���Ŗ@��O�\�O���O���̋K��̓K�p�ɂ��ẮA�����ɋK�肷��擾��́A���Y�擾��ɑ���������z�ɓ��Y�����Ŋz�̂������Y���n���������Y�ɑΉ����镔���Ƃ��Đ��߂Œ�߂�Ƃ���ɂ��v�Z�������z�����Z�������z�Ƃ���B�v�m2���ȉ����n
| ���Z�ې����F6�Ł�222.01 �|�{�Ǝ����E�Ŕ����a43�N10��31����14��12��1442�ŕS�I3��60ng ���Ă͏ȗ��B�������^�̏ꍇ�ɂ����n�����ېł���B(�������z�ېłƂ�����|�ł͂Ȃ�) ���|�@�u���̂悤�ȉېł́A���L���Y�������Ŕ��p���Ă��̑���^�����ꍇ�ȂǂƂ̒ލ�������v�Ó��B�܂������E��z���n�u�ɂ������Ď��Y�̏��n�����ېł�����v���邱�Ƃ�h�~���邱�Ƃ�����Ó��B cf.�^�L�Q��������z���n�����E�Ŕ��ߘa2�N3��24���W��263��63��br(��2.2.4.1.h�ʒB�̖@�����A3.1.4.2.�M�`���̓K�p�v��)(���J���j�E�W�����X�g1548��10-11�ŁA�����F���E�d�ŗ�2�N158-159�ŁA��ȏ͔@�E�W�����X�g1564��135-138��) �@�����Ŗ@59��1��(�݂Ȃ����n�ې�)�̓K�p�ɂ�������ꊔ���̕]���Ɋւ��A�����Ŋ�{�ʒB59�|�U�ɖ��L����Ă��Ȃ����Y�]����{�ʒB�̓Ǒւ������e��������B�����̒ʒB���ʂ�{���ɓ��Ă͂߂�ƁA����l���̎����䗦��15�������ł��邽�ߊ������ꊔ75�~(�z���Ҍ������ɂ��]���z�B�z�����Ȃ��ꍇ��75�~)�ƕ]������邱�ƂɂȂ邪�A�ō��ق́A����59��1�������n�l�̊܂݉v�ɐ��Z�I�ɉېł��邽�߂̋K��ł��邱�Ƃ��d�����āA���n�l���̎����䗦�ɒ��ڂ���Ƃ����B���̌�A���ߍT�i�R�ňꊔ2505�~(�ގ��Ǝ�䏀�����ɂ��]���z)���F�߂�ꂽ�B �@�F�ꍎ��E�{��T�q�⑫�ӌ��́A�ʒB���ʂ�K�p����p����ᔻ���A�@���͂����܂Ŗ@�߂ł��邱�Ƃ���������B �R�X�����݊�����Ў����E�����n���ߘa4�N2��14������30(�s�E)359��364��(�ޗ�F���ђʏ�������Ў����E����389��400��401��)�c�c��������������Ђ̊�����������Ђ�1��1500�~�ŏ��n�������Ƃ͏����Ŗ@59��1��2��(�����Ŗ@�{�s��169��)�̒�z���n�ł��莞�����n���[�������A�܂��A������Ђ�������Ђ̊������������j(������Ђ̑�\�����)��1��1500�~�ŏ��n�������Ƃ́A�����Ƃ̍��z���̏����Ŗ@28��1���u���^���v�̎x���ɓ�����A�Ƃ��ꂽ����B |
�����̉ېŌJ����h�~���邽��(���|�{�Ǝ������|)�B
�K�p�͈͏k���̌X���E�o�܂ɂ���6�Ł�222.08�l��������p�n������R�E�É��n�����a60�N3��14���s�W36��3��307��(��4.2.3.6.)���ڂ����B
���菳�F���̖@��[�����ɂ�������������15�N3��10������1861��1�ŕS�I5��44(���R�����n������14�N9��6����13(�s�E)414��)�c�c���菳�F�E�݂Ȃ����n�Ɋւ���푊���l�̏����ł̖@��[�����́A���菳�F�̐\�q�R�����m���ƍق��Ă���ł͂Ȃ��A�����l���푊���l�̎��S��m����������S�����ȓ��B
�����ւ̑��^�E�②�Ƒd��40����COLUMN4-6�E���b�N�E�C�����ʑ�B
����60����2��8.2.1.2.f�F���O�]�o���ېŐ��x(���O���ł�exit tax(�o����)�ƌĂ��)�c�c���Y�܂݉v�ېł̋@��Ȃ��Ȃ�ۂɐ��Z�I�ɉېł���B
4.2.3.6. �d�ő����̈��p���̗L��(60��)
���l��ɂ��ĊT��117-119��(�C������ď������̂ł��З������āI)([���]�����ɍl����Ɨ�5�`��7�̂a�ɂƂ��Ẳېŏ�̈����̈Ⴂ���`�E�a�Ԃ̉��i���ɉe������\��������B��d�ېłƂ����ᔻ������B�������A���������ɉېł��ꂽ��̒~�������ɂ������ł͉ۂ����̂ŁA��d�ېł͌��X�\�肳��Ă���B�ېŌ�̒~���ɂ��đ����ł��ۂ��ׂ��łȂ��A�Ƃ��������_�͐����ł���\�������邪�A��I�����T�O���l�������K�v������kw�B)| 6�Ł�222.06�S���t��������^����(�E�R����)�E�Ŕ�����17�N2��1���W��216��279�ŕS�I7��47gp �S���t������̕�����q�ւ̑��^�Ɋւ��A���`�����萔�����擾��Z����F�߂�����B����38���A60���̕����̉��߂Ƃ��Ă͎擾��Z����F�߂Ȃ��������R�̔��f�ɂ��ꗝ���邪�A�ō��ق�60���̎�|���u�����v�ɑ���ېł̌J���ׁv�Əq�ׂ��B�擾��Z����F�߂Ȃ�������A�����v�ɑ���ېł̌J�艄�ׂƂ�����|���瓱�����������z�̏��n�v�������Ă��܂����˂Ȃ��B |
| 6�Ł�222.08�l��������p�n�����E�Ŕ����a63�N7��19���W��154��443�ŕS�I7��44�E���R�����������a62�N9��9���s�W38��8=9��987�ŕS�I5��41�E���X�R�É��n�����a60�N3��14���s�W36��3��307��(��3.1.2.3.�ؗp�T�O�̏C��)nh �����E���_�@�`���w�ɓy�n���L�����^�B�w�͂`�̑Α�O�ҍ�(�`�̂b�ɑ����)��ٍς��邱�Ƃ�B�w�͓y�n���L�������a�ɏ��n���A�a���瓾�����(���v��2.6���~)�ŁA�`�̑Α�O�ҍ�(���v2600���~)��ٍρB����60��1��1���ɂ��A�w�͂`�̎擾���z�y�я��L����(�������n�����ƂȂ邩�����ƂȂ�)�������p�����H ���|�@�T�i���p(�������p)�@�u�ېŎ����̌J�艄�ׂ��F�߂��邽�߂ɂ́A���Y�̏��n�������Ă��A���̎����ɏ��n�����ېł�����Ȃ��ꍇ�łȂ���Ȃ�Ȃ��v�B �@�{�������S�t���^�̎��Ăł��邪�A59��2���E60��1��2���������u����ȊO�́A��ʌ����ɏ]�����̌o�ϓI���v�ɑ��ď��n�����ېł�����邱�ƂɂȂ�̂ł��邩��A�E�̉ېŎ����̌J�艄�ׂ��F�߂��Ȃ��v�B60��1���u1�����w���^�x�Ƃ́A�P�����^�Ƒ��^�҂Ɍo�ϓI���v���Ȃ����S�t���^�������v�B �l�@ �u���^�v�͖��@������ؗp�T�O�ł���Ή��W���Ȃ����̂ƈʒu�t�����Ă��邪�A�{���ł͏����Ŗ@�̎�|�E�\���ɑ����ďC�����ꂽ(�u���^�v�T�O�̏k������)�B��������ʐ��ł��邪�A������ł����Ă��A�����Ŗ@�̋K��̎�|�ɏƂ炵�ĕʈӂɉ��߂��ׂ��ꍇ�͕ʘ_�Ɛ�����Ă���̂ŁA�{�����ɂ��Ċw�E�ł��܂�٘_�͌����Ȃ��B �@�`�����L����ێ������܂܁A�a�ɔ��p���Ď������ٍς��A�c�z���w�ɓn���A�`���m���ɒ������n�����̉��b���邱�Ƃ��ł���̂ɁA�Ȃ��������Ȃ��������́A�l���Ăق����B |
| �E�����n���ߘa3�N10��12���ߘa��(�s�E)648���Ŏ�271������13617���p�E���������ߘa4�N3��24���ߘa3(�s�R)256���Ŏ�272������13692���p�m��(��ȏ͔@�E�W�����X�g1589��150-153��)�c�c�d�Ŕ��ጤ��������̕����}�������ĕ�����₷���Ǝv���܂��B |
4.2.3.7. ��������(58��)
����58��(�@��50�������|)�i�Œ莑�Y�̌����̏ꍇ�̏��n�����̓���j�u���Z�҂��A�e�N�ɂ����āA��N�ȏ�L���������Œ莑�Y�Ŏ��̊e���Ɍf������̂����ꂼ�����̎҂���N�ȏ�L���������Œ莑�Y�œ��Y�e���Ɍf������́c�c�ƌ������A���̌����ɂ��擾�������Y�e���Ɍf���鎑�Y(�c�c�u�擾���Y�v�c�c)�����̌����ɂ����n�������Y�e���Ɍf���鎑�Y(�c�c�u���n���Y�v�c�c)�����n�̒��O�̗p�r�Ɠ���̗p�r�ɋ������ꍇ�ɂ́A��O�\�O��(���n����)�̋K��̓K�p�ɂ��ẮA���Y���n���Y�c�c�����n���Ȃ������̂Ƃ݂Ȃ��B�v�m��`�܍����A2���ȉ����n�����͏��n�Ɋ܂܂�邪���������Œ莑�Y����p�r�������ɂ͏��n���Ȃ��������̂Ƃ݂Ȃ��Bgm
�l���v������(realize)��������F��(non-recognition)�Ƃ����COLUMN4-6���b�N�C�����ʑ�
�T120���}�\4-3 60����58���̔�r�𗝉����āI
| ��������(�d��37��)�ɂ��āc�c�����n���ߘa3�N9��17���ߘa��(�s�E)486����70��3��344�Ŋ��p(�ʚ����q2022�N7��1���d�Ŕ��ጤ�����)�E���������ߘa4�N5��18���ߘa3(�s�R)240����70��3��390�Ŋ��p�E�ňꏬ���ߘa4�N10��27���Ŏ�272������13766�s�A�m�� �@�����@�c���a�����`�ɖ{���y�n�P�������a59�N12���ɑ��^�����B���͑c���̍����������B���͂b�ɖ{���y�n�P�������a62�N7����3���~�i�����{���y�n�P��2��3400���~�j�ŏ��n���A���̔������Y�Ƃ��Ė{�����Y�i�����B2��3400���~�j���擾���A�d�œ��ʑ[�u�@37��1���i�u����̎��Ɨp���Y�̔������̏ꍇ�̏��n�����̉ېł̓���v�j�̓K�p��O��ɐ\�������B���͕���26�N7���ɖ{�����Y����Ђɏ��n�����B �@�Ŗ����̎咣�@�{�����Y�ɑd��37��1���̓K�p������A�d��37����3��1�������ɂ����u�m37���n�̓K�p�����ҁc�c�̔������Y�v�ɊY�����A37����3��1�������y�ѓ���3���ɂ��擾���z�͈��p���z�ł���B�m���̘_�_�͏ȗ��n �@���|�@�u�d�œ��ʑ[�u�@�R�V���̂R��P���������́C�w��R�V���P���i���ʓ����j�̋K��̓K�p�����ҁi���ʓ����j�x�ƒ�߂Ă���Ƃ���C��ʂɁC�w�K�p�x�Ƃ̕����́C�@�߂̋K���ΏۂƂȂ�ҁC�����C�������ɑ��Ă��Ă͂߁C��������邱�Ƃ��Ӗ�������̂ł���B�����āC���@�R�V���̂R��P���������́C���Y�����ɑ����āC����w�����ҁx�ƒ�߂Ă���C����w���邱�Ƃ��ł���҂ŁC���̓K�p�������́x�ȂǂƂ͒�߂Ă��Ȃ��B���̂悤�ȕ������ɏƂ炷�ƁC���瓯�@�R�V���P���̋K��Ă͂߂ē����ɋK�肷��v�������Ƃ���m��\�������o���C��������ē����̋K��̓K�p�ɂ��ېł̌J���ׂƂ������ʂ������҂́C����ɌW��C���\�����̒�o���͍X������������Ȃ�����C�q�ϓI�ɂ݂ē��Y�v�������Ă������ۂ��ɂ�����炸�C�w��R�V���P���i���ʓ����j�̋K��̓K�p�����ҁi���ʓ����j�x�ɊY�����邱�ƂɂȂ�v�B �@�ېŒ����[�Ŏ҂̐M�`���ᔽ�i���͋֔����j���咣����Ƃ�������������������Ȃ��B |
4.2.4. �R�я���(����32��)
����32���u�R�я����Ƃ́A�R�т̔��̖��͏��n�ɂ�鏊���������B�Q�@�R�т����̎擾�̓��Ȍ�ܔN�ȓ��ɔ��̂����͏��n���邱�Ƃɂ�鏊���́A�R�я����Ɋ܂܂�Ȃ����̂Ƃ���B�v�m3�E4�����n
����89��(�ŗ�)�u���Z�҂ɑ��ĉۂ��鏊���ł̊z�́A���̔N���̉ېő��������z���͉ېőސE�������z�����ꂼ�ꎟ�̕\�̏㗓�Ɍf������z�ɋ敪���Ă��ꂼ��̋��z�ɓ��\�̉����Ɍf����ŗ����悶�Čv�Z�������z�����v�������z�ƁA���̔N�����ېŎR�я������z���ܕ��̈��ɑ���������z�\�̏㗓�Ɍf������z�ɋ敪���Ă��ꂼ��̋��z�ɓ��\�̉����Ɍf����ŗ����悶�Čv�Z�������z�����v�������z���܂��悶���v�Z�������z�Ƃ̍��v�z�Ƃ���B�v�m�ŗ��\�E2�����n
����90���i�ϓ������y�їՎ������̕��ωېŁj�u���Z�҂̂��̔N�����ϓ������̋��z�y�їՎ������̋��z�̍��v�z�c�c�����̔N���̑��������z�̕S���̓�\�ȏ�ł���ꍇ�ɂ́A���̎҂̂��̔N���̉ېő��������z�ɌW�鏊���ł̊z�́A���Ɍf������z�̍��v�z�Ƃ���B
�@��@���̔N���̉ېő��������z�ɑ���������z���畽�ωېőΏۋ��z�̌ܕ��̎l�ɑ���������z���T���������z�c�c�����̔N���̉ېő��������z�Ƃ݂Ȃ��đO���ꍀ�̋K���K�p���Čv�Z�����Ŋz
�@��@���̔N���̉ېő��������z�ɑ���������z���璲���������z���T���������z�ɑO���Ɍf������z�̒����������z�ɑ��銄�����悶�Čv�Z�������z�v�m2-4�����n
����2��(1����\�O�@�ϓ������@���l���琶���鏊���A���쌠�̎g�p���ɌW�鏊�����̑��̏����ŔN�N�̕ϓ��̒��������̂̂������߂Œ�߂���̂������B
�@����\�l�@�Վ������@�̒�邱�Ƃɂ��ꎞ�Ɏ擾����_����ɌW�鏊�����̑��̏����ŗՎ��ɔ���������̂̂������߂Œ�߂���̂������B
�������[�u�Ƃ��Ă̎R�я����̈����\�\�R�я����͑��������z�ƕʂɌv�Z����(22��)�A�ܕ������(����89��1��)�ɂ��B(��q�̑ސE�������������[�u�̈��)
�ϓ������E�Վ������̕��ωېłɂ��Ă̓P�[�X�u�b�N6�Ł�243.01��332�ł̌v�Z�����Q�Ɓi�w�����͕�����Ȃ��Ă��悢�j�B
�����Ԃ����������̃X�|�[�c�I��E�|�\�l���͏���89���A90���ł��܂��~�ςł��Ȃ��B�~�ς��悤�Ǝv���Ȃ�y���U����/�����Ă���N���z�ɑ��ݐi�ŗ���K�p����悤���x�v���ׂ��B�Ƃ��낪�A�ꌩ���z�I�Ɏv���邱�̒�Ăɂ��đd�Ŗ@�w�҂̊Ԃł͂��܂�^���������Ȃ��B cf. William Vickrey, Averaging of Income for Income-Tax Purposes, 47 Journal of Political Economy 379-397 (1939)
4.2.5. �s���Y����(����26��)
| 6�Ł�224.01�s���Y�����̈Ӌ`�@���[�^�[�V���b�v�����������n�����E���É��n������17�N3��3�����^1238��204�ŕ���16(�s�E)9��(���B�N�E�W�����X�g1341��192��)�c�cX�����L�y�n�̒��ݎ،_��̍��Ӊ��ɍۂ��Ē��ؐl����X�ɖ����œy�n��̌������ړ]�������Ƃ�X�ɂƂ��ĕs���Y�����ɓ�����Ƃ̑O��ʼnېŏ������Ȃ��ꂽ���ꎞ�����ɓ�����Ƃ��ꂽ����B �q��@���[�X�g�����Ə������E������������28�N2��17���Ŏ�266������12800����27(�s�R)215��nw(���R�����n������27�N5��21������24(�s�E)459���B���ː^�[�E�W�����X�g1452��8��2013.4�A���ː^�[�u���Ə��v�̖@�I�E�o�ϓI�����Ə������ށv�d�Ō���795��74�ŁA�������u�������������̖@�I�����Ə����敪�\�������ٕ���28�N2��17��������f�ނƂ��ā\�v�ő�W���[�i��27��75�ŁA���ԑ叇�u�m�����R�[�X���Ə��v�̏��������v�R�Љ�Ȋw�I�v45��1��59-85�ŁA�g������E�d����28�A212��) �@�w��͖��@��̑g�����������čq��@���w�����A������q���Ђɒ��݂��鎖�Ƃ��c��ł����B�q��@�p���Ď��Ƃ��I������ہA[1]�q��@�̍w�������̈ꕔ�ƂȂ����ؓ����̈ꕔ�ɌW����̖Ə��������Ƃɂ�闘�v�A�y��[2]���Y�g���̋Ɩ����s�҂ɑ��Ďx�����ׂ��萔���ɌW����̖Ə��������Ƃɂ�闘�v�����������B�q��@���ݎ��Ǝ����͕s���Y�����ɌW��������z�ł��邩��A���Ə��v���s���Y�����ł���ƍ�(�ېŒ���)�͎咣�����B�����A�w�́A���Ə��v�͋����������邩��ꎞ�����ł���Ǝ咣�����B��R�A��R�Ƃ��A�ꎞ�����ł���Ɣ��f�����B ���@�����n������30�N4��19������2405��3�ŕ���26(�s�E)649��(�m��)(�����O�E�W�����X�g1534��126-129��)�ł́A�s���Y�����ɂ͕s���Y���݂ɕt������������܂܂��Ƃ��A���ݗp�s���Y���w�����邽�߂̎ؓ��ɌW����Ə��v�͕s���Y�����ɊY������Ɣ��f���ꂽ�B�����A�ٔ����̔��f�͈��肵�ĂȂ��悤�ł���B |
| �����n���ߘa4�N5��31���ߘa2(�s�E)224���Ŏ�272������13722(���p)�E���������ߘa5�N1��25���ߘa4(�s�R)180��(���p�A�m��)�c�c�s���Y�����̌v�Z�ɍۂ�����œ��̐Ŕ��o���������̗p���Ă���ꍇ�A�s���Y�̏��n�ɌW�����Ŋz�́A�K�v�o��ɊY�����Ȃ��B |
���v�ʎZ(����69��1��)�\lj�c�c6�Ł�241.01��胊�]�[�g�z�e�������E�����n������10�N2��24�����^1004��142�Ŋm��(��4.6.3.���v�ʎZ)�B
�s���Y�����̕K�v�o��c�c5�Ł�231.02(6�łȂ�)���ݗp�y�n���n�����E��㍂������10�N1��30���Ŏ�230��337��
�D�����[�X�E�q��@���[�X���ƌĂ��ϋɓI�ȑd�ʼn���̌ʓI�۔F�K��Ƃ����d��41����4��2�B(��6�Ł�143.04�p���c�B�[�i�����E�Ŕ�����18�N1��24�����W60��1��252�ł̓t�B�����̃��[�X)
| 6�Ł�225.03�q��@���[�X���Ɠ����g�������E�Ŕ�����27�N6��12�����W69��4��1121�ŕS�I7��22kj(�������E�W�����X�g1473��111��) �@�@�@�@���o���@�@�@�q��@�w����� �@�@�@�w�\�\�\�\�\���`�\�\�\�\�\�\�\���c�i�q��@���^�p�j �����g�����@�@�@�@�c�Ǝҁ@�@�@�q����(�q��@���n�l�����ؐl) �@�@�@�@�@�@�q��@���L�ҁc�c�c�c�c�c���q��@���� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���\�\�\�\�\�\�q��@�����x�� ���v�ʎZ���c�c�c�c�c�Ԏ� �����E���_�@�����g���_��(���@535��1���u�����g���_��́A�����҂̈����������̉c�Ƃ̂��߂ɏo�������A���̉c�Ƃ��琶���闘�v�z���邱�Ƃ�邱�Ƃɂ���āA���̌��͂���B�v)���������B�`�Ђ͂c�q���Ђ���q��@���w�����A�`���c�ɍq��@����݁i���[�X(Lease))���A�c�͂`�ɍq��@�������x�����B�`�͍q��@���L�҂Ƃ��đ��z���������p�����v�シ�邽�߁A�q��@����������Ă��Ԏ��ł���B�`���Ԏ��ł���̂ŁA�w�����̐Ԏ��v�ʎZ�ɗ��p���悤�Ƃ���B �@�w�������g���_���ʂ��Ă`����闘�v���z�̐����͂`�̎��Ƃ̓��e�Ɉˑ����A�{���ł͂`���q��@������Ƃ������Ƃ����Ă���̂ŁA�q��@������Ƃ����������ނ��w�ւƓ`�B�����(�p�X�E�X���[(pass through)�Ƃ���)�A�Ƃw�͎咣�����B����17�N�����O�ʒB���A�����Ƃ��ē����g���_���ʂ��Ď闘�v���z�ɂ��Ă̓p�X�E�X���[�����ł���i��O�I�ɓ����g�����ɂƂ��ĎG�����ƂȂ�j�ƋK�肵�Ă����B �@����������17�N�ʒB������A�����Ƃ��ē����g�����͏o�����ė��v���z��ɂ����Ȃ��i�����g���������Ƃ����Ă���킯�ł͂Ȃ��j�̂ŎG�����ƂȂ�i��O�I�ɁA�����g�������c�Ǝ҂̎��Ƃɐ[���֗^���Ă���ꍇ�̓p�X�E�X���[�����Ƃ���j�ƒʒB�͋K�肷�邱�ƂƂȂ����B�܂蕽��17�N�����O��ŁA�����Ɨ�O���t�]�����B��(�ېŒ���)�́A�V�ʒB�Ɉˋ����A�w�͎G�����Ă����̂ŁA�G�����ɌW��Ԏ��v�ʎZ�ɗ��p���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��A�Ǝ咣�����B ���|�@�u�����g���_��Ɋ�Â������g�������c�Ǝ҂���闘�v�̕��z�ɌW�鏊���敪�́c�c�����g�����������I�ɉc�Ǝ҂Ƌ������Ď��Ƃ��c�ގ҂Ƃ��Ă̒n�ʂ�L������̂ƔF�߂���ꍇ�ɂ́C�c�Ǝ҂̉c�ގ��Ƃ̓��e�ɏ]���Ĕ��f�����ׂ����̂Ɖ�����C�����C�����g���������̂悤�Ȓn�ʂ�L������̂ƔF�߂��Ȃ��ꍇ�ɂ́C�c�Ǝ҂̉c�ގ��Ƃ̓��e�ɂ�����炸�C�����g�����ɂƂ��Ă��̏������L���鐫���ɏ]���Ĕ��f������ׂ����̂Ɖ������B�����āC��҂̏ꍇ�ɂ����鏊���́c�c�c�Ǝ҂̉c�ގ��Ƃւ̓����ɑ�����̔z���Ƃ��Ă̐����Ɋӂ݂�ƁC���̏o���������g�������g�̎��ƂƂ��čs���Ă��邽�ߎ��Ə����ƂȂ�ꍇ�������C�����Ŗ@23������34���܂łɒ�߂�e�����̂�����ɂ��Y�����Ȃ����̂Ƃ��āC���@35��1���ɒ�߂�G�����ɊY������v�B �@�Ȃ��A���ʒB��M���Ă����w�̐\���ɂ��ĉߏ��\�����Z�ł�Ƃ��ׂ��u�����ȗ��R�v(�ʑ�65��4��)������Ƃ��Ă���B(��2.2.4.1.h�ʒB�Ɩ@���ACOLUMN2-6���Z�Ő��x�Ƒd�Ŗ@�̎����ߒ��A3.1.4.3.���Z�łɂ����鐳���ȗ��R�A4.2.6.2.�t�����W�x�l�t�B�b�g) �����n������30�N1��23���Ŏ�268������13115����26(�s�E)351��(�c���[�V�E�W�����X�g1558��131-134��2021.5)�c�u�������C�{����n�������ɂ����ĉʂ������������邢�͊֗^�̒��x�ɉ����C�������{����n�������̈ӎv����Ɋւ�蓾��n�ʂɂ��������ƂɊӂ݂�C�����́C�{����n�������Ɋւ��āC�����I�ɃC���^�j�Ƌ������Ă��̎��Ƃ��c�ގ҂Ƃ��Ă̒n�ʂ�L������̂ƔF�߂�̂������ł���B�v�u�������C���^�j����{����n�������ɂ�萶�������v�̕��z���邱�ƂɌW�鏊���敪�́C�C���^�j�̉c�ގ��Ƃ̓��e�ɏ]���Ĕ��f�����ׂ����ƂɂȂ�Ƃ���C�C���^�j�͕s���Y�����Ɋւ��鎖�Ɠ���ړI�Ƃ��銔����Ђł���C�{����n�������̓C���^�j���ړI�Ƃ��鎖�Ƃ��̂��̂ł��邱�ƂɏƂ点�C�������{����n�������ɂ�萶�������v�̕��z���邱�ƂɌW�鏊���敪�͎��Ə����ɓ�����C�{���������S���́C�����̎��Ə����̕K�v�o��ɂȂ�Ƃ����ׂ��ł���B�v�c�c���Ə������ۂ��i�������ƂȂ̂��A�G�����Ȃ̂��j�́A�C�ӑg���������g�����Ƃ������@��̐�������ɂ���Č��܂�̂ł͂Ȃ��A�������Ǝґg�D���Ō��܂�Ƃ����_�ŁA�Ŕ�����27�N6��12���Ɛe�a�I�B cf.�����n���ߘa6�N2��16���ߘa��(�s�E)388�����p�c�c�L���ӔC���Ƒg���̑g����A��(X�̕�)�y��B�������`�l�ɂ������Ή�����S�ċ���҂��ʂ̑g����X���݂̂ł���ꍇ�AX�������Ŗ@12���A����Ŗ@13���̎����I����҂Ƃ��Ĉ�����Ƃ�������B�d���Z�ł��ۂ���Ă���B[���:�����g�����ۂ��Ƃ������@��̐������肪���ߎ�ł͂Ȃ��Ƃ���c���[�V�̎咣�Ɛe�a�I�ł���Ǝv����B���A�d���Z�ł��ۂ���Ă��鎖�Ăł���L���ӔC���Ƒg���̓T�^��ł͂Ȃ��Ƃ��l������B] cf.�c���[�V�u�p�X�X���[�ېł̌���Ɩ����v�d�Ŗ@����51���w�I�[�v���C�m�x�[�V��������̊�ƉېŁx42-58�� |
| �f���E�F�A�B�k�o�r����(�R�����c�،�����)�E�Ŕ�����27�N7��17�����W69��5��1253�ŕS�I7��23 ly(��8.2.1.2.c) �@�@�@�@�o���@�@�@�@�s���Y�w����� �@�@�w��\�\�\�\�\���`�\�\�\�\�\�\�\�����ÏW���Z�� Limited Partner�@General Partner �@�@�@�@�@�@�s���Y���L�ҁc�c�c�c�c�c���s���Y���� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���\�\�\�\�\�\�s���Y�����x�� ���v�ʎZ���c�c�c�c�c�Ԏ� �����E���_�@�w��Ƃ`��(�f���E�F�A�B�@����)���f���E�F�A�B�@���~�e�b�h�E�p�[�g�i�[�V�b�v�@�Ɋ�Â��`�Ђ�General Partner�i�����ӔC�g�����B�Ɩ����s�g�����ł��邱�Ƃ������j�Ƃ��w��i���m�ɂ͂w��ƐM���_���������Ă������҂���a��s�ł��邪�����̕X�̂��߂a��s���ȗ�����j��Limited Partner�i�L���ӔC�g�����j�Ƃ���p�[�g�i�[�V�b�v�_���������k�o�r(Delaware State, Limited Partnership)��g�������B�k�o�r�̓A�����J�ŕs���Y(���ÏW���Z��)���w�����s���Y���Ƃ��c�B�k�o�r���Ԏ��ł������̂ŁA�w��͂k�o�r�����{�ł����g���ɋ߂����̂ł���Ƃ̗����Ɋ�Â��A�Ԏ��̑������k�o�r����w�Ƀp�X�E�X���[�����Ǝ咣�����B �@�����A��(�ېŒ���)�́A�f���E�F�A�B�@�Ɋ�Â��k�o�r�͓��{���猩�Ė@�l�i��L������̂Ƃ��Ĉ����邩��A�k�o�r���Ԏ��ł����Ă��k�o�r�����U���铙���Ȃ�����w��͐Ԏ��𗘗p�ł��Ȃ�(���������A������Ђ��Ԏ��ł����Ă����傪�Ԏ��𗘗p�ł��Ȃ��̂Ɠ��l��)�A�Ǝ咣�����B�w��͕�������A�����n�فA���É��n�فA���n�قōٔ��ƂȂ����B�n�فE���قŁA���Y�k�o�r���@�l�ł���Ƃ������f�Ɩ@�l�ł͂Ȃ��Ƃ������f�Ƃɕ�����A�ō��ق̌��_���҂��ꂽ�B ���|�@�u�O���@�Ɋ�Â��Đݗ����ꂽ�g�D�̂������Ŗ@2��1��7�����ɒ�߂�O���@�l�ɊY�����邩�ۂ��f����ɓ������ẮA�܂��A���q�ϓI����`�I�Ȕ��肪�\�ł����҂̊ϓ_�Ƃ��āA[1]���Y�g�D�̂ɌW��ݗ������@�߂̋K��̕�����@���̎d�g�݂���A���Y�g�D�̂����Y�O���̖@�߂ɂ����ē��{�@��̖@�l�ɑ�������@�I�n�ʂ�t�^����Ă��邱�Ɩ��͕t�^����Ă��Ȃ����Ƃ��^�`�̂Ȃ����x�ɖ����ł��邩�ۂ����������邱�ƂƂȂ�A���ꂪ�ł��Ȃ��ꍇ�ɂ́A���ɁA���Y�g�D�̂̑����ɌW��O�҂̊ϓ_�Ƃ��āA[2]���Y�g�D�̂������`���̋A����̂ł���ƔF�߂��邩�ۂ����������Ĕ��f���ׂ����̂ł���A��̓I�ɂ́A���Y�g�D�̂̐ݗ������@�߂̋K��̓��e���|������A���Y�g�D�̂�����@���s�ׂ̓����҂ƂȂ����Ƃ��ł��A���A�����@�����ʂ����Y�g�D�̂ɋA�������ƔF�߂��邩�ۂ��Ƃ����_����������v�B �@�f���E�F�A�u�B�k�o�r�@�̒�ߓ��Ɋӂ݂�ƁA�{���e�k�o�r�́A����@���s�ׂ̓����҂ƂȂ邱�Ƃ��ł��A���A���̖@�����ʂ��{���e�k�o�r�ɋA��������̂Ƃ������Ƃ��ł��邩��A�����`���̋A����̂ł���ƔF�߂���B�c�c��������ƁA�{���e�k�o�r�́A��L�̂Ƃ��茠���`���̋A����̂ł���ƔF�߂���̂ł��邩��A�����Ŗ@2��1��7�����ɒ�߂�O���@�l�ɊY��������̂Ƃ����ׂ��ł���A�c�c�{���e�s���Y���ݎ��Ƃ͖{���e�k�o�r���s�����̂ł���A�c�c�{���e�s���Y���ݎ��Ƃɂ�萶���������́A�{���e�k�o�r�ɋA��������̂ƔF�߂��A�{���o���҂�̉ېŏ����͈̔͂ɂ͊܂܂�Ȃ��v�B ���@�k�o�r�Ƃ������O�����Ă���Ζ@�l���������Ƃ����킯�ł͂Ȃ�(��̌��_��_���\���ɑ��Ă��w����͔ᔻ������)�B�p���̃o�~���[�_(Bermuda)�����@�Ɋ�Â��k�o�r�ɂ��ē����X�^�[�z�[���f�B���O�X�Ў����E������������26�N2��5������1450��10�ł͖@�l�ł͂Ȃ��Ɣ��f���A�Ō�����27�N7��17���Ŏ�265������12703�㍐�s��(���R�͏q�ׂĂȂ�)�Ŋm�肵���B �@�܂��A�ʌ��Ńf���E�F�A�B�k�o�r�ɂ��@�l�łȂ�������F�߂�Ƃ������������Œ��͌��(����29�N2��)�z�[���y�[�W�Ō��J�����B �@�j���[���[�N�B�@�Ɋ�Â��k�k�b(Limited Liability Conmpany)�ɂ��Ă͖@�l��������Ƃ�����Ⴊ���݂���B������������19�N10��10����54��10��2516�ŕS�I5��23lx |
4.2.6. ���^����(����28��)
4.2.6.1. ��`
| 6�Ł�223.01&224.02�ٌ�m�ږ◿�����E�Ŕ����a56�N4��24�����W35��3��672�ŕS�I7��38ni(��3.2.4.4.�i���̗��v) ���_�@�ٌ�m����Ђ��瓾���ږ◿�͋��^���������Ə������B ���|�@�u���Ə����Ƃ́A���Ȃ̌v�Z�Ɗ댯�ɂ����ēƗ����ĉc�܂�A�c�����A�L������L���A�������p�����Đ��s����ӎv�ƎЉ�I�n�ʂƂ��q�ϓI�ɔF�߂���Ɩ����琶���鏊���v �@�u���^�����Ƃ́A�ٗb�_�͂���ɗނ��錴���Ɋ�Â��g�p�҂̎w�����߂ɕ����Ē����J���̑Ή��Ƃ��Ďg�p�҂���鋋�t�������B�Ȃ��A���^�����ɂ��ẮA�Ƃ�킯�A���^�x���҂Ƃ̊W�ɂ����ĉ��炩�̋�ԓI�A���ԓI�ȍS�����A�p���I�Ȃ����f���I�ɘJ�����͖̒�����A���̑Ή��Ƃ��Ďx���������̂ł��邩�ǂ����v���d���B ���@���Ə����E���^�����̊�Ƃ��Ĉ��p����锻��ł���A�ËL���ׂ����|�ł���B���A�ێq��K�ɂ��̔��f��Ă͂߂Ă����܂������Ȃ����Ƃ�����(��f�F���s�ٌ�m����@�����k�����E��㍂������21�N4��22���Ŏ�259������11185�A6�Ł�223.03�ʋΒ�����ېŎ����E�Ŕ����a37�N8��10�����W16��8��1749��)�Bgq kx |
| ��223.02�哈�ʑi���R�E���s�n�����a56�N3��6���s�W32��3��342�� ��w�����̔��u�t���͎G�����ł͂Ȃ����^�����Ƃ�������B �@[���]�����Ɍ����Ď��������ȊO�ɏo�����Ƃ��Ɂu���l�̎w���ēc�ɕ����āv�������͂Ȃ��B�u���Ȃ̊댯�ƌv�Z�ɂ�v���ĂȂ��_�͎��Ə�������ے肷��ɂƂǂ܂�B�������^��������ϋɓI�Ɋ�b�Â���̂��H �@�]�k�F��w�����̍u������_���̌��e���͎G�����ł���B�w�p�U������ʌ������͋��^�����ېŁB |
| ���t�B�������E�Ŕ����a53�N8��29����24��11��2430�� �y�c�������@�C�I���j�X�g�̗�B���^�����ɓ�����Ƃ��ꂽ(���z�o��T���̉ہB�A���{���Ŏ��z�o��T�������悤�Ƃ���Ȃ�Όo��̓��@�C�I�����w����ł͂Ȃ��������p�������Ɍ����邱�Ƃɗ���)�B |
| ��B�d�͌��j�������E�����������a63�N11��22���Ŏ�166��505�� �@���j��Ƃ̈ϑ����Ă�������������V�͎��Ə��������^�������H �@���|�́u���ɁA(7)�̈ϑ��萔���́c�c�����Ȍ`�̏o�������ł����āA�J���̑Ή������ϔC�Ȃ������������̕�V�Ƃ��Ă̐��i�����v���X�̔F������A���_�Ƃ��Ă͎��Ə����Ƃ����B |
| ����Y�g�������E�Ŕ�����13�N7��13������1763��195�ŕS�I7��21gr �����E���_�@�J���o���������g�������g�����瓾�����������^�����ɊY�����邩�H �@�g�������Ƃ��s���ꍇ�̑g�����̏����͌����Ƃ��Ď��Ə����B����(transparent)(���Ό��opaque)�A�p�X�E�X���[(pass through)�Ƃ����B �@��R�͋��^���������Ƃ������A�@��R�͎��Ə��������Ƃ����B�g�����Ƒg�����ٗb�_�������ł���͂����Ȃ�����ł���B�@���_�Ƃ��ē�R�̍l�����ɂ��ꗝ����B ���|�@�j�������@�{�������͑g�����ł�����̂̑��̏]�ƈ��Ɠ��l���ٗb�ގ��̊W�ɂ���Ƃ������Ԃ��d�����A���^�����ɊY������ƔF�肵���B �l�@�@�g�������g���ƌ_���������邱�Ƃ͂��肤�邩�H�c�c�T�i�R�����͂��肦�Ȃ��ƍl���Ă���B�ō��ق͂��肤��ƍl���Ă��邩�̂悤�Ɉꌩ�v���邪�A�ٗp�ގ��̎����������邱�Ƃ������Ƃ��Ă���A�u�g���Ƒg�����Ƃ̊Ԃɖ��������@���W�̐�����F�߂邱�ƂɂȂ���̂ł��Ȃ��v�Ƃ��������͂��邪�A���炩�̌_��Ƃ����@���W�̐�����ϋɓI�ɔF�߂錾�����͐T�d�ɔ����Ă���B �@�ޑ�@�g�������g���Ɠy�n�̔����y�_��z����������Ƃ̑O��őg�����̓y�n���n�v�ɂ����n�������������Ƃ��ĉېł��Ă悢���H [���]�ō��ٔ��|����ǂݎ��͓̂�����A�����̐�������ɂ����Ă͔����_��ގ��̎����������Ƃ��Ĕ��f���Ă����Ƃ����̂��ō��ق̍l�����ł��낤���B�ނ��A�{�����|�͋��^�����݂̂ɂ��Ă̂��̂ł���A���^�����Ɋւ��Ă̂ݘJ���̑Ή��Ƃ����������d������Ƃ������_���l������̂ŁA���Ə����E���n�������̐�������ɂ��Ă����l�ɔ��f����Ƃ͌�����Ȃ��Bky |
| ���s�ٌ�m����@�����k�����E��㍂������21�N4��22���Ŏ�259������11185 �@�ٌ�m��@�����k�Z���^�[�̍s�Ȃ������@�����k�Ɩ�(���s�s���˗�)�ɕٌ�m���]�����ē����Ή��ɂ��āA��ԓI�A���ԓI�ȍS���̉��ŘJ����������Ƃ̑Ή��ł��邩�狋�^�����ɊY������A�Ƃ̎咣���˂����A���Ə����ł���Ɣ��f���ꂽ�B�����̌��_�ɂ��Ă��܂�ᔻ�͑����Ȃ��悤�Ɍ�������̂́A�������o��O�ɂ��̎��Ă������ɏo���ꂽ��A�ٌ�m�ږ◿�����E�Ŕ����a56�N4��24���̔��f���������w���̏��Ȃ��炸�����^�����ł���Ƃ������Ă��������ł��낤�B �@�Ȃ����Ə����Ƃ������_�ł���̂��B�ٌ�m�ٌ͕�m���ʂ��Ė@�����k�������Ă���Ƃ����ٌ�m�������v���ƂȂ��Ă���i��������O�Ƃ��Ă���Y�g�������E�Ŕ�����13�N7��13���Q�Ɓj�A�X�ٌ̕�m���@�����k�Ɩ��ɏ]������u�Ԃ����Ă�������Ȃ��̂ł���B |
| ���C�Y�����E�����n���ߘa2�N9��1������30(�s�E)268���ꕔ���p�A�ꕔ�p���A�m��(�ؑ��O�V���E�W�����X�g1568��134-137��2022.3) �@6�Ł�141.01�z�X�e�X��V�v�Z���Ԏ����E�Ŕ�����22�N3��2�����W64��2��420��(��3.1.1.3.)�ł̓z�X�e�X��V�����Ə����ł��邱�Ƃ��Öق̑O��ł��������A�{���ł̓L���o�N���̃L���X�g��V�����^�����ɊY������Ɣ��f��������B�����Ŗ@�����łȂ��A����Ŗ@��̎d���Ŋz�T���̉ۂƗ���ŁA���^�������ۂ��̍ٔ��������̂Ƃ��둝���Ă���B �@cf.�����n���ߘa5�N3��8������31(�s�E)102���Ŏ�273������13826�ꕔ���p�A�ꕔ�p�����z�X�e�X��V�����^�����ɊY������Ƃ�����Ŗ@��̎d���Ŋz�T����F�߂Ȃ�����(����Ŗ@2��1��12���A�����Ŗ@28��1��)�B�����Œ�1500�~���ۏ���������Ƃ͌����Ȃ��Ƃ���Ă���B �@cf.���Óh�H������Ў����E�����n���ߘa3�N2��26���ߘa2(�s�E)68�����p(���R�R���u����Ŗ@�ɂ����鎖�ƎҊT�O�v�V�E������Watch�d�Ŗ@No.169)�E���������ߘa3�N8��24���ߘa3(�s�R)73�����p�E�㍐�s�A�m��c�c�h���Ǝ҂̈ꕔ�̏]�ƈ����]�ƈ������łȂ��O���������Ăق����Ɨv�]���Ă�������(�Љ�ۏᕉ�S�����O)�B�w���ē��ɒ��ڂ��ċ��^��������B �@cf.�Љ���@�l�䂽����������E���É��n���ߘa6�N7��18���ߘa4(�s�E)67�����p�E���É������ߘa7�N1��30���ߘa6(�s�R)69�����p�c�c���Y�����]���҂Ɏx�������H���̏���Ŗ@��̉ېŎd����Y����(����)(�c���[�V�d�Ŕ��ጤ����2025�N2��7����)(�q���q���E�V�E������Watch�d�Ŗ@No.191) |
| ��t�m�掖���E���l�n���ߘa3�N3��24���Ŏ�271������13545�E���������ߘa3�N11��17���Ŏ�271������13631�E�ňꏬ���ߘa4�N4��21���Ŏ�272������13708�c�c��t�̗m�擙����̔��Ə��������Ə����ł͂Ȃ��G�����ł���Ƃ��ꂽ����B |
�͎m�ɂ��Ă͒ʒB������(��34.3.11����5-4)�B�v���싅�I�蓙�ɂ��ċK����������Ƃ͂Ȃ��B
�ېŎ����c�c��Ђ��]�ƈ��̂��߂ɔN���|�����ɋ��o�����ꍇ�A����(�m�苋�t��ƔN���K�Ɋւ������ŗ�64���F����̗v���̉��A���o����ې�)�̗v�������Ȃ���A�����Ƃ��ċ��o���ɏ]�ƈ��̋��^�����Ɋ܂܂�ĉېł����B�]�ƈ������̂��������R�Ɏg����킯�ł��Ȃ��̂ɏ]�ƈ��̉ېŏ����Ɋ܂܂�邱�Ƃɂ��ĎߑR�Ƃ��Ȃ��҂����邩������Ȃ��B���������~�Ɠ��l�ł���A���o���ɉېł����N�������ɉېł���Ƃ������Ƃ͉ېŌJ����F�߂�Ƃ������Ƃł��邩��A��I�����T�O�̌��n���炷��Ό����Ƃ��ĉېŌJ����F�߂��ɂ͂����Ȃ�(���ŗ�64���ɂ���ĉېŌJ����F�߂邱�Ƃ͉��b�I�[�u�Ƃ����ʒu�t��)�B
4.2.6.2. �t�����W�E�x�l�t�B�b�g(fringe benefit)
| ��223.03 �ʋΒ�����ېŎ����E�Ŕ����a37�N8��10�����W16��8��1749��nj ���_�@�ʋΔ�p���x�����ꂽ�ꍇ�̏����Ŗ@��̈����ɂ��āB ���|�@�ΘJ�҂��g�p�҂���ʋΔ�p�̎x�������Ƃ��A���^�������\������B�ʋΔ�p�蓖�Ă��Ă��Ȃ��ΘJ�҂Ƃ̌�����}��B
�@���@�ʋΔ�p�͌��������ł���Ƃ������f(�ƒ��Ƃ̔�r)���O��B(cf. William Klein, Income Taxation and Commuting Expenses: Tax Policy and the Need for Nonsimplistic Analysis of �gSimple�h Problems. 54 Cornell Law Rev. 871-896 (1968)) �@��ېŋK��E����9��1��5��(�ʋΎ蓖)���n�K���Ƃ����ʒu�t���ɂȂ�(��̓I�ɂ����ŗ�20����2�i��ېłƂ����ʋΎ蓖�j�A�����9-6��3�B�܂��P�g���C�Ɋւ�����57����2��2��5���̓���x�o�T�����Q��)�B�ނ��A�ʋΔ�̕K�v�o��Z���̉ۂ͍��ɂ���ĈقȂ�B�ٌ�m���̎��Ə����ғ��҂�����Ǝ��������������邽�߂̒ʋΔ�p�͍T���ł���(�n�K��ł���͂��̏���9��1��5���Ɉ��������Ă���)�Ƃ����̂����{�ł̈����ł���炵�����A�A�����J�ł͍T���ł��Ȃ��Ƃ���Ă���B |
�u�g�p�҂̕X�v���_(�u���Ǝ�s�����t�v)
����9��1��6���u���^������L����҂������g�p�҂������K�ȊO�̕�(�o�ϓI�ȗ��v���܂ށB)�ł��̐E���̐����㌇�����Ƃ̂ł��Ȃ������Ƃ��Đ��߂Œ�߂���́v
���ŗ�21��(��ېłƂ����E����K�v�ȋ��t)�u�@��9���1����6��(��ېŏ���)�ɋK�肷�鐭�߂Œ�߂���̂́A���Ɍf������̂Ƃ���B
��@�D���@�攪�\���ꍀ(�H���̎x��)�̋K��ɂ��x�������H�����̑��@�߂̋K��ɂ�������Ŏx�������H��
��@���^������L����҂ł��̐E���̐����㐧���𒅗p���ׂ��҂������g�p�҂���x������鐧�����̑��̐g��i
�O�@�O���ɋK�肷��҂����̎g�p�҂��瓯���ɋK�肷�鐧�����̑��̐g��i�̑ݗ^���邱�Ƃɂ�闘�v
�l�@���ƌ������h�ɖ@�c�c��\���(�����h��)�̋K��ɂ�������ŏh�ɂ̑ݗ^���邱�Ƃɂ�闘�v���̑����^������L����҂ł��̐E���̐��s���ނȂ��K�v�Ɋ�Â��g�p�҂���w�肳�ꂽ�ꏊ�ɋ��Z���ׂ����̂����̎w�肷��ꏊ�ɋ��Z���邽�߂ɉƉ��̑ݗ^���邱�Ƃɂ�闘�v�v
�@���Ǝ�s�����t���_�ɑ��锽�_�c�c�ېł̌�����}��ɂ������X�̌��p�͊�ł͂Ȃ��s�ꉿ�i����ƂȂ锤�ł���(��4.3.4.�A������)�B
�@�Ĕ��_�c�c�A�������̏�ʂ͔[�ŎҎ��g�ɑI���̎��R�����邱�Ƃ������B�����A���Ǝ�s�����t�̏ꍇ�A������������ꂽ�����ł����āA�s�ꉿ�i�ɑ�������։v���ĂȂ���ʂ��ތ^�I�ɑ����Ƒz��ł���B([���]�����͂����Ă�Google�Ƃ�Facebookkv�Ƃ��̃t�����W�E�x�l�t�B�b�g�͂߂���߂���[�����Ă���炵��)
���N���G�[�V�����Ƃ��Ă̎Ј����s���c�c�Љ�ʔO�Ő�����(�����36-30)�B
�n���C5��6�����s���ېőΏۂƂ�����c���R�n�����a54�N7��18���s�W30��7��1315�Ŋm��
���`2��3�����s���ېőΏۂƂ��Ȃ�������c��㍂�����a63�N3��31�����^675��147��(���R���s�n�����a61�N8��8���s�W37��7�E8��1020��)
���̌��ʒʒB��63.5.25����3-13�B([���W]���̒ʒB�ɂ���ē�����̂͒N���H�c�Ő��D���։v�̋A��)
�Б��\�\�ƒ����s�����ɒႯ��ΉېőΏۂƂȂ�(�����36-40�ȉ�)�B
�������ɂ��ېł��ׂ��A�Ƃ����ӌ���A�����̏Z�݂������ɏZ�߂Ȃ��ł͎s�ꉿ�i�Ǝ��ۂɎx�����ƒ��Ƃ̍��z���]�ƈ��̕։v�ƂȂ��Ă��Ȃ��A�Ƃ����ӌ��ɂ��āA��L���Ǝ�s�����t�̋c�_���Q�ƁB
�I�t�B�X��(���K�ȋ�)�\�\����ŋ��𗘗p���Ă���҂Ƃ̑Δ�B(cf.��h�ɂ̓d�C����:�����36-26)
�t�����W�E�x�l�t�B�b�g�͉ېł̌����̖�����N������̂́A�Љ�ʔO�E�����E���s�̍�������R�Ƃ���ĉېł���Ȃ����̂������B����57����2�̓���x�o���Q�ƁB
| �X�g�b�N�E�I�v�V�����E�Ŕ�����17�N1��25�����W59��1��64�ŕS�I7��39bs(���ŗ�84���Q��gs) ���{�q���(�a��)�Ζ��̖����w���A�����J�e���(�`��)����`�Ђ̃X�g�b�N�I�v�V������t�^���ꂽ�B�X�g�b�N�I�v�V�����̌����s�g�v���ꎞ���������^�������H(�Ζ��悩��̕։v�łȂ��̂Ŋw���ł͎G���������L�͂ł��������A�����Ă��Ȃ�)�B �ō��ق́A�ꎞ�����ł͂Ȃ����^�����ł���Ƃ����B �M�`���̖��c�c���ʒB�ł͈ꎞ�����Ƃ��Ĉ����Ă����̂ɕ���10�N�ʒB�����ȍ~���^���������ɐ�ւ����c�c�ʒB�����O�̔N�x�ɂ��Ă��ꎞ�����Ƃ��Đ\�����ꂽ���ɂ����k�y���ċ��^�����ł���Ƃ����X�����������Ă���B�ō��ق͂��̓_�ɂ��ĉ����G��ĂȂ�(�M�`���̖�肪����Ƃ��q�ׂĂ��Ȃ�)�B6�Ł�130.01�p�`���R���V�펖���E�Ŕ����a33�N3��28�����W12��4��624�łł͒ʒB�����O�̔N�x�ɑk�y���ĉېł��邱�Ƃ͍T���Ă������ƂƑΏƓI�B([���]�������ʒB�͗��@�ł͂Ȃ����߂ɂ����Ȃ��̂ł��邩��A�M�`���₻�̑����i�̎���Ȃ�����A�k�y���č\��Ȃ��ǂ��납�k�y���ׂ��ł��낤�B) ���Z���ɂ����X�g�b�N�E�I�v�V�������Z�Ŏ����E�Ŕ�����18�N10��24�����W60��8��3128��(��COLUMN2-6�A3.1.4.3.�M�`��)���Œ�65��4��(��5��1��)�́u�����ȗ��R�v���m�F(��2.2.4.1.)(6�Ł�225.03�q��@���[�X���Ɠ����g�������E�Ŕ�����27�N6��12�����W69��4��1121��) �]�͂�����l�́A���Z�ł́u�����ȗ��R�v�̑��ۂ̌��E����Ƃ��āA�Ŕ�����18�N4��20�����W60��4��1611�ŕS�I7��101(�[�Ŏ҂ɓ����Őŗ��m������ɒE�ł����݂���B�u�����ȗ��R�v�Ȃ�)�A�Ŕ�����18�N4��25�����W60��4��1728�ŕS�I7��100(�[�Ŏ҂ɓ����Őŗ��m���Ŗ��E���Ƌ��d���ĒE�ł����݂���B�u�����ȗ��R�v����)��ǂݔ�ׂĂق����B�u�����ȗ��R�v���F�߂����ʂ͂��Ȃ�����Ă��邱�Ƃ�������B |
�t�����W�E�x�l�t�B�b�g�Ƃ����Ƌ��K�ȊO�̋��t���O���ɒu���ꂪ���ł��������A�����p���u�g�p�҂���^��������������^�����Ƃ����͈́v�Ŗ����ጤ��61��21��kz�����K���t�̋��^�����Y�����ɂ��Ă�����N�����B
[1]�a�З��㕔���̂`�������_���l���B100���~�̕��c�c����͋��^���������̏������H���㕔���̘J���̑Ή��Ȃ̂��ʂ̌o�ϓI�����Ȃ̂��H
[2]�E������(�����@35��)�̑Ή��Ƃ��Ă̕�1000���~(�������錠���̌��n�A���͔����Ҍl�ł�����)�͋��^�������A���n�������A�ʂ̏������H�E������(���쌠�@15��)(�Ⴆ�A�V���ЂɌٗp����Ă���V���L�҂̋L��)�̒��쌠�͑����̑Ή��Ȃ����Ė@�l(�Ⴆ�ΐV����)�ɋA�����A�]�ƈ�(�Ⴆ�ΐV���L��)�̎�����͌����Ƃ��ċ��^�����Ƃ���邱�ƂƁA�ύt��}��ׂ����H�Ȃ��A�E�������ƐE������ƂŌ����̋A�����قȂ邱�Ƃ��K�R�ł���Ƃ͌����Ȃ����A��r�@�I�ɂ��E�������ƐE������Ƃ̈Ⴂ�͓��R������Ă��Ȃ����A���{�ł�����27�N�����@������͓������錠�����g�p�҂Ɍ��n�A������悤�ȋΖ��K�����F�߂��邱�ƂƂȂ����B
�����23�`35��-1(�g�p�l���̔������ɌW�����)�u(1)�Ɩ���L�v�Ȕ����A�l�Ė��͑n��������҂����Y�����A�l�Ė��͑n��ɌW��������錠���A���p�V�ēo�^���錠���Ⴕ���͈ӏ��o�^���錠�����͓������A���p�V�Č��Ⴕ���͈ӏ������g�p�҂ɏ��p���������Ƃɂ��x��������́c�c�����̌����̏��p�ɍۂ��ꎞ�Ɏx��������̂͏��n�����A�����̌��������p��������ɂ����Ďx��������͎̂G�����v�m(2)�ȉ����n
4.2.6.3. �ߑ����Ƌ��^�����T��(����28��3��)
����28��(���^����)�u���^�����Ƃ́A��A�����A�����A�Δ�y�яܗ^���тɂ����̐�����L���鋋�^�c�c�ɌW�鏊���������B�Q�@���^�����̋��z�́A���̔N���̋��^���̎������z���狋�^�����T���z���T�������c�z�Ƃ���B
�R�@�O���ɋK�肷�鋋�^�����T���z�́A���̊e���Ɍf����ꍇ�̋敪�ɉ������Y�e���ɒ�߂���z�Ƃ���B�m�㗪�n
�A���q��Đ��тɂ��Ă͋��^�����T���̏����210���~(���^����1000���~�ɑΉ�)�ɂȂ�B�d��41����3��11��1��
���^�����T���z �ߘa7�N�����O�Ɖ�����(�A�����^�������z660�������̏ꍇ�A�����Ŗ@�ʕ\����ɂ��B
| ���^�������z | �ߘa6�N�ȑO | �ߘa7�N�Ȍ� |
| 162.5���~�ȉ� | 55���~ | 65���~ |
| 162.5���~���`180���~�ȉ� | �������z�~40%�|10���~ | 65���~ |
| 180���~���`190���~�ȉ� | �������z�~30%�{8���~ | 65���~ |
| 190���~���`360���~�ȉ� | �������z�~30%�{8���~ | �������z�~30%�{8���~ |
| 360���~���`660���~�ȉ� | �������z�~20%�{44���~ | �������z�~20%�{44���~ |
| 660���~���`850���~�ȉ� | �������z�~10%�{110���~ | �������z�~10%�{110���~ |
| 850���~��(��q�����) | 195���~ | 195���~ |
| 850���~���`1000���~�ȉ�(�q��Đ���) | �������z�~10%�{110���~ | �������z�~10%�{110���~ |
| 1000���~��(�q�����) | 210���~ | 210���~ |
�N������(�����̕ߑ���)�ɂ��Ă�6�Ł�121.01�哈�i�ׂ��Q�ƁB
�N�������c�c�T�����[�}��9���A���c�Ǝ�6���A�_��4���@�܂���
�g�[�S�[�T���s���c�c�T�����[�}��10���A���c�Ǝ�5���A�_��3���A������1��
(���v�I�ɐ��m�ł��邩�肩�łȂ������m�ɐ\�����Ă��鎩�c�Ǝғ�����͔���������)
����57����2�i���^�����҂�����x�o�̍T���̓���[�����]�j�@���Z�҂��A�e�N�ɂ����ē���x�o�������ꍇ�ɂ����āA���̔N���̓���x�o�̊z�̍��v�z�����\�����i���^�����j�ɋK�肷�鋋�^�����T���z�̓̈�ɑ���������z����Ƃ��́A���̔N���̓����ɋK�肷�鋋�^�����̋��z�́A�����y�ѓ����l���̋K��ɂ�����炸�A�����̎c�z���炻�̒����镔���̋��z���T���������z�Ƃ���B
�Q�@�O���ɋK�肷�����x�o�Ƃ́A���Z�҂̎��Ɍf����x�o�i���̎x�o�ɂ����̎҂ɌW����\�����ꍀ�ɋK�肷�鋋�^���̎x��������ҁi�ȉ����̍��ɂ����āu���^���̎x���ҁv�Ƃ����B�j�ɂ���U����镔��������A���A���̕�U����镔���ɂ������ł��ۂ���Ȃ��ꍇ�ɂ����铖�Y��U����镔���y�т��̎x�o�ɂ��ٗp�ی��@�i���a�l�\��N�@����S�\�Z���j��\���܍��i���Ɠ����t�j�ɋK�肷�鋳��P�����t���A��q�y�ѕ��q���тɉǕw�����@�i���a�O�\��N�@����S��\�㍆�j��O�\����ꍆ�i��q�ƒ뎩���x�����t���j�ɋK�肷���q�ƒ뎩���x������P�����t�����͓��@��O�\����̏\�i���q�ƒ뎩���x�����t���j�ɂ����ď��p���铯���ɋK�肷�镃�q�ƒ뎩���x������P�����t�����x������镔��������ꍇ�ɂ����铖�Y�x������镔���������B�j�������B
�@��@���̎҂̒ʋ̂��߂ɕK�v�Ȍ�ʋ@�ւ̗��p���͌�ʗp��̎g�p�̂��߂̎x�o�ŁA���̒ʋ̌o�H�y�ѕ��@�����̎҂̒ʋɌW��^���A���ԁA�������̑��̎���ɏƂ炵�čł��o�ϓI�������I�ł��邱�Ƃɂ������ȗ߂Œ�߂�Ƃ���ɂ�苋�^���̎x���҂ɂ��ؖ������ꂽ���̂̂����A��ʂ̒ʋΎ҂ɂ��ʏ�K�v�ł���ƔF�߂��镔���Ƃ��Đ��߂Œ�߂�x�o
�@��@�Ζ�����ꏊ�𗣂�ĐE���𐋍s���邽�߂ɒ��ڕK�v�ȗ��s�ł��邱�Ƃɂ������ȗ߂Œ�߂�Ƃ���ɂ�苋�^���̎x���҂ɂ��ؖ������ꂽ���̂ɒʏ�v����x�o�Ő��߂Œ�߂����
�@�O�@�]�C�ɔ������̂ł��邱�Ƃɂ������ȗ߂Œ�߂�Ƃ���ɂ�苋�^���̎x���҂ɂ��ؖ������ꂽ�]���̂��߂ɒʏ�K�v�ł���ƔF�߂���x�o�Ƃ��Đ��߂Œ�߂����
�@�l�@�E���̐��s�ɒ��ڕK�v�ȋZ�p���͒m�����K�����邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ď�u���錤�C�i�l�̎��i���擾���邽�߂̂��̂������B�j�ł��邱�Ƃɂ��A�����ȗ߂Œ�߂�Ƃ���ɂ��A���^���̎x���҂ɂ��ؖ������ꂽ���̂̂��߂̎x�o���̓L�����A�R���T���^���g�i�E�Ɣ\�͊J�����i�@��O�\���̎O�i�Ɩ��j�ɋK�肷��L�����A�R���T���^���g�������B�����ɂ����ē����B�j�ɂ��ؖ������ꂽ���̂̂��߂̎x�o�i����P���i�ٗp�ی��@��Z�\���̓��ꍀ�i����P�����t���j�ɋK�肷�鋳��P���������B�����ɂ����ē����B�j�ɌW�镔���Ɍ���B�j
�@�܁@�l�̎��i���擾���邽�߂̎x�o�ŁA���̎x�o�����̎҂̐E���̐��s�ɒ��ڕK�v�Ȃ��̂Ƃ��āA�����ȗ߂Œ�߂�Ƃ���ɂ��A���^���̎x���҂ɂ��ؖ������ꂽ���̖��̓L�����A�R���T���^���g�ɂ��ؖ������ꂽ���́i����P���ɌW�镔���Ɍ���B�j
�@�Z�@�]�C�ɔ������v����ɂ���z��҂Ƃ̕ʋ����틵�Ƃ��邱�ƂƂȂ��ꍇ���̑�����ɗނ���ꍇ�Ƃ��Đ��߂Œ�߂�ꍇ�ɊY�����邱�Ƃɂ������ȗ߂Œ�߂�Ƃ���ɂ�苋�^���̎x���҂ɂ��ؖ������ꂽ�ꍇ�ɂ����邻�̎҂̋Ζ�����ꏊ���͋����Ƃ��̔z��҂��̑��̐e�������Z����ꏊ�Ƃ̊Ԃ̂��̎҂̗��s�ɒʏ�v����x�o�Ő��߂Œ�߂����
�@���@���Ɍf����x�o�i���Y�x�o�̊z�̍��v�z���Z�\�ܖ��~����ꍇ�ɂ́A�Z�\�ܖ��~�܂ł̎x�o�Ɍ���B�j�ŁA���̎x�o�����̎҂̐E���̐��s�ɒ��ڕK�v�Ȃ��̂Ƃ��č����ȗ߂Œ�߂�Ƃ���ɂ�苋�^���̎x���҂ɂ��ؖ������ꂽ����
�@�@�C�@���ЁA������s�����̑��̐}���ŐE���Ɋ֘A������̂Ƃ��Đ��߂Œ�߂���̋y�ѐ����A���������̑��̋Ζ��ꏊ�ɂ����Ē��p���邱�Ƃ��K�v�Ƃ����ߕ��Ő��߂Œ�߂���̂��w�����邽�߂̎x�o
�@�@���@���۔�A�ڑҔ�̑��̔�p�ŁA���^���̎x���҂̓��Ӑ�A�d���悻�̑��E����W�̂���҂ɑ���ڑҁA�����A�������̑������ɗނ���s�ׂ̂��߂̎x�o[3���ȉ���]
����x�o�Ɋ܂߂��Ȃ����̂ł����Ă����Ɏ��z�o����^�����T�������鎖�Ⴊ�������Ƃ�����ጛ���H(6�Ł�121.01�哈�i�ׂł����t�B�������ł����邱�Ƃ̎咣���������Ă��Ȃ����Ƃɗ���)
| �����Ȉ㎖���E�����n������24�N9��21���Ŏ�262������12043����23(�s�E)127���Ŏ��Ə�������280���~�̐l������T�����Ăق����Ɣ[�Ŏ҂��咣���Ă��������_�͋��^�����ł���̂ōT���͔F�߂��Ȃ������B�܂��A280���~���ȂɎx����������ł���̂ŁA���^�����Ɋւ��ጛ�̖�肪��������Ƃ͂����A�ʓr�A����56��(�Ƒ���p�T���۔F)�A57��(��]�ҍT��)�Ƃ̊W�����l���Ȃ���Ȃ�Ȃ�(��4.5.2.)�B |
��223.04 �Ő��������u�킪���Ő��̌���Ɖۑ�\21���I�Ɍ����������̎Q���ƑI���\�v98-101��(2000.7)
��111.01�哈�i�ׂ̈�R���s�n�����a49�N5��30���s�W25��5��548�ł͋��^�����T���̎�|�Ƃ��Ď��̂S�̎�|���f����B
[1]�K�v�o��̊T�Z�T���c�c�����Ƃ��Ő�������\�Ȃǂ��q�ׂ�ʂ�A�K�v�o��̊ϓ_�݂̂���Ȃ�A���^�����T�����Â����邱�Ƃ͓��v�I�ɋc�_�̗]�n�Ȃ��B
[2]�S�ŗ��̒����c�c���z�̋��^�Ƃ��̑��̏���(�z����)�Ƃ̔�r
[3]�ߑ����̊i���̒����c�c�O�q�̃N��������
[4]���������c�c�����ɂ�莩�c�Ǝ҂�葁�����ł���Ă��܂�
����6�Ł�121.01�哈�i�ׂ̍ō��ق́A�K�v�o��̊T�Z�T���݂̂��������ĂȂ��B
�i�ׂł̑������c�c���^�����Ǝ咣����ꍇ�͋��^�����T���̕������z�o��T�����L���ȏ�ʂł��邱�Ƃ������A���Ə����Ǝ咣����ꍇ�͋t�B
COLUMN4-2 �l�I���{(human capital)�F�J���Ɨ]�ɂƂ̑I���ɑ������
�����@�����ł��J���̈ӗ~���킮�ƌ����邪�{�����H�@�@�@�ېł����Εn�����Ȃ��Ĉ�w�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�̂ł͂Ȃ����H
�����(substitution effect)�F���i�̑��ΓI�ω��ɂ��A�������p�邽�߂̍��̑I�����ω�����B
�@(��F����������Ɣ�r���đ��ΓI�ɍ����Ȃ�A�l�͂���ȑO��葽�������悤�ɂȂ�)
��������(income effect)�F�������������͌������邱�Ƃɂ��A���̑I�����ω����邱�ƁB
�@(��F���^�����l���A��������ʕi�ł��郁�������ȑO�������������悤�ɂȂ�)
�@(�]�k�F���ʕi�Ƃ́A������1�����������ɏ���ʂ�1�������������(���v�̏����e�͐���1���傫������)�������B������1�����������ɏ���ʂ�1���������������Ȃ�����(���v�̏����e�͐���1��菬��������)���K���i�Ƃ����B)
�O��F�l�͎��Ԃ�J�����]�ɂɏ[�Ă�B(�t���^�C���J���҂ɂ���ȑI���͂ł��Ȃ��Ǝv����ł��낤���A�ƌv�����J����(���Ǝ�w/�v)�̘J�����Ԃ͒e�͓I�ɕω�����)(�w�҂̘J���Ɨ]�ɂ̋�ʂ́H)
�J���ɂ���ē��������ɂ͉ېł��Ȃ��������A�]�ɂɂ���ē������p�ɂ͉ېł���Ȃ��B
���ېłɂ��]�ɂƑΔ䂵�ĘJ��(�ɂ����K)�̑��ΓI�Ȗ��͂�������B���J�����Ԍ���(�����)
���ېłɂ��n�����Ȃ�A�����Ă������߂ɂ͋��K���K�v�B���J�����ԑ���(��������)
����ʂƏ������ʂƂ����E�������ĘJ�����Ԃ��ω����Ȃ��ꍇ�ł��A�����̘J�����Ԃ��ω����Ă��Ȃ�����Ƃ����āA�l�X�̍s���ɘc�݂������ĂȂ�(�s��ɔ�����������Ă��Ȃ�)�A�Ƃ������Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��B
�������̊ϓ_����́A����ʂɂ��s���̘c�݂݂̂��Ӗ������B�o�ϊw�҂��������̋c�_������Ƃ��́A�������ʂ��⏞���ꂽ��Ԃ����z���đ���ʂɂ��Ă̋c�_�����邱�Ƃ������B
����(���g������)���D���Ȃ`�c����1���~�̎d�����T6������B����6���~�ɉېŁB
�V�Ԃ̂��D���Ȃa�c����1���~�̎d�����T2������B����2���~�ɉېŁB�c�����ł��ӂ����D��(�����D������)�B
�@���ӁF�����ł͈�T�Ԃ̊Ԃœ������Ɨ]�ɂ̓��Ƃ�I������A�Ƃ����g�g�݂Ő������Ă��邪�A����̒��ʼn����ԓ������Ƃ����g�g�݂ł��A��N�̒��ʼn����������Ƃ����g�g�݂ł��A�����\�B
������(������)�̊ϓ_����`�Ƃa�Ƃ𒆗��I�Ɉ����ɂ́A���ۂɊ��҂������ł͂Ȃ��A���҂��\�������邩�ɒ��ڂ��ĉېł���ׂ��ł���A�Ƃ������ƂɂȂ�B�`�a�Ƃ��T�̎���7���~�Ƌ[������(�ŗ��͏���������)�ȂǁB
�@���W�F����ł͗V�ѐl�E�ӂ��҂�D��������ʂ������B�����̂��������(�Ⴆ�ΐH��)�Ƃ�����Ȃ�����(�Ⴆ�Ζϑz�ɒ^��Ȃ�)�Ƃ���ʂ��Ă݂���ŁA�l�@����B
�b�͏T�x2���ŔN��1000���~�҂��B
�c�͏T�x4���ŔN��1000���~�҂��B
�����ɂ́A�b�Ƃc�͓����ŕ��S�����ƂɂȂ�B�]�ɂ�D������Ӑ}���Ȃ���A�c�ɑ��Ăb�����d���ŕ��S���ۂ��ׂ��ł���B�ȏ�̐����͘J���Ɨ]�ɂƂ̊Ԃ�������(������)�ɂ��Ă̂��̂ł��邪�A�����̊ϓ_������A�b���c�ɏd���ېł��ׂ��Ƃ���悤(���s�̍���Ƃ����ϓ_��������)�B
�A�����҂��\�������邩����ɂ��邱�Ƃɂ́A���R��`�̊ϓ_����^�`���悳���Bgu
�\�\�L����w���Ƃ̂d�́A�ꗬ���(�N��2000���~)�̓����f��A���c�ɓ������B�A���o�C�g�ŐH���Ȃ����X�ł���N����200���~�B�ېŕW����2000���~�ł���ׂ���200���~�ł���ׂ����Hcf. ���@22���F�E�ƑI���̎��R([���]���ɂ��������Ő����������Ƃ��Ă����{�̍ٔ����͈ጛ�ƌ���Ȃ����낤�Ɛ������邪�A�l�ɂ���Ĉӌ����قȂ肤��)
�l�I���{�c�c�J���҂̐��Y���Ɏ�����J���Ҏ��g�̒m���E�Z�p���̐l�I�����̂��ƁB(cf.�������uhuman capital�Ƒd�Ŗ@�`�����m�[�g�`(�㉺)�v�W�����X�g956��104�ŁA961��215��)
�l���@�B�ɏ�����ƁA�@�B�ւ̓����Ɛl�̋���E�P���Ƃ��������́A�Ƃ��ɐ��Y���Ɋ�^����B
�l�X����w�ɍs���ہA�w������łȂ��A4�N�ԓ����Ă���Γ���ꂽ�ł��낤�������]���ɂ��Ă���ƌ�����(�@���p�̍l����)�B���ꂾ���̃R�X�g�������Ăł��l�I���{�����߂�(�����̍�����)�_��������B(�V�O�i�����O(signaling)�̈Ӗ������Ȃ��Ƃ����l������B[���]��w�����I������ɐc���������Ƃ�������V�O�i�����O�d���Ƃ�����B�c���������Ȃ���ΐl�I���{�琬�ւ̊��҂����낤�B)
�˔\���l�I���{�̈�Ƃ�����B�X�|�[�c�I���f���Ȃǂ���������(���K�E���ϓ��̓��������邪)�B
�@����(����E���K�E���ρE���`��)�̌��ʓ����鏊���ɉېł���A�����ɕ��̗U���������B
�@�˔\(�^���\�́E���e��)�̌��ʓ����鏊���ɉېł��Ă��A�l�X�̍s�����c�߂��Ȃ�(�����I)�B
envy(�i�݁E�Ƃ�)�\�\�����̌��ʂɑ��Ă��˔\�̌��ʂɑ��Ă��A�n�҂͓��l�ɓi�݁E�Ƃ݂�����������Ȃ��B�O�҂ւ̓i�݂ɂ��ېł͐l�X�̍s����c�߂����A��҂ւ̓i�݂ɂ��ېł͐l�X�̍s����c�߂Ȃ��B�X�[�p�[�X�^�[gt�̏����ɓi�݂�����ĉېł���̂͂��������A�Ƃ͌�����Ȃ��B
�^���\�͂���e�́A�ʏ�̎��v�������ߗ���(rent�Ƃ���)�������炷���̂ƍl������B
rent tax�̍l�����c�c�N��1���~�̃��f����9400���~�̐ł��ۂ����Ƃ��Ă��A���̃��f�����ʂ̎d�������ē�����ň��㏊����500���~�Ȃ�A���̃��f���̓��f�������߂Ȃ��B�������d(deadweight loss)���Ȃ����������Q���Ȃ��B
cf.���]�T�����[�}���ŋ��i���E�Ŕ��������N2��7����35��6��1029�ŕS�I5��9�ɂ�����A�u���^�����҂̐��v��͘J���͂̍Đ��Y�̂��߂̕K�v�o��Ƃ��čT�������ׂ��v�E�u�Œᐶ����͔�ېłƂ��ׂ��v�Ƃ����������̎咣(�A���s�i)�ɂ��āA[���]��Â�H��ɒS�ŗ͂��Ȃ��Ƃ����ʔO�́A�l�I���{�T�O�ň�����x�����\�ł��낤�B
�l�I���{�T�O���l���ɓ���ē����E����̋�ʂ��l����Ƃǂ��Ȃ邩�B
�Z����F�l�I���{�ւ̓����ł���A�����(�w�̂��߂̏��Д�����l)���o��Ƃ��čT�����邩�A���Y�v�サ���㌸�����p���ׂ��B
�@�k���s�@�F��{�I�ɋ���������ł���T���s�B�A���A�w�����ŋ��^�̐�����L���Ȃ����̂��ېőΏۂ���O����Ă���B����9��1��15���u�w���ɏ[�Ă邽�ߋ��t�������i�i���^���̑��Ή��̐�����L��������i���^������L����҂����̎g�p�҂������̂ɂ��ẮA�ʏ�̋��^�ɉ��Z���Ď���̂ł��āA���Ɍf����ꍇ�ɊY��������̈ȊO�̂��̂������B�j�������B�j�y�ѕ}�{�`���ґ��݊Ԃɂ����ĕ}�{�`���𗚍s���邽�ߋ��t�������i�v�m�C���n�j���n�A�����9-14�`9-16�Q�Ɓl
�Z��ÁF�l�I���{�̕�C�ł���A�@�B�̏C�U��Ɠ��l�ɁA��������T�����ׂ��B
�@�k���s�@�F��{�I�ɏ���B���������b�I������73��:��Ô�T�����F�߂���(��COLUMN4-4�ی����E���Q�������̔�ې�)�l
�Z�H���F�����ێ������͓����ł���A��������T�����ׂ��B�x�y�����͏���ł���A��������T�����Ȃ��B
�@�k���s�@�F��{�I�ɂǂ��������ł���T���s�B�A������9��1��6���A���ŗ�21��1���͑D���̐H�����ېłƂ��Ă���B�l
[���]�l�I���{�T�O�͐l�X(�l�I���{�Ƃ����T�O��m��Ȃ��Ă�)�̑d�Ō������ɉe�����Ă���Ǝv����B�������l�I���{�T�O��Ő��ɂ܂Ƃ��ɑg�ݍ������Ƃ���ƁA�ېŃx�[�X���������i�i�ɋ����Ȃ鋰��������B�l�I���{�T�O�͗��_�Ƃ��Ă͑�Ϗd�v�ȊT�O��������Ȃ����A���x�ɑg�ݍ��ނɂ͎��ۏ�̏�Q���傫���B
4.2.7. �ސE����(����30��)
����30���i�ސE�����j�u�ސE�����Ƃ́A�ސE�蓖�A�ꎞ�������̑��̑ސE�ɂ��ꎞ�Ɏ鋋�^�y�т����̐�����L���鋋�^�c�c�ɌW�鏊���������B�Q�@�ސE�����̋��z�́A���̔N���̑ސE�蓖���̎������z�����ސE�����T���z���T�������c�z���̈��ɑ���������z�i���Y�ސE�蓖�����A�Z���ސE�蓖���ł���ꍇ�ɂ͎��̊e���Ɍf����ꍇ�̋敪�ɉ������Y�e���ɒ�߂���z�Ƃ��A��������ސE�蓖���ł���ꍇ�ɂ͓��Y�ސE�蓖���̎������z����ސE�����T���z���T�������c�z�ɑ���������z�Ƃ���B�j�Ƃ���B
�@��@���Y�ސE�蓖���̎������z����ސE�����T���z���T�������c�z���O�S���~�ȉ��ł���ꍇ�@���Y�c�z�̓̈�ɑ���������z
�@��@�O���Ɍf����ꍇ�ȊO�̏ꍇ�@�S�\���~�Ɠ��Y�ސE�蓖���̎������z����O�S���~�ɑސE�����T���z�����Z�������z���T�������c�z�Ƃ̍��v�z
�R�@�O���ɋK�肷��ސE�����T���z�́A���̊e���Ɍf����ꍇ�̋敪�ɉ������Y�e���ɒ�߂���z�Ƃ���B
�@��@���߂Œ�߂�Α��N���c�c����\�N�ȉ��ł���ꍇ�@�l�\���~�ɓ��Y�Α��N�����悶�Čv�Z�������z
�@��@�Α��N������\�N����ꍇ�@���S���~�Ǝ��\���~�ɓ��Y�Α��N�������\�N���T�������N�����悶�Čv�Z�������z�Ƃ̍��v�z
�S�@��ɋK�肷���Z���ސE�蓖���Ƃ́A�ސE�蓖���̂����A�ސE�蓖���̎x��������҂���Z���Α��N���i�O����ꍆ�ɋK�肷��Α��N���̂����A�����ɋK�肷��������ȊO�̎҂Ƃ��Ă̐��߂Œ�߂�Α��N�����ܔN�ȉ��ł�����̂������B�掵���ɂ����ē����B�j�ɑΉ�����ސE�蓖���Ƃ��Ďx��������̂ł��āA�����ɋK�肷���������ސE�蓖���ɊY�����Ȃ����̂������B
�T�@��ɋK�肷����������ސE�蓖���Ƃ́A�ސE�蓖���̂����A�������c�c�Ƃ��Ă̐��߂Œ�߂�Α��N���c�c���ܔN�ȉ��ł���҂��A�ސE�蓖���̎x��������҂��瓖�Y�������Α��N���ɑΉ�����ސE�蓖���Ƃ��Ďx��������̂������B
�@��@�@�l�Ŗ@������\�܍��i��`�j�ɋK�肷�����
�@��@����c���y�ђn�������c�̂̋c��̋c��
�@�O�@���ƌ������y�ђn���������v�m6�E7�����n
��F�Α�24�N��2000���~�̑ސE�蓖������{2000�|800�|70�~(24�|20)}��2��460(���~)
�ސE�蓖���̐����F�u���^�̈ꕔ�㕥�v�u���N�̋Ζ��ɑ�����̑��^�v�u�Љ�ۏ�I�ȋ@�\�v
�\�\�V��҂̐����ۏ�A�ݐi�ŗ��̓K�p�̊ɘa (������)���D���̗��R�B�X�������ې��B
��������ސE�蓖(�Α�5�N�ȉ�)�ɂ����z�ېŔp�~(������n�蒹�̑ސE�����y�ۂ͂��������Ƃ̔ᔻ)�B
�����ٗp�E�I�g�ٗp��O��Ƃ����D������Ő��́A����ɑ����ĂȂ��A���̗��@�����_��̔ᔻ���������B
�ސE�����y�ۂ̂��߁A���^���������炵�đސE�����𑝂₷�A�Ƃ����ېœ����U������B
| 6�Ł�223.05 5�N�ސE�����E�Ŕ����a58�N9��9�����W37��7��962��bu�A10�N�ސE�����E�Ŕ����a58�N12��6������1106��61�ŕS�I7��40bx �ō��ق̂����ސE�����̗v���u(1)�ސE���Ȃ킿�Ζ��W�̏I���Ƃ��������ɂ�ď��߂ċ��t����邱�ƁA (2)�]���̌p���I�ȋΖ��ɑ���Ȃ������̊Ԃ̘J���̑Ή��̈ꕔ�̌㕥���̐�����L���邱�ƁA (3)�ꎞ���Ƃ��Ďx�����邱�Ɓv �Ζ��p�����\�肳��Ă��闼�����ɂ����ėv��(1)��������Ƃ����B�����ӌ��͑ސE��̐����ۏ���d�������̂ŁA�Ζ��p�����\�肳��Ă���Ȃ�Ώ����������Ƃ��Čy�ۂł��܂���ׂ������͂Ȃ����ƂɂȂ�B �Ȃ��A10�N�ސE�����ɂ����鉡���O���Έӌ��͗ݐi�ŗ��ɘa(������)���d�������̂ŁA�Ζ��p�����\�肳��Ă��萶���ۏ�̐S�z���������Ƃ��A10�N���̋��^�̌㕥������C�Ɏ������邱�Ƃ𗶂����Bil |
���s�n������23�N4��14���Ŏ�261������11669����20�N(�s�E)23�E37���m��(�������E�W�����X�g1429��100-101��(2011.9.15)�c�c��C�w�Z�̗������̕����ύX�i�Z���Ɗw�@���Ƃ����n�ʂ�ސE�j�ɂ��x�������������ސE�����ɊY������Ƃ�������B�ޗ�Ƃ��āA�w�Z�@�l�̗��������w�Z���y�э����w�Z����ސE����w���ɏA�C�����ۂ̑Ő�x���ސE���̑ސE�����Y������F�߂����n������20�N2��29�����^1268��164�Ŋm��A�g�p�l���玷�s���ɏA�C����ۂ̎q�{�����̑ސE�����Y������F�߂��V���f�B�����E���n������20�N2��29�����^1267��196��(��핐����E�W�����X�g1369��130��)(�T�i�R��㍂������20�N9��10���Ŏ�258������11020�m��)�B
�����n������24�N7��24���Ŏ�262������12010�m��(�]�����E�W�����X�g1457��8-9��2013.8)�c�c�A�����J�e��ЁiMerrill Lynch�j�̓��{�q��Ђ̏]�ƈ����e��Ђ̊����ɂ����錠�����Ă��đސE��Ɍ������m�肵���ꍇ�ł��ސE�����ł͂Ȃ��i���ƂȂ��Ă���restricted share�o���X�g���N�e�b�h�E�V�F�A�܂��̓��X�g���N�e�b�h�E�X�g�b�N�p�̏����Ƃ��đސE���v���Ƃ���Ă��Ȃ������j���^�����ł���Ƃ�������B
4.2.8. ���Ə���(����27��)
���Ə����̒�`�ɂ���6�Ł�223.01�ٌ�m�ږ◿�����E�Ŕ����a56�N4��24�����W35��3��672�ŁB| 6�Ł�224.03��Ў�������i�敨��������E���É��n�����a60�N4��26���s�W36��4��589�� �����E���_�@��Ђ̎���������i�敨����ɂ���Đ����������͎��Ə����v�Z��̑���(����69��1���F���v�ʎZ��)�ɓ����邩�A�G�����v�Z��̑���(���v�ʎZ�s��)�ɓ����邩�B �\���m���@���Z�敨����̑������G�����ɌW�鑹���Ƃ��ꂽ�ꍇ�̑��v�ʎZ�ے肪���@�ᔽ�ɓ����邩�ɂ��āA�����������a54�N7��17����25��11��2888�ŕS�I4��47�\�\���i�敨����ɂ�鏊�����u���Ə����ł͂Ȃ��G�����ƔF�肳���Ƃ���A����͎G�����Ƒ��̏����Ƃ̊Ԃɑ��v�ʎZ�̋K�肪�݂����Ă��Ȃ����Ƃ��炵�Č��@����Y���y�ѐE�ƑI���̎��R�̐N�Q�ɂȂ�Ɓv�̎咣�ɂ��A�u�G�����Ƒ��̏����̊Ԃɂ͏����̔�������ɍ��ق�����A�G�����ɂ����ẮA�����͗]�莑�Y�̉^�p�ɂ�ē�����Ƃ���̂��̂ł���A���̒S�ŗ͂̍��ɒ��ڂ���A�G�����ɑ��̏����Ƃ̑��v�ʎZ�̋K�肪�Ȃ����Ƃɂ͂��ꑊ���̍�������F�߂邱�Ƃ��ł��邩��A��������Č��@������A������Ɉᔽ����Ƃ̌����͍̗p�ł��Ȃ��B�v ���|�@���_�Ƃ��Ă͎G�����ɌW�鑹���B ��ʂ̊�i�{���Ł����Ə������ۂ��v�f�@�~���Ə������ۂ��Ȃ��v�f�j
|
Cf.FX��������E(���R���l�n������25�N7��3���Ŏ�263������12246)������������25�N11��14���Ŏ�263������12335�m��B�ޗ�c�����n������22�N6��24���Ŏ�260������11458����21�N(�s�E)449��
Cf.���Ə����͈̔́c�c5�Ł�224.03�����[�^�[�X�����E���É�������x�����a49�N9��6���s�W25��8=9��1096��gv
Cf.�K�v�o��̈Ӌ`�c�c5�Ł�231.02���ݗp�y�n���^�����E��㍂������10�N1��30���Ŏ�230��337��gx�c���`����q�w�ɓy�n�^�B�w�͑��^�̑O���ʂ��ĕs���Y���Ƃɏ]���B�s���Y�擾�ŁE�o�^�Ƌ��ł��A�s���Y�����v�Z��̕K�v�o��ɎZ�����悤�Ƃ�������B�u����x�o���K�v�o��Ƃ��čT�����ꂤ�邽�߂ɂ́A���ꂪ�q�ϓI�ɂ݂Ď��Ɗ����ƒ��ڂ̊֘A�������A���Ƃ̐��s�㒼�ڕK�v�Ȕ�p�łȂ���Ȃ�Ȃ��v�B�u���^�ɂ���Ď��Y���擾����s�ׂ��̂��̂́A�����邽�߂̎��v�����Ƃ݂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��v�B�s���Y���Ƃ̂��߂ł����Ă����^�Ƃ����u���i�ɕω��͂ȁv���B�y�n�ړ]�́u�傽��ړI�͂`����w�ɑ��鑊�����Y�̑O�n�ł���v�B�u�w���{���y�n�Ɋւ��ĕ��S�����o�^�Ƌ��ŁA�s���Y�擾�ł́A����45��1��1������̉Ǝ���̌o��ɊY�����A���@�{�s��96��1�A2������̋Ɩ��̐��s��K�v�ł������o��ɂ͊Y�����Ȃ��v�B
�ޗ�F���n������29�N3��15����64��2��260�Ő������p�A��㍂������29�N9��28����64��2��244�ōT�i���p�A�ŎO��������30�N4��17������30(�s�c)20���㍐���p�E�㍐�s��(������q�E�W�����X�g1527��140��)�c����37��1���u�K�v�o��v�Ɋւ��u���ځv�֘A����v���Ȃ��Ƃ���������������24�N9��19�����^1387��190��(�ٌ�m�̌��۔�̈ꕔ�̕K�v�o��Z����F�߂�)(�R�c�����u�ٌ�m��̖������Ƃ��čs�������Ǝ��Ə����ɂ�����w���Ɓx�Ƃ̊W�v�Ŗ@�w571��233-240��)�̗���ƈقȂ�A���^�ł̋Ɩ��Ƃ̊֘A���̗L���ɏœ_�Ă��A���^�ł̐����_����K�v�o���Y���̌��_���B
�L���n������23�N7��20����58��8��3058�ŁE�L����������24�N3��1����58��8��3045�ŁE�Ō�����24�N12��20���Ŏ�262������12121�c�ېŏ����̑i�ה�p�͊ҕt���Z��(�G����)�̕K�v�o��ɓ�����Ȃ��B�������n������23�N9��7������22(�s�E)13���E�������{��x������24�N2��15����58��8��3073�ŁE�Ō�����24�N10��25���Ŏ�262������12083�����|
Cf.��@�Ȏx�o��4.3.3. 6�Ł�231.03�����s���c��n���������E�����n�����a48�N6��28���s�W24��6��7��511��
Cf.��p���v�Ή��̌�����4.3.2.1.�K�v�o��̈Ӌ`
Cf.���㌴���c�c5�Ł�234.01(6��427��)�S���ގ擾���z�����E�Ŕ����a30�N7��26�����W9��9��1151��gy
Cf.����63���`67����2�c���ƂɊւ��āi���Ə����Ɍ���Ȃ��j�����E��p�̓����B
4.2.9. �ꎞ����(����34��)
����34���i�ꎞ�����j�u�ꎞ�����Ƃ́A���q�����A�z�������A�s���Y�����A���Ə����A���^�����A�ސE�����A�R�я����y�я��n�����ȊO�̏����̂����A�c����ړI�Ƃ���p���I�s�����琶���������ȊO�̈ꎞ�̏����ŘJ�����̑��̖��͎��Y�̏��n���Ή��Ƃ��Ă̐�����L���Ȃ����̂������B�Q�@�ꎞ�����̋��z�́A���̔N���̈ꎞ�����ɌW�鑍�������z���炻�̎����邽�߂Ɏx�o�������z�i���̎��������s�ׂ����邽�߁A���͂��̎������������̔����ɔ������ڗv�������z�Ɍ����B�j�̍��v�z���T�����A���̎c�z����ꎞ�����̓��ʍT���z���T���������z�Ƃ���B
�R�@�O���ɋK�肷��ꎞ�����̓��ʍT���z�́A�\���~�i�����ɋK�肷��c�z���\���~�ɖ����Ȃ��ꍇ�ɂ́A���Y�c�z�j�Ƃ���B�v
(1)23�`33���̏������ނɓ��Ă͂܂炸�A(2)�u�c����ړI�Ƃ���p���I�s�ׂ��琶���������ȊO�v�ŁA(3)�J�����́u�Ή��Ƃ��Ă̐�����L���Ȃ����́v(34��1��)
�Ⴆ�Ό��܋��A������n����(�Ȃ�������n�������ڔ�p(2��)�͈̔�(�����34-1(2)(��))�ɒ���)(���c���Z�̕��ߋ��̎x����������2019.1.19)
Cf.���Ə������ɊY�����Ȃ����Ή��̐�����L������́A�Ⴆ�Α�w�����̌��e���́A�G����
50���~���ʍT��(3��)�A�X�����z�ې��i����22��2��2���j�B�ݐi�ɘa�B(�S�ŗ͂͒Ⴂ�H�����H)
[�]�k]�s���o�ϊw�̊ϓ_(���z���̋��͎����Ȃ�)����A�ꎞ�����̒S�ŗ͂͒Ⴂ�Ƃ������Ƃ�����ł��邩�H
�l����̑��^�@���@9��1��16���ɂ�菊���Ŕ�ېŁ�COLUMN4-3(�����Ŗ@�ɂ�葡�^�ł��ۂ����)
�@�l����̑��^�@���@�ꎞ�����@(�@�l�i�K�ł̉ېł̗L�������ېœ��̖���5.2.3.5.c)
| 6�Ł�225.01�y�n�����擾�����E�É��n������8�N7��18���s�W47��7=8��632�ŕS�I7��15ku ���Ŏ����Ɋւ�����~�������E�Ŕ����a61�N3��17�����W40��2��420��ba�Ɋ�Â��A�������p���ɓy�n�̎��������z�̈ꎞ�����ɌW��������z��������B �����n������4�N3��10����39��1��139�ŕS�I5��50�����|(��4.2.3.4.�擾��͈̔�) ������͔ᔻ������A�������p�̗L�����ɂ��đ���������ꍇ�͎������p���ł͂Ȃ��ٔ��m�莞�Ɏ������z��������Ƃ��ׂ��ł���ƌ����Ă���(�S�I7��15���)�B�ٔ��m�莞�̌����_�ɂ��ā�4.4.3.�Ǘ��x�z��A6�Ł�232.03���������z���������E�Ŕ����a53�N2��24�����W32��1��43�� |
| 6�Ł�225.02�O��n�����������E�Ŕ�����29�N12��15�����W71��10��2235�ŕS�I7��48ca(�����n������27�N5��14������24(�s�E)849���E������������28�N4��21������27(�s�R)236��)(�j�X�j�ׁE�d�ői��17��131-148��{�[�Ŏґ��㗝�l}) �Y������(�O��n���w����p�T���F�e)�c(���n������25�N5��23������23(��)625���E��㍂������26�N5��9������25(��)858��)�Ŕ�����27�N3��10���Y�W69��2��434�ŕS�I6��45cd �O��n���w����p�T���ے��c(���R�����n������28�N3��4����63��7��1875��)������������28�N9��29����63��7��1860��(�Ō�����29�N12��20������29(�s�c)17��)�A(���R���l�n������28�N11��9����63��5��1470��)������������29�N9��28���Ŏ�267������13068(�Ō�����30�N8��29������30(�s�q)46��)�A(���R�����n���ߘa���N10��30�����^1482��174�ł͈ꕔ�G�����B�T�i�R�ŋt�]�����B�{�c���G�E�W�����X�g1556��123-126��2021.4)���������ߘa2�N11��4����67��8��1276�� �I�����C���X�|�[�c�q��(�O��q�����T���ے�)�c�����n���ߘa2�N10��15������30(�s�E)68���Ŏ�270������13464���p�E���������ߘa3�N8��25���ߘa2(�s�R)226���Ŏ�271������13597���p(��{�j���E�W�����X�g1596��144-147��) ���J��n�u���n�̕��ߋ��ɑ���ېœ��Ɋւ��鎿���ӏ��v(2024.4.17) �ݓc���Y�u�O�c�@�c�����J��n�N��o���n�̕��ߋ��ɑ���ېœ��Ɋւ��鎿��ɑ��铚�ُ��v(2024.4.26) |
| (�P6��281��)�t�n�[�t�^�b�N�X�v���������E�Ŕ�����24�N1��13�����W66��1��1��(�n�ӗT�ׁE�W�����X�g1446��118-121��2012.10)im �@30�ی����@�@�@�b�w�������̏ꍇ�@�@�b�w�����S�̏ꍇ �`�Ё\�\�\���a�@�b�@�`�Ё@�@�@�@�a�@�b�@�`�Ё��\�\�\�a �@30�ی����@���@�b�@�����ی���80���@�b�@�����ی���80�� �w���\�\�\���ہ@�b�@�w�����\�\�\�ہ@�b�@�w���@�@�@�@�� �{�V�ی��̓��e�c�c�`�ЂƂ��̑�\�҂w�����a�����ی���ЂƗ{�V�ی��_���������A�ی������`�ЂƂw�����ܔ����ėႦ��30����(���v60�̕ی���)�a�Ɏx�����B�������ɂ`�Ђ̑�\�҂w�������˂`�Ђ��ی��������i����`�Ђ��ی����̔����S�������o�����邱�Ƃɂ͐�����������Ƃ����咣�j�A�w���������Ă���w���������ی��������i�ی����̔����͂w���̕��S�Ƃ������O�ɂȂ��Ă���j�B �@���ʂƂ��Ăw���������ی���80��������ꍇ�A�w���̈ꎞ�����̋��z�̌v�Z��A����34��2���u���̎����邽�߂Ɏx�o�������z�v��30���i�ꎞ������80�|30��50���j�j�A60���i�ꎞ������80�|60��20���j�i�`�Вi�K�ő����Z���A�w���i�K�ŏ���34��2���Z���Ƃ����A��d�T���̋A���ƂȂ��Ă��܂��B �@�ō��ق́A�ی���60�̂����`�Ђɂ����ĕی����Ƃ��đ����o�������ꂽ����30������34��2���ɂ����u���̎����邽�߂Ɏx�o�������z�v�ɓ�����Ȃ��Ƃ����B �@�����������34-4�͕ی����̎x�o�҂��N�����肵�ĂȂ������̂ŁA�`�Е��S�ی���������34��2���̍T���Ώۓ��Ǝ����Ƃ͍l���Ă������A�ō��ق́A�ʒB���x�o�҂����肵�Ă��Ȃ��Ƃ��A����34��2���̕�������A�w��������x�o�����ی���(���͎��畉�S�����ی���)�Ɍ�����A�Ɣ��f�����B�ō��ق̖{�łɊւ��锻�f�͂Ƃ������A���Z�łɊւ����Œ�65��4���u�����ȗ��R�v�̔��f�̂��ߍ����߂����B���ߍT�i�R������������25�N5��20������24(�s�R)7���́u�����ȗ��R�v�͔F�߂��Ȃ��Ɣ��f�����B �@�T�i�R������������21�N7��29������21(�s�R)11���ō�����������A�ō��ق�������������O�A����23�N6��30�������ŗ�183��4��3����lj����A�`�Ђ����S�����ی����́A�w���̈ꎞ�����̌v�Z�ɂ����čT���ł��Ȃ����ƂL�����B �@�������A����34��2���ɂ��Ăw������x�o�����ی����Ɍ���Ƃ������߂��̗p���Ȃ��Ă��A�`����������30�̕ی����͂w���̎��S�m���ɏƂ炵�ĕs���ɍ�������(�Ⴆ�w���̎��S�m����5���Ȃ�A���ی���60�̂����`�Ђ�3���A�w����57�S���ׂ��ł���)�̂ŁA�K���ی����z(�Ⴆ��3)�Ƃ`�Ђ̎��ۂ̎x�o�z30�Ƃ̍��z27���A�`�Ђ���w���ɑ��Ă̋��^�ł���Ƃ��āA�w���ɋ��^�����ېł����ׂ��ł������B(��萭���E�W�����X�g1407��173-175�ŎQ��) �@�ޗ�@�Ŕ�����24�N1��16������2149��58��(��R�����n������22�N3��15������20(�s�E)58���͔[�Ŏ҂������������T�i�R������������22�N12��21������22(�s�R)12���́A��L�قǘI���ȑd�ʼn��_���̎��Ăł͂Ȃ��������A�������������j�������������A�X�ɐŒ�65��4���ɂ����u�����ȗ��R�v������Ƃ������R�̔��f�ɂ������߂���(���ߍT�i�R������������25�N5��20������24(�s�R)8��)�B �@[���]��l�̎����E�x�o�ɒ��ڂ��ď�����c�����ׂ��Ƃ����ԓx��COLUMN4-3�N�����������ی��N����d�ېŎ����̍ō��قƋ��ʂ��Ă���Ƃ��l������B �@[���]�{�����͉�Е��S�ی����܂ōT������Ƃ�����d�T���������̂́A�{���̂悤�ȗ{�V�ی��̖����ی������ꎞ�����������Ĕ��z�ېłɕ������߂�̂́A���^�����ېłƔ�ׂĂ��܂�Ɍy������̂ł͂Ȃ����H�Ƃ̖�肪���݂��Ă���B���X�����ی����͏���76���̐����ی����T���ɂ��D������Ă���̂ŁA���X�Ƃ����������邩������Ȃ�����ǂ��B |
| �����n������30�N9��25���Ŏ�268������13192����29(�s�E)128��(�F�e)(�m��)(�d�K�u�����̎����ɂ����łŐ�������Ə����v�̔F��Ə�������`�v�V�E������Watch26��241�őd�Ŗ@No. 154)�c�c�����w�����a�Ђ���5���~��̎؋������Ă����B�w���̐e�ł���`����2���~���a�ЂɎx�����A�`�����w���ɑ���������L���邱�ƂƂȂ����B�`�������S���w���ٕ̈��̂c�����`�����瓖�Y�������𑊑������Ɛ�������邪�A�`���̈⌾�̒��ŁA�`���̂w���ɑ���Q���~�̑������c���ɑ��������邱�ƂƂ���Ă����i�A���c���������ł�[�߂����ǂ����s�����B���炭�[�߂ĂȂ��ł��낤�Ƃ����O��Ō�����̋c�_�͐i�j�B�c�����w���ɑ��Q���~�̑�����L���Ă���Ǝ咣��200���~�̈ꕔ�����������B�ʑi�ł`�����������ł��咣���A�`�����i�Ŋm�肵���i���l�n������25�N5��24���j�B�Ŗ������́A�w���̑����̎������ł̉��p�𗝗R�Ƃ��Ăw���ɂQ���~�̈ꎞ�������������Ă���Ƃ��āi�ނ��A200���~�̈ꕔ�����ɑ��鎞�����ł̉��p�͓��Y200���~�̕����ɂ����y�ȂȂ��Ƃ����̂����@�ɂ����闝���ł���A�z�̓_�ł��ېŒ����̎咣�ɖ���������j�A���z�X�����������������B��ɁA�������̎������ł𗝗R�Ƃ��A�������R�̍��ւ���������邩�����_�ƂȂ��Ă���B���_�Ƃ��Ĉꎞ�����s�����B |
| (���R�����n������22�N10��8����57��2��524�ŕ���21(�s�E)209��)������������23�N6��29���Ŏ�261������11705����22�N(�s�R)356��(�ݓc��v�E�W�����X�g1460��123-126��2013.11)�c���@��̑g���ɕt�^���ꂽ�V���\�̍s�g�ɌW��o�ϓI���v���A�g���ɂ��̑Ή��Ƃ��Ă̐�����L����Ƃ��Ĉꎞ�����ł͂Ȃ��G�����ɊY������(�V���\�̍s�g�̑Ή��ł��邩��ꎞ�����ł���Ƃ������Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ�)�Ƃ��ꂽ����B |
| �����n���ߘa4�N12��21���ߘa3(�s�E)140�����p(�c���G���E�W�����X�g1603��154-157��)�E���������ߘa5�N8��2���Ŏ�273������13871���p�c�c��ꊔ���L�����s�ɂ��o�ϓI���v���l����ɐ������ƔF�߂�ꂽ��B�����23�`35��-7(�����ƈ������ɕ������ނׂ��z���L���ȋ��z�ł���ꍇ)�A��-9(����84��(���n�����t�����̉��z��)3��3���u�����ƈ������ɕ������ނׂ��z���L���ȋ��z�ł���ꍇ�ɂ����铖�Y�������擾���錠���v)�Q�ƁB�����̃}�[�P�b�g�E�C���p�N�g�_(���ʂ̊�������C�ɔ��낤�Ƃ���ƒl�������Ȃ���Ȃ�Ȃ�)���ٔ����͍̗p���Ȃ������B�c����(�}�[�P�b�g�E�C���p�N�g�_�s�̗p�Ɏ^������)�������������Ă��锤(�Ȃ̂ɔ����ʼn��i�ɔ��f����Ă��Ȃ����݂�����̂ł͂Ȃ���)�ƕ��͂��Ă���B |
| �����n���ߘa3�N1��29���ߘa��(�s�E)449���Ŏ�271������13518���p(���䗢�ہE�W�����X�g1579��146-149�ŁA���ˋM�V�E����E�w���Z����Ɖې�(7)�x15-28��)�c�c��\���������Ђ���������̎擾���z�Ɖ���z�Ƃ̍��z���A�Ή����i��\���������Ђɒ����̑Ή��j���Ȃ��Ă����������Ȃ��̂ňꎞ�����ł͂Ȃ��G�����ł���Ƃ��ꂽ����B�u�ꎞ�̏����v���ꎞ�������悷��v���i�������v���j�Ƃ����邩�H |
| �����n���ߘa5�N3��14���ߘa��(�s�E)615������2611��25�ňꕔ�F�e�A�ꕔ���p�E���������ߘa6�N1��25���ߘa5(�s�R)105���������ύX(����p�q2025�N3��21���d�Ŕ��ጤ�����)(���ԑ叇�u�ꎞ�����Ƃ��ē������Ə��v����T���ł���w���̎����邽�߂Ɏx�o�������z�x�F�����n���ߘa5�N3��14���̌����vTAINS�����235��1-12��(2023��) (BLOG))(�c�������u�푊���l�̂����a���Ɋ�Â����Ɋւ��鑊���l�ւ̍��Ə��v�ې��v�V�E������Watch�d�Ŗ@No.181 2024.1.26)(�q���q���u���T������Ȃ����������̑������Y�ւ̉ېłƍ��Ə��v�ېł̓�d�ېŊY�����v�V�E������Watch�d�Ŗ@No.189 2024.9.13)(����p�q�E�W�����X�g1610���d����6�N154-155��) �@���� �@�����灁�����`�{�����a�B�����`�͖S�d�̎q�A�����a�͖S�d�̍ȁB�S�d�͖S�e�̎q�ł���A�����`�͖S�e�̗{�q�B �@1993�N9��6���A�{����s���S�e���؎�A�S�d��ۏؐl�Ƃ���16���~��݂��t�����i�{���ݕt�j�B�S�e���`�Ń��}���V�����w���B �@2002�N2��15���A�{����s���S�e�S�d�ɑ��ԍς����߂Ē�i�B �@2002�N4��26���A�S�e�̔��f�\�͌��@�ɂ�����Ŗ{����s�ƖS�d���ʖd���S�e���`�̏����������ȂǂɊ�Â��A�S�e���{���ݕt�̍�����ݒ�o�L�̖����o�L�������i(�O�i)�B �@2002�N10��23���A�S�e���S�B �@2003�N8��25���A�S�e�����l�炪�����Ŗ������ɑ����ł̐\���B �@2003�N8��27���A�O�i�Ɋւ������n�ق��u�a���Ɍ����Ă̌����v���ʂ��쐬�B�@�{���ݕt���ōw���������}���V�����̉��i�����z��{����s�ɕԍς���B�A�S�d�͖S�e�̈�Y��1/6�i2.4���~�j��{����s�ɕԊ҂���B �@2003�N12��25���A�S�d�����}���V������4.11���~�Ŕ��p�B �@2004�N3��31���A�S�e�����l�炪��Y�������c�B�{���ݕt�����͖S�d�����p����B �@2004�N4��15���A�S�e�����l��͑O�i�ɂ��Ęa���i�{���a���j�B�S�d�͖S�e�̍���S�e�����l��i�S�d�������j���������B�S�d�͖{����s�ɉ��L���`���̋������x�����B�S�d���x�Ȃ����`���̋����x����������A�{����s�͂��̎x���`����Ə�����i�{�����Ə��j�B �@�y���@�����P�U�N�X���R�O��������R���V�P�R�O���~�z �@�y���@�����P�W�N�P�Q���R�P��������Q���T�O�O�O���~�z �@�y���@�����P�X�N���畽���Q�W�N�܂Ŗ��N�U���R�O��������T�O���~�i�P�O��A���v�T�O�O���~�j�z �@�y���@�����Q�W�N�V���R�P��������X���V�R�V�O���~�z �@2014�N10��27���A�S�d���S�B���`���ɂ��ĖS�d�͎x�������Ă����B �@2015�N6��24���A�S�d�����l��Ɩ{����s�́A��100���~�{���ɂ��āA�����`���ƐӓI�Ɉ����A�����a���d���I�Ɉ�����Ƃ̍�����_�������B �@2015�N8��12���A�S�d�����l�炪��Y�������c�B�{���ݕt�c���͌����`�����a�����������p�B �@2015�N8��21���A�S�d�����l�炪�����ł̐\���B �@2015�N6��30���y��2016�N6��30���A������͖{����s�ɂ���50���~�����x�������B �@2017�N3��16���A�������2016�N�i����28�N�j�̏����ł̐\���B �@2017�N5��12���A�S�d�����l�炪�����łɂ��ďC���\���B�{���ݕt�̎c����0�~�ƏC�������B �@2018�N4��25���A�����Ŗ������H���A�����炪�{�����Ə��ɂ��9��7370���~�̗��v�i�{�����Ə��v�j���Ƃ��āA����28�N���̌�����̑������ɔ��������Z�����i�{���e�����j�B �@���_3�F��d�ېł̔r��(�����Ŗ@9��1��17��)�̓K�p�̗L���i���_1���_2���_4���_5�͏ȗ��j �@��R�����@�u�����Ŗ@�X���P���P�U���́A�u�����A�②���͌l����̑��^�ɂ��擾������́v�ɂ͏����ł��ۂ��Ȃ��Ƃ��Ă���Ƃ���A����͑����A�②���͌l����̑��^�ɂ��擾������̂ɂ��ẮC�ʓr�����Ŗ��͑��^�ł��ۂ����邽�߁A��d�ېł�����邽�߂ɏ����Ŗ@��͔�ېłƂ��ꂽ���̂ł���B�����āA�{�����Ə��ɌW����Ə��v�ɂ��ẮA��~�����̐��A���S�d�̑��������̌�ł��邱�Ƃ���A�O�L�̂Ƃ���S�d��푊���l�Ƃ��鑊���łł͍l������Ă��Ȃ��B���������āA�{�����Ə��v�Ƃ��������̔������ɂ����S�d�̑����l�ł��錴����ɌW�鏊���ł̉ېőΏۂƂ��邱�Ƃ́A�����Ŗ@�X���P���P�U���̑O�L��|�ɔ�������̂ł͂Ȃ��v�B �@�u������̎咣����悤�ɁA���ɖ{�����Ə��ɌW������S�d�̏��ɍ��Y�Ƃ��Ă��̑������Y�̌v�Z�ɓ������ĎZ������Ă���A������̔[�t���ׂ������ł���������\�������������Ƃ͔ے肵���Ȃ����A�����Ŗ@�́A�{�����Ə��ɌW����̂悤�ȕs�m��ȍ��ɂ��ẮA�����ł̎Z��ɍۂ��č��Ƃ��Ă̎Z����F�߂Ă��Ȃ��̂ł���A���ɁA�{���ƈقȂ�A������̎���ɂ���Ė{�����Ə��̒�~���������A���Ȃ����Ƃ��m�肵���ꍇ�i���Ə��v�������邱�Ƃ��Ȃ��B�j�ɂ����Ă��A�k�y�I�ɑ������ɂ����ē��Y�����u�m���ƔF�߂���v���̂ł������Ƃ������Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��B�����ł���ȏ�A�{�����Ə��̒�~���������A���A���ɍ��Ə��v���������{���ɂ����āA�{�����Ə��ɌW����������łɂ����čl�����ꂸ�A���Ɏ����������Ə��v�ɑ��鏊���ł̉ېł�����邱�Ƃ���ނȂ����̂Ƃ����ׂ��ł���B�܂��A�����Ŗ@�X���P���P�U���́A�����ɂ�蓾���ϋɍ��Y�ɑ��A�����łɉ����ď����ł��ۂ����Ƃ��֎~�ΏۂƂ��đz�肵�Ă�����̂Ɖ�����A�������Ɂu�m���ƔF�߂��v�Ȃ��������߂ɍT�����F�߂��Ȃ���������ΏۂƂ��đz�肵���K��Ƃ͉����ꂸ�A��ɁA�����ł̉ېŊ�����鑊���������̌�ɒ�~���������A�������ʔ������ׂ����Ə��v�ɓK�p�������̂Ƃ͉�����Ȃ��B�v �@��R�����@�u�Q�@���_�R�i��d�ېł̔r���i�����Ŗ@�X���P���P�U���j�K�p�̗L���j�ɂ��� �i�P�j�m���n �i�Q�j�P�R������́A�S�d�̑������Y����{�������T�������ɉېʼn��i���Z�肵�đ����ł��ۂ��Ă����Ȃ���A�{�����̖Ə����Ȃ��ꂽ���ɂ͖{�����̑��݂�O��ɂ��̖Ə��v�����������Ƃ��Ă���ɏ����ł��ۂ��̂́A�����Ŗ@�X���P���P�U���ɔ������d�ېłƂ��ċ�����Ȃ��|�咣����̂ŁA���̓_�ɂ��Č�������B �@�����Ŗ@�X���P���́A���̒������ɂ����āu���Ɍf���鏊���ɂ��ẮA�����ł��ۂ��Ȃ��B�v�ƋK�肵�A���̂P�U���ɂ����āu�����C�②���͌l����̑��^�ɂ��擾������́i�����Ŗ@�̋K��ɂ�葊���A�②���͌l����̑��^�ɂ��擾�������̂Ƃ݂Ȃ������̂��܂ށB�j�v���f���Ă���Ƃ���A�����̎�|�́A�����Ŗ��͑��^�ł̉ېőΏۂƂȂ�o�ϓI���l�ɑ��Ă͏����ł��ۂ��Ȃ����ƂƂ��āA����̌o�ϓI���l�ɑ��鑊���Ŗ��͑��^�łƏ����łƂ̓�d�ېł�r���������̂ł���Ɖ������i�ō��ٔ��������Q�Q�N�V���U����O���@�씻���E���W�U�S���T���P�Q�V�V�Łj�B �@�܂��A�����ł́A�������Y���擾���������ɑ��ĒS�ŗ͂����o���ĉېł������̂ł���Ƃ���A�������Y�̎擾�҂��푊���l�̍������p���ĕ��S����ꍇ�ɂ͂��̕��S���ɂ��Ă͒S�ŗ͂����E����邱�ƂɂȂ邱�Ƃ���A�������Y����̓��Y���̍T����F�߂�Ƃ���̂������Ŗ@�m���炭�����Ŗ@�n�P�R���P���P���̎�|�ł���A�푊���l���珳�p��������u�m���ƔF�߂�����́v�łȂ��ꍇ�ɂ͒S�ŗ͂����E����邱�Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ�����A���Y���ɂ��Ă͑������Y����̍T����F�߂Ȃ��Ƃ���̂����@�P�S���P���̎�|�ł���Ɖ������B �@���̂悤�ȋK��̎�|�܂���A�S�ŗ͂����E��������̂ł͂Ȃ��Ƃ��đ������Y����T������Ȃ������������������J�n��ɖƏ���������Ƃ����āA����ɂ����҂ɐV���ȒS�ŗ͂���������̂Ɖ����邱�Ƃ͑����łȂ��B �@��������ƁA�푊���l���珳�p�������ɑ�������ł����āA�����Ő\���̍ۂ̉ېʼn��i�̎Z��ɂ������ċ߂������ɖƏ�����\�����ɂ߂č������Ɠ��𗝗R�ɑ����Ŗ@�P�S���P���́u�m���ƔF�߂�����́v�ɂ�����Ȃ��Ƃ��đ������Y����T������Ȃ����������A���̌�ɍ��҂ɂ��Ə����ꂽ�ꍇ�ɂ����铖�Y���Ə��ɌW�鑊���l�̗��v�ɂ��ẮA�`���I�ɂ͍��Ə��������_�Ŕ����������̂Ƃ�����Ƃ��Ă��A�����ʼnېłƂ̊W�ł́A���ݓI�ɂ͑����ɂ��擾���Ă������̂Ƃ݂邱�Ƃ��\�ł���A�܂��A���̋�̓I�ȓ��e���݂Ă��A��L�\���ɌW��ېʼn��i�̂����������Y����T������Ȃ�������L���ɑ������镔���̌o�ϓI���l�Ǝ����I�ɓ���̂��̂Ƃ������Ƃ��ł��邩��A���i�̎���̂Ȃ�����A����ɏ����ł̉ېł����邱�Ƃ́A�����Ŗ@�X���P���P�U���ɔ�������̂Ƃ��ċ�����Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���B �@�����{���ɂ��Ă݂�ɁA�{�����Ə��v�́A�푊���l�̖S�d����P�R�����炪���p�����{����s�ɑ�����ł����āA�{���a���̖��ɂ��Ə�����\�����ɂ߂č������Ƃ��瑊���ł̏C���\���̍ۂ̉ېʼn��i�̎Z��ɂ������đ����Ŗ@�P�S���P���́u�m���ƔF�߂�����́v�ɂ�����Ȃ��Ƃ��đ������Y����T������Ȃ������{�������A���̌�ɖ{���a���̖��Ɋ�Â��{����s�ɂ��Ə����ꂽ�ꍇ�ɂ�������Ə��ɌW��P�R������̗��v�ł���Ƃ�����B�����āA�{���ɂ����ẮA�{�����𑊑����Y����T�������ꍇ�Ƃ�������Ȃ��ꍇ�̑����Ŋz�̑����z�i���v�Q���P�X�V�Q���S�X�O�O�~�j�Ɩ{�����Ə��v���ꎞ�����Ƃ��ď����ł̉ېł����Ȃ��ꍇ�Ƃ���������ꍇ�̏����œ��̖{�Ŋz�̑����z�i���v�Q���Q�Q�V�R���Q�P�O�O�~�j�Ɍ��ʓI�ɒ����������Ȃ����Ɓc�c�Ȃǂ̏ɏƂ炵�Ă��A��L���i�̎���͌�������Ȃ��B���������āA�{�����Ə��v�ɏ����ł̉ېł����邱�Ƃ́A�����Ŗ@�X���P���P�U���ɔ����ċ�����Ȃ��B�v |
4.2.10. �G����(����35��)
����35���i�G�����j�u�G�����Ƃ́A���q�����A�z�������A�s���Y�����A���Ə����A���^�����A�ސE�����A�R�я����A���n�����y�шꎞ�����̂�����ɂ��Y�����Ȃ������������B�Q�@�G�����̋��z�́A���̊e���Ɍf������z�̍��v�z�Ƃ���B
�@��@���̔N���̌��I�N�����̎������z������I�N�����T���z���T�������c�z
�@��@���̔N���̎G�����i���I�N�����ɌW����̂������B�j�ɌW�鑍�������z����K�v�o����T���������z
�R�@�O���ɋK�肷����I�N�����Ƃ́A���Ɍf����N���������B
�@��@��O�\����ꍆ�y�ё�i�ސE�蓖���Ƃ݂Ȃ��ꎞ���j�ɋK�肷��@���̋K��Ɋ�Â��N�����̑������ꍆ�y�ё�ɋK�肷�鐧�x�Ɋ�Â��N���i����ɗނ��鋋�t���܂ށB��O���ɂ����ē����B�j�Ő��߂Œ�߂����
�@��@�����i�ꎞ�����������B�j�y�щߋ��̋Ζ��Ɋ�Â��g�p�҂ł����҂���x�������N��
�@�O�@�m�苋�t��ƔN���@�̋K��Ɋ�Â��Ďx������N���i��O�\����O���ɋK�肷��K��Ɋ�Â��ċ��o���ꂽ�|���̂����ɂ��̔N�����x������铯�@���\���ꍀ�i�����ҁj�ɋK�肷������ҁi�����ɋK�肷������҂ł����҂��܂ށB�j�̕��S�������z������ꍇ�ɂ́A���̔N���̊z���炻�̕��S�������z�̂������̔N���̊z�ɑΉ�������̂Ƃ��Đ��߂Œ�߂�Ƃ���ɂ��v�Z�������z���T���������z�ɑ������镔���Ɍ���B�j���̑�����ɗނ���N���Ƃ��Đ��߂Œ�߂����
�S�@��ɋK�肷����I�N�����T���z�́A���̊e���Ɍf����ꍇ�̋敪�ɉ������Y�e���ɒ�߂���z�Ƃ���B
�@��@���̔N���̌��I�N�����̎������z���Ȃ����̂Ƃ��Čv�Z�����ꍇ�ɂ���������ꍀ��O�\���i��`�j�ɋK�肷�鍇�v�������z�i�����y�ё�O���ɂ����āu���I�N�����ɌW��G�����ȊO�̍��v�������z�v�Ƃ����B�j���疜�~�ȉ��ł���ꍇ�@���Ɍf������z�̍��v�z�i���Y���v�z���Z�\���~�ɖ����Ȃ��ꍇ�ɂ́A�Z�\���~�j
�@�@�C�@�l�\���~
�@�@���@���̔N���̌��I�N�����̎������z����\���~���T�������c�z�̎��Ɍf����ꍇ�̋敪�ɉ������ꂼ�ꎟ�ɒ�߂���z
�@�@�@�i�P�j�@���Y�c�z���O�S�Z�\���~�ȉ��ł���ꍇ�@���Y�c�z�̕S���̓�\�܂ɑ���������z
�@�@�@�i�Q�j�@���Y�c�z���O�S�Z�\���~�����S��\���~�ȉ��ł���ꍇ�@��\���~�Ɠ��Y�c�z����O�S�Z�\���~���T���������z�̕S���̏\�܂ɑ���������z�Ƃ̍��v�z
�@�@�@�i�R�j�@���Y�c�z�����S��\���~����S�\���~�ȉ��ł���ꍇ�@�S�l�\�l���~�Ɠ��Y�c�z���玵�S��\���~���T���������z�̕S���̌܂ɑ���������z�Ƃ̍��v�z
�@�@�@�i�S�j�@���Y�c�z����S�\���~����ꍇ�@�S�\�ܖ��ܐ�~
�@��@���̔N���̌��I�N�����ɌW��G�����ȊO�̍��v�������z���疜�~����疜�~�ȉ��ł���ꍇ�@���Ɍf������z�̍��v�z�i���Y���v�z���\���~�ɖ����Ȃ��ꍇ�ɂ́A�\���~�j
�@�@�C�@�O�\���~
�@�@���@�O�����Ɍf������z
�@�O�@���̔N���̌��I�N�����ɌW��G�����ȊO�̍��v�������z����疜�~����ꍇ�@���Ɍf������z�̍��v�z�i���Y���v�z���l�\���~�ɖ����Ȃ��ꍇ�ɂ́A�l�\���~�j
�@�@�C�@��\���~
�@�@���@��ꍆ���Ɍf������z�v
�u������ɂ��Y�����Ȃ������v(�V���E�v�����Ɋ�Â����a25�N�����ɂ��)>
�S���ʈ����̔N�����Ƃ��̑��̎G�������G�����Ƃ�����ތ^�ɂ܂Ƃ߂�Ӌ`������̂��A�t�Ɉꎞ�����ƎG��������ʂ���Ӌ`������̂��A���A���@�_��̋c�_�̗]�n�͂���B
�G�����̌v�Z�㑹�����������Ă����̏������ނ����v�ʎZ�ł��Ȃ�������69��1����4.6.3.�B
COLUMN4-3 �N�����������ی�����d�ېŎ���
| 6�Ł�211.04�N�����������ی�����d�ېŎ����E�Ŕ�����22�N7��6�����W64��5��1277�ŕS�I7��34lc �@�ی����@�@�@�@�b�N�������I���@�@�@�b�ꎞ�����I�� �`�v�\�\�\���a�@�b�@�`�v(�S)�@�@�a�@�b�@�`�v(�S)�@�@�a �@�@�@�@�@�@���@�b�@230�N��x10�@���@�b�@2059�ꎞ���@�� �w�ȁ@�@�@�@���@�b�@�w�ȁ��\�\�\���@�b�@�w�ȁ��\�\�\�� �@�@�@�@�@�@�ہ@�b�@�@�@���\�\�\�ہ@�b�@�@�@���\�\�\�� �@�@�@�@�@�@���@�b�@4000�ꎞ���@���@�b�@4000�ꎞ���@�� �@�v�`���a�����ی���Ђɐ����ی������Ď��S���A�Ȃw�������J�n������10�N�Ԗ��N230���~�̐����ی��N��(���v2300���~)����邱�ƂƂȂ���(�ꎞ���Ƃ��đ���4000���~������Ă��邪����͑����ېł̘b�Ȃ̂ŏȗ�)�B�������������Ŗ@24��1��(�����u�C�@���Y�_��Ɋւ��錠�����擾�������ɂ����ē��Y�_������Ƃ����Ȃ�Ύx������ׂ����Ԗߋ��̋��z�v�ɑ�������K�肪�Ȃ�����)�ɂ�茻��1380���~�Ƃ��đ����ł̉ېŕW���Ɋ܂߂���(�ނ����̂w�̑����Ŋz��0�~�ł������炵���B�����Ŗ@�����b�T�����̘g���������̂ł��낤)�B �@�ېŒ��͍X�ɖ��N230���~�̔N���ɂ��āA�`�̊����ی����z��1/10�i��200���~�̊����ی����z�̂����N���ɑΉ����镔����1/10�ł���9.2���~�j���T�������G�����E��220���~�i230�|9.2��220.8�j��������̂Ƃ��ĉېł���(���ŗ�183��)(�`���Ⴍ���Ď���ł��܂��A�����ی����z�����Ȃ�����)�B����͏���60��1���ɂ���擾��̈��p��(��4.2.3.6.)�ɗނ���v�Z�ł���B �@�w�͂��̏����ېł�����9��1��16��(����15��)�ɔ�����Ǝ咣�����B���ɂw�������J�n���ɔN���̈ꎞ��(�O�q�̎��S�ꎞ��4000���~�Ƃ͕ʕ��ł��邱�Ƃɗ���)��I�����Ă����Ȃ�A�����ی���ЂƂ̌_��ɂ��230���~��8.956�{(2059��8800�~)����邱�Ƃ��ł���A�Ƃ������Ƃ��`�Ƃa�ЂƂ̊Ԃ̌_��Œ�߂��Ă����Ƃ���A�����ꎞ���̋��z�ɂ͑����ł��ۂ�����݂̂ł��菊���ł͉ۂ���Ȃ�(��4.2.3.5.�E����59��1�����݂Ȃ����n�ɗނ��鏊���ېł͂Ȃ�)�Ƃ���Ă���(�����9-18�N���̑��z�ɑウ�Ďx������ꎞ��)�B �@[���]���͂Ƃ����A���S�ꎞ��4000���~�E�N���̈ꎞ��2059��8800�~�ɂ��āA�����ł��ۂ��݂̂Ȃ炸�A����59��1���ɗނ��鏊���ېł�����A�Ƃ��Ă����A�ېł̐������͕ۂ���Ă����ł��낤�B����������59��1���̓K�p�͈͂����߂��Ă������o�܂ɏƂ炵�A���S�ꎞ��4000���~�E�N���̈ꎞ��2059��8800�~�ɂ��ď���59��1���ގ��̉ېł����邱�Ƃɂ͒�R�����������̂ł��낤�B �]���ɂ��āc�c�ꎞ����I�������2059��8800�~����邱�Ƃ��ł���̂ɁA�����Ŗ@24��1��(����)�ɂ��Ȃ�1380���~�ƕ]�������̂��H�c�c�����̑���24��1���̌v�Z�͕֖@�ɂ����Ȃ����A�[�Ŏ҂ɊÂ�����̂ŁA�{���̂悤�Ɉꎞ����I�������2059��8800�~����邱�Ƃ��ł���Ƃ����ꍇ�ɂ͂�����̊z�������Ŗ@����]���z�ƂȂ�悤�ɉ������ꂽ(�w�����Ŗ@�̂��ׂĕ���22�N�Łx427��)�B�N�����v�Z�ŁA���ڊz���v2300���~�������J�n����2059��8800�~�ƕ]�������悤�Ȋ������͖�2.54��(�N����)�A1380���~�ƕ]�������悤�Ȋ������͖�13.72��(�N����)�ƂȂ�B�O�҂͊T�ˎs��̎����ɓK���Ă�����̂ł��낤��(�Ɨ������҂ł���`�Ƃa�ЂƂ̌_��ɂ���Č��߂��Ă��邽��)�A��҂͍����̎s��̎����Ɣ�r���Ė��炩�ɍ������銄�����ł���(�����Ŗ@��̕]���z���Ⴍ�Ȃ��Ă��܂��A�[�Ŏ҂ɊÂ�����)�B ��R����n������18�N11��7������17(�s�E)6��(�����F�e)�c�c�N�����ƔN���Ƃ̎����I�E�o�ϓI�ȓ��ꐫ��_���Ƃ��A�u�����I�E�o�ϓI�ɂ�����̎��Y�Ɋւ��ē�d�ɉېł�����̂ł���v�Ƃ��āA�N���ɑ��鏊���ېł͏��łX���P��15���́u��|�v�ɂ���ċ�����Ȃ��Ƃ����B��������Ă��Ȃ����A���N�ȍ~���N���ւ̏����ېł����r�˂������̂Ɖ������B �����̔��_�c�c�u�Ⴆ�A�����ɂ��擾�������Y���ʎ��ł������悤�ȏꍇ�c���v�Ҍ������̍l�����ɂ��c�����c���v�i���n�����ʎ��̔��p�ɂ������j���A�����c�Ɉ��������c�B�c�ʎ��ɂ͈��̎���������c�ʎ����������p���Y�Ƃ���Ă��邱�ƂɏƂ炷�ƁA���Y�ʎ����瓾������v�́A���̌o�߂ɂ�铖�Y���Y�̉��l�̌����ƑΉ�����W�ɂ���c�B�c�ʎ��������ł̉ېőΏۂƂȂ����ꍇ�ł����Ă��A���̌�A���Y�ʎ����瓾������v�ɑ��A�����ł��ېł���邱�Ƃɂ��Ă͈٘_���Ȃ��v �T�i�R��������19�N10��25������18(�s�R)38��(�������p)�c�c�u�{���N���́A�{���N�����Ƃ��@�I�ɈقȂ��v�̂Łu�����Ŗ@�X���P��15������̔�ېŏ����ɊY�����Ȃ��v�B(���ɂ`�����������Ă����Ȃ�`���҂��������ɉېł���邱�ƂƂ̃o�����X����A�`�������ɂ������ʎ������ɂ��ď����Ƃ��ĉېł���Ƃ������ٔ����ɂ��ꕪ�̗�������) �ō��ٔ��|(�j�������E�����F�e)�@�����Ŗ@9��1��15(��16)�u���ɂ����w�����C�②���͌l����̑��^�ɂ��擾������́x�Ƃ́C�������ɂ��擾�����͎擾�������̂Ƃ݂Ȃ������Y���̂��̂��w���̂ł͂Ȃ��C���Y���Y�̎擾�ɂ�肻�̎҂ɋA�����鏊�����w�����̂Ɖ������B�����āC���Y���Y�̎擾�ɂ�肻�̎҂ɋA�����鏊���Ƃ́C���Y���Y�̎擾�̎��ɂ����鉿�z�ɑ�������o�ϓI���l�ɂق��Ȃ炸�C����͑����Ŗ��͑��^�ł̉ېőΏۂƂȂ���̂ł��邩��C�����̎�|�́C�����Ŗ��͑��^�ł̉ېőΏۂƂȂ�o�ϓI���l�ɑ��Ă͏����ł��ۂ��Ȃ����ƂƂ��āC����̌o�ϓI���l�ɑ��鑊���Ŗ��͑��^�łƏ����łƂ̓�d�ېł�r���������̂ł���Ɖ������B�v �@�u�N���̕��@�ɂ��x�������L�ی����i�N�����j�̂����L����������ɓ�������̂ɂ��ẮC[�����Ŗ@24���P]��1���̋K��ɂ��C���̎c�����Ԃɉ����C���̎c�����ԂɎ�ׂ��N���̑��z�ɓ�������̊������悶�Čv�Z�������z�����Y�N�����̉��z�Ƃ��đ����ł̉ېőΏۂƂȂ邪�C���̉��z�́C���Y�N�����̎擾�̎��ɂ����鎞���i���@22���j�C���Ȃ킿�C�����ɂ킽���Ď��ׂ��N���̋��z��푊���l���S���̌��݉��l�Ɉ������������z�̍��v�z�ɑ������C���̉��z�Ə�L�c�����ԂɎ�ׂ��N���̑��z�Ƃ̍��z�́C���Y�e�N���̏�L���݉��l�����ꂼ�ꌳ�{�Ƃ����ꍇ�̉^�p�v�̍��v�z�ɑ���������̂Ƃ��ċK�肳��Ă�����̂Ɖ������B���������āC�����̔N���̊e�x���z�̂�����L���݉��l�ɑ������镔���́C�����ł̉ېőΏۂƂȂ�o�ϓI���l�Ɠ���̂��̂Ƃ������Ƃ��ł��C�����Ŗ@9��1��15���ɂ�菊���ł̉ېőΏۂƂȂ�Ȃ����̂Ƃ����ׂ��ł���B�v �@�u�����Ŗ@207������̐����ی��_�Ɋ�Â��N���̎x��������҂́C���Y�N�������@�̒�߂鏊���Ƃ��ď����ł̉ېőΏۂƂȂ邩�ۂ��ɂ�����炸�C���̎x���̍ہC���̔N���ɂ��ē��@208������̋��z�����C����������łƂ��č��ɔ[�t����`�������̂Ɖ�����̂������ł���B �@���������āC�a�������{���N���ɂ��Ă�����������̋��z�̒����͓K�@�ł��邩��C�㍐�l�������ł̐\�����̎葱�ɂ����ď�L�������z���Z�o�����Ŋz����T�������͂��̑S���Ⴕ���͈ꕔ�̊ҕt���邱�Ƃ͋��������̂ł���B�v �ō��ق́A�������ɂ��擾�������Y�������炷�u�����v(���u���Y���Y�̎擾�̎��ɂ����鉿�z�ɑ�������o�ϓI���l�v)�̕���(�܂�1380���~�̕���)�ɂ��āA����9��1��16���ɂ�菊���ېł͋�����Ȃ��Ɣ����������A�ԐړI�ɁA2300�|1380��920(���~)���^�p�v�����ɂ��Ă̏����ېł͗e�F�����(�^�p�v�̕�������R�̔��f�ƈقȂ�)�Ɣ��f�������̂Ɨ��������B�����A�[�Ŏ҂̋t�]���i�ƌ��`���ꂽ���̂́A�����I�ɂ͔[�ŎҘZ�����i�A�l���s�i�̓��e�ł���B �{���ł͑����J�n���Ɏ��N��230���~�ɂ��Ă̎G�����ېł̐������_�ƂȂ�Ȃ������̂ʼn^�p�v�������Ȃ��������Ăł���A�ō��ق͉^�p�v�̌v�Z���@�ɂ��ĉ���q�ׂȂ������B���N�ȍ~�Ɏ��N��230���~�̂����A�ǂ̂悤�ɉ^�p�v�������v�Z����̂��A�Ƃ�����肪�c�����B ��Ȗ��_�c(1)�����̉^�p�v��F�����邩�H (2)�^�p�v������������ی����z���T���ł��邩�H ����22�N���ߑ�214���ɂ��������ŗ�183���`186���A�ی�2�|27(����22�N10��20��)�̏����35-4��2�y��35-4��3(����)�ɂ�荑�ł̈��������炩�ɂ��ꂽ�B (1)��0�N�ɑ������J�n��(���̎��_��230���~��邪��0�N�̉^�p�v��0�~)�A��1�N�`��9�N�ɂ����Ė��N230���~�����ۂ̉^�p�v�̌v�Z �N�x�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c_1_�b_2_�b_3_�b_4_�b_5_�b_6_�b_7_�b_8_�b_9_ �ʒB�ɂ��^�p�v�̌v�Z�̔��z�c�c028�b052�b074�b092�b109�b124�b136�b148�b158 ��I�����T�O�ɒ����ȉ^�p�v�c�c158�b148�b136�b124�b109�b092�b074�b052�b028 �@�ʒB�͎��̂悤�Ȕ��z�ʼn^�p�v���v�Z���Ă���B��P�N�x��230���~�̔N���́A��O�N�x�ɂ�����230/1.137��202�i���~�j�i�N����13.7���̑O��j�Ƃ��đ����ł̉ېŕW���ɎZ������Ă����̂ŁA��P�N�x�̉^�p�v�́A��O�N�x��202���~�𗘎q��13.7���i�N�����j�łP�N�ԉ^�p�������̂ƍl�����邩��A230�|202��28�i���~�j�ł���B��Q�N�x��230���~�̔N���́A��O�N�x�ɂ�����230/1.1372��178�i���~�j�Ƃ��đ����ł̉ېŕW���ɎZ������Ă����̂ŁA��Q�N�x�̉^�p�v�́A��O�N�x��178���~�𗘎q��13.7���i�N�����j�łQ�N�ԉ^�p�������̂ƍl�����邩��A230�|178��52�i���~�j�ł���B�ȉ����l�ɑ�R�N�x�����X�N�x�܂Ōv�Z����B�i�\�ł͖��~�ȉ��l�̌ܓ��̒[�������̃Y���̂��ߍ��v��920�ł͂Ȃ�921�ɂȂ��Ă���B�j �@��������I�����T�O�ɒ����ɉ^�p�v���v�Z����Ȃ�A���̂悤�ɍl������B���q��13.7���i�N�����j�ʼn^�p�������1380���~�����O�N�����X�N�ɂ����Ė��N230���~���������Ƃ��A�Ƃ�����Ɠ��l�ɏ����v�Z���邱�ƂɂȂ�B��O�N��1380���~����230���~�i�^�p�v������0�~�ł���j���������Ƃ����̂ŁA�c��1150���~�𗘎q��13.7���łP�N�ԉ^�p�����^�p�v158���~�i��1150���~�~13.7���j����P�N�̏����ł���B��P�N��230���~���������Ƃ��̂ŁA1150�{158�|230��1078�i���~�j���P�N�����Q�N�ɂ����ė��q��13.7���łP�N�ԉ^�p����B����Ƒ�Q�N�̉^�p�v��148���~�ł���B�ȉ����l�ɑ�R�N�x�����X�N�x�܂Ōv�Z����B �@��I�����T�O�ɒ����ɉ^�p�v���v�Z�����ꍇ�͑�P�N�����X�N�ɂ����ĉ^�p�v���������Ȃ��Ă�������A�ʒB�̔��z�ɂ��ƁA�^�p�v�͑�P�N�����X�N�ɂ����đ傫���Ȃ��Ă����B�P���ɍ��v�����920���~�i�\�ł͒[�������̃Y���̂���921�ɂȂ��Ă��邪�j�ł���B���������ɑ��z�̏������v�コ���Ɣ[�Ŏ҂ɕs���ł��邩��A�ʒB�̔��z�̕����[�Ŏ҂ɗL���ł���B�Ȃ��ʒB�̔��z�̕����[�Ŏ҂ɗL���Ȃ̂��B�ʒB�̔��z�́A�Ⴆ�Α�Q�N�x�ɂ��Č��Ă݂�ƁA��O�N��178���~�����q��13.7���i�N�����j�łQ�N�ԉ^�p���ꂽ�Ƃ����O��Ōv�Z����Ă���B��I�����T�O�ɒ����Ɍv�Z����Ȃ�A��O�N��178���~���Q�N�ԉ^�p�����ꍇ�ɑ�P�N�ɂ��������Ă��锤�̑����v�i178�~13.7����24�i���~�j�j���ېŏ����Ɋ܂߂Ȃ���Ȃ�Ȃ����A�ȕ֖@�̊�̍l�����́A��O�N��178���~�Ɋւ���P�N�ɂ͎������Ȃ��̂Ŕ�ېł̂܂܂Q�N�ԉ^�p����Ƃ����O��Ōv�Z���Ă���B���̂悤�Ɏ�����`��O��Ƃ��Ă���ȕ֖@�̊�̍l�����ɂ��v�Z�́A��I�����T�O�ɒ����Ȍv�Z�Ɣ�ׁA�[�Ŏ҂ɗL���Ȃ��̂ƂȂ��Ă���B �@�ʒB�͏\�{�̔N���������ɑ����Ă���B��I�����T�O�ɒ����ɍl����Ȃ�A�����J�n����1380���~�ƕ]�������N��������̎��Y�ƊϔO���Čv�Z���ׂ��ł���B���������s�����Ŗ@����I�����T�O�ɒ����ł͂Ȃ��������ɉېł��邱�Ƃ������Ƃ��Ă��邱�ƂƂ̋ύt����l����A�ʒB�̔��z�ɂ��ꗝ����B��ȏ͔@�E�@�w����2010�N11����45�ŎQ�ƁB (2)�`�̊����ی����z���T�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ƃ���ƁA�����ی����������^�C�v�̐����ی��N��(�Ⴆ�ΐϗ��̐��i����������)�Ɋւ��Ă͍ō��ٔ����ɂ�鈵�����]���̈���(����60��1���̑d�ő����̈��p�ɗނ��鈵��)���[�Ŏ҂ɕs���ɓ����\����������(�ō��ْ������͂����l���Ă����B[���]���������ی����z�̍T���s�̑O��ŕ]�߂������Ă��܂���)�B �����@�߁E�ʒB�ɂ��A�������ی��������z���A���{�Ԋҕ����Ɖ^�p�v�����ƂɈ�������ŁA�T���Ƃ��Ă���B���̌v�Z���@�Ȃ�A�ō��ٔ������[�Ŏ҂ɏ]�����s���ɓ����\���͂Ȃ��B�]���ĒN���i�ׂ��N���Ȃ��ł��낤�B([���]�������A����60��1��(�d�ő����̈��p)�ɗނ���ېł�˂������ƂƂ̐������������̂ł͂Ȃ����Ƃ̋^��͎c��B�X�ɁA�t�n�[�t�^�b�N�X�v���������E�Ŕ�����24�N1��13�����W66��1��1�ł��A���ҕ��S�̕ی����̍T����ے肵�����ƂƁA�����I�łȂ��\�����o�Ă���B)(����������E�Óc�F�v�E�W�����X�g1423��100�ňȉ��A104�ł��^���悷�B) �����ŁE���^�ł��ۂ��ꂽ�u�����v�����ɂ��āA�����ł��ۂ����Ƃ͋�����Ȃ��A�Ƃ����_�����˒��́H �c�c�����ɂ����Ē���̓��B�y�n�̊܂݉v�Ɋւ��Ă��A������(���炭���^�ł��j���ۂ��ꂽ�u�����v�����ɂ��āA�����ł��ۂ���邱�Ƃ����邪�A�܂�������60��1��������9��1��16���ɂ���ĕ��邱�Ƃ͍l�����Ȃ�(���������Ŗ@�̋K��ł��蓯�i�ł��邩��B�{���͏����Ŗ@�Ǝ{�s�߂Ƃ̊W�ŏ����Ŗ@���D�悷��Ɖ��߂������̂Ɨ����ł���)�B�����̎����������̔z�����̗��v�̊������݉��l�ł���Ƃ���ƁA�����������ɂ��̎����ɂ��đ����ł��ۂ��A�z������̎��ɏ����ł��ۂ����Ƃ��A�{���ō��ٔ���̎˒��Ɋ܂߂���\�����A�F���Ƃ͌����Ȃ��B�܂��A�������E���쌠���ɂ��Ă����l�̖�肪�c��B �@���݂܂ł̂Ƃ��딻��E�ٔ���͎˒������������Ă���i��d�ېł����e���Ă���j�B�y�n�܂݉v�ɂ��āA(�����n������25�N6��20������24(�s�E)243���E������������25�N11��21������25(�s�R)268��)�Ō�����27�N1��16���Ŏ�265������12588(�R�c��Y�E�W�����X�g1476��112-115��2015.2)���A�z���ɂ���(���n������27�N4��14����62��3��485�ŁE��㍂������28�N1��12������27(�s�R)85��)�Ō�����29�N3��9���Ŏ�267������12990�B �@�푊���l�`���ۗL���Ă����a���y�єz�����Ҍ��ɑ����ł��ۂ��A�`���S��̔z���ɂ��đ����l�w�������ېł��邱�Ƃ́A�����Ŗ@67����4���ېŌJ���̎�|�ł��邩��A�Ŕ�����22�N7��6���̎˒��O�ł���A���@�ł���c�c���n���ߘa3�N11��26���ߘa2(�s�E)137�����^1503��58�Ŋ��p�E��㍂���ߘa6�N1��18���ߘa3(�s�R)149����70��9��910�����p(�㍐�A�㍐�\��)(�d�Ŕ��ጤ����a�J��O2023�N1��20����)�B �����Ŗ@67����4�u���Z�҂���Z�\���ꍀ�e���i���^���ɂ��擾�������Y�̎擾��j�Ɍf���鎖�R�ɂ�藘�q�����A�z�������A�ꎞ�������͎G�����̊���ƂȂ鎑�Y���擾�����ꍇ�ɂ����铖�Y���Y�ɌW�闘�q�����̋��z�A�z�������̋��z�A�ꎞ�����̋��z���͎G�����̋��z�̌v�Z�ɂ��ẮA�ʒi�̒�߂�������̂������A���̎҂������������Y���Y�����L���Ă������̂Ƃ݂Ȃ��āA���̖@���̋K���K�p����B�v �����̓K�ۂ��ҕt�����̉ۂɊւ��āc�c(�P6��339��)�����f�Վ����E�Ŕ�����4�N2��18�����W46��2��77��(2.3.2.2.a.)�́A���^�x����(�Ⴆ�ΐ�Ȃ��ٗp���Ă��闧���w�@)�ɂ�錹���Ɍ�肪����ꍇ�A����120��1��5���E6���Ɋւ��A�뒥���Ŋz����(�Ⴆ�T�����[�}��������)�̐\���Ŋz����T�����邱�ƈ������ҕt�𐿋����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��A�Ɣ������Ă����B����Ɗ֘A���āA�{��(�Ŕ�����22�N7��6��)�ɂ����āA���ɔ�ېŏ����ł���Ȃ�A�����ی���Ђ������������Ƃ��뒥���ł���Ƃ���A�����l�ł���w������ҕt�𐿋����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ȃ�̂ł͂Ȃ����A�Ƃ�����肪���݂��Ă����B �@�ō��ق́A�x���҂���a�����ی���Ђ̌����`�����m�肵�A�������K�@�ł��邽�߂w������ҕt���������邱�Ƃ��������Ƃ����_����g�ݗ��Ă��B �@���̘_�����Ŕ�����4�N2��18���Ɩ������Ă���Ɗ���������Ƃ����Ȃ��炸����悤�ł��邪�A�`���I�Ɍ���������ύX�����Ă��Ȃ��̂ōŔ�����4�N2��18������������ł͂Ȃ��c�c���^���̎x����(�Ŕ�����4�N2��18��)�ƔN���̎x����(�Ŕ�����22�N7��6��)�Ƃ͕ʂł���Ƃ����_���ƂȂ�B���J���j�E�W�����X�g1410��28�ŎQ�ƁB��Ђ��������^���x���������������^�x���������ł������ꍇ�̌����Ŋz�̊ҕt�����ɂ��āA�Q�ƁA����u�łŃ�������ǂ�����i��4��j�`�Ŗ��Ɩ@���͎Ԃ̗��ց`�vcf. �k���L���� |
4.3. �������z�E�K�v�o��
4.3.1. �������z
4.3.1.1. �������z�̒�`(����36��)
����36��1���u���̔N�ɂ����Ď������ׂ����z(���K�ȊO�̕����͌������̑��o�ϓI�ȗ��v�����Ď�������ꍇ�ɂ́A���̋��K�ȊO�̕����͌������̑��o�ϓI�ȗ��v�̉��z)�v�c��F�����ʼnv��: ���n������24�N2��28����58��11��3913��(�����F�e�E�m��)�c���Ə��v�̎������z�s�Z����F�߂�(��26�N�����Ŗ@44����2���@�O�̏����36-17�Q��)����B�n�ӓO��E�W�����X�g1449��8��er����39����4.3.4.�A�t�����W�E�x�l�t�B�b�g��4.2.6.2.�A�N�x�A��(�u�������ׂ��v�̕����̉���)��4.4.2.�B
����64��2���@�ۏ؍����� 2���̑�\�I�����R�ٔ���ɗ��ӁB
(1)�D�y�n������4�N3��26���Ŏ�188��941�ŁE�D�y��������6�N1��27�����^861��229�ŏ�41��10��2637�Łc�u�����Ŗ@�Z�l��́A�ۏ؍��𗚍s���邽�߂̎��Y�̏��n���������ꍇ�ɂ����āA���̗��s�ɔ��Ȃ��������̑S�����͈ꕔ���s�g���邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ����Ƃ��́A���̍s�g�s�\�ƂȂ������z�ɑΉ����镔���̋��z�́A���Y�����̋��z�̌v�Z��A�Ȃ��������̂Ƃ݂Ȃ��|�K�肵�Ă���Ƃ���A���̎�|�́A�ʏ�A�ۏؐl�͕ۏ؍��𗚍s���邱�ƂƂȂ��Ă��C����҂ɑ��ċ��������s�g���邱�Ƃɂ��ŏI�I���S��Ƃ꓾��Ƃ̌��ʂ��̂��Ƃɕۏ،_������������̂ł��邪�A�ۏ؍����s�̂��ߎ��Y�����n���Ă��A����ɔ����ċ��������s�g�ł��Ȃ������Ƃ��ɂ́A���̌��x�Ŏ��Y���n�ɌW�鏊���ɑ���ېł������T���悤�Ƃ�����̂Ɖ������B���������āA�ۏؐl���ۏ،_��������ɁA���Ɏ���҂ɑ��ċ��������s�g���邱�Ƃ��s�\�ł��邱�Ƃ��m���ɔF�����Ă����Ƃ��ɂ́A���̎����͎���҂ɑ�����I�ɗ��v�����^������̂ɂق��Ȃ�Ȃ�����A�E��|���炵�ď����Ŗ@�Z�l���K�p���ׂ��ꍇ�ɊY�����Ȃ��v�B�i�k�����߁j
(2)�������ܒn������16�N4��14�����^1204��299�Ŋm��c�u�����Ŗ@�U�S���Q���ɒ�߂�ۏ؍��̓���̓K�p���邽�߂ɂ́A���̓I�v���Ƃ��āA�[�Ŏ҂��i�A�j���҂ɑ��č��҂̍���ۏ������ƁA�i�C�j��L�i�A�j�̕ۏ؍��𗚍s���邽�߂Ɏ��Y�����n�������ƁA�i�E�j��L�i�A�j�̕ۏ؍��𗚍s�������ƁA�i�G�j��L�i�E�j�̗��s�ɔ����������̑S�����͈ꕔ���s�g���邱�Ƃ��ł��Ȃ����ƂƂȂ������Ƃ��K�v�ł���A������ő����v�B�u�ۏ؍��̗��s���w�]�V�Ȃ������x���ł�ނɂ�܂ꂸ���Y�����n�����ꍇ�łȂ���Ȃ�Ȃ��Ɓv�����u�퍐�̎咣�͍̗p�ł��Ȃ��B�v�`�Ђ̍���ۏ��Ă����w���`�Б�\������ł����Ă��A�`�Ђ̎��Ɣp�~�́u��Ў��g�̔��f�ł���A����������Ē����ɕۏؐl�̔��f�Ƃ݂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�v
�����n������23�N11��11������22(�s�E)23��(�T�i�R������������24�N9��20���Ŏ�262������12041���|�j�c�����Ŗ@64��2���u�������v���s�g���鑊����ɂ́A�A�ѕۏؐl���܂܂��B
4.3.1.2. ��O�F��ېŏ���(����9��)
����9���̔�ېŏ����ɂ��Ă͐F�X�Ȏ�|������F�X�Ș_�_�Ɨ��ށB9��1��5�� �ʋΎ蓖 �y�� 6�� ���Ǝ�s�����t��4.2.6.2.�t�����W�E�x�l�t�B�b�g
9��1��9�� �����̗p�ɋ�����Ƌ�A�����ɕK�v�ȓ��Y �y�� 9��2��1�� ���n��������4.6.3.���v�ʎZ
9��1��10�� ����ٍς��邱�Ƃ�����������ł���ꍇiu
9��1��15�� �}�{�`���̗��s��4.1.3.�ېŒP��
9��1��17�� �����A�l����̑��^��COLUMN4-3�N�����������ی��N����d�ې�
9��1��18�� ��COLUMN4-4�ی����E���Q�������̔�ې�
��������t�ؕ[�@13���̂悤�Ȕ�ېŋK�������B�Ȃ��A���n�͉ېł����B(cf.���\��u�ꎞ�����ƎG�����v)
| ���ŕs���R�����ߘa3�N3��24���ٌ����(��)��2��46��(������)(�R�����i�u�C�K���t���͕K�v�o��̂Ȃ��G�����ł���Ƃ������ŕs���R�����ߘa�R�N�R���Q�S���ٌ��v2021.4.11(�X�V2025.1.10)�œ���\)�E���n���ߘa4�N12��22���ߘa3(�s�E)48���Ŏ�272������13795���p�E��㍂���ߘa5�N7��26���ߘa5(�s�R)15�����p�E�œ��ߘa5�N12��22���ߘa5(�s�q)375���s�� cf.�g���Y�u�ٔ����@67����2��1���Ɋ�Â��C�K���t���̉ېŏ�̎戵���ɂ��ā\�\���ŕs���R�����ٌ��ߘa3�N3��24���̌����\�\�v������w�@�ȑ�w�@���[���r���[17��80-102��(2022)�A���ԑ叇�u�i�@�C�K���������{���t������яC�K��O�����̔�ېŏ����Y�����v�V�E������Watch�d�Ŗ@No.186 (2024.7.19)�A�c�����u��ېŏ����Y�������߂���ߎ��̕�����v�Ŗ����ጤ��202��11-32��(2024) ���_1�{�����t���������Ŗ@��̊w�����ɊY�����邩(����) ���_2�{�����������z�������Ŗ@��̊w�����ɊY������(����) ���_3�{����p���G�����̋��z�̌v�Z��K�v�o��ɎZ���ł��邩(����) ���_4�{�����t�����ېŏ����ƔF�߂Ȃ����Ƃ�{����p��K�v�o��ƔF�߂Ȃ����Ƃ����@14��1���m���������n�ɔ����邩(����) ��R���|�@���_1�u�u�w���ɏ[�Ă邽�ߋ��t�������i�v�Ƃ́A�w�Z���̋���@�ւɂ����Ċw�p���̋���E�w�����邽�߂ɕK�v�Ȕ�p�i�w��j�ɏ[�Ă邽�߂ɋ��t�����������������̂Ɖ������v�B �u��{���t���́A���̋K��̕�����A�u�i�@�C�K�������̏C�K���Ԓ��̐������ێ����邽�߂ɕK�v�Ȕ�p�v�ɏ[�Ă邽�߂Ɏx��������̂Ƃ���Ă��邱�Ɓi��L�A�j�A�i�@�C�K���́A�i�@�C�K�ɂ����鋳��E�w���̑Ή��i���Ɨ����j�S���邱�Ƃ��Ȃ��A���̌o�ϓI����ɂ�����炸�ꗥ�Ɉ��z�̊�{���t���̎x�����A����������Ȃ��p�ɏ[�Ă邩�͑S�����R�ł��邱�Ɓi���A�j�A��{���t���̐��x�́A�o�ϓI�Ȏ���ɂ��w���i�w��j�S���邱�Ƃ�����Ȏi�@�C�K���̎x����ړI�Ƃ��ē������ꂽ���̂ł͂Ȃ��A�@���l�ފm�ۂ̏[���E������}��Ƃ��������I�ȖړI�Ɋ�Â��ē������ꂽ���̂ł��邱�Ɓi��L�C�j�A��{���t���̋��z�́A�i�@�C�K���̊w���i�w��j�Ƃ��Ăǂ̒��x�̔�p���K�v���Ƃ����ϓ_�ł͂Ȃ��A�i�@�C�K�������̐������ێ����邽�߂ɂǂ̒��x�̔�p���K�v���Ƃ����ϓ_����A�����I�ȗv���������܂��Č��肳�ꂽ���̂ł��邱�Ɓi��L�E�j�Ȃǂ̎�����w�E���邱�Ƃ��ł���B �@�����̎���𑍍�����ƁA��{���t���́A�@���l�ފm�ۂ̏[���E������}��Ƃ��������I�ȖړI�Ɋ�Â��A�C�K��O�`������������҂����Ƃ̂ł��Ȃ��i�@�C�K���̐�����S�ʂɏ[�Ă邽�߁A�g�r�����肹���Ɏx���������̂ł����āA�w���i�i�@�C�K�ɂ����鋳��E�w�����邽�߂ɕK�v�Ȕ�p�j�ɏ[�Ă邽�߂Ɏx���������̂Ƃ͂����Ȃ�����A�����Ŗ@��̊w�����ɂ͓�����Ȃ��v�B |
COLUMN4-4 �ی����E���Q�������̔�ې�(����9��1��17��)
����9��1��18��:�ی����E���Q���������͔�ې�fb��4.1.2.2.����51���A72���c�u�ی����A���Q�������v���ŕ�U����镔�����K�v�o��E�����T���Ɋ܂܂�Ȃ��B
���ŗ�30���i��ېłƂ����ی����A���Q���������j�u�@�����ꍀ��\�����c�c�ɋK�肷�鐭�߂Œ�߂�ی����y�ё��Q�������c�c�́A���Ɍf������̂��̑������ɗނ�������i�����̂��̂̊z�̂����ɓ����̑��Q�����҂̊e�폊���̋��z�̌v�Z���K�v�o��ɎZ���������z���U���邽�߂̋��z���܂܂�Ă���ꍇ�ɂ́A���Y���z���T���������z�ɑ������镔���j�Ƃ���B
�@��@���Q�ی��_��c�c�Ɋ�Â��ی����A�����ی��_��c�c�Ɋ�Â����t���y�ё��Q�ی��_�͐����ی��_��ɗނ��鋤�ςɌW��_��Ɋ�Â����ϋ��ŁA�g�̂̏��Q�Ɋ�����Ďx��������̕��т��S�g�ɉ�����ꂽ���Q�ɂ��x������Ԏӗ����̑��̑��Q�������i���̑��Q�Ɋ�����ċΖ����͋Ɩ��ɏ]�����邱�Ƃ��ł��Ȃ������Ƃɂ�����^���͎��v�̕⏞�Ƃ��Ď���̂��܂��B�j
�@��@���Q�ی��_��Ɋ�Â��ی����y�ё��Q�ی��_��ɗނ��鋤�ςɌW��_��Ɋ�Â����ϋ��c�c�����Y�̑��Q�Ɋ�����Ďx��������̕��т��s�@�s�ׂ��̑��˔��I�Ȏ��̂ɂ�莑�Y�ɉ�����ꂽ���Q�ɂ��x�����鑹�Q�������i�����̂������\�l���i���Ə����̎������z�Ƃ����ی������j�̋K��ɊY��������̂������B�j
�@�O�@�S�g���͎��Y�ɉ�����ꂽ���Q�ɂ��x�����鑊���̌������i���\�l���̋K��ɊY��������̂��̑��̑Ή����鐫����L������̂������B�j�v
���ŗ�94���i���Ə����̎������z�Ƃ����ی������j�u�s���Y�����A���Ə����A�R�я������͎G�������ׂ��Ɩ����s�Ȃ����Z�҂��鎟�Ɍf������̂ŁA�����Ɩ��̐��s�ɂ�萶���ׂ������̏����ɌW��������z�ɑ��鐫����L��������m�������v�⏞�n�́A�����̏����ɌW��������z�Ƃ���B
�@��@���Y�Ɩ��ɌW�邽�ȉ����Y�c�c�A�R�сA�H�Ə��L���c�c���͒��쌠�c�c�ɂ������������Ƃɂ��擾����ی����A���Q�������A���������̑������ɗނ�����́c�c
�@��@���Y�Ɩ��̑S�����͈ꕔ�̋x�~�A�]�����͔p�~���̑��̎��R�ɂ�蓖�Y�Ɩ��̎��v�̕⏞�Ƃ��Ď擾����⏞�����̑�����ɗނ�����́v�m2�����n
���ŗ�206��3���@�@�掵�\����ꍀ�̋K���K�p����ꍇ�ɂ����āA�����ɋK�肷�鎑�Y�ɂ��Ď������̋��z�́A���Y�����������̒��O�ɂ����邻�̎��Y�̉��z�i���̎��Y�����̊e���Ɍf���鎑�Y�ł���ꍇ�ɂ́A���Y���z���͓��Y�e���Ɍf���鎑�Y�̋敪�ɉ������Y�e���ɒ�߂���z�j����b�Ƃ��Čv�Z������̂Ƃ���B
��@�@��O�\�����i���n�����̋��z�̌v�Z��T������擾��j�ɋK�肷�鎑�Y�i�����y�ё�O���Ɍf������̂������B�j�@���Y�����̐��������ɂ��̎��Y�̏��n���������̂Ƃ݂Ȃ��ē����̋K��i���̎��Y�����Ɍf���鎑�Y�ł���ꍇ�ɂ́A���Ɍf���鎑�Y�̋敪�ɉ������ꂼ�ꎟ�ɒ�߂�K��j��K�p�����ꍇ�ɂ��̎��Y�̎擾��Ƃ������z�ɑ���������z�m�C���n�ȉ����n
| 6�Ł�211.05 �}���V�������ݏ����������E���n�����a54�N5��31���s�W30��5��1077��fe �����@�}���V�������݂ɔ����גn���Z�҂̑��Q��⏞���邽�߂Ɏx����ꂽ310���~�̈��������_�B ���|�@�u���ꂽ310���~�͑i�O�`�Ђ̃}���V�������݂ɂ��w�̎����Q���⏞����ړI�ƁA�}���V�������݂ɂ��Ăw�������邱�Ƃ��Ή��Ƃ���ړI�̑o���̎�|�ł���v�B�w�̑��Q��30���~���Ȃ��ƔF�肵�A310���~�|30���~�|40���~(�����̈ꎞ�����T��)���u240���~�����Ȃ��Ƃ��ېł�����ꎞ�������z�ɂȂ�B�v �ߔ[���̊ҕt���Z���ɂ��čŔ����a53�N7��17����24��11��2401�ŁA���������������Q�����ł͂Ȃ��ꎞ�����Ƃ��ꂽ�i�x�����Q���͎G�����j��Ƃ��čŔ�53�N6��23���Ŏ�101��578�ŁA���S�ی����͑��Q�̉ł͂Ȃ��̂ŏ����ł̉ېőΏۂƂȂ�Ƃ�����Ƃ��čŔ�����2�N7��17������1357��46��(�����p���E�W�����X�g984��206��) |
| �敨������Q�a���������E���É��n������21�N9��30������2100��28�ŕS�I7��35�i�ޗ�F������������22�N10��12���敨����ٔ���W61��59�Łj ���i�敨����ő��Q�������w�������i������ł���`����������Ђ�����a�����͔�ېŏ����ɓ�����B |
| ���C�u�h�A���Y���������E�_�˒n������25�N12��13������2224��31��fc �����C�u�h�A�̋��U�L�ڂɂ�芔�������̑��Q�������w�������C�u�h�A�Ƃ̘a���ɂ��擾�����������́A���ŗ�30���e���ɃX�g���[�g�ɂ͓��Ă͂܂�Ȃ��̂ŁA�[�Ŏ҂��~���_�����\�z����̂͑�ϓ���B �@��(1) 9�̔���(�������z)�A8�̎d��(�K�v�o��)�A1�̏�����\���B���̌�A�d�����̕s�@�s�ׂɂ��d���z���s����3�ނ�グ���Ă������Ƃ����o���A3�̑��Q��������������ꍇ�c�c���Q���������ېŏ����Ƃ���i9�|8�{0��1�j�ƁA�s�@�s�ׂȂ��肵�ꍇ�i9�|(8�|3)��4�j�Ƌύt�������B���̓�d�T����h�~���邽�߁A�K�v�o���U�^�̑��Q�������͔�ېŏ������珜�O�����i9�|8�{3��4�j�i���ŗ�30�𒌏����ʏ��j�B �@��(2) �G�����ɌW��5�̎������z�A8�̕K�v�o��ŁA�G�����ɌW�鏊����-3�i�܂葹���j�ł������ꍇ�A���v�ʎZ�ł��Ȃ��B���̌�A�d�����̕s�@�s�ׂɂ��d���z���s����3�ނ�グ���Ă������Ƃ����o���A3�̑��Q��������������ꍇ�c�c�s�@�s�ׂȂ��肹�ΎG������0�ł������i5�|(8�|3)��0�j�̂ɁA����3�̑��Q���������K�v�o���U�^�ł��邩���ېŏ������珜�O�����ƂȂ�ƁA�G�����ɂ��Ă�5�|8��-3�������v�ʎZ�ł��Ȃ�����ېŏ����ɗ^����e����0�ł�������3�����ېŏ����ɎZ������Ă��܂��A�s�@�s�ׂȂ��肵�ꍇ�Ƃ̋ύt���Ƃ�Ȃ��B����͔[�Ŏ҂ɍ��Ȍ��ʂƂȂ�B�������ǎd���Ȃ��A�Ƃ����l���������肦�Ȃ��ł͂Ȃ��B���Q�҂������͂�������3�̑��Q������������Ȃ��̂�����A����Ɣ�ׂ��3����邱�Ƃ��ł��������}�V�ł���Ƃ����l�������A���肦�Ȃ��ł͂Ȃ��B �@�������ٔ����́A����_��ς��Ĕ[�Ŏ҂��~�ς����B �@��(1)�y�ї�(2)��3�̑��Q��������������N�x�ɒ��ڂ��Ă��邪�A�G�����ɌW�鎑�Y���w�������N�x�ɂ����鏊��51��4�����ʏ��u�c�c���Q�������c�c�ɂ���Ă�镔���̋��z�c�c�������v�̉��߂ɍٔ����͒��ڂ����B�y8�̕K�v�o��i�s�@�s�ׂȂ��肹�ΕK�v�o���5�j�A3�̑��Q�������z�Ƃ����\���ł͂Ȃ��A�y8�̎d���̂���3�̎��Y�����A3�̑��Q�������z�Ƃ����\���Ƃ��A�y5�|8��0{���v�ʎZ�s��}�A+3�z�Ƃ����\���ł͂Ȃ��A�y5�|(8�|3)��0�z�Ƃ����\���Ƃ��āA�[�Ŏ҂��~�ς����i���ȏ��́u�����̉��l�̉����Ƃ������Y�����i����51��4���Q�Ɓj�̕�U�ł����ېŏ����ɓ�����v�Ƃ����L�q�����ǂ�ł������ł��Ȃ������Ǝv�����A�����̐���Ɋӂ݂������������������j�B �@�ٔ����́A���Ƃ��Ă��[�Ŏ҂��~���Ƃ����p����creative�ȉ��߂͂������B�A���A����͎G�����Ɋւ���d���������Ƃ������Y�ł��������珊��51��4���ŋ~�����Ƃ��ł������A�G�����Ɋւ���d�����ł���ꍇ�͖{�����̂悤�ȉ��߂̋Z�I���Â炵�Ă��[�Ŏ҂��~���Ȃ��A�Ƃ������E������B |
| �ٌ�m���������ޗ������E������������26�N2��12���Ŏ�264������12405����25(�s�R)70�� ���ޗ��ɂ��ē����̃^�b�N�X�A���T�[No.3155���ꎞ�����������Ă���i�Q�ƁF�����33-6�A34-1(7)�j���Ƃ������ɁA��������w�ٌ�m�����؎������̗����ނ��ɍۂ����ݐl����������i���ޗ��j���ꎞ�����ł���Ǝ咣�����B ���ق́A�K�v�o���U�����i�̂������������z��U���y�ѐV�������J�ݔ�p��U���j�����Ə����Ƃ��ꂽ�i��R�����n������25�N1��25������23(�s�E)736�����班���ύX���ꂽ�j�B ���̎����ō����̈ӌ����������������p���́A��p���v�Ή��̌����̋t�o�[�W�����Ƃ��āA���v��p�Ή��i�����̑���ł���l�����Y�t���Ă����ł͂Ȃ�����Ȃ͗ǂ��\�����Ǝv���j�Ƃ����l�����ɂ��A���Ə����ɌW��K�v�o����U��������͎��Ə����ɓ�����A�Ƃ������������Ă���B �^�b�N�X�A���T�[No.3155 �؉Ɛl�����ޗ�����������Ƃ� ���ޗ��́A���̒��g���玟��3�̐��i�ɋ敪����A���ꂼ�ꂻ�̏����敪�͎��̂Ƃ���ƂȂ�܂��B 1�@���Y�̏��ł̑Ή��⏞�Ƃ��Ă̐��i�̂��� �Ɖ��̖��n���ɂ���ď��ł��錠���̑Ή��̊z�ɑ���������z�́A���n�����̎������z�ƂȂ�܂��B 2�@�������z�܂��͕K�v�o��̕�U�Ƃ��Ă̐��i�̂��� �����ނ��ɔ����āA���̉Ɖ��ōs���Ă������Ƃ̋x�Ɠ��ɂ��������z�܂��͕K�v�o����U������z�́A���Ə������̎������z�ƂȂ�܂��B 3�@���̑��̐��i�̂��� ��L1�����2�ɊY�����镔�������������z�́A�ꎞ�����̎������z�ƂȂ�܂��B |
| ��Ô�T�������K�l�i���E������������2�N6��28���s�W41��6=7��1248�ŕS�I5��54�c�c�ዾ�y�уR���^�N�g�����Y�̍w��������тɎ��͌�����p���͏����Ŗ@73��2���y�����ŗ�207���ɋK�肷���Ô�ɓ�����Ȃ� ����73���i��Ô�T���j�u���Z�҂��A�e�N�ɂ����āA���Ȗ��͎��ȂƐ��v����ɂ���z��҂��̑��̐e���ɌW���Ô���x�����ꍇ�ɂ����āA���̔N���Ɏx�������Y��Ô�̋��z�i�ی����A���Q���������̑������ɗނ�����̂ɂ���Ă�镔���̋��z�������B�j�̍��v�z�����̋��Z�҂̂��̔N���̑��������z�A�ސE�������z�y�юR�я������z�̍��v�z�̕S���̌܂ɑ���������z�i���Y���z���\���~����ꍇ�ɂ́A�\���~�j����Ƃ��́A���̒����镔���̋��z�i���Y���z����S���~����ꍇ�ɂ́A��S���~�j���A���̋��Z�҂̂��̔N���̑��������z�A�ސE�������z���͎R�я������z����T������B �Q�@�O���ɋK�肷���Ô�Ƃ́A��t���͎��Ȉ�t�ɂ��f�Ö��͎��ÁA���Ö��͗×{�ɕK�v�Ȉ��i�̍w�����̑���Ö��͂���Ɋ֘A����l�I�̒̑Ή��̂����ʏ�K�v�ł���ƔF�߂�����̂Ƃ��Đ��߂Œ�߂���̂������B�v[3����] |
| ���n���ߘa4�N12��22���ߘa3(�s�E)48��(���p)�E��㍂���ߘa5�N7��26���ߘa5(�s�R)15��(���p)�E�œ��ߘa5�N12��22���ߘa5(�s�q)375��(�s��)(���ԑ叇�u�i�@�C�K���������{���t������яC�K��O�����̔�ېŏ����Y�����v�V�E������Watch�d�Ŗ@No.186 (2024.7.19))�c�c�����Ŗ@9��1��15���u�w���ɏ[�Ă邽�ߋ��t�������i�v��Y�� |
4.3.2. �K�v�o��
4.3.2.1. �K�v�o��̈Ӌ`�ƒ�`(����37��)
����37��(�K�v�o��)1���u���̔N���̕s���Y�����̋��z�A���Ə����̋��z���͎G�����̋��z�c�c�̌v�Z��K�v�o��ɎZ�����ׂ����z�́A�ʒi�̒�߂�������̂������A[1]�����̏����̑��������z�ɌW�锄�㌴�����̑����Y���������z�邽�ߒ��ڂɗv������p�̊z�y��[2]���̔N�ɂ�����̔���A��ʊǗ���̑������̏������ׂ��Ɩ��ɂ��Đ�������p�i���p��ȊO�̔�p�ł��̔N�ɂ����č��̊m�肵�Ȃ����̂������B�j�̊z�Ƃ���B�v�m2�����n[1]���ڔ�p�c�c��p���v�Ή��̌����c�c�@�l�Ŗ@22��3��1���ƑΉ�
[2]�Ԑڔ�p�c�c���m���c�c�@�l�Ŗ@22��3��2���ƑΉ�
[3]�@�l�Ŗ@22��3��3��(����)�ɑΉ�����K��͂Ȃ��B����51���A72���������I�ɋK�肷��(��4.6.2.)
�ٌ�m���۔���E������������24�N9��19������2170��20�Łc�c�x�o�ƋƖ��Ƃ́u���ځv�֘A����v���Ȃ��B
���[�^���[�N���u�N�����E���������ߘa���N5��22����65��11��1657�Łc�c�u���ځv�֘A�����Ȃ���p�̕K�v�o��Y������۔F�B
���n������30�N4��19���Ŏ�268������13144����27(�s�E)393���E�T�i�R��㍂������30�N11��2���Ŏ�268������13206����30(�s�R)59���c�c�O����̕K�v�o��Y������۔F�B�u�K�v�v�Ƃ͂����Ȃ��B
�i�ה�p�E�ٌ�m��p�̕K�v�o��Z���ۂɂ��čٔ���̌X���͒�܂��Ă��Ȃ��B
�ېŏ����̑i�ה�p�͊ҕt���Z���i�G�����j�̕K�v�o��ɓ����邩�c�c���ɁF�������{��x������24�N2��15����58��8��3073�ŁA�L����������24�N3��1����58��8��3045�ŁB
�ߔ[�ł̊ҕt���i��ېŏ����j�Ɗҕt���Z���i�G�����j�����߂����߂ɗv�����ٌ�m��p�̕K�v�o��Y�������A�ҕt���Z���ɑΉ����镔���ɂ��Ĉ��I�ɔF�߂��邩�c�c�ϋɁF������������22�N10��12���Ŏ�260������11530�敨����ٔ���W61��59�Łi��R�啪�n������21�N7��6���Ŏ�259������11239����19(�s�E)6���B���É��n������21�N9��30������2100��28�ŕS�I7��35�ɗނ�������c�c�敨������Q�a�����j�B
���ɁF�N���E���t�@�X�i�[�����E������������29�N12��6����64��9��1366�ŕ���29(�s�R)2���i��R�����n������28�N11��29���Ŏ�266������12940����27(�s�E)388���j�B
4.3.2.2. �Ǝ���E�Ǝ��֘A��(����45��)
����45��(�Ǝ��֘A��̕K�v�o��s�Z����)�u���Z�҂��x�o�����͔[�t���鎟�Ɍf������̂̊z�́A���̎҂̕s���Y�����̋��z�A���Ə����̋��z�A�R�я����̋��z���͎G�����̋��z�̌v�Z��A�K�v�o��ɎZ�����Ȃ��B�@��@�Ǝ���̌o��[�Ǝ���]�y�т���Ɋ֘A����o��[�Ǝ��֘A��]�Ő��߂Œ�߂���́m���ŗ�96���A�����45-2�Q�Ɓn
�@��@������(�s���Y�����A���Ə������͎R�я������ׂ����Ƃ��s�����Z�҂��[�t�����131���3��(�m��\���Ŋz�̉��[�ɌW�闘�q��)�c�c�̋K��ɂ�闘�q�łŁA���̎��Ƃɂ��Ă̂����̏����ɌW�鏊���ł̊z�ɑΉ�������̂Ƃ��Đ��߂Œ�߂���̂������B)
�@�O�@�����ňȊO�̍��łɌW�鉄�ؐŁA�ߏ��\�����Z�ŁA���\�����Z�ŁA�s�[�t���Z�ŋy�яd���Z�ŕ��тɈŖ@�c�̋K��ɂ��ߑӐŁm�O���̓n
�@�l�@�n���Ŗ@�c�c�̋K��ɂ�铹�{�����ŋy�юs��������(�s���ŋy�ѓ��ʋ斯�ł��܂ށB)
�@�܁@�n���Ŗ@�̋K��ɂ�鉄�؋��A�ߏ��\�����Z���A�s�\�����Z���y�яd���Z���m�Z�����n
�@���@�����y�щȗ��c�c���тɉߗ��m��4.3.3.�n
�@���@���Q�������c�c�Ő��߂Œ�߂���́m��COLUMN4-4�n�m��`�\�l�����n
�Q�@���Z�҂����^������Y�@�c�c��198��(���d)�ɋK�肷���d�G���͕s�������h�~�@�c�c��18���1��(�O�����������ɑ���s���̗��v�̋��^���̋֎~)�ɋK�肷����K���̑��̗��v�ɓ�����ׂ����K�̊z�y�ы��K�ȊO�̕����͌������̑��o�ϓI�ȗ��v�̉��z(���̋��^�ɗv�����p�̊z������ꍇ�ɂ́A���̔�p�̊z�����Z�������z)�́A���̎҂̕s���Y�����̋��z�A���Ə����̋��z�A�R�я����̋��z���͎G�����̋��z�̌v�Z��A�K�v�o��ɎZ�����Ȃ��B�m��4.3.3.�n�v�m3�����n
�s���Y�ɌW�鑡�^�ł͏����Ŗ@45��1���e���Ɍf�����Ă��Ȃ����l�̕s���Y�����ɌW��K�v�o��ɎZ������Ȃ��Ƃ������_�͑����̍ٔ���ň��肵�Ă���B���������R�t�������肵�Ă��Ȃ��B�c�c5�Ł�231.02���ݗp�y�n���^�����E��㍂������10�N1��30���Ŏ�230��337�ŕ���9(�s�R)6������㍂������29�N9��28����64��2��244��(�s���Y�����ɌW��K�v�o��Z�������^�łɊւ��ĔF�߂��邩�ɂ��A�۔F����Ƃ������_�͊T�ˋ��ʂ��邪�A���R�ɂ��Ă͎��ʂ��Ă��Ȃ��B���n������29�N3��15����64��2��260�ł��֘A���ɒ��ڂ��Ĕ۔F���A���̍T�i�R�͑��^�ł��s���Y���݂ɍۂ��s���ł͂Ȃ��i�����Ŕ����Α��^�ł͂�����Ȃ��j�̂ŕK�v�o��Z����۔F����)���r�B
�Ȃ��A6�Ł�222.06�S���t��������^����(�E�R����)�E�Ŕ�����17�N2��1������1893��17�ł̌�A�����37-5�ɒ�1���lj����ꂽ�B
�����37-5(�Œ莑�Y�œ��̕K�v�o��Z��)�@�Ɩ��̗p�ɋ�����鎑�Y�ɌW��Œ莑�Y�ŁA�o�^�Ƌ����i�o�^�ɗv�����p���܂݁A���̎��Y�̎擾���z�ɎZ���������̂������B�j�A�s���Y�擾�ŁA�n���ŁA���ʓy�n�ۗL�ŁA���Ə��ŁA�����Ԏ擾�œ��́A���Y�Ɩ��ɌW��e�폊���̋��z�̌v�Z��K�v�o��ɎZ������B
�i���j1�@��L�̋Ɩ��̗p�ɋ�����鎑�Y�ɂ́A�����A�②���͑��^�ɂ��擾�������Y���܂ނ��̂Ƃ���B
2�@���̎��Y�̎擾���z�ɎZ�������o�^�Ƌ��łɂ��ẮA49�|3�Q��
4.3.3. ��@�ȗ����E��@�Ȏx�o(����36�A37�A45��)
| 6�Ł�211.02���������@�ᔽ��������(������)�E�Ŕ����a46�N11��9�����W25��8��1120�ŕS�I7��33na �����E���_�@���������@�̐����߂��Ă����ꍇ�̗����̉ېłɂ��āB ���|�@�����F�e�B[4]���������@�̐������ߕ����̗����̂������������͉ېőΏۂƂȂ�Ȃ��B �@(���_�ł͂Ȃ����A[2]��@�łȂ������ɂ��Ă͖����ł����Ă����s���������ɏ����Ƃ��ĉېőΏۂƂȂ��4.4.1.������`) ���_�ł͂Ȃ���������X���p����镔���@[3]�������������ꂽ�ꍇ�ɂ��āu�������ߕ��������܂߂��A�����Ɏ��ꂽ���̗����E���Q���̑S�����ݎ�̏����Ƃ��ĉېł̑ΏۂƂȂ�v�B�u�ݎ�́A���������߂̗����E���Q�������Ă��A�@���ケ������ȂɕۗL�����Ȃ����Ƃ����邪�A���̂��Ƃ̌̂������āA�����Ɏ��ꂽ���ߕ������ېł̑ΏۂƂȂ蓾�Ȃ����̂Ɖ����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��v�Bev �ȉ���4�p�^�[���A�C��t���āB�i[1]�͋C��t���Ȃ��Ă悢���ǁj [1]�K�@�ȗ����Ŏ����� [2]�K�@�ȗ����Ŗ�����̎� [3]��@�ȗ����Ŏ����� [4]��@�ȗ����Ŗ�����̎� �����36-1(�������z)�u�@��36���1���ɋK�肷��u�������z�Ƃ��ׂ����z�v���́u���������z�ɎZ�����ׂ����z�v�́A���̎����̊���ƂȂ����s�ׂ��K�@�ł��邩�ǂ�������Ȃ��B�v ���a26�N�����148�́u�ꉞ���L�����ړ]������́v�ł��邩�ǂ����ɂ���ʁB���ʒB�͂��̋�ʂɋ����ĂȂ��B(���ʒB�͐ޓ����ƍ��\���Ƃ����)eu ���@�Ɉˋ�����A��@�����̕Ԋҍ����Ă��锤�ł���A��@�����̊z�ƕԊҍ��̊z�Ƃ͓���������A���E����Ώ����͗�̔��ł́H��4.4.3.�Ǘ��x�z�(6�Ł�232.03���������z���������E�Ŕ����a53�N2��24�����W32��1��43��)�Ƃ��[���֘A����B �����Ɏ����������ߗ�������Ɏ؎�ɕԊ҂��ꂽ�ꍇ�́H(��4.8.2.��2.3.2.2.b.) ����152��(�e�폊���̋��z�Ɉٓ������ꍇ���X���̐����̓���)�u�m��\�������o���A���͌���������Z�ҁc�c�́A���Y�\�������͌���ɌW��N���̊e�폊���̋��z�ɂ���Z�\�O���i���Ƃ�p�~�����ꍇ�̕K�v�o��̓���j���͑�Z�\�l���i���Y�̏��n���������s�\�ƂȂ��ꍇ���̏����v�Z�̓���j�ɋK�肷�鎖�����̑�����ɏ����鐭�߂Œ�߂鎖�������������Ƃɂ��A���Œʑ��@���\�O���ꍀ�e���i�X���̐����j�̎��R���������Ƃ��́A���Y���������������̗�������ȓ��Ɍ���A�Ŗ������ɑ��A���Y�\�������͌���ɌW���S��\���ꍀ��ꍆ�Ⴕ���͑�O������攪���܂��i�m�菊���\�����̋L�ڎ����j���͑�S��\�O����ꍆ�A��܍��A�掵���Ⴕ���͑攪���i�m�葹���\�����̋L�ڎ����j�Ɍf������z�c�c�ɂ��āA���@���\�O���ꍀ�̋K��ɂ��X���̐��������邱�Ƃ��ł���B���̏ꍇ�ɂ����ẮA�X���������ɂ́A�����O���ɋK�肷�鎖���̂ق��A���Y�����������������L�ڂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�v ���ŗ�274��(�X���̐����̓���̑ΏۂƂȂ鎖��)�u�@��S�\����c�c�ɋK�肷�鐭�߂Œ�߂鎖���́A���Ɍf���鎖���Ƃ���B �@��@�m��\�������o���A���͌���������Z�҂̓��Y�\�������͌���ɌW��N���̊e�폊���̋��z�c�c�̌v�Z�̊�b�ƂȂ������̂����Ɋ܂܂�Ă��������ȍs���ɂ�萶�����o�ϓI���ʂ����̍s�ׂ̖����ł��邱�ƂɊ�����Ď���ꂽ���ƁB �@��@�O���Ɍf����҂̓��Y�N���̊e�폊���̋��z�̌v�Z�̊�b�ƂȂ������̂����Ɋ܂܂�Ă������������Ƃ̂ł���s�ׂ��������ꂽ���ƁB�v �Œ�23��(�X���̐���)�u�[�Ő\�������o�����҂́A���̊e���̂����ꂩ�ɊY������ꍇ�ɂ́A���Y�\�����ɌW�鍑�ł��@��\�����������ܔN�i��Ɍf����ꍇ�̂����@�l�łɌW��ꍇ�ɂ��ẮA�\�N�j�ȓ��Ɍ���A�Ŗ������ɑ��A���̐\���ɌW��ېŕW�������͐Ŋz���c�c�ɂ��X�������ׂ��|�̐��������邱�Ƃ��ł���B �@��@���Y�\�����ɋL�ڂ����ېŕW�����Ⴕ���͐Ŋz���̌v�Z�����łɊւ����@���̋K��ɏ]�Ă��Ȃ������Ɩ������Y�v�Z�Ɍ�肪�������Ƃɂ��A���Y�\�����̒�o�ɂ��[�t���ׂ��Ŋz�c�c���ߑ�ł���Ƃ��B�m��E�O�����n �Q�@�[�Ő\�������o�����Җ��͑��\���i����j�̋K��ɂ�錈��c�c�����҂́A���̊e���̂����ꂩ�ɊY������ꍇ�i�[�Ő\�������o�����҂ɂ��ẮA���Y�e���ɒ�߂���Ԃ̖�����������O���ɋK�肷����Ԃ̖����������ɓ�������ꍇ�Ɍ���B�j�ɂ́A�����̋K��ɂ�����炸�A���Y�e���ɒ�߂���Ԃɂ����āA���̊Y�����邱�Ƃ𗝗R�Ƃ��ē����̋K��ɂ��X���̐����c�c�����邱�Ƃ��ł���B �@��@���̐\���A�X�����͌���ɌW��ېŕW�������͐Ŋz���̌v�Z�̊�b�ƂȂ������Ɋւ���i���ɂ��Ă������i�����Ɠ���̌��͂�L�����a�����̑��̍s�ׂ��܂ށB�j�ɂ��A���̎��������Y�v�Z�̊�b�Ƃ����Ƃ���ƈقȂ邱�Ƃ��m�肵���Ƃ��@���̊m�肵�����̗�������N�Z�������ȓ��v�m�ȉ����n �@�l�Ŗ@�Ɋւ����������@�ᔽ�����i�y�ђx�����Q���j���v���Z�����Ă������Ƃɂ��čX���̐��������p�������Ⴊ����c�c(�P6��380��)TFK�����i�����x�m�����j�E�����n������25�N10��30������2223��3�ŁE�T�i�R������������26�N4��23�����Z�@������2004��107�ŁB6�Ł�321.03�N�����B�X�����E�Ŕ��ߘa2�N7��2�����W74��4��1030�� cf.(�P6��123��)�x�m�d�H�����E�Ŕ����a38�N10��29������352��30��cs�c�u�Ŗ@�̌��n�ɂ����ẮA�ېł̌����ƂȂ��s�ׂ��A�����Ȗ@�߂̉��ߓK�p�̌��n����A�q�ϓI�]���ɂ����ĕs�K�@�A�����Ƃ���邩�ǂ����͖��łȂ��A�Ŗ@�̌��n����́A�ېł̌����ƂȂ��s�ׂ��W�����҂̊ԂŗL���̂��̂Ƃ��Ď�舵���A����ɂ��A�����ɉېł̗v���������݂�����Ă���ƔF�߂���ꍇ�ł��邩����A�E�s�ׂ��L���ł��邱�Ƃ�O��Ƃ��đd�łے������邱�Ƃ͉����W�����Ȃ��B�v�Ƃ̈�ʘ_�̉��A�I�풼�O�A��s�@��Ђ̍��c�ւ̈ڊǂ̉��Ɏ��ނ���������A�I���A�R���H���p�~�ɔ������ނ����ԉ�Ђ��錴���ɕ����������A��̔��������Z���~�]�i���ꂪ�펞�⏞�������ƂȂ�j���略������l���~�]�̌��x�ɂ����đ��E���A�����āu���̖@���{�s�O�ɐ펞�⏞�������ɂ��Č��ς����v�i�펞�⏞���ʑ[�u�@����j�Ƃ������Ăɂ����āA���ނ̔����Ƒ��E�Ƃ����ɖ��E���@�̌����ȉ��ߓK�p�㖳���Ƃ���铙�̏ꍇ�ł��A�ېŏ������������ҊԂŗL���Ƃ��Ď�舵���A�����ɑ��E�ɂ�錈�ς��Ă����ƔF�߂������A�펞�⏞���ʐł��ۂ����Ƃ��������Ƃ�������c�c���q�G���n�ߊw�E�͂��̍ō��ٔ�������悤�Ƃ��Ă������A�эL�_�o�O�ȕa�@����(��q)���A�ߔN�A���p���͎Q�Ƃ���邱�Ƃ������Ă���B �эL�_�o�O�ȕa�@�����E������������23�N10��6����59��1��173�ł̈�R�E�����n������22�N12��17����59��1��186�ł��Ŕ����a38�N10��29�����Q�Ɓc�c�l�a�@�������s���Ȑf�Õ�V�ɂ��Č��N�ی��@�E�������N�ی��@�E���ی��@�Ɋ�Â��Ԋҍ����������X�ɉ��Z�����ۂ��ꂽ���ĂŁA�Ԋҍ��̐������_(���������_)�ł́A�܂����Z���ɂ��ẮA�K�v�o��Z�����F�߂��Ȃ�(�����Ŗ@37��1���A45���A51���A���ŗ�98���A141��)�B �������UNIKE�����E�����n������28�N7��19����63��8��2001�ŕ���26(�s�E)498��(�������p)�E������������29�N1��19����63��8��2059�ŕ���28(�s�R)291��(�T�i���p)(�ݓc��v�u�����g���_��Ɋ�Â����v�̕��z�̌����K�p�̉ۂɂ��āv�W�����X�g1512��135-138��)���Ŕ����a38�N10��29�������p�c�c�����g���_��Ɋ�Â����v���z���������Z�Ɋ�Â���@�Ȃ��̂ł������i�^���͏o���̕����߂��Ƃ����ׂ����̂ł������j�ꍇ�̌����`�����m�肵���B �������q�����E���É��n���ߘa6�N4��22���ߘa5(��)1522���c�c���\�A���\�A�����Ŗ@�ᔽ�̎����B�N�i��ɂ����āu�����ɏ����������Ă���ƔF�߂������A�ېł̌����ƂȂ����s�ׂ������Ȗ@�߂̉��ߓK�p�̌��n����q�ϓI�]���ɂ����ĕs�K�@�E�����Ƃ���邩�ǂ����͖��ł͂Ȃ��A���Y�����ɑd�łے������邱�Ƃ͉���W�����Ȃ��v�Ƃ��čŔ����a46�N11��9���ƍŔ����a38�N10��29�����Q�Ƃ���B�Ȃ��A���É������ߘa6�N9��30���ߘa6(��)170���j�������ƂȂ��Ă��邪�ېŕ����͕ύX����ĂȂ��B |
| 6�Ł�231.03 �����s���c��n���������E�����n�����a48�N6��28���s�W24��6=7��511��nb �����E���_�@��Ɩ@�ᔽ�̑㗝��V���x�������ꍇ�ɏ���37�����K�v�o���Ƃ��ĔF�肳��邩�B �y�n�̏��n���������̂�����s�Ȃ�ꂽ�ɂ����Ȃ��̂��A�ېŏ�������i�ׂ̐R���Ώۂ͉���(���i�ו��F3.2.4.2.)�A���Ə����̈Ӌ`�͉����A�Ƃ������l�X�Ș_�_������Ă���A�ꗱ�ʼn��x�������������ĂƂ�����B ���|�@���z��`�����_��`�c�u�ېŏ�������i�ׂ̐R���̑Ώۂ́A�ېŒ��̌��肵���������z�̑��ۂ��̂��̂ł���A�����̎咣�����̓I��@���R�ł͂Ȃ��v�u�ېŒ��͑i�ׂ̉ߒ��ɂ����āk�����l�����l������Ȃ������V���Ȏ����ł��A�E�����𐳓��Ƃ��闝�R�Ƃ��Ď咣���邱�Ƃ͉\�ł���v �{�����_�����@�u�E�@���Ɉᔽ�����V�_������@��̌��͂�����͖��ł���Ƃ��Ă��A�����ɉE�@������̕�V�z�ȏ�̂��̂��x����ꂽ�ꍇ�ɂ��A�����Ŗ@��͉E�����Ɏx����ꂽ���z���o��(�E��V�̎x�������s���Y����Ǝ҂ɂ��Ă͏���)�Ƃ��ĔF�肷�ׂ��v ����45��(�Ǝ��֘A��̕K�v�o��s�Z������4.3.2.2.) 1��7���������c�c�����ېł̗��_���猾���A�������A�K�v�o��̐���(ex.���Ԉᔽ)������Ă���Ȃ�A�{���͏�������T�������ׂ��ł���(����͈�@�Ȏx�o�Ɋւ����f�ٔ���̒ʂ�ł���)�B�������A�����̍T����F�߂�ƁA�����̌��ʂ��ŗ���������܂�B�Ⴆ�A���E�ŗ�40%�̔[�Ŏ҂ɂ�100�̔����̍T�����F�߂���ƁA100�̔������Ȃ������肪�o�ϓI���S�Ƃ��Ă�60�ɂƂǂ܂��Ă��܂��B �@����45��1���e�����Ꭶ�K��Ȃ�A��L�̎�|����ʉ�������̂Ƃ��āu����(public policy)�̗��_�v(45����ސ����߂��Ă���)�Ɍq����B������45��1���e����������ł���A���ߘ_�Ƃ��Ă͖���������B (�ނ��A�����܂Ōo������O��Ƃ��Ă������A�ٔ��ł͌o��̗L�������R�Ɍ���������ꂦ�悤�c�c���ɖ\�͒c�Wey) �@cf. �A�����J�@�ł�IRC ��162(a)���uordinary and necessary�v�ƒ�߂Ă������œ��{�̏����Ŗ@37��1���́u�K�v�v�Ƃ��������Ă��Ȃ��A�Ƃ����Ⴂ������B �@����45��2��ex�̐����c�d�G�͌o��̐���������������Ȃ����c�c�����ᔽ�H��̉ېʼn\���H �@�@�l�łɂ��Ă͕ʘ_�̗]�n����B��5.2.3.5.b.�A6�Ł�323.03�G�X�E�u�C�E�V�[�����E�Ō�����6�N9��16���Y�W48��6��357�� |
4.3.4. �A������
�A������(imputed income)�̓T�^��ł����A���ƒ�imputed rent�̗�Q�ƁB�ƒ��(��4.1.3.�ېŒP��)�b�͎���A�`���a�ɉƂ�݂��A�Ƃ�����ŁA�a�̒����x���͍T������Ȃ����a�̒�����500���~�Œ����x�o��120���~�ł��ېŏ�����380���~�Ɍ��炸500���~�̂܂�(�g�}�g���Ă��ېŏ���������Ȃ��̂Ɠ���)�B
�A���ƒ���ې�(�ېł��Ă����Ƃ��ăI�����_fa)�������炷�����̐��l��Q��ez�B
�a�̎x���ƒ��̍T����F�߂Ăa�E�b�Ԃ̒�������}��ƁA�ǂ̂悤�Ȕ������V���ɐ����邩�H�v�l�@�B
�����̊ϓ_�ŋA������(�s�ꉿ�i�ŎZ��)�͎Z�肳��邱�Ƃɗ���(�������̊ϓ_�Ɨ]�Ɂ�COLUMN4-2)�B
���ƘJ���̗�Ƃ��Ĕ���铙��z�N����B(���@���Ή�)
���Ə����ɂ��Ă͗��@�Ή��ς݁B
����39���i���ȉ����Y���̎��Ə���̏ꍇ�̑��������z�Z���j�u���Z�҂����ȉ����Y�c�c���Ǝ��̂��߂ɏ�����ꍇ���͎R�т̂��ĉƎ��̂��߂ɏ�����ꍇ�ɂ́A���̏�������ɂ����邱���̎��Y�̉��z�ɑ���������z�́A���̎҂̂��̏�������̑�����N���̎��Ə����̋��z�A�R�я����̋��z���͎G�����̋��z�̌v�Z��A���������z�ɎZ������B�v
����4��5��1���u�l���Ǝ҂��I�����Y���͒I�����Y�ȊO�̎��Y�Ŏ��Ƃ̗p�ɋ����Ă������̂��Ǝ��̂��߂ɏ���A���͎g�p�����ꍇ�ɂ����铖�Y����͎g�p�v�u�́A���ƂƂ��đΉ��čs��ꂽ���Y�̏��n�Ƃ݂Ȃ��B�v
����28��3��1���u��l���܍���ꍆ�Ɍf�������͎g�p�@���Y����͎g�p�̎��ɂ����铖�Y����A���͎g�p�������Y�̉��z�ɑ���������z�v�u�����̑Ή��̊z�Ƃ݂Ȃ��B�v
4.4. �����̔N�x�A��(�^�C�~���O)
4.4.1. ������`(cash method)��������`(accrual method)
�����Ŗ@36��1���F�������z(���v)�@37��1���F�K�v�o��(��p) (��O�̌�����`:����67��1��)�@�l�Ŗ@22��2���F�v��(���v)�@22��3���F����(��p)
(�l)�����ł̌v�Z���Ԃ͗�N(1��1���`12��31��)�ł��邪�A�@�l�ł̌v�Z���Ԃ͎��ƔN�x�Ɉˋ����A�@�l�ɂ���ĈقȂ�B�����N3����(4��1���`3��31��)�Ƃ��������ƔN�x���Ƃ�@�l�������B���������z(�@�l�Ȃ�v��)�E�K�v�o��(�@�l�Ȃ瑹��)�����Ă�ׂ����A���N�x�A���̖��B
�����̔N�x�A�����Ȃ����ƂȂ�̂��B
���:�Ŗ��s���̈���E�\���\���Ƃ����v��
���:�o�ϓI���̂Ƃ��Ă��L���s��������c�c(1)�ېŌJ���E(2)�K�p�ŗ��E(3)���v�ʎZ���̖��B
4.4.2. �����m���`(����36��)
����36��1���u���̔N�ɂ����Ď������ׂ����z�v�������m���`���̗p�B�@��22��2���u�v���̊z�ɎZ�����ׂ����z�́c����c�ɌW�铖�Y���ƔN�x�̎��v�̊z�Ƃ���B�v
���_�͉ߌ�[���̊ҕt�����E�s�������ԊҐ����ɂ��Ăł��邪�A6�Ł�232.01�G�����ݓ|���s�������ԊҐ��������E�Ŕ����a49�N3��8�����W28��2��186�ŕS�I7��102fi(cf.2.2.1.1.d.)�c�c�u���̔N�ɂ����Ď����������z�v(������`�I���z)�ƋK�肹���u�������ׂ����z�v�Ƃ����@�I�����W�ɒ��ڂ����K������Ă��邱�Ƃ���A�����Ƃ��āu�����̌������錠�����m��I�ɔ��������v���_���u�����̎����v�����Ɖ����Bfg fh
| (����57����3:�O������̊��Z�b66��:�H�������b67����2:���[�X��� ��) |
| �����ƐE���w�����@�ސE�蓖���������E�����n������29�N1��13���Ŏ�267������12954����27(�s�E)448��(���p)�E������������29�N7��6���Ŏ�267������13032����29(�s�R)41��(���p�A�m��)(�����S���E�W�����X�g1552��124�ŁA�c�������E�Ŗ@�w581��249��)�c�c�u�����̎������Ȃ��Ă��C�����ƂȂ�ׂ��������������錴���ƂȂ鎖���W���O�Ϗ㑶�݂��C���C���Y������@����s�g���邱�Ƃ��ł��C���������̉\�����q�ϓI�ɔF�����邱�Ƃ��ł����ԂɎ������Ƃ��́A�������m�肵���v�Ƃ���B�W�����ł���������Ă���ꍇ�A�����̎���������Ɣ��f�����B��232.03���������z���������E�Ŕ����a53�N2��24���̌����_(�ٔ��m�莞)���ꗂ��Ă���悤�Ɍ�����̂ŗ�������������B����͂Ƃ�������͗p���Ă��Ȃ�(�̂Ŗ��Ԋ�Ƃł��������_�ɂȂ肻��)�B |
| �����n���ߘa4�N8��31���ߘa2(�s�E)502���Ŏ�272������13749(���p)(�⊪���]�E�W�����X�g1589��10��)�E���������ߘa5�N5��24���ߘa4(�s�R)280���Ŏ�273������13852(�T�i���p)�c�c����26�N�AX��(�����A���Z��)���X�C�X�@�l�����s(Bank Julius Bear)�Ɠ�����C�_�����������B��s�͖{�����(�O���ʉ݂ő��̊O���ʉ݂�L���،����擾������)���s�����B�{������ɌW�鏊����X���͕���26�N�A27�N�̊m��\���Ɋ܂߂Ă��Ȃ������B�Ŗ������́A�{������ɂ��X���ɏ���(�ב֍����v)���������Ƃ̑O��ōX���������������B ���|�u�{���e����ɌW��ב֍����v���{���e����ɂ���ĐV���ɓ�����o�ϓI���v�ł���Ƃ����邩�ɂ��Č�������ɁA�O��������s�������Z�҂̏����̋��z���v�Z����ɓ������ẮA���Y�O��������s�������ɂ�����בփ��[�g�ɂ��A���Y�O������̋��z���~���Z���邱�ƂƂ���Ă���i�����Ŗ@�T�V���̂R��P���j�Ƃ���A�{���e����́A��������O���ʉ݂Ŏx�����s�������ł���A�O������ɊY�����邱�Ƃ��炷��ƁA�{���e����ɂ���ĐV���Ɍo�ϓI���v��������Ƃ����邩�ۂ��ɂ��Ă��A���̉~���Z�z�ɂ���Ĕ��f���ׂ����ƂɂȂ�B�����āA�{���e����O��̏��~���Z�z�Ɉ��������Ă݂�ƁA�@����O���ʉ݁i�`�j�ɂ�葼�̎�ނ̊O���ʉ݁i�a�j���擾�������ɂ��ẮA���Y���̎�ނ̊O���ʉ݁i�a�j�̎擾���z�̉~���Z�z���瓖�Y�O���ʉ݁i�`�j�̎擾���z�̉~���Z�z���T���������z���A�A�O���ʉ݂ɂ��L���،����擾�������ɂ��ẮA���Y�L���،��̎擾���z�̉~���Z�z���瓖�Y�O���ʉ݂̎擾���z�̉~���Z�z���T���������z�����ꂼ�ꐳ�̒l�ł���Ƃ��́A���̎���ɂ���āA�V���Ȍo�ϓI���v������ꂽ���ƂɂȂ�A�����������邱�ƂɂȂ�B�v |
������`�����z�ł��邪����������(�܂݉v�E�܂ݑ�)��F�����Ȃ����R(������`���̂闝�R)
| (Cf.��Ж@�ɂ�����l���A��Ɖ�v�ɂ�����l���͕ς���Ă���) |
�]���̖��y�є[�Ŏ����̖�肪�������Ƃ��ɂ́A������`�łȂ�������`���̂��Ă悢�̂ł́H
���@�l�Ŗ@�ŁA�����ړI�L���،����A�ꕔ�̎���Ɋւ��A������`(��5.2.2.3.d.)
�ʏ�A�y�]���̖��A�y�є[�Ŏ����̖��z����y������`�����z�������ۂ͎�����`�z���������B
�]���̋��ȏ��I�����F�ېŃx�[�X�͕�I�����T�O�B�ېŎ����ɂ��Ă͎��s�̍l�����������`�B
[���]���s��̗��R�����ł͐����s�[���ł��낤�B�ېŌJ���̗��v(��q)��ł��������߂̉ېŋZ�p�͊w����F�X��Ă���Ă��邪�ꕔ�ł����i�A�����J�ɂ�����OID���[�����c�c�w�����͕�����Ȃ��Ă悢�j�̗p����Ă��Ȃ��B������`���̗p����Ȃ��̂́A(1)(2)�̗��R�ɉ����āA(3)�l�X�̏���(�̔F������)�ɂ��Ă̊��o���e�����Ă���̂ł́H(��4.4.5.�����T�O�ƔN�x�A���Ƃ̊W)
�ېŌJ����(4.3.4.�Ō�q)�A���v�ʎZ(4.6.3.:����69��)�A�ŗ��ύX������ꍇ�̒Ⴂ�ŗ��̔N�x��_���������ȂǁA����\���͔[�Ŏ҂ɉېŏ�̗��v�������炵����B
COLUMN4-5 �N���X��������v�㎖��
| 2�Ł�411.01�N���X��������v�㎖���E���ŕs���R��������2�N4��19���ٌ��E�ٌ�����W39�W106�� �N���X����c�����ċ�(���肽�Ă��傭)�Ɣ����ċ�(�������Ă��傭)�Ƃ�������(����)�A�����ʁA���P���A�������z�Őݒ肳�ꂽ�敨����B���鏤�i(�Ⴆ�ΐΖ�)��50�Ŕ���Ƃ���������50�Ŕ����Ƃ����������o���A�K���ǂ��炩�������������Е�����������B�Ⴆ�Ύs�ꉿ�i��35�ł�������50�Ŕ���Ƃ����|�W�V�����͓��ł��邵50�Ŕ����Ƃ����|�W�V�����͑��ł���B�������A���蒍���E�����������o�����߂̎萔����������̂ŁA���v�ł͕K����������B �����E���_�@�w����ꊔ���̓�������̔���t��������t���𒍕����A����t���ɌW�銔���ɂ��Ēl����������݉��������B�w�͂��̔��p�����G�����̋��z�̌v�Z��T�����悤�Ƃ������A�F�߂��邩�B �ٌ��v�|�@������s���R���s�����A�Ƃ����咣�ɑ��āc�c�u�m���Ɂc�s���v�Ȏ���ł��邱�Ƃ͔ۂ߂Ȃ����A�c�{�����p���̊z�́A�ۗL���Ă��銔�����擾���z�ȉ��ɒl�����肵�����Ƃɂ���Đ��������̂����݉������������ł����āA�����ɑ��݂������̂ł���A�Ӑ}�I�ɍ��o�������̂ł͂Ȃ�����A�{������ɂ���Č��ʂƂ��đ�����������Ƃ��Ă��A����������Ė{��������o�Ϗ�s���R�A�s�����Ȃ��̂Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B�v �d�ł̕��S���y������ړI�������Ă��悢�B �����ېł̎咣�ɑ��āc�c�u�����ɂ����]�����̌v���F�߂Ă��Ȃ��̂́A�l�̔C�ӂɂ䂾�˂���]�����̂悤�����������F�߂�ƁA�������z�����ӓI�ɎZ�肳��邨���ꂪ���邩��ł���v����ŁA�u�����̎���ɂ���Ĕ������v������������m�肳���邱�Ƃ�ے肷�ׂ������͂ȁv���B�{���̏ꍇ���u�]�����Ɠ������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�v �d�ʼn���s�ׂƂ��F�肵�������B �l�@ �{���̎����ʂ��Ăw�̌o�ϓI�|�W�V�����͕ω����Ă��Ȃ����Ƃɗ��ӁB �@���ٌ̍��̎˒����z��ҊԎ���ɂ��y�Ԃ��H�[�Ŏҁ^�ېŒ����ꂼ��̗���Ŏ咣���l����ׂ��B����157��(������Ђ̍s�v�Z�̔۔F)�̂悤�ȑd�ʼn��۔F�K��A���͏���56��(�Ƒ�����p�۔F��4.5.2.)�̂悤�ȌʓI�۔F�K�肪�A�K�p�ł��邩�A�l����ׂ��B�[�Ŏ҂̎咣���鎄�@��̖@���\�������ېŒ��E�ٔ������ے�ł��邩�A�l����ׂ��B(�ٌ��̂����u�s���R�E�s�����v�̍L���Ƃ́H) �@�A�������̂��@�l�̏ꍇ�́u���p���Ȃ��������̂Ƃ��Ď�舵���v(�܂葹���̑��������͑ʖ�)�Ƃ���Ă���(�@���2-1-23��4:���p�y�эw���̓����̌_�̂���L���،��̎��)�B�@�l���ʒB�ɕ�������������̂ł���A�i�ׂ���A�Ƃ������ƂɂȂ낤���B |
| 2�Ł�411.02�X�g���h���ېŌJ�������E���ŕs���R��������2�N12��18���ٌ��E�ٌ�����W40�W140��ne �����E���_�@�w(�������)���A���⊔���̐敨����ɂ����ăN���X������s�Ȃ��A���a63�N1�����ɑ������v�シ�����A���Ύ�����������ċʂɂ��ė����ƔN�x�Ɍv�サ�悤�Ƃ����B�x�́A���Δ����̑����鎖�ƔN�x�ɑ������v�シ�ׂ��ł���Ƃ����B �ٌ��v�|�@�u�����̔������Ă������̌��ċʂɂ��Ď�d���������������ł͎�������������Ƃ͂������A���v�̔������Ă��錚�ċʂɂ��Ă���d���������ď��߂đS�̂̑��v���m�肷����̂Ƃ����ׂ��ł���B�v �l�@ �����ċʂƔ����ċʂƂ��ʂ̎��Y�ƌ��邩��g�ƌ��邩�H �@�x�̎咣�F�X�g���h������́u��ʓI�Ɍo�ϐl�̎���Ƃ��Ă͕s���R�A�s�����v�B�������ϓ���̈��p�͋����Ȃ��B(�����ċʂƔ������ċʂƂ����̎��Y�ł��邱�Ƃ͑O��Ƃ��Ă���) �@�ٌ��̍\���F�����ċʂƔ����ċʂ͈�̂ł���u���v�̔F�������҂𑍍����čs�Ȃ��ׂ��v�B �@��g�̂��̂ƌ������R�c�c��U��ړI�Ƃ��Đݒ肳��Ă��邱�ƁB�ނ��A��g�̂��̂ƌ��邱�Ƃ̂ł��Ȃ��ꍇ�Ɩ{���Ƃ��ǂ���ʂ��邩�ɂ��Ăٌ͍��͘_���Ă��Ȃ��B �@[���]�������ǂݎ��A�u���X��d���������ׂ��v���ۂ��A����ł��낤���Hfl |
4.4.3. �Ǘ��x�z�
| ��232.03���������z���������E�Ŕ����a53�N2��24�����W32��1��43�ŕS�I7��67nd ���|�@�����Ƃ��ĉېł����̂́A�����Ƃ��āu�ٔ����m���������v�����A��O�Ƃ��āu�W�����ł����Ă��c���łɋ��������A�����̎������������ƌ��邱�Ƃ��ł����Ԃ��������Ƃ��v[����͊Ǘ��x�z��Ƃ����\����p���Ă��Ȃ��B] �㋉�R�ŕ������ꍇ�u�X���̐����ɂ��~�ς��邱�Ƃ��ł���v��2.3.2.2.b.�Œ�23��2��1���c�㔭�I���R�Ɋ�Â��X���̐����A��4.3.3. ��211.02���������@�ᔽ�������� �l�@ �������z���������`�����Ɖ�����Ă���A���@��A�ݎ���ӎv�\���݂̂Ō��ʂ���������(������ɒ������z�̈ӎv�\�������B�������_)�B�������؎傪�������ꍇ�ɂ́A�Ŗ���͌����Ƃ��āu�ٔ����m�肵�����v�܂ő҂ƍō��ق͏q�ׂ�(�`�����Ƃ����ǂ����ۓI�Ȏ����̐��������ł͏����̎����Ƃ����ɂ͕s�[���ł���)�B�{���͍X�ɂ��̌�������O����O�I�Ȏ���Ƃ����ʒu�t���ƂȂ�B �@�Ǘ��x�z����̂̊�Ƃ��Ă̞B�����A�y�сA���鎖�Ăɂ����Č����m���`�Ɉˋ����ׂ����Ǘ��x�z��Ɉˋ����ׂ����̐U�蕪���̊�̞B���������邪�A����ł��A�Ǘ��x�z��Ɉˋ����ׂ����Ԃ̑��݂͔ے肵�������B�������A�Ǘ��x�z��̓K�p�͈͂��݂���Ɋg�債�Ă͂Ȃ�Ȃ��Ɛ������Bfm �@�Ȃ��A���������牽�ł�����ł����������ƍl���Ă͂����Ȃ��B�O����Ƃ��ď������ׂ��ꍇ������B�Ⴆ��2020�N4���`2021�N3�����̎Z�Տm�̌��ӂ�2020�N�ɑS�Ď�̂����ꍇ�ł�2021�N1���`2021�N3�����̌��ӂ�2021�N�x�̎������z�Ƃ��Ĉ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���^���쐿������O����(�ߘa2�N�F�R���i�x��)���Ă����v�m�莞��(�@�l�Ŗ@22��2��)�͑O���łȂ������]�O�Ɠ��l�ɖ̌����ł���Ƃ�������(���ŕs���R�����ߘa5�N12��21���ٌ��E�ٌ�����W133�W113��)�̏Љ�c�c�k���L�u�����Ƃ����͋����Ȃ��v |
4.4.4. �ېŌJ����
|
������`(mark-to-market)��������`(realization) �ېŌJ�����ɂ��ېł̎����I���S�͈قȂ�B �����E�������x���F�����Ă��炢�����E��p�������F�����Ă��炤���ƁA���[�Ŏ҂ɂƂ��ėL���B �ېŌJ���̗��v�́A�J�����Ԃ���������J���Ŋz�����������Z������̂Ɠ����ł����Bmo�@Cf.�������p��5.2.3.3.b. |
5.2.3.3.b. �������p��(depreciation cost)(����49���A�@��31��)(�����Ȃ蒵�邪������)fn
��F�v�Z�̕X�̂��ߗ��q���E��������10��(�N����)�A�ŗ����ꗥ40���̐��E��z�肷��B��0�N�x��1735�x�o���Ď��Ɨp�̋@�B(����1735)���w�������B��0�N�x�Ɋ��̑���������������(�����ɂ�钲���͖���)�B�c�c���K��1735���������Y��1735�������Ă���̂ŏ����Y����(���͏����Y����)��0�B��p���v�Ή��̌����@���@�������p���Y�̎擾��́A�擾�̔N�x�Ɉꊇ���Ĕ�p�Ɍv�シ��̂ł͂Ȃ��A�g�p�܂��͎��Ԃ̌o�߂ɂ���Ă��ꂪ��������̂ɉ����ď��X�ɔ�p�����ׂ��B�Ȃ��A�������p��̕K�v�o��E�����ւ̎Z���ɂ������̊m���͗v���Ȃ��B
��z�@(���ŗ�120����2��1��1���C(1)��fo)�F���N�����z���p�Ɍv�シ��B
�藦�@(���ŗ�120����2��1��1���C(2)��)�F��z�@��葁���B(���藦�@�E250���藦�@�͏ȗ�)
��F��0�N�x����1735�ōw�������@�B(�ϗp�N��5�N�A�c�����z0�Ƃ���B1735/5��347)���A��1�N�x����2000�Ŕ��p���ꂽ�B�������p���z�@�ōs�Ȃ��Ă���Ƃ��āA��1�N�x�̏��n�v�͊�炩(�����ɂ�钲���͖���)�B
���n���������z�|�擾������n�v(����33��3���ȉ�)
2000�|1735��265�@ �ł͂Ȃ��A
2000�|(1735�|347)��612�@�ł���B
���n�v���v�Z����ۂ̎擾����c�c�擾������|�������p��v
�ېŏ����̌v�Z�ɂ����Ă͌������p��(�K�v�o��̈��)���T������̂ŁA���Ɏ������Ȃ����(����33��4������)
612[���n�v]�|347[���Ə����̕K�v�o��]��265[���v�ʎZ��̏���]�@���ېŏ����ƂȂ�B
�@(���n�����̌v�Z�ɂ�������n�v�|50���~�̉ߒ��͌v�Z�̕X�̂��ߖ������A���n�v�����n�����Ƃ��Ă���)
��1�N�x�̊Ԃɋ@�B�𑀋Ƃ��Ď��Ə����Ă����������R�ېŏ����Ɋ܂܂��B
�Ⴆ�A��1�N�x�̎��Ə����ɌW�������500�ł���A���v�̉ېŏ�����
612[���n�v]�{(500�|347)[���Ə���]��765�@�ƂȂ�B
�y���n�v�̌v�Z�Ŏ擾��猸�����p��������z�A�y�����v�Z�ɂ����Č������p��������z�́A�ꌩ�A��x��ԂɌ����Ă��܂���������Ȃ����A��2�N�x�ȍ~�́A��x��Ԃł͂Ȃ����Ƃ��ȉ��̂悤�ɕ�����B
��������2�N�x����2000�ŋ@�B�����p���ꂽ�ꍇ�B
���n�v�����n���������z�|�擾��ł���A�擾������|(�v��)�������p��ł��邩��A
2000�|(1735�|347�~2)��959�@�ł���A
�ېŏ����̌v�Z�ɂ����āA���Ɏ������Ȃ���A
959[���n�v]�|347[���Ə����̕K�v�o��]��612[���v�ʎZ��̏���]�@�ł���B
��2�N�x�̎��Ə����ɌW�������500�ł���A���v�̉ېŏ�����
959�{(500�|347)��1112�@�ƂȂ�B
��F��1�N�x��1000�̎��Ǝ��v�������炵�A��2�N�x�ɂ�1000�̎��Ǝ��v�������炵�A��2�N�x���ɖ����l�ƂȂ�@�B���A��0�N�x���ɍw������ꍇ�A���̋@�B�̑�0�N�x���ɂ����銄�����݉��l��1000/1.1�{1000/1.12��1735�ł���B��2��(cash flow)�͑�1�N�x�A��2�N�x��1000���̎��Ǝ��v�̗����������Ă���B��3��(�@�B)�͑�0�N�x���A��1�N�x���A��2�N�x���̋@�B�̊������݉��l�������Ă���B
��z�@��藦�@�ɂ�炸�A��I�����T�O�ɒ����ɖ��N�x�����]�����č��z���������p��Ɍv�シ��Ƃ����^�̌o�ϓI�������p(true economic depreciation�BSamuelson depreciation�Ƃ�����)�ɂ��v�Z������ƁA��4��(�������p)�`��7��(�c�z)�̂悤�Ȍv�Z�ɂȂ�B
�����x���p(accelerated depreciation)�Ƃ��đ�1�N�x�ɑS�z���������p��Ƃ��Čv��ł���Ƃ���ƁA��8��(�������p)�`��11��(�c�z)�̂悤�Ȍv�Z�ɂȂ�B�ϗp�N�����Z�����Y(�������p������ɑ傫���o��)���d�ʼn���ɗp������B(��6�Ł�143.04�p���c�B�[�i����(�t�B�������[�X����)�E�Ŕ�����18�N1��24�����W60��1��252��)
���N�x�S�z���p(expensing)�i�S�z�����K�v�o��Z���A�S�z���������Z���ȂnjĂѕ��͊������B4.1.1.2.(����^�����T�O)�ŕ�����expensing�����Ɠ����j�Ƃ��āA��0�N�x�ɍw�����Ă����ɑS�z��K�v�o��͑����Ƃ��čT���ł���Ƃ���ƁA��12��(�S�z���p)�`��15��(�c�z)�̂悤�Ȍv�Z�ɂȂ�B
| - | cash flow |
�@�B | ���� ���p |
���� | �Ŋz | �c�z | ���� ���p |
���� | �Ŋz | �c�z | �S�z ���p |
���� | �Ŋz | �c�z |
| ��0�N | -1735 | 1735 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1735 | -1735 | -694 | 694 |
| ��1�N | 1000 | 909 | 826 | 174 | 70 | 930 | 1735 | -735 | -294 | 1294 | 0 | 1000 | 400 | 600 |
| ��2�N | 1000 | 0 | 909 | 91 | 36 | 964 | 0 | 1000 | 400 | 600 | 0 | 1000 | 400 | 600 |
| ���ڒl | - | - | - | 265 | 106 | 1894 | - | 265 | 106 | 1894 | - | 265 | 106 | 1894 |
| ��2�N���Z | - | - | - | 282 | 113 | 1987 | - | 191 | 77 | 2023 | - | 0 | 0 | 2100 |
��0�N�`��2�N�̐��l��P���ɑ��������ڒl�̍s������ƁA�^�̌o�ϓI�������p�A�����x�������p�A���N�x�S�z���p�ŁA�������ʂƂȂ��Ă���B�T���̃^�C�~���O��ς��Ă��邾���Ȃ̂œ�����O�ł���B�������A���v�͑����F�����Ă��炢��p�͒x���F�����Ă��炤�����L���ł���B���K�̎��ԓI���l���l���ɓ����ƁA���̕����[�Ŏ҂ɕs���A�E�̕����[�Ŏ҂ɗL���ł���B���̔�r�����邽�߂ɂ́A���݉��l�Ɋ��Z���Čv�Z���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
��������2�N���Z�̍s�ŁA��0�N�`��2�N�̐��l���2�N�x�̌��݉��l�Ɋ��Z���đ������킹�����l�������Ă���B���N�x�S�z���p�̏ꍇ�A������0�A�Ŋz��0�ƂȂ�̂������ł���(���Ȃ��Ƃ���Ȃ����߂đd�Ŗ@���w���͋�����)�B������expensing�����Ȃ̂����瓊���̗��q�ɑ���������v�����ɉېł��y�Ȃ��͓̂�����O�ł���B
���N�x�S�z���p(expensing)�̕ʂ̌v�Z��
|
���N�x�S�z���p(�x�o���S�z�����Z���Ƃ�����)�́A�����x�������p�̋��ɂƂ�������B �u���N�x�S�z���p�̏ꍇ�A�ň��O�̗��v���Ɛň���̗��v���͂Ƃ���300%�œ������Ȃ�B�d�ł������Ă��Ȃ��Ă����v���ɕς�肪�Ȃ��B���Ȃ킿�����ŗ����[���ł���v(�P�[�X�u�b�N�d�Ŗ@6��440��)�B |
�����R�X�g100�A���^�[��400�̃v���W�F�N�g�ɂ��āA����40%�A�[�Ŏ҂�60%�������������ƂɂȂ�(����40��[�Ŏ҂ɑ݂��t����300%�̃��^�[���Ă���)�A�Ƃ�������B�܂��A�ŏ��̓����z��100����167(��100��(1�|40��))�ɑ��₹�A�ېł��Ȃ��̂Ɠ�����Ԃ����o�����Ƃ��ł���B
�x�o���ɑS�z���Z������ېŕ��@���L���b�V���E�t���[�@�l��(cash flow tax)�Ƃ��Ă�A�����_�Ƃ��Ă͏��Ȃ��炸�̎x���҂�����Bfp fq
5�Ł�231.02���ݗp�y�n���^�����E��㍂������10�N1��30���Ŏ�230��337�łɊ֘A���āB
�y�K�v�o���Z���z�Ɓy���{�I�x�o�E�擾��Z���E�������p�z�Ƃ̈Ⴂ(cf.��COLUMN5-5)mn
��F��0�N�N��600�̋@�B�w�����֘A��p150�B�ϗp����3�N�A�c�����z0�A��z�@�B���������B
| �N�x | ��O�N | ��P�N | ��Q�N | ��R�N |
| �K�v�o��Z�� | ���Y600�@�o��150�@ | ���Y400�@�o��200�@ | ���Y200�@�o��200�@ | ���Y000�@�o��200�@ |
| �擾��Z�� | ���Y750�@�o��000�@ | ���Y500�@�o��250�@ | ���Y250�@�o��250�@ | ���Y000�@�o��250�@ |
4.4.5. �����T�O�ƔN�x�A���Ƃ̊W(�d�Ŗ@�T���ɂ͂Ȃ����ڂł�)
��F��0�N�x���Ɂu����3�N�ԁA���N�x����100����邱�Ƃ��ł���L���،��v�������Ƃ���B
|
�u�����Ƃ������t�����F�A���̒��ɂǂ�ȓ��e�荞�ނ̂�����X�����߂˂Ȃ�Ȃ�����T�O�ł���Ȃ�A$(0, 100, 100, 100)�Ƃ������e��������悤�ɏ����T�O���߂�悢�̂ł͂Ȃ����B���̍l�����͐��������A�������A���̂悤�ȈӖ��Œ�`���ꂽ�����Ƃ������t���Ӗ����Ă���̂́A���Y�̉��l���㏸���邱�Ƃ������Ȃ̂ł͂Ȃ��A�㏸�������l�����������ꂽ�Ƃ��ɂ͂��߂ď����ɂȂ�Ƃ������Ƃł���B�v�u���̂悤�Ȑł͂��͂⏊���łł͂Ȃ�����łł���B���ǁA�����T�O�͏���ł̑����������ł̒��ɉB���Ă��܂����ƂŁA2�̐Ő���B���ɑË������Ă���̂ł����B�v(�������u�d�Ő���̕��͘g�g��(�㉺)�v�W�����X�g1220��119�ŁA1221��145��(2002)��1220��124�ł��甲��) ����l�����\�\������`�́A���s��d���Ȃ��̂��Ă�����̂ł͂Ȃ��A�l�X�̏����̔F���̎d���Ɋ�Â��Ă���B(�x�������������Ŗ���L���Ȃ̂ɐl�X�͒x�点�悤�Ƃ��Ȃ��A�Ȃ�) |
COLUMN4-6 ���b�N�E�C������(��������)(Lock-in effect, Freezing effect)
| �N�x | (1)�ێ��A10%���� | (2)�����A10%���� | (3)�ێ��A9%���� | (4)������`�A10%���� |
| ��1�N�x | ��0 | ��400 | ��0 | ��400�؋�400 |
| ��2�N�x | ��440�c660 | ��24�c636 | ��436�c654 | �ԍ�440��24�c636 |
�o�����ɂ��ۗL�`�ԕύX(��:�`�Ђ����Ǝ��Y�b��ۗL����Ƃ����`�Ԃ���A�`�Ђ��b�������o�����Ăa�Ђ�ݗ����A�`�Ђ��a�Њ�����ۗL���a�Ђ��b��ۗL����Ƃ����`�Ԃւ̕ύX)��W���Ȃ��悤�ɂ��邽�߂ɁA����(realization)�͂����Ă���������F��(non-recognition)�Ƃ��郍�b�N�E�C�����ʑ��@�����(��5.4.1.3.�g�D�ĕҐŐ�)�B����58�������b�N�E�C�����ʑ�̈��Ƃ�����B
4.5. �����̐l�I�A��
4.5.1. ���������҉ې�(����12��)
4.5.1.1. �@���I�A�������o�ϓI�A����fu
����12��(�@��11���A����13�������l)�u���Y���͎��Ƃ��琶������v�̖@����A������Ƃ݂���҂��P�Ȃ閼�`�l�ł��āA���̎��v�������A���̎҈ȊO�̎҂����̎��v������ꍇ�ɂ́A���̎��v�́A���������҂ɋA��������̂Ƃ��āA���̖@���̋K���K�p����B�vft�M���͏���13���ŕʓr�K��B
���A�Ⴆ���≮(���@551��)�ɂ��Ă��A�@����̌����`���̋A���Ǝ����I�A���Ƃ̘���������B�����Ƃ��Ė≮�ł͂Ȃ��ϑ��҂ɑ��v���A������B
���@551���u���̏͂ɂ����āu�≮�v�Ƃ́A���Ȃ̖��������đ��l�̂��߂ɕ��i�̔̔����͔���������邱�Ƃ��ƂƂ���҂������B�v
���@552��1���u�≮�́A���l�̂��߂ɂ����̔����͔�����ɂ��A������ɑ��āA���猠�����擾���A�`�����B�v�m2�����n
| 6�Ł�213.04 �`�p�o�L�����E�Ŕ����a48�N4��26�����W27��3��629�ŕS�I7��108dy �����E���_�@X2�̎o�̕v�ł���C���A���҂���̒Njy��Ƃ�邽�߁AC���L�ł͂��邪��O�Җ��`�ƂȂ��Ă����y�n��������X1�EX2���`�Ƃ��A������X1�EX2����A�EB�ɔ��p�������Ƃɂ��Ă��܂����BX1�EX2�ɏ��n���������������Ƃ���Y�Ŗ������͉ېŏ������s�Ȃ��A�܂�X2���L�̍b�y�n���������������B �@Y�̉ېŏ����͏����̋A���̌��Ƃ������r��ттĂ���BX�炪�s���\�����Ԃ�k�߂�����ł������̖������咣�ł��邩������ꂽ�B ���|�@�����Ƃ��āu�ېŏ������@��̏����v���������ꍇ�ɂ́A�܂��s����̕s���\���Ă����A���ꂪ�e��Ȃ������Ƃ��ɂ͂��߂ē��Y�����̎�����𐿋����ׂ����̂Ƃ���Ă���v�u���̕s���\���Ăɂ��Ă͖@����Ԃ̏��炪�v������v�Ă���B �@�u�ېŏ����ɂ��Ă��A�s����̕s���\���葱�̌o�R��o�i���Ԃ̏����v�����Ȃ��ŁA���Y�����̌��͂𑈂����Ƃ̂ł����O�I�ȏꍇ�v�u�ېŏ����ɂ��Ă��A���R�ɂ�����Ƃ��ׂ��ꍇ�����肤��v �@�o�i���Ԃ̐������Ȃ��Ȃ�悤�ȁu��O�̏ꍇ���m�肷��ɂ��ĐT�d�łȂ���Ȃ�Ȃ��v����Łu��ʂɁA�ېŏ������ېŒ��Ɣ�ېŎ҂Ƃ̊Ԃɂ̂ݑ�������̂ŁA�����̑��݂�M�������O�҂̕ی���l������K�v�̂Ȃ����ƂȂǂ����āv �@�u�����ɂ�������e��̉ߌ낪�ېŗv���̍����ɂ��Ă̂����ł����āA���ōs���̈���Ƃ��̉~���ȉ^�c�̗v����Ύނ��Ă��Ȃ��A�s���\�����Ԃ̓k�߂ɂ��s���I���ʂ̔����𗝗R�Ƃ��Ĕ�ېŎ҂ɉE�����ɂ��s���v���Î��邱�Ƃ��A�������s���ƔF�߂���悤�ȗ�O�I�Ȏ����̂���ꍇ�ɂ́A�O�L�̉ߌ�ɂ�����r�́A���Y�����R�����Ȃ炵�߂�v ���� ����12���ł����u�P�Ȃ閼�`�l�v�ł���Ȃ����ĂƂ�����B �@�s�������̖����咣���F�߂��邽�߂ɂ́A�s�����������r���d�含�������������v�������A�Ƃ����邱�Ƃ�����i�ŎO�������a36�N3��7�����W15��3��381�Łj�B�{���ł́A�u�ېŗv���̍����ɂ��Ă̂���v(=�ߌ�)��v�����镔�������r�̏d�含��v�������|�ł���Ɠǂ߂邪�A���ɂ́u�s���v���Î��邱�Ƃ��A�������s���ƔF�߂���悤�ȗ�O�I�Ȏ���v��v�����邾���ŁA�������ւ̌��y���Ȃ��B���a36�N�Ŕ��Ɩ{�����a48�N�Ŕ��Ƃ̊W�ɂ��Ă͕S�I���Q�Ɓi�ېŏ����Ώێ҂̊֗^�̓x�����ɒ��ڂ��H�j�B�Ȃ��A�w���ł͖�������v�����邱�Ƃɑ�����^������B �@cf.�˂��ݍu�����^�V����Ƃ̉���E�ŎO��������16�N7��13���W��214��751�Łc�u��O�I�Ȏ���v���F�߂��Ȃ���������B�i�d�喾�����ɋ����Ă���j |
| ������������28�N2��26�����^1427��133�Łc�@�l���`�̎���B |
| ���}���≮�ݓ|�d���Ŋz�T�������E���n������25�N6��18���Ŏ�263������12235����23(�s�E)13��fv(��ȏ͔@�E�W�����X�g1495��135��) �����E���_�@�`��(��������������s��)�ɎQ�����i�̂Ȃ��a(�ϑ��ҁE�o��)�́A���}����ׂ��A�≮����w(����)�Ɉ˗������B�w�͖≮�Ƃ��ċ��}�����b(����l)�ɔ��p�������A�b�̎�����Ԃ������A���|���̉���������̂ŁA�ݓ|�������v�シ�邱�ƂƂȂ����B�����ŏ���Ŗ@3��9��1���Ɋ�Â��݂��|��ɌW�����Ŋz�̍T��(�d���Ŋz�T��)���咣�����B �@��(�ېŒ���)�́A�w�͖≮�ł���ɂ������A���}����������̑��v�͈ϑ��҂ł���`�ɋA��������̂Ƃ��ď���Ŗ@�㈵����ׂ��ł��邩��A�w�Ɏd���Ŋz�T�����͂Ȃ��A�Ǝ咣�����B �@�w�́A�������������X�N���ϑ��ҁE�o�҂���`�ł͂Ȃ��w�����S���Ă���̂ŁA�w�Ɏd���Ŋz�T����������Ǝ咣�����B ���|�@�u�`��ɂ����Č������≮�Ƃ��čs�����}������ɂ�鋍�}���̏��n�ɌW��Ή�������̂͌����ł͂Ȃ��ϑ��ҁi�o�ҁj�ł���Ƃ��������ł��邪�c�c���Y�̏��n�����s�����҂̎�������͂��̖@�I�����ɂ��ׂ����̂ł���Ƃ���C�ȉ��̏��_�Ɋӂ݂�C���}������̖@�I�����Ƃ��āC�@���㎑�Y�i���}���j�̏��n�����s�����Ƃ݂���҂��Ȃ킿�≮�ł���w���C�P�Ȃ閼�`�l�ɂ������C���Y���Y�i���}���j�̏��n�����s�������̂ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ����̂Ɖ�����̂������ł���B�v �@�u���}������ɌW�锃��l�ɑ��鋍�}���̔���͂w�ł����Ĉϑ��ҁi�o�ҁj�ł͂Ȃ��C����l�ɑ��锄�������������L����̂��ϑ��ҁi�o�ҁj�ł͂Ȃ��w�ł���B�m���s�n�@�����āC���}������ɌW�锃��l����̔����������̃��X�N���̂��ϑ��ҁi�o�ҁj�ł͂Ȃ��C�w�ł���B���Ȃ킿�C�w�́C����l���甄������̉�����ł������ۂ��Ɋւ�炸�C���̉��������ꂽ���̗����܂łɈϑ��ҁi�o�ҁj�ɑ������d�؋����x����Ȃ���Ȃ炸�c�c�C����l����̑��������ł��Ȃ������ꍇ�i�ݓ|��ƂȂ����ꍇ�j�ɁC�w���ϑ��ҁi�o�ҁj�ɑ��锄���d�؋��̎x����Ƃ�C���邢�́C�ϑ��ҁi�o�ҁj��������̔����d�؋��̕Ԋ҂��邱�Ƃ��ł���|�̒�߂͑����Ȃ��B�v �@�u�`��ɂ����鋍�}������ɂ����āC���x�エ�悻�w�������������̃��X�N��Ȃ��d�g�݂��\�z����Ă�����̂Ƃ͌�����B�����āC��L�̂Ƃ���C�w�Ɩ{���e����l�Ƃ̊ԂŒ������ꂽ���i�{���e���j�ɂ����ẮC�w�����������������̃��X�N������������Ƃ��āC������x�z�┃����x�����z�̒S�ۂ̍����ꓙ�̒�߂�݂��Ă������̂ł��邪�C�{���e���ɂ����Ă��C��L�̂Ƃ��蓯������x�z���Ăw�����}����̔����邱�Ƃ͋ւ����Ă��Ȃ��̂ł����āC�w���{���e����l�ɑ��C���̔�����x�z��啝�ɒ��߂������}���̔̔����s���C�܂��C������x�z�߂����̔����s�����セ�̒��ߊz�ɂ��Ē����ɐ��Z���邱�Ƃ����߂铙�̑[�u���̂�Ȃ��������Ƃ��{���e���̉����s�\�Ȃ炵�߂��傫�ȗv���Ƃ�����Ƃ��Ă��C���̂悤�ɂw�������������̃��X�N����������i���̂�Ȃ��������Ƃɂ�鑹�Q�́C�w���g�����ɕ��S���Ă�����̂Ƃ�����B�v |
| (Barclays)�o�[�N���C�Y��s�����E�����n���ߘa4�N2��1���ߘa2(�s�E)271���Ŏ�272������13665(�F�e)(�ɓ����u�E�W�����X�g1577��10-11�ŁA������q�E�W�����X�g1592��147-150�ŁA�]�����u�O���@�l�̓����x�X�����s�����Ѝ��q�̋A���Ǝ��������҉ېł̌����v�V�E������Watch�d�Ŗ@No.187 (2024.8.9)) �@�����@�w�Ёi�����B�p���@�l�B�o�[�N���C�Y�E�o���N�E�s�[�G���V�[�j�����x�X�i�s�x�X�j���w�Ѓ����h���{�X�i�k�{�X�j�ɑ��Ė{���Ѝs�����B�k�{�X�͂a�b�k�Ёi�w�Ђ̊��S�q��ЁB���N�Z���u���N�@�l�B�a�`�q�b�k�`�x�r�@�b�`�o�h�s�`�k�@�k�t�w�d�l�a�n�t�q�f�@�r�D�`�@�q�D�k�D�j�ɖ{���Ѝ����n�����B�a�b�k�Ђ͂h�s�r�Ёi���{�@�l�B�h�b�`�o���[�،�������ЁB�h�b�`�o�@�s�n�s�`�m�@�r�d�b�t�q�h�s�h�d�r�@�b�n�D�k�s�c�j�ɖ{���Ѝ����n�����B�w�Ђ́A�{���ЍɌW��{�����q�̎��v�������I�ɋ��Ă���҂́i�h�s�r�Ж��́��h�s�r�Ђł��邩�͑��_�ł͂Ȃ��Ȃ����j�k�{�X�ł���Ƃ��āA�{�����q�̊e�x���ɍۂ����������Ȃ������B���z�Ŗ������́A����҂͂a�b�k�Ђł���Ƃ��āA�{���e�����i�����ɌW�鏊���ł̊e�[�ō��m�����y�ъe�s�[�t���Z�ŕ��ی��菈���j�������B �@���_�@�{�����q�̎��������ҁi�����Ŗ@12���j���k�{�X���i�w���咣�j�A�a�b�k�Ђ��i�x���咣�j�B �@���|�@�u�����Ŗ@�P�Q���c�c�̎�|�́C�ېŕ����̖@����i���@��j�̋A���ɂ��C���̌`���Ǝ��������Ⴕ�Ă���ꍇ�ɂ́C�����ɑ����ċA���f���ׂ��Ƃ�����̂Ɖ�����C�{���̉ېŕ����ł���{�����q�̎��������҂f����ɓ������ẮC�{�����q�ɌW��o�ϓI���v�̋A����̂ق��C�{���������B����S�̂̎d�g�݁C�{���������B����Ɏ���o�܂��邢�͊W�҂̔F���C�{���������B����̎��{�ȂǏ��ʂ̎���𑍍��I�ɍl�����ׂ����̂Ɖ������B�v �@�u�{���������B����ɂ����ẮA�{�����q�ɌW����v���܂ޖ{���Ѝ��Ɋւ���o�ϓI�ȑ��v�ɂ��C�@�I�Ȍ����`���W��ʂ��āC�ŏI�I�Ƀ����h���{�X�ɋA������Ƃ����d�g�݂��̗p���Ă��邱�Ƃ̂ق��C�{���Ѝ��ɌW�鑹�v��S�ă����h���{�X�ɋA�������邱�Ƃ��{���������B��������{����s���̗v�f�ł��邱�Ƃ́C�{���������B������s���W�ҊԂɂ������т������ʔF���ł����āC�{���������B����̎��ۂ̎��{������ɉ����`�ōs���Ă�����̂ł���B������{�����q�̌o�ϓI���v�̋A������܂߂��{���������B����̎d�g�݁C�{���������B����Ɏ���o�܂��邢�͊W�҂̔F���C�{���������B����̎��{�Ɋӂ݂�C�{�����q�ɌW����v�ɂ��ẮC�����I�Ƀ����h���{�X���x�z������̂ł���C�h�s�r�Ђ��邢�͂a�b�k�Ђ����Y���v���x�z������̂ł͂Ȃ��Ƃ����̂��C�{���������B����̊W�ҊԂ̐^���̖@���W�ł���ƔF�߂�̂������ł���C�����h���{�X���{�����q�̎��������҂ł���Ƃ����ׂ��ł���B�v |
4.5.1.2. �Ƒ����ł̏����̋A���Ɖғ��҉ې�
�ΘJ�������̋A���ύX�۔F���ғ��҉ې��@(�A��6�Ł�213.02���Ȉ�@�e�q�����o�c�����E������������3�N6��6����38��5��878�łɗ���)���Y�������́A�����Ƃ��Ă��̎��Y�̏��L�҂ɋA������B(�A�����Y�ړ]�������^���ɗ���)
������������g�����d�ʼn��(���ŗ��K�p���)�̓�Ղ͏����̎�ނɂ��قȂ�Bfx
| 6�Ł�213.03�������ϔC�����E�F�{�n�����a57�N12��15����29��6��1202�� �w���w�̍Ȃɏ،��^������ł͂Ȃ��A�z������������蓊���M�����ւ����蓙���ȂɔC�����ɂ����Ȃ��ꍇ�A�e�،���ЂƂ̊Ԃ̗L���،�����ɂ��ẮA���̌ʓI�A��̓I�Ȏ���s���͍̂Ȃ��S�����Ă��Ă��A�w�̕�I�Ȉϑ��Ɋ�Â����̂ł����āA���̎���ɂ���������n�v�Ƃ��Ă̏����͑S�Ăw�ɋA�������B |
| �����n�����a63�N5��16������1281��87�ŕS�I6��29 cf.6�Ł�212.03��� ���@756���i�v�w���Y�_���̑R�v���j�@�v�w���@����Y���ƈقȂ�_��������Ƃ��́A�����̓͏o�܂łɂ��̓o�L�����Ȃ���A�����v�w�̏��p�l�y�ё�O�҂ɑR���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B �v�w���Y�_���������ŕv�̏����̔������Ȃ̏����ł���Ƃ��Đ\�����邱�Ƃ̉ہ\�\��������������Ŗ@��N�̏����ɑ����邩�́A���Y�����ɌW�錠�������������i�K�ɂ����āA���̌�����������Ƃ̊W�ŒN�ɋA�����邩�Ƃ������Ƃɂ���Č��肳��A�v�w���Y�_��̓o�L�̗L���Ɋւ��Ȃ��A�v���͍Ȃ̈�������鏊�����̂��̂����n�I�ɕv�y�эȂ̋��L�Ƃ���v�w�Ԃ̍��ӂ͂��̈Ӑ}�������ʂ��Ȃ��Bfw |
| ���n���ߘa3�N4��22������31(�s�E)51���Ŏ�271������13553�ꕔ�F�e�A�ꕔ�p���E��㍂���ߘa4�N7��20���ߘa3(�s�R)64���Ŏ�272������13735����������A�����ꕔ���p(�m��)(������q�E�V�E������Watch�d�Ŗ@No.174�A�d�K�E�Ō�222��86-89�ŁE�Ō�229��102-106�ŁA�����p���E�Ŗ����ጤ��191��27-49�ŁA�Z�i���ށE�V�E������Watch�d�Ŗ@No.183) ������q�ɒ��ԏ���g�p�ݎ��A���ԗ����i�s���Y�����j�̋A�������ł͂Ȃ��q�ł���Ɣ[�Ŏґ����咣��������i�_���͏��������Ƃ����������̎��S���̑����Ŕ[�Ŏ����m�ۖړI�ł������炵���j�B�Ȃ��A���̎g�p�ݎɊւ�������q�ւ݂̂Ȃ����^�i����9���j�ېł��Ȃ���邩�A�肩�łȂ��B����2-189���a48�N11��1���u�g�p�ݎɌW��y�n�ɂ��Ă̑����ŋy�ё��^�ł̎戵���ɂ��āv�Q�ƁB�Ȃ��A�����Ŋ�{�ʒB9-10�Ŗ������ݕt�̑��^�ʼnېł����肤��Ƃ���Ă��邱�ƂƐ������Ă��Ȃ��B ��R�͔[�Ŏґ��̎咣��F�߂����T�i�R�ŋt�]�����B ��R�c�c�u�{���e�g�p�ݎ،_�̋L�ڂǂ���C�{���e�g�p�ݎ،_��͐��������ƔF�߂���i�Ȃ��C�`���͂a�́C�����ɑ��C�f���y�n���͂g�y�n�̊e�N�̌Œ莑�Y�œ��̍��v�z�����z���x�������ƂƂ���Ă��邪�c�c�C����͎g�p���v�ɑ���Ή��̈Ӗ��������̂Ƃ͔F�߂��Ȃ�����C�{���e�g�p�ݎ،_��́C���@��̎g�p�ݎ،_��̐�����L������̂Ɖ������c�c�B�j�B�v �@�u�{���e�y�n�̒��ݎɊւ��閯�@��̖@���W���C�����Ŗ@�P�Q���̋K��ɏƂ炵�Ă݂�ƁC�`���͂a�́C�u���Y���͎��Ƃ��琶������v�̖@����A������Ƃ݂���ҁv�ɊY������v �T�i�R�c�c�u�A�X�t�@���g�ܑ��́A�H�ՂɃA�X�t�@���g��������~���ς��āA�]���@�B�ɂ�菊��̖��x��������܂Œ��ł߁A����̌`��ɕ��R�Ɏd�グ����̂ł���A�A�X�t�@���g�ܑ����ꂽ�n�ʂ̂����A�A�X�t�@���g���������܂܂��\�w�y�ъ�w���́A�y�n�̍\�������ƂȂ�A�Ɨ��̏��L������������]�n�͂Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���B�m���s�n�@���������āA�S�c�ɂ����āA�{���e���^�_��̂����{���e�ܑ������̏��L�����T�i�l�d�y�ѓ��f�Ɉړ]�����邱�Ƃ͌��n�I�ɕs�\�ł��邱�Ƃ͖��炩�ł��邩��A�{���e���^�_��̂����O�L�ܑ���������ΏۂƂ��镔���͂�����������Ƃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B��������ƁA�{���e�g�p�ݎ،_�̍쐬�ɂ��A�����҂������Ӑ}�����Ƃ���̔�T�i�l�d�y�ѓ��f���{���e�ܑ����������L���邱�Ƃ�ړI�Ƃ����{���e�g�p�ݎ،_���������Ɖ��߂���]�n�͂Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���B�v �@�u�s���Y�����ł���{���e�y�n�̒��ԏ�����́A�{���e�y�n�̎g�p�̑Ή��Ƃ��Ď�ׂ����K�Ƃ����@��ʎ��ł���i���@�W�W���Q���j�A���ԏ���ݎ��Ƃ��c�ގ҂̖̑Ή��ł͂Ȃ�����A���L���҂����̉ʎ����挠���O�҂ɕt�^���Ȃ�����A�������L���҂ɋA�����ׂ����̂ł���B�m���s�n�@�����āA�{���Ŕ�T�i�l�d�y�ѓ��f���{���e�y�n�̖@��ʎ�������ł��鍪���͎g�p�،��i���@�T�X�R���j�ł��邪�A�g�p�؎�́A���̖���������A�{���g�p�ݎ�̏����Ȃ�����A�@��ʎ����挠��L���Ȃ��Ƃ���i���@�T�X�S���Q���j�A�{���ɂ����ẮA���ɖ{���e�y�n�̏��L���Ɋ�Â����ԏ���ݎ��Ƃ��c��Œ����������擾���Ă����S�c���A�q�ł����T�i�l�d�y�ѓ��f�ɖ{���e�y�n���g�p�ݎ��A�@��ʎ��̎�����������āA���̎��Ƃ�O�L��T�i�l��ɏ��p�������Ƃ����̂ł��邩��A�{���e����́A�S�c���{���e�y�n�̏��L���̋A����ς��Ȃ��܂܁A����̑Ή������邱�ƂȂ��A�������琶����@��ʎ��̋A�����q�ł���O�L��T�i�l��Ɉړ]���������̂ƕ]���ł���B�������A�g�p�ݎɂ�����]�݂̏����A���Ȃ킿�@��ʎ����挠�̕t�^�́A���̖���������A���̏�����P�A�����Ɍ������ĕt�^���Ȃ����Ƃ��ł���ƍl�����邱�Ƃ��炷��ƁA���������S�c����g�p�ݎɊ�Â��@��ʎ����挠��t�^���ꂽ���ƂŁA���R�Ɏ����I�ɂ��{���e�y�n����̎��v������҂ƒf���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���B�v |
| ������������30�N8��29���Ŏ�268������13178�c�v�����ݗp�}���V�������ȂɎg�p�ݎ��A�Ȃ����ݐl�ƂȂ�������ŁA�v�̌����ɒ������U�荞�܂�Ă���A�v�̌�������ؓ����̕ԍς��Ȃ���Ă���Ȃǂ̎����A�v�������Ŗ@12���̎����I�A���҂ł���Ƃ��ꂽ����B |
4.5.2. �Ƒ����ƁF�Ƒ����ł̋��^���̕K�v�o��Z���̉�(����56�E57��)
����56���i���Ƃ���Ή�����e��������ꍇ�̕K�v�o��̓���j�u���Z�҂Ɛ��v����ɂ���z��҂��̑��̐e�������̋��Z�҂̉c�ޕs���Y�����A���Ə������͎R�я������ׂ����Ƃɏ]���������Ƃ��̑��̎��R�ɂ�蓖�Y���Ƃ����Ή��̎x������ꍇ�ɂ́A���̑Ή��ɑ���������z�́A[1]���̋��Z�҂̓��Y���ƂɌW��s���Y�����̋��z�A���Ə����̋��z���͎R�я����̋��z�̌v�Z��A�K�v�o��ɎZ�����Ȃ����̂Ƃ��A���A[2]���̐e���̂��̑Ή��ɌW��e�폊���̋��z�̌v�Z��K�v�o��ɎZ�������ׂ����z�́A���̋��Z�҂̓��Y���ƂɌW��s���Y�����̋��z�A���Ə����̋��z���͎R�я����̋��z�̌v�Z��A�K�v�o��ɎZ�������B���̏ꍇ�ɂ����āA[3]���̐e�����x�������Ή��̊z�y��[4]���̐e���̂��̑Ή��ɌW��e�폊���̋��z�̌v�Z��K�v�o��ɎZ�������ׂ����z�́A���Y�e�폊���̋��z�̌v�Z��Ȃ����̂Ƃ݂Ȃ��B�v����57���i���Ƃɐ�]����e��������ꍇ�̕K�v�o��̓��ᓙ�j�u�F�\�������o���邱�Ƃɂ��Ŗ������̏��F���Ă��鋏�Z�҂Ɛ��v����ɂ���z��҂��̑��̐e���c�c�Ő�炻�̋��Z�҂̉c�ޑO���ɋK�肷�鎖�Ƃɏ]����������i�ȉ����̏��ɂ����āu�F���Ɛ�]���v�Ƃ����B�j�����Y���Ƃ��玟���̏��ނɋL�ڂ���Ă�����@�ɏ]�����̋L�ڂ���Ă�����z�͈͓̔��ɂ����ċ��^�̎x�������ꍇ�ɂ́A�O���̋K��ɂ�����炸�A���̋��^�̋��z�ł��̘J���ɏ]���������ԁA�J���̐����y�т��̒̒��x�A���̎��Ƃ̎�ދy�ыK�́A���̎��ƂƓ���̎��Ƃł��̋K�͂��ގ�������̂��x�����鋋�^�̏��̑��̐��߂Œ�߂�ɏƂ炵���̘J���̑Ή��Ƃ��đ����ł���ƔF�߂�����̂́A���̋��Z�҂̂��̋��^�̎x���ɌW��N���̓��Y���ƂɌW��s���Y�����̋��z�A���Ə����̋��z���͎R�я����̋��z�̌v�Z��K�v�o��ɎZ�����A���A���Y�F���Ɛ�]�҂̓��Y�N���̋��^�����ɌW��������z�Ƃ���B�m2�����n
�R�@���Z���i��ꍀ�ɋK�肷�鋏�Z�҂������B�j�Ɛ��v����ɂ���z��҂��̑��̐e���c�c�Ő�炻�̋��Z�҂̉c�ޑO���ɋK�肷�鎖�Ƃɏ]����������i�ȉ����̏��ɂ����āu���Ɛ�]�ҁv�Ƃ����B�m�u�w��u���F���Ɛ�]�ҁv�Ƃ����n�j������ꍇ�ɂ́A���̋��Z�҂̂��̔N���̓��Y���ƂɌW��s���Y�����̋��z�A���Ə����̋��z���͎R�я����̋��z�̌v�Z��A�e���Ɛ�]�҂ɂ��A���Ɍf������z�̂��������ꂩ�Ⴂ���z��K�v�o��Ƃ݂Ȃ��B
�@��@���Ɍf���鎖�Ɛ�]�҂̋敪�ɉ������ꂼ�ꎟ�ɒ�߂���z
�@�@�C�@���̋��Z�҂̔z��҂ł��鎖�Ɛ�]�ҁ@���\�Z���~
�@�@���@�C�Ɍf����҈ȊO�̎��Ɛ�]�ҁ@�\���~
�@��@���̔N���̓��Y���ƂɌW��s���Y�����̋��z�A���Ə����̋��z���͎R�я����̋��z�c�c�Y���ƂɌW�鎖�Ɛ�]�҂̐��Ɉ�����������ŏ����Čv�Z�������z�v�m4���ȉ����nci
����56���̏��������֎~�K����݂Ȃ��K���ł���(���̗]�n���Ȃ�)�B
���ʂ͈ȉ���4��(�`�u���Z�ҁv���a�u�e���v�ɑΉ����x�������ꍇ)�B
[1]�`�̓��Y���ƂɌW�鎖�Ə������̕K�v�o��s�Z��
[2]�a�����Y�Ή��Ɋւ��������o��͂`�̕K�v�o��ɎZ������
[3]�a�����Ή��͂a�̏����̌v�Z��Ȃ����̂Ƃ݂Ȃ�
[4]�a���������o��͂a�̏����̌v�Z��Ȃ����̂Ƃ݂Ȃ�
����57��1�����g��Ȃ��Ă��@�l�������Ė@�l����Ƒ��]�ƈ��ɒ������x�����Ƃ����@�`���ɂ��Ă��܂��A���@�I�ɏ��������ł���B�Ƃ������A�@�l���肵����ƌl���Ƃ̗�ƂŒ��������m�ۂ��邽�߂ɏ���57��1�������@���ꂽ�Ƃ�������B4.2.6.3.���^�����T�����d�ŕ��S���̂��߂ɏd�v�B
| 6�Ł�234.02�ٌ�m�v�w�����E�Ŕ�����16�N11��2������1883��43�ŕS�I7��32fz �����@�ٌ�m�w���A�z��҂ł����ʂ̎��������J�݂��Ă���ٌ�m�`�ɑ��āA�w�̎��ƂɊ֘A��1�N������595���~�̑Ή����x�����A�w�̊m��\���ɂ����ĕK�v�o��ɎZ������(�`�̑��ł͏����Ɋ܂߂��Ă���)�B�x�Ŗ������́A����56���Ɋ�Â��A�w�̕K�v�o��Z����F�߂Ȃ������B��R�E��R�Ƃ��w�s�i�B ���|�@�㍐���p�B �@���Ə����ғ��҂��e�����ɑΉ����x�����āu�K�v�o��ɂ��̂܂Z�����邱�Ƃ�F�߂�ƁA�[�ŎҊԂɂ�����ŕ��S�̕s�ύt�������炷�����ꂪ����Ȃǂ̂��߁A�v�e�������u���Ƃɏ]�������������̑��̎��R�ɂ�蓖�Y���Ƃ���Ή��̎x������ꍇ�ɂ́v�u�K�v�o��ɎZ�����Ȃ����̂Ƃ����v�B �@�e�������u�ʂɎ��Ƃ��c�ޏꍇ�ł����Ă��A���̂��Ƃ𗝗R�ɓ���[�����Ŗ@56��]�̓K�p��ے肷�邱�Ƃ͂ł����A�����̗v���������肻�̓K�p������v�B �@�u���@56���̏�L�����@�ړI�͐����v�@�u�K�p�̑Ώۂm�ɂ��A�ȕւȐŖ��������\�ɂ��邽�߁v�@�u���@�ړI�Ƃ̊֘A�ŕs�����Łv�͂Ȃ��B �@�F�\��������̗v�������ꍇ�Ɍ���K�v�o��Z����F�߂�u57���̒�߂�ꍇ�Ɍ�����56���̗�O��F�߂Ă��邱�Ƃɂ��ẮA���ꂪ�������s�����ł��邱�Ƃ����炩�ł���Ƃ͂����Ȃ��v�B(����111.01�哈�i��) �l�@ ����56���̍��������̂ւ̋^��A�y�я���56���̓K�p�͈͂ɂ��Ă̋^�₪�A��N����₷���B����56���͈��@�ł���Ƃ����ӎ����w���ō������A�܂��A���̓K�p�͈͂��������߂����ׂ��A�Ƃ���X��������B�e�������ٗp�y�т���ɗނ���W�łw�̎��Ƃɏ]���I�ɏ]�����Ă���ꍇ��56���̓K�p�͈͂����肵�A�e�������Ɨ��̎��Ƃ��c��ł���ꍇ��Ή��x�������ӓI�ȉ��i�ݒ�ɂȂ�ɂ����ꍇ(�Ⴆ�Βʏ�̒n����ɂ����Ȃ��ꍇ�B��f�������������؎����Q��)�ɂ�56����K�p���ׂ��łȂ��A�Ƃ������l�����ł���B��̓I�ȉ��ߘ_�Ƃ��Ă�56���́u���Ƃɏ]�������������̑������R�v�̍L�������ƂȂ�B |
�ٌ�m�ŗ��m�����E�Ŕ�����17�N7��5���Ŏ�255������10070����16(�s�c)248��:�ٌ�m�v���ŗ��m�Ȏx���B�����n������15�N7��6������1891��44�ł�56��s�K�p�B���T�i�R�ȍ~56��K�p�B
�������������؎����E������������3�N5��22���Ŏ�183��799��:�v����:���������x���B56��K�p�B
�Ŕ����a51�N3��18������812��50�ŕS�I7��31cn�c�c�����̒��j�E���j������56���u���v����ɂ���c�e���v�ɓ����邩�B
������������29�N4��13���Ŏ�267������13010�m��c�c����57��1���F��]�ҍT���Ɋւ���u���ɐE�Ƃ�L����ҁv�Y�����B
4.5.3. �������ƂƎ��Ƃ̎�Ɏ�
| 6�Ł�213.02���Ȉ�@�e�q�����o�c�����E������������3�N6��6����38��5��878�ŕS�I7��28gb �����@���w���s���Ȉ�@���c��ł���A�q�r�͎��Ȉ�t���Ǝ����ɍ��i������A�w�ƂƂ��ɓ���@�ɂ����Đf�Âɏ]���B�r�͂r���g�̖��`�̌l���ƊJ�Ɠ͂���Ŗ������ɒ�o�B�w�Ƃr���������y�ё���p��ܔ����Ċm��\���B�x�Ŗ������́A�r�͂w�̎��Ɛ�]�҂ł���Ƃ��A�����E��p���w�ɋA������Ƃ����B ���|�@�������p�B �@��ʘ_�@�u���������l�̋ΘJ�ɂ����̂ł��邩�ł͂ȁv���B�u���鎖�Ƃɂ������́A���̌o�c��̂ł�����̂ɋA�������̂Ɖ����ׂ��v �@�����F��@�u�w�����a35�N����20���N����@���o�c���Ă����v�@�W���N�x�ɂ�����u��@�̎��Ԃ́c�w�̒��N�̈�t�Ƃ��Ă̌o���ɕt����M�p�͂̌��Ōo�c����Ă����ƌ���̂������ł���A���������āA��@�̌o�c�Ɏx�z�I�e���͂�L���Ă���̂͂w�ł���v �l�@ �u���������l�̏����ɑ����邩�́c�c���l�̎����ɋA�������Ŕ��f�������ł���v�����ł͏z�_�@�ł��舫�����āB�������u���l�̋ΘJ�ɂ�邩�ł͂Ȃ��v��������^����B(�Ȃ��Ŕ����a37�N3��16���Ŏ�36��220�ł͏���11����2�k��56���l�ɂ��u���j�����_�̂悤�ɓz��I���݂ɂȂ�Ƃ����킯�ł͂ȁv���Ƙ_����B) �@�ΘJ�ɂ�鏊�������^�����ł���ɂ����Ȃ��B���Ə������Ƃ������߂ɂ́A�J���̒ł͂Ȃ��o�c�҂Ƃ��Ă̎���(�ӔC�̕��S��)���Ȃ���Ȃ�Ȃ��A�Ƃ������f�g�g�݂��{���ɂ��p������Ă���B �@��l�����Ƃ̎�Ɏ�ga�Ȃ�(���������Ǝ�)������゠��ƌ�����B�Ȃ��A4.5.1.2.���������҉ېł��ғ��҉ې�(�ΘJ���ĂȂ��҂ɏ����͋A�����Ȃ�)�Ə�ʂ��قȂ�A�����ł͋ΘJ���Ă��Ă��������A�����Ȃ��҂��łĂ���B �@�ʒB�ł��������Ƃ��������ƂƔF�肹���Ȃ�ׂ���l�̎��Ƃł���ƔF�肵�悤�Ƃ���X����������B�����12-2�`�����12-5�Q�ƁB�ނ������̕����I�A�����ɔF�߂Ȃ��Ƃ������ł͂Ȃ��A�������ƂƂ��Ď������z�E�K�v�o��̕�����F�߂��ɂ����ӁB����̎��Y�������ɂ��Ă͏����12-1�y����213.03�������ϔC�����Q�ƁB �@���q�G�́A�ǂ��炩����Ɏ҂Ƃ����̂����Ԃɍ��킸�A�������ƂƔF�߂���ꍇ������Ƙ_����B �@�������C�ӑg���_�������ꂽ��A�����������ېŒ��͔۔F�ł��Ȃ��낤�B cf.�h�����N�h���S�� |
4.6. �}�C�i�X����
4.6.1. �K�v�o��(����37��)
4.6.2. ����(���Y���l�̌���)(����51���E72��)
4.6.2.1. ���ƁE�Ɩ��p�̎��Y(51��)
����51���i���Y�����̕K�v�o��Z���j�@���Z�҂̉c�ޕs���Y�����A���Ə������͎R�я������ׂ����Ƃ̗p�ɋ������Œ莑�Y���̑�����ɏ����鎑�Y�Ő��߂Œ�߂���̂ɂ��āA��肱�킵�A���p�A�Ŏ��i���Y���Y�̑���ɂ�鉿�l�̌������܂ށB�j���̑��̎��R�ɂ�萶���������̋��z�i�ی����A���Q���������̑������ɗނ�����̂ɂ���Ă�镔���̋��z�y�ю��Y�̏��n�ɂ�薔�͂���Ɋ֘A���Đ��������̂������B�j�́A���̎҂̂��̑����̐��������̑�����N���̕s���Y�����̋��z�A���Ə����̋��z���͎R�я����̋��z�̌v�Z��A�K�v�o��ɎZ�������B�Q�@���Z�҂̉c�ޕs���Y�����A���Ə������͎R�я������ׂ����Ƃɂ��āA���̎��Ƃ̐��s�㐶�������|���A�ݕt���A�O�n�����̑������ɏ��������̑ݓ|�����̑����߂Œ�߂鎖�R�ɂ�萶���������̋��z�́A���̎҂̂��̑����̐��������̑�����N���̕s���Y�����̋��z�A���Ə����̋��z���͎R�я����̋��z�̌v�Z��A�K�v�o��ɎZ������B�m3�����n
�S�@���Z�҂̕s���Y�����Ⴕ���͎G�������ׂ��Ɩ��̗p�ɋ����ꖔ�͂����̏����̊���ƂȂ鎑�Y�i�R�ыy�ё�Z�\����ꍀ�i�����ɒʏ�K�v�łȂ����Y�̍ЊQ�ɂ�鑹���j�ɋK�肷�鎑�Y�������B�j�̑����̋��z�i�ی����A���Q���������̑������ɗނ�����̂ɂ���Ă�镔���̋��z�m��COLUMN4-4�ی����E���Q�������̔�ېŁB���C�u�h�A���Y���������E�E�_�˒n������25�N12��13������2224��31�Łn�A���Y�̏��n�ɂ�薔�͂���Ɋ֘A���Đ��������̋y�ё�ꍀ�Ⴕ���͑���͑掵�\����ꍀ�i�G���T���j�ɋK�肷����̂������B�j�́A���ꂼ��A���̎҂̂��̑����̐��������̑�����N���̕s���Y�����̋��z���͎G�����̋��z�c�c�����x�Ƃ��āA���Y�N���̕s���Y�����̋��z���͎G�����̋��z�̌v�Z��A�K�v�o��ɎZ������B�m5�����n
51���́u�����v��4.6.3.���v�ʎZ�E����69���́u�����v�Ƃ̈Ⴂ�ɗ��ӁB
| 6�Ł�234.01���Ə�̑��� ���Ə����ݓ|���s�������ԊҐ��������E�Ŕ����a53�N3��16����24��4��840��cq�c�c�u���Ə����Ƃ��ĉېł̑ΏۂƂ��ꂽ���K��������ݓ|�ꓙ�ɂ�����s�\�ƂȂ��Ƃ��́A���̉���s�\�ɂ�鑹���z���A���Y����s�\�̎��������������N���̎��Ə����̋��z�̌v�Z��A�K�v�o��ɎZ�����ׂ����̂Ƃ���A����ɂ�Ĕ[�Ŏ҂͎����I�ɐ�̉ېłɂ��ċ~�ς��邱�Ƃ��ł����̂ł��邩��A����Ƃ͕ʂɁA�[�Ŏ҂����Ŏ҂��鍑�ɑ��A�E����s�\�ɂ�鑹���z�ɑΉ����钥�����݂̐Ŋz�ɂ��s�������Ƃ��ĕԊ҂𐿋����邱�Ƃ́A�@�̔F�߂Ȃ��Ƃ���ł����Ɖ����ׂ��ł���B�v 6�Ł�232.01�G�����ݓ|���s�������ԊҐ��������E�Ŕ����a49�N3��8�����W28��2��186�łƔ�r�B cf.�����n������23�N1��20����58��6��2488�Ő������p�E������������23�N9��8����58��6��2471�ōT�i���p(�P6��308��)(�����p���E�W�����X�g1471��124��)�c�c�o���@5���ᔽ�̑��Ǝ҂��ڋq�ɑݕt�����{��Ԋ҂����߂邱�Ƃ��ł��Ȃ����Ƃ̑������A�����Ŗ@51��2���ɂ����ݓ|�ꑹ���ɓ�����Ȃ��Ƃ��ꂽ����(���ŗ�141��3������Y���Ƃ��Ă���B����152���E��274���Ƃ̃o�����X�����U�����Ɍv�コ�ꂽ���̂������u�o�ϓI���ʁv�ɓ�����Ƃ��āA�����v�コ��悤���Ȃ����{�����͗�141��3���ɓ����肦�Ȃ��Ƃ��Ă���)�B[���]��141��3����Y���ɂ����u���O2013.6.8 cf.�}���t�@�i���l�ɂ���Benjamin M. Leff, Tax Planning for Marijuana Dealers �@�l�Ŗ@��̑ݓ|������5.2.3.4.b. 6�Ł�324.04���⎖���E�Ŕ�����16�N12��24�����W58��9��2637�ŁB |
���莖���E���n�����a51�N9��13����22��9��2330��(�e��Ђ��Ԏ��q��Ђɑ��������������ꍇ)���@���9-1-12(����������ɂ����銔���̕]����)
������������8�N10��23������1612��141��(�o�u���o�ϕ���ɔ����I�����Y�Ƃ��Ă̊G��̉��l�\��)
| �����n���ߘa4�N7��14���ߘa2(�s�E)195���Ŏ�272������13732(���p)(��핐����E�W�����X�g1595��148�ŁA�R�{���B�E�Ō�234��86���A�Z�i���ށE�d����5�A172��)�E���������ߘa5�N4��19���ߘa4(�s�R)222���Ŏ�273������13843���p�E�Ō��ߘa6�N1��17�����p�s��(���m�F)�c�c���{���Z�҂w�����p�̃o�[�W�������@�l�f�Ђ̑S������ۗL���Ă���B���Ã��b�g�i�{���D���j�w���y�ёD���ێ��Ǘ���p���ɏ[�Ă邽�ߎ����i4000�����[����j���w�����f�Ђɖ��S�ۖ����q�ő݂��t�����i�{���e�ݕt���j�B�w�͉Ƒ��Ƌ��Ɉ�x�����{���D���ōq�C�����A���̌�A�f�͖{���D������2965���i�w�����i3500�����[���ɑ�2145��7460���[���A61.31���j�Ŕ��p���A����26�N5��1���y��8���A�w�ɍ��v��2789��9950��ٍς����B�w�͈ב֍��v7��1258��8352�~���B����26�N12��2���A�w�͂f�Ђɑ��{���ݕt���̎c���i1989��8924���[���B�{���ݕt�c���j���������|�̒ʒm�������B �{���ݕt�c�������@51��4���u�G�������ׂ��Ɩ��̗p�ɋ�����c�c�鎑�Y�v(�Ɩ����p���Y)�ɂ������u�G�����̊���ƂȂ鎑�Y�v(�G����������Y)�ɂ��Y�����Ȃ��Ɣ��f���ꂽ�B ��tweet�ɂ��ȈՐ����B 1���[��=��100����X����G�Ђ�50m���[��(��50��)��݂�G��50m���[���őD���w���B 1���[��=��120����G���D��30m���[��(��36��)�Ŕ��p��G��X��30m���[��(��36��)�ٍς�X�͑�G�c��20m���[������(�������ނ��ȗ�)�B �S�̂Ł�14���̑������ב։v��6��(30m���[������30������36��)�����ېł���20m���[���̑ݓ|�����͔�T���B |
4.6.2.2. �����p�̎��Y(72��)
����72��(�G���T��)�@���Z�Җ��͂��̎҂Ɛ��v����ɂ���z��҂��̑��̐e���Ő��߂Œ�߂���̗̂L���鎑�Y�i��Z�\����ꍀ�i�����ɒʏ�K�v�łȂ����Y�̍ЊQ�ɂ�鑹���j�c�c�������B�j�ɂ����ЊQ���͓���Ⴕ���͉����ɂ�鑹�����������ꍇ�i���̍ЊQ���͓���Ⴕ���͉��̂Ɋ֘A���Ă��̋��Z�҂����߂Œ�߂��ނȂ��x�o�������ꍇ���܂ށB�j�ɂ����āA���̔N�ɂ����铖�Y�����̋��z�i���Y�x�o���������z���܂ނ��̂Ƃ��A�ی����A���Q���������̑������ɗނ�����̂ɂ���Ă�镔���̋��z�������B�ȉ����̍��ɂ����āu�����̋��z�v�Ƃ����B�j�̍��v�z�����̊e���Ɍf����ꍇ�̋敪�ɉ������Y�e���Ɍf������z����Ƃ��́A���������镔���̋��z���A���̋��Z�҂̂��̔N���̑��������z�A�ސE�������z���͎R�я������z�����T�������B�@��@���̔N�ɂ����鑹���̋��z�Ɋ܂܂��ЊQ�֘A�x�o�̋��z�c�c���ܖ��~�ȉ��ł���ꍇ�c�c�@���̋��Z�҂̂��̔N���̑��������z�A�ސE�������z�y�юR�я������z�̍��v�z�̏\���̈�ɑ���������z
�@��@���̔N�ɂ����鑹���̋��z�Ɋ܂܂��ЊQ�֘A�x�o�̋��z���ܖ��~����ꍇ�@���̔N�ɂ����鑹���̋��z�̍��v�z����ЊQ�֘A�x�o�̋��z�̂����ܖ��~���镔���̋��z���T���������z�ƑO���Ɍf������z�Ƃ̂����ꂩ�Ⴂ���z
�@�O�@���̔N�ɂ����鑹���̋��z�����ׂčЊQ�֘A�x�o�̋��z�ł���ꍇ�@�ܖ��~�Ƒ�ꍆ�Ɍf������z�Ƃ̂����ꂩ�Ⴂ���z�m2�E3�����n
����71���i�G�������J�z�T���m��4.6.4.�������̌J�z�n�j�@�m��\�������o���鋏�Z�҂����̔N�̑O�N�ȑO�O�N���̊e�N�ɂ����Đ������G�����̋��z�i���̍����͎����ꍀ�̋K��ɂ��O�N�ȑO�ɂ����čT�����ꂽ���̂������B�j�́A���߂Œ�߂�Ƃ���ɂ��A���Y�\�����ɌW��N���̑��������z�A�ސE�������z���͎R�я������z�̌v�Z��T������B�m2�E3�����n
����62���i�����ɒʏ�K�v�łȂ����Y�̍ЊQ�ɂ�鑹���j�@���Z�҂��A�ЊQ���͓���Ⴕ���͉��̂ɂ��A�����ɒʏ�K�v�łȂ����Y�Ƃ��Đ��߂Œ�߂���̂ɂ��Ď������̋��z�i�ی����A���Q���������̑������ɗނ�����̂ɂ���Ă�镔���̋��z�������B�j�́A���߂Œ�߂�Ƃ���ɂ��A���̎҂̂��̑����������̑�����N�����͂��̗��N���̏��n�����̋��z�̌v�Z��T�����ׂ����z�Ƃ݂Ȃ��B�m2�����n
���ŗ�178���i�����ɒʏ�K�v�łȂ����Y�̍ЊQ�ɂ�鑹���z�̌v�Z���j�@�@��Z�\����ꍀ�i�����ɒʏ�K�v�łȂ����Y�̍ЊQ�ɂ�鑹���j�ɋK�肷�鐭�߂Œ�߂���̂́A���Ɍf���鎑�Y�Ƃ���B
�@��@�����n�i���̋K�́A���v�̏��̑��̎���ɏƂ炵���ƂƔF�߂�����̗̂p�ɋ��������̂������B�j���̑��˂����I�s�ׂ̎�i�ƂȂ铮�Y
�@��@�ʏ펩�ȋy�ю��ȂƐ��v����ɂ���e�������Z�̗p�ɋ����Ȃ��Ɖ��Ŏ�Ƃ��Ď�A��y���͕ۗ{�m����241.01��胊�]�[�g�z�e�������E�����n������10�N2��24�����^1004��142�Łn�̗p�ɋ�����ړI�ŏ��L������̂��̑���Ƃ��Ď�A��y�A�ۗ{���͊ӏ܂̖ړI�ŏ��L���鎑�Y�c�c
�@�O�@�����̗p�ɋ����铮�Y�ő��\���i���n�����ɂ��Ĕ�ېłƂ���鐶���p���Y�͈̔́j�̋K��ɊY�����Ȃ�����
�Q�@�@��Z�\����ꍀ�̋K��ɂ��A�����ɋK�肷�鐶���ɒʏ�K�v�łȂ����Y�ɂ��Ď������ɋK�肷�鑹���̋��z�����̐��������̑�����N���y�т��̗��N���̏��n�����̋��z�̌v�Z��T�����ׂ����z�Ƃ݂Ȃ��ꍇ�ɂ́A���ɒ�߂�Ƃ���ɂ��B
�@��@�܂��A���Y�����̋��z�����̐��������̑�����N���̖@��O�\�O���O����ꍆ�i���n�����j�Ɍf���鏊���̋��z�̌v�Z��T�����ׂ����z�Ƃ��A���Y�����̋��z�̌v�Z��T��������Ȃ������̋��z������Ƃ��́A����Y�N���̓�����Ɍf���鏊���̋��z�̌v�Z��T�����ׂ����z�Ƃ���B
�@��@�O���̋K��ɂ��Ȃ��T��������Ȃ������̋��z������Ƃ��́A��������̐��������̑�����N�̗��N���̖@��O�\�O���O����ꍆ�Ɍf���鏊���̋��z�̌v�Z��T�����ׂ����z�Ƃ��A�Ȃ��T��������Ȃ������̋��z������Ƃ��́A����Y���N���̓�����Ɍf���鏊���̋��z�̌v�Z��T�����ׂ����z�Ƃ���B�m3�����n
���ŗ�206���i�G���T���̑ΏۂƂȂ�G�����͈͓̔��j3���@�@�掵�\����ꍀ�̋K���K�p����ꍇ�ɂ����āA�����ɋK�肷�鎑�Y�ɂ��Ď������̋��z�́A���Y�����������̒��O�ɂ����邻�̎��Y�̉��z�i���̎��Y�����̊e���Ɍf���鎑�Y�ł���ꍇ�ɂ́A���Y���z���͓��Y�e���Ɍf���鎑�Y�̋敪�ɉ������Y�e���ɒ�߂���z�j����b�Ƃ��Čv�Z������̂Ƃ���B
�@��@�@��O�\�����c�c�ɋK�肷�鎑�Y�i�����y�ё�O���Ɍf������̂������B�j�@���Y�����̐��������ɂ��̎��Y�̏��n���������̂Ƃ݂Ȃ��ē����̋K���i���̎��Y�����Ɍf���鎑�Y�ł���ꍇ�ɂ́A���Ɍf���鎑�Y�̋敪�ɉ������ꂼ�ꎟ�ɒ�߂�K��j��K�p�����ꍇ�����̎��Y�̎擾���Ƃ������z�ɑ���������z�m�C���n�A2���ȉ��A���n�m��COLUMN4-4�ی����E���Q�������̔�ې� �Ɋւ��镽26�����n
| 6�Ł�242.02�u�Г�v�����E�Ŕ����a36�N10��13�����W15��9��2332��gz�c�c�y�n���n�ɂ�����Ȃ�������������̂��߂�300���~�̎x�o���A���n�������z���珜����邩�A���n�o��A�܂��͎G���T���̑ΏۂƂȂ邩(����)�B cf.�L�c���������E���É��n�����a63�N10��31�����^705��160�Łc�c���\�E�����B �����{��k�Ђ̓���(�ȗ�)ff |
| �����n���ߘa6�N1��23���ߘa4(�s�E)372�����p(���{�[��2025�N4��18���d�Ŕ��ጤ�����) �@�����@�ߘa���N10���̑䕗19���ɂ�茴�����Z�ރ}���V�����̈ꎺ�Ɋւ��A��Џꏊ���u�n�����d�ݔ��v�Ƃ��A�Z�Ɠ��̔�Q���u��Z�ƐZ���v�i�Z�ƈȊO�̌��z���ɌW��Z���j�Ƃ����Q�����B���p�����̈ꕔ�Ƃ��Ēn���P�K���͒n��P�K�ɐݒu����Ă����d�C�A�d�b�A�ʐM�y�ы��r�����̐ݔ����i�u�{����Аݔ����v�j���C�U���̑[�u��v�����ԂɂȂ����B��L�����̔�Q�L�^�Ȃ��B�����́u���Q���z�v984��4270�~�y�сu�ی����Ȃǂŕ�U�������z�v0�~����b�Ƃ��āA�G���T���̊z���Z�o���A�\�������B �@���_2:�����Ŗ@72��1���́u�����v�̈Ӌ` �@���_3:�G���T���Ώۑ������z�̎Z�� �@���| �@���_2�u�i�P�j�����Ŗ@�V�Q���P���̎G���T���́A�ЊQ�ɂ�葹���������ꍇ�ɂ́A���̌���̂��߂ɑ����̏o���v���邱�Ƃɔ����A�����ɒS�ŗ͂����E����邱�Ƃɒ��ڂ��Đ݂���ꂽ���x�ł���B �@�����āA���鎑�Y���ЊQ�ɂ���Q�����ꍇ�ɂ����āA�����I���Q�i���Y���Y���̂��̂ɑ��镨���I�Ȕ�Q���璼�ڐ��������Q�j�ɂ��ẮA�ʏ�A�Ď擾���͏C�U�����s�����Ƃɂ�茴����\�ł���A����ɎG���T����F�߂�̂͏�L���x��|�ɂ��Ȃ����A�Ď擾���͏C�U���ɂ�錴������悻�z�肷�邱�Ƃ��ł��Ȃ����̂ɂ��Ă܂ŎG���T����F�߂邱�Ƃ́A�����x��|�ɔ�����Ƃ��킴��Ȃ��B �@�ȏ�ɂ��A�����Ŗ@�V�Q���P���́u�����v�Ƃ́A�ʏ�A�Ď擾���͏C�U�����s�����Ƃɂ�茴����\�ł��镨���I���Q�������A�����I�Ȕ�Q���璼�ڐ��������̂ł͂Ȃ����Q�́u�����v�ɓ�����Ȃ��Ɖ�����̂������ł���B�v �@���_3�u�i�P�j�G���T���Ώۑ������z�́A�u���Y�ɂ��Ď������̋��z�v�i�����Ŗ@�{�s�߂Q�O�U���R���Q�Ɓj�i�`�j�ɁA�����P���Œ�߂��ނȂ��x�o�i�ЊQ�֘A�x�o�B�������A�����Q�����̏Z��ƍ����̌���̂��߂̎x�o�ɂ��ẮA�ЊQ�ɂ�萶�����Z��ƍ����̓����R���ɋK�肷�鎑�Y�ɂ��Ď������̋��z�ɑ������镔���̎x�o�������B�ȉ������B�j�̋��z�i�a�j�������A�ی�������U���z�i�b�j�������������Ƃɂ��Z�肳���i�����Ŗ@�V�Q���A���@�{�s�߂Q�O�U���j�B �@�����āA�O�L�Q�ɂ��A�u���Y�ɂ��Ď������̋��z�v�i�`�j�́A��В��O�̎�������C�ЊQ�ɂ�镨���I���Q�݂̂�]�����ĎZ�肳�ꂽ��В���̎������������������z�ƂȂ邪�A�ʏ�A���̂悤�ɍЊQ�ɂ�镨���I���Q�݂̂�]�����Ĕ�В���̎������Z�肷��͍̂���ł���Ǝv����Ƃ���A�u���Y�ɂ��Ď������̋��z�v�i�`�j�́A���Y���ЊQ�O�̏�Ԃɖ߂����߂ɕK�v�Ȏx�o�ɑ���������z�i�`�f�j������̂ł͂Ȃ��ƍl������B��������ƁA���Y���ЊQ�O�̏�Ԃɖ߂����߂ɕK�v�Ȏx�o�ɑ���������z�i�`�f�j�ƍЊQ�֘A�x�o�̋��z�i�a�j�𖾂炩�ɂ��邱�Ƃ��ł���A�����̍��v�z�i�������A�d�������������B�j�́A�ʏ�A�u���Y�ɂ��Ď������̋��z�v�i�`�j�ƍЊQ�֘A�x�o�̋��z�i�a�j�Ƃ̍��v�z���邱�Ƃ͂Ȃ��B �i�Q�j�؋��i���R�j�y�ѕ٘_�̑S��|�ɂ��A�{���}���V�����ɂ��āA���Y��{���䕗�O�̏�Ԃɖ߂����߂ɕK�v�Ȏx�o�̋��z�i�`�f�j���͍ЊQ�֘A�x�o�̋��z�i�a�j�ɊY��������̂́A���L�A�Ȃ����I�̂Ƃ���ł���A���̍��v�z�́A�R���Q�U�U�T���W�Q�S�S�~�ƂȂ�B�����A�{���ɂ�����ی�������U���z�i�b�j�́A���L�J�̂Ƃ���A�R���R�R�R�R���P�W�U�W�~�ƔF�߂���B�v |
4.6.3. ���v�ʎZ(69��)
����69���i���v�ʎZ�j�@���������z�A�ސE�������z���͎R�я������z���v�Z����ꍇ�ɂ����āA�s���Y�����̋��z�A���������̋��z�A�R�������̋��z�������n�����̋��z�̌v�Z�㐶���������̋��z������Ƃ��́A���߂Œ�߂鏇���ɂ��A����𑼂̊e�폊���̋��z����T������B�Q�@�O���̏ꍇ�ɂ����āA�����ɋK�肷�鑹���̋��z�̂����ɑ�Z�\����ꍀ�i�����ɒʏ�K�v�łȂ����Y�̍ЊQ�ɂ�鑹���j�ɋK�肷�鎑�Y�ɌW�鏊���̋��z�c�c�̌v�Z�㐶���������̋��z������Ƃ��́A���Y�����̋��z�̂������߂Œ�߂���̂͐��߂Œ�߂�Ƃ���ɂ�葼�̐����ɒʏ�K�v�łȂ����Y�ɌW�鏊���̋��z����T��������̂Ƃ��A���Y���߂Œ�߂���̈ȊO�̂��̋y�ѓ��Y�T�������Ă��Ȃ��T��������Ȃ����̂͐����Ȃ������̂Ƃ݂Ȃ��B
����69��1���͕s���Y�A���ƁA�R�сA���n�����ɌW�鑹���̂���B
���������������Ȃ��c���q�A���^�A�ސE�^���������������邪���v�ʎZ�s�c�z���A�ꎞ�A�G
���Z�敨����ɌW�鑹�����G�����ɌW�鑹���ł���Ƃ��đ��v�ʎZ��ے肷�邱�Ƃ��A���@29�E22���Ɉᔽ���Ȃ��Ƃ�������Ƃ��āA�����������a54�N7��17����25��11��2888�ŕS�I7��49es
| 6�Ł�241.01��胊�]�[�g�z�e�������E�����n������10�N2��24�����^1004��142�Ŋm��nk �����E���_�@���^�����ғ��҂w�����ό����烊�]�[�g�z�e��(�{������)�̈ꎺ���w��(�ړI�͐ߐłƓ��@)���A���ό��ɑ݂��t���A����(�s���Y����)��(����sale & lease back)�B�w�́A�s���Y�����ɌW���p(����������p��)�̂��ߑ������������Ƃ��āA���v�ʎZ���咣�B�x�Ŗ������́A�{�������͏����Ŗ@69��2���E62��1���́u�����ɒʏ�K�v�łȂ����Y�v�ɓ�����Ƃ��A���v�ʎZ��۔F�B ���|�@�P�@�@69��2���̎�|�@�c�u�����v�ł��邩��B �@�w�́u�ۗ{�v�ړI�Ŗ{�����������L���Ă����ƔF��B �@(��)�u�ۗ{�v���u��v���鏊�L�ړI�ł��������H�@���������́u�{�������̗��p�ɂ�闘�v�̋���Ɣ�r���ĕ����I�Ȃ��̂Ƃ݂�����v�@�u��Ƃ��ĕۗ{�̗p�ɋ�����ړI�ŏ��L���Ă����v�ƔF��B �@(�O) �w�́u�ߐŌ��ʂɒ��ڂ��Ă����v�B�������ߐŌ��ʂ́u�����I�o�ό��ʂɂ����Ȃ��v�B�u�����ɒʏ�K�v�łȂ��s���Y�ɊY�����邩�ǂ����́A�q�ϓI�ɂ݂ē��Y�s���Y�̖{���̎g�p�A���v�̖ړI�������ɂ���Ĕ��f���ׂ��v�@�u�ߐŌ��ʁc����v�Ȕ��f�v�f�c�Ƃ��邱�Ƃ͖{���]�|�v �⑫�@���ŗ�178��1��2���̐����ɒʏ�K�v�łȂ��s���Y�ɊY�����邩�́A�q�ϓI�����Y�s���Y�̖{���̎g�p�A���v�̖ړI�������ɂ���Ĕ��f���ׂ��ł���A�ߐŌ��ʂ������邩�ǂ�������v�Ȕ��f�v�f�Ƃ��邱�Ƃ͖{���]�|�ł���Ƃ����ʂ̍ٔ���Ƃ��āA�{���Ɠ��������ɂ������f��������䍂������13�N4��24���Ŏ�250������8884������(���R�����n������11�N12��10���Ŏ�245��662�ł͋t�̌��_�ł�������)�B cf.���\��u�@�l�i�����́w����x�Ɋւ����l�@�v�W�����X�g1423��106�Łc�c�{������ېŏ����ɑΉ������p�̍T����F�߂Ȃ��Ƃ����ł������ł���B���z�_�Ƃ��ẮA�ېŏ����ɑΉ�����T���\�ȕ����Ɣ�ېŏ����ɑΉ�����T���s�\�ȕ����Ƃ̈��Ƃ������Ƃ��l������B |
|
6�Ł�222.03�T�����[�}���E�}�C�J�[�i���E�Ŕ�����2�N3��23������1354��59�ŕS�I5��49gn ��R�_�˒n�����a61�N9��24������1213��34�ł�����9��2��1���ɂ�茴���̐��������p�����B �T�i�R�ȍ~�͌��_�����Ȃ���69�E62���Ɉˋ������̂Ŋ�胊�]�[�g�z�e�������Ɠ����B ����9��2��1���͑��v�ʎZ�̘b�ł͂Ȃ����A�����ɒʏ�K�v�ȓ��Y(9��1��9��)�Ɋւ�����n�v����ې�(�����s�Nj�)�ł��邱�ƂƂ̑Ώ̂ŁA�����ɒʏ�K�v�ȓ��Y�Ɋւ������n��(9��2��1��)���T���ł��Ȃ��B ���ŗ�25���i���n�����ɂ��Ĕ�ېłƂ���鐶���p���Y�͈̔́j�@�@��9���1����9��(��ېŏ���)�ɋK�肷�鐭�߂Œ�߂鎑�Y�́A�����ɒʏ�K�v�ȓ��Y�̂����A���Ɍf�������(����͈�g�̉��z��30���~������̂Ɍ���B)�ȊO�̂��̂Ƃ���B �@��@�M�A���M�A�M�����A�^��y�т����̐��i�A�ׂ������i�A�����i�A���͂����i�A���������i���тɎ��i �@��@����A���Ƃ��y�є��p�H�|�i |
�@���v�ʎZ�Ɋւ��A�������p����z�̎��Y(�Ⴆ�Ό����A�D���A�q��@�A�f�擙)(��6�Ł�143.04�p���c�B�[�i�����i�t�B�������[�X�����j�E�Ŕ�����18�N1��24�����W60��1��252��)�̏��L�������w������Ƃ����^�C�v�̎��Ă����ƂȂ�B
�@�����x�������p���K�p����鎞��200(5�N�Ԏg���邪2�N�Ԃŏ��p�ł���Ƃ���)�̋@�B���`����1�N�x�ɍw����������1�N�x�̎��v(�������p�l���O)��70�ł������Ƃ���B���Ə�����70�|100���|30�ƂȂ��Ă��܂��̂ŁA�`�͌������p��̃}�C�i�X�𗘗p������Ȃ��B�`�ɑ��̏������ނɌW�����������Ȃ�A�Ⴆ�`�����ɋ��^���������Ă���Ȃ�A�`�̎��Ə����ɌW��30�̑������A���^�����̋��z����T�����鑹�v�ʎZ������悢�B�������A�`�ɂ͑��v�ʎZ�Ɏg����v���Ȃ��Ƃ������Ƃ�����B�������̌J�߂��E�J�z��(��4.6.4.)�ł��`���}�C�i�X�𗘗p������Ȃ��Ƃ������Ԃ������B
�@�`�����l�̋@�B������200�ő�1�N�x�ɍw����������ɁA���Ƃ��c�܂Ȃ��a�ɓ��Y�@�B�����n���A���Y�@�B���a����`�������Ă`�����Ƃ��c�ނƂ���B�`����1�N�����5�N�ɂ����Ė��N70�̎��Ə����ɌW������āA���N40�̒��ؗ����a�Ɏx�����i�`�ɑ��ɕK�v�o��͂Ȃ��j�Ƃ���ƁA�`�̖��N�̎��Ə����̌v�Z��70�|40��30�ƂȂ�(�����x�������p�ł͂Ȃ�5�N�����Ē�z�@�ŏ��p���Ă����Ƃ����ꍇ�̌������p������N40���ł��邩��A�`�����珊�L����5�N�Ԓ�z�@�Ōv�Z�����ꍇ�Ɠ��l�ɂȂ�)�B��1�N�x�̌������p��100�͋@�B�̏��L�҂ł���a���v�シ��B�a�ɂ͂`������������40�ȊO�Ɏ��Ə���(�D�����ł���Εs���Y����)�ɌW��������Ȃ���������Ȃ����A�a�ɑ��ɏ[���ȏ���(�Ⴆ���^����)������A���v�ʎZ��ʂ��Ăa�͌������p��100�Ƃ����d�ő����𗘗p�����̏����ɂ�����d�ŕ��S�����炷���Ƃ��ł���B
����72���G���T����4.6.2.2.�B
4.6.4. �������̌J�߂��E�J�z��(140�E70��)
|
����140��1��:�F�\���҂��������̌J�ߊҕt�B �@(�@��80����5.2.4.) ����70��1��:�������̌J�z�T��(2��:���F�\���Ҍ���) �@(�@��57����6�Ł�325.05) |
������������30�N3��8����64��12��1794�Łc�c�A�N��o�v��
������������30�N8��1����65��4��696�Łc�c�������������Ō�̊�����\���B
4.6.5. �����T��(����72�`86��)
4.6.5.1. �����T���̑�܂��ȕ���
����72���`78���F�x�o�E�����ɒ��ځB�G���T��(��4.6.2.2.)�A��Ô�T��(��COLUMN4-4)�A�Љ�ی����T���A���K�͊�Ƌ��ϓ��|���T���A�����ی����T���A�n�k�ی����T���A���T��(�͕�I�����T�O�̉��Ō����Ƃ��ď���Ɠ��������B�����I�ɍT���Ƃ����D����^����B�D�����ۂ����߂���_�킪����B)����79�`86���F�l�I����ɒ��ځB��Q�ҍT���A�Ǖw(�Ǖv)�T���A�ΘJ�w���T���A�z���(����)�T��gd�A�}�{�T���A��b�T��
�Ǖw�T���Ǖv�T�����ʍ������f�Ƃ��������n���ߘa3�N5��27���ߘa��(�s�E)236���Ŏ�271������13570�E���������ߘa4�N1��12���ߘa3(�s�R)166���Ŏ�272������13653�m��B�ޗ�Ƃ��Ĉ⑰�⏞�N�������ʍ������f�F�Ŕ�����29�N3��21���W��255��55�ŕ���27(�s�c)375���B
��b�T���z �ߘa6�N�ȑO�A�ߘa7�`8�N�A�ߘa9�N�ȍ~(���������^���������̏ꍇ)(�p���t)
| ���^�������z | �������z | �ߘa6�N�ȑO | �ߘa7�`8�N | �ߘa9�N�ȍ~ | 200��3999�~�ȉ� | 132���~�ȉ� | 48���~ | 95���~ | 58���~ |
| 200��3999�~���`475��1999�~�ȉ� | 132���~���`336���~�ȉ� | 48���~ | 88���~* | 58���~ |
| 475��1999�~���`665��5556�~�ȉ� | 336���~���`489���~�ȉ� | 48���~ | 68���~* | 58���~ |
| 665��5556�~���`850���~�ȉ� | 489���~���`655���~�ȉ� | 48���~ | 63���~* | 53���~ |
| 850���~���`2545���~�ȉ� | 655���~���`2350���~�ȉ� | 48���~ | 58���~ | 58���~ |
| 2545���~���`2595���~�ȉ� | 2350���~���`2400���~�ȉ� | 48���~ | 48���~ | 48���~ |
| 2595���~���`2645���~�ȉ� | 2400���~���`2450���~�ȉ� | 32���~ | 32���~ | 32���~ |
| 2645���~���`2695���~�ȉ� | 2450���~���`2500���~�ȉ� | 16���~ | 16���~ | 16���~ |
| 2695���~�� | 2500���~���� | 0�~ | 0�~ | 0�~ |
4.6.5.2. �Ƒ��Ɋւ��鏊���T��(����83���`84��)
����83���A83����2�̔z��ҍT���E�z��ғ��ʍT���́A����2�{�T���Ƃ��Ĕᔻ�𗁂т����Ƃ����������A�i�K�I�T�������[�u�ɕω������B���̌���A�������v�w�ɂƂ��Ĕz��ҍT�����͉��烁���b�g�łȂ�����p�~���ׂ��Ƃ����ӌ����������������A�����A�v�w�̕}�{�`��(���@752��)�Ɋӂ݂Ĕz��ҍT�������Ȃ������Ƃ͂��������Ƃ������_���������B����29�N�����ŁA���Ǝ�w�^�v�̒��J���A�J�j�Q���ʂ���߂�ׂ�(���{�̌l�P�ʎ�`�͓�擙�Ɣ�ׂĒ��J���A�J�j�Q���ʂ����X�ア����ǂ�)�A�z��ғ��ʍT�����g�[�����B�����āA�单���̏�����900���~����ꍇ�ɔz��ҍT������i�K�I�ɏ��������邱�ƂƂ��čĕ��z������}�����Bcf���}�r��=���Η����u�ېōŒ���u103���~�̕ǁv���グ�ɂ��ƌv�ƍ����ւ̉e�����Z�F��b�T����75���~���グ��Ɩ�7.3���~�̌����v(��a�����A2024.11.5)�A���䍎�F�u103���~�̕ǂ�����c�_�̓^���v�Ō�41��1��(241��)30-38��(2025.5)
�ߘa7�N�����O�Ɖ�����̉Ƒ��֘A�����T��
| �T���̖��O | �����O | �����O | ������ | ������ |
| �z��ҍT�� | �������z48���~�ȉ� | 38���~ | �������z58���~�ȉ� | 38���~ |
| �z��ғ��ʍT�� | �������z48���~���`133���~�ȉ� | 38���~�`3���~�֑Q�� | �������z58���~���`133���~�ȉ� | 38���~�`3���~���Q�� |
| �}�{�T�� | �������z48���~�ȉ� | ���38���~�A����63���~�A�����V�e58���~�A�����V�e�ȊO�̘V�l48���~ | �������z58���~�ȉ� | ���38���~�A����63���~�A�����V�e58���~�A�����V�e�ȊO�̘V�l48���~ |
| ����e�����ʍT��(19�Έȏ�23�Ζ����̕}�{�e���ŐF��]�҂łȂ���) | �V�� | �V�� | �������z58���~���`123���~�ȉ� | 63���~�`3���~���Q�� |
| ��Q�ҍT�� | �������z48���~�ȉ� | ��Q��27���~�A���ʏ�Q��40���~�A�������ʏ�Q��75���~ | �������z58���~�ȉ� | ��Q��27���~�A���ʏ�Q��40���~�A�������ʏ�Q��75���~ |
| �Ǖw�T�� | �}�{�e���̏������z48���~�ȉ� | 27���~ | �}�{�e���̏������z58���~�ȉ� | 27���~ |
| �ЂƂ�e�T�� | �q�̏������z48���~�ȉ� | 35���~ | �q�̏������z58���~�ȉ� | 35���~ |
| �ΘJ�w���T�� | �������z75���~�ȉ� | 27���~ | �������z85���~�ȉ� | 27���~ |
| 6�Ł�242.01�������u�z��ҍT���v�i���E�Ŕ�����9�N9��9����44��6��1009�ŕS�I7��50cr ���| �u�w�z����x�́A�[�ŋ`���҂Ɩ@����̍����W�ɂ���҂Ɍ�����v �Ŕ�����3�N10��17����38��5��911��eh�c�}�{�e��(����84���A2��1��34��)�Ɋւ��āA�ΏۂƂȂ�e���͖��@��̐e���Ɍ�����B �ؗp�T�O��3.1.2.2.�@���@�̍u�`�ŁA�����W�͊T�˖@�����Ɠ��l�Ɉ�����悤�ɂȂ��Ă���A�Ƌ���邪�A�����ƐŐ��Ɋւ��Ă͓��l�̈����łȂ��B cf.�Ŗ��s�������i�Љ�ۏ�@�͓����̕v�w��v�w�������邱�Ƃ������jge�A�@�I���萫�������̔z��҂�r��������قǏd�v���A��l�̗]�n�͂���B cf.�v�w�ʐ��i�ő匈�ߘa3�N6��23���W��266��1��mw(��\��E�W�����X�g1565��91-96�ŁA�E�c�[���E�W�����X�g1565��97-102��)�c�c���@750���A�ːЖ@74��1�������@24���Ɉᔽ���Ȃ��B�⑫�ӌ��A�ӌ��A���Έӌ�����j�E�������҂��~�ς��Ȃ����Ƃ̗��@�_��̐���H���o�^���A���Ȃ�J�덥�����x�P�p�H cf.�D�y�n���ߘa5�N9��11���ߘa3(��)1175��(�n糑וF�u�����J�b�v���́u�����㍥���W�Ɠ��l�̎���ɂ���ҁv�ɓ����邩�v�V�E������Watch���@�i�Ƒ��@�jNo.149 2023.11.10)�c�c�����J�b�v����鸂��X���E���̋��^�Ɋւ�����9��2��1���u�͏o�����Ȃ��������㍥���Ɠ��l�̎���ɂ���ҁv�ɓ�����Ȃ��B�}�{�蓖�s�x���B |
4.6.5.3. �����T���A�Ŋz�T���A�蓖
�����T�������͒�ŗ��҂ɒჁ���b�g�B���Ŋz�T�������ɂ��ׂ����Hgc������\��N�x���ɂ�����q�ǂ��蓖�̎x���Ɋւ���@�����q�ǂ��蓖������24�N4��1�����������蓖
4.7. �l�Z����
4.7.1. �n�������c�̂̌l�Ɋւ���Ō�ha
4.7.2. �[�ŋ`����
4.7.3. ���q���E�z�����E���������n������
4.7.4. ���Ɛ�
4.8. ������
4.8.1. �F�\��(����143���A166��)hb
4.8.2. �X���̐���(����152���A�Œ�23��)
4.8.3. ����(����181���ȉ�)
�����[�t�F�[�ŋ`���҈ȊO�̎҂ɑd�ł������[�t������B�����i�n���łł����ʒ����j���T�^�B| 6�Ł�250.01���m��ʎ����E�Ŕ����a45�N12��24�����W24��13��2243�ŕS�I7��114ei�c�c�����m��B �u�����̑ΏۂƂȂ�ׂ������̎x�����Ȃ����Ƃ��́A�x���҂́A�@�߂̒�߂�Ƃ���ɏ]�ď����ł����č��ɔ[�t����`���c�c���̂ł��邪�A���̔[�ŋ`���͉E�̏����̎x���̎��������A���̐����Ɠ����ɓ��ʂ̎葱��v���Ȃ��Ŕ[�t���ׂ��Ŋz���m�肷����̂Ƃ���Ă���i���Œʑ��@����c�c�j�B���Ȃ킿�A�����ɂ�鏊���łɂ��ẮA�\���[�ŕ����ɂ��ꍇ�̔[�Ŏ҂̐Ŋz�̐\���₱������邽�߂̐Ŗ��������̏����i�X���A����j�A���ۉېŕ����ɂ��ꍇ�̐Ŗ��������̏����i���ی���j�Ȃ����āA���̐Ŋz���@�߂̒�߂�Ƃ���ɏ]�ē��R�ɁA����Ύ����I�Ɋm�肷����̂Ƃ����̂ł���B�v �u�����ɂ�鏊���łɂ��Ă̔[�ł̍��m�́A�ېŏ����ł͂Ȃ����������ł��āA�x���҂̔[�ŋ`���̑��ہE�͈͉͂E�����̑O���肽��ɂ����Ȃ�����A�x���҂ɂ����Ă���ɑ���s���\���Ă������A�܂��͕s���\���Ă����Ă��ꂪ�r�˂��ꂽ�Ƃ��Ă��A�҂̌���[�ŋ`���̑��ہE�͈͂ɂ͂����Ȃ�e�����y�ڂ�������̂ł͂Ȃ��B�������āA�҂́A�����ɂ�鏊���ł�����܂��͊�����ɔ[�t�����x���҂���A���̐Ŋz�ɑ���������z�̎x���𐿋����ꂽ�Ƃ��́A���Ȃɂ����Č���[�ŋ`����Ȃ����Ƃ܂��͂��̋`���͈̔͂𑈂āA�x���҂̐����̑S���܂��͈ꕔ�����ނ��Ƃ��ł�����̂Ɖ������i�x���҂��E�̒����܂��͔[�t�̎��Ȍ�ɂ����Ď҂Ɏx�����ׂ����z����E�Ŋz�����z���T�������Ƃ��́A���̑S���܂��͈ꕔ�ɂ�����[�ŋ`���̂Ȃ����Ƃ��咣����҂́A�x���҂ɂ����Ė@���㋖�e���ꂦ�Ȃ��T�����Ȃ��A���̎c�z�݂̂��x�����͍̂��̈ꕔ�s���s�ł���Ƃ��āA���Y�T���z�ɑ���������̗��s�𐿋����邱�Ƃ��ł���j�B�v cf.������Ќ����������E�ő唻���a37�N2��28���Y�W16��2��212�ŕS�I7��113fy�c�c�������x�͌��@29��(���Y���ۏ�)�A14��(��������)�A18��(�z��I�S���֎~)�Ɉᔽ���Ȃ��B �����f�Վ����E�Ŕ�����4�N2��18�����W46��2��77��(���^�x���҂̌����̌��)��2.3.2.2.a. |
�S��ނ̌���(��3�����̂�����)
(1)���q�������������ې��c�c�m��\���s�v�B
(2)���^�����̌����c�c�N�������ő����̏ꍇ�m��\���s�v�B(ex.��Ȃ͔��̑�w����������^�����̂Ŋm��\�����Ă��܂�)lp
(3)�ސE�����̌����c�c�N�������͂Ȃ��������̏ꍇ�\���s�v�B
(4)��V���̌����c�c�m��\���Œ�������B(ex.��Ȃ��o�ŎЂ����錴�e����)
6�Ł�141.01�z�X�e�X��V�v�Z���Ԏ����E�Ŕ�����22�N3��2�����W64��2��420�Ł�3.1.1.3.
| 6�Ł�250.02�x�����̖����ƌ����`���@�N���J�O���[�v������㍐�R�����E�Ŕ�����30�N9��25�����W72��4��317�ŕS�I7��116hl(��3.1.2.4.���@����Ƒd�Ŗ@)(���{�ʁE�d����30�N195�ŁA�O������E�W�����X�g1533��128��) �@��ꎟ�㍐�R�E�Ŕ�����27�N10��8�����^1419��72��(�蕔�T�T�E�d����27�N203��)�́A�����\�͂̂Ȃ��Вc�̗������y�ѐꖱ�����̒n�ʂɂ������҂����Y�Вc����̎ؓ������̖Ə����邱�Ƃɂ�蓾�����v���A����28��1���ɂ����ܗ^���͏ܗ^�̐�����L���鋋�^�ɓ�����A�Ƃ����B �@���ߌ�A���Ə��̍��떳���i�����@���ō���͎�����R�j�咣�ɂ�茹���[�t�`����Ƃ�邩�����_�ƂȂ����B ���|�@�u���^�����ɌW�錹���ł̔[�t�`���𐬗�������x���̌����ƂȂ�s�ׂ������ł���C���̍s�ׂɂ�萶�����o�ϓI���ʂ����̍s�ׂ̖����ł��邱�ƂɊ�����Ď���ꂽ�Ƃ��́C�Ŗ������́C���̌�ɓ��Y�x���̑��݂�O��Ƃ��Ĕ[�ł̍��m�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ����̂Ɖ������B�����āC���Y�s�ׂ�����ɂ�薳���ł��邱�Ƃɂ��āC���̊��ԓ��Ɍ�����떳���̎咣�����邱�Ƃ��ł���|���߂�@�߂̋K��͂Ȃ��C�܂��C�@��[�����̌o�߂ɂ�茹���ł̔[�t�`�����m�肷����̂ł��Ȃ��B���������āC���^�����ɌW�錹���ł̔[�ō��m�����ɂ��āC�@��[�������o�߂����Ƃ����ꎖ�������āC���Y�s�ׂ̍��떳�����咣���Ă��̓K�ۂ𑈂����Ƃ�������Ȃ��Ƃ��闝�R�͂Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���B �T�@�ȏ�ƈقȂ錩���̉��ɁC�㍐�l���@��[�����̌o�ߌ�ɖ{�����Ə��̍��떳�����咣���邱�Ƃ͋�����Ȃ��Ƃ������R�̔��f�ɂ́C�@�߂̉��ߓK�p���������@��������̂Ƃ��킴��Ȃ��B�������Ȃ���C�㍐�l�́C�{�����Ə�������ɂ�薳���ł���|�̎咣��������̂́C�c�c�[�ō��m�������s��ꂽ���_�܂łɁC�{�����Ə��ɂ�萶�����o�ϓI���ʂ����̖����ł��邱�ƂɊ�����Ď���ꂽ�|�̎咣�����Ă��炸�C���������āC�㍐�l�̎咣�������Ă��ẮC�{���e��������@�ł���Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B��������ƁC�{���e�������K�@�ł���Ƃ������R�̔��f�́C���_�ɂ����Đ��F���邱�Ƃ��ł���B�v �Ȃ��A�\���[�łɊւ����J�a�q�����E�Ŕ�����2�N5��11����37��6��1080�ł́A���n�_��ɂ����n�����́A�_��̍��Ӊ���������ł��Ȃ��A�Ƃ������A�\���[������̍��떳���̎咣�̓K�ۂɂ��Ă͖��L���ĂȂ��B ���É��n������29�N9��21���Ŏ�267������13064����27(�s�E)125��(�����p���E�W�����X�g1540��107��)�c�c�ސE���ԊҎ��̌����Ŋҕt�����̎����̋N�Z�_�B |
| �Ŕ�����23�N1��14�����W65��1��1�ŕS�I7��118in(�Óc�F�v�E�W�����X�g1432��100�ŁB�H�c�Y�����g������E2012�N6��8�����������������ጤ����B���\��E�����2136��170�ŁG���\��u�j�Y�Ǎ��l�̌����`���ƌ����ō��̗D�揇�ʁ\�\�A�����J�@��f�ނƂ�����l�@�v�@������84��3��78-87��) �j�Y��Ђ̊Ǎ��l�����J���҂��ސE��(�O�L(3)�̗ތ^)���x�����ۂɌ����`�����Ǎ��l�ɂ͖����Ɣ��f�����B �@([���]�j�Y�ƊE�̊���ɍō��ق��Ë��������̂ŁA�d�Ŗ@�w�̗������炷��Ƃ��Ȃ��قȔ��f�Ɍ����邪�A�ō��ق��������̂�����d���Ȃ�) �@���@�Ǎ��l���Ǎ��l���g�Ɏx�����Ǎ��l��V(�O�L(4)�̗ތ^)�ɂ��Ă͌����`��������B |
| �Ŕ�����23�N3��22�����W65��2��735�ŕS�I7��117ld(�����]�m�S�E�W�����X�g1424��88��) ���^���̎x��������҂́A���̎x���𖽂��锻���Ɋ�Â��������s�ɂ�肻�̉������ꍇ�ł����Ă��A����183��1������̌����`�����B (�j�Y�̏ꍇ�̕���23�N1��14�������A�ʎ��s�̏ꍇ�̕���23�N3��22�������ŁA���_���Ⴄ���Ƃɗ��ӁB) |
| �����n������28�N5��19���Ŏ�266������12856����26(�s�E)114���S�I7��73(�T�i�R������������28�N12��1���Ŏ�266������12942����28(�s�R)219���Ŋm��)(�ޗ�E�����n������23�N3��4���Ŏ�261������11635����21(�s�E)121���S�I6��68)�c�c�Z�҂������s���Y�����n����ۂ̔���̌����`���B |
COLUMN4-7 �V�F�A�����O�E�G�R�m�~�[(Sharing Economy�BGig Economy�Ƃ�����)
5. �@�l�̏����ېŁ\�\�@�l�łƒn����
5.1. ���z��̂Ƃ��Ă̖@�l
5.1.1. �@�l�ł̈Ӌ`
�@�l���ݐ����Љ�I���̂Ƃ��Ă̖@�l���̂̒S�ŗ͂ɑ���Ǝ��̐łƂ��Ė@�l�ł��ʒu�t����B�@�l�[�������@�l�͐l�̏W���ɂ������A�@�l�ł͌l�����ł̑O���ł���ƈʒu�t����Bcc
�@�l�Ƃ́c�c�l�̏W�܂�ɂ������A�����`���̋A����̂Ƃ��Đl�H�I�ɍ��ꂽ���̂ł���ɂ����Ȃ��Bcb
���@�l���̂����p��������킯�ł͂Ȃ��̂ŁA�@�l�ł��ۂ��Ă��@�l���̂̑d�ŕ��S�Ƃ͂Ȃ肦�Ȃ��B
���@�l�ɉېł���̂ł͂Ȃ��l�����ɉېł���̂��d�Ő���̖{���B
�����A�@�l�ɉېł��Ȃ�(����������ېŁ����̌o�ϓI�������ېŌJ��)�Ȃ�Ζ@�l���Ƃƌl���ƂƂ����I�ł���B
���@�l�ɉېł��Ȃ��ƐV���Ȕ��������܂�Ă��܂��̂ʼnېł��邪�A�@�l���̂̒S�ŗ͂������ĉېł��Ă���̂ł͂Ȃ��A�l�����ł̑O����Ƃ��Ė@�l�ł��ۂ���Ă���B(���Ղ��Ƃ��납����)
�����ۓI�����̕����ɂ���������n�ې��Ƃ��Ă̖@�l�ŁBco
[���W]�@�l�ł��]�����A���ɂ���
�@�P���ɍl����A�@�l�ł͊���ɑ���ېłł���悤�Ɏv����B�������o�ϓI�Ȏ��̂Ƃ��āA���i�̉��i�㏸�Ƃ����`�œ]��(�O�]�Ƃ���)������A�]�ƈ��̋��^������ؓ������q�̌����Ƃ����`�œ]��(��]�Ƃ���)������A�Ƃ������Ƃ����肤��B����̑S���S�Ƃ������S�Ƃ��f����B�N�̕��S�����o�ϓI�Ɍ����Ɋώ@���邱�Ƃ͍���B�������A�]���̖@�l�ł̋c�_�ł��@�l�ł̕��S����犔��ɓ]�ł���Ƃ����O�����̂��Ă���B
��������Ă��Ȃ��ېŕ����ɂ�����
�@B/S�ݎؑΏƕ\�@�@�@�@�@�@�@���ېŁ@�@�@�@���ې�
�@���������������@�@�@�@�@�@���������@
�@���@�@���@�@�����q�@�@�@�@���@�l�������ˁ@����
�@���@�@�������ˋ�s�@�@�@���������z��
�@�����Y���@�@���ˎЍ���
�@���@�@���������@�@�@�@�@�@����ېŁ@�@�@���ې�
�@���@�@���@�@���z���@�@�@�@���������@
�@���@�@�����{���ˊ���@�@�@���g���������ˁ@�g����
�@���������������@�@�@�@�@�@�����������v���z
��Ђ̎������B�\�\debt/equity�̑I���y�ёg�D�`�Ԃ̑I���ɂ��������(��d�ېŁ�����)cf
debt����:��s��Ѝ��҂���̎����B���q�͖@�l�̏����v�Z��T�������B���@�l�i�K�ʼnېł���Ȃ��B
equity���Ȏ��{:���傩��̏o���B�z���͖@�l�̏����v�Z��T������Ȃ��B���@�l�E�����d�ې�
����Ƃ����ƌ`�Ԃ̑I����c�߂�B�c�g���L���B
���z��������c�߂�B�c�����������L���B
���@�l�����Ȏ��{�䗦���������������Ă��܂��A�|�Y�m����s�����ɍ��߂Ă��܂��B
| �Ƃ��낪�A�@�l�ېł��������L���ɂȂ��ʂ�����B |
(1)�ېŌJ��cg (2)�������� (3)���^�����T�� |
�@���̐헪�F�l���ň����10000�𓊎��B1�N�ڂ̐ň��O���v��1000�A�Ŋz��700�A�ň�����v��300�B�茳�Ɏc����10300���ē����B2�N�ڂ̐ň��O���v��1030�A�Ŋz��721�A�ň�����v��309�B�茳�Ɏc����10609���ē����c�c�Ƃ����菇���J��Ԃ��B���ǂ̂Ƃ���ېłȂ��̐��E�Ŏ��v��3%�k��10%�~(1�|0.7)�l�ŔN������2�N�ԉ^�p�����ꍇ�̌��ʂƓ����B�܂�10000�~1.03^2��10609�B20�N�ڂ�10000�~1.03^20��18061�B�]�kac
�@���̐헪�F�l���ň����10000���o�����Ė@�l��ݗ��B�@�l��10000�𓊎��B1�N�ڂ̐ň��O���v��1000�A�Ŋz��200�A�z���\���v��800�B�z�����Ă��܂��ƁA����i�K�ōX��560�̉ېŁB�l�̎茳�Ɏc��̂�240(���ꂪ�@�l�E�l�̓�d�ې�)�B�z���������������������N�ē����ɉB10800�𓊎�����A2�N�ڂ̐ň��O���v��1080�A�Ŋz��216�A�ň�����v��864�A�@�l�̎茳��11664�c��B���ǂ̂Ƃ���ېłȂ��̐��E�Ŏ��v��8%�k��10%�~(1�|0.2)�l��2�N�ԉ^�p�����ꍇ�̌��ʂƓ����ł���B�܂�10000�~1.08^2��11664�B20�N�ڂ�10000�~1.08^20��46610�B�z���\���v��36610�A�����S�Ĕz������ƁA����i�K��70%�̉ېł���̂ŁA�ň��㏊����10983�B
�@���̐헪�ƑΔ䂷��ƁA���̐헪�ł͓�d�ېł���Ƃ����s���v�����邪�A�@�l�i�K�ŒႢ�ŗ������ېŌJ�������邱�Ƃ̗��v����d�ېłɂ��s���v���������̂ł���B
�@��O�̐헪�F�������n�v�ɌW��l�����ŗ�������(35��)�ł���Ƃ���B���̐헪��20�N�ڂɊ��傪���������n�B10000���o�����ē���������46610�Ŕ�����̂ŁA���n������36610�ł���B35%�̐ŗ����K�p�����ƁA�ň��㏊����23797�ł���Bch
(2)�@�@�l�����ɂ�鏊�������@���@�����ݐi�ŗ��̉��
�@����56���F�Ƒ��]�ƈ����ւ̎x�����ɂ��Čo��̎Z����ے肵�A����������h���B
�@(����57���F�F��]�ҍT���c���̗v���̉��ʼnƑ��]�ƈ��ւ̋��^�x�����o��ɎZ���Bci)
�@����56����E�̂��ߖ@�l��ݗ����A�@�l����]�ƈ��ɋ��^���x�����A�Ƃ����@�`���ŁA���������\�B
| (�m�F���F���̏ꍇ�̖@�l�E�l�̓�d�ېł̖��́H) |
(3) ���^�����T���̗��p
�@�l�i�K�̏����v�Z�F�]�ƈ��ւ̋��^�x���������Z��
�l�i�K�̏����v�Z�F���^�����T���ɂ����ۂ̌o���葽�߂ɔ�p���F�߂���B
�l���Ƃ̏ꍇ�A�������g�ւ̋��^�x���͕K�v�o��ɂȂ炸�A���Ə����Ƃ��Ď��ۂ̔�p�����T���B
| 6�Ł�311.02 �w�}�[���[�Y�E���r���[�x(Mirrlees Review)or���q�G�_���u�@�l�łƏ����ł̓����vcjcm �N���V�J���E�V�X�e��(classical system)(��������):�@�l�E����̓�d�ېł���u�B �g������(partnership method):�@�l�ł��Ȃ����S�Ċ���i�K�ɏ������Ŗ����A�������ĉېŁB�����܂ŐŖ���ł�����ۂɕ��z���邩�ۂ��͖��W�B���݂ł��A�g���Ȃǖ@�l�ł�������Ȃ��@�`�����Ƃ�ꂽ�ꍇ�́A���ɑg�������̍\�����ɑ��ď����ł��ۂ����̂݁B���s������������B �������L���s�^���Q�C���ې������F�������ۂɂ�銔���㏸���ɂ�����i�K�ʼnېł���B�������������ۂ݂̂f���Ă����ł͂Ȃ��Ƃ������_������B �x���z�������Z������(dividend-paid deduction method)�F�@�l���z�����x���������ɁA�@�l�̏����v�Z�ɂ����čT����F�߂�B���݂̗��q�̈����Ɠ����B�������ە����ɂ��Ă͓������Ȃ���Ȃ��B ��d�ŗ�����(�x���z���y�ە���)�F�@�l�̏����̂����z���ɏ[�Ă������̖@�l�ŗ���Ⴍ����B �z�������T������(dividend-received deduction method)�F���傪�z��������Ă��A����i�K��(�S�����͈ꕔ��)�����Ɋ܂߂Ȃ��B�l�����ېł̗ݐi�Ő����z���ɂ͓K�p����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B �z���Ŋz�T������(dividend-received credit method)�F���傪������z���z�Ɉ��̗����|�����킹���z���A����̏����Ŋz����T������B�C���s���e�[�V��������(�@�l�Ŋ���A������)�͍X�ɐ��k�ȕ��@�ŁA�@�l�Ŋz���l����̏����Ŋz����T������B 6�Ł�311.03 ���{�̐��x�@�Ő�������u�Ő��̔��{�I�������ɂ��Ă̓��\�v(1986.10) �@�z���y��(�@�l�i�K�E���(5))�{�z���Ŋz�T��(����i�K�E���(7)) �� �@�z���Ŋz�T��(����i�K�E���(7))�ցB����92���F�z���T���B �@�i�A���\���s�v���x�̏ꍇ�A�z���Ŋz�T���͂Ȃ��B�d��8����5�j |
[���W]�@�l�ł̔[�ŋ`���҂͈͉̔͂ېŌJ���h�~�̊ϓ_����Z�p�I�ɒ�߂�����̂ł���A�@�l�T�O�ƃ����N��������{�̖@�l�Ő��݂̍���͔�r�@�I�ɂ͒������B�ƕ��ł͐l�I��Ђɂ��đg�����l�̉ېł����邵�A�A�����J�ł͖@�l�`�ԂƑg���`�ԂƂ̉ېŏ�̈����̈Ⴂ�����邱�Ƃ�O��ɔ[�Ŏ҂̑I���ɔC���Ă���Bcplg
���@����C�ӑg��(���@667��)
�@�l�ł̉ېł͂Ȃ��B�g�����ɑ��ĉېł����B������ʒB�ېŁBhp
�g����ʂ��ē����������g�����ɂǂ̂悤�ɔz������邩���ɂ߂Ė��Ȗ��B����Y�g�������E�Ŕ�����13�N7��13����48��7��1831�Ł�4.2.6.1.
(�C�ӑg�����̑g�����̑g�����ƂɌW�闘�v���̋A��)�����36�37���|19�@�C�ӑg�����̑g�����̓��Y�C�ӑg�����ɂ����ĉc�܂�鎖�Ɓc�ɌW�闘�v�̊z���͑����̊z�́A���Y�C�ӑg�����̗��v�̊z���͑����̊z�̂������z�����ɉ����ė��v�̕��z����ׂ����z���͑����S���ׂ����z�Ƃ���B
�@�������A���Y���z�������e�g�����̏o���̏A�g�����Ƃւ̊�^�̏Ȃǂ���݂Čo�ϓI��������L���Ă��Ȃ��ƔF�߂���ꍇ�ɂ́A���̌���ł͂Ȃ��B�m(��)���n
(�C�ӑg�����̑g�����̑g�����ƂɌW�闘�v���̋A���̎���)36�37���|19�̂Q�@�C�ӑg�����̑g�����̑g�����ƂɌW�闘�v�̊z���͑����̊z�́A���̔N���̊e�폊���̋��z�̌v�Z�㑍�������z���͕K�v�o��ɎZ������B
�@�������A�g�����ƂɌW�鑹�v�N�P��ȏ���̎����ɂ����Čv�Z���A���A���Y�g�����ւ̌X�̑��v�̋A�������Y���v������P�N�ȓ��ł���ꍇ�ɂ́A���Y�C�ӑg�����̌v�Z���Ԃ���Ƃ��Čv�Z���A���Y�v�Z���Ԃ̏I��������̑�����N���̊e�폊���̋��z�̌v�Z�㑍�������z���͕K�v�o��ɎZ��������̂Ƃ���B
(�C�ӑg�����̑g�����̑g�����ƂɌW�闘�v���̊z�̌v�Z��)36�37���|20�@36�E37���|19�y��36�E37���|19�̂Q�ɂ��C�ӑg�����̑g�����̊e�폊���̋��z�̌v�Z�㑍�������z���͕K�v�o��ɎZ�����闘�v�̊z���͑����̊z�́A����(1)�̕��@�ɂ��v�Z����B�������A���̎҂��p�����Ď���(2)����(3)�̕��@�ɂ��v�Z���Ă���ꍇ�ɂ́A���̌v�Z��F�߂���̂Ƃ���B
�@(1) ���Y�g�����ƂɌW��������z�A�x�o���z�A���Y�A�������A���̕��z�����ɉ����Ċe�g�����̂����̋��z�Ƃ��Čv�Z������@�@�k���z�@�l
�@(2) ���Y�g�����ƂɌW��������z�A���̎������z�ɌW�錴���̊z�y�є�p�̊z���тɑ����̊z�����̕��z�����ɉ����Ċe�g�����̂����̋��z�Ƃ��Čv�Z������@�@�k�ܒ��@�l
�@ �@���̕��@�ɂ��ꍇ�ɂ́A�e�g�����́A���Y�g�����ƂɌW�������ɂ��Ĕ�ېŏ����A�z���T���A�m��\���ɂ�錹���Ŋz�̍T�����Ɋւ���K��̓K�p�͂��邪�A�������A���������Ɋւ���K��̓K�p�͂Ȃ��B
�@(3) ���Y�g�����Ƃɂ��Čv�Z����闘�v�̊z���͑����̊z�����̕��z�����ɉ����Ċe�g�����ɂ�������@�@�k���z�@�l
�@ �@���̕��@�ɂ��ꍇ�ɂ́A�e�g�����́A���Y�g�����ƂɌW�������ɂ��āA��ېŏ����A�������A�������A�z���T���A�m��\���ɂ�錹���Ŋz�̍T�����Ɋւ���K��̓K�p�͂Ȃ��A�e�g�����ɂ�����闘�v�̊z���͑����̊z�́A���Y�g�����Ƃ̎傽�鎖�Ƃ̓��e�ɏ]���A�s���Y�����A���Ə����A�R�я������͎G�����̂����ꂩ��̏����ɌW��������z���͕K�v�o��Ƃ���B�m(��)���nio
���@535��(�����g���_��) �����g���_��́A�����҂̈����������̉c�Ƃ̂��߂ɏo�������A���̉c�Ƃ��琶���闘�v�z���邱�Ƃ�邱�Ƃɂ���āA���̌��͂���B
���@536���i�����g�����̏o���y�ь����`���j�@�����g�����̏o���́A�c�Ǝ��̍��Y�ɑ�����B
�Q �@�����g�����́A���K���̑��̍��Y�݂̂����̏o���̖ړI�Ƃ��邱�Ƃ��ł���B
�R �@�����g�����́A�c�Ǝ҂̋Ɩ������s���A���͉c�Ǝ҂��\���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B
�S �@�����g�����́A�c�Ǝ҂̍s�ׂɂ��āA��O�҂ɑ��Č����y�ы`����L���Ȃ��B
(�����g���_��ɂ��g�����̏���)�����36�37���|21�@�����g���_��c�c���������҂œ��Y�����g���_��Ɋ�Â��ďo���������(�c�c�u�����g�����v�Ƃ����B)�����Y�����g���_��Ɋ�Â��c�Ǝ҂���闘�v�̕��z���G�����Ƃ���B�m��17������4.2.5. 6�Ł�225.02�q��@���[�X���Ɠ����g�������E�Ŕ�����27�N6��12�����W69��4��1121�Łn
�@�������A�����g���������Y�����g���_��Ɋ�Â����c�Ǝ҂̉c�ގ��Ɓc�c�ɌW��d�v�ȋƖ����s�̌�����s���Ă���ȂǑg�����Ƃ��c�Ǝ҂Ƌ��Ɍo�c���Ă���ƔF�߂���ꍇ�ɂ́A���Y�����g���������Y�c�Ǝ҂���闘�v�̕��z�́A���Y�c�Ǝ҂̉c�Ƃ̓��e�ɏ]���A���Ə������͂��̑��̊e�폊���Ƃ���B
�i���j1�@�����g���_��Ɋ�Â��c�Ǝ҂���闘�v�̕��z�Ƃ́A�����g���������Y�c�Ǝ҂���x��������̂������i�o���̕��߂��Ƃ��Ďx��������̂������B ) �B�ȉ�36�E37���|21��2�ɂ����ē����B
�@2�@�c�Ǝ҂���闘�v�̕��z���A���Y�c�Ƃ̗��v�̗L���ɂ�����炸���z���͏o���z�ɑ����芄���ɂ����̂ł���ꍇ�ɂ́A���̕��z�͋��K�̑ݕt�����琶���鏊���ƂȂ�B
�@�Ȃ��A���Y���������Ə����ł��邩�ǂ����̔���ɂ��ẮA27�|6�Q�ƁB
(�����g���_��ɂ��c�Ǝ҂̏���)36�37���|21�̂Q�@36�E37���|21�ɂ��c�Ǝ҂������g�����ɕ��z���闘�v�̊z�́A���Y�c�Ǝ҂̓��Y�g�����ƂɌW�鏊���̋��z�̌v�Z���K�v�o��ɎZ�������B�m��d�ې��͂��Ȃ��Ƃ����Ӗ��n
�����g���͏��@�̍u�`�ł����܂�[�������Ȃ��ł��낤���d�Ŗ@�ł�(�A���A���ۉېłł�)�p�o�ł���(cf.8.2.2.1.b���{�K�C�_���g�����E������������19�N6��28������1985��23��)�B�����g���Ɂu�g���v�Ƃ������t���܂܂����̂́A�C�ӑg���̈���Ƃ���(�g�D�̈�`�ԂƂ���)������������ݕt�̈�`�ԂƂ��Ă̌_��Ƃ��ė�������������@�w�̗����ɋ߂��Bby(���̑��̑g�D�`��(�ȗ�)bz)
COLUMN5-1 �������
�@��2��10���@��������@��Ёc�c�̊��哙�c�c���O�l�ȉ����тɂ����Ɛ��߂Œ�߂����̊W�̂���l�y�і@�l�����̉�Ђ̔��s�ϊ������͏o���c�c�̑������͑��z���S���̌\���鐔���͋��z�̊������͏o����L����ꍇ���̑����߂Œ�߂�ꍇ�ɂ����邻�̉�Ђ������B�@��132��(������Г��̍s�ז��͌v�Z�̔۔F)[�����Ŗ@157���E�����Ŗ@64�������|be]�@�Ŗ������́A���Ɍf����@�l�ɌW��@�l�łɂ��X�����͌��������ꍇ�ɂ����āA���̖@�l�̍s�ז��͌v�Z�ŁA�����e�F�����ꍇ�ɂ͖@�l�ł̕��S���s���Ɍ��������錋�ʂƂȂ�ƔF�߂�����̂�����Ƃ��́A���̍s�ז��͌v�Z�ɂ�����炸�A�Ŗ������̔F�߂�Ƃ���ɂ��A���̖@�l�ɌW��@�l�ł̉ېŕW���Ⴕ���͌������z���͖@�l�ł̊z���v�Z���邱�Ƃ��ł���B�m��E�A2�����n
�R�@��ꍀ�̋K��́A�����ɋK�肷��X�����͌��������ꍇ�ɂ����āA�����e���Ɍf����@�l�̍s�ז��͌v�Z�ɂ��A�����Ŗ@��S�\�����ꍀ�c�c�Ⴕ���͑����Ŗ@��Z�\�l���ꍀ�c�c���͒n���Ŗ@�c�c��O�\����ꍀ�c�c�̋K��̓K�p�������Ƃ��ɂ��ď��p����B�m�Ή��I�����Ƃ����n
�@��67��(���蓯������̓��ʐŗ�)�@�����@�l�ł�����蓯������i��x�z����ŁA��x�z��Ђł��邱�Ƃɂ��Ă̔���̊�b�ƂȂ����哙�̂����ɔ�x�z��ЂłȂ��@�l������ꍇ�ɂ́A���Y�@�l�����̔���̊�b�ƂȂ銔�哙���珜�O���Ĕ��肷����̂Ƃ����ꍇ�ɂ����Ă���x�z��ЂƂȂ���́c�c�������A���Z���̂��̂������B�ȉ����̏��ɂ����ē����B�j�̊e���ƔN�x�̗��ۋ��z�����ۍT���z����ꍇ�ɂ́A���̓��蓯����Ђɑ��ĉۂ���e���ƔN�x�̏����ɑ���@�l�ł̊z�́A�O���ꍀ�m23.2���n���͑�m���{��1���~�ȉ��A����800���~�ȉ��̕����ɂ���19���n�̋K��ɂ�����炸�A�����̋K��ɂ��v�Z�����@�l�ł̊z�ɁA���̒����镔���̗��ۋ��z�����̊e���Ɍf������z�ɋ敪���Ă��ꂼ��̋��z�ɓ��Y�e���ɒ�߂銄�����悶�Čv�Z�������z�̍��v�z�����Z�������z�Ƃ���B
�@��@�N�O�疜�~�ȉ��̋��z�@�S���̏\
�@��@�N�O�疜�~���A�N�ꉭ�~�ȉ��̋��z�@�S���̏\��
�@�O�@�N�ꉭ�~������z�@�S���̓�\
�Q�@�O���ɋK�肷����x�z����Ƃ́A��Ёc�c�̊��哙�c�c����l���тɂ���Ɛ��߂Œ�߂����̊W�̂���l�y�і@�l�����̉�Ђ̔��s�ϊ������͏o���c�c�̑������͑��z���S���̌\���鐔���͋��z�̊������͏o����L����ꍇ���̑����߂Œ�߂�ꍇ�ɂ����邻�̉�Ђ������B�m3���ȉ����n
�T�v�F�ŕ��S�y����}�邱�Ƃ͌o�ϓI�����l�Ƃ��ē��R�ł���A�d�ʼn���������K��Ȃ��ɔ۔F���邱�Ƃ��d�Ŗ@����`�ᔽ�ƍl������B�������A������Ђ̏ꍇ�A������Ђł��邪�䂦��(���v�����L���Ă��邪�䂦��)�ُ�ȍs�ׁE�v�Z���Ȃ����A���������s�ׁE�v�Z�ɂ��ŕ��S�y���܂ŋ��e���邱�Ƃ͔���Ђ̊W�҂Ɣ�ׂĕs�����ł��邽�߁A��ʓI�۔F�K���Ƃ��Ė@132��1�����K�肳��Ă���(����3���͑Ή��I����)�B
�@�܂��A�������ۂɑ�����ʂ̉ېłƂ��Ė@��67�����K�肳��Ă���B
�@�@��132���u������Ёv��67���u���蓯����Ёv�̒�`���Ⴄ�B(35���u����x�z������Ёv�p�~)
������Ђ̍s�ׁE�v�Z�̔۔F�K�肾���ł͑Ώ��ł��Ȃ��̈�ɂ��ė��@����������A�i�X������ЋK��̓K�p�͈͂����߂��Ă������A��ʓI�۔F�K�莩�̂̏d�v���E�K�v�����Ȃ��Ȃ���̂ł͂Ȃ��B��6�Ł�112.01���������E��㍂�����a43�N6��28���s�W19��6��1130�Łc�ېŗv���@����`�Ɛ��߂ւ��ϔC�̉ۂƂ̊W�A�����Ė����ܗ^(���݂��������^:�@��34��)�K��n�݂ցB
���p���F�d�ʼn�����I�ɔ۔F����K��(GAAR(General Anti Avoidance Rule)�K�[�Ɣ��������)�͈ጛ���B�܂��d�ʼn��}���ɂƂ��Ăǂ�قǗL�����B���ˋM�V�u�u��������肵�Ȃ���ʓI�۔F�K��(GAAR)�v�Ƒd�Ŗ@����`�v�t�B�i���V�����E���r���[129��169��(2017)�����W���d�Ŗ@����`�̑����I�����i��ɒ�����=���J���j�Ғ��w�d�Ŗ@����`�̑����I�����x�L��t�A2021�Ɏ��^�j
�Q�l�F�h�C�c�ɂ͑d�ʼn������ʓI�ɔ۔F����K�肪����(AO 42��bl)�B
| ���y�����َ����E�D�y�������a51�N1��13����22��3��756�� ��������_�@X�Ђ�K��̓�����Ђł���BX�Ђ��L����{��������K���L����{���y�n���ꊇ����T�ɏ��n�����ہA�����K���S�Ď�̂����BX�Ђ͗����ƔN�x�ɖ{���������n�����̂v�サ�����A�{�������y�юؒn�����̏��n�ɂ��X��443���~�̏��������������͂��ł���Ƃ���Y���X�������B���̂����A18���~�]�̎G�����̔F��ɂ��āAY�́A�{�������y�юؒn���̏��n����v544���~��X�Ђ�K�������ő݂��t�����̂ł��邩��ʏ�擾���ׂ��������������v���v�シ�ׂ��ł���A�Ǝ咣�����B ���|�@X�̐������p�@�@�l�Ŗ@132���̍������ɂ��Ă̐����B �@�ؒn���̑Ή������z���v���̊z�ɉ��Z���������͓K�@�B �@�uX����̂��ׂ����̂ł���v544���~��X�́uK�ɖ����ő݂��t�������̂Ƃ����ׂ��v�Bbn |
| ��1��330.01�������Y������Ў����E�Ŕ����a33�N5��29�����W12��8��1254�ŕS�I6��60nn �@����ȍ���(�w���E�@�ȑ�w�@�ł͑g�D�ĕҐ�������Ȃ�)�̐����_�ł���̂Ŏ����W�⑈�_�͏ȗ��B �@�ٔ���ɂ����āu�s���Ɍ����v�v���̉��ߕ��@�͊T��2�ʂ�̌X��������B �@��R���|�@�u����Ђɂ͒ʏ�Ȃ����Ȃ��悤�ȍs�v�Z���Ƃ��Ί��傪�Ј��ɉ�Ђ̎��Y������Ŕ��p�v������ɓ�����B�����u�z�������O�ɔ퍇����Ђ̑S���������邱�Ƃ͕K������������Ђɂ��Ďn�߂ĂȂ�����悤�ȍs�ׂ��Ȃ킿�A���o�Ϗ��茩�ĕs�����ȍs�ׂł͂ȁv�����瓖���̖@�l�Ŗ@28��(���݂�132���ɑ���)�̑Ώۂ��蓾�Ȃ��B�ېŒ��̏����͈�@�ł���B �@��R���|�@�u���o�ϐl�̑I�ԍs�`�ԂƂ��ĕs�����Ȃ��́v���۔F�̑ΏۂƂȂ�(���_�͈�R�Ɠ����ł���A�ō��ق͉����q�ׂĂȂ�)�Boh �@�ǂ���ōl���Ă����_�ɍ����o�邱�Ƃ͖ő��ɂȂ�(�H�ł͂��邪�����o����Ƃ�����5��340.02(6��513��)����{�����R���N���[�g������Ў����E�������{��x�����a55�N9��29���s�W31��9��1982��bp�c�c��R�͔���Ђł��̗p����ł��낤�Œ�̔����z��F��ł��Ȃ��Ƃ��Ė@��132��s�K�p�A��R�͏��o�ϐl�̍s�ׂƂ��ĕs�����A�s���R�ł���Ƃ��Ė@��132��K�p)���A�w���́A��R�̔����̕����x������X���������B �@���o�ϐl�Ƃ����\���́A�����̖@�l�����O���[�v��̂ƌ��č����I���ۂ��ł͂Ȃ��A�@�l�P�̗̂��v�Nj��̊ϓ_���獇���I���ۂ���₤���߂ɗp�����Ă���B�Ⴆ�ΐԎ���Ћ~�ς̂��ߍ�����Ђ����i���������ď��i����邱�Ƃ̓O���[�v��̂ƌ��č����I�Ƃ����邩������Ȃ����A���Y������ВP�̗̂��v�Nj��̊ϓ_����͕s�����ł���B �@�܂��Aarm's length transaction�i�Ɨ������ҊԎ���j�����E�������́u�s���Ɍ����v�v�������ł��낤�Ƃ������Ă���B(���q�G�w�d�Ŗ@�x24��542��) |
| 6�Ł�340.02���j�o�[�T���~���[�W�b�N�����E�Ŕ��ߘa4�N4��21�����W76��4��480�ŕS�I7��63bm�c�c���{�@�l����A�����J�@�l�ɔz�����x�����W����A�g�D�ĕ҂����āA���{�@�l����A�����J�@�l�֗��q���x�����W�ɕύX��������(debt pushdown�c���q���S���q��Ђɕ��S������W)�B�ō��ق͈ȉ��̂悤�ɏq�ׂ�arm's length standard�����E���Ă��Ȃ����q�x���ɂ����{�@�l�̉ېŏ����������@�l�Ŗ@132��1���́u�s���Ɍ����v�v�������Ȃ��Ɣ��f���ꂽ�B�����炱��8.4.5.�d��66����5��2�̉ߑ�x�����q�Ő��ŗ��@�I�ɑΏ�����������Ȃ��B ���|�@�u������Г��ɂ����K�̎ؓ��ꂪ��L�̌o�ϓI ���������������̂��ۂ��ɂ��ẮA���Y�ؓ���̖ړI��Z���������̏�����𑍍��I�ɍl�����Ĕ��f���ׂ����̂ł���Ƃ���A�{���ؓ���̂悤�ɁA�����ƃO���[�v�ɂ�����g�D�ĕҐ��ɌW���A�̎���̈�Ƃ��āA���Y��ƃO���[�v�ɑ����铯����Г������Y��ƃO���[�v�ɑ����鑼�̉�Г�������K�̎ؓ�����s�����ꍇ�ɂ����āA���Y��A�̎���S�̂��o�ϓI�������������Ƃ��́A���Y�ؓ���́A��L������̂����A���̖ړI�A���Ȃ킿���Y�ؓ���ɂ���Ď������v����������邱�ƂŒB������ړI�ɂ����ĕs�����ƕ]������邱�ƂƂȂ�B�����āA���Y��A�̎���S�̂��o�ϓI���������������̂��ۂ��̌����ɓ������ẮA�@���Y��A�̎�����A�ʏ�͑z�肳��Ȃ��菇����@�Ɋ�Â�����A���ԂƂ͂����������`������o�����肷��ȂǁA�s���R�Ȃ��̂ł��邩�ǂ����A�A�ŕ��S�̌����ȊO�ɂ��̂悤�ȑg�D�ĕҐ����s�����Ƃ̍����I�ȗ��R�ƂȂ鎖�ƖړI���̑��̎��R�����݂��邩�ǂ������̎�����l������̂������ł���B�v �@�u�{���ؓ���͖��S�ۂōs���A��㍐�l�͖{���ؓ��ꂪ����ƂȂ��čŏI�I�ɑݎؑΏƕ\��͍����߂ƂȂ��Ă��邱�Ƃ�����������ȂǁA�{���ؓ���ɂ��Ɨ����Γ��ő��݂ɓ���W�̂Ȃ������ҊԂŒʏ�s�������Ƃ͈قȂ��_������B�m���s�n�@�������Ȃ���A�{���ؓ���́A�{���e�����@�l�̊����̍w������y�т��̊֘A��p�ɂ̂ݎg�p�������̉��ɍs���A���ۂɁA��㍐�l�́A�������擾���Ė{���e�����@�l�����Ђ̎x�z���ɒu�������̂ł���A�ؓ����z���g�r�Ƃ̊W�ŕs���ɍ��z�ł���Ȃǂ̎�������������Ȃ��B�܂��A�{���ؓ���̖��̂��������y�ѕԍϊ��Ԃɂ��ẮA��㍐�l�̗\�z����闘�v�Ɋ�Â��Č��肳��Ă���A���ɁA�{���ؓ���ɌW�闘���̎x��������ɂȂ����Ȃǂ̎���͂��������Ȃ��B�m���s�n�@��������ƁA��L�̓_�����邱�Ƃ������āA�{���ؓ��ꂪ�s���R�A�s�����Ȃ��̂Ƃ܂ł͂�����B�v ���{IBM�����E�����n������26�N5��9����23(�s�E)407(�����F�e)�E������������27�N3��25������2267��24��(�����F�e)�E�Ō�����28�N2��18��(�㍐�s��)bo���@�l�Ŗ@132��1���̓K�p��ے肵������B �@�}�P�@�@�@�@�@�@�č��@�@�@�@�@�@�@�@�}�Q�@�@�@�@�č� �@�@�@�@�@�@�������@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������ �@�@�@�@�@�@���`�������O�ōT���@�@�@�@�@�@�@���`���{���Z���̕ԍ� �@�{�@�{�a���������@�b���p�s�@�@�@�@�@�@�@��������(���q�̂����) �@���@���b�@�@���@�@�b�@�@�@�@�@�@�@�@�@���{�������b �@�Z�{���b�����������b�z���@�@�@�@�@�@�{�@�@���w�� �@���@�������@�@�@���b�@�@�@�@�@�@�@�@���a���������݂Ȃ��z�� �@�@�@�w�������@���������{�@�@�@�@�@�@�e�@�b��������(����Ŋҕt) �@�@�@�����w���@���a������Ł@�@�@�@�@���@�����a���b �@�@�@�@�������@�������@�@�@�@�@�@�@�@�n�@�@������ �T�i�R���|�@�u�@�l�Ŗ@�P�R�Q���P���́C�۔F�̗v���Ƃ��āC������Ђ́u�s�ז��͌v�Z�ŁC�����e�F�����ꍇ�ɂ͖@�l�ł̕��S��s���Ɍ��������錋�ʂƂȂ�ƔF�߂���v���Ƃ����߂Ă���ɂƂǂ܂�C���̕�����C�۔F�ΏۂƂȂ铯����Ђ̍s�ז��͌v�Z���C�d�ʼn��ړI�ł��ꂽ���Ƃ�v�����Ă͂��Ȃ��B�������C�@�l�Ŗ@�ɂ����铯����Ђ̍s�v�Z�̔۔F�K��ɂ��ẮC���a�Q�T�N�@����V�Q���ɂ������O�̖@�l�Ŗ@�R�S���P���ł́C�u������Ђ̍s�ז��͌v�Z�Ŗ@�l�ł�Ƃ��ړI������ƔF�߂�����̂�����ꍇ�ɂ����ẮC���̍s�ז��͌v�Z�ɂ�����炸�C���{�̔F�߂�Ƃ���ɂ��C�ېŕW�����v�Z���邱�Ƃ��ł���B�v�ƋK�肳��Ă����Ƃ���C�������ɂ��C�u������Ђ̍s�ז��͌v�Z�ŁC�����e�F�����ꍇ�ɂ����Ă͖@�l�ł̕��S��s���Ɍ��������錋�ʂƂȂ�ƔF�߂�����̂�����Ƃ��́C���̍s�ז��͌v�Z�ɂ�����炸�C���{�̔F�߂�Ƃ���ɂ��C���Y�@�l�̉ېŕW�����͌������z���v�Z���邱�Ƃ��ł���B�v�i��������̖@�l�Ŗ@�R�P���̂Q�j�Ɖ��߂��C����Ƃقړ����e�̋K�肪�C���a�S�O�N�@����R�S���ɂ��S��������̖@�l�Ŗ@�P�R�Q���P���ɂ������p���ꂽ�̂ł����āC�@�l�ł�Ƃ��ړI�����邱�Ƃ�K�p�̗v���Ƃ��ĕ����㖾���I�Ɍf���Ă����_�����߂�ꂽ�Ƃ��������̌o�܂�����B��������ƁC�@�l�Ŗ@�P�R�Q���P���́u�s���v���ۂ��f�����ŁC������Ђ̍s�ז��͌v�Z�̖ړI�Ȃ����Ӑ}���l�������ꍇ�����邱�Ƃ�ے肷�闝�R�͂Ȃ����̂́C�����ŁC��T�i�l���咣����悤�ɁC���Y�s�ז��͌v�Z���o�ϓI�������������Ƃ������߂ɂ́C�d�ʼn���ȊO�ɐ����ȗ��R�Ȃ������ƖړI�����݂��Ȃ��ƔF�߂��邱�ƁC���Ȃ킿�C���d�ʼn��ړI�ƔF�߂��邱�Ƃ���ɗv�����C���Y�ړI���Ȃ���Γ����̓K�p�ΏۂƂȂ�Ȃ��Ɖ����邱�Ƃ́C�����̕��������łȂ���L�̉����̌o�܂ɂ����v���Ȃ��B�v |
| 6�Ł�340.03������В˖{���X�����E�Ŕ����a48�N12��14����20��6��146��bt �����@�w�Ђ����L���錚���A�y�ю�����̂`�����L����y�n���ꊇ�ła�ɔ��p�B�`��5224���~�A�w��2238���~�����(7��3�B�a�ɂƂ��Č����͖����l)�B �@�x�Ŗ������́A�ؒn��������40%�ł���(2949���~)�Ƃ��A�����̑Ή�(90���~)���܂܂��Ƃ��āA�w��3039���~���ׂ��ł������Ƃ����ꎟ�X���������s���B���z800���~���w����`�ɑ�������ܗ^(�����B���Ȃ��������^)�ɂ�����Ƃ��A�w�������̔[�ō��m����(�ȉ��{����������)���s���B �@��ꎟ�X�����������R���L�s���ł���̂ő�X�������ő�ꎟ���������A��ꎟ�Ɠ����e�̑�O���X���������s���B �@��@�ȑ�ꎟ�X��������O��Ƃ���{�������������܂���@�ł���Ƃw���咣�����B ���|�@�㍐���p(�������p)�@�u�@�l�Ŗ@132���Ɋ�Â�������Г��̍s�v�Z�̔۔F�́A���Y�@�l�ł̊W�ɂ����Ă̂݁A�۔F���ꂽ�s�v�Z�ɑウ�ĉېŒ��̓K���ƔF�߂�Ƃ���ɏ]���ېł��s�Ȃ��Ƃ������̂ł��āA���Ƃ�������ɂȂ��ꂽ�s�v�Z���̂��̂����̓I�ϓ������߂���̂ł͂Ȃ��B�������āA�{���@�l�łɊւ��錴������ꎟ�X�������ɂ����Ăw�̍s�v�Z���۔F����A���̔۔F�z���w����`�ɑ�������ܗ^�Ƃ��Ăw�̉v���ɎZ�����ꂽ�Ƃ��Ă��A�`�ɑ��鏊���ł̊W�ɂ͂Ȃ��e�����y�ڂ����̂ł͂Ȃ��A���l�̏����łɊւ��čs�Ȃ�ꂽ���������������́A�E��ꎟ�X�������Ƃ͂������Ȃ��A�����Ŗ@�ɂ�Ė@���㓖�R�Ɋm�肵�������`���ɂ��Ă��̗��s�����߂���̂ł���Ɖ����ׂ��ł���B����䂦�A�E�X�������̎�����ɂ�āA�����Ŗ@��̌����`���͈̔͂����E����邢���͂Ȃ��A�E������͖{�����������̌��͂ɉe�����Ȃ��B�v |
| ���n���ߘa6�N3��13���ߘa4(�s�E)60�����^1524��124�ŋ���1694��18�ňꕔ�F�e�A�ꕔ���p(�T�i)(�ėR�ԁu�l�Ɠ�����ЂƂ̊Ԃ̒��ݎ،_��ɂ��čs�v�Z�۔F�K��̓K�p���ے肳�ꂽ�����v�V�E������Watch�d�Ŗ@No.192 (2025.3.7)�A���l�q�P�E�W�����X�g1610���d����6�N160-161��)(�ѓc�T��2025�N3��7���d�Ŕ��ጤ�����) �@ �@���_�@�{�����ݎ،_��ɌW�鏊���Ŗ@�P�T�V���P���K�p�̉ۋy�ь��� �@���|�@�u�����Ŗ@�P�T�V���P���́C�����e���Ɍf����@�l�ł��铯����Г��ɂ����ẮA������x�z���銔�哙�̏����ł̕��S��s���Ɍ���������悤�ȍs�ז��͌v�Z���s���₷�����ƂɊӂ݁A�ŕ��S�̌������ێ����邽�߁A���哙�̏����ł̕��S��s���Ɍ��������錋�ʂƂȂ�ƔF�߂���s�ז��͌v�Z���s��ꂽ�ꍇ�ɁA����𐳏�ȍs�ז��͌v�Z�Ɉ��������ē��Y���哙�ɌW�鏊���ł̍X�����͌�����s��������Ŗ������ɔF�߂����̂ł���B���̂悤�ȋK��̎�|�A���e���炷��A�����ɂ����u�����e�F�����ꍇ�ɂ͂��̊��哙�ł��鋏�Z�Җ��͂���Ɛ��߂Œ�߂����̊W�̂��鋏�Z�҂̏����ł̕��S��s���Ɍ��������錋�ʂƂȂ�ƔF�߂�����́v�Ƃ́A������Г��̍s�ז��͌v�Z�̂����A�o�ϓI�������I�Ȍ��n�ɂ����ĕs���R�A�s�����Ȃ��́A���Ȃ킿�o�ϓI���������������̂ł����āA���Y���哙�̏����ł̕��S�����������錋�ʂƂȂ���̂������Ɖ�����̂������ł���i�ȏ�ɂ��A�m�����p�`���R���a�����n�ō��ٕ����P�U�N�V���Q�O����O���@�씻���E�ٔ��W�����Q�P�S���P�O�V�P�ŁA�@�l�Ŗ@�P�R�Q���P���Ɋւ���m�������j�o�[�T���~���[�W�b�N�����n�ō��ٗߘa�S�N�S���Q�P����ꏬ�@�씻���E���W�V�U���S���S�W�O�ŎQ�Ɓj�B �@�{���̂悤�Ȋ��哙����ݐl�Ƃ�������Г�����ؐl�Ƃ���s���Y�̒��ݎ،_��L�̌o�ϓI���������������̂��ۂ��ɂ��ẮA���Y���ݎ،_��̖ړI�A���ݗ��̋��z��_��̏��������܂ޓ��Y���ݎ،_��̓��e���̏�����𑍍��I�ɍl�����Ĕ��f����̂������ł���B�����āA���Y���ݎ،_�o�ϓI���������������̂��ۂ��̌����ɓ������ẮA�@���Y���ݎ،_�A�ʏ�͑z�肳��Ȃ��菇����@�Ɋ�Â�����A���ԂƂ͂����������`������o������A���̒��ݗ����K���Ȓ��ݗ��ɔ䂵�Ē�������z�Ȃ��̂ɂ��ꂽ�肵�Ă���ȂǁA�s���R�Ȃ��̂ł��邩�ǂ����A�A�ŕ��S�̌����ȊO�ɓ��Y���ݎ،_���������邱�Ƃ̍����I�ȗ��R�ƂȂ鎖�ƖړI���̑��̎��R�����݂��邩�ǂ������̎�����l������̂������ł���B�v �@�u�{�����ݎ،_��́A��ʓI�ɂ͓���̃T�u���[�X�Ǝ҂Ɉꊇ���ē]�ݕ����Œ��݂��邱�Ƃ�����Ȏ�ʂ̈قȂ鑽���̕s���Y���ꊇ���ē]�ݕ����ɂ����݂�����̂ł���A�܂��A���X�N���݂̂Ȃ炸�A�_����Ԓ��ɍ��z�̎��v�����ł��镡���̑Ώەs���Y�̔��p���z�肳���ɂ������ɂ�������炸�A�Ώەs���Y�����p�ɂ�茸�����Ă����Y�_����Ԓ��̒����̊z�����z����Ȃ����Ƃɂ�镉�S�i���p���X�N�j���A���ؐl�ł���`�Ђɕ��킹����̂ƂȂ��Ă���B �@�ȏ�̂悤�Ȗ{�����ݎ،_��̓��e����ꐫ�ɏƂ点�A�{�����ݎ،_��ɂ��ẮA���̓K���Ȓ��ݗ����Z�肷��ɓ�����A�Ǘ��ϑ������Ǝ����I�ɓ������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂ł����āA�{�����ݎ،_��̓K���Ȓ��ݗ����Z�肷��ɓ�����A�Ǘ��ϑ���������ɎZ�肷����@���̂邱�Ƃɂ��ẮA���̊�b�I�v����������Ƃ����ׂ��ł���B���������āA��L�̔퍐�̎咣�́A���̑O�������Ă���A�̗p���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B �@��������ƁA�{���K�����ݗ��������Ė{�����ݎ،_��̓K���Ȓ��ݗ��ƔF�߂邱�Ƃ͂ł����A�{���ɂ����ẮA�؋���A�{�����ݎ،_��̓K���Ȓ��ݗ��̋��z�͕s���ł���Ƃ����ق��Ȃ��B�v �@�u�{�����ݗ����K���Ȓ��ݗ��ɔ䂵�Ē�������z�Ȃ��̂ɂ���Ă��邩����������B �@�{�����ݗ��́A�O�L�F�莖���C�̂Ƃ���A�����̌v�Z�ɂ��A�����Q�S�N�����畽���Q�X�N���܂ł̖{�����ݗ��̎��ۂ̂`�Г]�ݗ������ɌW�锄�㍂�ɐ�߂銄���́A��T�R�D�W�������U�T�D�V���܂ł̊ԂŐ��ڂ��Ă���A�퍐�̌v�Z�ɂ��{���e�N���i�����Q�V�N�����畽���Q�X�N���܂Łj�̖{�����ݗ��y�т`�Г]�ݗ������̋��z��O��Ƃ���A�����Q�V�N�����畽���Q�X�N���܂ł̖{�����ݗ��̂`�Г]�ݗ������ɐ�߂銄���́A��T�S�D�V�������T�X�D�W���܂ł̊ԂŐ��ڂ��Ă���B���̊����݂̂��炷��A�{�����ݗ��͓K���Ȓ��ݗ��ɔ䂵�Ē�z�Ȃ��̂ɂ���Ă���\��������Ƃ͂�����i���U�O�A�U�P���Q�Ɓj�B �@�������A�O�L�O���i�Q�j���тɑO�L�F�莖���A�y�уC�ɂ��A�{�����ݎ،_��́A�@�]�ݕ����i�}�X�^�[���[�X�_��j�ł����ċ��X�N�����؎�i�`�Ёj�����S������̂ł��邱�Ƃ̂ق��A�A��ʓI�ɂ͓���̃T�u���[�X�Ǝ҂Ɉꊇ���ē]�ݕ����Œ��݂��邱�Ƃ�����ȁA��ʁi�}���V�����i�P�����͋敪�j�A�X�܁A���ԏ�A�a�@���͎������j�⏊�ݒn��̈قȂ鑽���̕s���Y�i�G���h�E���[�U�[�����S�ɂ��y�Ԃ��Ƃ��������B�j���ꊇ���Ă`�Ђɒ��݂�����̂ł��邱�ƁA�B�_����Ԓ��ɍ��z�̎��v�����ł��镡���̑Ώەs���Y�̔��p���z�肳���ɂ������ɂ�������炸�A�Ώەs���Y�̈ꕔ�����p����đΏەs���Y���������Ă��A���Y�_����Ԓ��̒����͌��z����Ȃ����Ƃɂ�镉�S�i���p���X�N�j���؎�i�`�Ёj�ɕ��킹����̂ɂȂ��Ă��邱�ƂƂ��������ꐫ��L���Ă���A�����̇@����B�܂ł̎���͂�������{�����ݎ،_��ɂ�������ݗ��̌��z�v���ƂȂ蓾����̂ł���B �@�܂��A�O�L�A�̂Ƃ���A�{�����ݎ،_��̓K���Ȓ��ݗ��̋��z�͕s���ł���A�{�����ݗ��Ɣ�r���ׂ��K���Ȓ��ݗ������R�Ƃ��Ȃ�����A���������K���Ȓ��ݗ��Ɣ�r���Ė{�����ݗ�����z�ł���Ƃ����邩���������f���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B �@����ɁA�O�L�F�莖���G�̌����̕s���Y�����̋��z���݂�ƁA�O�L�F�莖���A�i�C�j�̂Ƃ���{�����ݎ،_���������悤�ɂȂ����͕̂����Q�S�N�V���ł���Ƃ���A����ȍ~�̕s���Y�����̋��z�͌������Ă��邪�A���N�ȍ~�{�����ݎ،_��̑Ώەs���Y���̂��������p����Č������Ă��邱�Ƃ���A�P���ɋ��z���r���邱�Ƃ��ł��Ȃ���A�����Q�U�N���ɂ͑O�N���̕����Q�T�N���̕s���Y�����̋��z������ȂǁA��т��ċ��z���������Ă���킯�ł͂Ȃ��A�܂��A�����Q�S�N�����畽���Q�X�N���܂ł�ʂ��āA�s���Y�����̋��z���ɂ߂Ē�z�ɂȂ�Ƃ��A�}�C�i�X�ɂȂ�Ȃǂ��Ă��炸�A�{�����ݎ،_�������������ɂ����Đ��S���~�Ȃ������疜�~�Ƃ����������̒��ݗ������Ă��邱�Ƃ��F�߂���̂ł����āA�����̕s���Y�����̋��z�̐��ڂ���݂Ă��A�{�����ݗ����K���Ȓ��ݗ��Ɣ�r���Ē�������z�ł���Ƃ͂����Ȃ��B �@�ȏ�̎���炷��A�{�����ݗ����K���Ȓ��ݗ��ɔ䂵�Ē�������z�Ȃ��̂ɂ���Ă���ƒf���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�v �@�u�ŕ��S�̌����ȊO�̖{�����ݎ،_���������邱�Ƃ̍����I�ȗ��R�ƂȂ鎖�ƖړI���̑��̎��R�̗L���i�O�L�i�P�j�A�Q�Ɓj�ɂ��� �@�O�L�F�莖���A�i�C�j�y�сi�E�j�ɂ��A�{�����ݎ،_��̒����Ɏ���o�܂ɂ́A�������A���Ȃ̏��L����s���Y����݂���s���Y���Ƃ��g�債�Ă������ƁA���̂��߂Ɍ����l�̕s���Y���ƂɌW�鎑���Ǘ�����x�Ǘ��A�Ŗ��\�����̎������ώG�ɂȂ��Ă������ƁA����̔N�����ɂȂ��Ă������Ɠ�����A�����l�ʼnc��ł����s���Y���Ƃ��A�@�l�ł���`�ЂɈړ]����Ƃ������ƖړI�����������̂ƔF�߂���B�����āA���ۂɂ��A�{�����ݎ،_��̒����ɂ��A�����l�̕s���Y���Ƃɂ��ẮA���ݗ����������肷��ƂƂ��ɁA�������ȑf�������Ȃǂ������Ƃ��F�߂��A�܂��A�����́A�����l���c��ł����s���Y���Ƃ�����ƂƂ��ɁA�`�ЂɎ��Ƃ��ړ]���邽�߁A�����Q�S�N�ȍ~�A�������Ȃ̏��L����s���Y���`�Ж��͑�O�҂ɔ��p������A�V���ɒ��ݗp�s���Y���擾����ꍇ�ɂ́A��{�I�ɂ́A�`�Ђ�������擾�����肵�Ă��邱�Ƃ��F�߂���B��������ƁA�{�����ݎ،_��́A�������A��L�̂悤�ȕs���Y���Ƃ̂`�Ђւ̈ړ]�Ƃ������ƖړI���������邽�߂ɁA�����Q�S�N�ȍ~�A���Ȃ̏��L����s���Y���`�Ж��͑�O�҂ɔ��p���邱�Ƃƕ��s���āA�{���s���Y���ꊇ���Ă`�Ђɑ��ē]�ݕ����ɂ����݂������̂ƔF�߂��A���̂悤�Ȗ{�����ݎ،_��̖ړI�͍����I�Ȃ��̂Ƃ�����B �@�Ȃ��A�����́A�O�L�F�莖���A�i�C�j�̂Ƃ���A�����̌ږ�ŗ��m���A�����i�l�j�Ƃ`�Ёi�@�l�j�Ƃ���̓I�ɍl����A�s���Y�����̑��z�͕ς�炸�A�l���͖@�l�̂ǂ��炩���łS���邩�Ƃ������Ƃł����āu�s���ė����v�̊W�ł��邩��A�Ŗ������������Ă���邾�낤���A���Ȃ����낤�Ƃ����ӌ����q�ׂ����Ƃ܂��A�{�����ݎ،_����������Ɏ����Ă���A�{�����ݎ،_��̒����̖ړI�Ƃ��Č����̏����ł̕��S�̌����̂��߂Ƃ����ړI���������Ƃ��Ă��A���ꂪ�傽��ړI�ł���Ƃ͔F�߂��Ȃ��B �@�ȏ�ɂ��A�ŕ��S�̌����ȊO�ɖ{�����ݎ،_���������邱�Ƃ̍����I�ȗ��R�ƂȂ鎖�ƖړI���̑��̎��R�����݂���Ƃ�����B�v |
1�Ł�330.02�R�H�s���Y�����E�Ŕ����a52�N7��12����23��8��1523��
3�Ł�340.04�r���s�����E�����n���������N4��17����35��10��2004��
5�Ł�340.04�p�`���R���a�����E�Ŕ�����16�N7��20����51��8��2126�ŕS�I4��94
�]�ݕ����E�Ŕ�����6�N6��21����41��6��1539�ŕS�I6��52
�a�@�Ǘ�����E�����n������4�N2��20���s�W43��2��157��(�����p����w�d�Ŗ@���K�m�[�g�x4��165�Łu������s���Y�����H�v)
5.1.2. �[�ŋ`����
5.1.2.1. ���܂��܂Ȗ@�l
5.1.2.1.a. �@�l�̕���
| �����n���ߘa5�N2��17���ߘa��(�s�E)539�����^1514��144��(�ꕔ�F�e)(���ԑ叇�E�W�����X�g1597���d����5�N176�ŁA�����M�s�E�W�����X�g2025�N1�����f�ڌ���)�c�c����(X�@�l)�́A�����@42��2���̓��ᖯ�@�@�l(���v���Ƃ����ې�)���畽��23�N2��3���Ɉ�ʍ��c�@�l(��c���^)(�S�����ې�)�ֈڍs�����BX���ڍs�O�Ɏ擾�����L���،��ƌ������p���Y�ɂ��āA�擾�����z���擾���z�Ƃ��Ĉ����ׂ����ڍs�����z���擾���z�Ƃ��Ĉ����ׂ���������ꂽ�B�����͎擾�����z�����̗p���T�ː�����F�e�����B�����̓�d�v��̉\�����w�E����퍐(��)�̎咣�ɂ��ꕪ�̗��͂���(�d�Ŕ��ጤ����ł͕]�҂͎��g�̌����͏q�ׂȂ��������t���A����͍����x������ӌ����o��)�����������̗����������Ă��邪�A�@�l�Ŗ@�{�s��119����2��1��1���́u�擾�v�̕������߂����ߎ�ƂȂ����Ɠlj��ł��悤���B |
| 6�Ł�312.04 �@�l�����4.5.2.�E����56��(�Ƒ����K�v�o��s�Z��)�E57��(��]�ҍT��)�Q�� |
COLUMN5-2 ��c���^�@�l
| 6�Ł�312.02�y�b�g���ՋƎ����E�Ŕ�����20�N9��12������2022��11�ŕS�I7��51no ��2�@���@�l�̐Ŗ� |
5.1.2.1.b. �l�i�̂Ȃ��Вc��
| 5�Ł�312.03�F�{�˂��ݍu�ŋ��i�����E������������2�N7��18����37��6��1092�ŕS�I5��22np(�}���`�̐���) �@�l�Ŗ@�R���u�l�i�̂Ȃ��Вc���́A�@�l�Ƃ݂ȁv���B ���Q���W���u�l�i�̂Ȃ��Вc���@�@�l�łȂ��Вc���͍��c�ő�\�Җ��͊Ǘ��l�̒�߂�������̂������B�v �����E���_�@�`(��ɔj�Y���A�j�Y�Ǎ��l�w�������ƂȂ�)���c��ł����l�Y�~�u���Ƃ�V����Ƃ̉�ɑ��^�����Ƃ��āA�x�Ŗ��������`�ɑ�����59�����݂Ȃ����n�ېł����݂�B��͎Вc�ɓ����邩�H ���|�@�u�l�i�Ȃ��Вc�v�T�O�͑d�Ŗ@�Ǝ����H�����u�����\�͂Ȃ��Вc�v�������̖@��̊T�O���ؗp�B �Ȃ��Ǝ��ɉ��߂��Ȃ��̂��H�����u�@�I���萫�v�u�������̖@�ƈ�`�I�ɉ��߂����̂������v �Вc�̐����v���́H�����u�l�̈ӎv�Ɨ��ꂽ�ʌƗ��̒c�̈ӎv�̑��݁v�u���Ɗ������ɗv����c�̌ŗL�̎��Y���l�Əs�ʂ���đ��݂���v �{���ւ̓��Ă͂߄����u���Ԃ͌l���Ƃł���̂ɂ�����������A�l�i�Ȃ��Вc�Ƃ����`���ɖ����肽���ٖ̈��̂��̂ł���ƒf����̂������v���l�i�̂Ȃ��Вc�ɓ�����Ȃ��B �������̖@��̎Вc�̐���4�v�� �Ŕ����a39�N10��15�����W18��8��1671�� [1]�c�̂Ƃ��Ă̑g�D [2]�������̌��� [3]�\�����̕ύX�ɂ�������炸�c�̂��̂��̂����� [4]���̑g�D�ɂ���đ�\�̕��@�A����̉^�c�A���Y�̊Ǘ����c�̂Ƃ��Ă̎�v�ȓ_���m�肵�Ă���Bah |
| 6�Ł�312.03�}���V�����Ǘ��g�������E�����n������30�N3��13����65��8��1228�ŕ���28(�s�E)411���E������������30�N10��31������30(�s�R)104��(�ݓc��v�E�W�����X�g1541��119��)�c�u�l�i�̂Ȃ��Вc���v�ɊY������Ƃ�������B ��R���|�@�u�@�l�Ŗ@��̐l�i�̂Ȃ��Вc���Ƃ́C�@�l�łȂ��Вc���͍��c�ő�\�Җ��͊Ǘ��l�̒�߂�������̂������Ƃ���i���@�Q���W���j�C���̂����@�l�łȂ��Вc�́C�������̖@�ɂ����錠���\�͂̂Ȃ��Вc�Ɠ��`�Ɖ�����邩��C����c�̂��l�i�̂Ȃ��Вc���ɊY������Ƃ������߂ɂ́C�@�c�̂Ƃ��Ă̑g�D������i�v���P�j�C�A�������̌������s���i�v���Q�j�C�B�\�����̕ύX�ɂ�������炸�c�̂��̂��̂��������i�v���R�j�C�C���̑g�D�ɂ���đ�\�̕��@�C����̉^�c�C���Y�̊Ǘ����̑��c�̂Ƃ��Ă̎�v�ȓ_���m�肵�Ă���i�v���S�j���̂łȂ���Ȃ�Ȃ��Ɖ������i�m�Ŕ����a39�N10��15�����W18��8��1671�Łn�Q�Ɓj�B�v �u�@�O���y�я؋��c�ɂ��C�����́C�{���}���V�������тɂ��̕~�n�y�ѕ����{�݂̊Ǘ������s�����Ƃ�ړI�Ƃ��āC�{���敪���L�ґS���ɂ���č\�������c�̂ł���C�{���}���V�������Ɏ��������u����Ă���ق��C�{���K��̋c�������ɂ��ċc�����s�����߂ɑ���J�Â���i�{���K��S�U���`�T�U���j�C�����Ƃ��ĂS���̗����y�тP���̊Ď�������ɂ��I�C����i�{���K��R�U���P���j�C�����̌ݑI�őI�C����闝�����͌������\���C�����̋Ɩ������s������̂Ƃ���i�{���K��R�U���Q���C�S�P���j�C�܂��C�����������ė�����\������ď���̋Ɩ����s�����̂Ƃ���Ă���i�{���K��T�V���`�U�P���j���Ƃ��F�߂��C����ɂ��C�����͒c�̂Ƃ��Ă̑g�D������Ă�����̂ƔF�߂���B�v �u�A�g�����͏Z�˂P�˂ɂ��P�c������L���C����̋c���͏o�ȑg�����̋c�����̉ߔ����Ō�����ȂǂƂ���Ă���i�{���K��T�O���C�T�R���j�C�����ɂ����Ă͑������̌������s���Ă�����̂ƔF�߂���B�v �u�B�{���}���V�����̋敪���L���̏��n���ɂ���Ė{���敪���L�҂ɂ��ύX���������ꍇ�ł��C�V���ɋ敪���L�҂ƂȂ����҂͓��R�ɑg�����ƂȂ���̂Ƃ���Ă���i�{���K��R�P���j�C�\�����̕ύX�ɂ�������炸�����Ƃ����c�̂��̂��̂�����������̂ƔF�߂���B�v �u�C��L�̂Ƃ���C�����̗��������������\���C�����̋Ɩ������s������̂Ƃ���Ă����C�{���K��ɂ����āC����̊J�Î����C���W�葱��c���Ɋւ��鎖������߂��i�{���K��S�U���`�T�U���j�C���v��i�{���}���V�����̕~�n�y�ы��p�������̊Ǘ��ɗv�����p�j�̕��S���v�Ɋւ����߂��u����Ă���i�{���K��Q�T���`�R�O���C�U�Q���`�U�W���j���ƂȂǂ���C��\�̕��@�C����̉^�c�C���Y�̊Ǘ����̑��c�̂Ƃ��Ă̎�v�ȓ_���m�肵�Ă�����̂ƔF�߂���B�v |
COLUMN5-3 �@�l�ېŐM��
5.1.2.2. �ېŕW��
5.1.2.2.a. �e���ƔN�x�̏���
5.1.2.2.b. ���v���Ɖې� (���v�@�l������ѐl�i�̂Ȃ��Вc��)ag
5.1.2.3. �ŗ�(�@��66���A�d��42����3��2)
5.1.3. ��Ж@�E��Ɖ�v�Ƃ̊W
5.1.3.1. �m�茈�Z��`(�@��74��1��)
�@��22��4��:���������(��Ж@431��) �� ��v�̎O�d�\���@ �@��74��1�������u�����@�l�́A�e���ƔN�x�I���̓��̗�������ȓ��ɁA�Ŗ������ɑ��A�m�肵�����Z�Ɋ�Â����Ɍf���鎖�����L�ڂ����\�������o���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�v�m�e���E2���ȉ����n5.1.3.2. �����o����
�����o��(2��25��)�̗v���c�c�t����̖�肪�w�E�����Bip5.1.3.3. ���������(��Ɖ�v������`)
| 6�Ł�321.02��Ɖ�v�Ƃ̊W �呠�Ȋ�Ɖ�v�R�c��ԕ��u�Ŗ@�Ɗ�Ɖ�v�Ƃ̒����Ɋւ���ӌ����vhq �Ŗ@�A���@�A��Ɖ�v�����́A���ꂼ��ŗL�̖ړI�Ƌ@�\�������Ă���B �������v�c����E���ғ��̗��Q�����@�\�Ə��@�\ �����@��v�c����y�щ�Ѝ��҂̗��v�ی�̂��߂̗��Q�����y�я��� �i�؎�@��v�c�����ҕی�̂��߂̏��c�Ȃ�ׂ����v��傫���B�������Z�̗U���j ���Ŗ���v�c�[�ŎҊԂ̌����i�Ȃ�ׂ��������������B�t�������Z�̗U���j�A�Ŗ����s�̓K���E�m���� |
| 5�Ł�321.03(6��390��)��|�f�Վ����E�Ŕ�����5�N11��25�����W47��9��5278�ŕS�I7��65hr �����E���_�@�[�Ŏ҂͈ב֎�g������A�ېŒ��͑D�ϓ�����咣 ���|�@�u���ɖ@�l�̂������v�v�Z���@�l�ł̊�}��������ȏ����v�Z�Ƃ����v���ɔ�������̂łȂ�����v�A�ېŏ����̌v�Z�����������e����A�Ƃ̈�ʘ_�̉��ŁA�{���ł͔[�Ŏ҂̗̍p������v�������F�߂��Ȃ��������Ƃɗ��ӁB(������2�l�̔��Έӌ��t���̍ۂǂ����f)�@cf.��4.4.2.�����m���` |
| 6�Ł�321.03����������\�\�O�����v�C�� �N�����B�X����(���v���~�X����)�E�Ŕ��ߘa2�N7��2�����W74��4��1030�ŕS�I7��66ag(������q�E�W�����X�g1559��131��)�c�c���������@�ᔽ�������Ă���A�s�������ԊҐ������ĕԊ҂��邱�ƂƂȂ����ꍇ�A�ǂ̔N�x�̑����Ƃ��ׂ����B�T�i�R�́A�������ߗ�����̔N�x�̉v���̊z�����z����v�Z������������ɍ��v����Ƃ��Ă������A�ō��ق͕������B �ō��ٔ��|�@�u�@�l�ł̉ېłɂ����ẮC���ƔN�x���ƂɎ��v���̊z���v�Z���邱�Ƃ������ł���Ƃ����邩��C���Ƃ��c�ޖ@�l����̂��C�\�����Ɏ��v�v�コ�ꂽ�������ߗ������ɂ��C��ɂ��ꂪ���������@����̐����������Ă��邱�Ƃ𗝗R�ɕs�������Ƃ��ĕԊ҂��ׂ����Ƃ��m�肵���ꍇ�ɂ����Ă��C����ɔ������R�Ɋ�Â���v�����Ƃ��ẮC���Y���R�̐��������̑����鎖�ƔN�x�̑����Ƃ��鏈���C���Ȃ킿�O�����v�C���ɂ�邱�Ƃ�����������ɍ��v����Ƃ����ׂ��ł���B�v cf.���É��n������13�N7��16�����^1094��125�ŕ���12(�s�E)14���m��(�������E�W�����X�g1232��201��)�c�c�Ζ��̔���Ђ��v���y�C�h�J�[�h�̔��s�ɍۂ��Ď���Ή��ɂ��A���s���Ɏ��v�Ƃ��Čv�シ�邱�ƂȂ��a����Ƃ��ď������A���̃J�[�h�̏����҂������ɏ��i�ƈ��������������_�Ŏ��v�v�シ������́A�Љ�I�ɔF�m����Ă��������ł��������̂́A�@�l�Ŗ@22��4���̌���������Ɉᔽ����B�v���y�C�h�J�[�h�̖��g�p�����ɌW�锭�s�Ή������̔��s�������̑����鎖�ƔN�x�̎��v�Ƃ��ĉv���ɎZ�����ׂ��B cf.TFK������Ў���(�����x�m����)�E�����n������25�N10��30����60��12��2668�ŕ���24(�s�E)212���������p�E������������26�N4��23����60��12��2655�ŕ���25(�s�R)399���T�i���p(�n�ӗT�N�E�W�����X�g1477��111��)�c�c���������@�ᔽ�������x�����Q�����Ă����@�l���|�Y���ߕ����ԊҐ������ɌW������X�����Ƃ��Ċm�肵���ꍇ�ɁA�]�O�v���Z�����Ă������������@�ᔽ�������x�����Q���ɂ��čX�������ׂ��|�̐����������Ƃ���A���p����A�O�����v�C�������ׂ��Ƃ��ꂽ����B ���a40�N���̖@�l�Ŗ@�͉�v�����̐F�������������A���a60�N������ېŒ����[�Ŏ҂̉�v�����ɑ��ăA�^�b�N���d�|����悤�ɂȂ�A���̏W�听������5�N��|�f�Վ����ō��ٔ����ł������B�u�@�l�ł̊�}��������ȏ����v�Z�Ƃ����v���v���A����5�N���͂��قNj�������ĂȂ��������A����20�N��ȍ~�A���������悤�ɂȂ�A��Ɖ�v�̐��E�ł͈�ʓI�ɔF�߂��Ă��鏈���ł��@�l�Ŗ@��͔F�߂��Ȃ��Ƃ����ٔ��Ⴊ�o�ꂷ��Ɏ������B���A��Ɖ�v�Ɩ@�l�Ŗ@22��4���Ƃ̊W�͂��Ȃ�ْ����̂���W�ɂȂ��Ă���B �s���Y�M������������(�r�b�N�J��������)�E�����n������25�N2��25����60��5��1103�Ő������p�E������������25�N7��19����60��5��1089�ōT�i���p�S�I7��59�c�c�s���Y�����������w�j�Ɋ�Â������̉�v�����i�A�����Ă̓��ꐫ�Ƃ��ĉ�v�����̎���I�Ȓ����\�\������،�������Ď��ψ���̎w���ɂ������\�\�Ƃ��čX���̐����������Ƃ�������������j���@�l�Ŗ@22��4���̌���������ɍ��v���Ȃ��Ƃ��ꂽ����B�B ���M������������(�I���b�N�X��s����)�E�����n������24�N11��2���Ŏ�262������12088�������p�E������������26�N8��29���Ŏ�264������12523�����F�e(�g������E�W�����X�g1451��8�ŁA��ȏ͔@�E�����@�w87��204���A�����C��E�W�����X�g1475��8�ŁA�_�R�O�s�E��27�d��189��)�c�c��R�͋��Z���i��v�����w�j105�������߂��A105���̗v�������Ă��Ȃ��Ƃ���105���ɉ�������v���������������̎咣��˂����B�������T�i�R�ŕ������B ����Y�m�u�ߎ��̔��ᓙ�ɂ݂�d�Ŗ@�̌����E�����v�d�Ō���769��104��(2013.11)�Q�ƁB ���ŕs���R�����ߘa6�N2��26���ٌ��E�ٌ�����W134�W�c�c���S�ی��������S��(�ߘa3�N12����)�ɉv���Z������邩�ی���Ђ̐R����(�ߘa4�N12����)���B�ߘa4�N12�����B(�k���L�u�łŃ�������ǂ�����(��10��)�`�܂����炦�邩������Ȃ���I�`�v2025.3.14) |
5.2. �@�l�̏����v�Z
5.2.1. ���v��p�A�v���[�` (��4.4.1.)
5.2.2. �v���̊z�̌v�Z
5.2.2.1. ���v�͈̔�
5.2.2.1.a. ���v�̈Ӌ`
6�Ł�321.05���{�����(�@��22��5��)�F�u�@�l�̎��{�����̊z�̑������͌������������тɖ@�l���s�����v���͏�]���̕��z�c�c�y�юc�]���Y�̕��z���͈��n���������B�v���{�����̊z(2��16��(�ȑO�́u���{���̋��z�v))�F�u�@�l�c�c�����哙����o���������z�c�c�v
cf.���v�ϗ����z(2��18��)�F�u�@�l�c�c�̏����̋��z�c�c�ŗ��ۂ��Ă�����z�c�c�vai
���v���(�@�ߗp��ł͂Ȃ��u�w��̗p��)�F���{������ȊO�̎���ł���A���v�̑����������炷�B�Ȃ��A�@�l�Ŗ@�́u����c�ɌW��c���v�v�ƋK�肵�Ă���̂ŁA������`�̍l��������{�Ƃ��Ă���Ɨ��������B
���{������ɂ���Ă��@�l�̎��Y�͑�������(cf.����������{�����Y����)���A���{������̂����̑O���͖@�l�E����Ԃ̎��Ȏ���ƍl������̂ŁA�@�l�̗��v�̌v�Z�ł͔r������B�㔼�́A�@�l�̉ېŏ�����@�l�̗��v�Ɗ�{�I�ɓ������̂ƍl���邱�Ƃ̕\��Ƃ�����B cf. �������aj
6�Ł�322.01�v���T�� �@�l�Ŗ@22��2���u�����@�l�̊e���ƔN�x�̏����̋��z�̌v�Z�㓖�Y���ƔN�x���v���̊z�ɎZ�����ׂ����z�́A�ʒi�̒����������̂������A���Y�̔̔��A�L�����������ɂ�����Y�̏��n�����̒��A�����ɂ�鎑�Y�̏������̑��̎�������{������ȊO�̂��̂ɌW�铖�Y���ƔN�x�̎��v�̊z�Ƃ���B �v
���u�ʒi�̒�߁v��F�@�l�Ŗ@23���@�@�l�����z���v���s�Z��
�@�l�̎��z�����ɑ��Ă͎x���@�l�̒i�K�Ŋ��ɖ@�l�ł��ۂ���Ă��邩��A�@�l�����ɑ�������ېł��邱�Ƃ�����邽�߂ɂ́A���@�l�̒i�K�ł����@�l�ł̑Ώۂ��珜�O����K�v������B
���u���{������v�u���(������`)�v�c�c���q
���u�L�����͖����v�u���Y�̏��n���͖̒v�c�����ł��v���v�オ�v�������(6�Ł�322.02, 6�Ł�322.03)�B
�@ �@�u�L���v�{�u���Y�̏��n�v
�@ �@�u�L���v�{�u�̒v
�@ �@�u�����v�{�u���Y�̏��n�v�̎l�ʂ肪����B
�@ �@�u�����v�{�u�̒v
���u�����ɂ�鎑�Y�̏��v�c�c�v����Ɏv(6�Ł�322.04)(���F�����Ŗ��邱�Ƃ͉v���v�サ�Ȃ��B�x�o���ׂ���p���������A���̕������ېŏ������������邩��)
�����Q�������̎擾���v���Z��(����9��1��17���Ƃ͈Ⴄ)
���@�l�Ŗ@22����2�Ŏ��v�̊z�̖��m����}��B
| �^�C�L�����s�����E�����n������22�N3��5���Ŏ�260������11392����19(�s�R)754��(�ҕx�v�E�W�����X�g1431��168��)�E������������22�N12��15���Ŏ�260������11571����22(�s�R)136���E�Ō�����24�N5��8���Ŏ�262������11945�c�^�C�֘A��Ђ̊z�ʔ��s�����̈����ɔ��������Ƃ̍��z�̎v���v�����\������Ƃ�������B([���]���������̊��������l�����Ȃ��������Ƃ̓��ۂɂ��ẮA�c�_�̗]�n�����肻���ł���B�����n�ق͊������͖����������ł��邩��l�����Ȃ��Ă悢�Ƃ����B����͂܂�A�������������ۂɏ��n�����ۂ̏��n�����̔������܂ő҂A�Ƃ������Ƃł��낤�B) |
| ���Y�����E�����n������24�N11��28����59��11��2895�ŕ���22(�s�E)314���A������������26�N6��12����61��2��394�ŕ���24(�s�R)480��(�g���T�v�E�W�����X�g1472��8�ŁA�J�����Õv�E�d����26�N213�ŁA�c���G���E�W�����X�g1489��130�ŁA�������E�@������86��9��130��)�E�ňꏬ������27�N9��24������26(�s�c)385������26(�s�q)416���c�c�q��Ђ̊�����ۗL����e��Ђ��A�q��Ђ̊������p�ɔ����A�K�����n�Ή����Ⴂ���z�̕��ߋ�������̂��Ȃ������ꍇ�A�����@��̌������ߌ��x���ߕ����ł����Ă��v���Ɍv�ス�˂Ȃ炸�A�X�ɖ@�l�Ŗ@37��1���̊�t���ɊY������Ƃ��ꂽ����B |
�Ŕ����a46�N11��16���Y�W25��8��938��(��5.2.2.2.b)
���Q�����������F��h�v���X�`�b�N�X�����E�Ŕ����a43�N10��17����14��12��1437��(��5.2.2.2.a)
5.2.2.1.b. �������
| 6�Ł�322.02�����ɂ�鎑�Y�̏��n �쐼�ʏ�������Ў����E�Ŕ�����7�N12��19�����W49��10��3121�ŕS�I7��52ak �����E���_�@X1�Ђ�X2���S�z�o�����Ă����Ђł���AX2����\������Ƃ��Čo�c���x�z���Ă���BX1�͏��a55�N�`61�N�ɂ����āA������s�̎������̂Ȃ�����(�{������)��1��225�~��14��9025���擾�����B���a63�N�y�ѕ������N�ɍ��킹��14��9025����1��225�~��X2�ɏ��n�����B����͒�z���n�ɓ�����ƍl����Y�Ŗ������́AX1�ɂ��Ă͎����Ƃ̍��z���v���Z�����AX2�ɂ��Ă͎����Ƃ̍��z�̋��^����(�ܗ^)�����̂ƔF�肵�āA���ꂼ��X��������ł����B ���|�@�㍐���p(�������p) �@�u���Y���������n�����v�̔��������ƂȂ�v�B�u�����t��Ȃ����̂ł����Ă��A���n���ɂ����鎑�Y�̓K���ȉ��z�ɑ���������v���F�����ׂ��v�B(�����n�����ېłɊւ������Z�ې����Ɨގ��̔��z) �@��z���n�̏ꍇ�Ɂu�K���ȉ��z�Ƃ̍��z�����̎��v���F�����꓾�Ȃ����̂Ƃ���A�O�L�̂悤�Ȏ戵�������������n�̏ꍇ�Ƃ̊Ԃ̌������������ƂɂȂ�v�B �@�u���Y�̒�z���n���s��ꂽ�ꍇ�ɂ́A���n���ɂ����铖�Y���Y�̓K���ȉ��z�������Ė@�l�Ŗ@22��2���ɂ������Y�̏��n�ɌW����v�̊z�ɓ�����v�B ��R�Ƃ̔�r�c�u����ȑΉ��Ŏ�����s�����҂Ƃ̊Ԃ̕��S�̌������ێ����邽�߂ɁA���������������v�������邱�Ƃ��[�������n�ݓI�ȋK��v���u�@�l�Ŗ@22��2�����K�p����A�{�������̏��n���i�Ǝ����Ƃ̍��z�ɑ���������z���v���ɎZ�������v�B cf.���݃^�N�V�[�����E�Ŕ����a41�N6��24�����W20��5��1146��al�c�cX�͎��Ƃ��s�Ȃ�������Ђł���A�b�Г��̊�����L���Ă����B�b�Г����������c�E�V���̊��劄�����s�����ƂɂȂ����B���AX�͓Ƌ֖@�㑝���V�����擾�ł��Ȃ��W�ɂ������BX�́A�V�����擾������ړI�Ŋ��喼���̖��`�����������A�b�Г����������Ђ̐ꖱ�����A��ɖ��`�ύX�����BA��͕������݂����ĐV����ƂȂ����BA��́A�V�����擾��A������X���`�ɕ��A�������B (�V���v���~�A���Ƃ́c�c�����O�̊�����350�~�ł��鎞�ɋ���1���ɂ��ĐV��1����V���������z50�~�Ŕ��s�����Ƃ���B(350+50)/2��200��葝����̊�����200�~�ƂȂ�̂ŁA���z��150�~���V���v���~�A���ƂȂ�B�Ȃ��������L�҂�150�~������B) Y�Ŗ������̏����E�咣�@{(�V���̉��z)�|(�������z)�̎c�z}��X�̉v���ɉ��Z�����BX���V������A��ɖ������n�������̂ł���A�V�������ܗ^�i�Q�ƁF���@�l�Ŗ@34���F�������^�������s�Z���j�Ƃ��ė��v�����������̂ł���B X�̎咣�@�Ƌ֖@�̋K���ɂ�茳�XX�͐V�����擾�ł��Ȃ��B�V������^������ׂ���������ɂ����銔��Ƃ͊��喼���̊���ł���B�]���āA�e��������̊��喼���̊���ł���A��͊�������ɂ��̐V�����R�����n�I�Ɏ擾�����B ���|�@�j�����߁i�����I��X�s�i�j (1)���Ɍo�ϓI���l�����邩�@�u��O�҂ɐV�������������邱�Ƃ̂ł���X��Ђ̒n�ʂ��̂����́A���K�Ɍ��ς��邱�Ƃ��ł����o�ϓI���l���闘�v�v�B�@�u�Ƌ֖@10���v���V���擾���ւ��Ă��Ă��u�����ɂ�肻�̊����ʂ����ׂ����v����Ђɂ����Ď����㋝�邽�߂ɍ̂�s�ׂ܂ł��Ƃ����|�Ƃ͉����������v�B�@�uX�́vA�炩��u�����̑Ή��v���邱�Ƃ��ł����͂��Ȃ̂Ɂu�O���̍s�ׂ��������Ƃ́A������Ђ̊����̏��L�Ɋ�Â�X������o�ϓI���v���ŏd�Ɏ��^�������Ƃ��Ӗ��v����B (2)�o�ϓI���v�̈ړ]�͉��ɂ��Đ��������@�u�ړ]�̑ΏۂƂȂ����o�ϓI���v�́A�����X���L�̑�����Њ����ɂ��Đ�����V���v���~�A������\���������̂Ƃ݂��A���̗��v�̈ړ]�́A���Џ��L�̑�����Њ����̒l��蕔���c�c�̉��l�̎ЊO���o���Ӗ�����v�B�@�u�����̒l��肪X�̉E�����̎擾���z(�L�����z)��������̂�����Ȃ�A���̕����͓��Ђ����v��̎��Y�v�B (3)�o�ϓI���v�̈ړ]������Ƃ��ĉ��̂�����v�シ��K�v�����邩�@�u���v��̎��Y���ЊO���o�v�ɂ�����u����ɓK���ȉ��z��t���ē��Ђ̎��Y�Ɍv�サ�A���o���ׂ����Y���l�̑��݂Ƃ��̉��z�Ƃ��m�肷�邱�Ƃ́AX�����Y�̑����m�ɔc�����邽�ߓ��R�K�v�ȑ[�u�ł���c�c���̑������Y�z�ɑ�������v��������������̂Ƃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�B (4)�v���E�����ɂ��ā@�u�d�Ɉړ]�������v�ɓ��Ђ̖��v��̎��Y���l���܂܂��ƔF�߂��邩����A���Y���ƔN�x�ɂ����Ă���ɑ��������v���̔������m�肹��������Ȃ��v�u���ʂ��̏d�ɑ��闘�v���^�ɂ��X�̎��Y�̌��������Ə�������ƂȂ����������̂Ƃ���c�v ���݃^�N�V�[���������Ɠ��l�̍l�������̗p������Ƃ��āA�܂��炸�⎖���E��㍂�����a43�N6��27����14��8��948�ŏ��a38(�l)353���B |
| 6�Ł�322.03�����ɂ��̒� �����y�����E��㍂�����a53�N3��30������925��51�ŕS�I7��53am �����@X�ЁET�Ђ͐e�q�W�Ŗ@�l�Ŗ@��̓������(�@�l�Ŗ@132���ɂ��Ă͌�q)�BX��T��2654���~�����ŗZ��(�u�{���������Z���v)�����BY�Ŗ������́A�{���������Z���ɂ��āA�N10���̗����ɂ�����������z�����ƔF�肵(�@�l�Ŗ@37���Q��)�A�������s�Z���z�Ƃ��āA���a39�N��206��1013�~�A���a40�N��258��2134�~�����Z�B��R�ł͑d�ʼn���s�ׂ̔۔F���F�߂�ꂸ�AY�T�i�B �x�T�i���R�@�{���������Z���ɌW�闘�������z�́A�@�l�Ŗ@22��2���́u�����ɂ��̒v�ɌW����v�Ƃ��ĔF������AX�̉v�����\������B��(��`��37��7��)�Ƃ��ĎЊO���o���Ă���A�@37��2��(�����B��3���A�y�ю{�s��73��)�̊������Z�����x�z���镔���͉v���Ƃ��Čv�シ�ׂ��B ���|�@�������ύX�E�m��B�N6%�̗��������z�͈̔͂�Y�̏������ێ��B �@(��)�@22��2���́u���{������ȊO�ɂ����Ď��Y�̑����̌����ƂȂ�ׂ���̎���ɂ���Đ��������v�̊z���v���ɎZ�����ׂ����̂Ƃ����|�Ɖ������B�����āA���Y�̖������n�A�̖������́A�����I�ɂ݂��ꍇ�A���Y�̗L�����n�A�̗L���ɂ���������㏞���ŋ��t�����̂Ɠ����ł���v �@(��)�@���K�͊�Ɠ��ŗ��p����邱�Ƃɂ��ʎ��������炷�B���炪���p���Ȃ��ꍇ�ł��u�����Ƃ���s���̋��Z�@�ւɗa�����邱�Ƃɂ�肻���ʎ������z�̗��v�����̗����̌��x�Ŋm�ۂ���Ƃ�����i�����݂��邱�Ƃ��l����v�c���@�l�̖������Z���͒ʏ킠�肦�Ȃ��v�B�@�������ݕt�������ꍇ�u�����I�Ȍo�ϖړI���̑��̎��������ꍇ�łȂ�������c�c�ʏ킠�肤�ׂ������ɂ����K�����z�̌o�ϓI���v���؎�Ɉړ]�������̂Ƃ��Č��݉������v�̂ł���A�����Ƃ��āu���v�Ƃ��ĔF������邱�ƂɂȂ�v�B �@(�O)�@�@37��5��(�����B��7��)�ɂ��u���v(cf.��5.2.3.5.c.)�̒�`�B�@���̂����u�ǂꂾ������p�̐����������A�ǂꂾ�������v�����̐������������q�ϓI�ɔ��肷�邱�Ƃ�����ł���Ƃ��납��A�@�́A�s���I�X�y�ь����̈ێ��̊ϓ_����A���̃t�B�N�V�����Ƃ��āA����I�ȑ����Z�����x�z��݂��v���B�@�u�@37��5��������������̂��̂ɊY�����Ȃ�������A���ꂪ���ƂƊ֘A��L���@�l�̎��v�ݏo���̂ɕK�v�Ȕ�p�Ƃ�����ꍇ�ł����Ă��A�������������Ƃ͂Ȃ��v�B �@(��)�@���Ă͂߁c�u���炩�̍����I�Ȍo�ϖړI���̂��߂ɂs�Ђɂ�����ŋ������v���H ���|(��)���u�w����i�K���ƌĂ��B�w���ɂ͈٘_������(�����Y���A���q�G���ɂ��ĊT���Q��)�B ���|�͖@�l�Ŗ@37��1���̊��ېł��m�F�I�K��ƈʒu�t���Ă���B�����n�ݓI�K��Ȃ�Ζ@�����O�ł��鏺�a39�N�ɂ��Ċ��ېł����邱�Ƃ������t�����Ȃ��Ȃ�B�@([���]��^��B�B���ɑ����Z�����x�z�ɂ��Ắu���̃t�B�N�V�����v�Əq�ׂĂ���Ƃ���A���@���ɂ����Ė���������Ă��Ȃ��t�B�N�V�����Ȃǂ��肦�Ȃ����낤) �@�v�Z�̎菇�c�c�{���́A�{���������Z���ɌW�闘�������z�S�z���v���v�サ�A���ɁA37��(�{�{�s��73��)�ɂ�鑹���Z�����x�z�͈͓̔��ő����v�シ�ׂ��B������������̓l�b�g�z�̂݉v���v�サ�Ă���B �����I�Ȍo�ϖړI�c�c�@���9-4-2(�q��Г����Č�����ꍇ�̖������ݕt����) �@�l�����̎q��Г��ɑ��ċ��K�̖����Ⴕ���͒ʏ�̗��������Ⴂ�����ł̑ݕt�����͍��������i�ȉ�9�|4�|2�ɂ����āu�������ݕt�����v�Ƃ����B�j�������ꍇ�ɂ����āA���̖������ݕt�������Ⴆ�Ɛѕs�U�̎q��Г��̓|�Y��h�~���邽�߂ɂ�ނ��s������̂ō����I�ȍČ��v��Ɋ�Â����̂ł��铙���̖������ݕt�������������Ƃɂ��đ����ȗ��R������ƔF�߂���Ƃ��́A���̖������ݕt�����ɂ�苟�^����o�ϓI���v�̊z�́A���̊z�ɊY�����Ȃ����̂Ƃ���B�m(��)���n ([���]�e��ЂƎq��ЂƂ͕ʌ̖@�l�i��L���Ă���̂ł��邩��A�e�q��̂ƌ���悤�ȏ�L�ʒB�͂��������̂ł͂Ȃ����A�Ƃ̔ᔻ���l������B�������A�e��Ђ��q��Ђɗ��v���ŋ��^���Ă��A���̗��v�̕������e��Ђ̎��Y���������ɁA�e��Ђ��ۗL����q��Ђ̊����̉��l���オ��̂ŁA�i����100���ۗL�W�ł���ꍇ�ɂ́j���ǂ̂Ƃ���e��Ђ͉����������Ă��Ȃ��A�ƌo�ϓI�ɍl���邱�Ƃ��ł���B�ނ��A�ۗL�q��Њ��̉��i�㏸�A�Ƃ������̘_���́A��ɔF�߂���킯�ł͂Ȃ��̂ŁA�����܂ŕ⋭�I�Ș_���ł���ɂ����Ȃ��B�Ⴆ�A�q��Ђ������߂Ɋׂ��Ă���ꍇ�A�q��Њ��̉��i��0�����ɂ͂Ȃ�Ȃ�����A�e��Ђ����v���q��Ђɖ����ŋ��^���Ă��A�q��Њ��̉��i��0�̂܂܂ł��邱�Ƃ����肤��B���̋��o�P�c�̂悤�Ȃ��́B����ł��Ȃ������F�肳��Ȃ����Ƃ������I�ɐ�������ɂ́A�q��Ђ̌����_�ł̓|�Y�h�~�������e��Ђɗ��v�������炷�\��������A�Ƃ����������ɂȂ낤�B) ������Вr��������E�����n������27�N4��24������24(�s�E)847�����p�E������������27�N11��26������27(�s�R)197�����p�c100%�q��Ђɑ���������̑ݓ|�����̌v�オ�F�߂�ꂸ�@�l�Ŗ@37��1���ɂ������ɓ�����Ƃ��ꂽ����B����ʼnېŕW���z����̍T�����ł��Ȃ��Ƃ��ꂽ����B �Ɨ���Ɗԉ��i(�u�w��͓Ɨ������Ҋԉ��i�Ƃ������B�p��arm's length price) �@�`���ŗ�20���@�������i�H�@�a���ŗ�40�� �d��200���o�Ё��������ԁ����r�Ё�����҂�1000 ������p400�@�@�@�@�@�@�̔���p100 �@�@�@�@�@�� �@�@�@�@�@���@�@�������i800 �@�@�@�@�@�����������ԁ�����O�ҁ�����҂�1000 �o�r�Ԃ̉������i���Ɨ������Ҋԉ��i800�Ȃ�A�o�Ђ�����200�A��40�A�r�Ђ�����100�A��40�A��Ђ��ł̍��v��80�A�o�r�Ԃ̉������i��900�ɂ����(���i����)�A�o�Ђ�����300�A��60�A�r�Ђ�����0�A��0�A��Ђ��ł̍��v��60�B �@�{���ł�X�ET���֘A��Ђł��邪�A�Ɨ��̓����҂ł������Ȃ�Εt����Ă����ł��낤�����̊z�������A�K���ȗ��������z�Ƃ�����B�d�ʼn���̈��@�ɁA�ړ]���i(transfer pricing)�Ƃ������̂�����B���ɍ��ۉېłŖ��ƂȂ�B���ێ���ɂ��ẮA�ړ]���i�ɂ���Ċ֘A�ҊԂŏ����̐U�ւ��s�Ȃ��Ă��A�Ɨ������Ҋԉ��i�ɂ��K���ȗ��v�̌v�オ���������B(�d��66����4��8.4.2.) �@����:�ٔ����́A���Ȃ��Ƃ���s�a�����q�ȏ�̉ʎ���X�͌��{���K���瓾����͂��A�Əq�ׂ�B([���]����X�ɋ�s�a���ȏ�̗L���ȋ��K���p�Ȃ������̂ł���A��s�a�����q�̊z�������K���ȗ��������z�ł���Ƃ���l���������肤��i���������̍l�����ɂ���s�a��������悢�̂ł��邩��F�肪�ȒP�ɂȂ�Ƃ������_������j�BX�ɂƂ��Ă���ȏ�̗��v����Ȃ������̂ł���AX���v���Ɍv�サ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��z�����̌��x�ɂƂǂ߂���ׂ��ł���Ƃ���l�����ł���B���������炭���̂悤�ȍl�����͍̂��Ă��Ȃ��B���Ɂi�{���I�ᔻ�ł͂Ȃ����jX�ɋ�s�a���ȏ�̗L���ȋ��K���p�Ȃ��������Ƃ��m�F����̂��ʓ|�ł���B���ɁAX�����̗��v��\�������������ɒ��ڂ��Ă���̂ł͂Ȃ��AX��T������̑㏞��͂��ł��������ɁA�K��y�эٔ����͒��ڂ��Ă���B�ٔ����̋�s�a���̂�����́A�����܂Łu�����Ƃ��v�̘b��ł���Ɨ��������ł��낤�B) ��ЊԂ������U���ɂ��� ���ێ���ƈقȂ�A�����@�l���m�̊Ԃł͕��ʓ����ŗ��ł���B(�ނ��A�֘A�ҊԎ���Ɍl���Ǝ҂���݂���Ηݐi�ŗ��̓K�p�����ƂȂ肤��) �@���ɐŗ��������Ȃ�A����ł��s�s���������邩? �@���F��������B����������Ă���@�l�ɏ������ڂ��Ήېŏ��������炷���Ƃ��ł���B �@���{�ł͈ړ]���i��(�d��66����4)�͍��ێ���ɂ����K�p����Ȃ����A��������ł����Ă��@�l�Ŗ@22��2���y��37���̍��킹�Z�ɂ��@�l�ɋ����I�Ɏ��v���v�コ���邱�Ƃ��ł��邱�Ƃ�����B �@���������̑����Z�����x�z�͈̔͂ŁA�����U�ւ͐�������A�Ƃ�������(���̂��Ƃւ̊w���̔��͋���)�B���̓_�őd��66����4�Ɣ�ׂĉېŌ��ʂ����S�Ɉ�v����Ƃ͌���Ȃ��B �@cf.�A�����J�̋K��(Internal Revenue Code��482)�͍�������ɂ��K�p�����B |
| 5�Ł�322.05(6��403��)�I�E�u���V���z�[���f�B���O�����E�Ŕ�����18�N1��24����53��10��2946�ŕS�I7��54an �����@X��(�����E�I�E�u���V���z�[���f�B���O)���L���Ă��銔(C���ED���F�e�������E����������)�p���邱�Ƃ��l�������A���̊��ɂ͑��z�̊܂݉v������A���ړI�ɔ��p���Ă��܂��Α��z�̉ېł��邱�ƂƂȂ��Ă��܂��B �@X�iE�E�Z���`�����[��49.6%�ۗL�j�͕���3�N�ɃI�����_�Ɏq��ЂƂ���A�ЁE�A�g�����e�B�b�N�i�y�[�p�[�J���p�j�[�j��ݗ��B���̍ہA���k�L��(����10�N�����O�@�l�Ŗ@51��)(���͕s��)�ɂ��ېŌJ�������Ă���(�����Ƃ��ďo�����Y�̊܂݉v��F�����Ȃ���Ȃ�Ȃ�����O�I�Ɋ܂݉v��F�����Ȃ��Ă悢�Ƃ�������)�B���s��������200���ŁA�z�ʋ��z��1��1000�M���_�[�A���v20���M���_�[�i��1500���~)�B���ߊz�͎��{�������B �@����7�N�AE�̓I�����_��B�ЁE�A�X�J�t�@���h��ݗ��B �@A�Ђ�B�Ђɒ������L���ȉ��z�ŐV�������蓖�Ă鑝�������呍��Ō��c�B1��������z�ʋ��z1000�M���_�[��3000���A���s���z���v�z��303��0303�M���_�[(1010.1�M���_�[/���A��5.9���~)�B�V�����������ɂ�����A�Њ����̎��Y���l�͖�234���M���_�[/��(��1��3648���~)�B �@���̐V�������ɂ��AX��A�Њ����ɂ��Ċ܂݉v�̌`�ŗL���Ă������v������(200/200����200/3200���A100����6.25���A��273���~����17���~�A���z��256��)�AA�Ђ̗��v��B�Ђ��x�z�i0/200��3000/3200���A0����93.75���j���邱�ƂɂȂ����B �@�@�@�@�@�@�@�@�@���{�@�@�@ �����@�@�@�@�I�����_ �@�@�@�M������49.6%�@�@�@�@ �@�F�@100%�o��200�����k�L�� �Z���`�����[�d �\�\ �����w�\�\�F�\�\���A�g�����e�B�b�N�` �@�@�@�b�@�e�����E�����������@�F�@�@�@�@�b�V������(3000��) �@100%�b�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�F�@�@�@�@���@�@�@�@�@�b�������n �@�o�����\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�F�\�A�X�J�t�@���h�a�@�b�܂݉v���� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�F�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��(���Ŕ�ې�) �����ҁ��\�n�l�Ё��\�\�\�\�\�\�F�\�\�\�\�\�\�\�i�h�З��@�l �@�@�@��Ɣ����@�@�@�@�@�@�@�@�F�@�@�������p �@�@�`���I�Ɍ���AX��A�Ƃ̊W�A�y��A��B�Ƃ̊W�͕ʁX�ł���B �@�������A����10�N�AY�Ŗ������́AX����B�ɗ��v���ړ]������(�܂݉v�̎������܂�)���̂Ɗώ@���A��t���ƔF�肵���B(�X���������ɂ͖@�l�Ŗ@132���F������ЋK��������Ƃ��Ă������A�i���A��ʓI�ɖ@22��2���F�v���̋K��A�\���I�ɖ@132���̓K�p���咣�B���@�Ɍ�ꂽ�U���h����@�Ƃ����_�_�ɂ��Ă͏ȗ�) �@�������ɕ\��Ă͂Ȃ����AA�̓O���[�v���̕ʂ̃I�����_�@�l(�}��JI��)�Ɋ��������ŏ��n���Ċ܂݉v�����������AJI�Ђ��O���[�v���̓��{�@�l(�}��OM��)�֊��������n���A���YOM�Ђ��O���[�v�O�̔����҂ɔ������ꂽ�B �@���ꂪ��肭�����A�O���[�v���L����e���r�������E�����������ɂ��ď��n�v�ېł�Ƃ�A�����̗\��ʂ�̔����҂Ɋ������n�ł��邱�ƂƂȂ�B�I�����_�Ŋ܂݉v�����������Ă���̂ŁA�܂݉v�ɂ��ẲېŌJ���ł͂Ȃ��ېł̉���ł���B ���_�@�����Ŗ��ƂȂ��Ă��镔���́AX(��������)��A(���q���)��B(���V����)�Ƃ����O�p�W�ɂ����āA�����傩��V����ւ̗��v�ړ]���F�߂��邩�A�ł���B ��R�@�����F�e�@�u�퍐�̎咣�́v�u�����傪���̗L���銔���̊܂݉v��r�����A����ɑ������闘�v��V�����s�����V���傪�擾�����ꍇ�ɁA���������Ԃ̖�������ɂ�闘�v�̈ړ]�ƂƂ炦��ɓ������v�B�@ �@���_�Ƃ��āA�u�����I�ɂ݂�X�ۗ̕L����A�Њ����̎��Y���l��B�ЂɈړ]�����Ƃ��Ă��A���ꂪX�̍s�ׂɂ����̂Ƃ͔F�߂��Ȃ�����A�����Y���l�̈ړ]��X�̍s�ׂɂ�邱�Ƃ�O��Ƃ��Ă���ɖ@22��2����K�p���ׂ��ł���|�̔퍐�̎�ʓI�咣�ɂ͗��R���Ȃ��B�v�i�Ȃ��A�@�l�Ŗ@132���E������Ђ̍s�v�Z�۔F�̓K�p���˂����B�j ��R�@����������E�������p�@�uX����L���Y�ɌW�銔��Ƃ��ėL���鎝����A�Ђ���Ȃ��̑Ή��邱�Ƃ��Ȃ��r�����CB�Ђ�������擾���������́C���ꂪ���Ђ̍��ӂɊ�Â��ƔF�߂���ȏ�C���ЊԂɂ����Ė����ɂ���L�����̏��n�����ꂽ�ƔF�肷�邱�Ƃ��ł���B�v �@�u���ЊԂɂ����閳���ɂ���L�����̏��n�́C�@22��2���ɋK�肷��w�����ɂ�鎑�Y�̏��n�x�ɓ�����ƔF�蔻�f���邱�Ƃ��ł���B�ނ��C��L�w�����̏��n�x�́C�����ɋK�肷��w���Y�̏��n�x�ɓ�����Ƃ��邱�Ƃɋ^�`�����Ȃ��ł͂Ȃ����C�w�����ɂ��E�E���̑��̎���x�ɂ͓�����ƔF�蔻�f���邱�Ƃ��ł���Ƃ����ׂ��ł���B���Ȃ킿�C��L�K��ɂ����w����x�́C���̕����y�ыK��ɂ�����ʒu�Â�����C�W�ҊԂ̈ӎv�̍��v�Ɋ�Â��Đ������@�I�y�ьo�ϓI�Ȍ��ʂ�c������T�O�Ƃ��ėp�����Ă���Ɖ������C��L�̂Ƃ���CX��B�Ђ̍��ӂɊ�Â��Ď������ꂽ��L�����̏��n������܂���ƔF�߂���B�v �ō��ف@�j�����߂��i�����������I�ɂ͍��ł̏����j�@�uX�ۗ̕L����A�Њ����ɕ\�͂��ꂽ���Ђ̎��Y���l�ɂ��ẮCX���x�z���C�������邱�Ƃ��ł��闘�v�Ƃ��Ė��m�ɔF�߂邱�Ƃ��ł���Ƃ���CX�́C���̂悤�ȗ��v���CB�ЂƂ̍��ӂɊ�Â��ē��ЂɈړ]�����Ƃ����ׂ��ł���B���������āC���̎��Y���l�̈ړ]�́CX�̎x�z�̋y�Ȃ��O�I�v���ɂ���Đ��������̂ł͂Ȃ��CX�ɂ����ĈӐ}���C���CB�Ђɂ����ė��������Ƃ��낪�����������̂Ƃ������Ƃ��ł��邩��C�@�l�Ŗ@22��2���ɂ�������ɓ�����Ƃ����ׂ��ł���B�v �@�����������̕]���̓_�Ō������͔j����Ƃ�Ȃ��Ƃ��č��߂���(����)�B �l�@ �ł��ɒ[�Ɍ����A�@�l�Ŗ@22��2���́u����v��X��B�ЂƂ̊Ԃ́u�����v�ɂ���ĔF�肵���A�Ƃ�������B �@�������A���̂悤�Ɍ����Ă��܂��ƁA�y�Ӑ}����o�ϓI���ʂƂ����B�����邽�߂̖@���\���Ƃ͈قȂ�z�Ƃ����]���̐��������ꂩ�˂Ȃ��B����o�ϓI���ʂ��u�Ӑ}�v���邱�ƂƂ��́u�����v���A�����́u���Ӂv���A�u����v�ƌĂ�ł悢���B�����͍ō��ٔ���ɏ]�킴������Ȃ����A(�w����E������ɂ����Ă݂̂���)�c�_�̗]�n���c��B �@�Ȃ��A���|���u�O�I�v���ɂ���Đ��������̂ł͂ȁv���Ƃ������ƂɌ��y���Ă���_���d�v�B�O�I�v���ɂ���ĕx�̏�Ԃ��ϓ�����T�^��Ƃ��Ă͊����̕ϓ��Ȃǂ���������B |
| 6�Ł�322.04�����ɂ�鎑�Y�̏��� �L����Њ`�ؑ������E������������3�N2��5���s�W42��2��199�� ��������_�@���X�̎����A�����S�BA����X�ɓy�n�̈②�BA�̑����lB�`E�̈◯�����E�����ɑ����z�ُ��B�y�n�̈②���������̂����a58�N�A���z�ُ������a59�N�iD�EE�����j�ł���ꍇ�ɁA���a58�N�ɂ����ĉ��z�ُ��̕������v�����������ƂƂ���邩�H �i�w�i�Ƃ��āA�◯�����E������(���݂͈◯���N�Q�z������)���`�����ł��肻�̌��͂��������ɂ܂ők���j ���|�@�T�i���p�iX�̐������p�j �@�u�②�ɂ��y�n�̎擾�́A�@�l�Ŗ@22��2������́w�����ɂ�鎑�Y�̏���x�ɓ�������̂Ƃ��ē��Y���ƔN�x�̎��v�ƂȂ�B�v �@�u�◯�����E����������A����ɔ�����̓I�Ȏv�̕ϓ��A���Ȃ킿��̓I�ɉ��z�ُ��̊z�����肳��A�v�̌������������ꍇ�ɁA���̎��_�̎��ƔN�x�ɂ����đ����Ƃ��ď������邱�ƂƂ��Ă��A�v�̗��v�����Q������̂ł͂Ȃ��B�v cf. �②�ɂ���A�ɏ����Ŗ@59��1��(�݂Ȃ����n)���K�p����Ă�����AX�̓y�n�̎擾���z�͊��ł���ƍl����ׂ����A�ɗ��ӁB cf. �������Y�̕]���͒Ⴍ���ꂪ���ł���B100%��_���ĉېŏ�����łƑi�ׂ��p������̂ł����锪���]���Ƃ����`�Ōł߂̕]��������̂��ʗ�B������80%��_���Č��ʂƂ��Ă���������Ă��܂�95%�ȂǂɂȂ��Ă��܂��Ă�100%���ĂȂ���Ήېŏ����͈�@�Ƃ����Ȃ��B�Ȃ��A�{����Y�Ŗ��������������i�����1��0631���~�ƕ]�������Ƃ������Ƃɂ��Ă��A�]���������i���̂����������T���߂̕]���ł���Ɨ�������Ă���̂ŁA�������Ƃ͌����ɂ����B |
| �t�@�[�X�g�y���M�������E�����n���ߘa3�N10��29���ߘa2(�s�E)334��(�����S���E�W�����X�g1572��10�ŁA�n�ӓO��E�W�����X�g�Q���Q��)(���������ߘa4�N4��14���ߘa3(�s�R)281���E�Ō��ߘa4�N11��11���ߘa4(�s�c)233���ߘa4(�s�q)254��)�c�c���Y����z�������ɓK���ȉ��z�Ƃ̍��z���v���Ɍv�サ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B |
COLUMN5-4 �����̐U��
5.2.2.1.c. �ʒi�̒��
5.2.2.2. ���v�̋A�����ƔN�x(���v�̔F���)
5.2.2.2.a. �����m���`(cf.��4.4.2.)
5�Ł�321.03��|�f�Վ����E�Ŕ�����5�N11��25�����W47��9��5278��| �s�������ԊҐ������F���h�Y�Ǝ����E�Ŕ�����4�N10��29������1489��90�ŕS�I7��68(�P6��392��)iq�c�c�ߑ�ɒ������ꂽ�d�C�����̕ԋ������ꍇ�̎��v�̌v�㎞�� �u�㍐�l�́A���a�l���N�l�����瓯�܋�N��Z���܂ł̈��N�ԗ]���̊��ԁA���k�d�͂ɂ��d�C�������̐����������Ȃ��̂ł���Ƃ̔F���̉��ł��̎x�����������Ă���A���̊ԁA�㍐�l�͂��Ƃ�蓌�k�d�͂ł����A���k�d�͂��㍐�l����ߑ�ɓd�C�����������Ă��鎖�������邱�Ƃ͂ł��Ȃ������̂ł��邩��A�㍐�l���ߎ��d�C�������̕Ԋ҂��邱�Ƃ͎�����s�\�ł������Ƃ����ׂ��ł���B�����ł���A�d�C�������̉ߑ�x���̓���������e���ƔN�x�ɉߎ��d�C�������̕ԊҐ��������m�肵�����̂Ƃ��āA�E�e���ƔN�x�̏������z�̌v�Z�����ׂ��ł���Ƃ���̂͑����ł͂Ȃ��B�㍐�l�̓��k�d�͂ɑ���{���ߎ��d�C�������̕ԊҐ������́A���a�܋�N�����A���k�d�͂ɂ���āA�v�ʑ��u�̌v��p�ϐ���̐ݒ��肪�������ꂽ�Ƃ����V���Ȏ����̔������āA�E���ҊԂɂ����āA�{���m�F���ɂ��Ԋ҂��ׂ����z�ɂ��č��ӂ������������Ƃɂ���Ċm�肵�����̂Ƃ݂�̂������ł���B���������āA�{���ߎ��d�C�������̕Ԗ߂ɂ����v���A�����ׂ����ƔN�x�́A�E���ӂ������������a�Z�Z�N�O��������������{�����ƔN�x�ł��v��B (���������Έӌ�������c�c����������) |
| 6�Ł�324.05�����Ƒ��Q�����������̊W ���{���������E������������21�N2��18����56��5��1644�ŕS�I7��69�c�cX��(10��1���`9��30�������ƔN�x)�̌o������(A��)�����\�s�ׂɂ��ˋ�O������v�サ�Ă����BX�͕���16�N9�����̓���A�����ق��AA�ɑ��Q���������i�ׂ��N�����B������A��X��1��8815���~���x�����ׂ��Ƃ��锻�����m�肵���BX�̕���9�N9�����`����15�N9����(����11�N9����������6���ƔN�x)�̉ˋ�O����̌v��Ɋւ��Ŗ�������X�ЂɍX�������y�яd���Z�ŕ��ی��菈���������B�R���������o�āA����13�N9�����y�ѕ���15�N9����(�u�{���e���ƔN�x�v)�̊e�������ێ����ꂽ�̂ŁA�����e�����̎������X�͋��߂Ē�i�����B ��R���|�@����16�N9�����ɑ��Q�����������̊z���v���v��B �@�u��ʂɁC���\���̔ƍߍs�ׂɂ���Ė@�l�̔�������Q�̔����������ɂ��Ă��C���̖@�l�̗L����ʏ�̋��K���Ɠ��l�ɁC���̌������m�肵�����̑����鎖�ƔN�x�̉v���Ɍv�シ�ׂ����̂ƍl�����邪�C�s�@�s�ׂɂ�鑹�Q�����������̏ꍇ�ɂ́C���̕s�@�s���ɋq�ϓI�ɂ͌�������������Ƃ��Ă��C�s�@�s�ׂ��閧���ɍs��ꂽ�ꍇ�Ȃǂɂ͔�Q�ґ������Q��������Q�҂�m��Ȃ����Ƃ������C��Q�ґ������Q��������Q�҂�m��Ȃ���C�������������Ă��Ă�������ɍs�g���邱�Ƃ͎�����s�\�ł���B�c�c�������@���㔭�����Ă��Ă��C���̍s�g��������s�\�ł���C����ɂ���Č����I�ȏ����\���̂���o�ϓI���v���q�ϓI���m���Ɏ擾�����Ƃ͂����Ȃ�����C�s�@�s�ׂɂ�鑹�Q�����������́C���̍s�g��������\�ƂȂ������C���Ȃ킿�C��Q�҂ł���@�l�i��̓I�ɂ͓��Y�@�l�̑�\�@�ցj�����Q�y�щ��Q�҂�m�������ɁC�������m�肵�����̂Ƃ��āC���̎����̑����鎖�ƔN�x�̉v���Ɍv�シ�ׂ����̂Ɖ�����̂������ł���i�m���h�Y�Ǝ��������n�Q�Ɓj�B�v �T�i�R���|�@�t�]�F�{���e���ƔN�x�i����13�N9�����A����15�N9�����j�ɑ��Q�����������̊z���v���v��B �@�u���Q�����������ɂ��ẮA�ʏ�A�����������������ɂ͑��Q�����������������A�m�肵�Ă��邩��A�������ɑ����Ɖv���ƂɌv�シ��̂������ł���ƍl������i�s�@�s�ׂɂ�鑹���̔����Ƒ��Q�����������̔����A�m��͂���Ε\���̊W�ɂ���Ƃ�����̂ł���B�j�B�v �@�u�Ⴆ�Ή��Q�҂�m�邱�Ƃ�����ł���Ƃ��A�������e��c�����邱�Ƃ�����Ȃ��߁A�����ɂ͌����s�g�i�����̎����j�����҂��邱�Ƃ��ł��Ȃ��悤�ȏꍇ�����蓾��Ƃ���ł���B���̂悤�ȏꍇ�ɂ́A�����i���Q�����������j���@�I�ɂ͔������Ă���Ƃ����邪�A�������������̉\�����q�ϓI�ɔF�����邱�Ƃ��ł���Ƃ͂����Ȃ��Ƃ����邩��A���Y���ƔN�x�̉v���Ɍv�シ�ׂ��ł���Ƃ͂����Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���i�c�c�m���h�Y�Ǝ��������n�Q�Ɓj�B���̂悤�ȏꍇ�ɂ́A���Y���ƔN�x�ɁA�����ɂ��Ă͑����v�シ�邪�A���Q�����������͉v���Ɍv�サ�Ȃ��戵�������邱�Ƃ��������̂ł���i�@�l�Ŋ�{�ʒB�Q�|�P�|�S�R�c�j�v �@�u���̔��f�́A�ŕ��S�̌�����@�I���萫�̊ϓ_���炵�ċq�ϓI�ɂ����ׂ����̂ł��邩��A�ʏ�l����ɂ��āA�����i���Q�����������j�̑��݁E���e����c���������A�����s�g�����҂ł��Ȃ��Ƃ�����悤�ȋq�ϓI�ɂ��������ǂ����Ƃ����ϓ_���画�f���Ă����ׂ��ł���B�s�@�s�ׂ��s��ꂽ���_�������鎖�ƔN�x�����Ȃ����[�Ő\�����ɔ[�Ŏ҂��ǂ������F���ł������i�[�Ŏ҂̎�ρj�͖��Ƃ��ׂ��łȂ��B�v �@�u�����m���`�ɂ����������ׂ������̊m��̎����ɂ��ẮA��{�I�ɂ͖@�I��ɂ���Ĕ��f���Ă������̂ł���i�@�I��ɂ�蔻�f���邱�ƂŁA�@�I���萫�A���ł̌��������S�ۂ����B�j����A���҂̎��́A���Y���Ƃ������o�ϓI�ϓ_�ɂ����̎����i���̗��s�j�\���f���A���ꂪ�R�����ꍇ�ɂ͉v���v������Ȃ��Ă悢�Ƃ��鏈���͑Ó��łȂ��Ƃ����ׂ��ŁA���̂悤�Ȍo�ϓI�ϓ_����̎����i���s�j�\���̖��́A���L�̑ݓ|�����̖��Ƃ��đ����Ă����̂������ł���B�v �@�u���Q���������������̎擾��������S�z����s�\�ł��邱�Ƃ��q�ϓI�ɖ��炩�ł���Ƃ���ƁA�����ݓ|�����Ƃ��Ĉ����A�@�l�Ŗ@�Q�Q���R���R���ɂ������Y���ƔN�x�̑����̊z�Ƃ��đ����ɎZ�����邱�Ƃ��������Ƃ����ׂ��ł���i�m���h�Y�Ǝ��������n�B�Ȃ��m6�Ł�324.04���⎖�������n�Q�Ɓj�B�܂��A�擾�����͂��������Ȃ������Ƃ��Ă��A���̌セ���Ȃ����Ƃ����ꍇ�́A���̎��_�̑����鎖�ƔN�x�̑����ɎZ�����邱�Ƃ��������Ƃ����ׂ��ł���B�v �@�uX�̌o���S���������ɔ邵�Ė{������s�ׂ��������̂ł���AX�̎������͓����{������s�ׂ�F�����Ă��Ȃ��������̂ł͂��邪�A�{������s�ׂ́A�o���S����������{���a����������̕��߂��y�ъO����ւ̐U���݈˗��ɂ��Č��ق���ۂɉ������Q�������K�̐U���˗������`�F�b�N����������Ηe�Ղɔ��o������̂ł������v����u�ʏ�l����Ƃ���ƁA�{���e���ƔN�x�����ɂ����āA�{�����Q�����������ɂ��A���̑��݁A���e����c���ł����A�����s�g�����҂ł��Ȃ��悤�ȋq�ϓI�ɂ������Ƃ������Ƃ͓���ł��Ȃ��v�B cf.�@���2-1-43(���Q���������̋A���̎���)�@���̎҂���x�����鑹�Q�������i���̗��s�x�ɂ�鑹�Q�����܂ށB�ȉ�2�|1�|43�ɂ����ē����B�j�̊z�́A���̎x������ׂ����Ƃ��m�肵�����̑����鎖�ƔN�x�̉v���̊z�ɎZ������̂ł��邪�A�@�l�����̑��Q�������̊z�ɂ��Ď��ۂɎx���������̑����鎖�ƔN�x�̉v���̊z�ɎZ�����Ă���ꍇ�ɂ́A�����F�߂�B (��)�@���Y���Q�������̐����̊���ƂȂ������Q�ɌW�鑹���̊z�́A�ی������͋��ϋ��ɂ���U����镔���̋��z�������A���̑��Q�̔����������̑����鎖�ƔN�x�̑����̊z�ɎZ�����邱�Ƃ��ł���B cf.3�Ł�324.05(�P6��458��)���{�������Y�����E�����������a54�N10��30�����^407��114�� �����@���\��Q�ɂ�����X�������v�サ���̂ɑ��AY�Ŗ������͑��z�X���B ���_�@���\��Q�ɂ�鑹���v��̂��߂ɁA�ǂ̂悤�Ȏ������v������邩�H�@�܂��A�����v��ƂƂ��ɁA���Q�������������v���v�コ��邱�Ƃ��猋�ǂ͑��E�����̂��H �@Y�̎咣�\�\�����Z���̂��߂ɂ͌Y���Ȃ��������̔����̊m���҂B�i���Q�������������v���Ɍv�シ�ׂ����ɂ��ẮAY����v���Ƃ��Ă̊m�肪�Ȃ��Ƃ��Ă���c�c�uY�ɂ����Ă������v�j ���|�@�����I��X���i �@��ʘ_�c�c�����m���`�̊m�F �@�����v��̉ۂɂ��āc�c�m�蔻����҂��Ȃ� �@�v���E�����̈�̐��̗L���ɂ��āc�c�u�v���A�����̂��ꂼ��̍��ڂɂ����z�𖾂炩�ɂ��Čv�シ�ׂ����̂Ƃ��Ă��鐧�x�{���̎�|���炷��A���v�y�ё����͂��ꂪ���ꌴ���ɂ���Đ�������̂ł����Ă��A�e�Ɨ��Ɋm�肷�ׂ����Ƃ������Ɓv����B �@���Ă͂߁c�c�{���ł́u���Q�����������͖{���W�����ƔN�x���ɉv���Ƃ��Ċm������Ȃ������v�̂ŁA�����Ɍv�サ���̂͑����B cf.��h�v���X�`�b�N�X�����E���l�n�����a40�N4��8���s�W16��4��589�ŁE�����������a40�N10��13���s�W16��10��1632�ŁE�Ŕ����a43�N10��17����14��12��1437�ŏ��a40(�s�c)107��(�P6��456��)ck�c�c���̔�Q�Ɋւ��āA�u���Q�ɑ���������z�̑��Q�������������擾����v�̂ŁA���̔�Q�ɂ�鑹�Q���v�シ��̂Ɓu�������ƔN�x�ɉv�����\������v�Ƃ��A�u���҂̖����͂��̑��̎��R�ɂ���Ă��̎����s�\�������ƂȂ������ɂ����đ����ƂȂ��ׂ��v�Ƃ̌������͎�m������Ƃ���B���̈�ʘ_�̂��Ɩ{���ł́u���Q�������̑S���܂��͈ꕔ�̎����s�\�����炩�ɂȂ����ƔF�߁v���Ȃ��A�Ƃ����B �@���{�������Y�����c�������v�シ��B���Q�������������v���v�シ�邽�߂ɂ͊m���v����B �@��h�v���X�`�b�N�X�����c�������v�シ��B���Q�������������v���v�サ(�����铯��������)�A�����s�\�������ƂȂ��Ă��瑹���Ɍv�シ��B �@�ꌩ�A�������͈Ⴄ���Ƃ������Ă���悤�ɓǂ߂Ă��܂���������Ȃ��B���Q����������������Ƃ��������Œ����ɉv���v��������邩(��h�v���X�`�b�N�X)�A���̊m���v�����邩(���{�������Y)�A�ԓx���Ⴄ���̂悤�ɓǂ߂Ă��܂���������Ȃ��B �@�������A���{�������Y���������́A����N�x���ɑ��Q�����������̏[�����}�����҂ł��Ȃ��ꍇ�́A���h�Y�Ǝ��������Ɠ��l�ɒ��ۓI�Ȍ����̐��������ʼnv���v���v������̂ł͂Ȃ�(�����A���h�Y�Ǝ��������ɂ����閡�������Έӌ��͓����������ł���)�A�Ƃ������̂Ƃ��ė������邱�Ƃ��ł���B���{�������Y���������́A����N�x���ɑ��Q�����������̏[�����}�����҂ł��Ȃ���ʂł���A��h�v���X�`�b�N�X���������́A����N�x���ɑ��Q�����������̏[�������҂ł��Ȃ��ł͂Ȃ��̂ň�U�͉v���v�サ����s�\�����炩�łȂ���Ή���s�\�������Ɍv�サ�Ȃ��icf.�ݓ|�����F6�Ł�324.04���⎖���E�Ŕ�����16�N12��24�����W58��9��2637�Łj�Ƃ�����ʂł���A�Ƃ��Đ����I�ɗ�������]�n������B cf.�����p���u���Ə���s�@�s�ׂɂ�鑹�Q�̏����`�N�x�A���̖��v�Ŗ����ጤ��115��53�ňȉ��A80�ł�蔲��(2010)�c�c�u�w���Q�����������Ƃ��������x�̊m��c�c�Ɓw���Q�������������s�g���Ď������ׂ������x�̊m��Ƃ��������邱�ƂɗR��������̂ł͂Ȃ����Ƒz�������B�v cf.���a���Y�����E���n������10�N10��28������8(�s�E)86���`90����48��10��2587�ŁE��㍂������13�N7��26������10(�s�R)67�����^1072��136�Łc�c�@�l�œ��̐\�����ɉېŗv�������̉B������������Ƃ��ďd���Z�ŕ��ی��菈�������ꂽ�B���̍s�ׂ������]�ƈ������o��W���邽�߉B���������������̂ł���A�@�l���B�������������̂ł͂Ȃ����珈���͈�@�ł���Ƃ��Ė@�l�͎�����������������p���ꂽ�B �]�k�c�c���Q�������������@�l�Ŗ@22��2��2���u����c�ɌW��c���v�v�Ɋ܂܂��̂��A�^�₪�c��Ȃ��ł͂Ȃ����A���炭�u����v�Ƃ����ꂪ���Q�����̂悤�ȏ�ʂʼnv���T�O�����肷���|�ł͂Ȃ��̂ł��낤�i���ӁF�u����v�Ƃ����ꂪ��ɖ��Ӗ��Ƃ�����ł͂Ȃ��j�B |
5.2.2.2.b. �Ǘ��x�z�(cf.��4.4.3.)
| ���n�����a42�N7��18���s�W18��7��921�ŁE��㍂�����a45�N1��26���s�W21��1��80�Łc�c�ېł̌����ƂȂ����s�ׂ������ƔF�߂���悤�ȏꍇ�ł����Ă��i�v�f�̍���\�����͖��������\�̂�������_��j�A���̍s�ׂ̌��ʁA�L���ȏꍇ�Ɠ��l�̌o�ϓI���ʂ��������������Ă���ꍇ�ɂ́A�����Ώۂɉېł����邱�Ƃ͈�@�ł͂Ȃ��A������̍s�ׂ̖����Ɋ�����Ă��̍s�ׂɂ���Đ������o�ϓI���ʂ������A�܂��͂���Ɠ������ׂ���ԂɂȂ����Ƃ��ɁA���z�X���̎葱���o�ĉߔ[���̊ҕt����Α����B�����ɂ���Ď擾�������Y�����@�l�Ŗ@�{�s�K���P�R���̂U��P���ɂ����u�����̂��߂Ɏ擾�������́v�ɓ�����Ƃ��Ĉ��k�L���ɂ�鑹���Z�����F�߂��Ȃ���������B |
| �Ŕ����a46�N11��16���Y�W25��8��938��cl�c�c���������@���ߗ����̖����������v���Ɋ܂܂�Ȃ�(���s�����������Ă��Ă�)�B(cf.6�Ł�211.02���������@�ᔽ���������E�Ŕ����a46�N11��9�����W25��8��1120��) |
���É��n������13�N7��16�����^1094��125��(��6�Ł�321.03)
| �x���R�����E�_�˒n������14�N9��12�����^1139��98�ŕ���12�N(�s�E)45���������p(�g������E�W�����X�g1258��199��)�c�c�������ՋƎ҂̌ݏ���I�ȗa����ɂ��ĊǗ��x�z��B �@�Ȃ��A�����Ŗ@59��1��2���̒�z���n�ɓ����邩�̔���ɍۂ����l�̖@�l�̊����̎������Z�肷��ۂɊ|���Ԋҍ����u�m���ƔF�߂���v��(�]���ʒB186)�ɓ�����Ȃ��̂œq�����ԍύ����T�����Ȃ��ŏ����Y���z�����ɂ�銔���̉��l���Z�肷�ׂ��Ƃ�������Ƃ��āA�����n���ߘa5�N4��21���ߘa2(�s�E)215��(���p)������B |
6�Ł�321.03�N�����B�X�����E�Ŕ��ߘa2�N7��2�����W74��4��1030��
5.2.2.3. �ʒi�̒��
5.2.2.3.a. ���[�X���n�\�\�����(�@�ŋ�63���A�@�ŗ�124���Acf.��4.2.3.2.)
5.2.2.3.b. �ꎖ�ƔN�x����H��(�@��64��)�\�\�H���i�s�(�@�ŗ�129���A�@���2-1-21��7)
5.2.2.3.c. ���[�X���(�@��64����2)
5.2.2.3.d. �Z���������i�E�����ړI�L���،�(�@��61����3�A61���A61����4�A61����5�A61����9�A6�Ł�321.04)
5.2.2.3.e. ���z����(�@��23��)
�@��23��1�����z���v���s�Z���@�icf.�O���q��Дz���v���s�Z����8.3.5.�j�u�����@�l�����Ɍf������z�i�c�c�u�z�����̊z�v�Ƃ����B�j����Ƃ��́A���̔z�����̊z�i[2]�֘A�@�l�������m4���F1/3��100�������̎x�z�����n�ɌW��z�����̊z�ɂ��Ă͓��Y�z�����̊z�������Y�z�����̊z�ɌW�闘�q�̊z�ɑ���������̂Ƃ��Đ��߂Œ�߂�Ƃ���ɂ��v�Z�������z���T�������m�����q�T���B�@�ŗ�19��1���F�z�����̊z��4���n���z�Ƃ��A[3]���S�q�@�l�������m5���F�z���v�Z���Ԃ�ʂ��Ċ��S�x�z�W����������@�l�����n�A�֘A�@�l�������y�є�x�z�ړI�������̂�����ɂ��Y�����Ȃ��������c�c�ɌW��z�����̊z�ɂ��Ă͓��Y�z�����̊z�̕S���̌\�ɑ���������z�Ƃ��A[4]��x�z�ړI�������m6���F�����䗦5���ȉ��n�ɌW��z�����̊z�ɂ��Ă͓��Y�z�����̊z�̕S���̓�\�ɑ���������z�Ƃ���B�j�́A���̓����@�l�̊e���ƔN�x�̏����̋��z�̌v�Z��A�v���̊z�ɎZ�����Ȃ��B�v�m1�`3���E2���ȉ����n
[1]���S�q�@�l������(100���ۗL)�c�c100���v���s�Z��
[2]�֘A�@�l������(1/3��100�������ۗL)�c�c�����q�T����100���v���s�Z��
[3]���̑�(5����1/3�ȉ��ۗL)�c�c50���v���s�Z��
[4]��x�z�ړI������(5���ȉ��ۗL)�c�c20���v���s�Z��
[5]�،������M��(���芔�������M���m[4]�Ɠ��l�n�������F�d��67����6��1��)�c�c100���v���Z��
�@�l���L�����̏��n���v�͌y�ۑ[�u�̑ΏۊO�ł��邱�Ƃɗ���(��F�@�l�Ŗ@23��2���c�c�Z�����L�������̏��O)
| 6�Ł�322.05���z���̉v���s�Z�� cf.���ۋ��ƊǗ�������Ў����E�����n������29�N12��6������27(�s�E)514�������F�e(�����C��E�W�����X�g1521��10��)�E���������ߘa���N5��29������29(�s�R)388���T�i���p�E�Ŕ��ߘa3�N3��11�����W75��3��418��gh(�r�����q�E�W�����X�g1580��89�ŁA�n�ӓO��E�W�����X�g1567��131�ŁA����M�q�E�V�E������Watch�d�Ŗ@No.165)(�w�����ɂ͓���̂łƂ��Ă悢) �@�u�@�l�Ŗ@�Q�S���P���R���́A���v��]���y�ю��{��]���̑o���������Ƃ��čs��ꂽ��]���̔z���̏ꍇ�ɂ́C���̂������v��]���������Ƃ��镔���ɂ��ẮC���̑S�z�𗘉v�����̕��z�Ƃ��Ĉ�������ŁC���{��]���������Ƃ��镔���ɂ��ẮC���v�����̕��z�Ǝ��{�����̕��߂��Ƃɕ����邱�Ƃ�z�肵���K��ł���C���v��]���������Ƃ��镔�������{�����̕��߂��Ƃ��Ĉ������Ƃ͗\�肵�Ă��Ȃ����̂Ɖ������B�v �@�u�@�l�Ŗ@�Q�S���R���̈ϔC���Ċ����Ή��������z�̌v�Z���@�ɂ��ċK�肷��@�l�Ŗ@�{�s�߂Q�R���P���R���́C��Ѝ��Y�̕��߂��ɂ��āC���{�����Ɨ��v�����̑o�����珃���Y�ɐ�߂邻�ꂼ��̔䗦�ɏ]���Ĕ��I�ɂ��ꂽ���̂Ƒ����Ċ����Ή��������z���v�Z���悤�Ƃ�����̂ł���Ƃ���C���O���ߓ��Ή����{���z���̌v�Z�ɗp����{�s�ߋK�芄�����Z�o����ۂɕ��q�ƂȂ���z�c�c�Y���{�̕��߂��ɂ���t�������K�̊z�ł͂Ȃ��������{��]���z�Ƃ��C���{��]���������Ƃ��镔���݂̂ɂ��ď�L�̔��I�Ȍv�Z���s�����ƂƂ�����̂ł��邩��C���̌v�Z���@�̘g�g�݂́C�O�L�̓��@�̎�|�ɓK��������̂ł���Ƃ������Ƃ��ł���B�������Ȃ���C�뉿�����Y���z�����O���{���z��菭�z�ł���ꍇ�Ɍ����Ă݂�C��L�̌v�Z���@�ł͌������{��]���z���钼�O���ߓ��Ή����{���z�����Z�o����邱�ƂƂȂ�C���v��]���y�ю��{��]���̑o���������Ƃ��čs��ꂽ��]���̔z���ɂ����ď�L�̂悤�Ȓ��O���ߓ��Ή����{���z�����Z�o�����ƁC���v��]���������Ƃ��镔�������{�����̕��߂��Ƃ��Ĉ����邱�ƂƂȂ�B �@��������ƁC�����Ή��������z�̌v�Z���@�ɂ��Ē�߂�@�l�Ŗ@�{�s�߂Q�R���P���R���̋K��̂����C���{�̕��߂������ꂽ�ꍇ�̒��O���ߓ��Ή����{���z���̌v�Z���@���߂镔���́C���v��]���y�ю��{��]���̑o���������Ƃ��čs��ꂽ��]���̔z���ɂ��C�������{��]���z���钼�O���ߓ��Ή����{���z�����Z�o����錋�ʂƂȂ���x�ɂ����āC�@�l�Ŗ@�̎�|�ɓK��������̂ł͂Ȃ��C���@�̈ϔC�͈̔͂���E������@�Ȃ��̂Ƃ��Ė����Ƃ����ׂ��ł���B�v |
5.2.3. �����̊z�̌v�Z
5.2.3.1. �����̊z�̋A���N�x
5.2.3.1.a. ��p�̈����\�\��p���v�Ή��̌���(cf.��4.3.2.1.)
6�Ł�323.01�����̈Ӌ` �T�� �@�l�Ŗ@22��3�� �����@�l�̊e���ƔN�x�̏����̋��z�̌v�Z�㓖�Y���ƔN�x�̑����̊z�ɎZ�����ׂ����z�́A�ʒi�̒����������̂������A���Ɍf����z�Ƃ���B�@��@���Y���ƔN�x�̎��v�ɌW�����㌴���A�����H���������̑������ɏ����錴���̊z[�ʑΉ��̌���]
�@��@�O���Ɍf������̂̂ق��A���Y���ƔN�x�̔̔���A��ʊǗ���̑��̔�p(���p��ȊO�̔�p�œ��Y���ƔN�x�I���̓��܂ł����̊m�����Ȃ����̂������B)�̊z[���ԑΉ��̌���]
�@�O�@���Y���ƔN�x�������̊z�����{������ȊO�̎���ɌW�����
���u�ʒi�̒�߁v�c�c��F�@�l�Ŗ@34���F�������^(6�Ł�325.01�O�a�N���G�[�V����)�A37���F��(6�Ł�322.03�����y 6�Ł�325.02���m���Y 6�Ł�325.03PL�_��)�A57���F�J�z������(6�Ł�325.05�s�c�d��)�A�d��61����4�F���۔�(6�Ł�325.04�ݗL����)�A�@���9-7-20�F�g�r�s�����A�d��62���F�g�r�铽��
���u���{������v�c�c�Ƃ�킯�x���z���̑����s�Z��(6�Ł�323.02�������� cf.6�Ł�221.02�����Z)
��1���c�c��p���v�Ή��̌���(6�Ł�324.01���v�s���㌴��)
��2���c�c��p���v�Ή��̌������K�p����Ȃ����́@(���̊m��F6�Ł�324.02�|�C���g�V�X�e��)
��3���u�����̊z�v�u����ɌW����́v�c�c������`(6�Ł�324.05���Q�����F���{����)�B�ݓ|����(6�Ł�324.04����Ǝ��Y�̕]����)�B
��22��4���c�c�v���E�����́u�z�́A��ʂɌ����Ó��ƔF�߂����v�����̊�ɏ]�Čv�Z�������̂Ƃ���B�v�@(6�Ł�323.03��@�x�o�F�G�X�u�C�V�[�A6�Ł�324.03�������p�FNTT�h�R��)
COLUMN5-5 ���������Z���Ǝ��Y��(��5.2.3.3.b.)
5.2.3.1.b. �����̈���(cf.��4.6.2.)
���V���������E���n������7�N10��3���Ŏ�214��1�ŕ���6(�s�E)61���c�c�u�@�����O���́w�����x�Ƃ́A���{������ȊO�̎���ŏ����Y�̌����̌����ƂȂ�x�o���̑��o�ϓI���l�̌������������̂ł���A���̂��������ꍆ�́w���㌴���A�����H���������̑������ɏ����錴���̊z�x�Ƃ́A���v�l���̂��߂ɔ�����ꂽ���y�і̑Ή��̂����A���v�ɒ��ڂ��ʓI�ɑΉ�������̂������A�����́w�̔���A��ʊǗ���̑��̔�p�x�Ƃ́A���v�ɌʓI�ɂ͑Ή��͂��Ȃ������Y���ƔN�x�̎��v�l���̂��߂ɔ�����ꂽ���y�і̑Ή����������̂ł����āA����������Ƃ̐��s��K�v�Ƃ������̂ł��邱�Ƃ͖��炩�ł���A�����O���́w�����x�Ƃ͍ЊQ�A����ʏ�̎��Ɗ����Ƃ͖��W�ȋ����I�v���ɂ�蔭�����鎑�Y�̌����������v�B�u�����͖{���y�n�����L������̂ł͂Ȃ��A���y�n�����猴���̎��Ƃɗ��p���Ă�����̂Ƃ������Ȃ�����A�{���Œ莑�Y�ł͌����̎��Ƃ̐��s��K�v�Ȏx�o�Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B�܂��A�E�̎����W�y�ь����Ƒ��ό��Ƃ̊Ԃɂ����Ă͑��ό������y�n�ɂ�����Œ莑�Y�łS����|�̍��ӂ����������Ƃ��炷��ƁA�E�Œ莑�Y�ł͍ŏI�I�ɂ͑��ό������S���ׂ����̂ŁA�����́A���ό��ɑ��A�{���Œ莑�Y�ő����z�ɂ��Ă̕s�������ԊҐ�������L������̂Ƃ����ׂ��ł��邩��A�������{���Œ莑�Y�ł����̔[�t�`���Ɋ�Â��Ĕ[�t��������Ƃ����āA�����̏����v�Z�ɂ����āA�����Y�̌����̌����ƂȂ�x�o���̑��o�ϓI���l�̌����𗈂������̂Ƃ������Ȃ��B���������āA�����̖@�l�ł̏����v�Z��A�{���Œ莑�Y�ł��ƔF�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��v�B5.2.3.2. ���㌴����(�@��22��3��1��)
5.2.3.2.a. ���㌴��
5.2.3.2.b. �����H������(�@���2-2-5)
5.2.3.2.c. �u�����ɏ����錴���v
�R������������Ў����E�����n�����a48�N1��30�����a43(�s�E)48���E����������48�N8��31�����a48(�s�R)5������717��40�Łc�c�u��n��������Ǝ҂̊O�����Ɏx�������̓I�Ȏ�����Ƃɒ�܂���������́A�̔����i��i�̌����Ƃ͈قȂ邪�A��̓I�ȕs���Y�����ɍۂ�����l�ł����n��������Ǝ҂����������������擾����̂ɔ��ĕ��S���邱�ƂɂȂ邵�A�܂������I�ɂ͓��Y�������̂��߂̊O�����̘J��������Ƃ����̈ꕔ���\�����Ă���̂ŁA�E�̌����ɏ�������̂Ƃ��Ĉ����̂𑊓��Ƃ���B�v�u�T�i�l�̊O�����Ɏx�����ׂ����������́A���ꂪ�����Ɏx����ꂽ�Ƃ��ł͂Ȃ��A����萔���̋��z�̖�肪���������ۂɓ����ɋ�̓I�Ɋm�肵���Ƃ������Ƃ��ł��A����͍T�i�l�̎擾������v�ł��钇��萔���ƑΉ�������̂ł���̂ŁA����萔�������v�Ƃ��Čv�コ��鎖�ƔN�x�ɑΉ����đ����Ɍv�コ���v�B5.2.3.2.d. ���㌴�����̌��όv��
| 6�Ł�324.01���㌴�� ���v�s���㌴�����ώ����E�Ŕ�����16�N10��29���Y�W58��7��697�ŕS�I7��56as �����E���_�@X����n�����̋���ہA���H�H����(1��4668���~�ƌ��ς���ꂽ)�S���邱�Ƃ����v�s���v������Ă������A�r���H�H�������a62�N�̎��_�ōs���ĂȂ��AX�͂܂����̕��S�����x�o���Ă��Ȃ��Ƃ����̉��ŁA���a62�N9�����̓y�n�̔����v�ɌW�����㌴���Ƃ���1��4668���~���ɎZ�����邱�Ƃ��ł��邩�B��R�E��R�ł͑����Z���s�B ���|�@�j�����߁@���a62�u�N9�������ɂ����āAX���߂������ɏ�L��p���x�o���邱�Ƃ��������x�̊m�����������Č����܂�Ă���A���A�����̌����ɂ�肻�̋��z��K���Ɍ��ς��邱�Ƃ��\�ł������v�B �� �@�l�Ŗ@22��3��2���ł́u���̊m���v�������I�ɗv������Ă���̂ɑ��A1���̔��㌴�����ɂ��āu�m��v�̕����͂Ȃ��B1���𗥂���̂���p���v�Ή��̌������u���v�ɌW��v�B �@���2-2-1(���㌴�������m�肵�Ă��Ȃ��ꍇ�̌��ς�)�@�@��22���3����1���s�����̊z�ɎZ������锄�㌴�����t�ɋK�肷��u���Y���ƔN�x�̎��v�ɌW�锄�㌴���A�����H���������̑������ɏ����錴���v�c�c�ƂȂ�ׂ���p�̊z�̑S�����͈ꕔ�����Y���ƔN�x�I���̓��܂ł��m�肵�Ă��Ȃ��ꍇ�ɂ́A�����̌����ɂ�肻�̋��z���K���Ɍ��ς����̂Ƃ���B���̏ꍇ�ɂ����āA���̊m�肵�Ă��Ȃ���p�����㌴�����ƂȂ�ׂ���p���ǂ����́A���Y���㌴�����ɌW�鎑�Y�̔̔��Ⴕ���͏��n���͖̒Ɋւ���_��̓��e�A���Y��p�̐����������Ă��č����I�ɔ��f����̂ł��邪�A���Ƃ����̔̔��A���n���͒Ɋ֘A���Ĕ��������p�ł����Ă��A�P�Ȃ鎖��I��p�̐��i��L������̂͂���Ɋ܂܂�Ȃ����Ƃɗ��ӂ���B cf.1�Ł�323.04�啪���z������Ў����E������������11�N2��17������8(�s�R)7����46��10��3878�ōT�i���p(���R�啪�n������8�N2��27�����^960��117�Ő������p) �����E���_�@���㌴���i�d�����i�j�������ݒ肵�A���̎��ƔN�x�Ɍ��ɂ���Ďd�����߂������A�Ƃ����@���\�����e�F����邩�B�d�����i�͖��m��ł����Č��ς���ɂ��Ƃ��ׂ����B ���|�@�u���Ȃ��Ƃ��{���e���ƔN�x�̎�����i�ɂ��āA�K�X���Ɩ@��̔F���i�������āA�@22��3��1���́w���㌴���x�ƕ]������̂͑����łȂ��B�v �u�w���Y���ƔN�x�̎��v�ɂ����锄�㌴���x���̊z�����Y���ƔN�x�I���̓��܂łɊm�肵�Ă��Ȃ��ꍇ�ɂ́A�����̌����ɂ�肻�̋��z��K���Ɍ��ς���Ȃ��Ă͂Ȃ�v�Ȃ��B �����̕��@�͂Ȃ��˂���ꂽ���H�c�c��̐��Z�ɂ����āu�`�͂w�ɑ��c�c�����̐��Z�����x�����A�`���g���A�E�F���i�������i�ł��邱�Ƃ�O��Ƃ�����v���������Ă����v�B �����i�Z����Ƃ����\���ƁA��������������m�肵����Ɏ��ƔN�x�I����̊��߂����ɂ���ĐV���Ɏd�����ߋ�����������Ƃ����\���Ƃ���ʂ����c�c�Ԗ߂Ƃ������߂ɂ́u�d�����z�ɑ��銄���ɂ́A���̐�����A���̌��x������v�B�u���ƔN�x�I������V���ȍ����Ɋ�Â��d�����߂��ł���Ƃ͉�����Ȃ��B� cf.������������8�N4��17���Ŏ�218��1498�Łc�c�ʑ��n�ɌW�関�{�H�����H���ɌW�錩�ό����ɂ��ĔF�e�B�i�Y�������E�L�߁A���s�P�\�j cf.���n�����a57�N11��17���s�W33��11��2285�Ŋm��c�c�̐Ώ�Ւn�̐��y�A�A�ѓ��̎��R����ɌW�錩�ό����ɂ��ĔF�e�B |
5.2.3.3. �̔����ш�ʊǗ��
5.2.3.3.a. ��p�̈Ӌ`(cf.��5.2.3.5.b.)
| 5�Ł�324.02������ЃP�[�G�������E�R���n�����a56�N11��5���s�W32��11��1916�ŏ��a53(�s�E)2���������p�m�� �����E���_�@���̊m��ɂ��āB�̔��������i�ɂ��Ď�t��p�̔��z�S����Ƃ������ł������̂ŁA���̔����ɂ��Ď�t��p��a�蕉�S���Ƃ��đ����v�サ�悤�Ƃ����B���̊m�肪�Ȃ��Ƃ��āi�@�l�Ŗ@22��3��2���Q�ƁB1���Ȃ�Ό��ς���v�オ�\�j�A�����v�オ�ے肳��邩�B�������Ɋւ��āA���������E�����S��E�c�������u�L�����s�ېł̍\���Ɩ��v���������ҁw�V�����@�l�Ŗ@�x(�L��t�A2007) ���|�@�@�l�Ŗ@22��3��1����2�����͂Ƃ������u��t��p�͓��Y���ƔN�x�I���̓��܂łɍ��Ƃ��Ċm�肵�Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�B�u���̊m�肠��Ƃ������邽�߂ɂ́A���Y���ƔN�x�̏I���̓��܂łɁA(1)�����������Ă��邱�ƁA(2)���Y���Ɋ�Â��ċ�̓I�ȋ��t�����ׂ������ƂȂ鎖�����������Ă��邱�ƁA(3)���z�������I�ɎZ��ł��邱�ƁA�Ƃ���3�̗v�������ׂĖ������Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�B ���͖@�l�Ŗ@22��3��1���ɂ��č��̊m��͗v������ĂȂ��B |
| 6�Ł�324.02���̊m�� �|�C���g�V�X�e�������E�����n���ߘa���N10��24���Ŏ�269������13329����29(�s�E)403�����p�m��(���R�R���E�W�����X�g1586��139��)�c�c�ڋq�������̊e�X�܂ŏ��i�����w������ۂɕt�^�����|�C���g�i�{���|�C���g�V�X�e���B����23�N6��1���O�F1�~1�|�C���g�B1���|�C���g���Ƃ�500�~�B�V�X�e�������F1�~������1�|�C���g�B1�|�C���g�P�ʂŏ[���\�j�̊e���ƔN�x���i10�����Z�j�ɂ����関�g�p���ɑ���������z�i�ȉ��u�{���|�C���g�����v��z�v�j�̑����Z����O��ɖ@�l�ŁA�������ʖ@�l�ł̊m��\���������B�L���Ŗ������͍����m�肵�Ă���Ƃ͔F�߂��Ȃ��Ƃ��đ����s�Z����O��ɍX���������������B�Ȃ��A�|�C���g�t�^���̔�����z�ɑ���l�����ł͂Ȃ����߁C�v���̊z���猸�Z���邱�Ƃ��ł��Ȃ����Ƃ͖��炩�B �@�����̎咣�@�u�J�[�h�������L�������s�g����ɓ�����C�������s�̍R�ٌ����̑���������I�ȏ�Q�͑��݂��Ȃ�����C��̓I�����������������Ă���v�B�u�{���|�C���g�V�X�e���ɂ�����|�C���g�́C���i�������ƌo�ϓI�������ގ����Ă���C���i�������ʒB�i��{�ʒB�X�|�V�|�R�j�̍l������{���ł��Q�Ƃ��ׂ��v�B ���| �@�u��Ɖ�v��C��p�̔F���́C�����锭����`�������Ƃ����C���Y��p�����ݏo�������v�Ɠ���̉�v�N�x���ɂ�����v�コ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ̍l�����i�ȉ��u��p���v�Ή��̌����v�Ƃ����B�j����C�����������邱�Ƃ��\�z����関�����̔�p�ł����Ă��C���̔����������ȑO�̎��ۂɋN�����C���C�����̉\�����������̂ɂ��ẮC�������Ƃ��Čv�シ�ׂ����̂Ƃ���Ă���B����C�@�l�Ŗ@�ɂ����ẮC���Y���ƔN�x�̏����̋��z�̌v�Z�㑹���̊z�ɎZ�����邱�Ƃ��ł���������͑ݓ|���������Ɍ��肳��Ă���c�c�C�����ɓ�����Ȃ���Ɖ�v��̈������ɂ��ẮC���@�Q�Q���R���e���̂����ꂩ�ɊY�����Ȃ����葹���̊z�ɎZ�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�����āC�����Q���ɒ�߂�̊ǔ�ɂ��ẮC�P���ɒ�߂錴���Ƃ͈قȂ�C���p��ȊO�̔�p�œ��Y���ƔN�x�I���̓��܂łɍ��̊m�肵�Ȃ����̂͑����̊z�ɎZ�����邱�Ƃ��ł��Ȃ����̂Ƃ���Ă���i���m��v���B�Q�����ʏ����j�C���̎�|�́C�������̔̊ǔ�ɌW��������ɂ��ẮC�����̌����݂���z�̎Z��ɂ��Ė@�l�̜��ӂ�����₷�����߁C���Y���ƔN�x�I���̓��܂łɍ����m�肵�����̂Ɍ��葹���Z����F�߂邱�ƂƂ��āC�ېŌv�Z�̓K����}�낤�Ƃ�����̂Ɖ������B�v �@�����ƈقȂ�u�̊ǔ�ɂ��ẮC����̎��v�ƌʓI���q�ϓI�ɑΉ������邱�Ƃ�����ł���C�������������p�̔����̉\���̕]�����p�ƂȂ���z�̎Z��ɓ������āC�@�l�̜��Ӑ������荞�݂₷�����Ƃ���C��Ɖ�v��͈��������v�シ��ƂƂ��ɔ�p�������鏈������ʂɌ����Ó��Ȃ��̂Ƃ�����ꍇ�ł����Ă��C�@�l�̏����̋��z�̌v�Z��́C���Y���ƔN�x�I���̓��܂łɍ����m�肵�����̂Ɍ��葹���Z����F�߂邱�ƂƂ��āC�����̊z�ɎZ�������̊ǔ�̊z�ɂ��@�l�̜��ӂ����荞�ޗ]�n��r�����C�����ĉېŌv�Z�̓K�����m�ۂ��悤�Ƃ���̂��C���m��v���̎�|�ł���v�B �@�u���m��ʒB�i��{�ʒB�Q�|�Q�|�P�Q�j�́C���m��v���̔����Ƃ��āC���Y���ƔN�x�I���̓��܂łɁC���Y��p�ɌW������������Ă��邱�Ɓi���m���@�j�C���Y���Ɋ�Â��ċ�̓I�ȋ��t�����ׂ������ƂȂ鎖���i��̓I���������j���������Ă��邱�Ɓi���m���A�j�y�т��̋��z�������I�ɎZ�肷�邱�Ƃ��ł��邱�Ɓi���m���B�j���߂�c�c�Ƃ���C���̓��e�́C��Ɖ�v��C���ׂĂ̔�p�y�ю��v�͂��̔����������ԂɊ��蓖�Ă�悤�ɏ������Ȃ���Ȃ�Ȃ����̂Ƃ��锭����`�̍l�����ɐ�������ƂƂ��ɁC���̔����̉\���̕]�����Ɋւ���@�l�̜��ӂ�r������Ƃ������m��v���̏�L��|�ɂ��������̂Ƃ�����B�����āC��L�̂Ƃ���@�l�Ŗ@���������̑����Z�������肵�Ă��邱�Ƃ�C��L�̍��m��v���̎�|�ɏƂ点�C���m���A�̋�̓I�������������������Ƃ������߂ɂ́C��Ɖ�v��������Ƃ��Čv��ł�����x�ɏ�����p����������\���������Ƃ���邾���ł͑��肸�C�����ɂ����Ĕ�p�̔�������b�t�����̓I���������̔������F�߂��Ȃ���Ȃ�Ȃ����̂Ɖ�����̂������ł���B�v �@�u�J�[�h����̏���w�����ɕt�^���ꂽ�|�C���g�́C��L�Q�N�̊��ԓ��Ɏ������Ďg�p����Ȃ��Ȃ�\���������C���ԓ��Ɏg�p�����Ƃ��Ă��C���C�ǂ̂悤�ȓ��e�i����[�����C�i�i�������B��҂̏ꍇ�C�ǂ̌i�i�ƌ������邩�B�j��I�����邩�ɂ���āC��p�̔������鎞������z���قȂ��Ă�����̂Ƃ�����B��������ƁC�J�[�h����̏���w�����Ƀ|�C���g���t�^���ꂽ���_�ł́C���ɂ��̎��_�Ō����̎咣������i����w�����ɂ��������[�����͌i�i���������ׂ����j���������Ă���Ƃ��Ă��C����w�����ɂ��������[���̑I�͌i�i�����̑I��������Ȃ�����C���̍��Ɋ�Â��ċ��t�����ׂ���̓I���e�����炩�ɂȂ�Ȃ����߁C����ɔ�����p�����������Ƃ͂������C���̔�p�̋��z�������I�ɎZ�肷�邱�Ƃ��ł���Ƃ������Ȃ��B���������āC���m��v���̂������Y���ƔN�x�I���̓��܂łɓ��Y���Ɋ�Â��ċ�̓I�ȋ��t�����ׂ������ƂȂ鎖���i��̓I���������j���������Ă��邱�Ɓi���m��v���A�j�C�����܂łɂ��̋��z�������I�ɎZ�肷�邱�Ƃ��ł�����̂ł��邱�Ɓi���m���B�j�̂�����ɂ��Ă��[�����Ă���ƔF�߂邱�Ƃ��ł����C�{���|�C���g�����v��z�ɂ��Ă͖{���e���ƔN�x�̏I���̓��܂łɍ����m�肵�Ă��Ȃ����̂Ƃ����ق��Ȃ�����C�����@�l�Ŗ@�Q�Q���R���Q���Ɋ�Â������̊z�ɎZ�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��v�B cf.���n������21�N1��30�����^1298��140�ŕ���18(�s�E)42��(�R�c��Y�E�W�����X�g1404��145��)�E��㍂������21�N10��16�����^1319��79�ŕ���21(�s�R)24���c�c����18�N���ߑ�125���ɂ������O�̖@�l�Ŗ@�{�s��134����2�i��72����3�j�́A�@�l�Ŗ@22��3��1���A2���̋K����e�̋Z�p�I�A�זړI�������߂����̂ł���(�u�ʒi�̒�߁v�ɂ͓����炸)�A�@�l�Ŗ@65���ɂ��ϔC(��6��112.02)�͈̔͂���E������̂ł͂Ȃ��Ƃ��ꂽ����c�c�g�p�l�ܗ^�ɂ��Ĉ��̌�����`�ɋ߂��K��ł���{�s�߂��A���m���́u�Z�p�I�A�זړI�Ȓ�߁v�ł���ƌ������̂́A����������̂ł͂Ȃ����A�ƎR�c��Y�͌����B(cf.���^156�ʼnE���u�`�ېł̌����y�ђ��ł̓K�����̊m�ۂ̌��n����A����ƈقȂ�K����݂��A�����āA�ېł̖��m���A���ꐫ��}�邱�Ƃ��A���Y��{�I�����ɂ��Ă̋Z�p�I�A�זړI�Ȓ�߂Ƃ��āA�d�Ŗ@����`�̗v���ɒ�G�����A���e�����ꍇ������`�v) |
6�Ł�323.03������ЃG�X�E�u�C�E�V�[�����E�Ō�����6�N9��16���Y�W48��6��357��(��5.2.3.5.b)
5.2.3.3.b. �������p��
(�A)�T�v(6�Ł�143.04�p���c�B�[�i�����E�Ŕ�����18�N1��24�����W60��1��252��)(�C)�������p�̌v�Z�v�f
(�E)�������p�̕��@
�����n���ߘa5�N3��9���ߘa2(�s�E)349��(���p)�c�c�@�l�Ŗ@��̌������p���Y�̎擾���Ə���Ŗ@��̉ېŎd����̓�������ꂽ�B������P5�ЂƂ̌_��������͕���27�N9��17���ł��邪�AP5�Ђ��@�B�������������͕̂���29�N7���Ȃ���9���ł���A����������28�N5�����ȑO�Ɂu�擾�v�u�ېŎd����v�����Ă��Ȃ��Ɣ��f���ꂽ�B
COLUMN5-6 ���z�������p���Y(�@�ŗ�133��)
6�Ł�324.03NTT�h�R���E�G���g�����X��������E�Ŕ�����20�N9��16�����W62��8��2089�ŕS�I7��57ir5.2.3.3.c. �J�����Y(�@�ŗ�14��1���A�@��32��1���A�@�ŗ�64��1��)
5.2.3.4. ����
5.2.3.4.a. �]����(�@��33��1���A�@�ŗ�68��1��)
| 1�Ł�323.09�P���E�b�h�����E�����n���������N9��25���s�W40��9��1205�ŏ��a59(�s�E)145��(�S�I4��108��)�E������������3�N6��26���s�W42��6=7��1033�ŕ�����(�s�R)99���c�c�A�����J�@�l�ō�����TKC�ƐԎ���KE��������A�ЂƂȂ�B����X��(���{�@�l)��A�Ђ̊�����L���Ă����BX��A���̒��뉿�z��0�~�Ɍ��z���A�����Z�����A�X�Ɍ������J�߂ɂ��ҕt�����������B�����Z���y�ъҕt�����͉\���B ���|�@X�̐��������p�B �@�K��̎�|�\�\�u�@�l�Ŗ@33���͎��Y�̕]�����̎戵���߂��K��ł���B�v�@1���́u�����Ƃ��āA�����@�l�����̗L���鎑�Y�ɂ��]���������ĕ]�����̑����o���������ꍇ�ł��A���̋��z�͏������z�̌v�Z�㑹���ɎZ�����Ȃ����ƂƂ��v�Ă���B�@2�����u���K�����������Y�ɂ��A�ЊQ�ɂ�钘���������v���̏ꍇ�ɁA����̗v���̉��A�u��O�I�Ɂv�u�����̊z�ɎZ�����邱�Ƃ�F�߂�B�v �@���@�K��ɂ��ā\�\�Ƃ���ŁA���@�͈��̏ꍇ�Ɂu�]�����̌v���K�v�I�Ȃ��̂Ƃ��Ă���A�@�l�Ŗ@33���ƕK�������O����ɂ��Ă͂��Ȃ��B�v �@���@���Ɖ�v�����Ɩ@�l�Ŗ@�Ƃ̊W�\�\�u�@�l�Ŗ@�����ɏ��@���Ɖ�v�����Ƃ͈قȂ����K���u�����Ƃ͂��蓾�邱�Ƃł����āA���̏ꍇ�ɂ͉ېł̊W�ł͖@�l�Ŗ@�̋K��ɂ��ׂ����Ƃ͓��R�̂��Ƃł���A���@22��4���͂��Ƃ�肱�̂悤�ȓ��@�̖����̋K���r������Ӗ��������̂ł͂Ȃ��v�B �@�@�l�Ŗ@33��2�������Ă͂܂�ꍇ�Ƃ́\�\�u�L���،��̉��z���������ቺ��������Ƃ����̂́A���뉿�z�c�c�ŕ]������Ă���L���،��̎��Y���l���A���̒��뉿�z�ɔ���ُ�Ɍ������������ł͑��肸�A���̌������Œ�I�ʼň������Ȃ�����ɂ��邱�Ƃ�v����v�B ���@���̔w��ɂ́A�����̌������Ɍv�シ��Ƒ����̓�d�v��i��Вi�K�̏����v�Z�ɂ�����}�C�i�X�ƁA����i�K�̏��n���v�v�Z�ɂ�����}�C�i�X�j�ƂȂ�A�Ƃ�����肪����B ���ۓIM&A�Ɋւ��P1��506�ŃR�����Q�ƁB |
5.2.3.4.b. �ݓ|����
| 6�Ł�324.04���⎖���E�Ŕ�����16�N12��24�����W58��9��2637�ŕS�I7��58fj �����E���_�@�Z��Ɋւ���ݓ|�����̔F�肪����ꂽ�B��R�[�Ŏҏ��i�A��R�ېŒ����i�B ���|�@�@�l�Ŗ@22��3��3���u���Y���ƔN�x�̑����̊z�v�c�u���Y���K�����S�z������s�\�ł��邱�Ƃ�v����v�u�S�z������s�\�ł��邱�Ƃ��q�ϓI�ɖ��炩�łȂ���Ȃ�Ȃ��v �u�Љ�ʔO�ɏ]���đ����I�ɔ��f�����v �@���u���ґ��̎���v �@�@���u���҂̎��Y�v �@�@���u�x���\�́v�� �@���u���ґ��̎���v �@�@���u������ɕK�v�ȘJ�́v �@�@���u���z�Ǝ旧��p�Ƃ̔�r�t�ʁv �@�@���u����������s���邱�Ƃɂ���Đ����鑼�̍��҂Ƃ̂��ꂫ�o�c�I�����v�� �@���u�o�ϓI���v�� �ݓ|�����̑����v��̉\���ɂ��Ă̐��Ƃ��ċ������鎖��c�c1�Ł�323.07�叺���Ɗ�����Ў����E���n�����a33�N7��31���s�W9��7��1403��(�[�Ŏ�X�́A�������z���Ƃ��Čv�サ�����AY�Ŗ������́A�������^�ł���Ƃ��āA�����v���۔F���悤�Ƃ�������) �@���|�́A�������p�B�������̑S�Ăɂ������v��������킯�ɂ͂����Ȃ��B�u��������s�\�ł���ꍇ�������������l�ɋA�����ꍇ�ɂ̂݁v�����Z���B�u����s�\�ł��邩�ǂ����́A�P�ɍ����������߂̏�Ԃɂ��邩�ǂ����ɂ���Č����ׂ����̂ł͂Ȃ��A���Ƃ������߂̏�Ԃɂ���Ƃ��Ă��Ȃ��x���\�͂����邩�ǂ����ɂ���Č��肷�ׂ��v �@����s�\�Ɍ��肷�闝�R�\�\�����I�ɂ́u���ɂ̑����ɂ����Ď��R�Ɏ��Ȃ̗��v�������v����悤�Ȝ��Ӑ��͔F�߂��Ȃ��Ƃ������ƁA�`���I�ɂ́u���K���ɂ��ẮA�]������F�߂Ȃ����Ƃ������Ƃ���Ă���v(�Q�ƁF�@��33��2���E3��)���ƁA����������B ([���W]: debt/equity swap)fk �@������(���@519��)�����^�ɓ�����ꍇ �� ���ې�(6�Ł�325.02 6�Ł�325.03)�̖��Ƃ��āA�����Z���ɐ�����������B�A���o�ϓI���v�̖������^�̂����̑S�Ă����ɊY������킯�ł͂Ȃ��A�o�ώ���Ƃ��č�����������Ί��ɓ�����Ȃ����Ƃ�����B �@�������������̉ېŊW�c�c���Ə��v�Ƃ��ĉv���v��B�A�����̑��ɑ������ςݏオ���Ă���Ⴊ�����̂ŁA�ʎZ(���E)�\�Ȃ��Ƃ�����(��4.6.4.�������E�������̌J�z���E�J�߂�)�B �@��22��3��(����)�@�@��33��(���Y���]�����̑����s�Z����) �@��p�T�O�Ƒ����T�O�̈Ⴂ�y��22���ɂ����鈵���̈Ⴂ�̗L���c�c���v�Ƃ̑Ή��W�̗L�� �@�Ȃ��u�S�z������s�\�ł��邱�Ɓv���u�q�ϓI�ɖ��炩�łȂ���Ȃ�Ȃ��v�Ƃ�����d�̗v�����H�u�S�z�v�łȂ��u�ꕔ�v�ł͑ʖڂȂ̂��H�u�q�ϓI�v�ł͂Ȃ����҂̔��f�ł͑ʖڂȂ̂��H �@��33���Ƃ̃o�����X�_�͂ǂ��܂ŏd�v���H �����F����߂����Ɖ�v�ƐŖ��Ƃ̑Η�������B �@��Ɖ�v�c��Ђɑ�����҂Ⓤ���Ƃւ̏��J���Ƃ����ϓ_����́A���������m��ł����Ă��������ł�����萳�m�ɐ��v���A�u���̉�Ђ̎��Y�͊�Ȃ��Ȃ�\��������v�ƒm�点�˂Ȃ�Ȃ��B �@�Ŗ��c���ӓI�ɑ����𐄌v���Čv�サ���̏����Ƒ��E���铙�͔F�߂��Ȃ��B �@cf.�@���9-6-3(�����Ԏ����~��ٍς��Ȃ��ꍇ���̑ݓ|��)�A�@���9-4-1(�q��Г�������ꍇ�̑������S��) �S���ݓ|��������ݓ|�� �@���q�G�E�������炪�����ݓ|��(�S�z����s�\�Ƃ������Ƃ܂ł͗v������Ȃ�)�̍l���������Ȃǂ��Ă���B�Ⴆ��3���~�݂��t��������1���~�̉���\�����Ȃ��Ȃ������_��1���~�̕����ɂ��Ă����ݓ|�ꑹ���̌v���F�߂悤�Ƃ�����̂ł���B�c�c�ō��ق͕s�̗p�B �ېŎ����̍���ւ̉e���c�c�ېœ��ǂ͂��̎��Č���ł͕��������̂́A�S�z����s�\�Ƃ����]���̔���ʂ�̂��n�t���͓��Ă���A�܂��ꕔ�w�����咣���镔���ݓ|��̍l�����͎e����Ă��Ȃ��B������[�Ŏ҂̍������ɑ��������ԓx���p�����邱�Ƃ������܂��B����ł͖{�����̈Ӌ`�͎ア�̂��Ƃ����ƁA�キ���Ȃ��B�{�����́u����������s���邱�Ƃɂ���Đ����鑼�̍��҂Ƃ̂��ꂫ�Ȃǂɂ��o�c�I�������Ƃ��������ґ��̎���C�o�ϓI���������܂��C�Љ�ʔO�ɏ]���������I�ɔ��f�����v�Əq�ׂĉ���s�\�Y�������L�������ƂɈӋ`������B �@([���]�]�k�F�Z�ꏈ�������萭�{��������Ă���Ȃ�A�����ċ�s�����̉���������Ȃ�A��s�Ƃ��Ắo���{�̎w���ɏ]������ɁA�����v��͔F�߂�悤�ېœ��ǂɎw�����Ă���p�Ƃ����v�]���\�ߎ����Ă��̊o�������t���Ă����ׂ��������̂ł��낤���B�@�w���Ř_����悤�ȓ��e�Ȃ̂��Ƃ����^��͂��Ă����B) cf.6�Ł�234.01���Ə����ݓ|���s�������ԊҐ��������E�Ŕ����a53�N3��16����24��4��840�� cf.���莖���E���n�����a51�N9��13����22��9��2330�Łc�c�e��Ђ��Ԏ��q��Ђɑ��������������ꍇ�ɑ�����̎q��Ђ̏����Y���l���}�C�i�X�ł��鎞�A�����̕]�����̌v��͔F�߂��Ȃ��B���a54�N�@���9-10-10��2�����@���9-1-12(����������ɂ����銔���̕]����) ������������8�N10��23������1612��141�Łc�c�o�u���o�ϕ���ɔ����I�����Y�Ƃ��Ă̊G��̉��l�\�����@�ŗ�68��1��1�����ɂ����u�����������v���͂���u�ɏ�������ʂȎ����v(�j)�ɓ�����Ȃ��B |
| ������ЃV�X�e���R���T���^���g�����E�����n���ߘa5�N1��27���ߘa3(�s�E)591��(���p)(��ˋM��d�Ŕ��ጤ����2024�N7��19����)�c�c�a�������S���t������̗a�������̑ݓ|�����v�㎞���̓S���t�N���u�މ�ł͂Ȃ��S���t�N���u�Đ��v��ɂ��x���Ə��̌��͂����������ł���Bcf.�@���9-6-1:���K���̑ݓ|��A�@���9-7-12�S���t������̗a�����̈ꕔ����̂Ă�ꂽ�ꍇ�̎戵�� |
5.2.3.4.c. �ݓ|������(�@��52��1���A�@�ŗ�96��1���A�d��57����9��1��)(�@��53��ԕi�����������͔p�~)
�Ⴆ�b�Ƃ������Z�@�ւ�1000�l�ɂ��ꂼ��10��37.5%�̗����ő݂��t�����Ƃ���B�ߋ��̎��т���͉���s�\�ƂȂ�Ɨ\�z�����Ƃ���B1000�l����\��ʂ����ł����13750���������邱�ƂɂȂ邪�A�\�z�ʂ��������ł��Ȃ������Ƃ����2750������ł����A���Ǎb��11000���������ɂƂǂ܂�B���̂悤�ȏꍇ�ɁA�݂��|��\�z�Ɋ�Â��ė\�ߑ����Ɍv�サ�Ă��܂����Ƃ����̂��ݓ|�������ł���B��Ɖ�v�̊ϓ_����A�\�z�����ݓ|���\�߃}�C�i�X�Ƃ��Ĉ������Ƃ͍����I�ł��邵�A�Ŗ��̊ϓ_��������Ӑ��̔r�����ł߂��Ă���Α����v���F�߂č\��Ȃ��B�@�@��22��3��3���y��33���Ƃ̊W�ŁA���Ⴊ�u�S�z������s�\�v�u�q�ϓI�ɖ��炩�v����Ȃɗv���������Ă��邱�Ƃ́A�@��52���������I�ɑݓ|������(����͌��njo�ϓI���ʂƂ��ĕ����ݓ|����m�F���邱�Ƃɋ߂�)�����e���Ă��邱�ƂƔ�r���āA�A���o�����X�ł���Ƃ��]��������B
5.2.3.5. �����Z���𐧌�����ʒi�̒��
5.2.3.5.a. �d�Ō���(�@��38���A39���A55��3��(��4��))
5.2.3.5.b. �s���o��(�@��55��1���E2���E5��(��6��))�E���ۋ���(55��3���E4��(��4���E5��))(��4.3.2.2.�Ǝ���)
�@��55��(�s���s�����ɌW���p��)�@�����@�l���A���̏����̋��z�Ⴕ���͌������z���͖@�l�ł̊z�̌v�Z�̊�b�ƂȂ�ׂ������̑S�����͈ꕔ���B�����A���͉������邱�Ɓc�c�ɂ�肻�̖@�l�ł̕��S�����������A���͌��������悤�Ƃ���ꍇ�ɂ́A���Y�B�������s�ׂɗv�����p�̊z���͓��Y�B�������s�ׂɂ�萶���鑹���̊z�́A���̓����@�l�̊e���ƔN�x�̏����̋��z�̌v�Z��A�����̊z�ɎZ�����Ȃ��B�Q�@�O���̋K��́A�����@�l���B�������s�ׂɂ�肻�̔[�t���ׂ��@�l�ňȊO�̑d�ł̕��S�����������A���͌��������悤�Ƃ���ꍇ�ɂ��ď��p����B
�R�@�����@�l���A�B�������s�ׂɊ�Â��m��\�����c�c���o���Ă���A���͊m��\�������o���Ă��Ȃ����ꍇ�ɂ́A�����̊m��\�����ɌW�鎖�ƔN�x�̑��\����O����ꍆ�c�c�Ɍf���錴���̊z�i���Y�̔̔����͏��n�ɂ����铖�Y���Y�̎擾�ɒ��ڂɗv�����z�y�ю��Y�̈��n����v����̒ɂ����铖�Y���Y�̎擾�ɒ��ڂɗv�����z�Ƃ��Đ��߂Œ�߂�z�������B�j�A������Ɍf�����p�̊z�y�ѓ�����O���Ɍf���鑹���̊z�i���̓����@�l�����Y���ƔN�x�̊m��\�������o���Ă����ꍇ�ɂ́A�����̊z�̂����A���̒�o�������Y�m��\�����ɋL�ڂ����掵�\�l���ꍀ��ꍆ�i�m��\���j�Ɍf������z���͓��Y�m��\�����ɌW��C���\�����c�c�ɋL�ڂ������@��\����l����ꍆ�i�C���\���j�Ɍf����ېŕW�����̌v�Z�̊�b�Ƃ���Ă������z�������B�j�́A���̓����@�l�̊e���ƔN�x�̏����̋��z�̌v�Z��A�����̊z�ɎZ�����Ȃ��B�������A���Ɍf����ꍇ�ɊY�����铖�Y�����̊z�A��p�̊z���͑����̊z�ɂ��ẮA���̌���łȂ��B
�@��@���Ɍf������̂ɂ�蓖�Y�����̊z�A��p�̊z���͑����̊z�̊���ƂȂ������s��ꂽ���Ƌy�т����̊z�����炩�ł���ꍇ�c�c
�@�@�C�@���̓����@�l����S��\�Z���ꍀ�i�F�\���@�l�̒��돑�ށj���͑�S�\���̓��ꍀ�i���돑�ނ̔��t�����j�ɋK�肷������ȗ߂Œ�߂�Ƃ���ɂ��ۑ����钠�돑��
�@�@���@�C�Ɍf������̂̂ق��A���̓����@�l�����̔[�Œn���̑��̍����ȗ߂Œ�߂�ꏊ�ɕۑ����钠�돑�ނ��̑��̕���
�@��@�O���C���̓��Ɍf������̂ɂ��A���Y�����̊z�A��p�̊z���͑����̊z�̊���ƂȂ����̑���������炩�ł���ꍇ���̑����Y������s��ꂽ���Ƃ����炩�ł���A���͐��������ꍇ�i�����Ɍf����ꍇ�������B�j�ł��āA���Y������ɑ��钲�����̑��̕��@�ɂ��Ŗ��������A���Y������s���A�����̊z���������ƔF�߂�ꍇ
�S�@�����@�l���[�t���鎟�Ɍf������̂̊z�́A���̓����@�l�̊e���ƔN�x�̏����̋��z�̌v�Z��A�����̊z�ɎZ�����Ȃ��B
�@��@���łɌW�鉄�ؐŁA�ߏ��\�����Z�ŁA���\�����Z�ŁA�s�[�t���Z�ŋy�яd���Z�ŕ��тɈŖ@�c�c�̋K��ɂ��ߑӐ�
�@��@�n���Ŗ@�̋K��ɂ�鉄�؋��c�c�A�ߏ��\�����Z���A�s�\�����Z���y�яd���Z��
�@�O�@�O�Ɍf������̂ɏ�������̂Ƃ��Đ��߂Œ�߂����
�T�@�����@�l���[�t���鎟�Ɍf������̂̊z�́A���̓����@�l�̊e���ƔN�x�̏����̋��z�̌v�Z��A�����̊z�ɎZ�����Ȃ��B
�@��@�����y�щȗ��c�c���тɉߗ�
�@��@������������ً}�[�u�@�c�c�̋K��ɂ��ے����y�щ��؋�
�@�O�@���I�Ɛ�̋֎~�y�ь�������̊m�ۂɊւ���@���c�c�̋K��ɂ��ے����y�щ��؋��c�c
�@�l�@���Z���i����@��Z�͂̓�i�ے����j�̋K��ɂ��ے����y�щ��؋�
�@�܁@���F��v�m�@�c�c�̋K��ɂ��ے����y�щ��؋�
�@�Z�@�s���i�i�ދy�ѕs���\���h�~�@�c�c�̋K��ɂ��ے����y�щ��؋�
�@���@���i�A��Ë@�퓙�̕i���A�L�����y�ш��S���̊m�ۓ��Ɋւ���@���c�c�̋K��ɂ��ے����y�щ��؋�
�U�@�����@�l�����^������Y�@�c�c��S��\�����i���d�j�ɋK�肷��d�G���͕s�������h�~�@�c�c��\�����ꍀ�i�O�����������ɑ���s���̗��v�̋��^���̋֎~�j�ɋK�肷����K���̑��̗��v�ɓ�����ׂ����K�̊z�y�ы��K�ȊO�̎��Y�̉��z���тɌo�ϓI�ȗ��v�̊z�̍��v�z�ɑ��������p���͑����̊z�c�c�́A���̓����@�l�̊e���ƔN�x�̏����̋��z�̌v�Z��A�����̊z�ɎZ�����Ȃ��B
| 6�Ł�323.03������ЃG�X�E�u�C�E�V�[�����E�Ō�����6�N9��16���Y�W48��6��357�ŕS�I7��55ls �����E���_�@�E�ł̂��߉ˋ�����v�サ������B���̎ӗ�Ƃ���A��200���~�E1700���~���x������(�u�{���萔���v)�B�{���萔���͉�Ђ������ƂȂ邩�H(��@�x�o�̗�Ƃ��Ė{�����������邪�A�ӗ玩�͈̂�@�łȂ��̂ŁA6�Ł�231.03�����s���c��n���������E�����n�����a48�N6��28���s�W24��6=7��511�łƃp�������Ƃ�����ł��Ȃ�) ���|�@�{���萔���u�́A�ˋ�̌o����v�シ��Ƃ�����v�����ɋ��͂������Ƃɑ���Ή��Ƃ��Ďx�o���ꂽ���̂ł����āc�c���̂悤�Ȏx�o���p���͑����Ƃ��đ����̊z�ɎZ�������v�������܂��A����������ɏ]�������̂ł���Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��v �@���݂͗��@�I�ɉ���(�m�F�K��H�n�K��H)�B �@�����K��ɂ��āA��@�x�o�̑����Z�����֎~���閾���̋K�肪�����Ȃ������B�c�c���R�u�����v����֎~���������̋K�肪�����Ƃ����ꎖ����A���̎Z�����m�F���邱�Ƃ͖@�l�Ŗ@�̎��Ȕے�ł����āA���@�������e�F���Ă�����̂Ƃ͓��������Ȃ��v�B����ɑ��ō��ق͈ꉞ�̍����Ƃ��Č��������(��5�Ł�321.03��|�f�Վ����E�Ŕ�����5�N11��25�����W47��9��5278��)���������B �@�@��22��3���̑����ɂ��������Y�����Ȃ��A�Ƃ������̗p���Ȃ������͉̂��̂��H �@�܂��A��@�x�o�͏�ɖ@��22��3��������Y���ƂȂ邩�H �@�{���萔���������A�̉ېłɂ��āc�c��@�ȏ������ېőΏ�(6�Ł�211.02���������@�ᔽ���������E�Ŕ����a46�N11��9�����W25��8��1120��)������A��@�Ȃ��Ƃɉ��S�������Ƃ̑Ή����ېł���悤�B�@�l����̑��^�ƍl������ꎞ�����B���^�ł͂Ȃ��̑Ή��ƍl������G����(�������Ɏ��Ə����ɂ͊Y�����Ȃ��ł��낤)�B�ǂ���̕����ŕ��S���d���Ȃ邩��ŕ��K����B |
�d��62��(�g�r�铽���̎x�o������ꍇ�̉ېł̓���)�@�@�l�c�c�́A���̎g�r�铽���̎x�o�ɂ��Ė@�l�ł�[�߂�`����������̂Ƃ��A�@�l�������Z�N�l������Ȍ�Ɏg�r�铽���̎x�o�������ꍇ�ɂ́A���Y�@�l�ɑ��ĉۂ���e���ƔN�x�̏����ɑ���@�l�ł̊z�́A���@��Z�\�Z���ꍀ�c�c�m���n�̋K��ɂ��v�Z�����@�l�ł̊z�ɁA���Y�g�r�铽���̎x�o�̊z���S���̎l�\�̊������悶�Čv�Z�������z�����Z�������z�Ƃ���B
�Q�@�O���ɋK�肷��g�r�铽���̎x�o�Ƃ́A�@�l���������K�̎x�o�c�c�̂����A�����̗��R���Ȃ��A���̑�����̎������͖��̋y�яZ�����͏��ݒn���тɂ��̎��R�c�c�Y�@�l�̒��돑�ނɋL�ڂ��Ă��Ȃ����́c�c�������B�m3���ȉ����n
5.2.3.5.c. �����ł̗��v���^�\�\���A���۔�(�@��37���A�d��61����4)
�@��37��(���̑����s�Z��)lm�@�����@�l���e���ƔN�x�ɂ����Ďx�o�������̊z�c�c�̍��v�z�̂����A���̓����@�l�̓��Y���ƔN�x�I���̎��̎��{�����̊z���͓��Y���ƔN�x�̏����̋��z����b�Ƃ��Đ��߂Œ�߂�Ƃ���ɂ��v�Z�������z���镔���̋��z�́A���Y�����@�l�̊e���ƔN�x�̏����̋��z�̌v�Z��A�����̊z�ɎZ�����Ȃ��B�m2�����n�R�@��ꍀ�̏ꍇ�ɂ����āA�����ɋK�肷����̊z�̂����Ɏ��̊e���Ɍf������̊z������Ƃ��́A���Y�e���Ɍf������̊z�̍��v�z�́A�����ɋK�肷����̊z�̍��v�z�ɎZ�����Ȃ��B
�@��@�����͒n�������c�́c�c�ɑ�����c�c�̊z
�@��@���v�Вc�@�l�A���v���c�@�l���̑����v��ړI�Ƃ��鎖�Ƃ��s���@�l���͒c�̂ɑ�����c�c�̂����A���Ɍf����v�������ƔF�߂�����̂Ƃ��Đ��߂Œ�߂�Ƃ���ɂ�������b���w�肵�����̂̊z
�@�@�C�@�L����ʂɕ�W����邱�ƁB
�@�@���@���疔�͉Ȋw�̐U���A�����̌���A�Љ���ւ̍v�����̑����v�̑��i�Ɋ�^���邽�߂̎x�o�ŋً}��v������̂ɏ[�Ă��邱�Ƃ��m���ł��邱�ƁB
�S�@��ꍀ�̏ꍇ�ɂ����āA�����ɋK�肷����̊z�̂����ɁA�����@�l�A���v�@�l���c�c���̑����ʂ̖@���ɂ��ݗ����ꂽ�@�l�̂����A���疔�͉Ȋw�̐U���A�����̌���A�Љ���ւ̍v�����̑����v�̑��i�ɒ�������^������̂Ƃ��Đ��߂Œ�߂���̂ɑ��铖�Y�@�l�̎傽��ړI�ł���Ɩ��Ɋ֘A������c�c�̊z������Ƃ��́A���Y���̊z�̍��v�z�c�c�́A��ꍀ�ɋK�肷����̊z�̍��v�z�ɎZ�����Ȃ��B�������A���v�@�l�����x�o�������̊z�ɂ��ẮA���̌���łȂ��B�m5�E6�����n
�V�@�O�e���ɋK�肷����̊z�́A���A���o���A���������̑�������̖��`�����Ă��邩���킸�A�����@�l�����K���̑��̎��Y���͌o�ϓI�ȗ��v�̑��^���͖����̋��^�i�L����`�y�ь��{�i�̔�p���̑������ɗނ����p���тɌ��۔�A�ڑҔ�y�ѕ���������Ƃ����ׂ����̂������B�����ɂ����ē����B�j�������ꍇ�ɂ����铖�Y���K�̊z�Ⴕ���͋��K�ȊO�̎��Y�̂��̑��^�̎��ɂ����鉿�z���͓��Y�o�ϓI�ȗ��v�̂��̋��^�̎��ɂ����鉿�z�ɂ����̂Ƃ���B�m������`�n
�W�@�����@�l�����Y�̏��n���͌o�ϓI�ȗ��v�̋��^�������ꍇ�ɂ����āA���̏��n���͋��^�̑Ή��̊z�����Y���Y�̂��̏��n�̎��ɂ����鉿�z���͓��Y�o�ϓI�ȗ��v�̂��̋��^�̎��ɂ����鉿�z�ɔ䂵�ĒႢ�Ƃ��́A���Y�Ή��̊z�Ɠ��Y���z�Ƃ̍��z�̂��������I�ɑ��^���͖����̋��^�������ƔF�߂�����z�́A�O���̊��̊z�Ɋ܂܂����̂Ƃ���B�m����59��1���݂Ȃ����n�̏��ŗ�169���̂悤�Ȏ����̔����Ƃ�����ł͂Ȃ����Ƃɗ��Ӂn�m9���ȉ����n
�@�ŗ�73��(��ʊ��������Z�����x�z)�@�@��O�\�����ꍀ�c�c�ɋK�肷�鐭�߂Œ�߂�Ƃ���ɂ��v�Z�������z�́A���̊e���Ɍf��������@�l�̋敪�ɉ������Y�e���ɒ�߂���z�Ƃ���B
�@��@���ʖ@�l�A�����g�����y�ѐl�i�̂Ȃ��Вc���c�c�@���Ɍf������z�����v�z�̎l���̈��ɑ���������z
�@�@�C�@���Y���ƔN�x�I���̎��ɂ��������{�����̊z�c�c���\��ŏ����A����ɓ��Y���ƔN�x�̌������悶�Čv�Z�������z�̐番�̓�E���ɑ���������z
�@�@���@���Y���ƔN�x�������̋��z�̕S���̓�E���ɑ���������z�m�ȉ����n
| 6�Ł�325.02���m���Y����l�������E������������4�N9��24���s�W43��8=9��1181�ŕ���3(�s�R)134��(���R�����n������3�N11��7���s�W42��11=12��1751�ŏ��a63(�s�E)213��) �����E���_�@A�̐Ԏ����~�ς��邽�߁AX��A�ɔ̔����Ă���_�|�����ɂ�������l����(�ړ]���i�Ɠ��l)�B���̊z��S�z�����v��ł��邩�A��(�@�l�Ŗ@37��1��)�ɊY���������s�Z���z�̕������ېŏ����ɉ��Z���Ȃ���Ȃ�Ȃ����H�@(�u�{�����������v�ɂ��Ă͏ȗ�) ��R�@�T�ˊ��p �u�@�@�Q�@�{������l�����y�і{�����������̊�t���Y���� �@�@�@�i��j�@��t���̑����s�Z���Ɋւ���@�l�Ŗ@�O�����̋K��̎�| �@�@�l�Ŗ@�O�����́A�ǂ̂悤�Ȗ��`�������Ă�����̂ł����Ă��A�@�l�����K���̑��̎��Y���͌o�ϓI�ȗ��v�̑��^���͖����̋��^�������ꍇ�ɂ́A�L����`�y�ь��{�i�̔�p���̑�����ɗނ����p���Ƃ������̂������āA�������t���Ƃ��Ĉ����A���̉��z�ɂ��ẮA���̑����Z�����x�z�������镔�����A���̖@�l�̏����̋��z�̌v�Z�㑹���̊z�ɎZ�����Ȃ����̂Ƃ��Ă���i����y�јZ���j�B���Ȃ킿�A�L����`��〈�{�i�̔�p�Ƃ�����������c�ƌo��Ƃ��Ďx�o�������̂������āA�@�l�̂����O�҂̂��߂̍��̕����A�Ə���o�ϓI���v�̖����̋��^�ɂ��ẮA���̉��z����t���Ƃ��Ĉ����ׂ����̂Ƃ��Ă���̂ł���B �@�����Ƃ��A�Ⴆ�A�@�l����O�҂ɑ��č��̕��������s���ꍇ�ł����Ă��A���̍��̉�����\�ł���̂ɂ�����������Ƃ����̂ł͂Ȃ��A���̉�����s�\�ł��邽�߂ɂ�����������ꍇ��A�܂��A�@�l����O�҂̂��߂ɑ����̕��S���s���ꍇ�ł����Ă��A���̕��S�����Ȃ���t�ɂ��傫�ȑ������邱�Ƃ����炩�ł��邽�߁A��ނ����̕��S���s���Ƃ������ꍇ�́A�����I�ɂ݂�ƁA����ɂ���đ�����Ɍo�ϓI���v���ŋ��^�������̂Ƃ͂����Ȃ����ƂƂȂ邩��A�������t���Ƃ��Ĉ������Ƃ͑����łȂ����̂ƍl������B�@�l�Ŋ�{�ʒB��|�l�|�ꂪ�A�u�@�l�����̎q��Г��̉��U�A�o�c���̏��n���ɔ������Y�q��Г��̂��߂ɍ��̈����̑��̑����̕��S�����A���͓��Y�q��Г��ɑ�����̕����������ꍇ�ɂ����Ă��A���̕��S���͕��������Ȃ��������傫�ȑ������邱�ƂɂȂ邱�Ƃ��Љ�ʔO�㖾�炩�ł���ƔF�߂��邽�߂�ނ����̕��S���͕���������Ɏ����������̂��Ƃɂ��đ����ȗ��R������ƔF�߂���Ƃ��ɂ́A���̕��S���͕������������Ƃɂ�萶���鑹���̊z�́A��t���̊z�ɊY�����Ȃ����̂Ƃ���B�v�ƒ�߂Ă���q���ؔԍ����r�̂��A�E�̂悤�Ȏ�|����A�����I�ɂ݂Čo�ϓI���v�̖����̋��^�Ƃ͂����Ȃ����̂���t���ɊY�����Ȃ����Ƃ𖾂炩�ɂ������̂Ɖ������B �@�@�@�i��j�@�{������l�����̌o�܂Ƃ��̊�t���Y���� �@(1)�@�f���|�ɑ��錴���̖{������l�����́A�O�L�̂Ƃ���A�f���|�ɑ��z�̐Ԏ��̔����������܂��悤�ɂȂ������Ƃ��炱��ɑ���~�ύ�Ƃ��čs���邱�ƂƂȂ������̂ł���i�ؐl���앶���̏،��j�A����ɔ����A�܂����a�Z��N�����O����t���Ō������f���|���Ăɔ��s�����������i�q���ؔԍ����r�j�ɁA�u�E���A�Q�l�r�L�i�`���E�S�N�Z�C�R�E�@�Z�K�c�h�A�J�W�j�^�C�X���G���W���j�v�Ƃ̋L�ڂ��Ȃ���A�O�L�r���b�g�̔������̂����ꉭ���Z�Z���~�i����́A�O�L�̂f���|�̏��a�Z��N�Z���O�Z�����݂̎c�����Z�\�ɂ����錇�����ꉭ��㎵�Z���O�Z�Z�Z�~�̈�Z�Z���~�����̕��������������z�ɒ��x����������z�ł���B�j�ɂ��Ēl�������s���A�����œ��N�����O����t���Ō������f���|���Ăɔ��s�����������i�q���ؔԍ����r�j�ɁA�u�E���A�Q�l�r�L�i�`���E�S�N�Z�C�R�E�@���K�c�h�A�J�W�j�^�C�X���G���W���j�v�Ƃ̋L�ڂ��Ȃ���A�O�L�r���b�g�̔������̂�����O�Z�Z���~�i����́A�O�L�̂f���|�̓��N�����O������݂̎c�����Z�\�ɂ����錇������O��Z���~�̈�Z�Z���~�����̕��������������z�ɒ��x����������z�ł���B�j�ɂ��Ēl�������s���Ă���B �@(2)�@�E�̂悤�Ȏ����W���炷��A�{������l�����́A�O�L�̂Ƃ���Ɛт��������Ă����f���|�ɑ��鉇���[�u�Ƃ��čs��ꂽ�����ɂ�闘�v�̖������^�̐�����L������̂Ƃ����ׂ��ł���A���������Ė@�l�Ŗ@�O��������̊�t���ɊY��������̂Ƃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �@����ɑ��A�����́A�{������l�����́A�������o�ϓI�A�����I�ɔ��f���Ăf���|�̖_�|�̐��Y���̎Z�̂Ƃ��悤�ɂ��邽�߃r���b�g�̔������z�ɂ��Č��������s���A���̌��z�������s�����ɉ߂��Ȃ����̂ł��邩��A��t���ɂ͊Y�����Ȃ��Ǝ咣����B�������A�O�L�̂悤�Ȑ������̋L�ړ����炷��A�{������l�����́A�f���|�̐Ԏ��ɑ��鉇���Ƃ��čs��ꂽ���̂ł��邱�Ƃ����炩�ł���A��ʂɔ���i�ɂ��ėʖڕs���A�i���s�Ǔ����������ꍇ�Ɉ��̋�̓I�ȎZ�o�����Ɋ�Â��čs����ʏ�̎���ɂ����锄��l�����Ƃ͂��悻���̐������قɂ�����̂ł����āA������ɂ��Ă��f���|�ɑ���u�o�ϓI�ȗ��v�̖����̋��^�v�Ƃ��Ė@�l�Ŗ@�O��������̊�t���ɊY��������̂Ƃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���������āA�����̉E�咣�͎����ł���B �@�܂��A�����́A���Ə�̕K�v�Ɋ�Â��^�ɂ�ނȂ������̕��S���́A�@�l�Ŗ@�O�����ɂ�����t���ɊY�����Ȃ����̂Ɖ����ׂ��ł���A�{������l�������A�����̎��Ə�̕K�v�Ɋ�Â���ނȂ��x�o�ł��邱�Ƃ����炩�ł��邩��A��t���ɊY�����Ȃ��Ǝ咣����B�������A�E�@�l�Ŗ@�O�����̋K��́A���̘Z���ɂ����āu�L����`�y�ь��{�i�̔�p���̑������ɗނ����p���тɌ��۔�A�ڑҔ�y�ѕ���������v�Ƃ����ׂ����̂��E��t�����珜�O���邱�ƂƂ��Ă���ɉ߂����A�E�̋K��ɂ����u�L����`�y�ь��{�i�̔�p���̑������ɗނ����p�v�Ƃ́A������c�ƌo��̐�����L������̂��w�����̂Ɖ����ׂ����Ƃ͑O�L�̂Ƃ���ł���B��������ƁA�{������l�����́A���̂悤�Ȃ�����c�ƌo��̐�����L������̂Ƃ͓���������Ȃ�����A�����̉E�咣�͍̗p�ł��Ȃ��B �@�X�ɁA�����́A�O�L�@�l�Ŋ�{�ʒB��|�l�|��̒�ߓ����炵�āA�{������l��������t���ɊY�����Ȃ����̂ł���Ǝ咣����B�����āA�m���ɁA���̉�����s�\�ł��邽�߂ɂ�����������ꍇ��A���̕��S�����Ȃ���t�ɂ��傫�ȑ������邱�Ƃ����炩�ł��邽�߁A��ނ����̕��S���s���Ƃ������ꍇ�́A����������I�ɂ݂�ƌo�ϓI���v�̖����̋��^�Ƃ͂����Ȃ����̂ƍl�����邱�Ƃ́A�O�L�̂Ƃ���ł���B�������A�ؐl���앶���y�ѓ��㓡��j�̊e�،��ɂ��A�{������l�������s��ꂽ���_�ɂ����āA�f���|�̋Ɛт͈������Ă������̂́A���U�A�o�c���̏��n�Ƃ������E�ʒB�Ɍf����ꂽ�悤�Ȏ��Ԃ������A���邢�͋�s�����~�������̂��ߓ|�Y��ԂɊׂ�Ƃ����悤�Ȏ��Ԃɂ܂Ŏ����Ă͂��炸�A���������Č������{������l�������s��Ȃ�����㌴���ɂ����Ă��傫�ȑ������邱�ƂƂȂ邱�Ƃ��Љ�ʔO�㖾�炩�ł���ƔF�߂���悤�ȏ����������̂Ƃ܂ł͓���F�߂��Ȃ��B�܂��A�E�̎������炷��A�{������l�����ɑ������錴���̂f���|�ɑ��锄�|���̉�����s�\�ȏɂ܂łȂ��Ă������̂łȂ����Ƃ����炩�ł���B���������āA�����̉E�咣���̗p�ł��Ȃ��B�v �T�i�R�@�������p�E�T�i���p �@�u�@�l�����K���̑��̎��Y���͌o�ϓI�ȗ��v�̑��^���͖����̋��^�������ꍇ�ɂ́c�c���Ƃ��Ĉ����A���̉��z�ɂ��ẮA���̑����Z�����x�z�������镔�����c�c�����̊z�ɎZ�����Ȃ��v �@�u�{������l�����́cA�ɑ��鉇���[�u�Ƃ��čs�Ȃ�ꂽX�ɂ�闘�v�̖������^�̐�����L����v cf.�F�{�n������14�N4��26������13(�s�E)1���Ŏ�252������9117���p�E������������14�N12��20������14(�s�R)12���Ŏ�252������9251���p�c�c���{�e��Ђ���O���q��Ђɑ���Ɩ��ϑ���ڂ̎x�o���@�l�Ŗ@37��1���̊��ɓ�����d�œ��ʑ[�u�@66����4��3���ɂ�葹���Z�����ł��Ȃ��Ƃ��ꂽ����B cf.�����n������21�N7��29������20(�s�E)116������21(�s�E)84������2055��47�Ŋ��p�E������������22�N3��25������21(�s�R)275���Ŏ�260������11405���p�m��c�c�����̌���\�҂��S�z�o�����鍑�O�֘A�@�l�ɑ�������������Ƃ��ꂽ����B cf.��a���[�X�L����Ў���(�����ύX��F�������|�X�L�����)�E���n�����a33�N9��25�����a28(�s)77���s�W9��9��1970�ŔF�e21010640�E��㍂�����a35�N12��6�����a33(�l)1328���s�W11��12��3298�Ŋ��p�m��c�c�w����ɂ��ē�����Ѝs�v�Z�۔F�K��i�����̖@�l�Ŗ@31����3��1���j��p���đ����Z����ے肵���������������ꂽ����B cf.�L����`��Ɗ��Ƃ̊W�ɂ��āF��Ö@�l�V������E�����n������24�N1��31����58��8��2970�ŕ���21(�s�E)492���������p�E������������24�N11��29������24(�s�R)68���T�i���p(���ΗY��Y�E�W�����X�g1468��118��)�c�c��Ö@�l���֘A�R���^�N�g�����Y�̔��Ǝ҂̐�`��S�������Ƃɂ��āA���Ƃ�������B |
| 6�Ł�325.03 PL�_�ꎖ���E��㍂�����a59�N6��29���s�W35��6��822�ŏ��a58(�s�R)9��ay �����E���_�@X�_��EF�Ђ̌J�z��������ł��������߁A�y�n���~�L�ό���1��7348��(��869�~)��X�_�ꁨ2��2622��(��1118�~)��F�Ё�(�y�n�̈ꕔ�B��3000�~)��K��(��O��)�Ɠ]�X���n�BY�Ŗ������́A(1)�~�L�ό����玞���Ƃ̍��z�̎v�A(2)�v�������ɉ��Z�A(3)�����Ƃ̍��z��F�Ђɑ�����A�Ƃ��čX�������B�Ȃ��A�ʑi�ɂă~�L�ό��ɑ�����ېł̏������m�F����Ă����B ���|�@(1)�ɂ��āc�c�uX�͖{���y�n�̔���ɂ���āA�]�����S�����ꂽ���z2��2622��4395�~�����̎��v�A�����ɔ��z1��7348��8535�~�����z�̌�����v�������A���v�̊z�͉E��������̂ł͂Ȃ��v�B �@X�̓~�L�ό����甃������F�ɏ���̉��z�Ŕ��p���邱�Ƃ��u�����_��̈���e�ƂȂ��Ă����v�B�@�uY�́A����6��0188��0890�~�ƉE���z�Ƃ̍��z4��2389��2355�~���AX���~�L�ό�������Ђ������I�ɑ��^�����z�ł���Ǝ咣����B�������A�E�ɂ��������͉��̓�����Ȃ��ꍇ�̎����ł���Ƃ���A�E�咣�͉E�����_��ɑO�L�̂悤�ȓ]�������邱�Ƃ����Ă��邩��A�̗p���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��v�i�Ȃ��A�@�l�Ŗ@37��1���ł͂Ȃ�22��2���̖��ł���j�B �@�u�d�ʼn���s�ׂł��邾���̗��R�ł��̌��ʂ�S�Ĕے�ł�����̂ł͂Ȃ��v�B�Ȃ��A�~�L�ό���X�Ƃ̎���őd�ʼn����}���Ă���̂̓~�L�ό��ł���i����������͖@�l�Ŗ@37��1���̋K���K�p�����ʑi�ɂ�莸�s�����jX�̖@�l�Ŋz������������̂ł͂Ȃ��A�uX�ɂƂ��Ắc�c�E�]���������������5000���~�]�̓]�����v��I�Ԃ��Ƃ̕����o�ϐl�Ƃ��Ă͍����I�v�B �@(2)(3)�ɂ��āc�c�uX�̖{���y�n�̔��p�ɂƂ��Ȃ����v�A�����͂������2��2622��4395�~�ł����āA���p���v�͑����Ȃ��v�B�uX���{���y�n�ɂ��ėL���Ă������v�A���l�͑O�L�̂Ƃ���2��2622��4395�~�ɂ����Ȃ���������AX�͂������z�̗��v�𑼂ɑ��^�ɂ��^���邱�Ƃ��ł��锤�͂Ȃ��v�BF�̗��v�́uX����^����ꂽ�ƕ]�����邱�Ƃ͂ł����A�~�L�ό�������Ђ��炻�̓]������ɂ��^����ꂽ�v�B �l�@ S�Ђ��e���P�ЂɌ���3���~�^�����ꍇ�B S�ЁF�������@���@�����Z�����x�z���ł̂ݑ����Z������B(�n����3���~�̌�����22��2���u�����ɂ�鎑�Y�̏��n�v�ɂ�����v���v�サ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��A�Ƃ������Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��B�����Z�����x�O�̕������������Z���ł��Ȃ��A�Ƃ�������) P�ЁF22��2���u�����ɂ�鎑�Y�̏��v���v3���~���v���v��(�����͂����́u���Y�v�Ɋ܂܂��) S�Ђ�P�ЂɎ���3���~�̓y�n�^�BS�ЂɂƂ��Ă̓��Y�y�n�̌�����1���~�̏ꍇ��5���~�̏ꍇ�Ƃŏꍇ�����B S�ЁF����1���~�̏ꍇ�@�c�c22��2���u�����ɂ�鎑�Y�̏��n�v���������n���[���B���n�v2���~���v���v��(����1���~�A����0�~�����n��1���~�ł͂Ȃ�)�B 3���~��������(�����Z�����x�z���ł̂ݑ����Z��) S�ЁF����5���~�̏ꍇ�@�c�c22��2���u�����ɂ�鎑�Y�̏��n�v���������n���[���B���n��2���~���v��(����5���~�A����0�~�����n��5���~�ł͂Ȃ�)�B 3���~��������(�����Z�����x�z���ł̂ݑ����Z��) P�ЁF�v3���~�����v���v��BP�ЂɂƂ��Ă̓y�n�̒��뉿�z��3���~(�����ɂ�0�~�Ŏ�������A�Ŗ����3���~�ōw�������K3���~�̑��^�������̂Ƌ[������Ă���Ƃ�������)�B���P�Ђ���O�҂ɓy�n��3���~�Ŕ��p�����P�Ђ̏��n�v��0�~�B S�ЂƐꑮ�_�������ł��钘���o�X�P�b�g�{�[���v���[���[���AP�Ђ̍L����`�̂��߂ɖ����Ŕh���B S�ЁF22��2���u�����ɂ��c�̒v���{��P��S�Ɏx�����ׂ��K���ȑΉ�(�Ⴆ��3���~�Ƃ���)�����������Ƌ[�����A���z���v���v��B 37��7�����ʏ��u�L����`��c�������v�̓K�p�̗L���ɂ��čl����K�v������B�L����`��ł���Α����Z����(3���~�̉v���A3���~�̑����A����ď���0�~)�B�L����`��łȂ���Ί��Ƃ��đ����Z�����x�z(�Ⴆ��1���~�Ƃ���)���ߕ����̑����Z�������������(3���~�̉v���A1���~�̑����A����ď���2���~)�B P�ЁF�����̖���ꍇ��22��2���ɋK��Ȃ��B�v���v��Ȃ��B�L����`��Ƃ��ĉ��������Ă��Ȃ����瑹���v���0�~�B(�����v�オ�Ȃ��������ېŏ������������A�Ɛ��������) ���n�l�E����l���l���@�l����4�p�^�[���o����B ���@�l���@�l�̓y�n���^�܂��͒�z���n�c�c��f ���l���@�l�̓y�n���^�܂��͒�z���n�c�c�l�ɂ��ď���59��1���݂Ȃ����n�ېł̖��A�@�l�͖@��22��2���̎v�̌v��̖��B ���@�l���l�̓y�n���^�܂��͒�z���n�c�c�@�l�ɂ��Ė@��37��1�������̖��(�����Z���\���̖��)�A�l�ɂ��Ďv���ꎞ�����ɂȂ���B ���l���l�̓y�n���^�܂��͒�z���n�c�c���n�l�ɏ���59��1���݂Ȃ����n�ېłȂ��B����l�ɑ��^�ł̉ېŁB |
�d��61����4(���۔����̑����s�Z��)�@�@�l���c�c�x�o������۔�̊z�c�c�ɂ��ẮA���Y���۔�̊z�̂����ڑ҈��H��̊z�̕S���̌\�ɑ���������z���镔���̋��z�j�́A���Y�K�p�N�x�̏����̋��z�̌v�Z��A�����̊z�ɎZ�����Ȃ��B
�Q�@�O���̏ꍇ�ɂ����āA�@�l�c�c�̂������Y�K�p�N�x�I���̓��ɂ����鎑�{���̊z���͏o�����̊z���ꉭ�~�ȉ��ł�����́i���Ɍf����@�l�������B�j�ɂ��ẮA�O���̌��۔�̊z�̂�����z�T�����x�z�i���S���~�ɓ��Y�K�p�N�x�̌������悶�Ă�����\��ŏ����Čv�Z�������z�������B�j���镔���̋��z�����āA�����ɋK�肷�钴���镔���̋��z�Ƃ��邱�Ƃ��ł���B
�@��@���ʖ@�l�̂������Y�K�p�N�x�I���̓��ɂ����Ė@�l�Ŗ@��Z�\�Z���܍�����͑�O���Ɍf����@�l�ɊY��������́m�ȉ����nlh
| 6�Ł�325.04�ݗL�����E�����n������14�N9��13������11(�s�E)20���Ŏ�252������9189���p�E������������15�N9��9������14(�s�R)242������1834��28�ŕS�I7��62����������A�����F�e(�m��)(�ҕx�v�E�W�����X�g1270��210��) �����E���_�E���|�@��w�a�@�̉@����̉p���Y����⏕���邱�Ƃ����۔�ɓ�����Ƃ�����R���������������۔�ɓ�����Ȃ��i���瑹���Z�����������j�Ƃ�������B �l�@ ���۔�K����n�K�����H�c�c���ʋK�肪�Ȃ���Ύ��ƂƂ̊֘A�������镔���ɂ������Z�����F�߂���ׂ��B���X�͌��۔�͎���~�����̂��߂̊�Ɖ�v��̔�p�ł���ƍl�����Ă���B �@�ł͂Ȃ������Z����ے肷��̂��H (1)����ߖ� (2)���{�~�����i([���]corporate governance�̖��ł����Ė@�l�ł������o���ׂ����ł��낤���H) (3)���۔��������ւ̉ې��̍���B[���]���ƂƂ̊֘A�������Ȃ������ɂ��ẮA�����������Ɣ�p�ł͂Ȃ��i���������{���̈Ӗ��̌��۔�ɂ�������Ȃ��j�A���v�����ɋ߂�����A�����Z���ے�͊m���Ɏ��̓I�ɐ����������B���q�E�㔼����(���E����)�ɂ��āA��Г���(corporate governance)���ő�����̂��ł��낤���A�����̐����͕�����₷���B���۔�̕։v���Ă��鑊�葤�ɂƂ��Ă͏���ł��邩�瑊�葤�̉ېŏ�����{���͑��傳������̂ł���Ƃ���A���s�̍����A�ېŘR�ꂪ�����̏�ʂŐ����Ă��悤�B�����Ŏx���ґ��̒i�K�ŗ\�ߕX�I�ɉېł��Ă��܂��A�Ƃ����i���e�����o�ϓI���̂ɏƂ炵�ċ̒ʂ����j�����ł���B cf.3�Ł�325.04�r�䏤���I�[�g�I�[�N�V���������E���l�n������4�N9��30������3(�s�E)25���s�W43��8=9��1221�Ŋ��p�E������������5�N6��28������4(�s�R)110���s�W44��6=7��506�ŕS�I5��64���p�c�c�I�[�g�I�[�N�V�����ɂ�����i�i�̍w����p���x��������Ƃ��đ����Z�����悤�Ƃ����Ƃ���A���۔�ɓ�����Ƃ��đ����Z�����ے肳�ꂽ����B Cf.�I���G���^�������h���|�ϑ��������E�����n������21�N7��31������2066��16�Ő������p�E������������22�N3��24����58��2��346�ōT�i���p�c�c�I���G���^�������h���A�E���c�̊����̊֘A���Ǝ҂Ɏx���������|�ϑ����̈ꕔ�Ȃǂ��ېőΏۂƂȂ���۔�Ƃ������̏����̎���������߂��i�ׂŁA�����͓K�@�ł���Ƃ��ꂽ����B |
| MOSH�ЁESTAND�Ў����E�����n���ߘa5�N5��12���ߘa��(�s�E)607��614��(�ꕔ�F�e�A�ꕔ���p) ���|�@�u�ʑ��@�Q�R���P���Ɋ�Â��X���̐����́A�[�Ŏ҂̒�o�����[�Ő\�����ɋL�ڂ����ېŕW�����Ⴕ���͐Ŋz���̌v�Z�����łɊւ���@���̋K��ɏ]���Ă��Ȃ��������Ɩ��͓��Y�v�Z�Ɍ�肪���������Ƃɂ��A���Y�\�����̒�o�ɂ��[�t���ׂ��Ŋz���ߑ�ł���ꍇ���ɁA�[�Ŏ҂��A�Ŗ������ɑ��A���Y�\�����ɌW�鍑�ł̖@��\����������T�N�ȓ��Ɍ����Ă��邱�Ƃ��ł�����̂ł���B�����R���́A�X���̐��������悤�Ƃ���҂́A���̐����ɌW��X���O�̉ېŕW�������͐Ŋz���A���Y�X����̉ېŕW�������͐Ŋz���A���̍X���̐��������闝�R�A���Y�X���̐���������Ɏ���������̏ڍׂ��̑��Q�l�ƂȂ�ׂ��������L�ڂ����X���̐�������Ŗ������ɒ�o���Ȃ���Ȃ�Ȃ��|�K�肵�A���̍X���̐��������闝�R���A�ېŕW�����鏊�����ߑ�ł���Ȃǂ̂Ƃ��́A���̗��R�̊�b�ƂȂ鎖�����ؖ����鏑�ނ��X���̐������ɓY�t���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ��Ă�����̂ł���i�ʑ��@�{�s�߂U���Q���j�B �@�����āA�\���[�ŕ����ɂ�鍑�łɌW��Ŋz�́A���̌�ɍX��������Ȃ�����A�[�Ŏ҂̔[�Ő\���̂Ƃ���m�肷����̂ł��邱�ƁA�[�Ő\���̑O��ƂȂ��������W�y�т�������ł���Ƃ��鎖���W�͍X���̐���������[�Ŏ҂��n�m���Ă��邱�Ƃ���ʓI�ł��邱�ƂȂǂ̎���ɏƂ点�A�X�������ׂ����R���Ȃ��|�̒ʒm�����̎���i�ׂɂ����ẮA�X���̐����ɌW�鎖���W�͔[�Ŏ҂��錴���ɂ����Ď咣�A�����ׂ����̂Ɖ�����̂������ł���B�v �u�d�œ��ʑ[�u�@�U�P���̂S��S���́A���۔�̈Ӌ`�ɂ��āA���۔�A�ڑҔ�A�@����̑��̔�p�ŁA�@�l���A���̓��Ӑ�A�d���悻�̑����ƂɊW�̂���ғ��ɑ���ڑҁA�����A�Ԉ��A�������̑������ɗނ���s�ׂ̂��߂Ɏx�o������̂������Ƃ��A�����P���́A���̂悤�Ȍ��۔�ɂ��ẮA�����Ƃ��ď����̋��z�̌v�Z��A�����̊z�ɎZ�����Ȃ��|�K�肵�Ă���i�����s�Z�����x�j�B �@�����Ƃ��A�@�l���x�o�������۔�̊z�̂����u�ڑ҈��H��v�̊z�̂P�O�O���̂T�O�ɑ���������z���Ȃ������̋��z�i�T�O�������Z���j�A�y�ђ����@�l�ɂ����ẮA�T�O�������Z���ɑウ�āA�x�o�������۔�̊z����z�T�����x�z�ł���N�W�O�O���~���Ȃ������̋��z�ɂ��ẮA�����s�Z�����x�̓���Ƃ��āA�����̊z�ɎZ�����邱�Ƃ��ł���Ƃ���Ă�����̂ł���i�����@�l�����Z������j�B �E�@�����ŁA�{���e�x�o�ɂ��āA�����s�Z�����x�ɑ����L����Ɋ�Â������̊z�ɎZ�����邱�Ƃ��ł��邩��������ɁA�T�O�������Z���̑ΏۂƂȂ�u�ڑ҈��H��v�Ƃ́A���۔�̂������H���̑�����ɗނ���s�ׂ̂��߂ɗv�����p�ł����āA�u�ڑ҈��H��v�ł��邱�Ƃɂ��āA�����茳�����̒��돑�ނɁA�@���Y���H��ɌW����H���̂������N�����A�A���Y���H��ɌW����H���ɎQ���������Ӑ�A�d���悻�̑����ƂɊW�̂���ғ��̎������͖��̋y�т��̊W�A�B���Y���H��ɌW����H���ɎQ�������҂̐��A�C���Y���H��̊z���тɂ��̈��H�X�A�����X���̖��̋y�т��̏��ݒn�A�D���̑����H��ł��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ��邽�߂ɕK�v�Ȏ����i�ȉ��u�{���L�ڎ����v�Ƃ����B�j���L�ڂ���Ă��邱�Ƃ��v���Ƃ���Ă�����̂ł���B �@�������Ȃ���A������̑����茳���ɂ����āA�{���e�x�o�Ɋւ���L�A����D�܂ł̖{���L�ڎ������L�ڂ���Ă��邱�Ƃ�F�߂�ɑ����؋��͂Ȃ��A����炪�u�ڑ҈��H��v�ɊY������ƔF�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B �G�@��������ƁA�{���e�x�o�ɂ��ẮA�����炪����������{���̊z���P���~�ȉ��̒����@�l�ł��邱�Ƃ��炷��ƁA�T�O�������Z���ɑウ�āA�{���e�x�o�������@�l�����Z������̑ΏۂƂȂ���۔�ɊY�����邩�ۂ��ɂ��āA�������邱�Ƃ�v���邱�ƂɂȂ�B�v |
�@���9-7-20(��r�s���̌��۔)�@�@�l�����۔�A�@����A�ڑҔ�̖��`�������Ďx�o�������K�ł��̔�r�����炩�łȂ����̂́A�����̊z�ɎZ�����Ȃ��B
�ʒB�͖@�K�͐���L���Ȃ�������߂̍����Ƃ͂Ȃ�Ȃ����Ƃ��Ċm�F�B
�Ƃ���ŁA�ٔ��Ŕ�r�𖾂炩�ɂ��锽�͋�����邩�Hbc
5.2.3.5.d. �������^
| 6�Ł�112.01���߂ւ̈ϔC ���������E��㍂�����a43�N6��28���s�W19��6��1130��bg �����E���_�@������Ђł���w�Ђ��g�p�l���������ł���`�a�b�c��4���Ɏg�p�l���ܗ^�Ƃ��đ��z�̋������x�������B�x�Ŗ������́A���Y�����͖����ܗ^�ł����đ����Ƃ͔F�߂��Ȃ��Ƃ����B�����A�����ܗ^�̐Ŗ���̈����ɂ��Ă͎{�s�K��(����)�ŋK�肳��Ă������A�w�́A���@84���ᔽ�ł���A�@�l�Ŗ@�̈ϔC�͈̔͂��Ă���(���ېŗv���@����`�ᔽ)�A�Ǝ咣�����B ���|�@�x�́A���̐��߂��@�l�Ŗ@9��1��(����)�́u���ߋK��ł���Ǝ咣���Ă���v���A�����u�ɂ͂��̉��ߋK���݂��邱�Ƃ𖽗߂ɈϔC����Ƃ̕����͂Ȃ��B���������āA�x�̎咣�͓���̗p�ł��Ȃ��B�v �@�u�d�Ŗ@����`�̌�������A�@�������߂ɈϔC����ꍇ�ɂ́A�@�����̂���ϔC�̖ړI�A���e�A���x�Ȃǂ����炩�ɂ���Ă��邱�Ƃ��K�v�ł���A�����v���ւ̎Z���s�Z���Ƃ������ېŗv���ɂ��āA�@���ŊT���I�A���n�I�ɖ��߂ɈϔC���邱�Ƃ͋�����Ȃ��v�B �@�u�g�p�l�����c�Ɏx�������ܗ^�̂����A�g�p�l�Ƃ��ĐE���̑Ή��Ƃ��Ďx������镪�́A�����̐�����L���A�]�����痝�_���������������Ƃ��Čo�����ׂ����̂Ƃ���A������Ђɂ����Ă����f�ł������v�A�܂��A�u������Ђɂ��ẮA�ʂɋ��@31����3(���@132��)�ɓ����۔F�̋K�肪����A���ۓI��ʓI�łȂ��A��̓I�ʓI�ɓ�����Ђł��邽�߂ɋN�菟���ȕs���ȍs�v�Z���۔F���ꂽ�v�B �@�u�Ȃ�قǁA������Ђł́c�����̌o����̕s�����s�Ȃ���v���A������Ƃ����āu�����W�҂̂��ׂĂ��c��Ўx�z�ɑ傫�ȉe���͂�����킯�ł͂Ȃ��v�B ���@�l�Ŗ@9��1���E8��(����)�ƋK��(����)�̋K��̓��e�̐��� ���s�����߂ւ̈ϔC�ɂ��Ă̈�R�ƍT�i�R�̔�r �@��R�u�v����ɐV���ȑd�ł�݂���Ɠ���̌��ʁv �@�T�i���R�u���ߋK��ł����āc�n�ݓI�ɒ�߂�ꂽ�K��ł͂ȁv���B �@�T�i�R�u�@�����̂���ϔC�̖ړI�A���e�A���x�Ȃǂ����炩�ɂ���Ă��邱�Ƃ��K�v�v�B�u�ېŗv���ɂ��āA�@���ŊT���I�A���n�I�ɖ��߂ɈϔC���邱�Ƃ͋�����Ȃ��v ���������p�Ƃ���Ă�����̂̑����Z����ے肷�邱�Ƃ��זړI�Ƃ����邩�H ����ʓI�E�����I�ϔC�ł����߂̓��e���Ó��Ȃ�Ηǂ����H�\�\�d�Ŗ@����`(�̒��̉ېŗv���@���`)�̈Ӌ`�A���Ȃ킿�����`�̈Ӌ`���ǂ������邩�A�̖��B(cf.�o�^�Ƌ��Ők�Г��᎖���E�_�˒n������12�N3��28����48��6��1519�ŃP6��29��{���̌���㍂������12�N10��24����48��6��1534�ŁE�Ŕ�����17�N4��14�����W59��3��491�ŕS�I7��122�s���S�III8��155ao�c�c�ߑ�ɓo�^�Ƌ��ł�[�t���ēo�L�������҂��o�^�Ƌ��Ŗ@31��2��(����14�N�����O)����̐����̎葱�ɂ��Ȃ��ʼnߌ�[���̊ҕt�𐿋����邱�Ƃ̉�})[���]���g���Ó��ȑd�ł̋K����A�����J�l����߂��Ƃ��āA�K�肪����Ήېŗv�����m��`�̖��i���R��`���炭��\���\���̖��j�͐����Ȃ����A���e�Ɋւ��Ă��A��������������{�̍�����A�����J�l�̕��������I�ȑd�ł̋K�������Ă���邩������Ȃ��B�������A�d�Ŗ@�͐����I�����̉ʂĂɂł�����̂ł���A�Ƃ����_�͋��炭�ʼn߂ł��Ȃ��B���߂̏ꍇ�́A�����Ɏ������邩�ǂ����Ƃ������B ���u�ϔC���߂̑̌n�݂̂���_���I�ɓ����o�����Ƃ��ł��邩�v�u���炩�̊�b�I�ȍl�����ɏƂ炵�Ď��Ă����f����Ă���ƍl����ׂ����v�\�\�_���̌n�݂̂Ȃ炸�A��v�ɂ����鈵���ȂǁA�w�i������l������邩�H�Ⴆ�A��v�ɂ����Ė����ܗ^���������p�Ƃ���Ă��Ȃ������Ƃ�����A���̑����Z����ے肷�鐭�߂��d�Ŗ@����`�ᔽ�Ƃ��ꂽ���ǂ����H ��������Ђ̍s�ׁE�v�Z�̔۔F�K�肾���ł͑Ώ��������������c�c�Łu���S��s���Ɍ���������v�ꍇ�ɖ{���������邩�H�@��p�����F�߂���������^�̑����Z�����@132���Ŕ۔F���ꂤ�邩�H[���]�Łu���S��s���Ɍ���������v�ꍇ�c�c��p�łȂ����̂��p�ł���Ƃ��đ����ɂ��邱�ƂȂǂł��낤���A�����Ɏx�����������̂ǂ̕������ł́u���S��s���Ɍ���������v�����ł���̂��A�܂�ǂ�����ǂ��܂ł���p�łǂ����炪��p�łȂ��Ȃ�̂��A�݂Ȃ��K��Ȃ��ɑΏ�����͓̂���낤�B�܂��A�{���̂悤�ɔ�p�����F�߂���Ƃ��ꂽ�����ɂ��ẮA�Ȃ�����۔F���������낤�B |
| 6�Ł�113.01�ے��D�H������Ў����E���É��n������6�N6��15������2(�s�E)5����41��9��2460�Ŋ��p�E���É���������7�N3��30������6(�s�R)21���Ŏ�208��1081�Ŋ��p�E�Ŕ�����9�N3��25������7(�s�c)110���Ŏ�222��1226�Ŋ��p�m��ap�c�c�ېŗv�����m��`(��2.2.1.1.b)���s�m��T�O�Ƃ̊W�ɂ��� �u�@�l�Ŗ@�O�l���ꍀ�̋K��̎�|�A�ړI�y�і@�l�Ŗ@�{�s�ߘZ����ꍆ�̋K����e�ɏƂ点�A�@�l�Ŗ@�O�l���ꍀ����́w�s�����ɍ��z�ȕ����̋��z�x�̊T�O���A�s���m�Ŕ��R�Ƃ��Ă���Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ�����A���_�ጛ�̎咣�y�ѓ��������肵�ĉ��߂��ׂ��ł���Ƃ���咣�́A���̑O��������A�������ɏ��_�̈�@�͂Ȃ��A�_�|�́A�̗p���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�v |
��Ђ̗��v������ɔz���Ƃ����`�Ŕz��Γ�d�ېł��N����B�����ɑ����V�Ƃ����`���Ȃ�A�@�l�i�K�ł̉ېł�����ł���B�����������͖@�l�ɑ���ʏ]�ƈ��Ƃ͈قȂ����ȊW�ɂ���B(���Ė����ܗ^�����v�̏����ƍl�����Ă������A�������萷��h�~�̈Ӗ�����)
���@�ō����t�������m���B
�@��34��(�������^�̑����s�Z��)�@�����@�l�����̖����ɑ��Ďx�����鋋�^�c�c�̂������Ɍf���鋋�^�̂�����ɂ��Y�����Ȃ������̊z�́A���̓����@�l�̊e���ƔN�x�̏����̋��z�̌v�Z��A�����̊z�ɎZ�����Ȃ��B
�@��@���̎x���������ꌎ�ȉ��̈��̊��Ԃ��Ƃł��鋋�^�i�����C�ɂ����āu������^�v�Ƃ����B�j�œ��Y���ƔN�x�̊e�x�������ɂ�����x���z�����z�ł�����̂��̑�����ɏ�������̂Ƃ��Đ��߂Œ�߂鋋�^�i�����ɂ����āu������z���^�v�Ƃ����B�j
�@��@���̖����̐E���ɂ�����̎����ɁA�m�肵���z�̋��K���͊m�肵�����̊����c�c�Ⴕ���͐V���\�Ⴕ���͊m�肵���z�̋��K���ɌW���\�l���ꍀ�c�c�ɋK�肷�������n�����t�����Ⴕ���͑�\�l���̓��ꍀ�c�c�ɋK�肷�����V���\����t����|�̒�߂Ɋ�Â��Ďx�����鋋�^�ŁA������z���^�y�ыƐјA�����^�̂�����ɂ��Y�����Ȃ����́c�c
�@�@�C�@���̋��^��������^���x�����Ȃ������ɑ��Ďx�����鋋�^�c�c�ȊO�̋��^�c�c�ł���ꍇ�@���߂Œ�߂�Ƃ���ɂ��[�Œn�̏����Ŗ������ɂ��̒�߂̓��e�Ɋւ����͏o�����Ă��邱���B�m���O�m��͏o���^�n
�@�@���@��������t����ꍇ�@���Y�������s�ꉿ�i�̂��銔�����͎s�ꉿ�i�̂��銔���ƌ�������銔���i�c�c�u�K�i�����v�Ƃ����B�j�ł��邱�ƁB
�@�@�n�@�V���\����t����ꍇ�@���Y�V���\�����̍s�g�ɂ��s�ꉿ�i�̂��銔������t�����V���\���i�c�c�u�K�i�V���\�v�Ƃ����B�j�ł��邱�ƁB
�@�O�@�����@�l�c�c�����̋Ɩ����s�����c�c�ɑ��Ďx�������ƐјA�����^�ŁA���Ɍf����v���������́c�c�m�C�`�����n
�Q�@�����@�l�����̖����ɑ��Ďx�����鋋�^�c�c�̊z�̂����s�����ɍ��z�ȕ����̋��z�Ƃ��Đ��߂Œ�߂���z�́A���̓����@�l�̊e���ƔN�x�̏����̋��z�̌v�Z��A�����̊z�ɎZ�����Ȃ��B�m3���ȉ����n
�u�����ܗ^�v�Ƃ������t�͂Ȃ��Ȃ������A��ӂƂ��Ă͑����Z���ł��Ȃ����Ƃ�����Ƃ������ƁB
����(�@��2��15��)��g�p�l(�ߑ�ȏꍇ)�ɂ����鋌34���`36����3�̋K�肪�A�V34���`36���ւƐ������ꂽ�B
���Ă��ƐјA���^��V������Ɏx�����Â炢�Ƃ����ᔻ�����������A���v�A�����^�̂�������̗v���������̂ɂ��Ă͑����Z�����F�߂���悤�ɂȂ����B
| 6�Ł�325.01�O�a�N���G�[�V����������Ў����E�����n������24�N10��9������23(�s�E)652����59��12��3182�ŕS�I7��60�E������������25�N3��14����59��12��3217��(��ȏ͔@�E����ŗ�2014�N7��11��44-49�ŁA�n�ӓO��E�W�����X�g1480��127-130��) ���O�m��͏o���^�Y�����͌��������f�����B(�ޗ�c�c�����n������26�N7��18������24(�s�E)536�����p) cf. ������Ѓz�N���N�����E�����n���ߘa6�N2��21���ߘa4(�s�E)566�����p�E���������ߘa6�N10��2���ߘa6(�s�R)93�����p�c�c�͏o�ƈقȂ�z���x�������ꍇ�͎��O�m��͏o���^�ɓ�����Ȃ��B |
| 2�Ł�325.01�����R��ʊ�����Ў����E(�����n������6�N11��29������4(�s�E)83���E������������8�N3��26������6(�s�R)217���E)�Ŕ�����10�N6��12������8(�s�c)138������1648��53�ŕS�I4��110��aq �����E���_�@�������Ƃ��ď��a51�N�AX��Ђ����̎�����EA����y�n�E�������w���B�{�����n�Ƃ��ď��a62�N�AA�̑ސE�ԘJ���̈ꕔ�Ƃ��Ė{���y�n�����뉿�z(��2500��)�Ō����x���B����ɂ��A�X���������Ƃ��āAY�Ŗ������́A�{���y�n�̎����͖�1.6���~�ȏ�Ƃ��A���n�v��X�̉v���Ɍv��B ���|�@�u�㍐�l�́A�ސE���������ɑ���ސE���^�̎x���Ƃ��āA�㍐�l�̌Œ莑�Y�ł���y�n�����̒��뉿�z�ł����܁Z�Z���~�ŏ��n���A�E���n�ɌW�鎖�ƔN�x�̊m�肵�����Z�ɂ����Ă��̎|�̌o�����������A�E�y�n�̉E���n���ɂ�����K���ȉ��z�͏��Ȃ��Ƃ��ꉭ�Z�Z�O���l�O�Z�Z�~��������̂ł͂Ȃ������Ƃ����̂ł��邩��A�E�����W�̉��ɂ����ẮA�E�y�n�̏��n���ɂ�����E�K���ȉ��z�ƉE���뉿�z�Ƃ̍��z�͖@�l�Ŗ@�O�Z���ɂ��������o�������Ȃ��������z�ɊY������Ƃ������R�̔��f�́A�����v�B �����o����v�����闝�R�\�\��p�ł���Ƃ����ӎv�\��(�����I�ɂ��O���I�ɂ�)�B�܂��A�����̓K���Ȕc���̂��߁B�����22��4���������Ó��ȉ�v�����̊�ɏ]�����Ƃ�v�������|�ɂ��Y���B(�A�����ݑ����o���͗v������Ă��Ȃ�) A�̉ېŁ\�\���Ȃ��Ƃ�1.6���~�̑ސE��������������̂Ƃ��ĉېł����B ���������ꍇ�\�\���@�ɒ����ɍl����A�k����X����A�ւ̓y�n�̈ړ]���Ȃ��������ƂɂȂ�̂ŁAX�ɏ��n�v�͔�������X�ւ̍X�������͕s���ƂȂ�AA�̑ސE��������͖{���y�n�����̊z�̕��͈�����ĉېŏ������Čv�Z����A�X���̐��������邱�ƂɂȂ�B�A���o�ϓI���ʑr���v����[�����ƔF�߂��Ȃ��B 22��2���v���F����1.6���~�ŏ��n�����Ƌ[���B���n�v1.35���~�����B 22��3�������E34���F1.6���~�����̖������^�̂����u�s�����ɍ��z�ȕ����v�̑����Z���s�B�{���ł͑����o�����Ă��Ȃ������i1.35���~�j�̑����Z�����F�߂��Ȃ��B A�ɂ������ېł��Ȃ����̂ŁA�@�l�E�l�̓�d�ېł��������邱�Ƃɂ����ӁB |
| �����n���ߘa5�N3��23���ߘa2(�s�E)456������1675��24��(���p)(���{���G�E�W�����X�g1590��10�ŁA�R�c�����E�d��2024�N6��21���A���q�F�T�E�d�ői��17��101��)�E���������ߘa6�N1��18���ߘa5(�s�R)112������1693��36��(���p)(���m��)�c�cX��(����)�͖��X���̐����A���A�̔�����ړI�Ƃ�������@�l�ł���BX�Ђ��{���e����(���Y�A���Y�A�Ԏq��3�l�B3�l�͌Z��)�Ɏx�������������^�̂����s�����ɍ��z(�@�l�Ŗ@34��2��)�ȕ����͑����ɎZ���ł��Ȃ��Ƃ����O��œ��R�Ŗ��������X���������������B �@���|�@�u���R�Ŗ������́A�����Q�T�N�X�����@�l�ōX�������Ȃ��������Q�W�N�X�����X�������ɂ����āA���Y�y�ю��Y�̓K�����^�z���Z�肷��ɓ�����A�{���ގ��@�l�̖������^�ō��z�̕��ϊz�ɁA���㍂�A����c�Ɨ��v�y�ьl���Z���������Ă��ׂ��v�f�Ƃ��ē����̏d�݂Â������ď悶�ĎZ�o������@�i�{���Z���j�ɂ��K���Ȗ������^�z���Z�肵�����̂ł���B�{���Z���ɂ����Ė{���ގ��@�l�̖������^�ō��z�̕��ϊz����l�Ƃ��ꂽ���Ƃɂ��ẮA���Y�y�ю��Y�������̑�\����L���������ł��������ƁA�����̎��Ɠ��e�i�F�莖���A�i�C�j�j�y�ь����̎��v�i�F�莖���C�j�Ɋӂ݂�ƁA�����I�Ƃ�����B�����āA���Y�������̔��グ�邽�߂ɉʂ������E�ӂ�B�������Ɛсi�F�莖���A�y�уC�j�Ɋӂ݂�ƁA���R�Ŗ��������A�{���ގ��@�l�̖������^�ō��z�̕��ϊz�Ɉ��̉��d�����邱�Ƃ������ł���Ɣ��f���āA�����Ɩ{���ގ��@�l�Ƃ̊Ԃɑ�����������邽�߂ɁA�@�l�Ŗ@�{�s�߂V�O���P���C�ɂ����ēK�����^�z�̔��f�v�f�Ƃ��ċK�肵�Ă���u���ƋK�́v�̎w�W�ɓ�������̂Ƃ��Ĕ��㍂�A�u���v�v�ɓ�������̂Ƃ��ĉ���c�Ɨ��v�y�ьl���Z�����i������Ђɂ���������I�ȏ������z�Ɖ������B�j�����ėv�f�Ƃ��čl�������{���Z����p���ĎZ�o�������Ƃ͍����I�ł���A�Ԏq�������̔��グ�邽�߂ɉʂ������E�ӂ�ƐтɊӂ݂�ƁA�Ԏq�ɂ��Ă��A���l�ɁA�{���Z����p����̂������ł���B���������āA���Y�y�щԎq�ɂ��ẮA�{���Z���ɂ��Z�o�������z���K�����^�z�ɊY�����A���������z���u�s�����ɍ��z�ȕ����̋��z�v�ɊY������ƔF�߂�̂������ł���B �@����ɑ��A���Y�ɂ��ẮA�����Q�V�N�P�P���܂ł͌����̋Ɩ���S���Ă��炸�A�������狋�^�̎x��������Ă��������Q�V�N�P�Q�����畽���Q�W�N�R���܂ł̂S�����Ԃɉʂ������E���̓��e���Ɋӂ݂Ă��A�{���ގ��@�l�̖������^�ō��z�̕��ϊz�Ɉ��̉��d�����邱�Ƃ������Ƃ͔F�߂��Ȃ��B���������āA�{���ގ��@�l�̖������^�ō��z�̕��ϊz�̂S�������i�R���̂P���悶�����z�j���K�����^�z�ɊY�����A���������z���A�u�s�����ɍ��z�ȕ����̋��z�v�ɊY������ƔF�߂�̂������ł���B�v |
5.2.4. �������̌J�z�T���E�J�߂��ҕt(�@��57���A58��)(��4.6.4.������)
| ��325.05�s�c�d����������E�Ŕ����a43�N5��2�����W22��5��1067�ŕS�I3��44et�c�c�@�l�Ŗ@57��(���@�l�Ŗ@9��5��)����̌������J�z�T�������A���@103��(����17�N�����O)����̍����@�l�ɏ��p�����ׂ��퍇���@�l�́u�����v�Ɋ܂܂��A�Ƃ����w���i������l�i���p���F�����Y�A�k��O�v�j�����������̂́A����͏��ɐ����̗p�����B �@�Ԏ���Ђ�������Ђ��z������z������(�������t�������ɂ��Ċ�����ЃT���G�X�����E�L���n������2�N1��25���s�W41��1��42�ł͖@�l�Ŗ@132��1��(������Ѝs�v�Z�۔F�K��)�ɂ�茇�����J�z�T����۔F�����B �@����13�N������̖@�l�Ŗ@57��2���͓K�i�������̌������J�z�T�����̈��p��F�߂邱�ƂƂȂ����B�����ɂ��Ē��ˋM�V�w���ƍĐ��ƉېŁ@�R�[�|���[�g�E�t�@�C�i���X�Ɩ@�����_�̓��Ĕ�r�x�i������w�o�ʼn�A2017)�Q�ƁB |
5.3. �o���҂Ƃ̊W�\�\���{�����
5.3.1. ���{������̈Ӌ`(�@��22��5��)
5.3.2. ���`�̎��{�����
5.3.3. ���v�E��]���̕��z��
5.3.3.1. ���v�܂��͏�]���̕��z
| 6�Ł�323.02��������������Ў����E�ő唻���a43�N11��13�����W22��12��2449��nr �����E���_�@���告���Z���c�ފ�����Ђw������Ɏx��������D�ҋ�(������܂��͎ӗ��)�́A���v�z���ɓ�����(�����Z���͔F�߂��Ȃ�)���H��p�Ƃ��ĔF�߂��邩�H ���|�@�㍐���p(�w�s�i)�u������w���v�̏����x�̂��Ƃ����A�N�x���Ƃ̏����z���Z�肳��A�ېł��ꂽ��ɂ͂��߂ĉ\�ƂȂ���̂ł��邩��A�����z�Z��̗v�f�Ƃ��Ă̑����Ɋ܂܂�Ȃ��v �u����ɁA�o�ϓI�����I�ɂ͎��ƌo��ł���Ƃ��Ă��c���̂悤�Ȏ��ƌo��̎x�o���̂��@����֎~����Ă���悤�ȏꍇ�ɂ́A���Ȃ��Ƃ��@�l�Ŗ@��̎戵�̂����ł́A�����ɎZ�����邱�Ƃ͋�����Ȃ��v �{���̂悤�Ɂu��Ђ̌��Z���ɂ��������v�̗L���ɊW�Ȃ��v�x�����悤�Ȏ������B���@�́u���@���������鎑�{�ێ��̌����ɏƂ炵�ċ�����Ȃ��v �u��Ђ��犔�傽��n�ʂɂ���҂ɑ����傽��n�ʂɊ�Â��ĂȂ������K�I���t�́A���Ƃ��A�w�ɗ��v���Ȃ��A���A���呍��̌��c���o�Ă��Ȃ���@������Ƃ��Ă��A�@�l�Ŗ@��A���̐����͔z���ȊO�̂��̂ł͂��蓾���A������w�̑����ɎZ�����邱�Ƃ͋�����Ȃ��B�v �{���̎x�����u�z���Ƃ͂��̐������قɂ��邱�Ƃw�̎咣�̂Ƃ���Ƃ��Ă��A���̂悤�ȋ����̎x���́A�O���̂Ƃ���A�@���㋖����Ȃ��̂ł��邩��c�v �l�@�@�������R(1)��@�Ȏx�o�̑����s�Z��(2)���傽��n�ʂɊ�Â��x��������̂͑S�Ĕz���c�c�ǂ����H �@���c�ӌ��@���傽��n�ʂɊ�Â����K���t�͑S�Ĕz���ł���A��@���͖��W�B �@���씽�Έӌ��@��s�a�����q�Ɠ��l�ł���A���ƌo��ł���B��@���͖��W�B �@�Ƃ���Ŗ{���̒��ڂ̑����́y�����Z���̉ہz���y�z���Y�����z���H�z���Ɨ�����p�Ƃ����I�\���͍̂�Ȃ��̂��H[���]�{������ratio decidendi�������Z���s�������Ƃ���A���́u�z���ȊO�̂��̂ł͂��蓾���v�͖T�_�Ƃ������ƂɂȂ�̂�������Ȃ��B �@��@�x�o�̑����Z������ʂɔے肷���Ƃ������̂肽���Ƃ��A���ꂪ����@���Ƃ��Čł܂��Ă��邩�ɂ��Ă͋^��̗]�n����(cf. 6�Ł�323.03�G�X�u�C�V�[�����E�Ō�����6�N9��16���Y�W48��6��357��)�B�x�o�̈�@���������s�Z���ɒ��������ł͂Ȃ��Ƃ���A�����s�Z����⋭���邽�߂ɔz���ɊY�����Ȃ��Ƃ��������Ȃ邪�A����ƍ��x��6�Ł�221.02�����Z�����E�Ŕ����a35�N10��7�����W14��12��2420��(��4.2.2.1.�z�������̒�`)(��Ђ̑��v�v�Z��̗��v�Ɋ�Â��Ȃ���Δz���łȂ�)�Ɩ{��(���傽��n�ʂɊ�Â��x���͑S�Ĕz��)�Ƃ���������H �@�����͂Ȃ��Ɩ�������������Ȃ�c�c�x���҂Ǝ��l�Ƃœ�����ނł���K�R���͂Ȃ�(?) �@���̌�A���c�ٔ������Ŕ����a45�N7��16���W��100��227�ŏ��a43(�s�c)112���͖��炩�ɔz���͈̖̔͂��i�����Z�̏㍐���R�Ɠ��l�j�Ƃ��Ę_����B |
5.3.3.2. �c�]���Y�̕��z
5.4. �g�D�ĕҁE��ƌ���bv
5.4.1. ��{�I�l����
5.4.1.1. �P�̉ېŌ����Ɗ�ƃO���[�v
5.4.1.2. ���S�x�z�W�E�x�z�W
5.4.1.3. �O���[�v�@�l�Ő��E�A���[�Ő��x�Ƒg�D�ĕҐŐ�
5.4.2. �O���[�v�@�l���E�A���[���x
5.4.2.1. ����
5.4.2.2. �O���[�v�@�l��
5.4.2.1.a �O���[�v�@�l�Ԃ̎��Y���n
5.4.2.1.b �O���[�v�@�l�Ԃ̔z��
5.4.2.1.c �O���[�v�@�l�Ԃ̊�
5.4.2.3. �A���[���x
5.4.2.3.a �A���̊J�n�E�I��
5.4.2.3.b �A���������z����јA���@�l�Ŋz�̌v�Z
5.4.2.3.c �A�������ɂ�鑹�������݂̐���
5.4.2.3.d �����뉿�C��
5.4.3. �g�D�ĕҐŐ�
5.4.3.1. ��{�I�v�f
5.4.3.1.a �x�z�W�p���v��
COLUMN5-7 �X�s���I�t��
5.4.3.1.b ���ƌp���v���E�]�Ǝ҈��p�v��
5.4.3.1.c �����ȊO�s��t�v��
COLUMN5-8 �Ή��v���̊ɘa
5.4.3.1.d �������Ƃ��c�ނ��߂̍����ɂ����Ēlj������v��
| �����O���[�v�{�Њ�����Ў����E�����n���ߘa5�N7��20���ߘa3(�s�E)588��(�F�e�A�m��)(���������Y�E�d��2024�N7��5���A�����ɗ��E�W�����X�g1600��10��) �@�f���[�Ђ̕���25�N12��31�����_�̑ݎؑΏƕ\��̏����Y���v�z�́|4��8824��1430�~�������B���W�e���Ђ̕���24�N2��29�����_(�����͋����g��������)�̑ݎؑΏƕ\��̏����Y���v�z�́|2��9581��4159�~�������B���W�e���Ђ̕M���o���҂͂l�m���e�[���Ђł��莟�_���f���[�Ђ������B���W�e���Ђ͑g�D�ύX�ɂ�蕽��26�N2��1���Ɋ�����ЂɂȂ����B �@�f���[�ЁA�l�m���e�[���Ћy�яt�Ⴓ�ԁ[��Ђ�3�Ђ́A����26�N2��3���A���W�e���Ђɑ��Ă��ꂼ�ꂪ�L���Ă����e�����͋��ɌW����̊z�������o�����A���W�e���Ђ�3�Ђɑ��đ�O�Ҋ��������ɂ�蕁�ʊ����s�����idebt equity swap�B�u�{��DES�v�j�B �@�f���[�Ђ́A����26�N2��10���A���Ɗ֘A�����`���i�u�{�����p���Y���v�j�����W�e���Ђɏ��p������Ƃ����z������������|�̌_�����������B���W�e���Ђ̓f���[�Ђɕ��ʊ���9083���s�����B�f���[�Ђ͕���26�N12��31���ɉ��U�����B����26�N12�����̃f���[�Ђ̐\���ɂ����āA�{���������@�l�Ŗ@62����3��1���̓K�i���Ќ^�����ɊY�����邱�Ƃ�O��Ƃ��A���n���v���v�サ�Ă��Ȃ�����(�����������͑i�ׂɂ����đg�D�ĕ҂̓K�i�����咣���Ȃ�����)�B�f���[�Ђ͕���27�N12��1���Ɍ���(X�ЁB�����O���[�v�{�Њ������)(�f���[�Ђ̊��S�e���)�ɋz���������ꂽ�B �@�Ŗ������́A�f���[�Ђ̕���26�N12�����̏����v�Z�Ɋւ��A�������̖{�����p���Y���̉��z��6��0132���~�i���뉿�z2598��6096�~�j�ł���ƎZ�肵�A�K�i���Ќ^�����ɊY���������n���v���v�シ��K�v������A�Ƃ����B �@���|�@�u�@�l�Ŗ@�U�Q���P���́u�������p�@�l�ɓ��Y�ړ]���������Y�y�ѕ��̓��Y�i�����j�����̎��̉��z�v�Ƃ́A�������ɂ����鎞�����������̂Ɖ����ׂ��Ƃ���A�����Ƃ́A���Y�̋q�ϓI�Ȍ������l���������̂ł���A���ꂼ��̍��Y�̌����ɉ����A�s���葽���̓����ҊԂŎ��R�Ȏ�����s����ꍇ�ɒʏ퐬������ƔF�߂��鉿�z���������̂Ɖ�����A�ېł̖��m����������m�ۂ���ϓ_����́A���̋q�ϓI�Ȋ�ɂ���ĎZ�肳�ꂽ���z�ł��邱�Ƃ��v�������Ƃ����ׂ��ł���B�v �@�u�{�����ƌv��̓��e�ɍ������E�q�ϐ�������Ƃ͂�����A�{�����l�Z��̉ߒ����_�����E�q�ϐ����S�ۂ��ꂽ�����Ȃ��̂ł������Ƃ������Ƃ͂ł����A���̑��A�{�����p���Y���̎������U���O�P�R�Q���~�ƎZ�肵�����Ƃ������I�ł���ƔF�߂�ɑ����؋��͂Ȃ��B�܂��A�{���ɂ����Ă͊Ӓ肪���{����Ă��炸�A�{���S�؋��ɂ���Ă��A�c�b�e�@�ɂ��A�{���������̖{�����p���Y���̉��z�̎Z����s���̂ɕK�v�Ȑ��l���m�肷�邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�v �@�u�{���ɂ����ẮA�{���Œ�o����Ă���؋��Ɋӂ݁A�{�����p���Y���̎������A�v���[�^�X�̏�L�ӌ����̕]���z�̏���ł���P�V�Q�X���T�O�O�O�~�ƔF�߂�̂������ł���B�v |
5.4.3.2. �������̈��p��
5.4.3.3. ����i�K�̉ې�
5.4.4. ��I�۔F�K��
5.5. �@�l�Z���ŁA�@�l���Ɛł���ђn���@�l���ʐ�
5.5.1. �@�l�Z����
5.5.2. �@�l���Ɛ�
5.5.3. �n���@�l���ʐ�(�n���@�l���ʏ��^��)
6. �����
6.1. ����ېł̓����ƕ���
6.1.1. �l�X�ȏ���ې�
6.1.1.1. ���ڏ���łƊԐڏ����
���������:������s�����҂ɒ��ډېŁB�S���t�ꗘ�p�ŁA�����œ��B�Ԑ������:�[�ŋ`���҂�����҂ƈقȂ邪����҂ɑd�ŕ��S���]��(��2.2.4.2.)����邱�Ƃ��\�肳���B���{�̏����(��q�̕t�����l��)�B
6.1.1.2. �ʏ���łƈ�ʏ����
������ŁF�ېł̑ΏۂƂ��ꂽ���i�E�T�[�r�X�ɑ��Ă̂݉ېŁB��ŁE�����ŁE�K�\�����œ��B�������ŁF�����Ƃ��đS�āi��ېłƂ���Ȃ�����j�̏��i�E�T�[�r�X�ɑ��ېŁB���{�̏���Ŗ@���B
6.1.1.3. �P�i�K����łƑ��i�K�����
�P�i�K����ŁF�������珬���Ɏ���i�K�̂����̈�ł̂݉ېł���B�A�����J�̏�������œ��B���i�K����ŁF�������珬���Ɏ��镡���̒i�K�ʼnېł���B�����̕t�����l�œ��B
6.1.2. �t�����l�ł̊�{�I�\��
6.1.2.1. ������łƕt�����l�ł̔�r
| �Ő� | ���� | ������� | ����� | �t�����l�� | �ȈՂa80�� | invoice�a5% | ��������a5% |
| �_�� �` |
2000 | 2000�~1.1 =2200��200 |
2000 ��0 |
2000�~1.1 =2200��200 |
2200 ��200 |
2200 ��200 |
2200 ��200 |
| ���� �a |
6000 | (2200+4000)�~1.1 =6820��620 |
6000 ��0 |
6000�~1.1=6600 ��600-200=400 |
6600 ��600-480=120 |
6300 ��300-200=100 |
6300 ��300-200=100 |
| ���� �b |
7000 | (6820+1000)�~1.1 =8602��782 |
7700 ��700 |
7000�~1.1=7700 ��700-600=100) |
7700 ��700-600=100 |
7700** ��700-300=400 |
7700*** ��700-573*=127 |
*�a����̎d���z6300�Ȃ̂�6300�~10/110��573�B
**�a���b�����300�l�����肵�Ă���̂ŁA�b�̔����7700-300=7400�ƂȂ�Ƃ��l���邱�Ƃ��ł���B���̏ꍇ�A7400�~10/110=673�Ȃ̂łb�[�Ŋz��673-300=373�Ƃ��l������B
***��**�Ɠ��l�ɂb�̔��オ7400�ƂȂ邱�Ƃ��l������B���̏ꍇ�̂b�[�Ŋz��673-573=100�B
���ł̐��E�Ŕ_�Ƃ`���d������(��n�Ƒ��z�̌b�݂���)�ŕĂ����A�`���Ă���݉��a��2000�Ŕ���A�a�����݂����A�����Ǝ҂���b�ɐ��݂�6000�Ŕ���A�b�͏���҂c��7000�Ő��݂�A�Ƃ������l����B���ɁA��3��A��4��A��5��̂悤�ȏ����(������ŗ���10%�Ƃ���B)���������ꂽ�Ƃ��A�v�Z�̕X�̂��ߏ���ł͑S�ē]�ł������҂ɋA������Ƒz�肷��i���̑z��͌����̎s��ɑ����ĂȂ���6.4.6.�B�����܂Ő����̕X�̂��߁j�B
| ��6��(�ȈՂa80%)(��6.2.4.2.c)�A��7��(invoice�a5%)(��6.3.3.2.)�A��8��(��������a5%)(��6.4.4.2.a) |
��3����������F�e����i�K�̔���ɑ����̔�����z���ېŕW���Ƃ��ĉۂ��Bturnover tax
��4������������F�����Ǝ҂ɑ����̔�����z���ېŕW���Ƃ��ĉۂ��Bretail sales tax
��5���t�����l���F�e����i�K�̎��Ǝ҂ɑ����̕t�����l���ېŕW���Ƃ��ĉۂ��Bvalue added taxhs
������ł̔���:�ŕ��S�̗ݐ�(�J�X�P�[�h����)(cascade effect)����Ƃ̐����I���������I�ɗL���ɂȂ�B��Ƃ̐����I�����ɒ����I�ȕt�����l�ł̊̂��d���Ŋz�T���ł���B
�@��������ł��t�����l�ł�(���z�I�Ɏ��s�����Ȃ��)��Ƃ̐����I�����ɑ������I�B
�@(���W�F��������������ł̉��Ŏ��ۂɂ͑Ώ���Ҏ���ƑΎ��ƎҎ���Ƃ̋�ʂ����ƂȂ�A�ł̗ݐς������ɂ͐����Ă��܂��Ă���B�A�����J�ŏ�������ł��̗p����Ă�����̂́A�A�����J�̌����҂��A�����J�̎d�g�݂̓}�Y���̂ŕt�����l�ł����ׂ��ł���Ǝ咣���Ă���̂��吨�ł���B������ł����łȂ���������ł����E�I�ɂ͒x�ꂽ�Ő��ł���Ƃ����������m�����Ă���B�ł͂Ȃ��A�����J�͕t�����l�ł��ł��Ȃ��̂��H[���]�n��������A�����ƕM���������A�A�M���@���������Ȃ���Ȃ�Ȃ����A�M���@�����̌����݂������Ȃ�����B�ł�������Ă���ς�A�n��������A�ƕ]���Ă�����ˁB)
6.1.2.2. �t�����l�Ƃ͉����H
|
�@�@�@�J���ҁ@�@�s���Y�����L�� �@�@�@�@�b���@�@�n���b�y�n �@�@�@�J�b�b���@��b�b���� �@�@�@���b�b���@���b�b�@�B�ݔ� �@�@�@�@���b�@�@�@�b�� �d���@�@���������������@�@�̔� �\�\�\�����@���Ǝҁ@���\�\�\�\���@�w���� ���\�\�\�����������������\�\�\�\�@ �d���@�@���b�z�@�@�b���@�@�@���� �@�@�@�o�b�b���@���b�b�� �@�@�@���b�����@�q���b�t �@�@�@�@����@�@�@���� |
6.1.2.2.a �T���@�Ɖ��Z�@�T���@:���Ƃ̑�������z����A������w�������y�n�E�����E�@�B�ݔ��E���ޗ��E���͓��ɑ���x�o���T���������z�B���Z�@:�����E�n��E���q����ъ�Ɨ��������v�������z�B �i�T���@�Ɖ��Z�@�͌v�Z���@���Ⴄ�����ŁA���e�͓����ł���j 6.1.2.2.b �t�����l�ł̎O�ތ^����^�t�����l:�@�B���ɂ��Ă������T����C=GDP-I(����=���������Y-����)�����^�t�����l:�@�B���ɂ��Ă͌������p��NDP=GDP-�������p(net domestic product���������Y) ����^�t�����l:�@�B���ɂ��Ă͍T���s��GDP(gross domestic product���������Y) |
6.1.2.3. �t�����l�ł̎��s��mq
6.1.2.4. ���ۓ�d�ېŔr���̕���
���Y�n��`�ł͎��̂悤���ŗ��̈Ⴂ�ɂ�������������c�߂��Ă��܂��Bli| �� | ���{(10��) | �w��(20��) | �x��(0��) |
| �_�� | �`2200��200 | �d2400��400 | �h�@2000��0 |
| ���� | �a6600��400 | �e7200��800 | �i�@6000��0 |
| ���� | �b7700��100 | �f8400��200 | �j�@7000��0 |
| ���� ��� |
�b���e����7200�ŗA����1100��悹��8300�Ŕ���100�[�� �b���i����6000�ŗA����1100��悹��7100�Ŕ���100�[�� |
�f���a����6600�ŗA����1200��悹��7800�Ŕ���200�[�� | �j���a����6600�ŗA����1000��悹��7600�Ŕ���0�[�� |
�d���n��`�������Ƃ��ēK�p�����B�ŗ��̈Ⴄ���̊�Ƃł������s��ɂē������ŋ����ł���B
�A�o�Ɛ�:�A�o����ȑO�̐Ŋz���ҕt�B0%�ʼnېł���i0�ŗ��j�Ƃ������B(�A�o���i�̔���)ht
�A���ې�:�Ŋւň������҂��[�Ł@�i�T�[�r�X����ɂ��Ă͓K�p���ɂ����j
���W�F���Y�n��`���ʖڂȗ��R�͏]����L�̂悤�ɐ�������Ă������A�ב֒������̌o�H�ɂ�茴�Y�n��`�ł����������͘c�߂��Ȃ��A�Ƃ�������������B�o�����p�����t�����l�ŗ���0%�̂Ƃ��A�o���́�100���p���́�1�������Ƃ��A�q�Ђ͂o���ɂā�200�ŁA�r�Ђ͂p���ɂā�2�ŏ��i����Ă����Ƃ���B�q�Ђ��p������҂ɒ���Ƃ��̉��i�́�2�ł���B���ɁA�o�������ŗ�20%�̕t�����l�ł������Y�n��`�ʼnېł����ꍇ�A�p���̎҂��o������A������̂ɍ��܂ł�1.2�{������̂ŁA�בւ́�120=��1�ƂȂ�B���̏ꍇ�q�Ђ��p������҂ɔ��鎞�̉��i�͂�͂聏240=��2�ło���̕t�����l�œ����O�ƕς��Ȃ��B
COLUMN6-1 �ʏ��@�Ɩ@�l�ŁE�t�����l�Ł\�\�ĕ��f�Ֆ��C
6.2. ����Ŗ@�̍\��
6.2.1. �ېŕ���(�ېł̑Ώ�)
6.2.1.1. ��{�\��
�ېŕ����F����4��1���u�����ɂ����Ď��Ǝ҂��s�������Y�̏��n���v�i��������ېŎ���������j�A���ېŁF���@4��2���u�ېŒn�悩����������O���ݕ��v�c�c����҂�������鎞���ېł����B
�@�Q�ƁF�A���i�ɑ����������ł̒������Ɋւ���@��(�A���@)13��(�Ɛœ�)1��1�����Œ藦�@14��(�������Ɛ�)18��(���z�ݕ�)�A�J�X�^���A���T�[1703
���Ǝ�������2��1��4���u�l���Ǝ҂���і@�l�v�c�c�l�E�@�l�̋�ʂ��Ȃ��B
���Y�̏��n���F����2��1��8���u���ƂƂ��đΉ��čs�������Y�̏��n�y���ݕt�����т��̒��v
���Ə����F����4��5��1���u�l���Ǝ҂��I�����Y[��]���Ǝ��̂��߂ɏ���A���͎g�p�����ꍇ�v�A�u���ƂƂ��đΉ��čs��ꂽ���Y�̏��n�Ƃ݂Ȃ��v�B
6.2.1.1.a �������
6.2.1.1.a.1 �����ɂ����čs������
| �A�}�]���萔�������E�����n���ߘa4�N4��15������31(�s�E)201�����p(���F���l�E�W�����X�g1584��10��)(���������ߘa4�N12��8�����p���������o�ږ��m�F) ���|�@�u����Ŗ@�{�s�߂U���Q���V���ɂ����w���������x�Ƃ́C���Y�̒ɒ��ڊ֘A���鎖�Ɗ������s���{�݂��������̂Ɖ�����C���̏��ݒn�������āC�̒ꏊ�ɑ���ېőΏۂƂȂ邩�ۂ��̊NJ��̊�Ƃ��Ă����|���炷��C���Y�̒̊Ǘ��E�x�z���s�����Ƃ�O��Ƃ�����������������ɓ�����v�B �@�u�o�i�T�[�r�X�́C�T�[�r�X�̗��p�҂��A�}�]���ɂ����Ē��ڔ̔����邽�߂ɏ��i���f�ڂ��邽�߂̃T�[�r�X�ł���C�T�[�r�X�̗��p�҂̏��i�����̃A�}�]���T�C�g�Ɍf�ڂ��C�̔����i�y�уv�����[�V�������s�����Ƃ���e�Ƃ�����̂ł���Ƃ���C�f�ڂ��ꂽ���i�̓C���^�[�l�b�g��ɊJ�݂��ꂽ�A�}�]���̃T�C�g��ʂ��āC�S���E�̐l�X���{���ł���̂ł��邩��C�o�i�T�[�r�X�́C�S���E�̐l�X�������̏��i�Ɋւ�������{�����邱�Ƃ��\�ɂ�����̂Ƃ����C�܂��C�{���S�؋��ɂ���Ă��C���̖̑Ή��ł���o�i�萔���������̖ɑΉ����镔���ƍ����ȊO�̒n��̖ɑΉ����镔���Ƃɍ����I�ɋ敪����Ă���Ƃ͂����Ȃ��B�m���s�n�@��������ƁC�o�i�T�[�r�X�́C�w�����y�э����ȊO�̒n��ɂ킽���čs����̒��̑��̖̒��s��ꂽ�ꏊ�����炩�łȂ����́x�i����Ŗ@�{�s�߂U���Q���V���j�ɊY������v�B �@�u�o�i�T�[�r�X�ɌW��w�̒��s���ҁx�i����Ŗ@�{�s�߂U���Q���V���j�́C�č��A�}�]���Ђł���Ƃ����C�č��A�}�]���Ђ̎��������̏��ݒn���č��ɂ��邱�Ɓc�c���炷��C�o�i�T�[�r�X�̖̒ɒ��ڊ֘A���鎖�Ɗ������s���{�݂ł����āC���Y�̒̊Ǘ��E�x�z���s�����Ƃ�O��Ƃ������������́C�č������ɏ��݂��Ă���v�B �@�u�o�i�T�[�r�X�ɌW��̒������ɂ����čs��ꂽ�Ƃ͔F�߂��Ȃ�����C�o�i�萔���́C����Ŗ@�R�O���P���ɋK�肷��d���Ŋz�T���̑ΏۂƂȂ�ېŎd����ɊY�����Ȃ��v�B |
COLUMN6-2 �d�q���ЁE���y�E�L�����̓d�q�z�M�Ə����
6.2.1.1.a.2 ���Ǝ҂����ƂƂ��čs�����
| �x�R�n������15�N5��21������14(�s�E)5���Ŏ�253������9349���p�E���É�������x������15�N11��26������15(�s�R)5���Ŏ�253������9473���p(�����p���E�Ō�148���ŐV�d�Ŕ���60�E169��)�c�c����(�l)��A�L�����(��������\��)�ɑ���������ݎ��Ă��邱�Ƃ�����Ŗ@2��8���́u���Y�̏��n���v�ɓ����茴��������Ŗ@2��3���́u���Ǝҁv�ɓ�����B |
| �����n���ߘa5�N3��8������31(�s�E)102���ꕔ���p�A�ꕔ�p���c�c�z�X�e�X��V�����^�ɓ�����d���Ŋz�T�����F�߂��Ȃ��������� |
6.2.1.1.a.3 �Ή��čs������hu
| �L���n���ߘa6�N1��10���ߘa5(�s�E)3���F�e�E�m��(����nj[�u���ޗ��ɂ��ď���Ŗ@��́u���Y�̏��n�v�̑Ή��ɓ�����Ȃ��Ƃ�������v�W�����X�g1609��130-133��) �@�����@C�Ђ͍L���s���̖{���y�n��{���e�n���҂����Ă����B���a62�N7��7���A����(�p�`���R���c�މ��)��C�Ђ���{���y�n�y�і{������(�p�`���R�X�̂��߂̐V�z�B11��2�����z)�������{�����_�����������B�����͌�275���~(�ō�288��7500�~)�B �@B��(���Î����Ԕ̔���)���{���y�n�̗��p����]�����B����31�N4��19���t�ŁA������B�Ђ͖{�����菑���쐬�����B�������{�����_����������AB�ЂƖ{���e�n���ҋy��C�ЂƂ̊ԂŐV���ݎ،_���������邱�ƁAB�Ђ������ɑ����⏞�Ƃ��Ė{�������������2000���~���A�{���s���Y���n������1��8000���~���x�������Ƃ��A�{�����菑�ɋL����Ă����B�����AB�Ћy��C�Ђ́A�ߘa���N8��28���t���u�_���̒n�ʏ��p�Ɋւ���o���v�i�u�{���o���v�j���쐬���A���̋L�ړ��e�ɂ��č��ӂ����i�u�{���o�����Ӂv�j�B �@B�Ђ͌�����2000���~��31�N4��19���ɁA1��8000���~��ߘa���N8��29���Ɏx�������B���v2���~��{�����K�Ƃ����B�����͖{�����K���ېŕW���Ɋ܂߂Ȃ��O��ŏ���ŁE�n������ł̔[�Ő\���������B����Ŋz553��8800�~�A�n������Ŋz156��2200�~�B �@�����s�����́A�{�����K�́A����Ŗ@2��1��9���u�ېŎ��Y�̏��n���v�ɊY������Ƃ��āA1��8518��5185�~��{���ېŊ���(����31�N1��1���`�ߘa���N12��31��)�̉ېŕW���z�ɉ��Z���ׂ��ł���Ƃ��A�ߘa3�N6��29���t�ŁA�{���X�������y�щߏ��\�����Z�ŕ��ی��菈���������B����Ŋz1720��5500�~�A�n������Ŋz471��0300�~�A���Z�Ŋz186��6500�~�B �@cf.�����5-2-7�i�������ݎ،_��̉������ɔ������ޗ��̎戵���j�u�������̒��ؐl�����ݎ̖ړI�Ƃ���Ă��錚�����̌_��̉����ɔ������ݐl������闧�ޗ��i�s���Y�Ǝғ��̒�����s���҂��o�R���Ď���ꍇ���܂ށB�j�́A���ݎ̌��������ł��邱�Ƃɑ���⏞�A�c�Ə�̑������͈ړ]���ɗv�������⏞�Ȃǂɔ����������̂ł���A���Y�̏��n���̑Ή��ɊY�����Ȃ��B (��)�@�������̒��ؐl����n�ʂ���ݐl�ȊO�̑�O�҂ɏ��n���A���̑Ή��𗧑ޗ����Ƃ��Ď����Ƃ��Ă��A�����͌������̒��،��̏��n�ɌW��Ή��Ƃ��Ď�̂������̂ł���A���Y�̏��n���̑Ή��ɊY�����邱�ƂɂȂ�̂ł��邩�痯�ӂ���B�@�v �@���_�@�{�����K������Ŗ@�S���P���A�Q�W���P���̉ېőΏۂɂȂ邩�ۂ��A���Ȃ킿�A�{�����K�����@�Q���P���W���́u���Y�̏��n���v�̑Ή��ɓ����邩�B �@�퍐�̎咣�@�u�������{���s���Y�ɂ����Čo�c���Ă���p�`���R�X����P�ނ��A�a�Ђ��{���y�n�ɐV�X�܂��o�X����Ƃ����ړI��B�����邽�߂ɍŏI�I�ɑI�����ꂽ�@�`���́A�{������Ɋ�Â��{�����_��̍��Ӊ����ł͂Ȃ��A�{���o�����ӂɊ�Â��{�����_���̒n�ʂ̈ړ]�ł���A���̂��Ƃ́A�{���o�����ӂ̌o�܋y�і{���o���̋L�ړ��e���疾�炩�ł���B�܂��A�V�X�܊J�X�ɔ����A���Ђ��������珳�p�����{�����_�a�ЂƂb�ЂƂ̊Ԃō��Ӊ������ꂽ���̖{���o�����ӂ̗��s�܂���ƁA�{���o�����ӂ����ꂽ���_�ł́A�����Ƃb�ЂƂ̊ԂŖ{�����_���Ӊ�������Ă��炸�A�{�����_���ł��Ă��Ȃ��������Ƃ͖��炩�ł���B�v �@���|�@�����F�e�@�u�����́A�{���s���Y����̓P�ނɓ�����A���Î����Ԕ̔��Ǝ҂̂a�ЂƋ��c��������Ȃ��Ȃ������A���̌��ʁA�p�`���R�X�̉c�ƂɌW�錠�����̑r���A�p�`���R�X�ܗp�e��{�݂̓P���̔�p���̑����Ȃǂ������邱�ƂɂȂ������Ƃ���A���̕⏞���a�Ђɋ��߂����ƁA�a�Ђ�����ɉ����邱�ƂɂȂ������߁A�����Ƃa�Ђ́A�u�����́A�{�����_�����������B�a�Ђ́A�b�ЂƂ̊ԂŐV���Ȓ��ݎ،_����������ƂƂ��ɁA�����ɑ��Ė{�����_����������ēX�܂̓P�ނ����邱�Ƃɔ��������鑹���⏞���Ƃ��ĂQ���~���x�����B�v���Ƃ���e�Ƃ���{�����������������ƁA�a�Ђ͖{������Ɋ�Â��ĕ����R�P�N�S���P�X���ɂQ�O�O�O���~���A�ߘa���N�W���Q�X���ɂ́u�{������Ɋ�Â������⏞���̎x���������߂�v�|�L�ڂ��ꂽ�{���������ɉ�����`�Ŏc���P���W�O�O�O���~���x���������Ƃ��F�߂���B���������āA�{�����K�́A�{�����_���̉��ɂ�蓯�_���̒n�ʂ����ł��邱�Ƃɑ���Ή��ł���Ƃ�����B �@�m���ɁA�{���o�����ӂł́A�{�����_���̒n�ʂ���������a�ЂɈړ]������|�����ӂ���Ă���B�������A�O�L�F�莖���ɂ��A�{������Ɋ�Â��{�����_��_��̊��Ԗ�����������������邱�Ƃɂ��āA�b�Ђ��������Ȃ��Ȃ邱�Ƃɂ��Ă̕s����i���A�{���e�n���҂̈ꕔ�������ɑ��������𐿋����ׂ��ł���|�̈ӌ����o�������ƁA�ɂ�������炸�A���ǁA��������b�Ђɒ����������Q���̎�|�̋������x�����邱�ƂȂ��A�b�Ђ������ɑ��������𐿋����邱�Ƃ̂Ȃ��܂܁A��������a�Ђւ̒��ؐl�̒n�ʂ̏��p�ɂ��Ăb�Ћy�і{���e�n���҂����ӂ������ƁA�{���o�����ӂł́A�a�Ђ̉c�ƊJ�n���������Ė{���s���Y��ΏۂƂ���{�����_������Ӊ�A�������n���Ƃ���{���y�n�݂̂�ΏۂƂ��鎖�Ɨp����ؒn����ݒ肷�邱�ƂƂȂ��Ă������ƁA���X�A�a�Ђ́A�{���y�n�݂̂���]���Ă���A�{�������͕s�v�ł��������ƁA�{���o�����ӌ�ɖ{�������͉�̓�����A�a�Џ��L�̌������V�X�܂Ƃ��Č��z���ꂽ���Ƃ��F�߂��邪�A�����̎����Ɋӂ݂�ƁA�{���o�����ӂ́A�����ς�A�������{���s���Y����P�ނ����i�������x�������R���Ȃ��Ȃ����j����a�Ђ��{�����_��̒������p�����Ďx�����Ƃ����@�`�����̂邱�ƂŁA�b�Ђ��������Ȃ����Ԃ��Ȃ������ƁA�y�сA�����ɑ��{�����_��̑������ɔ����������𐿋����Ȃ����Ƃɂ��Ė{���e�n���҂̔[���邱�Ƃ�ړI�Ƃ��āA�������ꂽ���̂ł���Ƃ����A�a�Ђ��{�����_���̒n�ʂɊ�Â��Ė{�������̎g�p���v�����邱�Ƃ͂��悻�\�肳��Ă��Ȃ������Ƃ�����B�܂��C�{���o���ɂ́A�V���ɒ��ؐl�ƂȂ�a�Ђ����ݐl�̂b�ЂɎx���������Ɋւ���L�ڂ͂��邪�A���ؐl�̒n�ʏ��p�ɔ����a�Ђ������Ɏx���������Ɋւ���L�ڂ��邢�͖{������Ɋ�Â��x������Q���~��{���o�����ӂɊ�Â��x������Q���~�ɐU��ւ��铙�̋L�ڂ͂Ȃ��B����ɁA�{������Ɋ�Â��Q���~���x����ꂽ���Ƃ𗠕t����؋��i�b�X�j�͂���̂ɑ��A�{���o�����ӂɊ�Â��a�Ђ������ɉ��炩�̋������x���������Ƃ𗠕t����؋��͂Ȃ��B��������ƁA�{�����K��{���o�����ӂɊ�Â��{�����_���̒n�ʂ̏��n�ɑ���Ή��Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B�v |
| ������Ђӂꂠ�����Ȏ����E�����n���ߘa6�N2��9���ߘa4(�s�E)496�����p(�������d�Ŕ��ጤ����2025�N7��4����) �@�����@�����́A���Ȏs���A���̎{�݁i�n�������@�Q�S�S���P���j�ł���{���{�ݓ��̊Ǘ��^�c�̂��߁A�ꕔ�o�������āA�����P�O�N�U���P���ɐݗ�����������Ђł���B �@���Ȏs�́A�����Q�W�N�R���P�W���A�{�����T���P���Ɋ�Â��A������{���{�݂̎w��Ǘ��҂Ɏw�肵���i�w����Ԃ͕����Q�W�N�S���P�����畽���R�P�N�R���R�P���܂Łj�B�����́A�����Q�W�N�S���P���t���ŁA���Ȏs�Ƃ̊ԂŁA�{���{�݂̊Ǘ��y�щ^�c�Ɋւ���Ɩ��ɂ��āA�{���{�݂̊Ǘ��Ɋւ����{���菑�i�ȉ��u�{����{���菑�v�Ƃ����B�j����������B���Ȏs�́A�{���Ǘ��Ɩ��̎��{�̑Ή��Ƃ��āA�����ɑ��Ďw��Ǘ������x�����i21��1���j�B �@���_�F�{���e�x���������Y�̏��n���́u�Ή��v�i����Ŗ@�Q���P���W���j�ɓ����邩�B �@���|�@�u����Ŗ@�Ɋ�Â�����ł́A����ɍL���������S�����߂�Ƃ����ϓ_����A�ېł̑Ώۂ��L���ݒ肵�A���̐Ŋz�́A���Ǝ҂����镨�i��T�[�r�X�̉��i�ɏ�悹�i�]�Łj����A�ŏI�I�ɏ���҂����S���邱�Ƃ��\�肳��Ă���łł���B���̂��߁A���Ǝ҂�����o�ϓI���v������ł̉ېŗv���Ƃ��Ă̎��Y�̏��n���́u�Ή��v�i���@�Q���P���W���j�ɓ�����Ƃ����邽�߂ɂ́A���Ǝ҂�����o�ϓI���v�Ǝ��Ǝ҂��s�����ʋ�̓I�Ȏ��Y�̏��n���Ƃ̊ԂɁA���Ȃ��Ƃ��Ή��W�����邱�Ƃ��K�v�ł���B��������ƁA���Y�ʋ�̓I�Ȏ��Y�̏��n�������邱�Ƃ������Ƃ��ē��Y�o�ϓI���v�������Ƃ�������Ή��W�����邱�Ƃ��K�v�ł��邪�A����ȏ�̗v���͗v������Ă��Ȃ����̂Ɖ�����̂������ł���B �@�{����{���菑�y�і{���e�N�x���菑�ɂ����āA���Ȏs�́A�{���Ǘ��Ɩ��̎��{�̑Ή��Ƃ��ĂU�O�O�O���~���x�����Ƃ���Ă���̂ł����āc�c�A����ɂ��A�����Ɖ��Ȏs�́A�����Q�W�N�x���畽���R�O�N�x�܂ł̖{���Ǘ��Ɩ��̑Ή��Ƃ��āA�e�N�U�O�O�O���~�̎w��Ǘ������x�����|���ӂ������̂ƔF�߂���B�܂��A�{���e�x�����̎x���Ɋւ��A�����́A�{���{�݂̎w��Ǘ����Ƃ��ĂU�O�O�O���~�𐿋�����|�̋L�ڂ̂��鐿���������Ȏs�ɑ��t���A���Ȏs�́A�{���e�x�������u�ϑ����v�Ƌ敪������ʉ�v�\�Z�c�ċy�ш�ʉ�v�Γ��Ώo���Z�����c��ɒ�o���Ă��̋c�����͔F����o��ƂƂ��ɁA�{���e�x�����̎x�o�ɓ�����A�u�m�{���{�݁n�w��Ǘ����v�Ƃ��Ďx�o���S�s�ׂɌW��s���̌��ق��Ă���c�c�B�ȏ�̊e�����ɂ��A�{���e�x�����́A�{���Ǘ��Ɩ��̗��s�Ƃ��������ꂽ���Ƃ������Ƃ��Ďx����ꂽ�w��Ǘ����ł���A�{���Ǘ��Ɩ��́u�Ή��v�ł���ƔF�߂���B�v |
6.2.1.1.a.4 ���Y�̏��n����ёݕt���Ȃ�тɖ̒�
| ������Јɏ��E�����n������9�N8��8������8(�s�E)34���s�W48��7�E8��539�Ŕ��^977��104�Ŋ��p�m��S�I6��85�c�c�����̒��ݎ،_��̍��Ӊ����ɍۂ����ؐl�Ɏx���������ޗ��ɌW�����ő����z����ݐl�ɌW�����Ŗ@30��1���́u�ېŎd����ɌW�����Ŋz�v�Ƃ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B |
| ���s�n������23�N4��28����58��12��4182�ŕ���19(�s�E)48�����p�E��㍂������24�N3��16����58��12��4163�ŕ���23(�s�R)86�����p(�O�؋`��E�W�����X�g1448��123��)�c�c�ٌ�m��̈˗��ŕٌ�m���@�����k�Ɩ������˗��҂��ꍇ�ɕٌ�m��ٌ�m�����̂��镉�S���ٌ͕�m��̉ېŎ���̑Ή��ł���B |
6.2.1.1.b �A�����
6.2.1.2. ��ېŎ��(����6���A�ʕ\��1)
| �_�˒n������24�N11��27������22(�s�E)61���Ŏ�262������12097���p�m��c�c��Â�����Ŗ@�Ŕ�ېłȂ̂ŁA�t�����l�ŕ�����Ö@�l�����S���邱�ƂɂȂ��Ă���i���͐f�Õ�V�̉���ł̒l�グ���s�\���ł���j���Ƃ��ጛ�ł���Ƃ̎咣��˂���B |
| �J���[�g�����E�����n������24�N1��24������22(�s�E)171������2147��44�ŐŎ�262������11859���p�E������������25�N4��25���Ŏ�263������12209����24(�s�R)84�����p�m��c�c�@���@�l�̕�Γ��̔����@�l�Ŗ@�{�s��5��1��1���̕��i�̔��Ɓi�J���[�g�ɂ��Ă͕s���Y�ݕt�Ɓj�ɓ�����i�@�l�Ŕ�ېł́u����n�̑ݕt���v�o�@��5��1��5���j�G�@���15-1-18�p�ɓ�����Ȃ��j�B��n���Ǘ����͖̑Ή��ł��邩�����Łi����Ŗ@�ɂ͌��v�@�l�E�@���@�l���̗D���K��͂Ȃ��j�̉ېŕW���Ɋ܂܂��i����n�̑ݕt�͓y�n�̑ݕt�����猳�X��ېŁj�Bcf.6�Ł�312.02�y�b�g���ՋƎ����E�Ŕ�����20�N9��12������2022��11�� |
| �����n���ߘa3�N3��10���Ŏ�271������13540���p�E���������ߘa3�N12��7���Ŏ�271������13639���p�E�ŎO�����ߘa4�N6��21���Ŏ�272������13729���p�A�s�c�c�L���V�l�z�[���ɂ�����H���͔�ېŎ���ɓ�����Ȃ��B |
| �����n���ߘa5�N5��25���ߘa3(�s�E)123��(���p)(���䍎�F�E�d�Ŕ��ጤ����\��)�c�c���ÏZ����d����Ĕ̔����鎖�ƁB����Ŗ@�{�s��45��3���u�ېŎ��Y�̏��n�̑Ή��̊z�Ɣ�ېŎ��Y�̏��n�̑Ή��̊z�Ƃɍ����I�ɋ敪����Ă��Ȃ��Ƃ��v�Y�����B |
COLUMN6-3���Z����ƕt�����l��(�����)ob
6.2.1.3. �ƐŎ��(�A�o�Ɛ�)(����7���E8��)
| �C���f�B�[���[�V���O���[�O�����E�����n������22�N10��13������20(�s�E)730����57��2��549�Ŋ��p�m��S�I7��88(���G���l���^�痺��2023.3.30�O�����)�c�c����Ŗ@4��3��2���A����Ŗ@�{�s��6��2��7���u�����y�э����ȊO�̒n��ɂ킽���čs����̒v�Ɋւ��āB�A�����J�ŔN��15�܂���16���[�X�A���{�ŔN��1���[�X�̃J�[���[�X�iIndy Racing League�j�ɎQ�킷����{�@�l�̖̑Ή��������ɌW����̂ƍ��O�ɌW����̂Ƃɍ����I�ɋ�ʂł��Ȃ��i��ʂł���ꍇ�ɂ��Ă͏���Ŗ@28��1���Q�Ɓj���Ƃ���A���[�X�̃X�|���T�[�_��ɂ���Ή����A���ׂē��{�̏���ł̉ۂ�������̂ł���Ƃ�����B�ނ��{���ł̓X�|���T�[��ƌQ�����{�@�l�������̂ŁA�X�|���T�[�����d����Ŋz�T�����Ƃ邽�߂ɁA�e���[�X���Ƃ̌ʂ̌_��Ƃ���̂ł͂Ȃ��A�킴�ƈ�N�Ԃ��Ƃ̌_��Ƃ��ĉېŎ���������Ӑ}�����A�Ƃ���������������悤�ł���B |
| Hanatour Japan�����E�����n������27�N3��26����62��3��441�ŕ���23(�s�E)718�����p(�A�؏���E�W�����X�g1500��160��)�E������������28�N2��9������27(�s�R)156�����p�S�I7��89�c�c�����ό��q�ւ̖��A�o�ƐŎ���i����Ŗ@7��1���A����Ŗ@�{�s��17��2��7���n�j�ɊY�����Ȃ��Ƃ��ꂽ����B |
| ������Ђ����������E�����n������28�N2��24������26(�s�E)250������2308��43�Ŋ��p�m��c�c�K���c�A�[�A�o�ƐŔ�Y���B |
| �A�o���i�̔��ꐧ�x�ɂ��āA��c�����d�@������Ў����E�����n���ߘa2�N6��19������30(�s�E)321���Ŏ�270������13415���p(���������Y�E�W�����X�g1575��155��)�E���������ߘa3�N9��2���ߘa2(�s�R)146���Ŏ�271������13599���p�c�c�����E��c�����d�@������Ёi�ȉ��w�Ёj�͕������N�ȑO����{���̔���ɂ��ĕ��i�Ŗ@���̗A�o���i�̔���̋����Ă����B�A�o���i�̔���p���o�c�͏o��(����Ŗ@����4��)���o���������N4��1��������Ŗ@8��6���̗A�o���i�̔���̋��������̂ƌ��Ȃ����B���`�y�ъ؍��̗��s��Ёi��ƍ��ۗ��^�L�����i�i���`�Ёj�A������Ђk�n�s�s�d�i���b�e�Ёj�A�c�n�m�f�|�`�@�s�q�`�u�d�k�@�`�f�d�m�b�x�i�h���A�Ёj�j�̏]�ƈ����֗^���{���̔���ŋ��H�|�i�̖{�����n���{���e�ېŊ��ԁi����28�N4��1������29�N2��28���j�ɂȂ��ꂽ�B�{���e���n�ŊO���l���s�ҁi�{���e���`�l�B7000�l�ȏ�j�������̋��H�|�i�i1kg�B��450���~�j���w�����ꖼ�`�l������1000���~���̑���x�������Ȃ��ꂽ�Ƃ���Ă���B�_�c�Ŗ������́A�{���e���n������Ŗ@8��1���ɂ����Z�҂ɊY�����Ȃ��Ƃ��čX�������������B�ٔ������������ێ������B�{���͏z����i����carousel fraud�A��]�ؔn���\�j�i�����Ё˂w�Ё˃h���A�Ё˖����Ёj�i�����ЂƂw�Ђ͓��{�@�l�B�h���A�Ђ͊؍��@�l�B�����Ђ����H�|�i���j�i�o�ŎЂ̖����ЂƂ͕ʁj�ł��邪�A�z����ł��邩�ۂ��͔��|�Ɛ[���ւ��Ȃ��悤�ɓǂ߂�B cf.�����n������18�N11��9���Ŏ�256������10569����16(�s�R)392�����p�m��(�������O�E�ŗ�51��11��129��)�c�c���V�A�l�D�����ւ̒��Î����Ԃ̔̔����A�o�ƐőΏێ���ł͂Ȃ��Ƃ��ꂽ����B cf.�{�씎�s�u����ł̖ƐŐ��x�Ɋւ����l�@�\�A�o���i�̔��ꐧ�x�݂̍���𒆐S�Ƃ��ā\�v�Ŗ���w�Z�_�p64��89��(2010.6.29)�Q�ƁB[���]����҂̍w���ɂ��Ă܂ŗA�o�Ɛł�K�p���邱�Ƃ������E�������ɓK�����^��B |
| �����n���ߘa4�N7��15���ߘa2(�s�E)339��(���p)�c�c��p�ւ̗A�o�Ɋւ����i���d���ꂽ�̂�����(���{�@�l)�ł͂Ȃ���p�@�l�ł���Ƃ��ꂽ����B |
| ������ЃA�y�b�N�X�����E�����n���ߘa4�N1��21���ߘa2(�s�E)198��(���p)�E���������ߘa5�N1��25���ߘa4(�s�R)41��(���p)�c�c�����̃R�s�[�̒�o���Ȃ�����Ŗ@8��1���̏���ł̖Ə����F�߂��Ȃ��������� |
6.2.2. �[�ŋ`����
6.2.2.1. �N���[�ŋ`�����̂�(�ȗ�)
6.2.2.2. �[�ŋ`���̖Ə�(�ƐŎ��ƎҐ��x)
����9���F�N���ېŔ��㍂1000���~�ȉ��c�c�Ə��Ə����Ă��邪�u�w��̖ƐŁE�[���ŗ��ƈႢ�l�I��ېŁB��F6.1.2.1.�̂b�Ɠ���̎��Ƃ��s�Ȃ��Ă���ʂ̏����Ǝ҂d���A�t�����l�Ő��̉��A�b�Ɠ����l�i(7700)�ŏ���҂c�ɑ��̔����Ă��邪�A�d�͏���9���ɂ���ېłł������B�d�͂b�Ɣ�ׂĊ�瓾�����邩�H�c�c700�~�ł͂Ȃ��B
������ЃV���z�g�[�T�[�r�X�����E�����n������11�N1��29������9(�s�E)121�����p�E������������12�N1��13������11(�s�R)52�����p�E�Ŕ�����17�N2��1�����W59��2��245�ŕS�I7��90oc�c�c����Ԃ̔��㑍�z��3052���~�ł������B�@9���̉ېŔ��㍂�̎Z�o�ɓ�����A100/103���悸�ׂ����ۂ��������A�ٔ����́A�ƐŎ��Ǝ҂ɂ��Ă͏悶�Ȃ��Ƃ����B
COLUMN6-4 ��ېłƃ[���ŗ��̍���
6.2.3. �ېŕW���E�ېŊ��ԁE�ŗ�
6.2.3.1. �ېŕW��(����28��)(�����10-1-11)
| ������ЃJ�`�^�X�����E�����n���ߘa5�N5��25���ߘa3(�s�E)123������2606��45�Ŋ��p�E���������ߘa6�N5��30���ߘa5(�s�R)176�����p(�ЎR���q�E�W�����X�g1609��10-11�ŁA������q�E2025�N7��18���d�Ŕ��ጤ�����) �@�����@X��(�����E�T�i�l)�͒��ÏZ����Ĕ̔����鎖�Ƃ��c��ł���B����̍ۂ��Ĕ̔��̍ۂ��y�n(��ېŎ��Y)�ƌ���(�ېŎ��Y)���ꊇ�Ŕ������Ă���B����������z�ɐ�߂錚������̊����́AX���ߋ��ɔ���������ˌ��ďZ����́y�����̌Œ莑�Y�ŕ]���z/(�y�n�̌Œ莑�Y�ŕ]���z�{�����̌Œ莑�Y�ŕ]���z)=34%�z�Ƃ��������̕��ϒl(������������)�ł���Ƃ����O��ŁA����Ŗ@28��1���́u�ېŎ��Y�̏��n���̑Ή��̊z�v���v�Z���Ă���(�{�������Z�o���@:����~2.7%�B2.7%��34%�~8%)(�����ŗ������O��8%)�BX�́A�����_�ɂ����āA�������������ɂ��y�n����z�ƌ�������z�Ƃ̋敪�����Ă����B �@�ː��Ŗ������́A����Ŗ@�{�s��45��3���́u�ېŎ��Y�̏��n�̑Ή��̊z�Ɣ�ېŎ��Y�̏��n�̑Ή��̊z�Ƃɍ����I�ɋ敪����Ă��Ȃ��Ƃ��v�ɊY������Ƃ̑O��ŁA�X��������������(��q���{���퍐�Z�o���@:�������茾���y(���������{���t�H�[����)/(�y�n+�����̎d�����)�z)�B �@���_1:�y�n�y�ь����̈ꊇ���n�ɓ�����A�����_�ɂ����ēy�n�̑㉿�y�ь����̑㉿���敪����Ă���ꍇ�ɁA����Ŗ@�{�s�߂S�T���R����K�p���邱�Ƃ��ł��邩�ۂ� �@���_2:���_1�����Ȃ�A�{���e�����̏��n���A����Ŗ@�{�s�߂S�T���R���ɋK�肷��u�ېŎ��Y�̏��n�̑Ή��̊z�Ɣ�ېŎ��Y�̏��n�̑Ή��̊z�Ƃɍ����I�ɋ敪����Ă��Ȃ��Ƃ��v�ɊY�����邩�ۂ� �@���_3:���_2�����Ȃ�A�{���e�X�������ɂ����ĎZ�肳�ꂽ�����̏��n�ɌW�����ł̉ېŕW���́A����Ŗ@�{�s�߂S�T���R������̕��@�ɂ���ĎZ�肳�ꂽ���̂Ƃ����邩�ۂ� �@��R�@�������p �@���_1�@�u����ł̉ېŕW���́A�u�ېŎ��Y�̏��n���̑Ή��̊z�i�Ή��Ƃ��Ď��A���͎��ׂ���̋��K���͋��K�ȊO�̕��Ⴕ���͌������̑��o�ϓI�ȗ��v�̊z�k�ȉ����l�j�v�ł���i����Ŗ@�Q�W���P���{���j�B�����āA�ېŎ��Y�݂̂����n����悤�ȏꍇ�ɂ́A���Y���n�̓����ҊԂŎ��邱�Ƃ����ӂ����Ή��̊z���u�ېŎ��Y�̏��n���̑Ή��̊z�v�ɓ����邱�Ƃ͋q�ϓI�ɂ����炩�ł���B�����A�ېŎ��Y�Ɣ�ېŎ��Y�Ƃ�̎҂ɑ��ē����ɏ��n�i�ꊇ���n�j����ꍇ�ɂ́A���̓����ҊԂŎ��邱�Ƃ����ӂ����Ή��̊z���������Ƃ��Ă��A�@���̓���߂��Ȃ������ꍇ��A�A��߂�ꂽ���X��̂��̂ɂ����Ȃ��ꍇ�������āA��L�̍��ӂ����Ή��̊z�̂����́u�ېŎ��Y�̏��n���̑Ή��̊z�v�������ɋq�ϓI�ɖ��炩�ł���Ƃ͂����Ȃ�����i�Ⴆ�A����ɂ����ĕX���ېŎ��Y�̋��z��������荂���A�ېŎ��Y�̋��z���������Ⴍ�ݒ肵�Ă����ɂ����Ȃ��ꍇ�k�A�l�ɂ́A�ېŎ��Y�̑Ή��̊z�́A����ɂ����Ė������ꂽ���z�ɁA��ېŎ��Y��������荂������n�����Ƃ��ł���Ƃ�������ɂƂ��Ă̌o�ϓI���v��������K�v�����邱�Ƃ�����A���̂Ƃ��́A���Y�o�ϓI���v�̉��l����̓I�ɎZ�肷�ׂ����ƂƂȂ�B�j�A���̂悤�ȏꍇ�̉ېŕW���̊z���Z�肷�邽�߂ɕʓr�̌v�Z���K�v�ƂȂ�B�����T���́A��L�A�̂悤�ȏꍇ���܂߂āA�ېŕW���̊z�̌v�Z�̍זڂɊւ��K�v�Ȏ������߂邱�Ƃ߂ɈϔC�������̂Ɖ����ׂ��ł���B�v �@�u����ł̕��S�̋ɏ����Ƃ����ϓ_����́A���Ǝ҂ɂ����ĉېŎ��Y�̏��n�̑Ή��̋��z�ӓI�ɒႭ�ݒ肵����A���ꂾ���������ґo���̍��ӂ����u�Ή��̊z�v�ł���Ƃ��Ă��̔[�ŋ`����Ƃ�悤�Ƃ��鎖�Ԃ��N���蓾��B�����āA�����������Ԃ́A����Ŗ@�ɂ����Ĉ��̔�ېŎ����@�肵���ꍇ�ɂ͓��R�ɗ\�z���邱�Ƃ��ł�����̂Ƃ����邱�Ƃ��炷��A���@�Q�W���P���{���������鎖�Ԃ����e���Ă���Ƃ�������B���@�̐���Ɠ����ɒ�߂�ꂽ�����̏���Ŗ@�{�s�߂S�T���R���ɂ����Ă����݂Ɠ���|�̒�߂�����Ă����Ƃ���A�������P�Ɂu�敪����Ă��Ȃ��Ƃ��v�Ƃ����̂ł͂Ȃ��u�����I�ɋ敪����Ă��Ȃ��Ƃ��v�Ƃ��Ă���̂��A�����鎖�Ԃ�h�~����_�ɂ��̎�|������ƍl�����A����𗠕t������̂Ƃ�����B�������āA�����̎咣����悤�ɁA�ꊇ���n�̏ꍇ�ɂ������҂̍��ӂ����ېŎ��Y�̑Ή��̋��z����Ɂu�ېŎ��Y�̏��n���̑Ή��̊z�v�ł���Ɖ�����Ȃ�A�����҂̍��ӂ�����ȏ�ېŎ��Y�Ɣ�ېŎ��Y�ɌW��Ή��̊z�̋敪�͏�ɑ��݂��邱�ƂɂȂ�A���̍���������������]�n���{���Ȃ��͂��ł����āA�@���̕��������������߂��̗p���邱�Ƃ͍���ł���v�B �@���_2�@�u�ꊇ���n�̏ꍇ�ɂ����āA���Y���n�̓����ҊԂŁA�ېŎ��Y�̑Ή��̋��z�Ɣ�ېŎ��Y�̑Ή��̋��z���敪���č��ӂ��Ă����Ƃ��ɁA����Ŗ@�{�s�߂S�T���R������́u�ېŎ��Y�̏��n�̑Ή��̊z�Ɣ�ېŎ��Y�̏��n�̑Ή��̊z�Ƃɍ����I�ɋ敪����Ă��Ȃ��Ƃ��v�ɊY�����邩�ۂ��f����ɓ������ẮA��L�P�i�Q�j�Ő��������Ƃ���A�������u�����I�ɋ敪����Ă��Ȃ��Ƃ��v�Ƃ��Ă����|���A���Ǝ҂����ӓI�ɉېŎ��Y�̏��n�̑Ή��̋��z��ݒ肵�Ĕ[�ŋ`����Ƃ�悤�Ƃ��鎖�Ԃ�h�~����Ƃ���ɂ����邱�ƂɊӂ݂�A�������w�E����悤�ȍ��ӂ̌`���ߒ��ɍ����������邩�ǂ����Ɍ��炸�A���Y�ېŎ��Y�y�є�ېŎ��Y�̂��ꂼ��̖{���I�ȉ��z�̔䗦��A�������d���ꂽ�ۂ̂��ꂼ��̑Ή��̊z�̔䗦�Ƃ̔�r�ɂ����āA�ېŎ��Y�̑Ή��̊z�̊������ߏ��ɂȂ��Ă��Ȃ����ǂ����Ȃǂ̎�������l�����ׂ����̂Ɖ�����̂������ł���B�v �@�u�����̔̔����ɖ{�������Z�o���@�ɂ���Ĕ���������z�ɐ�߂錚���̑���z���Z�o�����ꍇ�ɂ́A���t�H�[���ɂ���č��߂��������l������������z�ɐ�߂錚���̑���z�̔䗦�ɓK�ɔ��f����Ȃ��v �@���_3�@�u����Ŗ@�{�s�߂S�T���R���́A�ꊇ���n�̏ꍇ�̑Ή��̊z���ېŎ��Y�̏��n�̑Ή��̊z�Ɣ�ېŎ��Y�̏��n�̑Ή��̊z�Ƃɍ����I�ɋ敪����Ă��Ȃ��Ƃ��́A���ꂼ��̉��z�A���Ȃ킿�����̔�ň����āA���Y�ېŎ��Y�̏��n���ɌW�����ł̉ېŕW�����Z�肷�邱�Ƃ��߂Ă���B������Ƃ���A�@�����Ƃ͕K��������`�I�ɒ�܂���̂ł͂Ȃ��A���ꎩ�̕��̂���T�O�ł��邱�ƁA�A�����ɂ�����u���z�v�͉ېŕW�����̂��̂ł͂Ȃ��A������z�ɐ�߂�ېŎ��Y�Ɣ�ېŎ��Y�̊e���������߂̂��̂ɂ������A���z�̔䗦�����K�ł���ΉېŕW���Ƃ��đ����Ȋz�����Ƃ��\�ł��邱�ƁA�B�����ɂ������z��s���Y�Ӓ�]����ɏ]���ĎZ�o���ꂽ���̂Ɍ��邱�ƂƂȂ�A���ƂȂ�s���Y�ɂ��Ă͑S�ĕs���Y�Ӓ�m�ɊӒ�]�����˗����Ȃ���Ȃ炸�A���Ŏ�����z�肵��K�͂̉ߑ�ȕ��S���������邱�ƂȂǂ��炷��A�����ɂ����u���z�v�Ƃ́A�ېŎ��Y�̏��n�̑Ή��̊z�Ɣ�ېŎ��Y�̏��n�̑Ή��̊z�Ƃɍ����I�ɋ敪���邽�߂̔䗦�����Ƃ��\�Ȃ��̂ł���Α������̂Ƃ����ׂ��ł���B�v �@�u�{���퍐�Z�o���@�́A�{���e�����̌����Ɠy�n�̉��z�ɂ��āA�����Ɠy�n�̊e�d���ꎞ�̎x������z�i�����̑���z�̔䗦�͎d���ꎞ�̌Œ莑�Y�ŕ]���z���̔䗦�ɉ��������̂ƂȂ��Ă���B�j����b�Ƃ��A�����ɁA�������s�������t�H�[�����̔�p�̂��������ɌW����̂͌����̉��z�Ƃ��āA�y�n�ɌW����͓̂y�n�̉��z�Ƃ��āA���҂ɋ��ʂ�����͎̂d���ꎞ�̎x������z�̔䗦�ň��������̂����ꂼ��̉��z�Ƃ��ĕt�����邱�Ƃɂ��Z�o�����z�������āC����Ŗ@�{�s�߂S�T���R���́u���z�v�Ƃ�����̂ł���B�v �@�u�x������z�̔䗦�i���Ȃ킿�Œ莑�Y�ŕ]���z���̔䗦�j�����̂܂ܗp�����ꍇ�A���t�H�[���ɂ��y�n�E�����̌������l�̑������K�ɔ��f����Ȃ��Ƃ�����肪������B�����ŁA�{���퍐�Z�o���@�ɂ����ẮA�������s�������t�H�[�����̔�p�ɂ��āA�������y�n�ƌ����̂�����̔��㌴���Ƃ��Ĉ����Ă��邩�ɉ����Ă��ꂼ��̎x������z�ɉ��Z���A�ŏI�I�ȉ��z�����߂Ă�����̂Ɖ������Ƃ���A��ʂɁA��p���|���ă��t�H�[�������{���A���̕��A���Y�s���Y�̌������l�͍��܂�͂��ł���i���Ǝ҂́A��ʓI�ɁA���㌴����������ė��v�������߂���x�̔̔����i��ݒ肷��̂��ʏ�Ɖ������B�܂��A�O�L�Q�i�R�j�ɂ����Đ��������Ƃ���A�s���Y�Ӓ�]���̊�{�I�Ȏ�@�̈�Ƃ���錴���@�ɂ����Ă��A�����̑����z�E�C�U�E�͗l�ւ����́A���̓��e�܂��A�Ē��B�����̍���ɓK�ɔ��f������ׂ����̂Ƃ���Ă���B�j����A���̂悤�ɂ��ē������z�������i���Y�̏��n�̎��ɂ�����ېŎ��Y�̉��z�j�ƕ]�����邱�Ƃ����̎��`�ɔ�������̂Ƃ͂����Ȃ���A����ɂ��A��L�̃��t�H�[���ɂ��������l�̑��������f����Ȃ��Ƃ�����������������̂Ƃ��č�������������̂ƔF�߂���B�v �@�T�i�R �@���_1:����Ŗ@�{�s�߂S�T���R���̋K�肪����Ŗ@�Q�W���T���̈ϔC�͈̔͂�����̂��ۂ� �@���_2:�{���e�����̏��n���A����Ŗ@�{�s�߂S�T���R���ɋK�肷��u���Y�̏��n�̑Ή��̊z���ېŎ��Y�̏��n�̑Ή��̊z�Ɣ�ېŎ��Y�̏��n�̑Ή��̊z�Ƃɍ����I�ɋ敪����Ă��Ȃ��Ƃ��v�ɊY�����邩�ۂ� �@���_3:�{���e�X�������ɂ����ĎZ�肳�ꂽ�����̏��n�ɌW�����ł̉ېŕW���́A����Ŗ@�{�s�߂S�T���R������̕��@�ɂ���ĎZ�肳�ꂽ���̂Ƃ����邩�ۂ� �@�T�i�R���|�@�T�i���p �@���_1�@�u����Ŗ@�Q�W���P���{�����ېŎ��Y�̏��n���̑Ή��̊z�������ĉېŎ��Y�̏��n���ɌW�����ł̉ېŕW���Ƃ��Ă���̂́A����x�o�ɒS�ŗ͂�F�߁A���̒S�ŗ͂ɉ������ېł��s�����Ƃ�����|�ɂ����̂ł���B�ېŎ��Y�݂̂����n���ꂽ�ꍇ�ɂ́A���̏���x�o�͓��Y�ېŎ��Y�̏��n�̑Ή��̊z�Ƃ������ƂɂȂ邪�A�ېŎ��Y�Ɣ�ېŎ��Y���ꊇ���n���ꂽ�ꍇ�ɂ́A���̏���x�o�͈ꊇ���n�̑Ή��̑��z�ƂȂ�̂ł����āA����Ŗ@�{�s�߂S�T���R���̒�߂́A���̂����ǂ͈̔͂��ېŎ��Y�̏��n�ɌW�����x�o�ƌ��邩�Ƃ����ېŕW���̎Z����@���߂����̂ł��邩��A���@�Q�W���T���ɂ����u�ېŕW���̊z�̌v�Z�̍זڂɊւ��K�v�Ȏ����v���߂����̂Ƃ������Ƃ��ł���B�v �@�u�ېŎ��Y�Ɣ�ېŎ��Y���ꊇ���n���ꂽ�ꍇ�ɂ́A���̏���x�o�͈ꊇ���n�̑Ή��̑��z�ƂȂ�̂ł��邩��A����ł̉ېŕW�������̑Ή��̑��z����b�Ƃ��ĎZ�肳���ׂ����Ƃ͓����̎�|���狁�߂���Ƃ��Ă��A�ꊇ���n�̑Ή��̑��z�̂����ǂ͈̔͂��ېŎ��Y�̏��n�ɌW�����x�o�ƌ��邩�Ƃ�����ʂɂ����āA��������ҊԂ̍��ӂɐ�ΓI�ȍS���͂�F�߂邱�Ƃ͓����̎�|���狁�߂���Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B�������āA����ł̕��S��s���ɖƂ�邽�߂ɁA��������ҊԂŜ��ӓI�ɉېŎ��Y�̑Ή��̊z�Ɣ�ېŎ��Y�̑Ή��̊z�̋敪�����ӂ��ꂽ�ꍇ���܂߂āA��������ҊԂł��̋敪�Ɋւ��鍇�ӂ�����ȏ�A���Y�敪�̍���������Ƃ��邱�ƂȂ��A��ɓ��Y�敪�ɏ]���ĉېŕW�����߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ���ƁA����x�o�ɒS�ŗ͂�F�߁A���̒S�ŗ͂ɉ������ېł��s�����Ƃ��������̎�|�ɔ����邱�ƂɂȂ�Ƃ����ׂ��ł���B�v �@���_2�@���R�����p �@���_3�@���R�����p |
6.2.3.2. �ېŊ��Ԃƒ��Ԑ\���E���Ԕ[��(����19���E42���E48��)
6.2.3.3. �ŗ�(����29���A�n���Ŗ@72����83)
6.2.4. �Ŋz�̌v�Z�Ǝd���Ŋz�T��(����30���A45��1��1��)
6.2.4.1. �ېŕW���z�Ɣ���Ŋz
6.2.4.2. �d���Ŋz�T��oi
| �A���R�C���X�����E���������ߘa���N9��26����66��4��471�ŕ���31(�s�R)90���S�I7��91(Ab)�̌��R�����n������31�N3��15����66��4��488�ŕ���29(�s�E)143��(Aa)�������E�W�����X�g1555��136-139�ŎQ�Ɓc�c����25�N6��10���`30���̂w�̉ېŊ��ԂɊւ��A�����w���i�ېŎd����j���_�����������6��28�����A�������n��������7��31�����B�w�́A����25�N6��17���A�ؒJ�M����������n��5g��2��3475�~�ōw�����A����26���A�����n���Ђ�2��0915�~�Ŕ��p�����B�{���ېŊ��Ԃ̂w�̎��Y�̏��n���̑Ή��̊z�͂���݂̂ł������̂ŁA�ېŔ��㊄����100���ł������B ��RAa�c�c�u�ېŎ��Y�̏��n���̎����Ƃ́C���Y�ېŎ��Y�̏��n���������ɍs��ꂽ���C���Ȃ킿�C���Y�̏��n�ɂ����ẮC�����Ƃ��āC���Y���Y�ɌW�錠���i���L���j���ړ]�������������v�B�c�c�����m���`�ƈႤ�ƌ����Ă���B�X�Ɂu����ł̉ېőΏۂ��w���Y�̏��n���x�Ƃ�������s�ׂƂ���C���̑Ή��̊z���ېŕW���Ƃ����ɂƂǂ܂����Ŗ@�̏ꍇ�Ƃ́m�����Ŗ@�A�@�l�Ŗ@�́n�O����قɂ�����̂ł���B���������āC����ł̉ېŕW���Ƃ��Ă̑Ή��̊z�̎Z��ɓ�����C�����m���`�̍l����������]�n�͂��蓾��Ƃ��Ă��C����ɂ��Ή�����̎����̎����������ɓ��Y���Y�̏��n���̎����ƂȂ���̂ł͂Ȃ��B�v�ŔO�����B �T�i�RAb�́u����łɂ��Ă��C�����錠���m���`���Ó�����B�c�c����Ŗ@�R�O���P���P���ɂ����u�ېŎd������s�������v�Ƃ́C�d����̑�����ɂ����āC���Y���Y�̏��n���ɂ��āC�������s�̍R�قȂǂ̖@�I��Q���Ȃ��Ȃ�C�Ή������ׂ��������m�肵�������������̂Ɖ�����̂������ł���C���̂悤�ɉ����邱�Ƃ��C����i�K�̐i�W�ɔ����ŕ��S�̗ݐς�h�~����Ƃ����d���Ŋz�T���̐��x��|�ɍ��v������̂ł���B�v�c�c�����m���`���̗p�B�A�����_�͈�RAa�Ɠ����B �v���p�e�B�G�����E�����n������31�N3��14�����^1481��122��(Ba)�i���n�����g��������Ŋҕt�_���j�c�c�u�ېŎ��Y�̏��n���ɂ��Ή������錠�����m�肵�����_�ŁC�ېŎ��Y�̏��n���������Ƃ݂�̂������ł���C���@�R�O���P���P���ɂ����w�ېŎd������s�������x�ɂ��Ă��C�ېŎ��Y�̏��n���ɂ��Ή������錠�����m�肵�������������̂Ɖ�����̂������ł���i���̈Ӗ��ŁC����łɂ����Ă��C�����錠���m���`���Ó�����B�j�B�v�c�c�����m���`���̗p�c�c���������ߘa���N12��4���Ŏ�269������13351����31(�s�R)106��(Bb)�ł��ێ��B �����n������31�N3��15������29(�s�E)144��(Ca)�c�c�u����Ŗ@�R�O���P���P���ɂ����w�ېŎd������s�������x�́C���Ǝ҂����ƂƂ��đ��̎҂��玑�Y��������ꍇ�ɂ����铖�Y�ېŎ��Y�̏��n�������ꂽ�����������̂ł���C����́C���n�l�̉��Ő������t�����l������l�Ɉړ]���邱�Ƃ��m�肵�����Ɖ�����̂������ł����āC��̓I�ɂ́C����ł̉ېł̑Ώۂł���t�����l�̈ړ]�̌����ƂȂ�ېŎ��Y�̏��n�����C�Ⴆ�C����̎x���C���Y�̈��n�����ɂ���ĊO���ɔF�������Ɏ�������ԁC���Ȃ킿�C�ېŎ��Y�̏��n���ɌW�錠�����͍����m�肷��Ɏ�������Ԃ������������w���v�c�c�����m���`���̗p�c�c�T�i�R���������ߘa���N9��26����31(�s�R)96��(Cb)�ňێ������������m���`�̍̔ۂɂ��Ė���������Ă���B ���n���ߘa2�N6��11������30(�s�E)149��(Da)�c�c�u����Ŗ@�Q�W���P���{�����c�c�����Ɏ������K���݂̂Ȃ炸�C�u���ׂ��v���K��������Ɋ܂߂Ă��邱�Ƃ��炷��C����Ŗ@�́C�[�Ŏ҂̜��ӂ��������C�ېł̌����������Ƃ����ϓ_����C�ېŎ��Y�̏��n���ɂ��Ή������錠�����m�肵�����_�ł��̎��ׂ��Ή����擾�������̂Ƃ��āC���̎��_�̑�����ېŊ��Ԃ̉ېőΏۂƂ��闧��ɗ��v�B�i�P5�Ł�321.03��|�f�Պ�����Ў����E�Ŕ�����5�N11��25�����W47��9��5278�ŕS�I7��65���Q�Ƃ��Ă���j�c�c��㍂���ߘa2�N11��27���ߘa2(�s�R)97��(Db)���p�c�c�����m�����̗p�������R�̕\����ς��Ă��Ȃ��B �����������E�����n������30�N3��6����65��2��171��(Ea)�E������������30�N9��5����65��2��208��(Eb)�i�㍐���p�A�㍐�s�j�c�c�����m���`�Ɍ��y���Ă��Ȃ��BEa���c�u���Y�̏��n�Ƃ́C���Y�̓��ꐫ��ێ����C���̏��L���𑼐l�Ɉړ]����s�ז��͂���ɓ������邱�Ƃ̂ł���s�ׂ������v�B �_�˒n������24�N3��29���Ŏ�262������11924(Fa)�m��c�c�����m���`�Ɍ��y���Ă��Ȃ��B�u�w�ېŎd������s�������x�Ƃ́A�y�n�A�����ɂ��ẮA���n�������������Ƃ݂�ׂ��ł���A�y�n�Ɋւ��ẮA����̎x�����������A���A���L���̈ړ]�o�L�̐\�����������_��A�����Ɋւ��ẮA���̈��n�������s���A����ɂ����Ďg�p���v���\�ƂȂ������_�ȂǁA���Y�_������̓��e�ɉ����āA���n���̓��Ƃ��č����I�ł���ƔF�߂�����Ɖ�����v�B �������CENTER PARK�����E�����n���ߘa2�N12��22������31(�s�E)150�����p�c�c�u�����̓R�J�E�R�[���E�G�X�g�ɑ��Ď����̔��@�̐ݒu�ꏊ����邱�ƁC���Ђ̏]�ƈ����������̔��@�ւ̏��i�E���ޗ��̕⊮�C������̉���C�@�B�̕ۑS�E�C���C�P�����̂��߂ɐݒu�ꏊ�֗������邱�Ƃ�F�߂邱�ƁC��e��̏����ɋ��͂��邱�ƁC�����̔��@�Ɍ̏Ⴊ�������ꍇ�͒����ɓ��ЂɘA�����邱�ƁC�����̔��@�ɌW��d�C�����S���邱�ƂƂ������̋`�����C����C�R�J�E�R�[���E�G�X�g�͌����ɑ��Ĕ̔����i�̂Q�O���ɑ�������z��̔��萔���Ƃ��Ďx�����`�����v�B�u�{������Ɋ�Â��������x������̔��萔���́C�������R�J�E�R�[���E�G�X�g�ɑ��Ē���ɑ���Ή��ł���v�B�u�{�����菑�ɂ͔̔��萔���ɂ��āu���������C�����P�T�������v�Ƃ̋L�ڂ����邱�ƂɏƂ炷�ƁC�e���̂P�����疖���܂łɒ����ɑ��C���̑Ή��Ƃ��Ĕ̔��萔���̎x�����錠������������v�m�����m���`�Ɠ��l�n�B �@�u�����́C�R�J�E�R�[���E�G�X�g�̏]�ƈ����������̍Ō�̖K����ɔ��㍂����߂��Ƃ����������{�����菑�̒��߂̎����ł��邱�Ƃ��_����e�ł���|���咣����v���A�u�R�J�E�R�[���E�G�X�g�̏]�ƈ����ɂ��K��i���㍂�̊m�F�j�͂P�����̂����ɕ�����ɋy�Ԃ��Ƃ����蓾��i�b�P�R�j�Ƃ���C���ʂƂ��ē��Y���̖K�␔���P��ł������ꍇ�ł��C���ꂪ���Y���ɂ�����ŏI�̖K��ł��邩�ۂ��́C���Y���̖������o�߂����Ƃ��Ɋm�肷��̂ł����āC���Y�K����̎��_�ɂ����Ă͖����m�肵�Ă��Ȃ����̂Ƃ��킴��Ȃ��B�v �����n���ߘa5�N3��9���ߘa2(�s�E)360��394�����p(�傽�鑈�_�͖@�l�Ŗ@��̌������p���Y�̎擾��)�c�c�u�����y�тo�T�Ђ́A�����Q�V�N�X���P�V���A�~���[�Z�����`�̕��@�ɂ��p���b�g���i��ʎY���ł�����x�̔\�͂�L����ˏo���`�@�y�ѐ��䑕�u���o�T�Ђ��������A����������ɕ�V���x�����|�̐����_�����������v�B �u���̈��n����v���鐿���_��ɂ����Ắc�c�u�ېŎd������s�������v�́A�ړI���̑S���������������������n���̂��������������Č�����v�B�c�c�����m���`�ƈقȂ����Ƃ��Ă���悤�ɓǂ߂����ŁA�@�l�Ŗ@��̎擾���Ɠ����ł���Ƃ��Ă���B |
6.2.4.2.a. ���z�ɂ��T��
| �Љ���@�l�䂽����������E���É��n���ߘa6�N7��18���ߘa4(�s�E)67�����p�E���É������ߘa7�N1��30���ߘa6(�s�R)69���T�i���p(�q���q���u�Љ���@�l�����Y�����]���҂Ɏx�����H���́u�ېŎd����ɌW��x���Ή��v�Y�����v�V�E������Watch�d�Ŗ@No.191�A�c���[�V�E�W�����X�g2025�N10�����f�ڌ����A���䍎�F�E�W�����X�g1610���d����6�N162-163��) �@�����@�����́A�����Q�T�N�S���P�����畽���Q�X�N�R���R�P���܂ł̊ԁA����������É��s�����͈��m�����i���É��s�ȊO�j�ɏ��݂��A��Q�ґ����x���@�Q�X���P���̎w������P�R�̎��Ə��i�{���e���Ə��j�ɂ����āA���w��ɌW�鐶�����A�A�J�ڍs�x���y�яA�J�p���x���a�^�i�A�J�p���x���a�^���j�̊e��Q�����T�[�r�X�i�{���e�����T�[�r�X�j�ɌW�鎖�Ƃ��s���Ă����B�����́A�{���e���Ə��ɂ����āA���p�҂ɑ��Ė{���e�����T�[�r�X��������A��]���闘�p�҂ɐ��Y�����̏����A���Y���p�҂�����ɂ���Đ��Y�������i���s��Ŕ��p����Ȃǂ��A���̔��p�v���̂����̈�蕔����{���H���Ƃ��ė��p�҂Ɏx�����Ă���B �@���_�@�{���H��������Ŗ@�R�O���P���ɋK�肷��ېŎd����ɌW��x���Ή��ɊY�����邩 �@���|�@�������p�@�u����Ŗ@�́A�u�ېŎd����v�ɂ��āA���ƂƂ��đ��̎҂��玑�Y������A�Ⴕ���͎�A���͖̒��邱�Ɓi���̎҂����ƂƂ��Ė̒��������Ƃ����ꍇ�ɉېŎ��Y�̏��n���ɊY��������́j�ƒ�߂�i�Q���P���P�Q���j����A����x�����ېŎd����ɌW��x���Ή��ɊY�����邽�߂ɂ́A���Y�x������҂����ƂƂ��Ė̒��������Ƃ����ꍇ�ɁA���Y�x�������Y���́u�Ή��v�i�����W���j�ƔF�߂���K�v������B �@�����āA��L������������ł̐��i�y�щېł̎d�g�݂��炷��A����Ŗ@�́A����x�����]�ł��\�Ȓ��x�Ɍʋ�̓I�Ȗ̒��ƌ��т��Ă���ꍇ�ɉېőΏۂƂ����|�ł���A�����́u�Ή��čs����E�E�E�̒v�Ƃ́A��̓I�ɂ���Ďx�����������Ƃ����Ή��W���F�߂���悤�Ȗ̒��Ӗ�������̂Ɖ������B �@���������āA����x�����ېŎd����ɌW��x���Ή��Ƃ��Ďd���z�T���̑ΏۂƂȂ�̂́A���Y�x�����ʋ�̓I�Ȗ̒������Ƃɂ���Đ������Ƃ����Ή��W���F�߂��邱�Ƃ��K�v�ƂȂ�Ƃ����ׂ��ł���B�v �@�u�{���e��Ə��̗��p�҂́A�����ɂ������{���e�����T�[�r�X���p�̈�Ƃ��āA����̒m���y�є\�͂̌��㓙�̂��߂̌P���Ƃ��Đ��Y�����ɏ]�����Ă���v�B �@�u�{���e���Ə��̗��p�҂́A�����Ƃ̊ԂŁA�����A�ϔC���̌_���������Đ��Y�����ɏ]�����A�����ɖ���������t�Ƃ��Ė{���H������̂��Ă���̂ł͂Ȃ��A�����ɂ��{���e�����T�[�r�X�̈�Ƃ��āC���Y�����ɌW�鎖�Ƃ̎������琶�Y�����ɌW�鎖�ƂɕK�v�Ȍo����T�������c�z�i��]���j�̕��z�Ƃ��Ė{���H������̂��Ă���v�B �@�u�����́A�{���e�����T�[�r�X�̈�Ƃ��āA�{���e���Ə��̗��p�҂ɑ��A�H���x�����܂ސ��Y�����̋@�����Ă�����̂ł����āA�{���H���͐��Y�����ɂ�鐬�ʕ��̔̔�����ɓ]�ʼn\�Ȓ��x�ɐ��Y�����ւ̏]���ƌ��т��Ă���Ƃ͂����Ȃ�����A�{���H���̎x�������p�҂ɂ��̒ɑ��锽���t�ł���Ƃ͔F�߂�ꂸ�A�{���H���̎x���́A���Y�����ւ̏]���ɔ����̒������ƂɑΉ����Ă���Ƃ͂����Ȃ��B���������āA�{���H��������Ŗ@�R�O���P���ɋK�肷��ېŎd����ɌW��x���Ή��ɊY������ƔF�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�v |
6.2.4.2.a.�A �����㍂�ɑ���ېŔ���̊�����95���ȏ�̏ꍇ
6.2.4.2.a.�C �����㍂�ɑ���ېŔ���̊�����95�������̏ꍇ�܂��͉ېŔ��㍂��5���~���̏ꍇ
| �C�c�Z�����Ў����E�����n������9�N5��27������8(�s�E)4������1648��60�Ŋ��p�m��S�I4��83�c�c���z����������y�n�ƈꊇ���n�����ꍇ�̉ېŎd����ɌW�����Ŋz�̍T���Ŋz���ꊇ���z�������ɂ��v�Z���Ċm��\����������C�v�Z���@�̌��𗝗R�Ƃ��ČʑΉ������ɂ��v�Z�Ɋ�Â��Ă����X���̐����ɑ��C�ꊇ���z��������K�p���Ă�������ł̍X���̈ꕔ����������C���p���ꂽ����B |
| ���������N�Z���^�[�o�e�h������Ў����E�����n������24�N9��7������23(�s�E)184���Ŏ�262������12032���p�m��(�A�؏���E�W�����X�g1474��139��)�c�c�����EX�Ђ͓������Ƃ̊ԂŖ{���{�ݐ����^�c���ƌ_�����������B�_����z�͖�17.8���A�����{���{�݂̐����Ɋւ���Ήۂ͖�10.5���Ƃ��Ă����B��������32���Ŏx�����Ƃ��Ă����B�������{�z��9.5���A����������1���BX�́A����20�N1��28���`���N3��31���̉ېŊ��Ԃɂ����Ċ���萔�����̎x�������A���ꂪ����Ŗ@30��2��1���C�u�ېŎ��Y�̏��n���ɂ̂ݗv����ېŎd����v�ɓ�����Ƃ̑O��Ő\���������B�Ŗ������͓������u�ېŎ��Y�̏��n���Ƃ��̑��̎��Y�̏��n���ɋ��ʂ��ėv����ېŎd����v�ɓ�����Ƃ̑O��ōX�����������A�ٔ������������ێ������B |
| �G�[�E�f�B�[�E���[�N�X�����E�����n���ߘa2�N9��3������30(�s�E)559���F�e�E���������ߘa3�N7��29���ߘa2(�s�R)190������������E�Ŕ��ߘa5�N3��6�����W77��3��440�ŗߘa4(�s�q)10�����pix(�c�����E�W�����X�g1555��10�ŁA�������E�W�����X�g1563��134�ŁA���R�R���E�W�����X�g1557��164�ŏd����02�N�A����M�q�E�W�����X�g1586��10�ŁA�ЎR���q�E�V�E������Watch�d�Ŗ@No.179�A�n�ӎ��E�Ō�230��78�ŁA�R�{��E�W�����X�g1592��110�ŁA���������Y�E�@�w�Z�~�i�[830��114�ŁA�������E�W�����X�g1597���d����5�N178-179��)�c�c����(X��)�͓]���ړI�ŏW���Z���(�}���V����)84�����w�����A�ʑΉ������ɂ�肱�̍w���ɌW��ېŎd����(�{���e�ېŎd����)���ېőΉ��ېŎd����ɋ敪�����O��ŁA�w���ɌW�����Ŋz�̑S�z���w�����̑�����ېŊ��Ԃ̎d���Ŋz�T���̊z�Ƃ��Đ\�����Ă����BX�́A�}���V�������w�����Ă���]���܂ł̊ԁA�I�����Y�Ƃ��Čv�サ�Ē���(��ېŎ��)����̂��Ă������Ƃ���A�Ŗ������́A�{���e�ېŎd����͋��ʑΉ��ېŎd����ɋ敪�����O��ŁA�w���ɌW�����Ŋz�S�z�ł͂Ȃ��A�ېŔ��㊄�����悶���z�������d���Ŋz�T���̊z�ƂȂ�Ƃ���X�������������B 95�����[���̌������ɂ��āw����23�N�x �Ő������̉���x648�ňȉ��Q�ƁB ��R(�����F�e)�c�c�{���e�ېŎd����͉ېőΉ��ېŎd����ɓ�����B �T�i�R(����������B�������p)�c�c�{���e�ېŎd����͋��ʑΉ��ېŎd����ɓ�����B�ߏ��\�����Z�łɊւ����Œʑ��@65��4��1���ɂ����u�����ȗ��R�v�͔F�߂��Ȃ��B �ō��ٔ��|�c�c�u�P�@����Ŗ@�́A���Y�A���ʓ��̊e�i�K�œ�d�A�O�d�ɐł��ۂ���Đŕ��S���ݐς��邱�Ƃ�h�~���A�o�ςɑ��钆�������m�ۂ��邽�߁i�Ő����v�@�P�O���Q���j�A�ېŊ��Ԓ��ɍs�����ېŎd����ɌW�����Ŋz�Y�ېŊ��Ԃ̉ېŕW���z�ɑ������Ŋz����T��������̂Ƃ��Ă���i����Ŗ@�R�O���P���P���j�B�����Ƃ��A���@�́A����̏ꍇ�ɂ����ē��Y�ېŊ��Ԓ��ɍs�����ېŎd����ɂ��p�r�敪�����炩�ɂ���Ă��Ȃ��Ƃ��́A�ېŎd����ɌW�����Ŋz�ɁA�ېŔ��㊄���A���Ȃ킿�A�ېŊ��Ԓ��̏���̔��グ�̑��z�ɐ�߂�ېŎ��Y�̏��n���ɌW�锄�グ�̊������悶�Čv�Z������@�ɂ��T���Ώێd���Ŋz���v�Z������̂Ƃ��i�����Q���Q���j�A�܂��A����y�ѐ��������̕ۑ����Ȃ��ꍇ�ɂ͌����Ƃ��ē��Y�ېŎd����ɌW�����Ŋz�̍T����F�߂Ȃ����̂Ƃ���i�����V���j�ȂǁA�ېł̖��m���̊m�ۂ�K���Ȓ��ł̎����Ƃ��������̖ړI�Ƃ̒��a��}�邽�߁A�ŕ��S�̗ݐς������Ă��ېŎd����ɌW�����Ŋz�̑S�����͈ꕔ���T������Ȃ��ꍇ�����邱�Ƃ�\�肵�Ă�����̂Ƃ������Ƃ��ł���B �@�����āA�ʑΉ������ɂ��T���Ώێd���Ŋz���v�Z����ꍇ�ɂ����āA�ŕ��S�̗ݐς�������ېŎ��Y�̏��n���Ɨݐς������Ȃ����̑��̎��Y�̏��n���̑o���ɑΉ�����ېŎd����ɂ��ꗥ�ɉېŔ��㊄����p���邱�Ƃ́A�ېł̖��m���̊m�ۂ̊ϓ_�����ʂɍ����I�Ƃ�����̂ł���A�ېŔ��㊄����p���邱�Ƃ����Y���Ǝ҂̎��Ƃ̏ɏƂ炵�č����I�Ƃ����Ȃ��ꍇ�ɂ́A�ېŔ��㊄���ɏ����銄����K�ɗp���邱�Ƃɂ��ʂɐ�����}�邱�Ƃ��\�肳��Ă���Ɖ�����邱�Ƃɂ��ӂ݂�A�ېŎ��Y�̏��n���Ƃ��̑��̎��Y�̏��n���̑o���ɑΉ�����ېŎd����́A���Y���ƂɊւ��鎖���₤���ƂȂ��A���ʑΉ��ېŎd����ɊY������Ɖ�����̂�����Ŗ@�̎�|�ɉ������̂Ƃ����ׂ��ł���B���̂悤�ɉ����邱�Ƃ́A�ېŎd������ېŎ��Y�̏��n���u�ɂ̂݁v�v������́i�ېőΉ��ېŎd����j�A���̑��̎��Y�̏��n���u�ɂ̂݁v�v������́i��ېőΉ��ېŎd����j�y�ї��ҁu�ɋ��ʂ��āv�v������́i���ʑΉ��ېŎd����j�ɋ敪���铯���Q���P���̕����ɏƂ炵�Ă����R�ł���Ƃ������Ƃ��ł���B �@��������ƁA�ېőΉ��ېŎd����Ƃ́A���Y���Ǝ҂̎��Ƃɂ����ĉېŎ��Y�̏��n���ɂ̂ݑΉ�����ېŎd����������A�ېŎ��Y�̏��n���݂̂Ȃ炸���̑��̎��Y�̏��n���ɂ��Ή�����ېŎd����́A�S�ċ��ʑΉ��ېŎd����ɊY�������Ɖ�����̂������ł���B�v �@�u�Q�@�O�L�����W���ɂ��A�{���e�ېŎd����͏㍐�l���]���ړI�Ŗ{���e�������w���������̂ł��邪�A�{���e�����͂��̍w��������S�����͈ꕔ���Z��Ƃ��Ē��݂���Ă���A�㍐�l�́A�]���܂ł̊ԁA���̒����������Ƃ����̂ł���B��������ƁA�㍐�l�̎��Ƃɂ����āA�{���e�ېŎd����́A�ېŎ��Y�̏��n���ł���{���e�����̓]���݂̂Ȃ炸�A���̑��̎��Y�̏��n���ł���{���e�����̏Z��Ƃ��Ă̒��݂ɂ��Ή�������̂ł���Ƃ������Ƃ��ł���B �@����āA�{���e�ېŎd����́A���̏㍐�l�̎��Ƃɂ�����ʒu�t����㍐�l�̈Ӑ}���ɂ�����炸�A���ʑΉ��ېŎd����ɊY������Ƃ����ׂ��ł���B�v �⑫�F�ߘa2�N�x�Ő�������A���Z�p�������ɌW��ېŎd����͒ʏ�̎d���Ŋz�T���̑ΏۊO�B �ޗ�F���Q���G�X�e�[�g�����E�����n���ߘa���N10��11������29(�s�E)590�����p�E�����n���ߘa���N10��16������29(�s�E)590���p���E���������ߘa3�N4��21���ߘa��(�s�R)281���ꕔ���p�A�ꕔ�ύX(�ߏ��\�����Z�ŕ��ی��菈���������)�E�Ŕ��ߘa5�N3��6���ߘa3(�s�q)260���j������(�ߏ��\�����Z�ŕ���) |
�Ŗ����s��̃����b�g�Ƃ��Ă��}�b�`���O(matching)�E��������p�c�c�Ⴆ��6.1.2.1.�̂a���E�ł��悤�Ǝv���Ƃ��A��������������邩�d����傫�����������邱�Ƃ��l������B�������A�a����������������������悤�Ƃ��Ă��A�b�͂a����̎d�����������������������Ȃ��̂ŁA�a�Ƃb�̗���������A�a����������������������Ă��Ŗ����ɉR�����i�`�E�a�Ԃ����l�j�B�Ƃ͂����A�Ŗ������������������邱�Ƃ͂ł��Ȃ�����A��͂��Ȃ���ΒE�ł͂���B�}�b�`���O�́A�����ېł̕����ł�������x�͈Ӗ������B�������A���^�̂悤�ɁA�x���҂̑��ōT�����ꂸ���l�̕��ŏ����ɉ��Z�����i�܂��d�ېł�����j�ꍇ�A�}�b�`���O���Ȃ��B
6.2.4.2.b. ����E�������̕ۑ��`��(����30��7��)
�Ŕ�����16�N12��16�����W58��9��2458�ŕS�I7��94(��3.1.1.4.�k������)�Ŕ�����17�N3��10�����W59��2��379�ŕS�I7��110�c�c����s���̐F�\�����F��������͓K�@�B
����9�N3��31���܂Œ����܂������������̕ۑ��`���ł��������A���͒����y�����������̕ۑ��`���ɂȂ��Ă���B�C���{�C�X���������ւ̒n�Ȃ炵�B(���Œ��p���t2020.6)
6.2.4.2.c. �ȈՉېŐ��x���v�����(����37��)
����Ŗ@������b���̊ԉv�Ŕᔻ�������������A�c�_�̒��S�͉ېōŒ���i����9��:����3000���~�A����1000���~�j�ȉ��̏��K�͎��Ǝ҂̉v�ł����J��A�ȈՉېŐ��x(����37��)�ɂ������B���������̊ȈՉېŐ��x�F�ېŔ��㍂��5���~�ȉ��̎��Ǝ҂ɁA���グ�ɂ�����Ŋz��80%�i�����Ƃ̏ꍇ��90%�j�����z���d���Ŋz�Ƃ݂Ȃ��āA�T�����邱�Ƃ�F�߂Ă����B
�c�c���ۂ̎d������80%�����̎��Ǝ҂ɂ͉v�ł��������B6.1.2.1.�̂a��80���̎d������K�p�����ꍇ
���̌�̖@�����@�K�p����̉ېŔ��㍂�F5���~��4���~��2���~��5000���~
�݂Ȃ��T�����F�ꗥ80%�@���Ǝ�ɉ�����90%�A80%�A70���A60%�A50%�A40%��6�i�K
����:����Ŗ@�����̍ۂ̒�R�c(1)����҂̒�R�@(2)������Ƃ̒�R�c�ȈՉېŐ��x���B
6.3. ����Ŗ@�ɂ����镡���ŗ����C���{�C�X����
6.3.1. ����28�N�x�Ő������ɂ��y���ŗ��ƓK�i���������ۑ������̓���
6.3.2. �y���ŗ��̓���
COLUMN6-5 �y���ŗ��̑Ώۂ̐�����
6.3.3. �C���{�C�X�����̓���
6.3.3.1. �K�i���������ۑ����������܂ł̌o�ߑ[�u
6.3.3.2. �K�i���������ۑ�����(��6.1.2.1.��7��A��8���r)
6.4. ����ېłƐŐ����v
6.4.1. �{�߂̍\��
6.4.2. �ΘJ������(wage tax)�Ə���ېł̗ގ���
COLUMN6-6 ��I�����łƏ���ېł̍��ق͈ӊO�Ə������H(��4.1.1.2.)
6.4.3. ���ڐł̏���ېʼn�
6.4.3.1 �t���b�g�łƂw��(Flat Tax, X Tax)
6.4.3.2. �x�o��
6.4.4. �ݐi�I�ȏ���ېł͉\���H
6.4.4.1. �ݐi���̃����N�}�[���F���E�ŗ��ƕ��ϐŗ�
�`��1000�҂��A990������B�a��2000�҂��A990������B�b��2000�҂��A1980������B(�t�����l�ŗ�10%)���t�����l�ł͏���z�ɔ�Ⴗ��̂ŁA�i�����K���i�ɓ��ʂɏd���ېł����Ă���Ȃǂ̎���Ȃ�����j����z����ɂ���t�i�I�ɂȂ肦�Ȃ��B�`�E�a�E�b�̉�����A����z����Ƃ����10/110�̕��S�B����^�����T�O�ɂ��A�t�����l�ł͋t�i�I�ł͂Ȃ����I�B
���t�����l�ł��t�i�I�ł���Ƃ����咣�́A��������Ƃ����l�����B�������A�`�Ƃb���r����A90/1000��180/2000�̕��S�B�t�i�I�ł���Ƃ����咣���X�ɁA�������҂̕������~���������Ƃ������Ƃ�O��Ƃ��Ă���(��������Ⴂ�ƕ\�����邱�Ƃ�����)�B�`�Ƃa���r����A90/1000��90/2000�̕��S�ł���B
��I�����T�O����r�̍ۂ̊�ƂȂ�ׂ��ł����ď���^�����T�O�����D��Ă���A�Ƃ������Ƃ̗��_�I�����E�N�w�I�����́A�܂��[���ɂ͋l�߂��Ă��Ȃ��B
�@���C�t�E�T�C�N���Ō���Ώ�������Ƃ��Ă��Ȃ��t�i���͑傫���Ȃ��Ƃ����咣����|���Y
�@���鎞���ɒ��~���Ă��A���N�ȍ~�ɏ����A��͂�t�����l�ł��ۂ�����B�ŏI�I�ɍ��Y���₳�Ȃ��i���ʂ܂łɎg����j�̂ł���A�����z����Ƃ��Ă�����z����Ƃ��Ă��t�����l�ł͔��I�ł����ċt�i�I�ł͂Ȃ��B����^�����T�O�_�҂͐��ɐ��U�I�Ȍ��n���������_���A���~�����������ɉ��̂ł��邩�璙�~�����͉ېőΏۂƂ��ׂ��łȂ��ƍl����B
�@�������҂̕��������̊����̍��Y���₷�A�ƌ����ď��߂āA�t�����l�ł͋t�i�I�ł���Ƃ����邱�ƂɂȂ�B�y�i��Y�z�|�����z�j�����U�����z�z�̌v�Z���ŁA�{���ɍ������҂̕������̊����������̂��̎��̖��B
�@�i[���]�ꐶ�U�Ő��������܂܂ł���Ƃ������Ƃ͂��܂�Ȃ��B���낱��Ő����ω����钆�A�{���Ƀ��C�t�E�T�C�N���őd�ŕ��S�̔z���Ɋւ���������l���邱�Ƃ��K�Ȃ̂��ɂ��āA�^��������B�j
6.4.4.2. �����ŗ��Ƃ��̖��_hv
6.4.4.2.a ��������̖��(��6.1.2.1.��8��)
6.4.4.2.b ��ŗ��ƍ��ŗ����K�p�����Ώۂ̋��
6.4.4.2.c ������ɑ�������H
6.4.4.2.d �ȈՉېł݂̂Ȃ��d���ꗦ(��6.1.2.1.��6��)
6.4.4.2.e �N�����b������̂��H
6.4.4.3. ��z���t���ɂ�����ł̗ݐi��
�����ŗ��ȊO�̒Ꮚ���҂ւ̔z�����@�������Ō��Łi���呠�Ȃ̐����j�c�c���X���������Ȃ��l�ɂƂ��Ă͌��ł���Ă����Ӗ��B
�������K���i�ɂ�����t�����l�Ŋz�ɂ�������҂Ɋҕt�B�葱���Ƃ��ẮA���݂̈�Ô�T���Ɠ��l�ɁA�����K���i�̏���z���L���ꂽ���V�[�g��������҂��m��\���Ő\�����A�ҕt����A�ȂǁB
�����z�v�Z���ʓ|�����z�̋��K���t�B�y�����K���i����z�T�Z�~�t�����l�ŗ��z�̎��ɂ��z��z��A�t�����l�ł��Ꮚ���҂̐�������������Ƃ����ᔻ���������Ȃ��Ȃ�Bhw
�����z�ҕt���ʓ|�������Ŕ[�ł̍ۂ����z�̐Ŋz�T�����i�����T���ł͂Ȃ����Ƃɒ��Ӂj�B�����Ŋz�����̐Ŋz�T���z��菬�����l�ɂ��ċ��K���t�Ƒg�ݍ��킹��A�ȂǁB
6.4.5. �⑫�F�ʏ�����Ƃ̓�d�ې�(���ȏ��ɂ͂Ȃ�)
��F�Ŕ���1000�~�̏��i��50%�̌ʏ����(�Ⴆ�Δ얞���łƂ��č����ɉې�)���ۂ���Ă���Ƃ���B1000�~1.5�{1000�~1.1��1600�ł͂Ȃ��A
(1000�~1.5)�~1.1��1650�Ŕ����邱�ƂɂȂ�B�łɐł�������itax on tax�ł���j�B
tax on tax�A���A���Ƃ͌�����Ȃ��B�ŕ��S�̏d�����s�s���Ȃ�A�ʏ���ł̐ŗ���������悢�B
�ʏ���ł̐ŗ���45.45%�ɂ���A�ŏI�I�ȉ��i��1600�ɂȂ�B�i1454.5�~1.1��1600�j
���ۏ���A��������̉��Ōʏ���ł̕��S��r������͍̂���B
�ꎞ���K�\�����łɂ��Ă̐����A�s�[�������������A���̍��͍����Ȃł͂Ȃ��Ȓ��Ԃ���ѐ����ƊԂ̓꒣�葈���B
6.4.6. �⑫�F����ł̕��S�͏���҂Ɛ��Y�҂Ƃŕ��S�����(���ȏ��ɂ͂Ȃ�)
���v�Ȑ��F����҂��x�����Ă��悢�ƍl�����P�ʂ�����̉��i�ŁA�ʂ�������ƒႭ�Ȃ��Ă����B�����Ȑ��F���Y�҂����Y���鎞�ɗv�����P�ʂ�����̔�p�ŁA�ʂ�������ƍ����Ȃ��Ă����B
�i���i����������Ă��\��Ȃ��B���鉿�i�̂Ƃ��ɍw���ł���ʂ����v�Ȑ��������Ă���A���鉿�i�̂Ƃ��ɋ����ł���ʂ������Ȑ��������Ă���j
����җ]���F�ύt���i����Ŏ��v�Ȑ���艺�̖ʐ�
���Y�җ]���F�ύt���i��艺�ŋ����Ȑ�����̖ʐ�
�@�d�ł̌o�ϓI�ȕ��S�����v�Ȑ��E�����Ȑ��̉��i�e�͐�(�X��)�ɂ���Č��܂�B
�@�W���I�ȍ����w�̋��ȏ��ł́A�N�ɉېł��邩�́A�o�ϓI�ɖ��Ӗ��ł����Ƙ_������B����͕t�����l�łɂ��Ă̂ݓ��Ă͂܂�����ł͂Ȃ��A�l�X�ȑd�ŁE���ۂɓ��Ă͂܂�B�Ⴆ�A�����N����[�߂��̂��J���҂݂̂ł��邩�J���҂Ǝ��Ǝ҂̐ܔ��Ƃ��邩�ŁA�o�ϓI�Ȍ��ʂ͕ς��Ȃ��B
�@�t�����l�ł̎d�g�݂Ƃ��āA�d�ŕ��S������҂ɓ]�ł���邱�Ƃ��@����\�肳��Ă���B������������@����\�肳��Ă���Ƃ��������ɂ������A�o�ϓI�ȕ��S�̋A���́A���{���ǂ������ł�����̂ł͂Ȃ��B
�@�t�����l�ŗ���5%����10%�ɏ㏸�����Ƃ��A�ō����i��1050�~����1100�~�ɏ㏸�����̂ł���A�@����\�肳��Ă���̂Ɠ��l�ɐŕ��S������҂ɓ]�ł���Ă���Ɓi�Z���I�ɂ́j������B�������A�l�i��1050�~�ɐ����u���ꂽ�̂ł���A�ŕ��S�͖@����̗\��Ƃ͈قȂ苟���҂������Ă��邱�ƂɂȂ�B�Ȃ��Ȃ�A�ō����i���㏸�����Ȃ��Ƃ������҂�1050�~10/110�̐ł�[�߂˂Ȃ炸�A�Ŕ����i��1000�~����955�~�i��1050�~100/110�j�ɂȂ��Ă���B
�@�u�Z���I�ɂ́v�̈Ӗ��\�\�����I�ɂ́A�l�グ�T�����̌`�Ōo�ϓI�ɕt�����l�ł̕��S�����Ƃ�����B
�@�����҂��łS����̈Ӗ��\�\�����ґ��̒N���ŕ��S���̂��͍X�Ɉł̒�(�@�l�ł̋c�_��z�N)�B
7. ���Y��
7.1. �����ŁE���^��
7.1.1. ����
7.1.1.1. �����ł̈Ӌ`
| ��400.01�Ő�������u�킪���Ő��̌���Ɖۑ�\21���I�Ɍ����������̎Q���ƑI���\�v290-291��(2000.7) (1)�@�����ɂ�鎑�Y�����͕�I�����T�O�ɂ��Ώ����ł���̂ŁA�����ېł̕⊮�Ƃ�������B���A�����Ŗ@��K�p����ƂȂ�ƒᏊ���K�w�ɂƂ��Đŕ��S���d�߂��邱�ƂƂȂ肪���Ȃ̂ŁA�����ł�Ƃ��i����9��1��16���j�����Ŗ@��K�p���邱�Ƃɂ���Ď��ۂ̐ŕ��S���y���Ȃ�B (2)�@�x�̍ĕ��z�Ƃ������������̂ŁA�������K�w�ɂƂ��Ă͐ŕ��S���y���Ȃ�Ƃ͌���Ȃ��B (3)�@�u�푊���l�̐��O�����ɂ������Z�ې��v[���]�����Ă͂Ȃ�Ȃ����Ƃł���ƍl����B�^�����ɔ[�ł��Ă����푊���l�Ƃ̊W�Ő��������Ȃ��B�܂��A�푊���l�i�K�ŏ��n�����ېł��Ȃ���Ȃ����������ɂ��āA�����ʼnېłɂ�葊���l�i�K�ł̏��n�����ېł��Ȃ��Ȃ�d�g�݂ł��Ȃ��B (4)�@�u���Y�̈��p���̎Љ�v�c�c�v����ɘV�l�Љ�ۏ�̌��Ԃ�Ƃ��Ă̑����ېŁB�{���͔푊���l�ւ̎Љ�ۏዋ�t�̕��i�̂����A�ی��̘_���ł͋��t������������Ȃ������j�A������ے肷��ׂ��B�����Ă��̎�|���炷��Ό��݂̊�b�T���͍�������B ��Y���F��Y�ɒ��ځB���Y�ŁB��ɉp�āB ��Y�擾���F�����l�̕x�̑����ɒ��ځB�����ł̕⊮�B��ɓƕ��B �������ǂ�������O�^�ɂ����Ȃ��B ���{�͈�Y�擾�ł̑̌n�ɑ����Ƃ���Ă��邪�A��q����悤�Ɉ�Y�ł̍l��������������Ă���B |
�@��4�����ɂ��ƁA1�N�Ԃ̎��S�Ґ��͖�157���l�A�����ł̉ېőΏۂƂȂ����푊���l���͖�15���l�B�ېŊ����i150858��1569050�j�͖�9.6���B�w�ǂ̉ƌv�ő����ł͉ۂ����Ȃ��̂����Ԃł���B��b�T���k���ɂ��A�ېŊ���������25�N�ȑO��4���ォ��オ�����Ƃ͂����A�����Ŋz��2��7989���~�A�t�����l�ł�1���ɑ�������Ŋz�i2���~�j������������x�B����ł����{�͏��O���Ɣ�ב����ł̉ېŊ�����Ŏ��͑傫�����ł���B
�@���Ȃ��炸�̍��ő����ł�p�~������A�����͔z��ҁE�q�̑����ɂ��đ����ł�p�~�����肷�铮�����������Ă���B�����Ŕp�~�Ƃ����Ă��A�����Łi���{�Ō����Έꎞ�����E���n�����j�Ƃ̊W�ŕK�������d�ŕ��S���y���Ȃ����ł���Ƃ͌���Ȃ����Ƃɗ��ӁB
��Y���@�Ƃ̊Wie
(1)�\�h���~�F�����ʂ����m�ɗ\���ł��Ȃ��̂ŁA���͒��~���g���ʂ����O�Ɏ��ʁ@�icf.���N���j
(2)�����F�q�ɘV��̖ʓ|�����Ă��炤���߂̐헪�@�i�����O���^�͂ł��Ȃ��j
| (3)�����F�q�̊�т��e�̊�тł����� (4)���^�̊�сF���^���邱�Ǝ��̂Ɋ�т����o�� |
�o�ϊw�I���f���ł�(3)��(4)�͈Ⴄ�Ӗ��������A�������E�ł̋�ʂ͗e�ՂłȂ� |
7.1.1.2. ���{�̑����ŁE���^�ł̓���
7.1.2. �����ŁE���^�ł̔[�ŋ`����
����1����3:�������͈②�ɂ����Y���擾�����l����1����4:���^�ɂ����Y���擾�����l(cf.��N���^�T�|�[�g�T�[�r�X�������24-1(�u��������t�_��Ɋւ��錠���v�̈Ӌ`))
�����ɏZ����L���Ȃ����݊O���Y�̎ɂ��đ��^�ł��ۂ���Ȃ��Ƃ��������3.1.3.4. 6�Ł�142.01���x�m�����E�Ŕ�����23�N2��18������2111��3��
���݂͏Z�������O�ɂ���ꍇ�ł����{���ЕۗL�҂ł���ꍇ��5�N���[���c����1����3�A1����4�A2���A2����2�B
�J���t�H���j�A�B�s���Y���^�����E������������19�N10��10���Ŏ�257������10797����19(�s�R)142��(�W���C���g�E�e�i���V�[���^�����Ƃ�����)hy
���{�ݏZ�̕v�w���A�����J�ݏZ�̑��q�v�w�ɕs���Y�^�������āB����12�N4��1���ȍ~��5�N���[���ɂ��A�ٔ����́A���^�ɂ�鏊�L���ړ]������4��1���Ȍ�ł���Ɣ��f�����B[���]���ʕt���^�̔���i�Ŕ����a60�N11��29�����W39��7��1719�Łj�ɏƂ炵�A���^�ɂ���������������3��29�����Ƃ݂�]�n�����茋�_�ɋ^��i�Ⴆ��2015�N��99�~��������Ƃ������ʕt���^�_���2014�N�ɒ���������A2014�N��90�~�i�������N10���̉���j�^�������Ƃ��Ĉ�����j�B
�����o�ŊO���M�������E���É���������25�N4��3����60��3��618��
���{�ݏZ�̑c������A�����J���ЂŃA�����J�ݏZ�̑��i�w�j�ɐM����ʂ��č��O���Y�i�A�����J����500���h���j�^���悤�Ƃ�������B�i�A�����J�ł͓��{�ƈقȂ�҂ł͂Ȃ����^�҂ɒ��ڂ��đ��^�ł̉ېŊW���l���邽�߁A�A�����J�ł����^�ł̉ېł��Ȃ��A�Ƃ����_���B�j
��R�@���Y�����u��v�ҁv�i�����Ŗ@4��1���j�ɓ�����Ȃ��Ƃ��āA���^�ʼnېłȂ��B
��R�@�c�����M����ݒ肵�����ɂw���M����v����L����ƔF�肵�u��v�ҁv�i�����Ŗ@4��1���j�ɓ�����Ƃ�����ŁA�u���e�ɊČ�{�炳��Ă����w�ɂ��Ă��c�����̖{���͒��v��̎���ł���ƔF�߂�v�A�u�w�́A�o������{���M���s���܂ł̊��Ԃ̂����č��ɂP�W�R���؍݂��Ă����̂ɑ��A���{�ɂ͂V�Q�������؍݂��Ă��Ȃ��|�咣����B�m���ɁA�ʏ�ł���A�؍ݓ����͏Z���f����ɓ������Ă̏d�v�ȗv�f�̈�ł��邪�A��L�̂Ƃ���A�{���ɂ����ẮA�w�͏o����Ԃ��Ȃ������ł���Ƃ�������Ȏ������������A�ނ��뗼�e�̐����̖{�����d�v�ȗv�f�Ƃ��čl�����ׂ��ł����A�؍ݓ����ɂ��Ă��A�{���M���s��́A�ނ�����{�ɂ�����Ԃ̕��������Ȃ��Ă��邱�ƂɏƂ炷�ƁA�w�̏o������{���M���s���܂ł̕č��ɂ�����؍ݓ��������{�ɂ�����؍ݓ�����蒷�����Ƃ́A��L�F������E����ɑ���Ȃ��v�B
7.1.3. �����ł̉ېŕ���
����2��:�������͈②�ɂ��擾�������Y�c�c�Z���E���Ђɂ��݊O���Y���܂ނ��Ⴂ����������B����20����2:�݊O���Y�ɂ��ĊO���Ŋz�T���B
�݂Ȃ��������Y:����3���`9����6(5���E6���݂͂Ȃ����^���Y)�c�c�푊���l���瑊�������Ɩ@���I�ɂ͂����Ȃ����A�o�ϓI�ɂ���ɋ߂��W�̂��́B�����ی���(3��1��1��)(����211.04�N�����������ی�����d�ېŎ����E�Ŕ�����22�N7��6�����W64��5��1277�ŕS�I7��34)�Ƃ��ސE�蓖��(3��1��2��)�Ƃ��B9�����u�Ή����x����Ȃ��ŁA���͒������Ⴂ���z�̑Ή��ŗ��v�����ꍇ�v�Ƃ���������E���I�K���݂��Ă���Bms
| 6�Ł�413.01�������Y�̎�ށE�͈�(1) �_�n����/���告�������E�Ŕ����a61�N12��5����33��8��2149�ŕS�I7��80���Ŕ����a61�N12��5����33��8��2154��id �@�_�n�̔���i���L���܂��j�����S�����ꍇ�A�y�n�i�]���z299���~�j���������Y�ɎZ������c�������1965���~���������ł���ƂȂ邩�i�[�Ŏ҂̎咣�j�A�y�n�͑������Y�łȂ��c��������͊m���ƔF�߂��Ȃ��������ł���ƂȂ邩�i�Ŗ����̎咣�j�B �@�_�n�̔���i���L������j�����S�����ꍇ�A�����ł̉ېō��Y�͔_�n�i�]���z2018���~�A��������t����1600���~�͗a����ł��葊�����F�[�Ŏ҂̎咣�j���A�c�����2939���~�i��t�����͑������łȂ��F�Ŗ����̎咣�j���B ����\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\���� ����̋��K���L��(1965���~)�@�@�@�@�y�n���L��(2018���~?) �y�n���L���ړ]������(299���~?)�@�@�����c�����(4539���~) �����c����x���`��(-1965���~) �@�@�y�n���n�`��(-4539���~?) ���| �@�_�n�̔��傪���S�����ꍇ�A�u�����ł̉ېō��Y�́c���L���ړ]���������̍��I�����v�ł���A���́u���z�͉E�����_��ɂ�铖�Y�_�n�̎擾���z�ɑ�������1965��1470�~�v�B�u�ʒB�̒�߂�]�����@�ɂ��]��������̂Ƃ���Ă���_�n���̂Ɠ��l�Ɏ戵�����Ƃ͂ł��Ȃ��v�B �@�_�n�̔��傪���S�����ꍇ�A�u�y�n�̏��L���́c�����ł̉ېō��Y���\�����Ȃ��v�B�u�ېō��Y�ƂȂ�̂́A���������2939��7000�~�v�B �l�@ �@���L���ړ]���c�c���@�̌����ɏ]���Έӎv�̍��v�i�����_��j�����������B�������y�n�ɂ��ẮA�_��̉��߂Ƃ��ď��L���ړ]���͔����c������x����ꂽ���Ƃ���|�̓����݂����Ƃ������F�����肤��B�܂��A�_�n�̏ꍇ�́A�m���̋��̂��肽���A�Ƃ����������肤��B �@���L���ړ]�O�̔��告���c�c�y�n���L���A�����c������A�y�n���n�`���𑊑��B �@���L���ړ]�O�̔��告���c�c����̋��K���L���A�y�n���L���ړ]�������A�����c����x���`���𑊑��B �@���告�����Ắu�{�������ł̉ېō��Y�́c���I�����ł����āc�_�n�����Ɠ��l�Ɏ戵�����Ƃ͂ł��Ȃ��v�ɂ��āc�c�ʒB�ɏ]�����y�n�̕]����299���~�A���I�������_��ɏ]���ĕ]�������1965���~�B �@�ٔ����͂��̃M���b�v�ɂ���Ĕ[�Ŏ҂��������邱�Ƃ�F�߂Ȃ������B �@���告�����Ăɂ����āA1965�{299�|1965�Ƃ��Ă��܂��ƁA�[�Ŏ҂ɕs���ɗL���ɂȂ��Ă��܂��B������ō��ق́u�ېō��Y�v�ł���u���L���ړ]���������̍��I�����v�́u���z�́c1965��1470�~�v�ł����āu�_�n���̂Ɠ��l�Ɏ戵�����Ƃ͂ł��Ȃ��v�Ƃ��A1965�{1965�|1965�Ƃ����B�i���������L���ړ]��ɑ����������������Ăł���A�ېō��Y�͓y�n���L���ł���Ƃ��킴��������A�ʒB�ɂ��Ⴂ�]����F�߂�������Ȃ������ł��낤�B�j �@���@�����ł͖{���̌��_�͓����o����Ȃ��B�ʒB�Ɋ�Â��]�����������i��艺��肪���A�Ƃ����w�i������B�@���_�Ƃ��Ă̏œ_�́A�y�n(��]��)�Ȃ̂��A�y�n�ɌW����I����(����)�Ȃ̂��B �@���告�����Ăɂ����āA�y�n���L�����ېō��Y�Ɋ܂߂�ƁA���̕]���͒Ⴍ�Ȃ炴������Ȃ��i2018���~�j�B�����A���I�`���ł���y�n���n�`���告�����ĂƓ��l�ɕ]������ƁA�����_��Œ�߂�ꂽ����z�i4539���~�j�ŕ]�����邱�ƂƂȂ�B������2018�{4539�|4539�ł͔[�Ŏ҂ɕs���ɗL���ɂȂ��Ă��܂��B �@���̓_�A�y�n���n�`����2018���~�ł���ƕ]������Ȃ�A2018�{4539�|2018�ƂȂ�A�[�Ŏ҂ɕs���ɗL���ƂȂ�Ȃ��B�������A�y�n���n�`���Ƃ�������y�n�̕]���z�Ɠ����Ƃ��Ă��܂��ƁA���告�����Ăɂ����āu���L���ړ]���������̍��I�����v�̕]���́u�_�n���̂Ɠ��l�Ɏ戵�����Ƃ͂ł��Ȃ��v�Əq�ׂ����ƂƁA�������Ȃ��B �@�����ŁA���告�����Ăɂ����āA�ō��ق́A�y�n���L�����̂��ېō��Y����O���A�y�n���n�`���̕]���̖������킹�ĊO�����ƂŁA�����c������݂̂��ېőΏۂƂ���i��g�I�ɂ�0�{4539�|0�B�{���ł͎�t������̂�0�{2939�|0�j�Ƃ����B �@�w���͔����ɔᔻ�I�B�y�n���L��������Ɏc���Ă��Ȃ���ېō��Y�Ɋ܂߂Ȃ��ȂǂƂ��������͊�ɂ�����B�y�n���̂��̂����������ꍇ�ɂ́A�y�n�̎������i�ƒʒB�ɂ��]���Ƃ̃M���b�v�ɂ���Ĕ[�Ŏ҂������Ă��܂����Ƃ͔������Ȃ��Ƃ���A�����r��̏ꍇ�������告���ł����告���ł��]���M���b�v�ɂ��[�Ŏ҂̓���F�߂����Ȃ��Ƃ����͓̂s���悷���B cf.�����n������26�N1��24������24(�s�E)89���c�c�푊���l�����̏��L����y�n�i�_�n���܂ށB�j�̔����_���������C��t���������c����̎�̋y�є_�n�@����̓͏o�̑O�Ɏ��S�����ꍇ�ɂ����āC���y�n�̏��L���͎c����̎x���Ɠ����Ɉړ]����|�̓������̓���͂��̎������c����������̊m�ۂɂ��������ƁC�_�n�@����̓͏o���s���ɂ��@����̏�Q���Ȃ��������ƂȂǔ����̎���̉��ł́C�����ł̉ېō��Y�́C���y�n�ł͂Ȃ��C�������ɌW��c����������ł���B |
| 6�Ł�431.02�������Y�̎�ށE�͈�(2) ��쎖���E���ŕs���R��������17�N6��20���ٌ��E�ٌ�����W69�W217���E�啪�n������20�N2��4������17(�s�E)13���E������������20�N11��27������20(�s�R)9���E�Ŕ�����22�N10��15�����W64��7��1764�ŕS�I7��103at �푊���l����[���������ł̊ҕt�����i�ׂ��N���A�����l���i�ׂ������p���A�������B ��[�����ł̊ҕt���͔푊���l�����Ƒk�y�I�ɍl����ׂ����H �@�k�y���遨�����l���������̉ېł���B �@�k�y���Ȃ��������l���ꎞ�����Ƃ��ĉېł����B �ō��ق́A�ҕt���������������Y�ɓ�����Ɣ��f�����B(�ǂ��炪�L�����͐l�ɂ���ĈقȂ�) |
7.1.4. �����ł̉ېŕW���ƐŊz�̌v�Z
7.1.4.1. �����Ŋz�̌v�Z���@
7.1.4.1.a �ېʼn��i�̌v�Z���@
�}�\7-1 �����Ŋz�̌v�Z�̗����Q������11����2:�������͈②�ɂ��擾�������Y�̉��z�̍��v�z(12������ېō��Y)
����13�������T���́u�����J�n�̍ی��ɑ�������́v�Ɍ���B�܂��u�m���ƔF�߂�����̂Ɍ���v(14��)�B�c�c���������A��������m���ƔF�߂��Ȃ��������߂ɉېō��Y�Ɋ܂܂�Ȃ������i�ېʼn��i���������Ȃ������j���A���Y���ɂ��Č�ɑ����l���ٍς����A�Ƃ����ꍇ�ł����Ă��A�����Ŋz������I�ɒ�������邱�Ƃ͐��x��\�肳��Ă��Ȃ��B���@�_�Ƃ��Ă͋^�₪�c��B
| 6�Ł�414.01���T�� �ۏ؍����������E���É��n������10�N11��11������9(�s�E)3�����^1061��149�Ŋ��p�E���É���������11�N4��16������10(�s�R)38���Ŏ�242��138�Ŋ��pia�c�c�ۏ؍��̍��T��(�����Ŗ@13���A14��1��)���F�߂��Ȃ���������B |
| 4�Ł�414.01 �B�Y���o�������E�����n�����a53�N9��28�����a51(�s�E)123�����p�E�����������a55�N9��18�����a53(�s�R)76�����p�m�� �����E���_�@�`�̑������Y�ɑ�����L����Ђr�̏o���̉��z���A�����Y���z�����ɂ��]������ɍۂ��āA�����̑ސE�������z���A�����Y���z����T�����ׂ����Ɋ܂܂�邩�ۂ��B�i�ސE�����������ݒ肵�Ă���Ζ��Ȃ��T���ł���j ���|�@�T�i���p(�������p�E�m��)�m���ƔF�߂�����ɓ�����Ȃ��Ƃ����B (1)�l����(2)����Ђ̊���(3)�������̂Ȃ������̕]���̔�r�B (3)�ō��T����F�߂Ȃ������{���̌��_��(2)�Ɣ�ׂ�ƍ�����(1)�ɋ߂��Ƃ���������B �⑫�c�c��~�����t���͖��炩�Ɋm���ȍ��ł͂Ȃ��B���������t���́A���ݍ��Ƃ��đ��݂��Ă�����̂̏�����������邩������Ȃ����̂ł���A�������ɂ����Ă͊m���ȍ��ł���Ƃ��v���邪�A���݂͂�����m���ȍ��ł͂Ȃ��ƍl�����Ă���([���]���^��)�B�����̒�߂̂Ȃ����͊m���ƔF�߂���B �⑫�c�c�Ѝ��o���Ă����Ђ̏����Y��]������ꍇ�A�Ѝ������Ă���̂ł��̕��Ⴍ�]�������B�]���Ѝł����̗������Ă͂܂邩�v�l�@�B |
| �����n������22�N7��2������20(�s�E)721����57��4��879�Ŋ��p�E������������22�N12��16������22(�s�R)266����57��4��864�Ŋ��p(��ȏ͔@�E�W�����X�g1445��124��)�c�c�����[�ŋ`���҂���푊���l���C���@(��17�����O)266��1��4���y��5���̋K��Ɋ�Â��ĕ����Ă������Q�������y�ѓ����ɂ���ЍX���@�Ɋ�Â�����\�������̏����ɗv�����ٌ�m��V�x�����͑����Ŗ@13��2��2���y��3���́u���v�ɊY�����Ȃ��Ƃ��ꂽ����B |
7.1.4.1.b �����ł̑��z�̌v�Z
����15��:��b�T��lq3000���~�{600���~�~�����l���@�{�q�̐��ɒ��ӁB�Ŕ�����29�N1��31�����W71��1��48��nl�c�c�����Ōy���ړI�̗{�q���g�̉��g�ӎv�͗L���B����16��:��Y�擾�Ł��e�����l�̑����ɂ���Ď擾�������Y�݂̂��ېőΏۂƂȂ�ׂ������A��Y�œI�ɏC���B���@����̊e�����l�����@����̑������ɉ����Ĕ푊���l�̍��Y�𑊑������Ɖ��肵���ꍇ�̑��Ŋz���v�Z����B
7.1.4.1.c �e�����l����ю��҂̐Ŋz�̌v�Z
����17��:�����ł̑��z�~�e�����l�̉ېʼn��i�^�e�����l���̉ېʼn��i�̍��v�z| ���ŕs���R�����ߘa6�N7��3���ٌ��E�ٌ�����W136�W49��(�k���L�E�łŃ��߂���ǂ�����(��13��)�`�ُ����ƌ��߂��Ȃ����`)�c�c�Z�ɑS�đ���������|�̌����؏��⌾�B���́A��ʓI�Ɉ⌾�̖������咣���A�\���I�Ɉ◯�����E����(���@1031��)���咣�����B�a�����A�Z�����ɉ��������x�������B���̉������̑S�z���◯���̉��z�ُ���(���@1041��)�ł���Ƃ����O��(�����Ŗ@32��1��3��)�ŁA�ېŒ���(�Z�͑����Ŋz�����z������X������)���̑����Ŋz�z������X������(�@��[��������5�N���o�ߌ�B���Œʑ��@70��1��1���̏��ˊ��ԎQ��)�������B�a������A�������̑S�z���◯���̉��z�ُ����ł���Ƃ͌����ꂸ�A�Z���A�����ٌ̕�m�̗����ɐH���Ⴂ������A�������̑S�z���◯���̉��z�ُ����ł���Ƃ����O��łȂ��ꂽ�X�������͎�����ꂽ�B |
�A���ʂ̍��Y�擾�҂̑����ɒ��ڂ������Z�E���Ƃ�����B
����18��:�z��ҁE�q�E�e�ȊO����������ꍇ��20�����Z�B
����19����2:�z����͖@�葊�����܂���1��6000���~�̂����ꂩ�傫���z�܂Ŕ�ېŁB
����19��3�F�����N�ҍT���A����19����4�F��Q�ҍT��
����20��:���������T���c�����̊Ԋu���Z��(10�N�ȓ�)�ꍇ�ɂ��̒Z���ɉ����Đŕ��S���y������B
7.1.4.2. �@�葊�����ېŕ����̎�|
16���E17�������킹�čl����ƁA�����ł̑��z�́A��Y���ǂ̂悤�ɕ�������Ă��قړ��������ƂɂȂ邵�A���̑����̒��ŁA�������������҂Ə��Ȃ����������҂����ʂ���ŗ��͓����ł���B�����ɂ͓�̈Ӗ�������B[1]�����ł̕��S�����������邽�߂Ɏ��ۂ̈�Y�̕������B�������ϕ��������s�Ȃ����悤�ɉ�������X��������A�����j�~����B
[2]��l�̎q������Y�̑啔���𑊑�����ꍇ�ɐŕ��S���ߏd�ɂȂ邱�Ƃ�h���B
�����ŁA��Y�擾�ŁE�ݐi�ېł̗��O�ɑ����Ă��Ȃ��Ƃ����ᔻ������������B
�`�����S���A���q�a�E�b�����������B��Y�������c�ŁA�a��1���~�A�b��5000���~�𑊑������B
�@1.5���|4200����1.08���B�@��l5400�����������Ɖ���B
�@1000�~0.1�{2000�~0.15�{2000�~0.2�{400�~0.3��920
�@���z1840���B���a1840�~2/3��1227���~
�c�����S���A���q�d�E�e�����������B��Y�������c�ŁA�d��1���~�A�e��2���~�𑊑������B
�@3���|4200����2.58���B��l1.29�����������Ɖ���B
�@1000�~0.1�{2000�~0.15�{2000�~0.2�{5000�~0.3�{2900�~0.4��3460
�@���z6920���B���d6920�~1/3��2307���~
7.1.5. ���^�ł̈Ӌ`
�����ł��⊮:���O���^���ɂ�葊���ł�������邱�Ƃ�h���B�@�icf.�@�N�whz�ł͑��^�̎��R���d�����邩�Ř_���̓I�j
���{�ł�1�N���Ƃɉېł���(����21����2)���A���O���ł͗ݐϓI�ɉېł���������B
7.1.6. ���^�ł̉ېŕ���(��3.1.3.2. 6�Ł�422.01�����؏����^)
7.1.7. ���^�ł̉ېŕW���ƐŊz�̌v�Z(����21����7)(�d��70����2��5�F���n����)
[1]��x��1���~���^�@[2]1000���~�̑��^��10�N�ԌJ��Ԃ��ꍇ�@�̔�r(time value of money��)[1]�@200�~10���{(300�|200)�~15���{(400�|300)�~20���{(600�|400)�~30���{(1000�|600)�~40���{(1500�|1000)�~45���{(3000�|1500)�~50���{(9890�|3000)�~55����5039.5
[2]�@200�~10���{(300�|200)�~15���{(400�|300)�~20���{(600�|400)�~30���{(890�|600)�~40����20�{15�{20�{60�{116��231
7.1.8. ���������Z�ې����x(����21����9�ȉ�)
����16��������21����7���r����ƁA���^�̏ꍇ�ɐŕ��S���d���Ȃ肪���ł��邱�Ƃ�������B����15�N����������21����9�ȉ�:���O���^�ɂ��Ă��̐��x���I������ƁA���^���̑��^�ʼnېł��Ⴍ�}�����A���̌�ɑ��������ۂɑ��^���Y�Ƒ������Y�����v���đ����ł��ۂ����B�i���^�z�|2500���~�̔�ېŘg�c21����12�j�~20%�k21����13�l�B
���Y�̐���Ԉړ]�𑣐i����_���B�i��27�����ő��܂ށj
7.1.9. �\���E�[�t
7.1.9.1. �\��(����27��1��)
| �ňꏬ���ߘa3�N6��24���ߘa2(�s�q)103�����W75��7��3214��jz(�r�����q�E�W�����X�g1582��78-86�ŁA�����A�q�E�ʍ��W�����X�g261���s������S�I8��196����404-405�ŁA�����S��E�W�����X�g1570���d���ߘa3�N176-177�ŁA�T��B�ƁE�@��142��3-4��304-336��) �@�����@�푊���l������16�N2��28�����S�B�����l�̈�l�ł��錴��X���́A���N12��27���A��Y�������𗝗R�ɁA�����Ŗ@55���Ɋ�Â����@�̖@�葊�����i1/7�j�ō��Y���擾�����O��Ő\���iA�Њ���1��1185�~/���AB�Њ���2��1009�~/���A�ېʼn��i22��6374��4000�~�A�Ŋz10��7095���~�j�������B�]�����Ŗ������͍X�������iA�Њ���1��9002�~/���AB�Њ���6��4908�~/���A�ېʼn��i41��2068���~�A�Ŋz19��9989��9200�~�j�������BX�͍X�������̎�����𐿋������B �@�����n������24�N3��2������2180��18�Łi�����ۗL�����ЂɊւ��鎖���j�́AA�Њ���4653�~/���AB�Њ���3��1189�~/��(�����������n������24�N3��2���̘_���Ɋ�Â��Đ������v�Z��������1��9132�~/��)�ƕ]�����AX�̐\���Ŋz(10��7095���~)���镔���̍X����������������B������������25�N2��28���Ŏ�263������12157����R���ێ����A�m�肵���B�i�����p���u�����ۗL������25.9���̑��Ђ������ۗL�����ЂɊY�����Ȃ��Ƃ��ꂽ����v�W�����X�g1443��8-9��(2012.7)�A�a�J��O�u�����ۗL�����Ђ̐��l��̍������v�W�����X�g1448��8-9��(2012.12)�A�{�舻�]�u�����ۗL�������Q�T���ȏ�ł���]����Ђ��ꗥ�Ɋ����ۗL�����ЂƂ���]���ʒB�̍�������ے肵������v�@�w�Z�~�i�[�����E������Vol.12, 197��(2013/4/25)�A�i��F��u�����ۗL�����Њ����̕]�����@�̐���v�Ō�170��84-87��(2013.7)�A�≺����u����̕]����Ёv�Ŗ����ጤ��134��58-98��(2013.7.20)�A���{�玟�u�����ۗL�����Ђ̔����\�\�������ٕ���25�N5��28�������ƒʒB�����v�Ŗ��O��61��8��115-121��(2013.8)�A�R�������u�����ۗL�����̔����̌������\���ٔ�������v�Ōo�ʐM68��9��38-48��(2013.8)�A�ɓc���u�u�ʒB�s���Ǝi�@�ɂ��`�������W�i�]���ʒB�Ɋւ��镽��25�N�Q��28���������ٔ������ނƂ��āj�v�d�Ō���768��174��(2013.10)�A��ȏ͔@�u�����ۗL��������܁�������Ђ����Y�]����{�ʒB�ꔪ���(2)�ɂ��������ۗL�����ЂɊY�����Ȃ��Ƃ��ꂽ����v����]�_661��2-6��(�����2208��140-144��)(2014.3.1)���Q�Ɓj �@�����n������24�N3��2���Ɠ�����������25�N2��28����O�i�ƌĂԂ��ƂƂ���B �@X�\����:A�Њ���1��1185�~/���AB�Њ���2��1009�~/���B �@�O�i����:A�Њ���4653�~/���AB�Њ���1��9132�~/��(�������v�Z���������ꍇ�̒l)�B �@�܂�X�\�������O�i�����̕��������]���z���Ⴂ�B �@����26�N1��16���A��Y�������₪�������AX�͊�����6/7���擾�����B���N5��16���AX�́A�����]���ɂ��đO�i������O��Ƃ��A�����Ŗ@32��1���i��32��1��1���j�̍X���̐����iA�Њ���4653�~/���AB�Њ���1��9132�~/���A�ېʼn��i9��6080��5000�~�A�Ŋz4��4199��0400�~�j�������B�Ŗ������́A�����]���̐����͑����Ŗ@32��1���̑Ώۂł͂Ȃ��A�����\���ɂ�����]����O��Ƃ��ׂ��Ǝ咣���A�X�������ׂ����R���Ȃ��|���{���ʒm���������A���̑����l�̌��z�X�������ɔ��������Ŗ@35��3���Ɋ�Â��{���X�������iA�Њ���1��1185�~/���AB�Њ���2��1009�~/���A�ېʼn��i49��0410��9000�~�A�Ŋz23��2567��1800�~�j�������B �����Ŗ@32���i�X���̐����̓����j(��1��)�u�����Ŗ��͑��^�łɂ��Đ\�������o�����Җ��͌�������҂́A���̊e���̂����ꂩ�ɊY�����鎖�R�ɂ�蓖�Y�\�����͌���ɌW��ېʼn��i�y�ё����Ŋz���͑��^�Ŋz�i���Y�\�������o�����㖔�͓��Y���������C���\�����̒�o���͍X���������ꍇ�ɂ́A���Y�C���\�����͍X���ɌW��ېʼn��i�y�ё����Ŋz���͑��^�Ŋz�j���ߑ�ƂȂ��Ƃ��́A���Y�e���ɋK�肷�鎖�R�����������Ƃ�m�����̗�������l���ȓ��Ɍ���A�[�Œn�̏����Ŗ������ɑ��A���̉ېʼn��i�y�ё����Ŋz���͑��^�Ŋz�ɂ��X���̐����i���Œʑ��@���\�O���ꍀ�i�X���̐����j�̋K��ɂ��X���̐����������B��O�\�O���̓�ɂ����ē����B�j�����邱�Ƃ��ł���B ��@��\���̋K��ɂ�蕪������Ă��Ȃ����Y�ɂ��Ė��@�i���S�l���̓�i��^���j�������B�j�̋K��ɂ�鑊�������͕�②�̊����ɏ]�ĉېʼn��i���v�Z����Ă����ꍇ�ɂ����āA���̌㓖�Y���Y�̕������s���A���������l���͕���҂����Y�����ɂ��擾�������Y�ɌW��ېʼn��i�����Y���������͕�②�̊����ɏ]�Čv�Z���ꂽ�ېʼn��i�ƈقȂ邱�ƂƂȂ����ƁB�v�m�ȉ����n �����Ŗ@35���i�X���y�ь���̓����j�m1-2�����n3���u�Ŗ������́A��O�\����ꍀ��ꍆ�����Z���܂ł̋K��ɂ��X���̐����Ɋ�Â��X���������ꍇ�ɂ����āA���Y�����������҂̔푊���l���瑊�����͈②�ɂ����Y���擾�������̎ҁi���Y�푊���l������\����̋��O���̋K��̓K�p������Y�^�ɂ��擾�����҂��܂ށB�ȉ����̍��ɂ����ē����B�j�ɂ����Ɍf���鎖�R������Ƃ��́A���Y���R�Ɋ�Â��A���̎҂ɌW��ېʼn��i���͑����Ŋz�̍X�����͌��������B�������A���Y�����������������N���o�߂������ƍ��Œʑ��@�掵�\���i���ł̍X���A���蓙�̊��Ԑ����j�̋K��ɂ��X�����͌�������邱�Ƃ��ł��Ȃ����ƂƂȂ���Ƃ̂����ꂩ�x�����Ȍ�ɂ����ẮA���̌���łȂ��B ��@���Y���̎҂����\�����Ⴕ���͑��\����̋K��ɂ��\�����i�����̐\�����ɌW�������\�����y�яC���\�������܂ށB�j���o���A���͑����łɂ��Č�������҂ł���ꍇ�ɂ����āA���Y�\�����͌���ɌW��ېʼn��i���͑����Ŋz�i���Y�\�����͌��肪������C���\�����̒�o���͍X���������ꍇ�ɂ́A���Y�C���\�����͍X���ɌW��ېʼn��i���͑����Ŋz�j�����Y�����Ɋ�Â��X���̊���ƂȂ���������b�Ƃ��Čv�Z�����ꍇ�ɂ����邻�̎҂ɌW��ېʼn��i���͑����Ŋz�ƈقȂ邱�ƂƂȂ邱�ƁB�v�m�ȉ����n �����Ŗ@55���i��������Y�ɑ���ېŁj�u�����Ⴕ���͕�②�ɂ��擾�������Y�ɌW�鑊���łɂ��Đ\�������o����ꍇ���͓��Y���Y�ɌW�鑊���łɂ��čX���Ⴕ���͌��������ꍇ�ɂ����āA���Y�������͕�②�ɂ��擾�������Y�̑S�����͈ꕔ�����������l���͕���҂ɂ�Ă܂���������Ă��Ȃ��Ƃ��́A���̕�������Ă��Ȃ����Y�ɂ��ẮA�e���������l���͕���҂����@�i���S�l���̓�i��^���j�������B�j�̋K��ɂ�鑊�������͕�②�̊����ɏ]�ē��Y���Y���擾�������̂Ƃ��Ă��̉ېʼn��i���v�Z������̂Ƃ���B�������A���̌�ɂ����ē��Y���Y�̕���������A���Y���������l���͕���҂����Y�����ɂ��擾�������Y�ɌW��ېʼn��i�����Y���������͕�②�̊����ɏ]�Čv�Z���ꂽ�ېʼn��i�ƈقȂ邱�ƂƂȂ��ꍇ�ɂ����ẮA���Y�����ɂ��擾�������Y�ɌW��ېʼn��i����b�Ƃ��āA�[�ŋ`���҂ɂ����Đ\�������o���A�Ⴕ���͑�O�\����ꍀ�ɋK�肷��X���̐��������A���͐Ŗ������ɂ����čX���Ⴕ���͌�������邱�Ƃ�W���Ȃ��B�v �s�������i�ז@33��1���u�������ٌ͍��������������́A���̎����ɂ��āA�������ٌ͍��������s�������̑��̊W�s�������S������B�v�m2���ȉ����n �@���_1:�{���X�������̎���������߂Ă���ۂ́A�{���ʒm�����̎���������߂�i���̗��v�̑��ہB �@���_2:�{���X�������͓K�@���c�c�O�i�������\�����̊����]�����Ⴂ�����]����F�肵����A�����Ŗ@32��1���̍X���̐�������35��3��1���̋K��ɂ��X������������ɍۂ��A���Y�̕]���̌��𗝗R�Ƃ��邱�Ƃ��ł��邩�B �@���_3:�{���X�������͓K�@���c�c�O�i�̎�������̍S����(�s�������i�ז@33��1��)�ɂ��A�ېŒ��͑O�i�����̊����]����p���邱�Ƃ��`���t�����邩�B �@�����n������30�N1��24�����^1477��155��(����p�q�E�W�����X�g1565��10-11�ŁA�J���q�I�E�W�����X�g1583��131-134��)�c�c���_1:�p���B�{���ʒm�����𑈂����v�͖{���X�������𑈂����v�ɋz�������B���_2:���Y�]���̌��𗝗R�Ƃ��鑊���Ŗ@32��1���̍X���̐����͂ł��Ȃ��B35��3��1���̍X���̗��R�ɂ��Ȃ�Ȃ��B���_3:�s�i�@33��1���̍S���͂ɂ��A�����Ŋz(4��4689��9300�~)���镔���̑��z�X�������̎�����͔F�߂���B �@���������ߘa���N12��4���Ŏ�269������13350�c�c���_1:�i���̗��v����B�{���ʒm�����Ɩ{���X�������͓��e����ʂ��قȂ�̂Ŗ{���ʒm�����̎�����ɂ��Ă��i���̗��v������B���_2:�����Ŗ@32��1���̍X���̐����������Ŗ@35��3��1���̍X�����ł��Ȃ��B���_3:�s�i�@33��1���̍S���͂ɂ��A�ېŒ��͑O�i�����̊����]���z����b�Ƃ��Ĉ�Y������̉ېʼn��i�y�є[�t�Ŋz���v�Z���Ȃ���Ȃ�Ȃ��BY(��)�̎咣���ꕔ�F�e���Ŋz10��7095���~���镔����������B �@Y(��)���㍐�\���Ă������B �@�ō��ٔ��|�@�j�������B �@���_1:�p���B���_2or3:X�̐��������p(Y(��)�̎咣��F�e)�B �@���_1�u�����Ŗ@�T�T���Ɋ�Â��\���̌�Ɉ�Y�������s��ꂽ�ꍇ�ɂ��������̑����l�ɂ�铯�@�R�Q���P���̋K��ɂ��X���̐����ɑ���X�������ׂ����R���Ȃ��|�̒ʒm�����Ɠ��Y�����l�ɑ��铯�@�R�T���R���P���̋K��ɂ�鑝�z�X���́C�O�L�S�i�Q�j�m���L���_2�n�ɏq�ׂ��Ƃ���C����������Y��Y�����ɂ��e�����l�̎擾���Y�̕ϓ��Ƃ��������œ��L�̌㔭�I���R����b�Ƃ��Ă��ꂽ���ꑊ���l�ɑ��鏈���ł���C��L���z�X���́C��U�m�肵�Ă����Ŋz�Y��Y�������s��ꂽ���Ƃ𗝗R�ɑ��z�����Ċm�肷�鏈���ł��邩��C���Y��Y�����ɔ����Ŋz�����z���ׂ����R�͂Ȃ��Ƃ�����L�ʒm�����̓��e�������I�ɕ�ۂ�����̂Ƃ������Ƃ��ł���B�����āC��L�X���̐���������Ă��邽�߁C���Y�����l�́C��L���z�X���̎���i�ׂɂ����āC��L�X���̐����ɌW��Ŋz���镔���̎���������߂邱�Ƃ��\�ł���Ɖ������B��������ƁC�{���ʒm�����ɂ��ẮC���̎���������߂闘�v�͂Ȃ��C�{���i���̂����{���ʒm�����̎���������߂镔���͕s�K�@�ł��邩��C�p�����ׂ��ł���B�v �@���_2�u�����Ŗ@�R�Q���P���̋K��ɂ��X���̐����ɂ����ẮC��L�㔭�I���R�ȊO�̎��R���咣���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂ł��邩��C��L�̂Ƃ����U�m�肵�Ă��������Ŋz�̎Z���b�ƂȂ����X�̍��Y�̉��z�ɌW��]���̌��Y�����̗��R�Ƃ��邱�Ƃ͂ł����C�ېŒ����C���Œʑ��@����̍X���̏��ˊ��Ԃ��o�߂�����́C���Y�����ɑ��鏈���ɂ����ď�L�̕]���̌������邱�Ƃ͂ł��Ȃ����̂Ɖ�����̂������ł���B�܂��C�ېŒ��́C�����Ŗ@�R�T���R���P���̋K��ɂ��X���ɂ����Ă��C���l�ɁC��L�̕]���̌������邱�Ƃ͂ł����C��L�̈�U�m�肵�Ă��������Ŋz�̎Z���b�ƂȂ������z��p���邱�ƂɂȂ�v �@���_3�u�������������������m�肵���ꍇ�ɂ́C���̍S���́i�s�������i�ז@�R�R���P���j�ɂ��C�����������s�������́C���̎����ɂ����Y�����ɂ�����啶�������o�����̂ɕK�v�Ȏ����F��y�і@�����f�ɏ]���čs�����ׂ��`�������ƂƂȂ邪�C��L�S���͂ɂ���Ă��C�s�������@�ߏ�̍����������s�����`���t��������̂ł͂Ȃ�����C���̋`���̓��e�́C���Y�s������������s���@�ߏ�̌�����������̂Ɍ�������̂Ɖ������B �@�m���n���Y�����̌X�̍��Y�̉��z��]�����@�Ɋւ��锻�f�����ɂ��čS���͂������邩�ۂ���_����܂ł��Ȃ��C�ېŒ��́C���Œʑ��@����̍X���̏��ˊ��Ԃ��o�߂�����ɑ����Ŗ@�R�Q���P���̋K��ɂ��X���̐����ɑ��鏈���y�ѓ��@�R�T���R���P���̋K��ɂ��X��������ɍۂ��A���Y�����̍S���͂ɂ���ē��Y�����Ɏ����ꂽ�X�̍��Y�̉��z��]�����@��p���ĐŊz�����v�Z���ׂ��`�������Ƃ͂Ȃ��v cf.���_1�Ɋւ��A���z�X��������ɍ��Œʑ��@23��1���̍X���̐������������X�����闝�R���Ȃ��Ƃ���ʒm���������ꍇ�A�ʒm�����ɂ��đi���̗��v�͂���Ɣ��f����Ă���c�c�݂��ً�sCFC�ېŎ����E�Ŕ��ߘa5�N11��6�����W77��8��1933�ŁB |
7.1.9.2. �[�t
����38��1��:5�N�����x�Ƃ����N�����[�������邱�Ƃ��ł���B�A�����q(52��)�����B����41��:���[�������邱�Ƃ��ł���B( ��452.02�y�n���[od)
7.1.9.3. �A�є[�t�`��(����34��1��)
| 6�Ł�452.01���������l�A�є[�t�����E�Ŕ����a55�N7��1�����W34��4��535�ŕS�I7��79aw(�������E�@��99��9��1435��)�c�c�u�A�є[�t�`���́A���@�������Œ����̊m�ۂ�}�邽�߁A���݂Ɋe�����l���ɉۂ������ʂ̐ӔC�ł��āA���̋`�����s�̑O��������Ȃ��A�є[�t�`���̊m��́A�e�����l���̌ŗL�̑����ł̔[�ŋ`���̊m��Ƃ��������ɏƉ����āA�@���㓖�R�ɐ�������̂ł��邩��A�A�є[�t�`���ɂ��i�ʂ̊m��葱��v������̂ł͂Ȃ��v�B �ɓ������⑫�ӌ��u���_�́A�v����ɁA�����Ŗ@�O�l���ꍀ�̋K��ɂ�葼�̑����l���̌ŗL�̑����Ŕ[�ŋ`���ɂ��ĘA�є[�t�`���������l���́A�Ŗ����ǂɂ�镊�ۉېŕ����ɑ����葱������Ȃ�����A�[�t���ׂ����z�A�[�t�����A�[�t�ꏊ�A�[�t�z�̌��x�A�X���E����̗L�������̋�̓I���e�����ۏ�e�Ղ��m���ɒm�邱�Ƃ��ł��Ȃ����ł��邱�Ƃ𗝗R�Ƃ��Č��R�̔��f�������̂Ɖ������B�������ɁA�����l���̎���͈�l�ł͂Ȃ�����A�X�̋�̓I���Ăɑ����čl���Ă݂�ƁA�ꍇ�ɂ�ẮA�A�є[�t�`���҂ɑ��ʏ�̐\���[�ŕ����ɂ��ېł̈�ꍇ�Ƃ��Ă̒��Ŏ葱�����̂܂܍s�����Ƃ��A���̎҂��s�ӑł��̊���^���邱�Ƃ�Ƃ�Ȃ�����A�[�t���ׂ��z���̑��̋�̓I�Ȕ[�t�`���̓��e�̕s���m�ɂ�肻�̎҂����f������悤�Ȏ��ԂɂȂ邱�Ƃ��Ȃ��킯�ł͂Ȃ��ƍl������B�������Ȃ���A���̂��Ǝ��̂́A�m�肵���d�ł̒����葱�Ɋւ��Đ�������ł����āA�Ŋz�̊m��葱�Ɋւ�����ł͂Ȃ��Ɖ����ׂ��ł���B�������āA�E�̂悤�ȕs�ӑł��̊���^�����荢�f�����鎖�Ԃ��邨���ꂪ���邱�Ƃ𗝗R�Ƃ��āA�A�є[�t�`���ɂ��āA���ł̊m��葱�Ɋւ���K��ł��鍑�Œʑ��@����A��Z���̓K�p������Ǝ咣���鏊�_�͍̗p���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�v |
7.1.10. �ŕ��S�̕s���Ȍ����̖h�~(����63���`66����2)
7.1.11. ���Y�̕]��(����22��)
| 6�Ł�444.01�ٍϊ��������̍��̕]�� �ᗘ�����]������(�O�z����)�E�����n�����a46�N3��31�����a42(�s�E)224�����p�E�����������a47�N4��25�����a46(�s�R)25�����p�E�Ŕ����a49�N9��20�����W28��6��1178�Ŕj������au�E���ߍT�i�R�����������a50�N3��20�����a49(�s�R)68���T�i���p�m�� ���|�@�u�㍐�l��̔푊���l�ł�������ɏ��́A���a���N�ꌎ��������ЎO�z����ꉭ���Z�Z���~�𗘑��N�ꕪ�̖��Ŏؓ���A���O���N��ꌎ�������ٍ̕ϊ��܂łȂ��܈�N���c���Ď��S���A�{���������J�n�������A�����̒ʏ�̗����́A���Z�s��̐�������݂ĔN�����Ƃ���̂������ł������A�Ƃ����̂ł���B��������ƁA�㍐�l��́A�E�������ɂ��N�ꕪ�̖�藘�����x�����Ă��Ȃ��A�ٍϊ��܂ł̌܈�N�Ԗ��N�ؓ��z�̎����i�ʏ�̗����Ɩ�藘���Ƃ̍��j�ł����Z�O���~�����̌o�ϓI���v�𗯕ۂ����邱�ƂƂȂ�̂ŁA����ɂ��ĔN�����̕����v�Z�ɂ��܈�N�Ԃ̒��ԗ������T���������������{���z���獷�������ƁA�ꔪ�O�ܖ��O�O�Z�܉~�ƂȂ邱�Ƃ��v�Z�㖾�炩�ł��邩��A����������đ����J�n�̎��ɂ�����{�����̕]���z�Ƃ��ׂ��ł���B �@������ɁA���R�́A�E�������ɂ���Đ�����o�ϓI���v�̊z�����{���z���獷�����������̂��{�����̕]���z�ƂȂ邱�Ƃ�F�߂Ȃ���A�E���������ׂ��o�ϓI���v�̊z�̎Z��ɂ��ẮA�ʏ�̗����Ɩ�藘���Ƃ̍��ł���N�����̊����ɂ�蒆�ԗ������T�����ׂ����̂Ƃ��A���ǁA�{�����̊z���l�Z�㖜��Z�܁Z�~�ƕ]�����Ă���B�������A�E�o�ϓI���v�ɂ��Ē��ԗ������T������̂́A���ꂪ�ٍϊ��܂ł̊Ԓʏ�̗����ʼn^�p����邱�Ƃ�O��Ƃ�����̂ł��邩��A�{���ɂ����Ă͔N�����̊����ɂ���Čv�Z����̂����R�ł����āA����Ɩ�藘���Ƃ̍��ɂ��ׂ����R�͂Ȃ��A���R�̌v�Z���@�́A���Ƃ��킴������Ȃ��B�v �٘_�Ƃ��āA���q�G�u�����ł̉ېʼn��i�̎Z�o��T�����ׂ��ٍϊ��������̋��K���̕]�����@�v�@�w����G��95��8��1412�Łi�����l�ɂƂ��Ẳ^�p�v������ׂ��j |
| 6�Ł�443.01��ꊔ�����̕]�� �i��Y�Ǝ����E���n�����a59�N4��25���s�W35��4��532�ŕS�I7��85�i�T�i�R��㍂�����a62�N9��29���s�W38��8�E9��1038�ŁA�㍐�R�Ŕ��������N6��6���Ŏ�173��1�ŏ��a62�N(�s�c)145���j�c�c��ꊔ���𑊑�������Ŋ������\����������ł��A������̉��i�̍����E�����͍l�����Ȃ��B��萭���u���������̉��i�̖\���ɑ���ЊQ���Ɩ@�̗ސ��K�p�̉ہv�Ŗ�����22��4��9-13�ŁB |
| 5�Ł�441.01�j�`�A�X�������S�t���^�����E������������7�N12��13���s�W46��12��1143�Łi��R�����n������7�N7��20���s�W46��6�E7��701�� ���Y�]����{�ʒB169�i��ꊔ���̕]���j��ꊔ���̕]���́A���Ɍf����敪�ɏ]���A���ꂼ�ꎟ�Ɍf����Ƃ���ɂ��B �i1�j�@(2)�ɊY�����Ȃ���ꊔ���̉��z�́A���̊�������ꂳ��Ă�����Z���i������i������2�ȏ�̋��Z���i������ɏ�ꂳ��Ă��銔���ɂ��ẮA�[�ŋ`���҂��I���������Z���i������Ƃ���B(2)�ɂ����ē����B�j�̌��\����ېŎ����̍ŏI���i�ɂ���ĕ]������B�������A���̍ŏI���i���ېŎ����̑����錎�ȑO3�����Ԃ̖����̍ŏI���i�̊e�����Ƃ̕��ϊz�i�ȉ��u�ŏI���i�̌����ϊz�v�Ƃ����B�j�̂����ł��Ⴂ���z����ꍇ�ɂ́A���̍ł��Ⴂ���z�ɂ���ĕ]������B �i2�j�@���S�t���^���͌l�Ԃ̑Ή�������ɂ��擾������ꊔ���̉��z�́A���̊�������ꂳ��Ă�����Z���i������̌��\����ېŎ����̍ŏI���i�ɂ���ĕ]������B�m(2)�͕���2�N�����Œlj����ꂽ�n �����@���a63�N11��29���AA����N����23.8�����̌��������̒������o�����BX1(A�̑�)��X2(A�̎q)�͂��ꂼ��N����11.9�������̐M�p����̒������o�����B1950�~/���BA��K��s����2��4990���~������ꂽ�B���a63�N12��15���AA��X1�y��X2��1��2495���~���̍�����������Ƃ���N����11.9�������^�����B�����̊�����1980�~/���������B1��������̕��S��1050�~/��(��1��2495���~/11.9����)�ł������BX��́A����N���͒ʒB(����2�N�����O)�ɏ]���ĕ]�������1��������1033�~/���ł���A���S������̂ŁA���Y�̉��z��0�~�ł���Ƃ����O��ő��^�ł̊m��\���������B�Ŗ������́A���^���_�̏،�������ɂ�����ŏI���i��O��Ɉ�l������1��1067���~(��(1980�|1050)�~11.9��)�̎�����Ƃ��čX���������������B ���| �u�����Ƃ́A�ېŎ����ɂ����āA���ꂼ��̍��Y�̌����ɉ����A�s���葽���̓����ҊԂŎ��R�Ȏ�����s��ꂽ�ꍇ�ɒʏ퐬�����鉿�z�������v |
| �員�����E���H�n������13�N12��18����49��4��1334��(��ȏ͔@�E�W�����X�g1230��129��)�́A���j���̖�(�s�ꂪ�܂�����)�ɑ��������敨����̌��ʂ̕]���ɂ��āA���j���̑���ɂ�邱�Ƃ�F�߂��i�敨����͈ϔC�ɂ����̂ł���Ƃ���A���S�ɂ���Ė��@�㌴���Ƃ��ď��ł���ϔC�_���̒n�ʂɂ��đ����ł̑ΏۂƂȂ�̂��Ƃ��������������j�B[���]���́A���ꂪ�����l�ɂƂ��č����I�ȓw�͂ɂ���Ď��������鉿�l�ł��邩��Ƃ������R�ŁA�Ó��Ȕ��f�ł������Ǝv���B�������A�������̎����ɂ��Ƃ����@���̂����ŏꍇ�ɂ���Ă͑����l�ɍ��Ȃ��Ƃ�����B�Ⴆ�A�������Ɏ���5���~���������������l�����낤�Ƃ����Ƃ��ɂ͎������R�ɂȂ��Ă����ꍇ�Ƃ��A�������̎���1���~�̉Ƃ������̗����ɉΎ��ŏ������Ă��܂����ꍇ�Ƃ��B�A�����J�ł́A������̑������Y�̉��l�̋}���ɂ��Ď�̋~�ϋK�肪����B���{�@�̗��@�_�Ƃ��ẮA�y�������̎����z�ł͂Ȃ��A�y�����l�������I�ȓw�͂ɂ���Ď��������鉿�l�z�𑊑��ł̉ېŕW���ɂ���ׂ��ł���Ǝ��͎v���B |
| �����n������24�N3��2������2180��18�Ő����F�e(������������25�N2��28������24(�s�R)124���T�i���p�m��)(��ȏ͔@�E�����2208��140�ł͔��|����)�c�c�����ۗL������25��������Ђ����Y�]����{�ʒB189��(2)�ɂ��������ۗL�����ЂɊY�����Ȃ��Ƃ��ꂽ����B |
6�Ł�441.01�}���V�����]�������E�Ŕ��ߘa4�N4��19�����W76��4��411�Ł�2.2.1.2.b�����戵����
| �����n���ߘa5�N1��26���ߘa��(�s�E)490�����^1526��163�Ŋ��p(���䗢�ہE�W�����X�g2026�N2�����f�ڌ���)�E���������ߘa5�N12��13���ߘa5(�s�R)62�����p �����@�a(���a61�N�v)�Ƃ`(����26�N�v)�͕v�w�ł���A�w(����)�E�b�E�c�͕v�w�̎q�ł���B �@���a40�N�A�a�Ƃd�͖{���e�y�n��Ƀ}���V���������݂����B�n��1�K�`�n��4�K���a�����L���A5�K�`10�K���d�����L�����B�a�͂d�ɑ��A�{���e�y�n�ɂ��āA�d���}���V�������w�K�����L���邽�߁A����60�N�A�n��2��7138�~/��(�n���ɉ����ĕϓ�����)�Ƃ���n�㌠��ݒ肵���B�d�͂a�ɑ��m��擾�̑Ή��Ƃ���2220���~���x�������B�}���V�����͏��a41�N2�����Ɋ��������B���̌�A�d�̓}���V�������w�K��n�㌠�����Ƌ��ɏ������������B �@���a61�N�A�a���S�B�a�̑����l�ł���`�E�w�E�b�E�c����Y�������c�����A�`���{���e�y�n���擾���A�w���}���V������w�K���擾�����B �@����10�N�A�w�͂e��(�w����\��)�ɑ��A�{���}���V������w�K��3976���~�Ŕ��p�����B�`�Ƃe�́A�ݎ���`�A�؎���e�A������10���~/���Ƃ���y�n���ݎ،_���쐬�����B�����Ԋғ͏o����o����B �@����21�N�A�d�́A�n�㌠����1/2�S���ɂ��āA���^�������Ƃ��Ăe�Ɉړ]����|�̓o�L�葱���������B �@����26�N�A�`�͎��S�����B�w�y�тb�́A�`�̈⌾�ɂ��A�{���e�y�n�̎���1/2�����擾�����B �@����27�N9��18���A�w�͖ڍ��Ŗ������ɑ������ł̐\���������B�{���e�y�n��1/2�͂e���g�p�ҁA1/2�͕������L�҂��g�p�҂ł���A��������]���ʒB25(1)�Ɋ�Â����p�n���z����ؒn������70�����T�����Ă����B �@���_�@�{���e�y�n�̂����e���g�p�҂Ƃ��镔��(�}���V������w�K�̕~�n����)�̎��� �@���|�@�������p �@�u�����Ŗ@�Q�Q���́A�������ɂ��擾�������Y�̉��z�Y���Y�̎擾�̎��ɂ����鎞���ɂ��Ƃ��邪�A�����ɂ��������Ƃ͓��Y���Y�̋q�ϓI�Ȍ������l���������̂Ɖ������B���������āA�����ł̉ېʼn��i�ɎZ���������Y�̉��z�́A���Y���Y�̎擾�̎��ɂ�����q�ϓI�Ȍ������l�Ƃ��Ă̎���������Ȃ�����A�����Ɉᔽ������̂ł͂Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���i�ō��ٗߘa�Q�N�i�s�q�j��Q�W�R�����S�N�S���P�X����O���@�쌈��Q�Ɓj�B �@�����āA�]���ʒB�y�ё����n��ʒB�́A��L�̈Ӗ��ɂ����鎞���̕]�����@���߂����̂ł���Ƃ���A�㋉�s���@�ւ������s���@�ւ̐E�������̍s�g���w�����邽�߂ɔ������ʒB�ł���A���ꂪ�����ɑ��Ē��ڂ̖@�I���͂�L����Ƃ����ׂ������͌�������Ȃ��B�����Ƃ��A�]���ʒB�y�ё����n��ʒB�͑������Y�̉��z�̕]���̈�ʓI�ȕ��@���߂����̂ł���A�ېŒ�������ɏ]���ĉ��I�ɕ]�����s���Ă��邱�Ƃ܂���ƁA�������Y�̋q�ϓI�Ȍ������l��]������ɓ������ẮA�]���ʒB�y�ё����n��ʒB�ɒ�߂�]�����@�̎�|�܂��Č�������̂������ł���B�v �@�u�ؒn�l�͎ؒn�؉Ɩ@�̕ی���ċ���������L���邱�ƂɂȂ�ق��A�y�n���L�҂ɂƂ��ẮA�����A�y�n�̉��z�̏㏸�ɉ����Ēn��̒l�グ���ł���Ƃ����ۏ��Ȃ����Ɠ��̗��R����A���Y�y�n�̋q�ϓI�Ȍ������l�́A�������n���z�Ƃ��ĕ]������̂������ł���B�����āA�������L��ړI�Ƃ���ؒn���̓��e�́A�n��I�Ȋi���͂�����̂́A�T�ˈ�l�ł��邱�Ƃ���A�ؒn���̋q�ϓI�Ȍ������l�́A���Y�y�n�̎��p�n�Ƃ��Ẳ��z�ɁA���ʎؒn���̔������ቿ�z�A���ʎ҈ӌ����i�y�ђn��̊z������Ƃ��A�ގ��n�悲�Ƃɒ�߂�ꂽ���ŋǒ��̒�߂銄�����悶�ĕ]������̂������ł���i�]���ʒB�Q�T�i�P�j�A�Q�V�y�ѓ��ʒB�̒�������i���Q�U�j�Q�Ɓj�B �@�����Ƃ��A�ؒn���ݒ�_����Ă��A�y�n���L�҂����ɂ��̗��p�ɂ����̐�������ق��ɂ́A�ؒn�l�ɑ�����o�ϓI���v���ړ]���Ă��Ȃ��ꍇ������B���̂悤�ȏꍇ�A���Y�y�n�̋q�ϓI�Ȍ������l��]������ɓ������ẮA���Y���p��������鉿�l���������l������Α����Ƃ���A���Y���p������������̂��̂ɂƂǂ܂�Ƃ����邱�Ƃ��炷��A���̋q�ϓI�Ȍ������l�͎��p�n�Ƃ��Ẳ��z�̂W�O�������z���������̂ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃ��ł���B�����āA�ؒn�_��ɌW��o�ϓI���Ԃ͗l�X�ł�����̂́A�@�ؒn���̐ݒ�ɍۂ����̐ݒ�̑Ή��Ƃ��Ēʏ팠�������x����������s������ƔF�߂���n��ł���ɂ�������炸�A�������̎�����Ă��炸�A�A���ۂɎx�����Ă���n�オ���̒n��ɂ�����ʏ�̎ؒn���ݒ�_��ɂ�����n��i�ʏ�̒n��j�Ɠ����x����������Ⴂ�z�ł����āA�B�y�n���L�҂Ǝؒn�l�Ƃ̊ԂŁA�����ؒn�l�����Y�y�n���ŕԊ҂���|���ӂ���Ă���ꍇ�ɂ́A���i�̎���Ȃ�����A�ؒn���ݒ�_����Ă��A�y�n���L�҂���ؒn�l�ɑ��Ă͉���o�ϓI���v���ړ]���Ă��Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���i�����n��ʒB�T�y�тW�Q�Ɓj�B�Ȃ��Ȃ�A���̂悤�ȏꍇ�A�ؒn���҂́A�ؒn���̌o�ϓI���v�ɑ������錠�������x���킸�i�@�j�A���A�n��Ƃ��āA��n���̌o�ϓI���v�ɑ�������ʏ�̒n����x����������Ⴂ�z�̎x���������Ă��炸�i�A�j�A�܂��A�������◧�ޗ������z���y�n���L�҂���ؒn���҂ɑ��^���ꂽ���̂Ƃ�������i�B�j����ł���B�v �@�u�{���e�y�n�́A�ؒn���̐ݒ�ɍۂ����̐ݒ�̑Ή��Ƃ��Ēʏ팠�������x����������s������ƔF�߂���n��ɏ��݂�����̂́i���P�X�̂R�A�Q�U�j�A�S�`�Ƃe�Ƃ̊Ԃł́A�{���y�n���ݎ،_�̍쐬���ɁA�������̎���͍s���Ȃ��������̂ƔF�߂���i������T�������ʂU�ŁA���P�Q�A�ؐl�f�j�B �@���ɁA�e�͖S�`�ɑ��A�{���e�y�n�̂����e���g�p�҂Ƃ��镔���̗��p�̑Ή��Ƃ��Č��z�P�O���~���x�����Ă���i�b�Q�W�A���P�Q�A�P�W�̂P�`�S�j�B���̓_�A�{���e�y�n�̂����e���g�p�҂Ƃ��镔���̎��p�n�Ƃ��Ẳ��z�͖S�`�̎��S���ɂ����Ė�P���W�W�W�P���~�ł���i�ʕ\�S�|�P�����k�P�P�l�Q�Ɓj�A��n���z�̂U����ʏ�̒n��̊z�Ƃ����ꍇ�A���̊z�͌��z��Q�W���~�i�P���W�W�W�P���~�~�i�P�|�ؒn�������i�O�D�V�t�~�U���~�P�^�P�Q�j�ł��邱�ƁA�{���e�y�n�͓s�S�ɋ߂��l�����W�n�ɏ��݂��i�b�P�S�j�A�e�͖{���e�y�n�𗘗p���邱�Ƃɂ��A�e�K���ʐϖ�R�O�O�������[�g���łT�K�������̖{���}���V������w�K������v���グ���邱�Ƃ��l������A�{���}���V�������z��T�O�N���o�߂��Ă������Ƃ��l�����Ă��A�{���e�y�n�̗��p�̑Ή��ł��錎�z�P�O���~�Ƃ������z�́A���̏��ݒn��ɂ�����ʏ�̎ؒn���ݒ�_��ɂ�����n��Ɠ����x����������Ⴂ���̂Ƃ������Ƃ��ł���B �@����ɁA�e�́A�{���y�n���ݎ،_���쐬�����ہA�S�`�ɑ��A�����{���e�y�n���ŕԊ҂���|�������̂ƔF�߂���i���P�Q�j�B �@�����āA�S�`�Ƃe���A�ڍ��Ŗ������ɑ��A�{�������Ԋғ͏o�����o���Ă��邱�Ƃ́A�S�`����e�ɑ�����o�ϓI���v���ړ]���Ă��Ȃ��Ƃ̎����𗠕t������̂ł���B �@���������āA�{���e�y�n�̂����e���g�p�҂Ƃ��镔���ɂ��ẮA�e���{���}���V������w�K�̕~�n�����Ƃ��ė��p���邱�Ƃɂ�茻�Ɉ��̐�������ɂƂǂ܂�A�S�`����e�ɑ��Ă͉���o�ϓI���v���ړ]���Ă��Ȃ��ƔF�߂�̂������ł��邩��A���̋q�ϓI�Ȍ������l�́A���p�n�Ƃ��Ẳ��z�̂W�O�������z���������̂ł͂Ȃ��ƔF�߂���B�v cf. �����n������20�N7��23������20(�s�E)41�����p�m��(��ȏ͔@�E�W�����X�g1405��197-200��)�͖����Ԋғ͏o���ɂ��āu���@��̍s�ׂƂ��āc�c�L���ɐ����v�ȂǂƔ��������B���̎����ł́A�[�Ŏґ����@�l�ŊW�Ŗ����Ԋғ͏o���̗L������O��Ƃ������ŊW�Ŗ����Ԋғ͏o���̖��������咣���邱�Ƃ��A�M�`���ᔽ�ł���A�ƉېŒ������咣���Ă����B�����͐M�`���ɐG��Ă��Ȃ��B |
COLUMN7-1 �y�n�̕]��(��6�Ł�413.01�_�n����/����)
7.1.12. ���ʑ[�u
7.1.12.1. ���K�͑�n�̕��S�y���[�u(�d��69����4)ic
�d��69����4�i���K�͑�n���ɂ��Ă̑����ł̉ېʼn��i�̌v�Z�̓���j�@�l���������͈②�ɂ��擾�������Y�̂����ɁA���Y�����̊J�n�̒��O�ɂ����āA���Y�����Ⴕ���͈②�ɌW��푊���l���͓��Y�푊���l�Ɛ��v����ɂ��Ă������Y�푊���l�̐e���i��O���ɂ����āu�푊���l���v�Ƃ����B�j�̎��Ɓi�c�c�j�̗p���͋��Z�̗p�i�c�c�j�ɋ�����Ă�����n���i�c�c�j�c�c������ꍇ�ɂ́A���Y�������͈②�ɂ����Y���擾�����҂ɌW��S�Ă̓���Ώۑ�n���̂����A���Y�l���擾����������Ώۑ�n�����͂��̈ꕔ�ł��̍��̋K��̓K�p������̂Ƃ��Đ��߂Œ�߂�Ƃ���ɂ��I�����������́i�c�c�j�ɂ��ẮA���x�ʐϗv�������ꍇ�c�c�Ɍ���A�����Ŗ@��\����̓�ɋK�肷�鑊���ł̉ېʼn��i�ɎZ�����ׂ����z�́A���Y���K�͑�n���̉��z�Ɏ��̊e���Ɍf���鏬�K�͑�n���̋敪�ɉ������Y�e���ɒ�߂銄�����悶�Čv�Z�������z�Ƃ���B�@��@���莖�Ɨp��n���ł��鏬�K�͑�n���A���苏�Z�p��n���ł��鏬�K�͑�n���y�ѓ��蓯����Ў��Ɨp��n���ł��鏬�K�͑�n���@�S���̓�\
�@��@�ݕt���Ɨp��n���ł��鏬�K�͑�n���@�S���̌\
�Q�@�O���ɋK�肷����x�ʐϗv���́A���Y�������͈②�ɂ�����Ώۑ�n�����擾�����҂ɌW�鎟�̊e���Ɍf����I�����Ώۑ�n���̋敪�ɉ����A���Y�e���ɒ�߂�v���Ƃ���B
�@��@���莖�Ɨp��n�����͓��蓯����Ў��Ɨp��n���i��O���C�ɂ����āu���莖�Ɨp����n���v�Ƃ����B�j�ł���I�����Ώۑ�n���@���Y�I�����Ώۑ�n���̖ʐς̍��v���l�S�������[�g���ȉ��ł��邱�ƁB
�@��@���苏�Z�p��n���ł���I�����Ώۑ�n���@���Y�I�����Ώۑ�n���̖ʐς̍��v���O�S�O�\�������[�g���ȉ��ł��邱�ƁB
�@�O�@�ݕt���Ɨp��n���ł���I�����Ώۑ�n���@���̃C�A���y�уn�̋K��ɂ��v�Z�����ʐς̍��v����S�������[�g���ȉ��ł��邱�ƁB
�@�@�C�@���莖�Ɨp����n���ł���I�����Ώۑ�n��������ꍇ�̓��Y�I�����Ώۑ�n���̖ʐς����v�����ʐςɎl�S���̓�S���悶�ē����ʐ�
�@�@���@���苏�Z�p��n���ł���I�����Ώۑ�n��������ꍇ�̓��Y�I�����Ώۑ�n���̖ʐς����v�����ʐςɎO�S�O�\���̓�S���悶�ē����ʐ�
�@�@�n�@�ݕt���Ɨp��n���ł���I�����Ώۑ�n���̖ʐς����v�����ʐρm3���ȉ����n
| 6�Ł�414.02⦍�y�n��搮�����Ǝ����E�����n������16�N1��20������14(�s�E)26���ꕔ���p�A�ꕔ�p���E������������16�N11��26������16(�s�R)7�����p�E�Ŕ�����19�N1��23������17(�s�q)91����54��8��1628�ŕS�I7��83�ꕔ�j�����߁A�ꕔ���pib�E������������19�N7��19������19(�s�R)6����54��8��1642�ňꕔ�ύX�A�ꕔ�F�e�A�ꕔ���p�A�m�� �y�n��搮�����Ƃɂ����鉼���n�̎w��ɔ����������ɂ����čX�n�ƂȂ��Ă������A�d��69����3(�����B��69����4)�̏��K�͑�n����͓K�p�����B�Ƃ�������B�ʒB������������ꂽ�B�[�u�@�ʒB69��4-3�B��������߂���O��Ă��錙���͂���B 2�Ł�514.02���̒��ԏꎖ���E������������9�N5��22������8(�s�R)80���s�W48��5��6��410�Ŋ��p(���R�����n������8�N6��21������7(�s�E)208���s�W48��5=6��424�Ŋ��p) �����E���_�@X�炪A���瑊�������{����n���ɑd��69����4�̓���̓K�p�����邩�B�{����n�������J�n�O���玖�Ƃ̗p�ɋ�����Ă������B ���| �K��̎�|�@�u�����l���̐�����Ղ̈ێ��̂��߂ɕs���v�u���Ɏ��Ɨp��n�ɂ��ẮA�ِl�A����擙���Ǝ҈ȊO�̑����̎҂̎Љ�I��Ղɂ��Ȃ�A���Ƃ��p��������K�v���������c�v ���f��@�u���Y��n���������Ɏ��Ƃ̗p�ɋ�����Ă������ۂ��Ƃ����ϓ_���画�f�����ׂ��v cf.�����n������28�N7��22������27(�s�E)57�����p�i���ŕs���R��������26�N8��8���ٌ��A������������29�N1��26�����p�m��j(�ėR�ԁE�W�����X�g1516��118��)�c�c�S�Ă̑����l�ɂ�鏬�K�͑�n������̑I�ӏ�����o����ĂȂ����Ƃ𗝗R�ɓ��Y����i�d�œ��ʑ[�u�@69����4�j�̓K�p���F�߂��Ȃ��Ƃ�������B cf.���l�n���ߘa2�N12��2������31(�s�E)10�����p�E���������ߘa3�N9��8���ߘa3(�s�R)1�����p�c�c���K�͑�n����u���v����ɂ��Ă����v�v����[����B |
| �����n���ߘa6�N1��25���ߘa5(�s�E)172�����p(���ˋM�V2025�N6��6���d�Ŕ��ጤ�����) �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�� �@�����������������������������������������@�� �@���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���������������@���@�� �@���@�����������������@���@�@�@�@�@���@������ �@���@���@�@�@�@�@�@���@���e���̎���@���H�� �@���@���@�{������@���@���������������@���@�� �@���@���@�@�@�@�@�@���@�������������������@�� �@���@�����������������@���@�@�@�@�@�@�@���@�� �@���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@�@���@�� �@���������@�@�@�@�@�@�@�� �@�����{���@�@�@�@�@�@�@�� �@���������@�@�@�@�@�@�@�� �@�����[���������������@�� �@�����������{���q�Ʉ��@�� �@���������������������@�� ���������������������������������� �@�@�@�@�@���H ���������������������������������� �@�����@�푊���lE��������30�N10��6�����S�B�����l�̈�l�ł���X��(����)�́A������n�̂��A�[���̕~�n�̗p�ɋ�����Ă��镔����d�œ��ʑ[�u�@69����4��3��1���̓��莖�Ɨp��n���A����ȊO�̕�����2���̓��苏�Z�p��n���Ƃ��āA�����ł̊m��\���������B �@�����͉Y�a�Ŗ������ɑ��A�u�X���̐����̗��R�A�v������(�X���̐����̗��R�C�ȗ�)�B �@�X���̐����̗��R�A�F�{����n�ɌW��{������K�p�z�Ɍ�肪���������ƁA��̓I�ɂ́A�{����n�̂����{���q�ɂ̕~�n�̗p�ɋ�����Ă��镔���ɂ��āA�{�������\���y�і{���C���\���ɂ����Ă͓��苏�Z�p��n���Ɋ܂߂Ă������A���莖�Ɨp��n���Ɋ܂߂�ׂ��ł������Ȃǂ̌�肪����A���莖�Ɨp��n���ł���I�����Ώۑ�n���̖ʐς����ۂɂ͂S�P�W�D�S�U�������[�g���ƂȂ邩��A�{������K�p�z�̌v�Z�ɓ������ẮA���莖�Ɨp��n���̌��x�ʐϗv���ł���S�O�O�������[�g������ɍs���ׂ��ł���B �@�Y�a�Ŗ������́A�ߘa�S�N�P���U���t���ŁA�{���X���̐����̗��R�A�ɂ��āA�����́A�[�u�@�U�X���̂S�̋K��ɔ�������͂Ȃ��A���莖�Ɨp��n���Ƃ��ĂV�T�������[�g�����A���苏�Z�p��n���Ƃ��ĂR�R�O�������[�g����I������|�L�ڂ����{�������\�������o���A�܂��A���Y�I���Ɋ�Â��ېʼn��i�̌v�Z�Ɍ��͂Ȃ����߁A�{���X���̐����ɂ����莖�Ɨp��n���ɂ��ĂS�O�O�������[�g����I�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��A�Ƃ���{���X�������������B �@���_�@�{���X���̐����̗��R�A�����Œʑ��@�Q�R���P���P���̗v���������ۂ��B �@���|�@���Œʑ��@23��1��1�u���̎�|�́A�����v�Z�̓���A�Ɛœ��̑[�u�ň�莖���̐\������K�p�����Ƃ��Ă�����̂ɂ��Ă��̐\�����Ȃ��������߁A�[�t���ׂ��Ŋz�����̐\�������������ꍇ�ɔ䂵�ĉߑ�ƂȂ��Ă���ꍇ�ɂ����āA�X���̐����Ƃ����`���ł��̉ߑ�ƂȂ��Ă��镔�������z���邱�Ƃ�r�����邱�Ƃɂ���v�B �@�u�[�u�@�U�X���̂S��U�����A�{������̓K�p���悤�Ƃ���҂̂����铖���\�������͂��̏C���\�����ɓ����P���̓K�p���悤�Ƃ���|���L�ڂ��A�����̋K��ɂ��v�Z�Ɋւ��閾�����̑��̍����ȗ߂Œ�߂鏑�ނ̓Y�t������ꍇ�Ɍ��蓯����K�p����|���߂Ă��邱�Ƃɉ����A�����y�ѓ����R���ɂ����āA���莖�Ɨp��n���Ɠ��苏�Z�p��n���Ƃ͕ʂ̋敪�ɊY��������̂Ƃ��ċK�肳��A�[�u�@�{�s�߂S�O���̂Q��T���P���ɂ����Ă��A�[�u�@�U�X���̂S��P���́u�K��̓K�p������̂Ƃ��đI�����悤�Ƃ��铖�Y����Ώۑ�n�����͂��̈ꕔ�ɂ��ē����e���Ɍf���鏬�K�͑�n���̋敪���̑��̖��ׂ��L�ڂ������ށv��\�����ɓY�t���邱�Ƃ����߂��Ă��邱�ƂɏƂ炷�ƁA�{������́A�[�Ŏ҂��A�����\�����͂��̏C���\���ɂ����āA�{�����������̂Ƃ��ē��Y����Ώۑ�n�����͂��̈ꕔ�ɂ��ď��K�͑�n���̋敪���̑��̖��ׂ��L�ڂ������ނ������đI�������͈͂œK�p�����Ƃ����ׂ��ł���A��ɂȂ��Ă�����A�{������̓K�p���g�傷���|�ōX���̐��������邱�Ƃ������Ȃ����ƂƂ������̂Ɖ������B�v �@�u�{���������ɂ����āA���莖�Ɨp��n���ɋ敪����Ă���͖̂{���[���~�n�����i�V�T�D�O�O�������[�g���j�݂̂ł���A�{����n�̂��̑��̕����i�{���q�ɕ~�n�������܂ށB�j�ɂ��Ă͓��苏�Z�p��n���ɋ敪����Ă��邱�Ƃ��炷��A�{���������ɂ����āA�{���q�ɕ~�n���������莖�Ɨp��n���Ƃ��ċ敪����Ă����ƔF�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B���������āA�{�������\���y�і{���C���\���ɂ����āA�[�u�@�U�X���̂S��R���P������̓��莖�Ɨp��n���Ƃ��Ė{���q�ɕ~�n������I���������̂Ƃ͔F�߂��Ȃ�����A�{���q�ɕ~�n�����ɂ��A��������̓��莖�Ɨp��n���Ƃ��Ė{�������K�p���邽�߂̗v������������Ă���Ƃ͂����Ȃ��B�v �@�u���K�͑�n���̋敪�̎�����F�́A���Œʑ��@�Q�R���P���Ɋ�Â��X�������ׂ��|�̐��������邱�Ƃ��ł��鎖�R�ł���u���Y�v�Z�Ɍ�肪�������v�ꍇ�ɂ͊Y�����Ȃ��v�B ���Œʑ��@23��1��1���̉��߂Ɋւ���٘_�Ƃ��ďa�J��O�u�X���̐������߂��鍡���̘_�_�v�d�Ŗ@����37���w�d�Ŏ葱��̔[�Ŏ҂̌����ی�x89��(2009) |
7.1.12.2. ���ꊔ�����ɌW��[�ŗP�\���x(�d��70����7�ȉ�)
��Y(���O���^��)�ɉېł��邱�Ƃ����Ə��p�̏�Q�ƂȂ�Ƃ������O������Bcf.��ȏ͔@�uCON�icapital ownership neutrality�F���{���L�������j�̉��p�F���Ə��p�ɂ�����M�����̊��p�Ɍ������v�����@�w86��216-196�ł́A���葊���l�������Ƃ��p���ꍇ�ƐV�K�Q���҂Ƃ��r����B����21�N�����Ŏ��Ə��p�Ő��i���̗v���̉��ʼnېł��ɘa�j�����B���d��70����7�`70����7��4lr
7.1.12.2.a ���^�ł̔[�ŗP�\���x
7.1.12.2.b �����ł̔[�ŗP�\���x
7.1.12.2.c ���Ə��p�Ő��̓��ᐧ�x(��30�������d��70����7��5�`70����7��8)
7.2. �Œ莑�Y��mx
�O������w�Œ莑�Y�ŕ]�����`�x(�M�R�ЁA2023)7.2.1. �Œ莑�Y�ł̈Ӌ`
�Ŕ�����15�N6��26�����W57��6��723�Ł�6�Ł�441.017.2.2. �䒠�ېŎ�`
7.2.3. �ېŕ����i�ېŋq�́j
COLUMN7-2 ���p���Y�ɑ���Œ莑�Y��
7.2.4. �[�ŋ`����
7.2.4.1. �y�n�E�Ɖ�
| ���n������25�N4��26������21(�s�E)25���ꕔ�p���A�ꕔ���p�A�ꕔ�F�e�E��㍂������26�N2��6������25(�s�R)99���ꕔ����A�Ŕ�����27�N7��17������26(�s�q)190������2279��16�Ŕj������az�c�c�o�L��̕\�蕔�̏��L�җ��Ɂu�厚���v�ȂǂƋL�ڂ���Ă���y�n�ɂ��A�n���Ŗ@343��2����i�̗ސ��K�p�ɂ��A���Y�y�n�̏��݂���n��̏Z���ɂ��g�D����Ă��鎩����͒�����Y�y�n�̌Œ莑�Y�ł̔[�ŋ`���҂ɓ�����Ƃ������R�̔��f�Ɉ�@������Ƃ��ꂽ����B (1)�u�d�Ŗ@����`�̌����ɏƂ炷�ƁC�d�Ŗ@�K�݂͂���ɋK��̕����𗣂�ĉ��߂��ׂ����̂ł͂Ȃ��v�B�u���̂��Ƃ́C�n���Ŗ@�R�S�R���̋K��̉��ɂ�����Œ莑�Y�ł̔[�ŋ`���҂̊m��ɂ����Ă����l�ł���C�ꕔ�̓y�n�ɂ��Ă��̔[�ŋ`���҂���肵���Ȃ�����Ȏ�����邽�߂ɂ��̕��ے��������邱�Ƃ��ł��Ȃ��ꍇ����������Ƃ��Ă��ς����̂ł͂Ȃ��B�v (29�u����y�n�ɂ��n���Ŗ@�R�S�R���Q����i�ɂ��Œ莑�Y�ł̔[�ŋ`���҂ɊY������Ƃ������߂ɂ́C���Ȃ��Ƃ��C�Œ莑�Y�ł̕��ۊ����ɂ����ē��Y�҂�������i�ɂ����u���Y�y�n�c�����ɏ��L���Ă���ҁv�ł��邱�ƁC���Ȃ킿�C��L���ۊ����ɂ����ē��Y�y�n�̏��L�������Y�҂Ɍ��ɋA�����Ă������Ƃ��K�v�ł���B�����āC��L�i�P�j�ɂ����Đ��������Ƃ���ɏƂ点�C����y�n�ɂ��C�Œ莑�Y�ł̕��ۊ����ɂ����Ă��̏��L�������Y�҂Ɍ��ɋA�����Ă������Ƃ��m�肷�邱�ƂȂ��C������i�Ɋ�Â��ē��Y�҂��Œ莑�Y�ł̔[�ŋ`���҂Ƃ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��v�B |
| �Ŕ����a47�N1��25�����W26��1��1�ŕS�I7��95�c�c�u�Œ莑�Y�ł́A�y�n�A�Ɖ�����я��p���Y�̎��Y���l�ɒ��ڂ��ĉۂ����镨�łł���A���̕��S�҂́A���Y�Œ莑�Y�̏��L�҂ł��邱�Ƃ������Ƃ���B�����A�n���Ŗ@�́A�ېŏ�̋Z�p�I�l������A�y�n�ɂ��Ă͓y�n�o�L��i���a�O�ܔN�@�����l��������Z���ɂ������O�͓y�n�䒠�j�܂��͓y�n��[�ېő䒠�ɁA�Ɖ��ɂ��Ă͌����o�L��i�E�����O�͉Ɖ��䒠�j�܂��͉Ɖ���[�ېő䒠�ɁA���̎��_�ɁA���L�҂Ƃ��ēo�L�܂��͓o�^����Ă���҂����L�҂Ƃ��āA���̎҂ɉېł���������̗p���Ă���̂ł���B�������āA�^���͓y�n�A�Ɖ��̏��L�҂łȂ��҂��A�E�o�L��܂��͑䒠�ɏ��L�҂Ƃ��ēo�L�܂��͓o�^����Ă��邽�߂ɁA���ł̔[�ŋ`���҂Ƃ��ĉېł���A�����[�t�����ꍇ�ɂ����ẮA�E�y�n�A�Ɖ��̐^�̏��L�҂́A����ɂ�蓯�ł̉ېł�Ƃꂽ���ƂɂȂ�A���L�҂Ƃ��ēo�L�܂��͓o�^����Ă���҂ɑ���W�ɂ����ẮA�s���ɁA�E�[�t�Ŋz�ɑ������闘�����������̂Ƃ����ׂ��ł���B�����āA���̗��́A����̐��i��L����s�s�v��łɂ��Ă����l�ł���B����䂦�A����Ɠ��|�̌����̂��ƂɁA�������i���̈��p������R�������܂ށB�ȉ������B�j�̌��x�ɂ����āA�s�������������Ƃ����㍐�l�̖{�i������F�e�������R�̔��f�͑����ł��āA�������ɏ��_�̈�@�͂Ȃ��B��㍐�l���A�m�蔻���Ɋ�Â������o�L�`���𗚍s�����A������̏��L�����s�g���Ă������̎���A�E�������̑��ۂɉe�����y�ڂ��Ȃ����Ƃ��A�܂��A�������̔�������Ƃ���ł���B�v |
| �Ŕ�����26�N9��25�����W68��7��722��ev�c�c�u�y�n���͉Ɖ��ɂ��C���ۊ����̎��_�ɂ����ēo�L�떔�͕�[�ېő䒠�ɓo�L���͓o�^������Ă��Ȃ��ꍇ�ɂ����āC���ی��菈�����܂łɕ��ۊ������݂̏��L�҂Ƃ��ēo�L���͓o�^����Ă���҂́C���Y���ۊ����ɌW��N�x�ɂ�����Œ莑�Y�ł̔[�ŋ`�����v�B |
7.2.4.2. ���p���Y
7.2.5. ��ې�
7.2.5.1. �l�I��ې�
7.2.5.2. ���I��ې�
�n���Ŗ@348��(�Œ莑�Y�ł̔�ېł͈̔́j�@�s�����́A�����тɓs���{���A�s�����A���ʋ�A�����̑g���A���Y��y�э��������ɑ��ẮA�Œ莑�Y�ł��ۂ��邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�Q�@�Œ莑�Y�ł́A���Ɍf����Œ莑�Y�ɑ��Ă͉ۂ��邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�������A�Œ莑�Y��L���Ŏ���҂���������Ɍf����Œ莑�Y�Ƃ��Ďg�p����ꍇ�ɂ́A���Y�Œ莑�Y�̏��L�҂ɉۂ��邱�Ƃ��ł���B
�@��@�����тɓs���{���A�s�����A���ʋ�A�����̑g���y�э��Y�悪���p���͌����̗p�ɋ�����Œ莑�Y�m�㗪�n
�n�������@242����2�i�Z���i�ׁj�@���ʒn�������c�̂̏Z���́A�O���ꍀ�̋K��ɂ�鐿���������ꍇ�ɂ����āA�����܍��̋K��ɂ��č��ψ��̊č��̌��ʎႵ���͊����Ⴕ���͓����㍀�̋K��ɂ�镁�ʒn�������c�̂̋c��A�����̑��̎��s�@�֎Ⴕ���͐E���̑[�u�ɕs��������Ƃ��A���͊č��ψ��������܍��̋K��ɂ��č��Ⴕ���͊������Z���̊��ԓ��ɍs��Ȃ��Ƃ��A�Ⴕ���͋c��A�����̑��̎��s�@�֎Ⴕ���͐E���������㍀�̋K��ɂ��[�u���u���Ȃ��Ƃ��́A�ٔ����ɑ��A�����ꍀ�̐����ɌW���@�ȍs�ז��͑ӂ鎖���ɂ��A�i�������Ď��Ɍf���鐿�������邱�Ƃ��ł���B
�@�m��`�O�@���n
�@�l�@���Y�E�����͓��Y�s�Ⴕ���͑ӂ鎖���ɌW�鑊����ɑ��Q�������͕s�������Ԋ҂̐��������邱�ƂY���ʒn�������c�̂̎��s�@�֖��͐E���ɑ��ċ��߂鐿���B�������A���Y�E�����͓��Y�s�Ⴕ���͑ӂ鎖���ɌW�鑊��������S�l�\�O���̓�̓��O���̋K��ɂ�锅���̖��߂̑ΏۂƂȂ�҂ł���ꍇ�ɂ́A���Y�����̖��߂����邱�Ƃ����߂鐿��
| �Ŕ�����6�N12��20�����W48��8��1676�ŕS�I7��96ho�c�c�����R�s���{���y�n��50�~/�ŏ��L�҂����ăe�j�X�R�[�g����݂����B�ʏ�̒����z��500�`1373�~/�ł���Œ莑�Y�Ŋz��100�`200�~/�������B�s�ŏ��ł͎s���u�L���Łv�Œ莑�Y����Ă���ꍇ�ɏ��L�҂ɌŒ莑�Y�ł��ۂ��Ƃ��Ă����B�s��Y(�퍐�A�T�i�l�A�㍐�l)�͒n���Ŗ@348��2��1���̌Œ莑�Y�ɓ�����O��Ŗ{����ېő[�u�������B�Z��X��(�����A��T�i�l�A��㍐�l)��Y�̌Œ莑�Y�ŕs���ۂƂ����ӂ�ɂ��Ēn�������@242����2��1��4��(��14�����O)�Ɋ�Â��Z���i�ׂ��N�����B ���|�@�n���Łu�@�O�l����́A���̂��������ɂ����āA�Œ莑�Y��L���Ŏ���҂�������e������̌Œ莑�Y�Ƃ��Ďg�p����ꍇ�ɂ́A�{���̋K��ɂ�����炸�A�Œ莑�Y�ł��E�Œ莑�Y�̏��L�҂ɉۂ��邱�Ƃ��ł���Ƃ��Ă���Ƃ���A�����ł����w�Œ莑�Y��L���Ŏ���x�Ƃ́A�ʏ�̎����Œ莑�Y�̑ݎ̑Ή��ɑ�������z�Ɏ���Ȃ��Ƃ��Ă��A���̌Œ莑�Y�̎g�p�ɑ���㏞�Ƃ��ċ������x�����Ă���Ƃ��ɂ́A����ɓ�������̂Ƃ����ׂ��ł���B �@�܂��A�s�ŏ��l�Z���̘Z�ɂ����w�Œ莑�Y��L���Ŏ���x���A����Ɠ���|�ł���Ɖ����ׂ��ł���B �@�Ƃ���ŁA���s���{���e�y�n�̏��L�҂�ɑ��A�y�n�̎ؓ���̌��Ԃ�Ƃ��Ďx�����Ă����̋��z�́A�ꗥ�ɎO�E�O�������[�g�������茎�z�܁Z�~�ł���A����́A�{���e�y�n��������ꍇ�̒����̈�Z���̈�ȉ��ł��邯��ǂ��A�ʐςɉ����ĕ�x�����Ă��邱�ƁA�O�L�̎g�p�ړI����݂Ė{���e�y�n�̏��ݏꏊ���ɂ���Ă��̗��p���l�ɑ傫�ȍ�������Ƃ͍l�����Ȃ����Ƃ��炷��ƁA��͓y�n�g�p�̑㏞�ł����āA���s���{���e�y�n�����x�����Ď�����Ƃ́w�Œ莑�Y��L���Ŏ���x�ꍇ�ɓ�����v�B �@�u�㍐�l���{����ېő[�u���̂������Ƃɂ�铯�s�̑��Q�ƁA�E�[�u���̂�Ȃ������ꍇ�ɕK�v�Ƃ����{���e�y�n�̎g�p�̑Ή��̎x�������邱�Ƃ�Ƃꂽ�Ƃ������s�������O�L�̍������v�Ƃ́C�Ή��W������A�܂��A�������ʊW������Ƃ����ׂ��ł��邩��A���҂͑��v���E�̑ΏۂƂȂ���̂Ƃ����ׂ��ł���B�����ł���A��҂̊z�͑O�҂̊z���������̂ł͂Ȃ�����A���s�ɂ����ẮA���ǁA�㍐�l���{����ېő[�u���̂������Ƃɂ�鑹�Q�͂Ȃ������Ƃ������ƂɂȂ�B�v |
7.2.6. �ېŕW��
7.2.6.1. �y�n�E�Ɖ�
COLUMN7-3 �y�n�̕]���ƌŒ莑�Y�ŕ��S
7.2.6.2. ���p���Y
7.2.6.3. �Œ莑�Y�̕]������щ��i���̌���
�Ŕ�����25�N7��12�����W67��6��1255�Ł�6�Ł�441.01| ���ŕs���R�����ߘa6�N5��27���ٌ��E�ٌ�����W135�W�c�c�o�^�Ƌ��ł̕]���z(�ߘa4�N12���̖@���ǂ̉B�ېő䒠�ɓo�^���ꂽ���i���Ȃ�����)���ߘa5�N1��1���Œ莑�Y�ŕ]���z���������̂Ŋҕt������������B�W���n����r�Ώۓy�n���g���ɂ����Bcf.�k���L�u����ɍs���Έ�ڗđR�v(�łŃ�������ǂ������12��) |
| �O�HUFJ�M����s�����E�Ŕ��ߘa7�N2��17���ߘa5(�s�q)177��kc
(���n���ߘa4�N3��24������1644��12�Ŕ��^1506��102�ŗߘa��(�s�E)154���F�e�E��㍂���ߘa5�N1��26���ߘa4(�s�R)67�����^1526��78�Ō��������)(�����ցE��80��4��214-228�ŁA�����ցE���Y�]�����266��3-12�ŁA�����S��E�Ō�41��1��(241��)110-116��) �����[�Ŏ҂̓��l�̘_�_�̎����̔����������ɏo�Ă���B ���n���ߘa4�N3��25������1645��16�Ŕ��^1506��106�ŗߘa��(�s�E)138���F�e�E��㍂���ߘa4�N12��13���ߘa4(�s�R)66���T�i���p�E�Ŕ��ߘa7�N2��17���ߘa5(�s�q)142���j������ �L���n���ߘa3�N7��19���ߘa2(�s�E)2�����p�E�L�������ߘa5�N3��9���ߘa3(�s�R)17������������A�����F�e�E�Ŕ��ߘa7�N2��17���ߘa5(�s�q)207���j������ ���_�@�����\���Ɖ�(��80�`90�������S����(S��:steel)�A��10�`20�������S���S�R���N���[�g���y�ѓS�R���N���[�g��(SRC��:steel reinforced concrete))�̕]���ɂ����ČŒ莑�Y�]����ʕ\��13�̌o�N���_�����K�p����ɍۂ����ʐϊ��������ɂ�炸��w�K�����ɂ����SRC���̌o�N���_�����K�p���邱�Ƃ��A�Œ莑�Y�]����Ɉᔽ���邩�H ���|�@�@(1)�u�Ɖ��̊�N�x�ɌW�镊�ۊ����ɂ�����o�^���i���]����ɂ���Č��肳��鉿�i������ꍇ�ɂ́A���̓o�^���i�̌���͈�@�ƂȂ�c�c�i�m�Ŕ�����25�N7��12�����W67��6��1255�Łn�Q�Ɓj�v�B �@(2)�u�]����́A��ؑ��Ɖ��̕]���ɓ�����K�p���ׂ��o�N���_����ɂ��A���Y��ؑ��Ɖ��̍\���敪�ɏ]���A�{����\�Ɏ�����Ă��铖�Y��ؑ��Ɖ��̌o�N���_����ɂ���ċ��߂���̂Ƃ��邪�A��ؑ��Ɖ��������\���Ɖ��ł���ꍇ�ɓK�p���ׂ��o�N���_����̋�̓I�ȋ��ߕ����߂Ă��Ȃ��B�v �@(3)�u�{����\�̒�߂�o�N���_����́A�ʏ�̈ێ��Ǘ����s�����̂Ƃ����ꍇ�ɂ����Ă��̔N���̌o�߂ɉ����Ēʏ퐶���錸������b�Ƃ��Ē�߂�ꂽ���̂ł���A��ؑ��Ɖ��̍\���敪�ɉ������A�\���ϗ͂̌����⑹���ɂ����̕����I�v���ɂ���܂�ϗp�N���i�Ɖ����g�p�ɑς��Ȃ��Ȃ�܂ł̔N���������B�ȉ������B�j����b�Ƃ��āA�@�\�I�v����o�ϓI�v���ɂ���܂�ϗp�N���Ȃǂ����l�����Ē�߂�ꂽ���̂Ɖ������B�v �@(4)�u�����\���Ɖ��ł����Ă��A�g�p�ɑς��Ȃ��Ȃ������̂Ƃ��Ă���������ǂ����ɂ��ẮA��{�I�Ɉ�P�ʂŔ��f�����v�B �@(5)�u�Ɖ��ɍ�p����d��O�͂��A�ŏI�I�ɂ͒�w�K���\������\���ɂ���ĕ��S����邱�ƂɂȂ邱�Ƃ��炷��A��L�̂悤�ȍ\���̖{���Ɖ��ɂ��ẮA���̒�w�K���\������\���̑ϗp�N�����o�߂��Ȃ�����A���̗]�̍\���̕����̕�C���ɂ���ĂȂ����̌����Ƃ��Ă̌��p�̈ێ���}�邱�Ƃ��ł�����̂ƍl������̂ł���A��L�̎�ɌW�锻�f���A��w�K���\������\���ɒ��ڂ��Ă������̂Ƃ݂邱�Ƃ��A�s�����Ƃ͂����Ȃ��B�v �@(6)�u�{���Ɖ��ɂ��āA���̒�w�K���\������\���ɉ������o�N���_����������Ă��̕]���ɓ�����K�p���ׂ��o�N���_����Ƃ��邱�Ƃ��A�m���|(3)�n�̕]����̒�߂�o�N���_����̎�|�ɏƂ炵�č��������������̂Ƃ͂������A�]����㋖�e�����v�B |
7.2.6.4. ���J�����x
7.2.6.5. �R���̐\�o����ѕs���\����
�Ŕ��ߘa���N7��16�����W73��3��211�Ł�3.2.3.�n���łɊւ���s���\���葱�Ŕ�����22�N6��3�����W64��4��1010�Ł�2.3.2.2.b.��O�I�ȑd�Ŋm��葱
| �@������E�Ŕ��ߘa2�N3��24�����W74��3��292�ŕ���30(��)388��kk(���ꗝ�s�E�W�����X�g1554��84�ŁA�_�R�O�s�E�W�����X�g1557��160��)�c�c�{���Ɖ��̌��z�����ɎZ�o���ꂽ�V�z�����̍Č��z��]�_���ɂ͌�肪����C�������b�Ƃ��ď����Z�o���ꂽ���̌�̊e��N�x�̍Č��z��]�_���ɂ���肪������Ȃǂ������߁C�{���Ɖ��ɂ��ߑ�ȌŒ莑�Y�œ��̕��ی��肪����C�����[�t�������Ƃɂ�葹�Q���������Ǝ咣���āC��ʎВc�@�l�@����͓����s�ɑ��C���Ɣ����@1��1���Ɋ�Â��C����4�`20�N�x�̌Œ莑�Y�œ��̉ߔ[���y�ѕٌ�m��p�����z�̑��Q�����𐿋������B ���|�@�u�Ɖ��̕]���Ɋւ��Č�肪������ƁC�c�c���Y��肪���̔N�x�ɂ����鉿�i����╊�ی��肾���łȂ�����N�x�ɂ�����]�����ɂ��e�����y�ڂ��C�����ɂ�����ߑ�ȌŒ莑�Y�œ��̕��ۂƂ������ʂ����������ꂪ������Ƃ������Ƃ͂ł�����̂́C���̌�̎葱�ɂ����ĉېŒ��̔��f���ɂ�蓖�Y��肪�C�������Ȃǂ���C�ߑ�ȌŒ莑�Y�œ����ۂ���邱�Ƃ͂Ȃ��C���L�҂ɑ��Q�͔������Ȃ����ƂƂȂ�B�܂��C���Y��肪��������ɏ��L�҂ɕύX������C�ߑ�ȌŒ莑�Y�œ����ۂ���đ��Q����҂��ς�邱�ƂƂȂ�B���̂悤�ɁC���Y��肪���������_�ł́C����������Ƃ��Ď��ۂɉߑ�ȌŒ莑�Y�œ����ۂ���邱�ƂƂȂ邩�ۂ��C�ߑ�ȌŒ莑�Y�œ����ۂ���đ��Q����҂��N�ł��邩�Ȃǂ́C�Ȃ��s�m��ł����Ƃ��킴��Ȃ��B�����āC���Y��肪�C�������Ȃǂ��邱�ƂȂ��葱���i�߂��C����Ɋ�Â�������N�x�̌Œ莑�Y�œ��ɂ����ی���y�є[�Œʒm���̌�t������ď��߂āC��������҂����Y���ی���̒�߂�Ŋz�ɂ��[�ŋ`�������Ƃ��m�肷�����ƂƂȂ�B �@��������ƁC�Œ莑�Y�œ��̕��ۂɊւ��C���̐Ŋz���ߑ�ł��邱�Ƃɂ�鍑�Ɣ����ӔC�������ꍇ�ɂ����āC����ɌW���@�s�y�ё��Q�́C���L�҂ɋ�̓I�Ȕ[�ŋ`���������镊�ی��蓙��P�ʂƂ��āC���Ȃ킿�N�x���Ƃɂ݂�ׂ��ł���C�Ɖ��̕]���Ɋւ��铯��̌��������Ƃ��ĕ����N�x�̌Œ莑�Y�œ����ߑ�ɉۂ��ꂽ�ꍇ�ł����Ă��C����ɌW�����Q�����������́C�N�x���Ƃɔ��������Ƃ����ׂ��ł���B�����āC����N�x�̌Œ莑�Y�œ��̉ߔ[���ɌW�鑹�Q�����������Ƃ̊W�ł́C��Q�҂ł��鏊�L�҂ɑ��ē��Y�N�x�̋�̓I�Ȕ[�ŋ`���������镊�ی���̌��͂��y���_�C��̓I�ɂ��[�Œʒm���̌�t�����ꂽ���_�������āC���ˊ��Ԃ̋N�Z�_�ł���w�s�@�s�ׂ̎��x�Ƃ݂����Ƃ������ł���B�ȏ�̂��Ƃ́C���L�҂��C���Y�N�x�ȑO�̊�N�x���̉��i����₱��Ɋ�Â��ĉۂ��ꂽ�Œ莑�Y�œ��Ɋւ��C�]���̌�蓙�𗝗R�ɐR���̐\�o�y�ю���i�ז��͍��Ɣ��������i�ׂ������đ��������Ƃ��Ă��C���E�������̂ł͂Ȃ��B �@���������āC�Ɖ��̕]���̌��Ɋ�Â�����N�x�̌Œ莑�Y�œ��̐Ŋz���ߑ�Ɍ��肳�ꂽ���Ƃɂ�鑹�Q�����������̏��ˊ��Ԃ́C���Y�N�x�̌Œ莑�Y�œ��ɌW�镊�ی��肪���ꏊ�L�҂ɔ[�Œʒm������t���ꂽ������i�s������̂Ɖ�����̂������ł���B�v |
7.2.7. �ŗ�����іƐœ_
8. ���ۉې�iy lt
8.1. ���ۓI��d�ېł͂Ȃ������邩
8.1.1. ���ƊNJ����ƉېŊNJ���
8.1.2. ���ƊNJ����ƉېŊNJ���
8.1.2.1. �NJ����̋y�Ԕ͈�
�d�Ŗ@���W�ł͍��Ёiex.���{�l���ۂ��j���ǂ��ɏZ��ł��邩���d�v�B���Z�ҁE�Z��(resident/non-resident)�c���R�l�i�l�j���ǂ��ɋ��Z���Ă��邩�B
�����@�l�E�O���@�l(domestic/foreign corporation)�c�@�l�̋��Z�n���ǂ����B
| �i���R�l�E�@�l�Ђ�����߂āA���Z�ҁE�Z�҂ƌĂԂ��Ƃ�����j |
���Z�ېŊNJ�(residence tax jurisdiction):���Z�҂ɑ��S���E�����ېŁi�������[�ŋ`���j
����ېŊNJ�(source tax jurisdiction):�Z�҂ɑ����������ېŁi�����[�ŋ`���j
���͎����ɋ��Z���Ă���҂ɑ���������(source)���ǂ������킸�ېł��Ă悢�Bjb
��������(source)�̏����Ȃ炻��Ă���҂̋��Z���ǂ������킸�ېł��Ă悢�B
�Z�҂̍��O�����ɂ��āA���Ə����Ƃ̊Ԃɉېł𐳓������錋�т�(nexus(���ێ��@�ł͘A���_�ƌĂ肷�邪�d�Ŗ@�ł͒�Ȃ��B�l�N�T�X�ƌĂ�ł���), connection)���Ȃ��B
���Ђ�Q�����͉ېō����Ƃ���ĂȂ��B�u��\�Ȃ����ĉېłȂ��v�͊ѓO����ĂȂ��B
�icf.���Z�ېŊNJ����ΐl�NJ��A����ېŊNJ����Ε��NJ��Ɛ������鏑���J�ɂ͂��邪�A���ۖ@���炷��ǂ�����Ε��NJ��ł��锤�ł���B�ΐl�NJ��͍��Ђ���Ƃ���B�j
(cf.�A�����J�͗�O�I�ɑS���E�����ېł̊�����Z�����ł͂Ȃ��A�s����(citizenship)���S���E�����ېł���b�t����BCook v. Tait, 265 U.S. 47 (1924.5.5); Ruth Mason, Citizenship Taxation, 89 Southern California Law Review 169-239 (2016); ���ː^�[�u�|��@�V�e�B�Y���V�b�v�ېŁv���R��w�@�w��G��66��2��658-592��(2016.12)�A�⊪���]�u�A�����J���O���ɂ�����s�����ېł̗��_�I�����v�Ō�41��2��(241��)18-27��)
8.1.2.2. ��O�Ƃ��Ă̎匠�Ə�
| �匠�Ə��̑��ΖƏ���`(�����Ə���`):�����O�m�f�Պ�����Ђ�p�L�X�^���E�C�X�������a�������E�Ŕ�����18�N7��21�����W60��6��2542��iz�c�c�u�����ɂ����ẮC�O�����Ƃ͎匠�I�s�ׂɂ��Ė@��n���̖����ٔ����ɕ����邱�Ƃ�Ə������|�̍��ۊ��K�@�̑��݂ɂ��ẮC��������������m�F���邱�Ƃ��ł�����̂́i�ō��ٕ����P�P�N�i�I�j��W�W�V���C���N�i��j��V�S�P�����P�S�N�S���P�Q����@�씻���E���W�T�U���S���V�Q�X�ŎQ�Ɓj�C�O�����Ƃ͎��@�I�Ȃ����Ɩ��Ǘ��I�ȍs�ׂɂ��Ă��@��n���̖����ٔ�������Ə������|�̍��ۊ��K�@�͂��͂⑶�݂��Ȃ��v�B |
| �����n������16�N11��30����51��9��2512�Łc�c�A�����J��g�ِE���̏����łɂ��ăA�����J�͌����`����Ȃ��B |
| �����n���ߘa5�N3��16���ߘa2(�s�E)508��(���p)(���_�����E�W�����X�g1597���d����5�N267-268��)�c�c���ێi�@�ٔ����̍ٔ����ł������҂����ێi�@�ٔ����ސE��ɎĂ��������͔�ېŏ����ł͂Ȃ��G�����ł���B |
8.1.3. ���ۓI��d�ېłƂ��̔r��
8.1.3.1. ���ۓI��d�ېłƂ͉���
8.1.3.2. ���ۓI��d�ېł�r�����邽�߂̕��@�\�\�����@�E�d�ŏ��
���ێ���j�Q�v�������O���邱�Ƃ̈Ӌ`�\�\��r�D��(comparative advantage)�A�C���V���^�C���͓V�˓I���z�݂̂Ȃ炸�^�C�s���O�����������炵���B�����Ń^�C�v���ׂ����H����Ȕn���ȁB�鏑���A�C���V���^�C�����^�C�s���O������ł��A�C���V���^�C�����^�C�s���O�Ɏ��Ԃ��g���̂͂��������Ȃ��B�@���@���������Ȃ��̈Ӗ��́H�@���@�@���p�̕��������B
��F�`���_�n1ha�Ŕ���10�A�Ă�20���Y�ł���B�a���_�n1ha�Ŕ���6�A�Ă�18���Y�ł���B
�`���E�a�����ꂼ��ɔ_�n��100ha������B�`�����͕�1000���A�a�����͔�300���m�ۂ������B
| �� | ��50�F��50 ���� | �`��70:��30 �a��25:��75 | ��150��400���� |
| �`�� | ��500��1000 | ��700��600 | ��550��1000 |
| �a�� | ��300��900 | ��150��1350 | ��300��950 |
�@�`���ŕĂ͔����Q�{���Y�ł���B�a���ŕĂ͔����R�{���Y�ł���B
�@�`���ŕĂ͔���1/2�̔_�n��v����B�a���ŕĂ͔���1/3�̔_�n��v����B
�@�`���͔����Y�ɂ��āA�a���͕Đ��Y�ɂ��āA��r�D���ɂ���B
��r�D�ʂɂ�����̐��Y�������������ԂŖf�Ղ��������������o�ό��������܂�B
| cf.���ƊԂ݂̂Ȃ炸�l�Ɛl�Ƃ̔�r�ɂ����Ă��K����r�D�ʂ͂���B |
|
�q���@�@�@�@�@�@�r�� �w�Ё��\�\�\�\�\���� �@���@�@�@�@�@�@�� ����@�@�@�@�@�@�x�� |
�@��F�q��(�ŗ�40%)�Ƃr��(30%)�B �@�w�Ђ̂r������100�ɂ��ē�d�ېŊ��S���u100-30-40=30 �@�w�Ђ��q������100���҂�100-40=60 �@�x�Ђ��r������100���҂�100-30=70 |
��d�ېł͉��������爫���̂ł͂Ȃ��B�o�ϊ�����c�߂邱�Ƃ������B
�@�w�Ђ��r�������邱�Ƃ́A�q�������邱�Ƃ��A�s���ł���B
�@�w�Ђ��r�������邱�Ƃ́A�x�Ђ��r�������邱�Ƃ��A�s���ł���B
�����ۓI��d�ېł���u��������ێ�����ޏk����B
��̒������T�O�Ɠ�ʂ�̓�d�ېŋ~�ϕ��@
�O���Ŋz�T��(credit method)�c�c�c�c�c100�|30�|(40�|30)��60
���ۓI��d�ېł����{�A�o�������iCEN: capital export neutrality: �q���̂w�Ђ��猩�Ď����ɓ������邩�O���ɓ������邩�ɂ��Ẳېł̒������j��j�Q����B�O���Ŋz�T���Ȃ�Ύ��{�A�o���������Q���Ȃ��B�i��ɓ`���I�ɓ��Ăō̗p�j
�O���Ŋz�T�����łw�Ђ��r�������邱�ƂƁA�q�������邱�ƂƂ��A�����I�Ɉ�����B
�@
���O�����Ɛ�(exemption method)�c�c�c100�|30�|0��70
���ۓI��d�ېł����{�A���������iCIN: capital import neutrality: �r������̎��Ƃ̏ꏊ���猩�Ď������瓊�����Ă��炤���O�����瓊�����Ă��炤���ɂ��Ẳېł̒������j��j�Q����B���O�����ƐłȂ�Ύ��{�A�o���������Q���Ȃ��B�i��ɉ��B�ō̗p�j
���O�����Ɛʼn��łw�Ђ��r�������邱�ƂƁA�x�Ђ��r�������邱�ƂƂ��A�����I�Ɉ�����B
8.1.3.3. ����n���ېł̍l�����Ɠ������ҋ�
PE�ipermanent establishment�F�P�v�I�{���j�c�c�x�X�E�H��E�㗝�l��PE�Ȃ���Ύ��Ə����ېłȂ�
�@ex.�A�����J�@�l�����{�Ɏx�X���i�Ⴆ�Δ̔����_�j��݂��Ď��Ə���������{�͉ېłł��邪�A�A�����J�@�l�Ɠ��{�̌ڋq�Ƃ̊Ԃ̒��ڎ���i�Ⴆ�l�b�g�ł̉��y�_�E�����[�h�̔��Ȃǁj�ɂ�鎖�Ə����ɑ��ē��{�͉ېłł��Ȃ��B (�|�\�l��^���I�蓙�ɂ��Ă͗�O�K�肪����)
����n����PE�ɋA�����闘���̂��ېłł���B�i�̔����_�݂̂������H��E�̔����_������݂��Đi�o���Ă�������PE�ɋA�����闘���͕ς���Ă��邾�낤�j���������ҋ�(national treatment)�c�Z�ҁE�O���@�l������Ƃ����Ă߂��Ⴍ����ɉېł��Ă悢�킯�ł͂Ȃ��A���Z�ҁE�����@�l�Ɣ�ׂč��ʓI�ɏd���ېł��邱�Ƃ͋�����Ȃ��B
�㗝�l��PE�ɊY�����邱�Ƃ�����i�㗝�l�o�d�j�B�Ɨ��㗝�l�͑㗝�lPE�ɓ�����Ȃ����Ƃ������B
8.1.3.4. ���ۓI�ȓ����E�ʏ��𑣐i���邽�߂̓���Ƃ��Ă̐Ŗ@�E���
���q�E�z���Ȃǂ����{�����i���������j�ɂ��Ă�PE�Ȃ��ł�����n���ېł��F�߂���B�������E���쌠���A���`���Y���g�p���ɂ��Ă͌���n���ېł��d�ŏ�Ƃɂ���ĔF�߂���ꍇ�ƔF�߂��Ȃ��ꍇ������B�i���đd�ŏ��Ɠ��Ƒd�ŏ��Ƃ̔�r�j
ex.���{�̋�s���A�����J��PE��݂����A�����J�@�l�ɑݕt�����ė��q���ғ�����ꍇ�B
�����ېŁc�����ғ��҂͓��{�̋�s�ł��邪�A���K���҂���A�����J�@�l������ɃA�����J�̍��ɂɔ[�ł���B�ŗ���10%�Ȃ�A����100�ł����ۂ̎x����90�B
�@���{�@�@�@�@�@�@�@�A�����J�@�@�@�b�@�@���{�@�@�@�@�@�@�@�A�����J
�@�@�@�@�@�P�O�O�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�@�@�@�@�@�@�X�O�@�@�@�@���P�O
�l�H��s�@���\�\�\�@�V�e�B�p���N�@�b�@�l�H��s�@���\�\�\�@�V�e�B�p���N
8.1.3.5. ���ۉېłɂ�������̖���
�u���ۑd�Ŗ@�v�Ƃ����@�͂Ȃ��B�ېł𗥂���̂́A�e���̍����@�߂Ɓi��������Ă���j�d�ŏ��B���ی��@�i��ʍ��ۖ@�j�ɂ��ېł̌��E�Ƃ������͂��肤�邪�A��ʂɂ͊e�����}���I�ɉېŌ����s�g���Ă���̂ŁA���ی��@�ɂ���ĉېł��ւ������ʂ����ƂȂ邱�Ƃ͖ő��ɂȂ��Ƃ����Blu
���鍑���ېŌ���\�������Ă��A�H���~�߂�p�͎�����Ȃ��B�i���̕��Q�͍����̂Ƃ��댰���łȂ��H�j
���{�ł͑d�ŏ�����@�ɗD�悷��(���@98��2��)�B��������@�D���̍����������Ȃ��B
cf.������@��茵�����ېł������Ă���ꍇ�ł������@��茵�����ېł����Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ���preservation clause(���͖����v���U�[�x�[�V���������ƌĂ��)���}������邱�Ƃ���ɂ��邪(���đd�ŏ��1��2��)�A�ł���Ɖ�����Ă���B���N��u���̃v���U�x�[�V���������\�d�ŏ����ߘ_�̍č\�z��ڎw���ā\�v(���m�_����)
�d�ŏ��͖w�ǂ����ibilateral�j�Œ�������Ă���(�����ԋ���͏��Ȃ������c�c�k���Ɠ��)�B
�d�ŏ��̈Ӌ`�����ۓI��d�ېŖh�~�@���@�o�ό𗬊������B����n���̉ېŌ��}�����A����ł��Ȃ������Ă��܂���d�ېł��~�ς���`�������Z�n���ɉۂ��Blv
�ߔN�͑d�ŏ��̈Ӌ`�Ƃ������ۓI�E�ŁE�d�ʼn���̖h�~�����������B�d�ŏ��ɍ��Ƃ��ᔽ�����ꍇ�̍��ۓI�Ȑ��ق͋ɂ߂Ďア�i�����ł͍ٔ����̑ԓx����c���{�͔�r�I�^�����H�����r�㍑�ł́H�j�B
���ᔽ���̑��荑�͏���j���ł��邪�A�o�ό𗬊������̂��߂ɏ������̂ɔj������̂ł͈Ӗ����Ȃ��B����̑d�ŏ��̉��߂��̍ٔ����̊ԂŐH���Ⴄ�\��������B
���Ǎ��Ƃ̉ېŌ�����̂́A�@�I�ɍl����Ɓi�����̖@����`�͂Ƃ������j���ۓI�ɂ͂��܂�Ȃ��B
�n�d�b�c���f���d�ŏ���i2017�N12��18�����j(OECD, Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2017)�����ەW���B
(cf.�t�m���f���d�ŏ��(2017�N��)(United Nations Model Double Taxation Convention between Developed and Developing Countries)�͍��ەW���ł͂Ȃ������B�ߔN���݊��𑝂�����Blw)
�����ɒ��������ԑd�ŏ��̃��f���E���^�ɂ����Ȃ��A�Ƃ����̂��@�I�ʒu�Â��B
���ۂɂ͂n�d�b�c���f���d�ŏ���ەW���̒n�ʂ��l�����Ă���̂ŁA������ɂ߂ďd�v�B�w�ǂ̑d�ŏ��́A�n�d�b�c���f���d�ŏ������~���Ƃ��āA�ʂ̎���ɍ��킹�����������s�Ȃ��Bjc
�ʏ�����ɂ�����v�s�n(World Trade Organization)�̂悤�������ԋ���(multilateral)�͒��炭�Ȃ������B
������2012�N������BEPS��̋c�_���n�܂�A2016�N�ɑ����ԏ��̏��������A���{��2017�N6���Ɂu�Ō��Z�H�y�ї��v�ړ]��h�~���邽�߂̑d�ŏ��֘A�[�u�����{���邽�߂̑������ԏ��v�iBEPS�h�~�[�u���{����j�ɏ��������B�iBEPS(�x�b�v�X�Ɣ�������): Base Erosion & Profit Shifting�j�i���ۓI�ɂ�MLI (Multilateral Instrument)�ƌĂ��j
�A���A�����̓ԑd�ŏ��𑽍��ԏ��ŏ㏑������Ƃ����\���ł���A�����̓ԑd�ŏ��̗����������ԏ����y���Ȃ���A�����ԏ��ł͂Ȃ������̓ԑd�ŏ��̌��͂�����������B�����ԏ��ɂ��Ċe���́u�����͎^���A�������͔��v�Ƃ����悤�ɍ��ږ��Ɏ^�ۂ�I���ł���BBEPS�h�~�̂��߂̑����ԏ��ł���Ƃ͂����A�A�����J�͂��܂�^�����ĂȂ��i���X�ABEPS��́A�A�����J�n�����Њ�Ƃ̑d�ŕ��S�y�����ڂɗ]��Ƃ������ƂŎn�܂����̂ŁA�A�����J������Ƃ���BEPS�h�~�ɏ��ɓI�ł���͓̂�����O�ł͂���j�̂ŁA���đd�ŏ��ȂǁA�A�����J���������Ă�������̓ԑd�ŏ��Ɋւ��ẮA���I�ɕω������킯�ł͂Ȃ��B
�Љ�ۏ����ۋ��i�N���ی����A���N�ی����A�Љ�ۏ�œ��j���d�ŏ��̓K�p�ΏۂƂȂ�Ȃ����A������d�v�Ȗ��ƂȂ��Ă���B��d���ۂ̖�肾���łȂ��A���ۋ��Ƌ��t�Ƃ̔�Ή����d����i�h�C�c�œ��������ɔN���|�������ۂ���Ă����{�ŘV����߂����Ƃ��ɓ��{�̔N�����ł��Ȃ��̂ł͍���j�B
�Љ�ۏዦ��(���J���̖ړI�c�c�u��d�����v�̖h�~�B�u�ی����Ԃ̒ʎZ�v
8.2. �Z�ҁE�O���@�l�ɑ���ې�
8.2.1. �Z�ҁE�O���@�l�̒�`
8.2.1.1. ��̉ېŕ���
8.2.1.1.a �Ȃ���̉ېŕ��������݂���̂�
8.2.1.1.b �ȉ��̏��q�̏���
8.2.1.2. ���Z�ҁE�����@�l�ƔZ�ҁE�O���@�l
8.2.1.2.a. �u�����v�̈Ӌ`
�I�f�R�嗤�I�����E�����n�����a57�N4��22���s�W33��4��838�ŁE�����������a59�N3��14���s�W35��3��231�ŕS�I7��70ja�c�c�嗤�I�����{�̖@�l�Ŗ@2��1���́u�����v�i�u���̖@���̎{�s�n�v�j�Ɋ܂܂��Ƃ��銵�K���ۖ@���������Ă���Ƃ����B�Ȃ��ȑO�͓��{�͒������x�����đ嗤�I�͍����ł͂Ȃ��Ƃ���������̂��Ă����B8.2.1.2.b. �u�Z���v�̈Ӌ`(����2��1��3���`5���A5���A7��)(��3.1.3.4. 6�Ł�142.01���x�m)
�����Ŗ@2���i��`�j�@�O�@���Z�ҁ@�������Z����L���A���͌��݂܂ň�����������N�ȏ㋏����L����l�������B
�@�l�@��i�Z��jd�@���Z�҂̂����A���{�̍��Ђ�L���Ă��炸�A���A�ߋ��\�N�ȓ��ɂ����č����ɏZ�����͋�����L���Ă������Ԃ̍��v���ܔN�ȉ��ł���l�������B
�@�܁@�Z�ҁ@���Z�҈ȊO�̌l�������B
����7���i�ېŏ����͈̔́j�@�����ł́A���̊e���Ɍf����҂̋敪�ɉ������Y�e���ɒ�߂鏊���ɂ��ĉۂ���B
�@��@��i�Z�҈ȊO�̋��Z�ҁ@�S�Ă̏���
�@��@��i�Z�ҁ@���\���ꍀ�i�O���Ŋz�T���j�ɋK�肷�鍑�O�����c�c�ȊO�̏����y�э��O�����ō����ɂ����Ďx�����A���͍��O���瑗�����ꂽ����
�@�O�@�Z�ҁ@��S�Z�\�l���ꍀ�e���i�Z�҂ɑ���ېł̕��@�j�Ɍf����Z�҂̋敪�ɉ������ꂼ�ꓯ���e���y�ѓ����e���ɒ�߂鍑������
�@�l�@�����@�l�@�����ɂ����Ďx�������S���\�l���e���i�����@�l�ɌW�鏊���ł̉ېŕW���j�Ɍf���闘�q���A�z�����A���t��U���A�����A���v�A���v�A���v�̕��z�y�я܋�
�@�܁@�O���@�l�@��S�Z�\����ꍀ�i���������j�ɋK�肷�鍑�������̂���������l�������\�ꍆ�܂ŋy�ё�\�O�������\�Z���܂łɌf������́m�㗪�n
| �����V��2006�N7��26���u�n���E�|�^�|��̏�������A�R�T���~�\���R��̎w�E�v �ǔ��V��2007�N6��12���u�R�U���\���R��w�E�̃n���|�^�|��ҁA���{�ېłœ��Ǎ��Ӂv �@�n���[�E�|�b�^�[�̖|��ҁE�����C�q���ɂ��āA���{���Z���X�C�X���Z���A�̑����B�|��ɂ��Ă̒��쌠�g�p���ɑ��A���{�������ېł��s�Ȃ����Ƃ��ł��邪�A���{���Z�ł���ƍŏI�I�ɒʏ�̏����ŗ����K�p�����i�����ŗ��ƌ����ŗ��̍��̐ŋ����\���[�t����K�v������j����A�X�C�X���Z�ł���Ƃ���Ɠ��{�̉ېł͌����ېł����ł��܂����̓X�C�X�ł̏����ł̓K�p�ƂȂ�B �@��҂̋L���ɂ��A���{�E�X�C�X�ېœ��ǂ������c�ŋ��Z�ɂ��č��ӂɒB�����ƕ���Ă���B���{�͏������ɑ���7���~���ǒ����z�i�{���̏����ŗ���K�p�����ꍇ�̐Ŋz�ƌ����Ŋz�Ƃ̍��z�A�y�����\�����Z���j���ۂ��B �@�]�k�F���������ŏ��ɃX�C�X���Z���Ǝ咣���ē��{�ɐ\�����Ȃ��̂ł͂Ȃ��A���O�m�F���x�Ȃǂ𗘗p���Ă���A���\�����Z�Łi9000���~���x�H�Ɛ����j�͉ۂ���Ȃ��Ă��ς�������Ȃ��B���������ŗ��m�E�ٌ�m�̏����œ��{�ւ̐\�������Ȃ������̂��Ƃ���ƁA�ŗ��m�E�ٌ�m�ɑ��Q�����𐿋��ł��邩�H |
| �����n�����a56�N3��23�����a49(�s�E)101������1004��41�ŁE�����������a59�N9��25�����a56(�s�R)24����31��4��901�Łc�c(������61��)�A�����J�R(MSTS�FMilitary Sea Transportation Service)�Ɍٗp���ꂽ���{�l�����Z�҂ɓ�����Ƃ��ꂽ����B�ČR��LST��g���Ƃ��ăx�g�i���C�擙�ŌR�������̗A���ɏ]�����댯�ɑ����������{�l�D���ɑ�����{�����{�̈��S�ی�`���ᔽ�̎咣���r�˂��ꂽ����B�ČR������댯�Ĉ��|�͔�ېő��Q�������ɓ�����Ȃ��Ƃ��ꂽ����B |
| ��|�f�Պ�����Б�\��������Z�n���莖���E�_�˒n�����a60�N12��2�����a59(�s�E)6�����^614��58�ŁE��㍂�����a61�N9��25�����a60(�s�R)59����33����1297�Łc�c�����̍���(���O)�؍ݓ������A���a52�N246(119)���A53�N207(158)���A54�N209(156)���A55�N206(160)���A56�N189(176)���ł���������B��R���|�c�c�u�����Ŗ@�Q���P���R���́C�w���Z�ҁx�Ƃ́C�����ɏZ����L���C���͌��݂܂ň��������ĂP�N�ȏ㋏����L����l�������ƋK�肵�Ă���B�Ƃ���ŁC���@���C���@�ɂ�����̂Ɠ���̗p����g�p���Ă���ꍇ�ɁC�����Ŗ@�����ɖ����������Ă��̎�|���疯�@�ƈقȂ�Ӌ`�������Ďg�p���Ă���Ɖ����ׂ����i�̎��R������ꍇ�������C���@��g�p����Ă���̂Ɠ���̈Ӌ`��L����T�O�Ƃ��Ďg�p������̂Ɖ�����̂������ł���B���������āC�E�̏����Ŗ@�̋K��ɂ�����w�Z���x�̈Ӌ`�ɂ��Ă��C�E�Ɠ��l�ł����āC�����Ŗ@�̖����܂��͂��̉��ߏ�C���@�Q�P���̒�߂�Z���̈Ӌ`�C�����e�l�̐����̖{���ƈق�Ӌ`�ɉ����ׂ��������݂����������C�����Ŗ@�̉��߂ɂ����Ă��C�Z���Ƃ͊e�l�̐����̖{�����������̂Ƃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����́C��d�ېł�������Z�҂̐\���̍�����~�����߂ɂ́C���Y�l���p�����ĂP�N�ȏ㋏�Z���邱�Ƃ������Ŗ@��̏Z���̗v���Ƃ��ĕs���̂��̂Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝ咣���邪�C���₷����m���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�v ���������c�c�_�˒n������2�N5��15���Ŏ�176��785�ŏ��a62(�s�E)11��(���p)�E��㍂������3�N9��25���Ŏ�186��635�ŕ���2(�s�R)33��(�ꕔ�F�e�A�ꕔ���p�E�T�i�l�㍐)�E�Ŕ�����5�N2��18���Ŏ�194��416��(���p) |
| ���n������11�N12��30���Ŏ�249��848��(���p)�E��㍂������13�N7��31���Ŏ�251��(���p�E�m��)�c�c�u�����ɑ���d�łɊւ����d�ېł̉���y�ђE�ł̖h�~�̂��߂̓��{�����{�ƃA�����J���O�����{�Ƃ̊Ԃ̏��v�R���R���ɂ�苏�Z�҂Ƃ����|�̔[�Ŏ҂̎咣���A�����́A�o�����Z�҂Ɋւ��钲���K��ł���A�����@�i�����Ŗ@�j��Z�҂ƂȂ�҂������̋K��ɂ�苏�Z�҂ƂȂ邱�Ƃ͂Ȃ��Ƃ��Ĕr�˂��ꂽ����B |
| �_�˒n������14�N10��7������13(�s�E)9���Ŏ�252������9208���p�E�m��)�c�c���{�̈�ˌ��ďZ��ɉƍ��������c�����܂ܓn�Ă��A�č��؍ݒ������{�ւ̍q����ɏ������Ă������ƁA�č��̉i�Z�����擾���Ă��Ȃ����ƂȂǂ���A�����Ŗ@�Q���P���R���ɋK�肷��u���Z�ҁv�ɊY������Ƃ̔[�Ŏ҂̎咣���A�č����ł̋��Z�A���{�ł̑؍ݓ����Ȃǂ���q�ϓI�ɂ݂āA�[�Ŏ҂̓��{�ɂ�����؍݂͗��A��ړI���̈ꎞ�I�Ȃ��̂ɂ������A�����̖{���͕č����̏Z���ł������ƔF�߂��邱�Ƃ���u�Z�ҁv�ɊY������Ƃ��ꂽ����B |
| �����n������17�N1��28�����^1204��171�ŕ���15(�s�E)518��(�ꕔ�F�e�A�ꕔ���p)�E����������������17�N9��21���Ŏ�255������10139����17(�s�R)102��(���p)�c�c�����Ŗ@1����2�́u�Z���v�ɂ��āB�[�Ŏ҂����`�ɕ�������ړI���A�Ŗ���㍁�`�ł̋��Z�҂Ƃ����O�`����o���邱�Ƃɂ���A�{�����^�_�������ꂽ����9�N12��18�������́A�z�e����10�����āA�Z���_��̃A�p�[�g�Ɉڂ낤�Ƃ��Ă������Ԃł����āA���Z�̈��萫�ɂ��R�������ƁA�[�Ŏ҂́A�����y�ї��X���ɂ����{�ɋA�����������A����10�N3��27���ȍ~���N7��16���܂ł́A�啔���̊��ԓ��{�ɑ؍݂��Ă������ƁA�[�Ŏ҂̍��`�ł̓����̋Ζ��`�Ԃ͌�w���C�̐F�ʂ��������Ɠ��𑍍����Ă���ƁA�[�Ŏ҂́A���`�ɕ��C����A���̏Z�������O�ɂ���A�����Ŗ@��̔Z�҂ɊY������Ƃ����O�`����o���邱�Ƃ��ł�����̂Ɗ�}���āA����9�N12��9���ɓ��{���o�����č��`�ɓ��������ɂ������A�����̑��^��������18�������A�[�Ŏ҂̐����̖{�������`�Ɉړ]���Ă���Ƃ܂ł͂������A�ˑR�Ƃ��ē��{�����̃}���V�����ɑ��݂��Ă������̂ƔF�߂���Ƃ��ꂽ����B |
| �����n������21�N1��27������20(�s�E)419�����Ŏ�259������11126�c�c���m�܂��닙�D�̏�g���̏Z���o�^�n�ł̉ېł͓K�@�B�ޗ�F���n������21�N4��16������20(�s�E)5���Ŏ�259������11180�E���n������22�N7��6���Ŏ�260������11471 |
| ���j�}�b�g�����E�����n������19�N9��14������18(�s�E)205�����^1277��173�ŔF�e�E������������20�N2��28������19(�s�R)342�����^1278��163�ōT�i���p�m��c�c�������n�����Ɋւ��A�V���K�|�[���ɏZ������ƔF��B |
| �����n������25�N5��30������2208��6�ŕ���21(�s�E)310���ꕔ�F�e�A�ꕔ���p�A�ꕔ�p��(��c���E�W�����X�g1482��112��)�c�c�A�����J�ɏ��a57�N����20�N�Z�݃A�����J�ʼni�Z�����擾�����҂ŁA����s�ɏZ����L���鋏�Z�҂��A�����Ŗ@2��1��4���́u��i�Z�ҁv�ɓ�����Ƃ���A�i�Z�҂ł��邱�Ƃ�O��Ƃ����ېŏ����͈�@�Ƃ��ꂽ����B(�n���łɊւ���1��1���̏Z���o�^������邽�߂ɓ��{����o�čs���Ă����Ƃ������Ԃ�����A�n���ł̉�������������Ƃ������ƂōT�i���Ă����炵�����A��艺�����Ċm�肵���|�A�d�Ŕ��ጤ����ɂĐ�c�����⑫�����B) |
| �����n���ߘa���N5��30������28(�s�E)434������1574��16��(�F�e)�E���������ߘa���N11��27���ߘa��(�s�R)186������1587��14�Ŋ��p�B�m��(���R�R���E�W�����X�g1554��118-121��)�c�c�Đ���3���؍ݓ����ύt����B���_�Ƃ��ē��{�ɏZ���Ȃ��Bjg |
| �����n���ߘa5�N4��12���ߘa��(�s�E)400���ꕔ�F�e�A�ꕔ���p(�ʚ����q2024�N11��15���d�Ŕ��ጤ�����)�c�c�������(���{�@�l)�̌���\�҂�����25�N5��30���ɃV���K�|�[���֓]�o����Z���o�^�Ɋւ���͏o��24���ɂ����B�Ŗ������́A��������\�҂�����25�N�`����27�N�̊Ԃ����{���Z�҂ł���Ƃ����O��ʼnېŏ����������B �@���|�@�u�����Ŗ@�Q���P���R���́A�u���Z�ҁv�Ƃ́A�u�����ɏZ����L���A���͌��݂܂ň��������ĂP�N�ȏ㋏����L����l�v�������|���K�肵�Ă���Ƃ���A�����ɂ����u�Z���v�Ƃ́A���̉��߂����ׂ����i�̎��R���Ȃ��ȏ�A�����̖{���A���Ȃ킿�A���̎҂̐����ɍł��W�̐[����ʓI�����A�S�����̒��S���w�����̂ł���A���̏ꏊ������҂́u�Z���v�ł��邩�ۂ��́A�q�ϓI�ɐ����̖{��������̂�������Ă��邩�ۂ��ɂ�茈���ׂ����̂Ɖ�����̂������ł���i�m��������w���䗾�����E�n�ō��ُ��a�Q�X�N�i�I�j��S�P�Q�����N�P�O���Q�O����@�씻���E���W�W���P�O���P�X�O�V�ŁA�ō��ُ��a�R�Q�N�i�I�j��T�T�Q�����N�X���P�R����@�씻���E�ٔ��W�����Q�V���W�O�P�ŁA�ō��ُ��a�R�T�N�i�I�j��W�S�����N�R���Q�Q����O���@�씻���E���W�P�S���S���T�T�P�ŁA�m�������x�m�����E�n�ō��ٕ����Q�O�N�i�s�q�j��P�R�X�����Q�R�N�Q���P�W����@�씻���E�ٔ��W�����Q�R�U���V�P�œ��Q�Ɓj�B�����āA�q�ϓI�ɐ����̖{��������̂�������Ă��邩�ۂ��́A�@���̎҂̏��݁i�؍ݓ����y�яZ���j�A�A�E�ƁA�B���v����ɂ���z��҂��̑��̐e���̋����A�C���Y�̏��ݓ��𑍍��I�ɍl�����Ĕ��f���ׂ����̂Ƃ�����B�v �@�u�����Q�T�N�y�ѕ����Q�U�N�ɂ����ẮA��������\�҂̐����̖{��������̂������̃��������������������ɂ������ƔF�߂��邪�A�����Q�V�N�ɂ����ẮA���̐����̖{��������̂������ɂ������Ƃ܂ł͔F�߂��Ȃ��v�B �@�m����25�N�`26�N�ɂ��ān �@�u��������\�҂��u�Z���v���V���K�|�[���Ɉړ]����ӎv��L���Ă������Ƃ͖��炩�Ƃ�����B�m���s�n�@�����Ƃ��A���̏ꏊ������҂́u�Z���v�ł��邩�ۂ��́A�q�ϓI�ɐ����̖{��������̂�������Ă��邩�ۂ��ɂ�茈���ׂ����̂ł��邩��A���̂悤�Ȉӎv�݂̂������āA�����ɂ���f���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��v�B �@�u�؍ݓ����́A�ʎ��U�̕\�̂Ƃ���ł���i�����Q�T�N�ɂ����ẮA�������P�S�P���A�V���K�|�[�����T�U���A�����Q�U�N�ɂ����ẮA�������Q�T�R���A�V���K�|�[�����W�X���j�m���n�v �@�u��������\�҂́A�����Q�T�N�y�ѕ����Q�U�N�ɂ����āA�V���K�|�[���ɑ؍ݒ��A���j�Ђ̃��C�����Ƃɏ]�����Ă���A���̋Ɩ��̓��e���Ɋӂ݂Ă��A����V���K�|�[���ɑ؍݂���K�v�������������̂ƍl�����邪�A�����ŁA�����Q�T�N�y�ѕ����Q�U�N�ɂ����鍑�ʑ؍ݓ��������݂�ƁA�ʎ��U�̕\�̂Ƃ���A�P�����ȏ���A�����ăV���K�|�[���֓n�q���Ă��Ȃ����Ԃ��ԁX���������ƂȂǂ��F�߂��邩��A���̕p�x�����炵�āA��������\�҂̐����̖{��������̂f�����Ō���I�Ȏ���ɂ͂Ȃ�Ȃ��v�B �@�u��������\�҂ɂ́A���v����ɂ���z��҂��̑��̐e�������炸�A�{���O�Ȃɂ��ẮA���N�A�ʋ���Ԃł��������A�{�������ɂ��Ă��A�𗬓��͂Ȃ��������Ƃ��F�߂���v�B �@�m����27�N�ɂ��ān �@�u��������\�҂́A�j�Ђ̃��C�����Ƃ��O���ɏ��n�߁A�V���K�|�[���ɑ؍݂���K�v�������܂������Ƃ�����A�����Q�V�N�ɂ����ẮA�ʎ��U�̕\�̂Ƃ���A�V���K�|�[���֓n�q����p�x���������A�����V���K�|�[���ɑ؍݂���悤�ɂȂ������A����܂ŃV���K�|�[���Ŏg�p���Ă����I�[�`���[�h�����ł́A�苷�ɂȂ������Ƃ���A�R�K���ĂŃ��C���q�ɂ݂����R�[���E�F�C����������A�����Ő������Ă������ƂȂǂ��F�߂���B�܂��A��������\�҂̕����Q�V�N�ɂ�����؍ݓ����ɂ��Ă݂�ƁA�ʎ��U�̕\�̂Ƃ���ł���i�������P�V�V���A�V���K�|�[�����P�U�R���j�A�����ł̑؍ݓ����́A�����Q�T�N�y�ѕ����Q�U�N�ɂ�����؍ݓ����Ƃ͈قȂ�A�N�Ԃ̔����ɖ����Ȃ����A�V���K�|�[���ł̑؍ݓ����Ɣ�r���Ă��A�L�ӂȍ�������Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B�����āA��������\�҂́A�����Q�V�N�ɂ����Ă��A�������������������������_�Ƃ����̏ꏊ��]�X�Ƃ��Ă���A�����ɑ؍ݒ��A�����ɑ؍݂��Ȃ����Ƃ�������������ŁA�V���K�|�[���ɑ؍ݒ��́A�V���K�|�[�������ȊO�̏ꏊ��]�X�Ƃ��Ă����Ƃ��鎖��͔F�߂��Ȃ��Ƃ���A�O�L�A�i�L�j�ŏq�ׂ��悤�ɁA�������̏ꏊ�ł̂ݑ؍݂��鎖�ĂƁA���Y����̏ꏊ�����_�Ƃ������̏ꏊ��]�X�Ƃ��ē��Y����̏ꏊ�ő؍݂��Ȃ����Ƃ��������ĂƂ��r�����ꍇ�A���̎҂̐����Ƃ̊W��Ȃ���̒��x���̓_�ŁA���̂����獷�ق�������̂ƍl�����邵�A���̑��ɂ��A�{���ł́A�����ɂ́A�p���I�Ȑ����𑗂邽�߂̏Z���Ƃ����邾���̎��̂��Œ���������ɂƂǂ܂�A�I�[�_�[���C�h�̂��̂��܂߉Ƌ��ߕ������\���ɔ������Ă����V���K�|�[�������Ɣ�r����ƁA����炪�[�����Ă����Ƃ͂����Ȃ����ƂȂǂ��w�E���邱�Ƃ��ł���B�v �@�u�E�Ƃɂ��Ă݂Ă��A��������\�҂́A�V���K�|�[���ɑ؍ݒ��A���j�Ђ̃��C�����Ƃɏ]�����Ă���A���̋Ɩ��̓��e���Ɋӂ݂Ă��A����V���K�|�[���ɑ؍݂���K�v�����������Ƃ���A�ȏ�ŏq�ׂ��悤�ɁA�����Q�V�N�ɂ����ẮA�j�Ђ̃��C�����Ƃ��O���ɏ���āA���̕K�v�������܂������Ƃ�����A�V���K�|�[���֓n�q����p�x���������A�����V���K�|�[���ɑ؍݂���悤�ɂȂ����v�B �@�u�����Q�V�N�ɂ����ẮA��������\�҂̐����̖{��������̂������̃��������������������ɂ��������Ƃ�ϋɓI�Ɋ�b�t���邱�Ƃ͂ł��Ȃ����A�{���̎����W�̉��ł́A�ނ���A���̐����̖{��������̂̓V���K�|�[�������ɂ������v�B |
| KPT General Trading LLC�����E�����n���ߘa5�N5��30���ߘa3(�s�E)334���ߘa4(�s�E)378��(�c���ǁE�W�����X�g1602��10-11�ŁA��ؗI�ƁE�W�����X�g1610���d����6�N158-159��) �@�����@�����́A�h�o�C���̏Z����{�X���ݒn�Ƃ��i�ȉ��A���{�X���u�h�o�C�{�X�v�Ƃ����B�j�A�A�o���Ɋւ���f�ՋƖ��y�т���ɕt�ъ֘A�����̎��Ƃ�ړI�Ƃ���k�k�b�ł���B�A�M���Ƃł���t�`�d�ɂ����ẮA�@�l�i�k�k�b���܂ށB�ȉ������B�j�ɑ���A�M���x���̉ېŐ��x���݂����Ă��炸�A�e�����Ǝ��̉ېŐ��x��L���Ă���B�܂��A�h�o�C�ɂ����ẮA�h�o�C�����Ŗ��߂��A�S�ẲېőΏێ҂̉ېŏ����ɑ��ď���̐ŗ��ɂ�鏊���ł��ۂ��|�K�肵�Ă��邪�A�����_�ɂ����āA���ۂɑd�ł��ۂ����̂́A�Ζ���ЁA�K�X��ЁA�Ζ����w��Ж��͊O����s�̎x�X���Ɍ����Ă���B���̂��߁A�����́A�t�`�d�y�уh�o�C�ɂ����đd�ł��ۂ���Ă��Ȃ��B �@�L���Ŗ������́A�ߘa���N�V���Q�X���t���ŁA�������ŋǂ̐E���̒����Ɋ�Â��A�����̕����Q�V�N�P�Q�����ƔN�x���畽���Q�X�N�P�Q�����ƔN�x�܂ł̖@�l�ł̊e���菈���y�і��\�����Z�ł̊e���ی��菈���A���тɁA�����Q�V�N�P�Q���ېŎ��ƔN�x���畽���Q�X�N�P�Q���ېŎ��ƔN�x�܂ł̒n���@�l�ł̊e���菈���y�і��\�����Z�ł̊e���ی��菈�������A�����ɑ����̎|�ʒm�����B �@���_1�F�����ɖ{�����(�����ɑ���d�łɊւ����d�ېł̉���y�ђE�ł̖h�~�̂��߂̓��{���ƃA���u���A�M�Ƃ̊Ԃ̏��)�̓K�p�����邩�i�������{�����S���P�ɋK�肷��u����̒��̋��Z�ҁv�ɓ����邩�j �@���_2�F�������{���e���ƔN�x�ɂ����Ĕ[�t���ׂ��@�l�ł̉ېŕW���ƂȂ鍑�������̗L���y�т��͈̔� �@���_3�F�{���e�����ɗ��R�t�L�̕s���̈�@�����邩 �@���|�@���_1�u�{�����S���P�́A�u����̒��̋��Z�ҁv�ɂ��āA���Z�Ҋ�ɂ�蓖�Y����̒��ɂ����ĉېł���ׂ����̂Ƃ����҂������|�K�肵�Ă���B �@�������A�O�L�i�Q�j�A�̂Ƃ���A�A�M���ƂƂ��Ă̂t�`�d�́A�@�l�ɑ���ېŐ��x��݂��Ă��Ȃ��B �@�܂��A�O�L�i�Q�j�C�̂Ƃ���A�h�o�C�����Ŗ��߂̋K��ɂ��A�h�o�C�ɏ��݂���P�v�I�{�݂�ʂ��ăh�o�C�ɂ����Ď��Ƃ��s���@�l�́A���̐ݗ��n�A�{�X���͎傽�鎖�����̏��ݒn�����킸�A�������u�ېőΏێҁv�ɊY�����A���A�h�o�C�ɂ����������͎��ƂɗR�����鏊���Ɍ����ĉېőΏۂƂ���|�K�肳��Ă���̂ł��邩��A�h�o�C�����Ŗ��߂Ɋ�Â��A�u�Z���A�����A�{�X���͎傽�鎖�����̏��ݒn�A���Ƃ̊Ǘ��̏ꏊ���̑������ɗނ����v�i���Z�Ҋ�j�ɂ��ېł���ׂ����̂Ƃ����҂͂Ȃ��B �@��������ƁA�ȏ�̂悤�Ȃt�`�d�y�уh�o�C�̐Ő��̉��ɂ����ẮA�h�o�C�@�l�́A�h�o�C�́u���Z�ҁv�A���Ȃ킿�{�����S���P�̋K�肷��u����̒��̋��Z�ҁv�ɂ͓�����Ȃ��i�Ȃ��A�{���c�菑�Q���́A�t�`�d���U�@�ւ��u����̒��̋��Z�ҁv�Ɋ܂܂��|�K�肵�Ă���Ƃ���A����́A��L�̂Ƃ���A�t�`�d�y�уh�o�C�̐Ő��̉��ɂ����āA�t�`�d���̓h�o�C�́u���Z�ҁv�Ƃ����҂͂Ȃ����ŁA���{�Ƃt�`�d���A�t�`�d�̖@�l���Ŗ{�����̓��T������ł���҂���ɍ��ӂɂ���߂����̂Ɖ������B�j�B�v |
8.2.1.2.c. ���������u�@�l�v�Ƃ����邩(��4.2.5. Delaware LPS)
8.2.1.2.d. �����@�l�ƊO���@�l�̋��(�@��2��3���E4���A5���A9��
�@�l�Ŗ@2���i��`�j�@�O�@�����@�l�@�������{�X���͎傽�鎖������L����@�l�������B
�@�l�@�O���@�l�@�����@�l�ȊO�̖@�l�������B
�@��5���i�����@�l�̉ېŏ����͈̔́j �@�����@�l�ɑ��ẮA�e���ƔN�x�c�c�̏����ɂ��Ċe���ƔN�x�̏����ɑ���@�l�ł��A���Z�����ɂ��Đ��Z�����ɑ���@�l�ł��ۂ���B
�@��9���i�O���@�l�̉ېŏ����͈̔́j�@�O���@�l�ɑ��ẮA�e���ƔN�x�̏����̂�����141���e���i�O���@�l�ɌW��@�l�ł̉ېŕW���j�Ɍf����O���@�l�̋敪�ɉ������Y�e���Ɍf�������������ɌW�鏊���ɂ��āA�e���ƔN�x�̏����ɑ���@�l�ł��ۂ���B �m2�����n
���ӁI�@�`���@�l���a�����q�����݂���ƁA����͂a�����Z�҂ł���B
�@�@�@�@�`���@�l���a�����x�X��݂���ƁA����͂`�����Z�҂̈ꕔ�ł���B
���ĉ��Ŗ@�l�̋��Z�n�������قȂ�B
�{�X���ݒn��c�c���{���猩�Ĉ���@�l�̖{�X�����{�ɂ��邩�ۂ��ŋ�ʁB
�ݗ������@��c�c�A�����J���猩�Ĉ���@�l���A�����J�̖@���i�Ȃ��A�A�����J�̉�Ж@�͏B�@�j�ɏ������Đݗ����ꂽ�̂��ۂ��ŋ�ʁB
�Ǘ��x�z�n��c�c�C�M���X���猩�Ĉ���@�l�̒��S�I�ȊǗ��x�z���C�M���X�ōs���Ă��邩�iex. De Beers v. Howe [1906] A.C. 455, 5 TC 198�j�B��ɉ��B�ō̗p����Ă����B
8.2.1.2.e. �����̍��ŋ��Z�ҁE�����@�l�ƈ�������
8.2.1.2.f. �[�ŋ`���҂̒n�ʂ̕ύX
���O�]�o���ېŐ��x(�����Ŗ@60����2�ȉ�)�n��(��4.2.3.5.)8.2.1.3. �d�ŏ��ɂ�����[�ŋ`���҂̕���
8.2.1.3.a. �d�ŏ���́u���Z�ҁv(OECD���f��4��1���������@���Q�ƁB��d���Z�̏ꍇ�A2���y��3��tie breaker rule)
8.2.1.3.b. ���l�ȃG���e�B�e�B�̈���(Hybrid Mismatch Arrangement)(BEPS Action 2)
8.2.2. �\���E�[�t�̑ΏۂƂȂ鏊���͈̔͂Ƃ��̌v�Z
8.2.2.1. �u�P�v�I�{�݁v�Ƃ͉���
8.2.2.1.a. �u�P�v�I�{�݁v�T�O�̋N��(OECD���f��5���A����2��1��8����4�A���ŗ�1����2�A�@��2��12����19�A�@�ŗ�4����4)
�@��2���\��̏\��@�P�v�I�{�݁@���Ɍf������̂������B�������A�䂪�����������������ɑ���d�łɊւ����d�ېł̉�͒E�ł̖h�~�̂��߂̏��ɂ����Ď��Ɍf������̂ƈقȂ��߂�����ꍇ�ɂ́A���̏��̓K�p����O���@�l�ɂ��ẮA���̏��ɂ����čP�v�I�{�݂ƒ�߂�ꂽ���́i�����ɂ�����̂Ɍ���B�j�Ƃ���B
�@�C�@�O���@�l�̍����ɂ����x�X�A�H�ꂻ�̑����Ƃ��s�����̏ꏊ�Ő��߂Œ�߂����
�@���@�O���@�l�̍����ɂ��錚�ݎႵ���͐��t���̍H�����͂����̎w���ē̖̒��s���ꏊ���̑�����ɏ�������̂Ƃ��Đ��߂Œ�߂����
�@�n�@�O���@�l�������ɒu�����Ȃ̂��߂��_���������錠���̂�������̑�����ɏ�����҂Ő��߂Œ�߂����
�@�ŗ�4����4�i�P�v�I�{�݂͈̔́j�@�@�����\�̏\��C�i��`�j�ɋK�肷�鐭�߂Œ�߂�ꏊ�́A�����ɂ��鎟�Ɍf����ꏊ�Ƃ���B
�@��@���Ƃ̊Ǘ����s���ꏊ�A�x�X�A�������A�H�ꖔ�͍�Ə�
�@��@�z�R�A�Ζ����͓V�R�K�X�̍B��A�̐Ώꂻ�̑��̓V�R�������̎悷��ꏊ
�@�O�@���̑����Ƃ��s�����̏ꏊ�mfixed place of business�n
�Q�@�@�����\�̏\�ネ�ɋK�肷�鐭�߂Œ�߂���̂́A�O���@�l�̍����ɂ��钷�����ݍH�����ꓙ�i�c�c�i�c�c��N���čs������́c�c�j�c�c�j�Ƃ���B�m3�����F������n
�S�@�O���@�l�̍����ɂ����鎟�̊e���Ɍf���銈���̋敪�ɉ������Y�e���ɒ�߂�ꏊ�c�c�́A��ꍀ�ɋK�肷�鐭�߂Œ�߂�ꏊ�y�ё�ɋK�肷�鐭�߂Œ�߂���̂��܂܂�Ȃ����̂Ƃ���B�������A���Y�e���Ɍf���銈���c�c���A���Y�O���@�l�̎��Ƃ̐��s�ɂƂ������I���͕⏕�I�mpreparatory or auxiliaryjn�n�Ȑ��i�̂��̂ł���ꍇ�Ɍ�����̂Ƃ���B
�@��@���Y�O���@�l�ɑ����镨�i���͏��i���ۊǁA�W�����͈��n���mstorage, display and delivery�n�̂��߂ɂ̂ݎ{�݂��g�p���邱�Ɓ@���Y�{��
�@��@���Y�O���@�l�ɑ����镨�i���͏��i�̍ɂ�ۊǁA�W�����͈��n���̂��߂ɂ̂ݕۗL���邱�Ɓ@���Y�ۗL���邱�Ƃ݂̂��s���ꏊ
�@�O�@���Y�O���@�l�ɑ����镨�i���͏��i�̍ɂ����Ƃ��s�����̎҂ɂ����H�̂��߂ɂ̂ݕۗL���邱�Ɓ@���Y�ۗL���邱�Ƃ݂̂��s���ꏊ
�@�l�@���̎��Ƃ̂��߂ɕ��i�Ⴕ���͏��i���w�����A���͏������W���邱�Ƃ݂̂�ړI�Ƃ��āA��ꍀ�e���Ɍf����ꏊ��ۗL���邱�Ɓ@���Y�ꏊ
�@�܁@���̎��Ƃ̂��߂ɑO�e���Ɍf���銈���ȊO�̊������s�����Ƃ݂̂�ړI�Ƃ��āA��ꍀ�e���Ɍf����ꏊ��ۗL���邱�Ɓ@���Y�ꏊ
�@�Z�@��ꍆ�����l���܂łɌf���銈���y�ѓ��Y�����ȊO�̊�����g�ݍ��킹���������s�����Ƃ݂̂�ړI�Ƃ��āA��ꍀ�e���Ɍf����ꏊ��ۗL���邱�Ɓ@���Y�ꏊ�m5�����F�ו�����n�m6�����n
�V�@�@�����\�̏\��n�ɋK�肷�鐭�߂Œ�߂�҂́A�����ɂ������O���@�l�ɑ����mon behalf of�n�A���̎��ƂɊւ��A�����������Ɍf����_����������A���͓��Y�O���@�l�ɂ�ďd�v�ȏC�����s���邱�ƂȂ�����I�ɒ�������鎟�Ɍf����_��̒����̂��߂ɔ������Ď�v�Ȗ������ʂ����ҁi���Y�҂̍����ɂ����铖�Y�O���@�l�ɑ��čs�������c�c���A���Y�O���@�l�̎��Ƃ̐��s�ɂƂ������I���͕⏕�I�Ȑ��i�̂��́c�c�݂̂ł���ꍇ�ɂ����铖�Y�҂������B�����ɂ����āu�_������㗝�l���v�Ƃ����B�j�Ƃ���B
�@��@���Y�O���@�l�̖��ɂ����Ē��������_��
�@��@���Y�O���@�l�����L���A���͎g�p�̌�����L������Y�ɂ��āA���L�����ړ]���A���͎g�p�̌�����^���邽�߂̌_��
�@�O�@���Y�O���@�l�ɂ��̒̂��߂̌_��
�W�@�����ɂ����ĊO���@�l�ɑ��čs������҂��A���̎��ƂɌW��Ɩ����A���Y�O���@�l�ɑ��Ɨ��mindependent�B���Ό�͏]��dependent jm�n���čs���A���A�ʏ�̕��@�min the ordinary course of their business�n�ɂ��s���ꍇ�ɂ́A���Y�҂́A�_������㗝�l���Ɋ܂܂�Ȃ����̂Ƃ���B�������A���Y�҂��A��疔�͎�Ƃ��Ĉꖔ�͓�ȏ�̎��ȂƓ���̊W�ɂ���҂ɑ����s������ꍇ�́A���̌���łȂ��B�m9�����n
8.2.2.1.b. �x�XPE(����2��1��8����4�C�A�@��2��12����19�C
| ���{�K�C�_���g�����E������������19�N6��28������1985��23��jl(��5.1.1. 8.2.3.2.k.) �@�@���{�@�@�@�@�@�@�@�@�@�I�����_�@�@�@�@�@�A�����J ���������������������v���z���������@�H�H�@�������������� �����{�K�C�_���g���\�\�\�����������c�c�c�����K�C�_���g�� �������������������@�@�@�@���������@�@�@�@�������������� �@�@�c�ƎҁH�@�@�@�@�@�@�����g�����H ���_ (1)���{�K�C�_���g��(��)�K�C�_���g�̗��v���z�ł���A�����łȂ����ĊW�ł͂Ȃ����H(�����8.2.3.3.2.) (2)���{�K�C�_���g�ƌ����͓����g���_��Ə̂��邪���Ԃ͔C�ӑg���_��ł͂Ȃ����H (3)�����g���_��Ɋ�Â����v���z�̏����敪�͉����H�i�d�ŏ��̂ǂ̏��j (4)�����͓��{��PE��L����ƔF�肳��邩�H���̗��v��PE�ɋA������̂��H �w�i����@�����g���_��Ɋ�Â��c�Ǝ҂��瓽���g�����ւ̗��v���z�́AOECD���f��21���i�����d�ŏ��23���j�ɂ������̑�����(��8.2.3.3.)�ɓ�����̂ŁA����n���Ƃ��Ă̓��{�͉ېł��邱�Ƃ��ł��Ȃ��A�Ƃ����������������悤�ł���BTK�X�L�[���Ƃ��ėL���ƂȂ����Ƃ�������B �@�����A�����đd�ŏ��(2003�N�����O)�ɂ͂��̑������������Ȃ������B�@���@����n���Ƃ��ē��{�͓����g��������闘�v���z�ɑ��ېŌ���L����B�i�V���đd�ŏ��ł����{�̉ېŌ����m�F�j�i��ɐV�����d�ŏ����j �@�����A���O���ł͓����g���_����܂ޗ��v���L�W�ɂ����ĔZ�҂�����n������PE��L����ƔF�肳���i���{�ł��C�ӑg���Ȃ�PE�F��j�̂��ʗ�Ƃ���Ă���B�{���Ɋւ��Ă��A�����̓I�����_�ېœ��ǂ���u���{��PE�ېł���̂ŃI�����_�ł͉ېł��Ȃ��v�Ƃ����戵�����Ă����Ƃ����B �ٔ����̔��f (1)�����̓A�����J�@�l�̃_�~�[�ł͂Ȃ��A�I�����_���Z�҂Ȃ̂ŁA�����d�ŏ��̕։v������B (2)�����g���_��Ə̂��Ă��邱�ƂɋU��͂Ȃ��B�C�ӑg���_��ł��Ȃ����A�ېœ��ǂ��咣����悤�Ȕ�T�^�����g���Ȃ���̂ł��Ȃ��B�i�������قōł�����������ꂽ�悤�ł���j (3)�����敪�͂��̑������ł���B�i�����n�ق̔��f�𓌋����ق����̂܂ܐ��F�j �i(4)PE�̑��ۂɂ��āA���̑������Ȃ̂ŁA�����Ӗ����Ȃ��j �����@(1)(2)�ɂ��āc�c�d�ŏ��̖��̑O�ɂ܂��_������̖�肪����B �@�_�̋L�ڂ��o���_�����A���ꂪ�S�Ăł͂Ȃ��B�������ېœ��ǂ��_�̋L�ڂƈقȂ�_����߂�F�肵�Ă��炤���Ƃ͗e�Ղł͂Ȃ��B�����s���ł͂Ȃ��ƔF�肳�ꂽ(��3.1.3.2. 6�Ł�143.02���ݔ���etc)�B �@(3)(4)�ɂ��āc�c�����g���_��̏ꍇ�A�y���̑������Ƃ����z�yPE���F�肳��Ȃ��z�Ƃ������E�I�Ɍ��Ă��Ȃ�ٗ�Ȕ��f�����{�ł͂Ȃ���邱�Ƃ��ٔ��ɂ���Ė��炩�ƂȂ����B �@���̑������Ƃ���Ă���̂ŁAPE�F��̊�͕s���̂܂܂ł���B �@���̑��A���{���I�����_���ېł��Ȃ��Ƃ�����d��ې��̋A���ƂȂ邱�Ƃɂ��A�d�ŏ��̖ړI�͓�d�ېŖh�~�����łȂ���d��ېŖh�~�ł�����̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����٘_���l������B���A�ٔ����́A���O���̐Ŗ��戵���d��ېł̖��ɂ��Ă͋ɂ߂đf���C�Ȃ���̂ĂĂ���B �@�i[���]�I�����_�܂߉��B�̏펯�Ƃ��Ă͓����g���_��ɌW�闘�v�̕��z�́A����n����PE����Ƃ��ĉېł����(�����͗��q�����Ƃ��ĉېł����)�Ƃ������ƂɂȂ��Ă��邪�A���{�̉ېŒ��́A�����g���_��̏ꍇ��PE���F��ł���Ƃ����咣�����Ȃ������B���̌l�I�����������̕����ɑ��������߂Ƃ��Ă͉��B�̏펯�̕�������������(���͂����茾���Č��_���肫�ʼn��B�l�͍l���Ă���ɂ����Ȃ�)�A�������ق͏����߂̐ߓx��������Ƃ�����Ǝv����j |
| �����ԕ��i�A���ƎҎ����E�����n������27�N5��28����63��4��1252�ŕ���24(�s�E)152���E������������28�N1��28����63��4��1211�ŕ���27(�s�R)222���S�I7��72(���J���j�E�W�����X�g1494��119��) �@�����w��(���{���ЂƎv����)��2004�N4��15���ɃA�����J�l�����ƌ�����2004�N10��23���ɓn�Ă��A�����J���Z��(���{���猩�ĔZ��)�ɂȂ����B�w��2002�N���玩���ԕ��i���A���Ƃ��c��ł����B�w�͓n�Č�����Ɍ������s�̃A�p�[�g�̕����Ŏ����ԕ��i�A���Ƃ𑱂����B2006�N11��29���͑q�ɂ������n�߂��B �@���{�̉ېŒ��́A�w�̗A���Ƃ̂��߂̃A�p�[�g�̕����y�ёq�ɂ�PE�ɓ�����Ǝ咣�����B �@�w�́A�A�p�[�g�̕����y�ёq�ɂ������I���͕⏕�I�Ȑ��i�̊����̂��߂̏ꏊ�ł���Ǝ咣�����B �@�ٔ����́A���đd�ŏ��5��4��(a)��storage, display and delivery�͏����I���͕⏕�I�Ȋ������Ꭶ�ɂ������A���Ƃ�storage��delivery(�Ƃ�킯���n��)�̂��߂̏ꏊ�ł����Ă������I���͕⏕�I�Ȑ��i�̊����łȂ����PE�ɓ�����Ɣ��f�����B �@(�⏕�m���FUN���f���d�ŏ��ł�delivery(���n��)�������I���͕⏕�I�Ȋ����̗�Ƃ��ċ����ĂȂ��B) �@�w�̕s���͗����ł��Ȃ��ł͂Ȃ��BAmazon�̓��{���ݑq�ɂ͏����I���͕⏕�I�Ȑ��i�̊����������ĂȂ��Ƃ������R��PE�ƔF��ł��Ȃ�(���{�̉ېŒ���PE�ƔF�肵�悤�Ƃ��������������c(��8.5.4.)�̌��ʁAPE�ł͂Ȃ��Ƃ������_�ɂȂ����ƕ���Ă���B�����V��2009�N7��4����)�̂�����B |
8.2.2.1.c. ���ݍ��PE(����2��1��8����4���A�@��2��12��19��)
8.2.2.1.d. �㗝�lPE(����2��1��8����4�n�A�@��2��12����19�n)
8.2.2.1.e. �d�ŏ��ɂ�����P�v�I�{�݂̒�`(OECD���f��5��)
8.2.2.2. �\�[�X�E���[���̈Ӌ`�Ƌ@�\(����161���A�@��138��)
����161���i���������j�@���̕҂ɂ����āu���������v�Ƃ́A���Ɍf������̂������B�@��@�Z�҂��P�v�I�{�݂�ʂ��Ď��Ƃ��s���ꍇ�ɂ����āA���Y�P�v�I�{�݂����Y�Z�҂����Ɨ����Ď��Ƃ��s�����Ǝ҂ł���Ƃ����Ȃ���A���Y�P�v�I�{�݂��ʂ����@�\�A���Y�P�v�I�{�݂ɂ����Ďg�p���鎑�Y�A���Y�P�v�I�{�݂Ɠ��Y�Z�҂̎��Əꓙ�c�c�Ƃ̊Ԃ�����������̑��̏����Ă��āA���Y�P�v�I�{�݂��A������ׂ������i���Y�P�v�I�{�݂̏��n�ɂ�萶���鏊�����܂ށB�j
�@��@�����ɂ������Y�̉^�p���͕ۗL�ɂ�萶���鏊���i�攪�������\�Z���܂łɊY��������̂������B�j
�@�O�@�����ɂ������Y�̏��n�ɂ�萶���鏊���Ƃ��Đ��߂Œ�߂����
�@�l�@���@��Z�S�Z�\�����ꍀ�i�g���_���j�ɋK�肷��g���_��c�c�Ɋ�Â����P�v�I�{�݂�ʂ��čs�����Ƃ��琶���闘�v�œ��Y�g���_��Ɋ�Â��Ĕz����������̂������߂Œ�߂����
�@�܁@�����ɂ���y�n�Ⴕ���͓y�n�̏�ɑ����錠�����͌����y�т��̕����ݔ��Ⴕ���͍\�z�������n�ɂ��Ή��c�c
�@�Z�@�����ɂ������l�I���̒��傽����e�Ƃ��鎖�ƂŐ��߂Œ�߂���̂��s���҂��铖�Y�l�I�̒ɌW��Ή�
�@���@�����ɂ���s���Y�A�����ɂ���s���Y�̏�ɑ����錠���Ⴕ���͍̐Ζ@�c�c�̋K��ɂ��̐Ό����ݕt���c�c�A�z�Ɩ@�c�c�̋K��ɂ��d�z���̐ݒ薔�͋��Z�ҎႵ���͓����@�l�ɑ���D���Ⴕ���͍q��@�̑ݕt���ɂ��Ή�
�@���@���\�O���ꍀ�i���q�����j�ɋK�肷�闘�q���̂������Ɍf������́m�C���n�j���n
�@��@���\�l���ꍀ�i�z�������j�ɋK�肷��z�����̂������Ɍf������́m�C�����n
�@�\�@�����ɂ����ċƖ����s���҂ɑ����ݕt���i����ɏ�������̂��܂ށB�j�œ��Y�Ɩ��ɌW����̗̂��q�i���߂Œ�߂闘�q�������A���̔��ߖ��͔��ߏ����t��������m����3.1.2.2. ��8.2.3.2.e.���|����B���������F���ŗ�283��3���A4���n�Ƃ��Đ��߂Œ�߂���̂��琶���鍷�v�Ƃ��Đ��߂Œ�߂���̂��܂ށB�j
�@�\��@�����ɂ����ċƖ����s���҂���鎟�Ɍf����m�m�I���Y���́n�g�p�����͑Ή��œ��Y�Ɩ��ɌW����́m�C���n���n
�@�\��@���Ɍf�������^�A��V���͔N���m�C���n���n
�@�\�O�@�����ɂ����čs�����Ƃ̍L����`�̂��߂̏܋��Ƃ��Đ��߂Œ�߂����
�@�\�l�@�����ɂ���c�Ə����͍����ɂ����Č_��̒����̑㗝������҂�ʂ��Ē��������ی��Ɩ@�����O���i��`�j�ɋK�肷�鐶���ی���Ж��͓����l���ɋK�肷�鑹�Q�ی���Ђ̒�������ی��_�̑��̔N���ɌW��_��Ő��߂Œ�߂���̂Ɋ�Â��Ď�N���c�c�ő�\���ɊY��������̈ȊO�̂��́c�c
�@�\�܁@���Ɍf���鋋�t��U���A�����A���v���͍��v�m�C���n�j�z�w���n
�@�\�Z�@�����ɂ����Ď��Ƃ��s���҂ɑ���o���ɂ��A�����g���_��c�c�Ɋ�Â��Ď闘�v�̕��z
�@�\���@�O�e���Ɍf������̂̂ق����̌������ɂ��鏊���Ƃ��Đ��߂Œ�߂����
�Q�@�O����ꍆ�ɋK�肷����������Ƃ́A�Z�҂̍P�v�I�{�݂Ǝ��Əꓙ�Ƃ̊Ԃōs��ꂽ���Y�̈ړ]�A�̒��̑��̎����ŁA�Ɨ��̎��Ǝ҂̊Ԃœ��l�̎����������Ƃ����Ȃ���A�����̎��Ǝ҂̊ԂŁA���Y�̔̔��A���Y�̍w���A�̒��̑��̎���i�����̎ؓ���ɌW����̕ۏA�ی��_��ɌW��ی��ӔC�ɂ��Ă̍ĕی��̈����̑������ɗނ������Ƃ��Đ��߂Œ�߂���̂������B�j���s��ꂽ�ƔF�߂�����̂������B
�R�@�P�v�I�{�݂�L����Z�҂������y�э��O�ɂ킽�đD�����͍q��@�ɂ��^���̎��Ƃ��s���ꍇ�ɂ́A���Y���Ƃ��琶���鏊���̂��������ɂ����čs���Ɩ��ɂ������ׂ������Ƃ��Đ��߂Œ�߂���̂����āA��ꍀ��ꍆ�Ɍf���鏊���Ƃ���B�mcf.OECD���f��8���͍��ۉ^�A�n
����162���i�d�ŏ��ɈقȂ��߂�����ꍇ�̍��������j�@�d�ŏ��c�c�ɂ����č��������ɂ��O���̋K��ƈقȂ��߂�����ꍇ�ɂ́A���̑d�ŏ��̓K�p����҂ɂ��ẮA�����̋K��ɂ�����炸�A���������́A���̈قȂ��߂��������ɂ����āA�����d�ŏ��ɒ�߂�Ƃ���ɂ���B���̏ꍇ�ɂ����āA���̑d�ŏ�����ꍀ��Z�������\�Z���܂ł̋K��ɑ��č����������߂Ă���Ƃ��́A���̖@���������̍��ɋK�肷�鎖���Ɋւ��镔���̓K�p�ɂ��ẮA���̑d�ŏ��ɂ�荑�������Ƃ��ꂽ���̂����Ă���ɑΉ����邱���̍��Ɍf���鍑�������Ƃ݂Ȃ��B
�Q�@�P�v�I�{�݂�L����Z�҂̑O���ꍀ��ꍆ�Ɍf���鏊�����Z�肷��ꍇ�ɂ����āA�d�ŏ��c�c�̓K�p������Ƃ��́A�����ɋK�肷���������ɂ́A���Y�Z�҂̍P�v�I�{�݂Ǝ��Əꓙ�Ƃ̊Ԃ̗��q�c�c�̎x���ɑ������鎖�����̑����߂Œ�߂鎖���́A�܂܂�Ȃ����̂Ƃ���B
����164���i�Z�҂ɑ���ېł̕��@�j�@�Z�҂ɑ��ĉۂ��鏊���ł̊z�́A���̊e���Ɍf����Z�҂̋敪�ɉ������Y�e���ɒ�߂鍑�������ɂ��āA���ߑ�ꊼ�i�Z�҂ɑ��鏊���ł������ې��j�̋K���K�p���Čv�Z�����Ƃ���ɂ��B
�@��@�P�v�I�{�݂�L����Z�ҁ@���Ɍf���鍑������
�@�@�C�@��S�Z�\����ꍀ��ꍆ�y�ё�l���i���������j�Ɍf���鍑������
�@�@���@��S�Z�\����ꍀ��A��O���A��܍�����掵���܂ŋy�ё�\�����Ɍf���鍑�������i������ꍆ�Ɍf���鍑�������ɊY��������̂������B�j
�@��@�P�v�I�{�݂�L���Ȃ��Z�ҁ@��S�Z�\����ꍀ��A��O���A��܍�����掵���܂ŋy�ё�\�����Ɍf���鍑������
�Q�@���̊e���Ɍf����Z�҂����Y�e���ɒ�߂鍑��������L����ꍇ�ɂ́A���Y�Z�҂ɑ��ĉۂ��鏊���ł̊z�́A�O���̋K��ɂ����̂̂ق��A���Y�e���ɒ�߂鍑�������ɂ��đ�O���i�Z�҂ɑ��鏊���ł������ې��j�̋K���K�p���Čv�Z�����Ƃ���ɂ��B
�@��@�P�v�I�{�݂�L����Z�ҁ@��S�Z�\����ꍀ�攪�������\�Z���܂łɌf���鍑�������i������ꍆ�Ɍf���鍑�������ɊY��������̂������B�j
�@��@�P�v�I�{�݂�L���Ȃ��Z�ҁ@��S�Z�\����ꍀ�攪�������\�Z���܂łɌf���鍑������
8.2.2.2.a. �\�[�X�E���[��(source rules)���߂�����{�@�̕ϑJ
8.2.2.2.b. �\�[�X�E���[���̎O�̃J�e�S���[
[1]�P�v�I�{�A�������c�c���z(net basis income = profit)(�������z�|�K�v�o�������(����)���ېŕW���ƂȂ�)�Ő\���E�[�t�`��(�����ې�)(����161��1��1���A165���A166���A�@��138��1��1���A142���A144����6)[2]�P�v�I�{�݂ɋA�����Ȃ��ŏ��z�Ő\���E�[�t�`���̂��鏊��(�����ې�)(����161��2�`3���A5�`7���A17���A164��1��1�����A����2���A�@��138��1��2�`6���A141��1�����A����2��)
[3]�P�v�I�{�݂ɋA�����Ȃ��ő��z(gross basis income)(�������z���ېŕW���ƂȂ�)�Ō����̑ΏۂƂȂ鏊��(�����ې�)(�l�Z�҂ɂ��Ă͏���161��1��8�`16���A164��2��1���A2���A169���ȉ��A212��1���B�O���@�l�ɂ��Ă͏���161��1��4�`11���A13�`16���A178���A212��3��)
8.2.2.3. �u�P�v�I�{�A�������v
8.2.2.3.a. �u�P�v�I�{�A�������v�̈Ӌ`
8.2.2.3.b. �P�v�I�{�A���O���������̑��v�̊z
8.2.2.3.c. �{�X���Ƃ́u��������v��ʂ��Ď��������Ƃ݂Ȃ���鑹�v�̊z(��AOA: Authorised OECD Approach 2010)
8.2.2.3.d. �P�v�I�{�ݓ����́u�v�Z�v
8.2.2.4. �\���E�[�t�̑ΏۂƂȂ邻�̑��̍�������
8.2.2.4.a. �����ɂ��鎑�Y�̉^�p�܂��͕ۗL�ɂ�萶���鏊��fd
8.2.2.4.b. �����ɂ��鎑�Y�̏��n�ɂ�萶���鏊��
8.2.2.4.c. �l�I�̒ɌW�鏊��(������̐\���E�[�t)jk
| �����n���ߘa4�N9��14���ߘa3(�s�E)268��(���p)�E���������ߘa5�N4��26��(���m�F)(���p�E�m��)(�g���_��Y�E�W�����X�g1588��10�ŁA�������}�E�W�����X�g1597���d����5�N174-175�ŁA��ؗI�ƁE�W�����X�g1598��151��) �@���O���Z�O�����y�Ƃ̓��{�����ɍۂ��A����X�Ђ͓��Y�O�����y�Ƃ��Ǘ����Ă���O���|�\�@�l�ɁA�o�����Ƃ͕ʂ��A�n�q��̗������x������(�{���e�x��)�B�{���e�x���ɂ���X�Ђ͌��������Ă��Ȃ������B����Ŗ������́A�{���e�x���������Ŗ@161��1��6���i����28�N3��31���ȑO�̎x���͕���26�N�����O�̏����Ŗ@161��2���j�ɂ����l�I�̒ɌW��Ή��ɓ�����Ƃ̑O��ŁA�����œ��̔[�ō��m�����y�ѕs�[�t���Z�ŕ��ی��菈���������B �@���|�@�u�����Ŗ@�P�U�P���P���́A�P�v�I�{�A�������̂悤�ȏ������T�O�i���z�x�[�X�j�ő���������̂ƁA���q�A�z���̂悤�Ȏ������T�O�i���z�x�[�X�j�ő���������̂��A�Ƃ��Ɂu���������v�Ƃ��đ��̂��Ă���Ƃ���A�������ꊇ���āu�����v�Ƃ��ĕ\�����邱�Ƃ͍������������Ƃ���A�����Ŗ@�́A�u���������v�Ɓu�����v�Ƃ���ʂ��Ă���A�Ⴆ�A�����������������T�O�Ƃ��ėp����ꍇ�ɂ́A�u���������v�ł͂Ȃ��A�u���������ɌW�鏊���v�i���@�P�O�Q���A�P�U�W���̂Q�j�Ƃ�����������p���ĕ\�����Ă���B �@���̂悤�Ȋϓ_����A�u�l�I�̒ɌW��Ή��v���݂�ƁA�u�Ή��v�Ƃ��������́A�u�����v�Ƃ��������i�����P���A�Q�����j�Ƃ͈قȂ�A�ʏ�̗p��@�Ƃ��ẮA�������T�O�ɑ�������̂Ƃ����邩��A�l�I�̒������҂ɂƂ��āA���l�I�̒ɑ��Ďx�������������z�̑��z���Ӗ�������̂ł���Ƃ�����B���̂��߁A�x���z�̒��ɁA���x���ɌW������邽�߂̋]���Ƃ��Ďx�o����A���Y�����̈ꕔ�������ď[�������ׂ��Ή��W�ɂ����p�����z���܂܂�Ă����Ƃ��Ă��A����p�����z�͎������z�̈ꕔ�Ƃ��āu�Ή��v�Ɋ܂܂����̂Ƃ����ׂ��ł���B�v �@�u�u�l�I�̒ɌW��Ή��v�̎x�������O�����Ǝ҂́A���u�Ή��v�ɂ��āA�ŏI�I�ɏ������ېł��邱�Ƃ��ł�����̂́A���̂��߂ɂ́A�O�����Ǝ҂ɂ����āA�Z�҂̑����ېł̑ΏۂƂȂ鏊���Ŗ��͖@�l�ł̊m��\�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���A�����Ŗ@�y�і@�l�Ŗ@���A���u�Ή��v�̎x������҂ɑ��A���u�Ή��v�ɌW�鏃�����̊m��\��������`���킹�����ŁA���u�Ή��v�̎x���҂ɑ��A���u�Ή��v�ɌW�鏃�����ɂ��Č���������`���킹�Ă���Ƃ͉�����Ȃ�����A�������ɂ��ẮA���u�Ή��v�ɌW��������z�̑��z��ΏۂƂ�����̂ł���Ƃ����ׂ��ł���B���̂��߁A�u�Ή��v�ɂ��āA��L�A�̂悤�ɁA������u�l�I�̒v�i�����Ŗ@�P�U�P���P���U���j�ɑ��Ďx����ꂽ�������z�̑��z���Ӗ����A�u�Ή��v�邽�߂ɗv������p�����̎x���z���܂ނ��̂Ɖ����邱�Ƃ́A�u�Ή��v�̎x�������O�����Ǝ҂ɑ��铯�u�Ή��v�ɂ��Ă̏����ł̉ېł̍\���Ƃ���������B�v cf.���ŕs���R��������15�N2��26���ٌ��E�ٌ�����W65�W283�� |
8.2.2.4.d. �����s���Y���̑ݕt���ɂ��Ή�
8.2.2.4.e. ���̑��̍�������(���ŗ�289���A�@�ŗ�180��)
8.2.3. �����̑ΏۂƂȂ鏊���͈̔͂Ƃ��̌v�Z
8.2.3.1. �����Ŗ@�ɂ�錹��
����178���i�O���@�l�ɌW�鏊���ł̉ېŕW���j�@�O���@�l�ɑ��ĉۂ��鏊���ł̉ېŕW���́A���̊O���@�l���x������ׂ���S�Z�\����ꍀ��l�������\�ꍆ�܂ŋy�ё�\�O�������\�Z���܂Łc�c�Ɍf���鍑�������c�c�̋��z�i��S�Z�\����ꍆ�A��A��l���y�ё�܍��i�����ېłɌW�鏊���ł̉ېŕW���j�Ɍf���鍑�������ɂ��ẮA�����̋K��ɒ�߂���z�j�Ƃ���B
����179���i�O���@�l�ɌW�鏊���ł̐ŗ��j�@�O���@�l�ɑ��ĉۂ��鏊���ł̊z�́A���̊e���̋敪�ɉ������Y�e���ɒ�߂���z�Ƃ���B
��@�O���ɋK�肷�鍑�������i�����y�ё�O���Ɍf������̂������B�j�@���̋��z�i��S�Z�\����A��l���y�ё�܍��i�����ېłɌW�鏊���ł̉ېŕW���j�Ɍf���鍑�������ɂ��ẮA�����̋K��ɒ�߂���z�j�ɕS���̓�\�̐ŗ����悶�Čv�Z�������z
��@��S�Z�\����ꍀ��܍��c�c�Ɍf���鍑�������@���̋��z�ɕS���̏\�̐ŗ����悶�Čv�Z�������z
�O�@��S�Z�\����ꍀ�攪���y�ё�\�܍��Ɍf���鍑�������@���̋��z�i��S�Z�\����ꍆ�Ɍf���鍑�������ɂ��ẮA�����ɒ�߂���z�j�ɕS���̏\�܂̐ŗ����悶�Čv�Z�������z
����180���i�P�v�I�{�݂�L����O���@�l�̎鍑�������ɌW��ېł̓���j�@�掵���ꍀ��܍��i�O���@�l�̉ېŏ����͈̔́j�y�ёO����̋K��́A�P�v�I�{�݂�L����O���@�l�Ő��߂Œ�߂�v��������Ă�����̂̂�����S�Z�\����ꍀ��l������掵���܂ŁA��\���A��\�ꍆ�A��\�O�����͑�\�l���c�c�Ɍf���鍑�������c�c�ł��̊O���@�l���P�v�I�{�݂ɋA����������i��S�Z�\����ꍀ��l���Ɍf���鍑�������ɂ��ẮA�����ɋK�肷�鎖�ƂɌW��P�v�I�{�݈ȊO�̍P�v�I�{�݂ɋA��������̂Ɍ���B�ȉ����̍��ɂ����āu�Ώۍ��������v�Ƃ����B�j�̎x��������̂��A���߂Œ�߂�Ƃ���ɂ��A���Y�x��������̂����Y�v��������Ă��邱�Ƌy�т��̎x�����邱�ƂƂȂ鍑���������Ώۍ��������ɊY�����邱�Ƃɂ����̖@�l�ł̔[�Œn�̏����Ŗ������c�c�̏ؖ����̌�t���A���̏ؖ����Y���������̎x��������҂ɒ����ꍇ�ɂ́A���̏ؖ��������͂�L���Ă���ԂɎx�����铖�Y���������ɂ��ẮA�K�p���Ȃ��B�m2���ȉ����n
����212���i�����`���j�@�Z�҂ɑ������ɂ����đ�S�Z�\����ꍀ��l�������\�Z���܂Łc�c�Ɍf���鍑�������c�c�̎x��������Җ��͊O���@�l�ɑ������ɂ����ē�����l�������\�ꍆ�܂ŎႵ���͑�\�O�������\�Z���܂łɌf���鍑�������i��S���\���ꍀ�i�P�v�I�{�݂�L����O���@�l�̎鍑�������ɌW��ېł̓���j�c�c�y�ѐ��߂Œ�߂���̂������B�j�̎x��������҂́A���̎x���̍ہA�����̍��������ɂ��ď����ł����A���̒����̓��̑����錎�̗����\���܂łɁA��������ɔ[�t���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�m2�����n
�R�@�����@�l�ɑ������ɂ����đ�S���\�l���e���i�����@�l�ɌW�鏊���ł̉ېŕW���j�Ɍf���闘�q���A�z�����A���t��U���A�����A���v�A���v�A���v�̕��z���͏܋��c�c�̎x��������҂́A���̎x���̍ہA���Y���q���A�z�����A���t��U���A�����A���v�A���v�A���v�̕��z���͏܋��ɂ��ď����ł����A���̒����̓��̑����錎�̗����\���܂łɁA��������ɔ[�t���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�m4�����n
�T�@��S�Z�\����ꍀ��l���ɋK�肷��z�����铯���Ɍf���鍑�������ɂ��ẮA�����ɋK�肷��g���_���������Ă���g�����c�c�ł���Z�Җ��͊O���@�l�����Y�g���_��ɒ�߂�v�Z���ԁc�c�ɂ����Đ��������Y���������ɂ����K���̑��̎��Y�c�c�̌�t����ꍇ�ɂ́A���Y�z��������҂Y���������̎x��������҂Ƃ݂Ȃ��A���Y���K���̌�t���������c�c�ɂ����Ă��̎x�����������̂Ƃ݂Ȃ��āA���̖@���̋K���K�p����B
8.2.3.2. �����̑ΏۂƂȂ鍑������
8.2.3.2.a. �g���_�Ɋ�Â��čs�����Ƃ��琶���闘�v�Ŕz���������(����161��1��4��)
8.2.3.2.b. �����ɂ���y�n���̏��n�̑Ή�(����161��1��5��)
| �����n������23�N3��4������21(�s�E)121���Ŏ�261������11635�S�I6��68(�T�i�R������������23�N8��3���Ŏ�261������11727�A�㍐�R�Ō�����24�N9��18���ňێ�) �@�w���`����y�n���w������ہA�u�`�͓��{���Z�҂ł���v�Ƃ`���w�ɍ����Ă����̂ŁA�w�͂����M�p���A�w�͓y�n���n�ɌW�錹����(����212��1���A213��1��2��)��[�t���Ă��Ȃ������B�������`�͔Z�҂ł������B�`���Z�҂ł��邱�Ƃ��w���m�F���钍�Ӌ`����ӂ����̂Ō����[�t�`�����ۂ����邱�Ƃ͂�ނ����Ȃ����B �@�����n�ٔ��|�c�c�u�@�ߏ�ɋL�ڂ̂Ȃ��u���҉\���v�Ȃ����u�\���\���v�Ƃ������v����݂��Č������x��������߁i����K�p�j����K�v�͂Ȃ��v�B �@�w���ł́A�w���猩�Ă`�����Z�҂ł��邩�ۂ��ɂ��Ĉ��̊m�F�葱����������A�����[�t�`���͖Ƃ��Ƃ��ׂ��ł���A�Ƃ����ӌ�������B�������A�ٔ����́A�w���猩�Ă`�����Z�҂ł��邩�m�F���Ƃ��܂ł͌����ŕ��̑�����x����Ȃ��ł����Ƃ������Ή�����A�Ǝw�E����B �@�ޗ�F�Z�F�s���Y�����E�����n������28�N5��19������26(�s�E)114���Ŏ�266������12856�E������������28�N12��1������28(�s�R)219���Ŏ�266������12942�S�I7��73(��Ɏ��E�W�����X�g1498��10�ŁA����p�q�u�Z�҂ɕs���Y�̏��n�Ή����x�����ҁi�����`���ҁj�̒��Ӌ`���v�V�E������Watch�d�Ŗ@No.137 (2017.3.10)�A���R�R���E�W�����X�g1522��140��) |
8.2.3.2.c. ���E�a�����̗��q��(����161��1��8��)
8.2.3.2.d. �z����(����161��1��9��)
| �A�W�����g�E�e�N�m���W�[�Y�E���N�X�R�E�G�X�E�A�[�E�G�[���E�G�������E�����n���ߘa4�N2��17���ߘa��(�s�E)453��(�F�e)�E���������ߘa5�N2��16���ߘa4(�s�R)72��(�T�i���p)(�m��)(�ؑ��_�V�E�W�����X�g1578��10�ŁA�⊪���]�E�W�����X�g1581��126�ŁA�_�c�m�E�W�����X�g1583��170�ŏd�ŗ�04�N�A�H���G�m�E���ېŖ�43��6��40�ŁA7��54�ŁA���{�G���E�W�����X�g1597���d����5�N265-266��)(���Œ��u�d�ŏ��ɂ�����u�����̕��z�ɌW�鎖�ƔN�x�̏I���̓��v�̎戵���ɂ����v�ߘa5�N3��) �@���N�Z���u���N�@�l���錴���w�Ђ͓��{�ɍP�v�I�{�݂�L���ĂȂ��B2014�N4��29���A�w�Ђ͓��{�@�l�`�Ёi�A�W�����g�E�e�N�m���W�[������Ёj�i���ƔN�x��11��1���`10��31���j�Ƃa�Ёi�A�W�����g�E�e�N�m���W�[�E�C���^�[�i�V���i��������Ёj�i���ƔN�x��11��1���`10��31���j�̊������֘A�@�l�i�I�����_�@�l�A���N�Z���u���N�@�l�j����100���擾���A100���ۗL�������Ă���B2014�N8��1���A�`�Ђ͔�K�i�����^�������s���A���Ƃ����p�@�l����i�Ёi�L�[�T�C�g�E�e�N�m���W�[������Ёj�ɏ��p�����A�`�Ђ͂i�Ђ̏o�������̏��n�����B�����A�`�Ђ́A�i�Ђ̏o����������]���̔z���Ƃ��Ăw�Ђɕ��z�����i�݂Ȃ��z�����z112��1962��2367�~�j�B�����A�a�Ђ͔�K�i�����^�������s���A���Ƃ����p�@�l���s��b�Ёi�L�[�T�C�g�E�e�N�m���W�[�E�C���^�[�i�V���i��������Ёj�ɏ��p�����A�a�Ђ͂b�Ђ̏o�������̏��n�����B�����A�a�Ђ͂b�Ђ̏o����������]���̔z���Ƃ��Ăw�Ђɕ��z�����i�݂Ȃ��z�����z27��2522��0652�~�j�B�`�ЁE�a�Ђ́A���{�̌�����20.42�����悶���z�i22��9104��6889�~�A5��5649��0057�~�j��[�t�����i�����Ŗ@24��1���A25��1��2���A212��1��1���A161��5���C�m��9���C�n�j�B �@���{���N�Z���u���N�d�ŏ��10��2��(a)25���ۗL�Ȃ�Δz������n���ŗ�5���A(b)�����Ȃ����15���B(�����͉p��) �@2015�N4��7���A�w�Ђ�(a)��5����O��ɁA���z�̊ҕt�𐿋������B2016�N3��7���A�Ŗ������́A(b)��15����O��ɁA���z���ҕt�����B �@(a)��6�J���ȏ�ۗL�v�������������_�ƂȂ����B �@3��2���uAs regards the application of this Convention by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws of that Contracting State concerning the taxes to which this Convention applies.�v�i���̏��́A�P�Ɍf����d�łɉ����Ė��͂���ɑ����Ă��̏��̏����̓��̌�ɉۂ����d�łł����ĂP�Ɍf����d�łƓ���ł�����̖��͎����I�ɗގ�������́i���łł��邩�n���łł��邩����Ȃ��B�j�ɂ��Ă��A�K�p����B�����̌����̂��铖�ǂ́A���ꂼ��̍��̐Ŗ@�ɂ��čs��ꂽ�����I�ȉ������A���̉�����̑Ó��Ȋ��ԓ��ɁA���݂ɒʒm����B�j �@10��2��(a)�u5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company which owns at least 25 per cent of the voting shares of the company paying the dividends during the period of six months immediately before the end of the accounting period for which the distribution of profits takes place;�v�i���Y�z���̎�v�҂��A�����̕��z�ɌW�鎖�ƔN�x�̏I���̓��ɐ旧�Z�ӌ��̊��Ԃ�ʂ��A���Y�z�����x�����@�l�̋c�����̂��銔���̏��Ȃ��Ƃ���\�܃p�[�Z���g�����L����@�l�ł���ꍇ�ɂ́A���Y�z���̊z�̌܃p�[�Z���g�j �@�w�Ђ̎咣�F�uthe end of the accounting period for which the distribution of profits takes place�i�����̕��z�ɌW�鎖�ƔN�x�̏I���̓��j�v�Ƃ́A�u�z�����x�����@�l�����̔z���̌����ł��鏊������ʂɌ����Ó��ƔF�߂����v�����̊�ɏ]���Čv�Z�����v���Ԃ̖����v�������B�����2014�N10��31���ł���A4��29������6�J���ȏ�o�߂��Ă���B �@�퍐�i�x�F���j�̎咣�F�u�z���̎�̎҂����肳��鎞�_�v�������B�����^�����̓��̑O���i2014�N7��31���j��4��29������6�J���ȏ�o�߂��Ă��Ȃ��B �@���|�@(2)�u�{�������́C���{�̖@�߂ɂ�����p��̈Ӌ`�Ƃ��ẮC�u�����̕��z�ɌW���v���Ԃ̏I���̓��v���Ӗ�������̂Ƃ����ׂ��ł���B�v �@(3)�u�{�������́C���̎�|�y�іړI�ɏƂ炵�ė^������p��̒ʏ�̈Ӗ��Ƃ��ẮC�u�����̕��z�i�z���j���s�����v���Ԃ̏I���v���Ӗ�����v�B �@(4)�u�{�������́C���{�̖@�߂ɂ����铖�Y�p��̈Ӌ`�i�E�B�[�����R�P���P���ɂ����u�����v�j�Ƃ��ẮC�u�����̕��z�ɌW���v���Ԃ̏I���̓��v���Ӗ�������̂ł���C���̎�|�y�іړI�ɏƂ炵�ė^������p��̒ʏ�̈Ӗ��Ƃ��ẮC�u�����̕��z�i�z���j���s�����v���Ԃ̏I���v���Ӗ�������̂ł���Ƃ���C�O�҂ƌ�҂Ƃ͎����I�ɓ��`�ł���Ƃ������Ƃ��ł���B��������ƁC�{�������̉��߂ɂ��ẮC�����Ɋ�Â�����������҂̕\���ɏ]���C�u�����̕��z�i�z���j���s�����v���Ԃ̏I���v�Ɖ�����̂������ł���B�v |
8.2.3.2.e. �ݕt���̗��q(����161��1��10��)
| ���|��������E������������20�N3��12������19(�s�R)171������1290��32��ko(���R�����n������19�N4��17������1986��23��)(��3.1.2.2.) ���{�@�����p�@�@�@�č��@�b�@���{�@���S�ے@�č� �i�Ё\�\�\�\�\�\�\���t�Ё@�b�@�i�Ё\�\�\�\�\�\�\���t�� �@�@���\�\�\�\�\�\�\�@�@�@�b�@�@�@���\�\�\�\�\�\�\�@�@ �@�@�@�@�@�������2000�@�@�b�@�@�@�@�@�@�@�ݕt��2000 �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�@ �@�@�@�@�@���Ĕ����@�@�@�b�@�@�@�@�@�@�S�ە��Ԋ� �i�Ё��\�\�\�\�\�\�\�t�Ё@�b�@�i�Ё��\�\�\�\�\�\�\�t�� �@�@�\�\�\�\�\�\�\���@�@�@�b�@�@�@�\�\�\�\�\�\�\�� �@�@�������2200�@�@�@�@�@�b�@�@�@�����ԍ�2200 �@�@���|���z�Q00�@�@�@�@�@�b�@�@�@���q�Q00 �@���|����Ƃ́A�����̍Ĕ����\��t�����ł���B�Ⴆ�A���{�@�l�i�Ђ��A�����J�@�l�t�Ђɍ���2000�Ŕ���A1�N��A�i�Ђ��t�Ђ��獑��2200�Ŕ����߂��irepurchase���k�߂ă��|�j�A�Ƃ�������ł���i���ۂ͂����ƒZ���̎���ł���j�B���̍��z200�i���|���z�A�Ĕ��������j�́A�i�Ђ��t�Ђɔ��鎞�_�Ƃi�Ђ��t�Ђ��甃���߂����_�̊Ԃ̋��K�̎��ԓI���l�itime value of money�j�ɑ���������̂ł���B �@�ېŒ��́A200�̃��|���z���A�i�Ђ���t�Ђւ̗��q�x�����ɑ���������̂ł���A�t�Ђ̗��q�����ɂ��Ăi�Ђ������[�t�`�����A�Ǝ咣�����B�O�q�̃��|����́A�i���t����2000���ؓ��ĒS�ۂƂ��č������o���A�P�N��A�i���t�Ɍ������v2200��ԍς��ĒS�ۂ�Ԃ��Ă��炤���ƂƁA�o�ώ����I�ɋ߂�����ł���B�����������Ŗ@161��6���i�����j�́u�����ɂ����ċƖ����s�Ȃ��҂ɑ����ݕt���i����ɏ�������̂��܂ށB�j�œ��Y�Ɩ��ɌW����̂����q�v�ƋK�肵�Ă���A���|���z���ݕt���̗��q�ɊY�����Ȃ��Ƃ��Ă��u����ɏ�������́v�ɂ͊܂܂��A�Ǝ咣�����B �@�������ٔ����́A�����Ƃ����@�`�����d�����A�ݕt���i���@587���̋��K����ݎ،_�����T�^�j�Ƃ͂����Ȃ���������Ƃ������Ȃ��A�Ƃ����B �@cf.�{��T�q�u�����郌�|����̐i���ƉېŁv�W�����X�g1253��122�� �@cf.���̌�A�������Ȃ����Ƃm�����闧�@�B���ŗ�283��3���E4���́u���������v�B |
| ���n������20�N7��24������18(�s�E)195�����^1295��216�Ő����F�e�E��㍂������21�N4��24������20(�s�R)127���Ŏ�259������11188�c�c���D�_��������i�D�����҂͓��{�@�l�B����͊O���@�l�j�͏���161��6��(����)�́u�ݕt���i����ɏ�������̂��܂ށB�j�v�́u���q�v��Y���B |
�o�[�N���C�Y��s�����E�����n���ߘa4�N2��1���ߘa2(�s�E)271����4.5.1.1.(�@���I�A�����ƌo�ϓI�A����)
8.2.3.2.f. �H�Ə��L�����E���쌠�̎g�p���܂��͂��̏��n�ɂ��Ή�(����161��1��11��)
��1�F���C�Z���X�@�@�@S���@�@�@�@�@�@�@�@R��
8000�@�@1500�g�p��
�\�\��S�\�\�\�\�\��R
2000����4000�@�@�@�@�@��1000
�̔��@�@�����@�@�@�@�@�@����
��1�FR�Ђ�R���Ō����J�����AS�����������擾����BS����S�Ђɓ����������C�Z���X�i���{�����j����BS�Ђ�4000�̐�����p�ŏ��i�����A�X��2000�̔̔���p��������8000�̔̔�������BS�Ђ�R�Ђ�1500�̓������g�p�����x�����B
1500�̎x���̏����敪�F12���̎g�p��
��������FS������
�i�����ېł�F�߂���ƔF�߂Ȃ������j
��2�F����R������
�@�@�@S���@�@�@�@�@�@�@�@R��
8000�@�@�@5500�̔��㉿
�\�\��S�\�\�\�\�\��R
2000���@�@�@�@�@4000����1000
�̔��@�@�@�@�@�@�@�����@�@����
��2�FR�Ђ�R���Ō����J�����AS�����������擾����BR�Ђ�R����4000�̐�����p�𓊂��ď��i������BS����S�Ђ�5500�Ŕ̔�����i�A����p�͖����j�BS�Ђ�2000�̔̔���p�𓊂���8000�̔̔�������B
5500�̎x���̏����敪�F7���̎��Ɨ���
��������FR������
�iS���ł�PE�Ȃ���ΉېłȂ��j
��2�ɂ����Ă��AR�Ђ�S����������ۗL���Ă���Ƃ��������͕ς��Ȃ��BS������̎g�p���̗v�f�͂ǂ����֏����Ă��܂����̂��H�\�\�d�ŏ����������ɋ敪���Ă��̏����敪���Ƃɍ��ƊԂʼnېŌ���z������Ƃ����A�v���[�`�́A��2��̂悤�Ȕ�r�ɂ����ĕs��������I�悷��i���A�d���Ȃ��j�B
�Q�ƁF��ȏ͔@�u��������̊�A�y��net��gross�Ƃ̊W(1�`3�E��)�v�@��121��8�`10��(2004)�A��ȏ͔@�E�R���M�u���ʑΒk�@�m�I���Y�̖@�����Ŗ��E�őO���v���ېŖ�28��12��14-37��(2008.12)
| �V���o�[���H�����E�����n������4�N10��27�����a63(�s�E)191���s�W43��10��1336�ňꕔ�F�e�A�ꕔ�p���E������������10�N12��15������4(�s�R)133����45��8��1553�Ŋ��p�E�Ŕ�����16�N6��24������11(�s�q)44������1872��46�Ŋ��p�m��S�I7��71jq(��ȏ͔@�E�W�����X�g1291��274��) �@���{��Ƃ̃A�����J�s��ւ̐i�o�Ɏ���Ă��Ă����A�����J��Ƃ`�Ђ��A���{�@�l���錴���w�Ђɑ��A�w�̓��{����A�����J�ւ̗A�o�͂`�Ђ̓�������N�Q���Ă���Ƃ��āA���~�i�ׂ��N�����B�w�Ђ́A�`�Ђ̓����͖����ł��낤�Ƃ̗\���𗧂Ă����A�ē��f�Ֆ��C�̌����������A�A�����J�ʼn��ɓ������������������Ƃ��Ă��ʏ��W�ŗl�X�ȖW�Q����ł��낤���Ƃ�\�����A���ǁA�w�Ђ͂`�Ђ̋����ɋ����Ęa���_���������A�w�Ђ��`�Ђɘa�������x�������B �@�ē����������̘a���_��ɂ�����x�����č������g�p���ł���(�W�����E�C�[�E�~�b�`�F�������̐�����������Ŕj�����Ӌ`������)�Ɣ��f����A�A�����J����ł���Ɣ��f���ꂽ�B �@cf.���̓����͌�������Ƃ���Ă��邱�ƁA�č���������N�Q����͓̂��{�@�l�ł͂Ȃ��č��q����̔��ł���A�č��q��Ђ��x�����ׂ��a��������{�e��Ђ���w�Ђ�����Ɏx�������Ƃ͂w�Ђ̕č��q��Ђɑ�����̖������߂�̂ł͂Ȃ����A���A��������[���_�_(����Ă��Ɍ����Γ����̖@���_�̃��x���̒Ⴓ)�������Ă���B cf.�W�����E�C�[�E�~�b�`�F�������E�����n�����a60�N5��13�����a57(��)3128�����^577��79�Ŋ��p�m��S�I3��47�c�c�����i�K�ɒ��ڂ��ē����g�p���̌���͓��{�ɂ���Ɣ��f�B cf.�������u���đd�ŏ��ɂ�����������g�p���̌���n�v�W�����X�g845��102�� |
| �e���v�����j���O����(�S�ď��q�I�[�v������)�E�����n������6�N3��30�����a62(�s�E)111���s�W45��3��931�ňꕔ�p���A�ꕔ���p�E������������9�N9��25������6(�s�R)69������1631��118�Ŋ��p(���쌠����S�I3��23)�E�Ŕ�����15�N2��27������10(�s�c)32���Ŏ�253������9294���p�m��c�c�X�|�[�c���Z�ɂ��ē��{�@�l���O���@�l�Ɏx�������e���r���f���������{����̒��쌠�g�p���ł���Ɣ��f���ꂽ�B |
| �Q�[���J���ϑ������E���ŕs���R��������21�N12��11���ٌ��E�ٌ�����W78�W208���m��c�c�Q�[���\�t�g�J����Ƃ��ē��{�@�l���O���@�l�Ɏx���������������쌠�̏��n�̑Ή��ł���Ƃ��Č����łɕ�����Ƃ����B cf. ���ŕs���R��������22�N5��13���ٌ��E�ٌ�����W79�W289�����p(�L�d���i�E���ېŖ�32��4��84��)�c�c�����Z�p�����_��̑Ή��x�������������g�p���Ƃ��Č����ɕ�����B |
8.2.3.2.g. ���^�E��V�܂��͔N��(����161��1��12���A���ŗ�285��)
| �����n������22�N2��12������18(�s�E)651���Ŏ�260������11378���p�m��(�������l�E�W�����X�g1424��134�ł͌��_�ɔ���)�c�c���{�@�l���L�̑D�œ����O���l���D���Ɋւ��Ďx���������������{���^�����Ɣ��f���ꂽ�B |
8.2.3.2.h. �L����`�̂��߂̏܋�(����161��1��13���A���ŗ�286��)
8.2.3.2.i. �����ی��_��Ɋ�Â��N����(����161��1��14���A���ŗ�287��)
8.2.3.2.j. ���Z�ގ����i�̍��v(����161��1��15��)
8.2.3.2.k. �����g���_��Ɋ�Â��Ď闘�v�̕��z(����161��1��16���A���ŗ�288��)(��8.2.2.1.b.���{�K�C�_���g)
8.2.3.3. �d�ŏ��ƃ\�[�X�E���[��(����162���A�@��139��)
8.2.3.3.1. OECD���f���d�ŏ��6���`21��(���ȏ��ɂ͂Ȃ�)
�n�d�b�c���f���d�ŏ��ɂ����鏊���敪�s���Y�i6���j
�����Ƃ��ĕs���Y���ݒn���̉ېŌ���F�߂�B���Z�n���̉ېŌ���ے肷���ł͂Ȃ��B
���ۉ^�A�Ə����i8���j
���ۉ^�A�Ƃ̏���������l����͖̂ʓ|����Ƃ̎����I�Ǘ��̏ꏊ�����݂��鍑�ɂ����Ă̂݉ېŁB
�z���i10���j
10��1���F�z����̎҂̋��Z�n���ł̉ېŁB([���]1���̑��݈Ӌ`�͂Ȃ���)
�@�@2���F�z���x���@�l�i�����j���Z�n���ł̉ېŁB��v(�ۗL)��(beneficial owner)�T�O�g�p�Bjp
�@�@�@a)�F25���ȏ㏊�L�@��5���ʼnېŁB(�e�q��Њԑ��d�ېłɔz����5.2.2.3.e.)
�@�@�@b)�F����ȊO�@�@�@��15���ʼnېŁB
�@�@3���F��`
�@�@4���FPE�ېŁB(��8.2.4.3.c.)
�@�@5���F�ǂ������ېł̋֎~�B
10��2���F�e�q��Њԓ��ɂ�������ʂȈ���
�@�@�@�c�q��ЁE�e��Ђɂ�������d�ې��ɔz���B
�@�@�@cf. �����ېłɂ����Ă����z���v���s�Z���i�@�l�Ŗ@23���j�œ�d�ېł�r���B
10��5���F����������Ƃ����Ă��O���@�l���痬�o���鏊���ɑ��ĉېł���̂͂�肷���A�Ƃ�����|�B
cf.�x�X���v��
�����q��Ё����O�e��Ђ̔z���F�q��Ћ��Z�n���ʼnېŁB
�����x�X�����O�{�X�̑����F�@�I�ɂ͎�������݂����A���ʂȋK��Ȃ��ɂ͉ېŊW�������Ȃ��B
���ɂ���ẮA�q��ЂƎx�X�Ƃ����������߂ɁA�x�X�ɑ��Ĕz���ېŗގ��̎x�X���v�ł��ۂ��Ă���B
���q�i11���j(��8.4.4.�ߏ����{�Ő�)
11��1���F���q��̎҂̋��Z�n���ł̉ېŁB
�@�@2���F��v(�ۗL)�҂ɂ��x����(����)�̋��Z�n��(����n��)�ېł𐧌��c10%�܂ŁB
�@�@3���F��`
�@�@4���FPE�ېŁB
�@�@6���F�ߏ����{��
�g�p���i12���j
12��1���F��v(�ۗL)�҂̋��Z�n���ɂ����Ă̂݉ېŁB�@�i��̎҂ł͂Ȃ��j
�@�@2���F��`
�@�@3���FPE�ېŁB
�@�@4���F�ړ]���i���ւ̑�B
�@���Ȃ��炸�̎��ۂ̑d�ŏ��i��F����d�ŏ��j�ł́A����n���ɂ�10�����x�̉ېŌ���F�߂Ă���B�iOECD���f���͂����܂œԂ̑d�ŏ����̏o���_�ɂ������A�Ԃł���ƈقȂ鍇�ӂ����č\��Ȃ��BUN���f��12��������n���̉ېŌ���F�߂Ă���j
10��2���A11��2���A12��1���͎�v��(beneficial owner)�T�O��p���Ă���B
���r������̎g�p�����q�����Z�҂���̂��邪��̎�(recipient)����v�҂łȂ��ꍇ�A12��1���͓K�p����Ȃ��B
���r���̉ېŌ���d�ŏ�������Ȃ��̂ŁA�r�������@�������r���͉ېŁi�����j���Ă悢�B
[���]���O���Ŏ�v�ҊT�O���߂���ٔ���͑������邪�A2010�N�ȑO�́A��v�ҊT�O�ʼnېŒ������i���邱�Ƃ͓���X�����������B���(��q)��Ƃ��āAbeneficial owner�T�O�͊��Ɣ�͂������B��v�҂łȂ�����d�ŏ��̉��b(�����ł̌��Ɠ�)��F�߂Ȃ��Ƃ����ېŒ����̎咣�́A�ٔ������炷��ƁA�@�l�i�۔F�̂悤�ɕ������āA�ȒP�ɂ͔F�߂��Ȃ��A�ƍl�������Ȃ̂�������Ȃ��B�ނ�2010�N��ȍ~�A��v�ҊT�O�ʼnېŒ������i������ڗ����n�߂Ă���Bjp
cf.���ŕs���R�����ߘa5�N8��15���ٌ��c�c����d�ŏ��12��1���E4���u�Z�p��̖ɑ��闿���v(FTS: Fees for Technical Services�v�ɊY������x������{�@�l���C���h�@�l�ɂ���ہA�����ł̑ΏۂƂȂ�x���z�́A�����ł�������Ȃ��O��(�̑Ή��łȂ��\�t�g�E�F�A�̏��n�Ή��Ƃ����O��ł�����)�ō��ӂ��ꂽ�z���A���Y�z��10/9���悶���z���c�c�k���L�u�łŃ�������ǂ�����(��6��)�l�Ԃ͊ԈႦ�鐶�����ł����v�B
���n�v�i13���j
13��1���F�s���Y���ݒn���ł̉ېŁB�@4���i�s���Y�ۗL��Ёj�͂��̈���B
�@�@2���FPE�̎��Ɨp���Y�c�cPE���ݒn���ł̉ېŁB
�@�@3���F�^�A�ƂɊւ�������B
�@�@5���F���n�҂̋��Z�n���ł̂݉ېŁB
�܂�A1�`4���̓����ɊY�����Ȃ��ꍇ�A��ʘ_�Ƃ���5���ɂ�茹��n���ɉېŌ��Ȃ��B
��F�q�����Z�҂ł���`�����r���@�l�ł���a�Ђ����z��������S���̌����ېł���B
�a�Њ������n�������n�v��Ƃ����`���Ȃ�A�r���ł̉ېł�Ƃ�邱�Ƃ��ł���B
�z���Ə��n�v�Ƃ����`�����Ⴆ�ǂ��A���̌����ގ����邱�Ƃ��l����A�������������̈Ⴂ�͐��F���������B
���@�����̍����������n�v�ɂ��ĉېŌ��𗯕ۂ��Ă���i13��5���̗�O���K�肷��j�BOECD��������OECD���f���d�ŏ��̏Ɏ^�����Ȃ��ꍇ��OECD�R�����^���[(OECD���f���d�ŏ��̉��ߓK�p�Ɋւ�OECD�d�ňψ���쐬���钍�ߏ��BCommentary�B�h�C�c��ł����Ƃ���̃R�������^�[��)�ɗ���(reservation)��t���B�ɔ��ł͂Ȃ���OECD�R�����^���[�̉��߂Ɏ^�����Ȃ��ꍇ�͈ӌ�(observation)��t���B
���R�E�Ə���(14��)�c�폜
���^�����i15���j
�@���^�����̌���͒ʏ�J���n�ɂ���ƍl�����Ă���A��{�I�ɂ͘J���n���ł̉ېł��F�߂���i���^�����҂̋��Z�n���ɂ�����ېł��ւ�����Ƃ͌���Ȃ��j�B�������A�J�����Z���Ԃł����āA���^���J���n���ȊO����x�����铙�̏ꍇ�A�ς�����邽�ߘJ���n���ł̉ېł𐧌����Ă���B
������V�i16���j
������V���x�����@�l�̋��Z�n���i�����̌���n���j�̉ېŌ���F�߂�B�i�����̋��Z�n���ېł͕ʘ_�j
�|�\�l�y�щ^�����i17���j
�@���ʂȋK�肪�Ȃ���A�|�\�l��X�|�[�c�I�肪���鏊���͎��Ə����ł���A���Ə����ł����PE�Ȃ���ΉېłȂ��̃��[���i7���j�ɂ�苏�Z�n���ł̂݉ېł��Ȃ���邱�ƂɂȂ肤��B
�@�������A�O���l�̎�̃R���T�[�g�iex.�}�C�P���E�W���N�\���j����z�N����APE���Ȃ��Ƃ�����ȏ�����\�����l������B�����ŁA�|�\�l���ɂ��Ă�PE���킸�Ɍ���n���ł̉ېŌ������e����B(�ŋ߂́APE���Ȃ��Ƃ��A�ł͂Ȃ��A�V����PE�T�O��17�����K�肵�Ă���̂ł���A�Ƃ������������邱�Ƃ�����)
17��2���F17���̓K�p�Ώۂ��|�\�l�����鏊���Ɍ��肷��ƁA�|�\�l�{�l�ł͂Ȃ��|�\�@�l���R���T�[�g���J�Â��A�|�\�l�͌|�\�@�l����x������A�Ƃ����`�ł̑d�ʼn�������s����̂ŁA�����h���B
�ސE�N���i18���j
�J���n������������ł��邪�A�ېł̔ς�����邽�߁A���Z�n���ł̉ېłɈ�{�����Ă���B
���{�E���i19���j
��{�I�ɂ́A���^�����x�������{�̍��ł̂݉ېł���B
�w���i20���j
���Z�n���Ƒ؍ݒn���Ƃ��قȂ�ꍇ�ɁA���Z�n���ɂ�����ېłɈ�{������B
���̑������i21���j(��8.2.2.1.b.���{�K�C�_���g)
6�`20���Ɍf�����ĂȂ������ɂ��āA���Z�n���ېłɈ�{������B
���ۂ̑d�ŏ���21���ɑ�������K�肪�Ȃ���A6�`20���Ɍf�����ĂȂ���ނ̏����ɂ��Ă͑d�ŏ��̋K�����Ȃ��Ƃ������Ƃł��邩��A����n�����ېł��邩�ۂ��͌���n���̖@�ɂ���Č�������B
8.2.3.3.2. ���(���ȏ��ɂ͂Ȃ�)
�@�`�������d�ŏ���a���@�b�@�`�������d�ŏ���a���@�@����������ېœ��@���������b�@����������ېœ��@��������
�@���`�Є��\�\�\�\�����a�Є��b�@���`�Є��\�\�\�\�����a�Є�
�ۄ��������@�@�@�@�@���������b�@���������@�@�@�@�@��������
�Łˁb�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�F�@
�@�@���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�F
�@���������@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�@���������@�@�@�@�@�@�F
�b���b�Є��@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�b���b�Є����d�d�d�d�d�E
�����������@�@�@�@�@�@�@�@�@�b����������
��jA������C���Ɏx�����Ȃ���A�������@���K�p���ꍂ���ŗ����K�p�����BC�����Z�҂ł���C�Ђ�A�����Z�҂ł���A�Ђƒ��ڎ�����s���̂ł͂Ȃ��A�Ԃ�B�����Z�҂ł���B�Ђ���݂����邱�Ƃ��l����B
�@A�Ё�B�Ђ̎x���ɂ��āAA-B�d�ŏ�K�p����AA���ł̉ېł��Ⴍ�}�����閔�͔�ېłƂȂ�B
�@�{��A-B�d�ŏ��̕։v���鎑�i�̂Ȃ�C�Ђ��A�_�~�[��ГI��B�Ёi�y�[�p�[�E�J���p�j�[�ł��邱�Ƃ�����j����݂����邱�Ƃɂ���ď��̕։v���邱�Ƃ����(treaty shopping)�Ƃ����B
�@���̕։v�𗘗p���邵�������̂Ȃ����̂̂Ȃ���Ђ�������Ёiconduit company�j�Ƃ��ĂԁBke
8.2.4. �ېł���鏊���͈̔́E�ېŕ����ɂ��Ă̂܂Ƃ�
8.2.4.1. �͂��߂�
8.2.4.2. ���Z�ҁE�����@�l�̏ꍇ
8.2.4.2.a. ���Z��
8.2.4.2.b. �����@�l
8.2.4.3. �Z�ҁE�O���@�l�̏ꍇ
8.2.4.3.a. �����ɍP�v�I�{�݂�L����Z��(�����164-1)
8.2.4.3.b. �����ɍP�v�I�{�݂�L���Ȃ��Z��
8.2.4.3.c. �����ɍP�v�I�{�݂�L����O���@�l jo
OECD���f��7��1����1���FPE�Ȃ���ΉېłȂ��ino taxation without PE�j
�@�@�@�@�@�@�@�@��2���FPE�ɋA�����鎖�Ɨ����݂̂ɉې�
OECD���f��7��2���F�Ɨ������Ҋ������iarm�fs length principle�j
����n�����Z�Ҋ�Ƃɑ��ĉېł���ۂ�3�֖̊�@[1]臒l�A[2]��������A[3]�ېŏ����͈̔�
OECD���f��7��1���́A�A��������`(attributed income principle)�ɑ����Ă���B
[1]臒l�FPE���Ȃ���Ό���n���͉ېł��Ă͂����Ȃ��B�i7��1����1���j
[2]��������FPE�����鏊����PE���ݒn���i����n���j�Ɍ����L���鏊���ł���B�i�K�薳���j
[3]�͈́FPE�ɋA�����鏊���݂̂Ɍ���n���͉ېł��邱�Ƃ��ł���B�i7��1����2���j
�i��26�����O�̓��{�@��1966�N�ȑO�̃A�����J�@�ɋ߂��S������`(entire income principle)���̗p���Ă���z����(force of attraction)���ᔻ����Ă������A��26������͓��{�@���A��������`�ɂȂ������A��26�����ȑO�ɂ����Ă��d�ŏ��������Ƃ̊W�ł͋A��������`���K�p����邱�Ƃ��w�ǂł���̂ŁA�S������`�̐����͏ȗ�����lz�j
OECD���f��7��2���cPE�ɋA�����闘���F�Ɨ������ҊԌ���
�@PE�ɋA�����闘�����Z�肷��ہA���YPE���{�X���Ƃ͕��������Ɨ��̊��(a separate and independent enterprise)�Ȃ�Γ����ł��낤�����A�����߂�B �i�Ɨ������ҊԌ����́A���X�e�q��Њԓ��̊֘A�ҊԎ���ɂ��ĉېł̓K������ۂ��߂ɔ��W�����l�����ł���BCf.�����ώ@�@Die isolierende Betrachtungsweise�cS����S���Ŋώ@�ł��鎖�ۂ݂̂Ɋ�Â��ĉېł���j
�@�e�q��Њ��̎��(transaction)���{�x�X���̓�������idealing�j�ɂ��āA�����Ɨ������ҊԌ����Ă͂߂ėǂ��̂��A�Ƃ����^�O�͂����ƈȑO����悹���Ă���B
�@�������{�x�X�ԓ�������ɂ��Ă��Ɨ������ҊԂł̎�����[��(fiction)����Ƃ����l�������x�z�I�B
�@�A���e�q��ЊԎ���Ɩ{�x�X�ԓ�������Ƃ����S�ɓ����ł���Ƃ͍l�����Ă��Ȃ��B�@�l�i�̗L��������E��������ɗ^����e���͂��肤��A�ƍl�����Ă���B�i�ނ��A�o�ϗ��_����@���_����ɂ߂ē���Ȗ��j
��p�E�����̔z���c�c�����n�����a57�N6��11������1066��40�Łc�O���@�l�̍���PE�����q��p���T���ł���Ɣ��f�B�O���@�l�������q��p�̂�������PE�̏����i�ۗL�����q�����j�ɑΉ�������̂Ƃ����z�������z�ɂ��āB
�n�d�b�c���f��24���c�����ʎ戵����
�e���͉ېłɍۂ��ċ��Z�҂ƔZ�҂Ƃ̊Ԃō��ʂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�Ƃ�킯�AS����R����S���x�X�iPE�j�ɉېł���ۂɁAS�����Z�҂ł����ЂƔ�ׂāA�����I�Ɉ����Ă͂Ȃ�Ȃ��B
�������A�x�X�ɖ@�l�i���Ȃ��AS�����Z�҂ɖ@�l�i������Ƃ����Ⴂ����A���S�ɓ����戵���ł���Ƃ�������Ȃ��B�ǂ̒��x�قȂ鈵����������i�K�v�Ƃ���j�A�ǂ̂悤�Ȉ����������ʌ����ɔ����邱�ƂƂȂ�̂��Hcf.����nj[�u�n�d�b�c���f���d�ŏ��24���i�����ʎ戵���j�Ɋւ���2007�N5��3�����J���c���Ăɂ��ā@�\�����m�[�g�\�v�g���X�g60�����p���w���ۏ�����ɔ����@�I�����(15)�x67��(2008.2)
OECD���f��10��4���i�z���j�A11��4���i���q�j�A12��3���i�g�p���j
�c�cPE�ɔz���E���q�E�g�p�����A�����鎞�A��ʂ̎��Ɨ����Ɠ��l��PE�ɋA�������������i��p�T����̏����j�ɑ��Ēʏ�̏����ېł�����B�i�u����profit�v�����������Ӗ�����j
���Ə����FPE�ɋA�����鏃�����ɑ��ې�
���{�����F�������i��p�T���̂Ȃ������j�ɑ������ې�(�A�����{�����ł����Ă�PE�ɋA�����鏊���ɂ��Ă͏�̃��[���ɕ키�B)
��FR����R�Ђ�S����S�ЂƎ�������ė��q�����Ȃǂ�Ƃ���B
R�Ж{�X����������Ă����̂ł���A�����ېŁB
R�Ђ�S���x�X����������Ă����̂ł���APE�̏������ɑ���ېŁB
�����ېłɂ��ŕ��S�͎��Ƃ��ďd�����邱�Ƃ�����B
R����R�Ж{�X��S����S�Ђ�1000�𗘎q��10%�őݕt���AR�Ђ͑�O�ҁET�Ђ���1000�𗘎q��9���Ŏ؎Ă����ꍇ�A100�̗��q�����āA90�̗��q�x�����Ȃ��B�ň��O��������10�B�������A10���̐ŗ��Ō��������ꍇ�A������100�ɑ��ĉۂ����̂ŁAR�Ђ̐ň��㏊����0�B
R�Ђ�S���x�X��100�̗��q�����AT�Ђɑ���90�̗��q�x��������ꍇ�AS���x�X�̐ň��O������10�ɑ���S���̒ʏ�̏����ŗ��i�Ⴆ��40���j���K�p�����ƁAR��S���x�X�̐ň��㏊����6�B
�����ƂƂ��ẮA�����ɂ��Č����ېł�������邩�������ƂȂ�B
8.2.4.3.d. �����ɍP�v�I�{�݂�L���Ȃ��O���@�l
8.3. ���Z�ҁE�����@�l�ɑ��鍑�ۓI��d�ېł̔r��
8.3.1. �O���Ŋz�T�������ƍ��O�����Ə�����
8.3.1.1. ��̗��O�^jr
���ƒ�����
R���̓�����R�����������ď�����Ƃ���BR���̐ŗ�40%�AS���̐ŗ�30%�Ƃ���B
�@�@�iR���AS�����Ahome���Ahost���ƌĂԂ��Ƃ�����j
R���͎����̐ň��㗘�v���ő�ɂȂ铊�����I�ԁB
R���̎��_���猩��ƁAR�����ېł��Ă�R���̎茳�Ɏc���Ă��A�ǂ����R������������(national income)�ł���BR�����{�͍��������ő剻��ڎw���ׂ��ł���B�Ŏ��ő剻��ڎw���킯�ł͂Ȃ��B
S���ɓ��������ꍇ�̗��v����rS�AR���ɓ��������ꍇ�̗��v����rR�Ƃ���B
rS��10%�ArR��6%�@��S���ɓ������邱�Ƃ����������ő剻�̊ϓ_����R���ɂƂ��Ė]�܂����B
rS��10%�ArR��8%�@��R���ɓ������邱�Ƃ����������ő剻�̊ϓ_����R���ɂƂ��Ė]�܂����B
���ۓI��d�ېł����u����Ă���Ƃ��āArS��10%�ArR��6%�̏ꍇ�A
�@S���ɓ��������R������������7%�AR���̐ň��㗘�v����rS(1�|0.3�|0.4)��3��
�@R���ɓ��������R������������6%�AR���̐ň��㗘�v����rR(1�|0.4)��3.6%
�@R����R���ɓ������Ă��܂��AR���̍����������ő剻����Ȃ��B
cf. rS��10%�ArR��8%�̏ꍇ�A
�@S���ɓ��������R������������7%�AR���̐ň��㗘�v����rS�i1�|0.3�|0.4�j��3���B
�@R���ɓ��������R������������8%�AR���̐ň��㗘�v����rR�i1�|0.4�j��4.8%�B
�@R����R���ɓ�������̂ŁAR�����������ő剻�̊ϓ_����͂��̂܂܂ł悢�B
�@�i�S���E�I�Ȋϓ_����͂��̂܂܂ł���Ƃ܂����B��q�j
rS��10%�ArR��6%�̏ꍇ�AR�����������ő剻�̊ϓ_�����S���������]�܂����̂ɁA�Ő���R���̓�����I�����܂��������ɗU�����Ă��܂��B
R�����������̊ϓ_����́AS�������̗��v����rS(1�|0.3)�ł���AR�������̗��v����rR�ł���B
R����R���̉ېł���O�ɂ���Ɠ����ɒ��ʂ���悤�Ɏd������悢�B
�����ŁAR����S���Ŏx�������ł���������T��(deduction)����Ƃ���B
rS��10%�ArR��6%�̏ꍇ�A
�@S���ɓ��������R���̐ň��㗘�v����rS(1�|0.3)(1�|0.4)��4.2���B
�@R���ɓ��������R���̐ň��㗘�v����rR(1�|0.4)��3.6%�B
�@R����S���ɓ�������悤�ɂȂ�AR�����������ő剻�̊ϓ_������]�܂����B
cf. rS��10%�ArR��8%�̏ꍇ�A
�@S���ɓ��������R���̐ň��㗘�v����rS(1�|0.3)(1�|0.4)��4.2���B
�@R���ɓ��������R���̐ň��㗘�v����rR(1�|0.4)��4.8%�B
�@R����R���ɓ�������悤�ɂȂ�AR�����������ő剻�̊ϓ_������]�܂����B
R�����������ő剻�̊ϓ_����S��������R�������Ƃ̑I���ɒ����I�ɂȂ邱�Ƃ����ƒ������iNN: National Neutrality�j�Ƃ����B
���{�A�o���������̌o�ό����݂̂��l����Ȃ���ƒ������̊ϓ_���獑�O�����ɂ����Y�O���ɂ�����Ŋz�������̉ېł̑O�ɏ����T���i�����Z���j������ׂ��ł���B
���O���Ŋz�����Z���ideduction method�j(���͊O���Ŋz�����T��)
���{�A�o������
���ƒ������ɂ��O���Ŋz�����Z�����x�́A���{�A�o���̗��ꂩ��͍œK(optimal)�ȐŐ��ł��邪�A�S���E�I�Ȏ��_����͍œK�ł͂Ȃ��B
rS��10%�ArR��8%�̏ꍇ �O���Ŋz�����Z������R����R���ɓ�������悤�ɂȂ�B�������S���E�I�Ȏ��_�����S���������]�܂����B
�S���E�I�������z���̌������̊ϓ_����́A�ň��O���v�����������ւ̓������d������ׂ��B
R���̎��_����́A�ň��㗘�v�����������ɓ�������B
�ېł��A�ň��O���v���̍������ւ�R���̓�����W���Ȃ��悤�ɂ���ׂ��B
�@��R����S���ɓ������Ă�R���ɓ������Ă������ŗ��ɒ��ʂ���悤�ɂ���ׂ��B
�@�@�@��������{�A�o�������iCEN: Capital Export Neutrality�j�Ƃ����B
�@��R����S���ɓ������Ă�R���ɓ������Ă��ŏI�I��R���̐ŗ��ɒ��ʂ���悤�ɂ���ׂ��B
�@��R����S���ɓ��������ꍇ�AS���̐Ŋz��R�����Ŋz����T��(credit)����ׂ��B
�@���O���Ŋz�T���icredit method�j
R����S����100�̏������҂����ꍇ�AS���̐Ŋz��30�AR���̐Ŋz�͌��X��40������������S���Ŋz30���T������̂ŁA�ŏI�I��R���̐Ŋz��10�ɂȂ�B
rS��10%�ArR��8%�ŊO���Ŋz�T�����x���̗p����Ă���ꍇ
�@S���ɓ��������R���̐ň��㗘�v����rS{1�|0.3�|(0.4�|0.3)}��6���B
�@R���ɓ��������R���̐ň��㗘�v����rR(1�|0.4)��4.8%�B
�@R����S���ɓ�������悤�ɂȂ�A�S���E�I�Ȏ��_������]�܂����B
����S���̐ŗ���50%��������H
R����S����100�̏������҂����ꍇ�AS���̐Ŋz��50�AR���̐Ŋz�͌��X��40������������S���Ŋz50���T������̂ŁA�ŏI�I��R���̐Ŋz��-10�ɂȂ�ׂ��A�܂�R����R����10�ҕt���ׂ��B
�������A���{�A�o�������̎�|�������܂ŊѓO����Ő����̗p���鍑�͏��Ȃ��B
�ʏ�A�O���Ŋz�T���͎����̐ŗ�������Ƃ��邱�Ƃ������B
���{�A��������
�O���Ŋz�T�����x�ł���d�ېł͔r�������B
�������AR���̊�Ƃł���R�Ђ�S���Ŏ��Ƃ��s�Ȃ��ꍇ�A���n��ƁiS���̊�Ɓj�ł���S�ЂƔ�ׂāA�Ő���قȂ鈵�����Ă��܂��B
S���s��ŋ��������Ƃ��ǂ��̍��̋��Z�҂ł��邩�ɂ���ċ����������قȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃ������������Ƃ����B
R����R�Ђ�S�������ɉېł��Ȃ���AR�Ђ͌��n��Ƃ�S�Ёi�����͑�O���ł���Ⴆ��T����T�Ёj�Ɠ���������S���ɂ����ċ������邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�B
�@�����O�����Ɛ��iexemption method�j
���{�A���������iCIN: Capital Import Neutrality�j�́A���O�����Ɛł̐��x�̉��ł́AR������S���ɓ������邱�Ƃ�S������S���ɓ������邱�ƂƂ���������������Ƃ������Ƃł���B
���� �����������Ǝ��{�A���������Ƃ���������邱�Ƃ����邪�A�����ɈقȂ�B
�����������͎��Ƃ��s�Ȃ���ʂ�z�肵�Ă���B
���{�A���������͎��{��A�������ʁi�����̏�ʁj��z�肵�Ă���B
���{�A���������͓����Ƃ����~�Ə���Ƃ̊Ԃ̑I���ɂ��Ă̒������ł���B
���{�A�o�������͓����Ƃ����{������I���ɂ��Ă̒������ł���B
���~����莑�{������I���̕����Ő��̉e����������ƍl�����Ă���A�`���I�Ɍo�ϊw�҂͎��{�A����������莑�{�A�o���������d������i���O�����Ɛł��O���Ŋz�T�����x�����߂�j�B
OECD���f��23���@���O�����ƐŁA�O���Ŋz�T��
�e���������̌o�ό����̍ő剻�݂̂��l����Ȃ�A���ƒ������̍l���ɂ��O���Ŋz�����Z���������̗p���邱�Ƃ��\�z�����B�����O���Ŋz�����Z�������ł͍��ۓI��d�ېł��r������Ȃ��B
�ň��O��R���̗��v����S���̗��v���������ł������Ƃ��Ă��@
�@R����S�������́AR����R���������s���ł���i���{�A�o�������̊ϓ_�j�B
�@R����S�������́AS����S���������s���ł���i���{�A���������̊ϓ_�j�B
�d�ŏ��͎��2�̖�����S���B
��S���ɂ����錹��ېŊNJ���}������B
�@�@�i���Ə����ɂ���PE�Ȃ���ΉېłȂ��A���{�����ɂ��Đŗ���Ⴍ����j
������ł��c�鍑�ۓI��d�ېł���̋~�ς��A���Z�ېŊNJ���L��R���ɋ`���Â���B
�@�@�iOECD���f��23����2�̕����L���Ă���B���ۂ̓ԏ��͂ǂ��炩���̗p����j
23A���@�Ə������E���O�����Ɛ�
23B���@�Ŋz�T�������E�O���Ŋz�T��
�Ȃ��A23A�������O�����Ɛł��̗p���Ă���Ƃ����Ă��A2�����A10���E11���̔z���E���q�ɂ��ĊO���Ŋz�T�����߂Ă���B���S�ȍ��O�����Ɛł��̗p���邱�Ƃ͖w�ǂȂ��B
�܂��A3���́A���O�����Ɛł�S���ʼnېł���邱�Ƃ������Ƃ��Ă���B
���{�̖@�l�Ŗ@69���E�����Ŗ@95���y�ѓ��{����������d�ŏ��͊O���Ŋz�T�����̗p���Ă���B
8.3.1.2. �@�l�Ŗ@69��
8.3.2. �Ŋz�T�������ׂ��O���̑d��
8.3.2.1. �u�O���@�l�Łv�̈Ӌ`(��COLUMN8-7�K�[���W�[)
8.3.2.2. �T���Ώۖ@�l�ł͈̔�
8.3.2.3. �u�[�t���邱�ƂƂȂ�ꍇ�v
8.3.3. �T�����x�z
8.3.3.1. �T�����x�z�̈Ӌ`
�@�l�Ŋz�~(���O�������z���������z)�����{�ŗ��~���O�������z
R����R�Ђ�S����T�����炻�ꂼ��100���̏������ꍇ�́H
�ŗ��́AR����40%�AS����30%�AT����50%�Ƃ���B
���ʌ��x�z���� S�������ɂ��āAS����30�[�ŁA�T�����x�z��40�AR���ł�10�[�ŁB
T�������ɂ��āAT����50�[�ŁA�T�����x�z��40�AR���ł͊ҕt�Ȃ��B
| Cf.�o�X�P�b�g����(�������ڕʌ��x�z����)�͏ȗ� |
S��������T�����������O�����Ƃ��ĂЂƂ܂Ƃ߂ɂ���B
S����30�[�ŁAT����50�[�ŁA�T�����x�z��80�Ȃ̂ŊO���Ŋz�S�čT���AR���ł͔[�łȂ��B
�ꊇ���x�z�����̉��ł́A��ŗ�������̏����Ă����ƂɁA�O���Ŋz�T���̗]�T�g��������B
���̗]�T�g������A���{��Ƃ͈��S���č��ŗ����ւ��i�o�ł���i�ލ�[�Ђ�]���p�Ƃ����j�B
�ꊇ���x�z�����ł���Ɠ�d�ېł���̋~�ςƂ�����|�ȏ�̗��v��[�Ŏ҂ɗ^���Ă��܂��i��d�ېŖh�~�̊ϓ_����́AT����50%�̉ېł��Ă��܂����Ƃ��d���Ȃ��j���A���ʌ��x�z�����͎��������B
| ���É��n���ߘa3�N12��8���Ŏ�271������13641(�Ō��ߘa4�N10��6���Ŋm��) �@�w�i�����B���{���Z�ҁB�N���ҁj������28�y��30�N�Ƀu���W������ۗL���A�����ɂ�����x���̎戵�ҁi�`�،��j��ʂ��ė��q�̎x�������B���������ɌW�鏊���ŗ���5���ł������B �@����28�N�F���q75��6065�~�A������11��5790�~�A�Z����3��7802�~�A��t�z60��2473�~�B�m��\���F�O���Ŋz�T���z11��3410�~�i��75��6065�~�~15���j�B���z�X�������F�O���Ŋz�T���z5��4524�~�i�����Ŗ@95��1��5��3403�~�B���������m�ۖ@14��1��1121�~�j�B �@����30�N�F���q80��2958�~�A������12��2972�~�A�Z����4��0147�~�A��t�z63��9839�~�B�m��\���F�O���Ŋz�T���z16��0591�~�i��80��2958�~�~20���j�B���z�X�������F�O���Ŋz�T���z5��3759�~�i�����Ŗ@95��1��5��2654�~�B���������m�ۖ@14��1��1105�~�j�B �@�K��@�����Ŗ@�{�s�߂Q�Q�Q���P���c�́A�O���Ŋz�T�����x�z�́A�����̋��Z�҂̂��̔N���̏����ł̊z�c�ɁA���̔N���̏������z�c�̂����ɂ��̔N���̒������O�������z�c�̐�߂銄�����悶�Čv�Z�������z�Ƃ���|���K�肷��B �@���_�@�w�������Ŗ@95��1���A�����Ŗ@�{�s��222��1����K�p���ĊO���Ŋz�T�����x�z���v�Z�������Ƃ������d�ŏ��ɔ������K�@�ł��邩�B �@���|�@�����u���Q�Q���P���i���j�i���j���������́A�O���Ŋz�T�����x�z�ɂ��āA�w���{���̑d�ł̊z�̂����A���̏����ɑΉ����镔�����Ȃ����̂Ƃ���B�x�ƋK�肷��ɂƂǂ܂�A����Ɂw���̏����ɑΉ����镔���x�̒�`�₻�̋�̓I�Ȍv�Z���@���߂�K��͂Ȃ��A���̓K�p���@�Ɋւ���K����Ȃ�����A�����������̓I�ȍT�����x�z���v�Z���邱�Ƃ͂ł����A�������̋K��ړK�p���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�������āA�����Q���Q���ɂ����ẮA����̒������̏���K�p����ꍇ�ɂ́A���ɒ�`����Ă��Ȃ��p��́A�����ɂ��ʂɉ��߂��ׂ��ꍇ�������ق��A���̏�K�p�����d�łɊւ��邻�̒��̖@�ߏ�L����Ӌ`��L������̂Ƃ���Ƃ���Ă��邱�Ƃ�A�����������ۓI��d�ېł̖��͒Ⴂ�ŗ��̍��̎����ŗ��͈͓̔��Ő����A�ʏ�̐Ŋz�T�������ɂ�����O���Ŋz�T�����x�z�͍��O�������z�ɍ����̎����ŗ����悶�Čv�Z�������̂ł��邱�Ɓi���j�ɏƂ炵�Ă��A�����d�ŏ��́A�u���W���Ŕ[�t�����d�ł̊O���Ŋz�T�����x�z�̌v�Z�ɂ��Ă͓��{�̖@�߂ɏ]�����Ƃ�\�肵�Ă�����̂Ɖ������B�v �@�u�u���W�����̗��q���擾�������{�̋��Z�҂ɑ��鏊���ł̊O���Ŋz�T�����x�z�̌v�Z�ɓ������ẮA���{�̏����œ��̊W�@�߂��K�p�����ׂ����̂ł���A�䂪���ɂ����Ă͏����Ŗ@�X�T���P���y�т��̈ϔC�������@�{�s�߂Q�Q�Q���P���̋K���K�p���ĊO���Ŋz�T�����x�z�̌v�Z������邱�ƂɂȂ邩��A�����̖{���e�N���̏����łɂ�����{���u���W�����̗��q�ɌW��O���Ŋz�T���̌v�Z�ɂ����̋K���K�p���邱�Ƃ������d�ŏ��Ɉᔽ������̂Ƃ͂����Ȃ��B�v �@�u�����́A�݂Ȃ��O���Ŋz�ł���O�������Ŋz�ɂ��A�{���u���W�����ɌW�闘�q�̊z�̓u���W���łQ�O���̊����Ŕ[�ł����ꂽ���̂Ƃ݂Ȃ��ꂽ��̂��̂Ƃ��ׂ��ł���A���{�Ŏx����ꂽ���q�̋��z�̂Q�T���i�����Ɏx����ꂽ���q�̋��z���W�O���~�P�O�O���j�~�Q�O���j�ƌv�Z�����ׂ��ł���Ǝ咣���邪�A�����d�ŏ��Q�Q���Q���i���j�i���j�́A�O���Ŋz�T���̓K�p��A�u���W���̑d�łƂ��ĂQ�O���̐ŗ��Ŕ[�t�������̂Ƃ݂Ȃ��čT������|���߂��K��ł��邩��A�O�������Ŋz����{�Ŏx����ꂽ���q�̋��z�̂Q�O���Ƃ��Čv�Z���邱�ƂɌ��͂Ȃ��i���j�A�����̏�L�咣�͍̗p���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�v |
8.3.3.2. �T�����x�z�����O���@�l�ł̈����E�]�T�g�̈���
6�Ł�143.03�O�ōT���]�T�g�肻�ȋ�s�����E�Ŕ�����17�N12��19�����W59��10��2964��8.3.4. �P�v�I�{�݂�L����O���@�l�ɑ���O���Ŋz�T��(�@��144����2)
8.3.5. �O���q��Ђւ̓����\�\�ԐڊO���Ŋz�T������O���q��Дz���v���s�Z����(�@��23����2)jv
R�Ђ�S�����x�X��ݒu��S���ېłɂ���R�Ђ�R���ŊO���Ŋz�T���ɂ��~�ς���BR�Ђ�S�����q�����ݒu���q��Ђ�S���ېłɂ��āAS���Ŕ[�ł����̂�R�Ђł͂Ȃ��q��Ђł���̂ŁAR�Ђ�����R���ŊO���Ŋz�T���̋~�ς��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�i�ېł̒������ɔ����j
��
�ԐڊO���Ŋz�T���c���@�l�Ŗ@69��8��
�@R�Ђ��O���q��Ђ���z�������Ƃ��A�q��Ђ̊O���Ŋz���Ŋz�T���̑ΏۂƂ���B
��
2009�N�����O���q��Дz���v���s�Z���c�c�@��23����2�icf.����5.2.2.3.e.�j
�@R�Ђ��O���q��Ђ���z�������Ƃ��AR�Ђ̉ېŏ����Ɂi�w�ǁj�܂߂Ȃ��B���{�͑S���E�����ېŁ{�O���Ŋz�T�������Ƃ����̌n���̗p���Ă��邪�A�q��Ќ`�Ԃł̊C�O�i�o�Ɋւ��Ă͎�����̍��O�����Ə������ɋ߂Â����B(�ԐڊO���Ŋz�T���������Ȃ�����ł͂Ȃ�)
R�Ђ�S���q��Ђ̊��������n�����ꍇ�ɂ͈��̏����̉��œ��{�̉ېł��邱�Ƃ�����A�z�����������n�v���Ƃ������v�җ����@�̈Ⴂ�ɂ��������c���Ă��܂��Ă���B
8.4. �ߐŃC���Z���e�B�u�ւ̑R�[�u
8.4.1. ��{�I���_
8.4.2. �ړ]���i�Ő�(transfer pricing)jx
8.4.2.1. �ړ]���i�Ő��Ƃ͉���(��������322.03�����y�APE��8.2.4.3.c.�A50%�ȏ�og)
�d�œ��ʑ[�u�@66����4�i���O�֘A�҂Ƃ̎���ɌW��ېł̓���j�@�@�l���c�c���Y�@�l�ɌW�����O�֘A���i�O���@�l�ŁA���Y�@�l�Ƃ̊Ԃɂ����ꂩ����̖@�l�������̖@�l�̔��s�ϊ������͏o���c�c�̑������͑��z���S���̌\�ȏ��̐����͋��z�̊������͏o���ږ��͊ԐڂɕۗL����W���̑��̐��߂Œ�߂����̊W�c�c�̂�����̂������c�c�j�Ƃ̊ԂŎ��Y�̔̔��A���Y�̍w���A�̒��̑��̎�����s���ꍇ�ɁA���Y����c�c�ɂ��A���Y�@�l�����Y���O�֘A�҂���x������Ή��̊z���Ɨ���Ɗԉ��i�ɖ����Ȃ��Ƃ��A���͓��Y�@�l�����Y���O�֘A�҂Ɏx�����Ή��̊z���Ɨ���Ɗԉ��i�����Ƃ��́A���Y�@�l�̓��Y���ƔN�x�̏����ɌW�铯�@���̑��@�l�łɊւ���@�߂̋K��̓K�p�ɂ��ẮA���Y���O�֘A����́A�Ɨ���Ɗԉ��i�marm's length price�n�ōs��ꂽ���̂Ƃ݂Ȃ��B�Q �O���ɋK�肷��Ɨ���Ɗԉ��i�Ƃ́A���O�֘A��������̊e���Ɍf�������̂�����ɊY�����邩�ɉ������Y�e���ɒ�߂���@�̂����A���Y���O�֘A����̓��e�y�ѓ��Y���O�֘A����̓����҂��ʂ����@�\���̑��̎�������Ă��āA���Y���O�֘A������Ɨ��̎��Ǝ҂̊ԂŒʏ�̎���̏����ɏ]�čs����Ƃ����ꍇ�ɓ��Y���O�֘A����ɂ��x������ׂ��Ή��̊z���Z�肷�邽�߂��ł��K�ȕ��@�ɂ��Z�肵�����z�������B
�@��@�I�����Y�̔̔����͍w���@���Ɍf������@
�@�@�C�@�Ɨ����i�䏀�@[CUP�@comparable uncontrolled price method�i��CUT�@comparable uncontrolled transaction�j]�i����̊W�ɂȂ�����Ɣ��肪�A���O�֘A����ɌW��I�����Y�Ɠ���̒I�����Y�Y���O�֘A����Ǝ���i�K�A������ʂ��̑������l�̏̉��Ŕ�����������̑Ή��̊z�i���Y����̒I�����Y�Y���O�֘A����Ǝ���i�K�A������ʂ��̑��ɍ��ق̂���̉��Ŕ����������������ꍇ�ɂ����āA���̍��قɂ�萶����Ή��̊z�̍����ł���Ƃ��́A���̒������s����̑Ή��̊z���܂ށB�j�ɑ���������z�����ē��Y���O�֘A����̑Ή��̊z�Ƃ�����@�������B�j
�@�@���@�Ĕ̔����i��@[RP�@resale price method]�i���O�֘A����ɌW��I�����Y�̔��肪����̊W�ɂȂ��҂ɑ��ē��Y�I�����Y��̔������Ή��̊z�i�ȉ����̍��ɂ����āu�Ĕ̔����i�v�Ƃ����B�j����ʏ�̗����̊z�i���Y�Ĕ̔����i�ɐ��߂Œ�߂�ʏ�̗��v�����悶�Čv�Z�������z�������B�j���T�����Čv�Z�������z�����ē��Y���O�֘A����̑Ή��̊z�Ƃ�����@�������B�j
�@�@�n�@������@[CP�@cost plus method]�i���O�֘A����ɌW��I�����Y�̔���̍w���A�������̑��̍s�ׂɂ��擾�̌����̊z�ɒʏ�̗����̊z�i���Y�����̊z�ɐ��߂Œ�߂�ʏ�̗��v�����悶�Čv�Z�������z�������B�j�����Z���Čv�Z�������z�����ē��Y���O�֘A����̑Ή��̊z�Ƃ�����@�������B�j
�@�@�j�@�C����n�܂łɌf������@����������@���̑����߂Œ�߂���@
�@��@�O���Ɍf�������ȊO�̎���@�����C����j�܂łɌf������@�Ɠ����̕��@ �@[3���ȉ���]
�莮���z�@(formulary apportionment)�Ƃ�
�֘A��Ђ̊W�ɂ���o�ЂƂr�Ђ̍��v��600�̗��v���オ���Ă���Ƃ���B�o�Ђ̎��Y��6000�A�J���҂̒�����3000�A�r�Ђ̎��Y��4000�A�J���҂̒�����7000�ł���Ƃ���B
���Y�݂̂ɔ�Ⴓ���ė��v��{�x�X�ԂŔz������ꍇ�A�r�Ђ̗����͎��̂悤�ɂȂ�B
600�~4000���i6000�{4000�j��240
���Y�ƒ����̗������������Ė{�x�X�ԂŔz������ꍇ�A�r�Ђ̗����͎��̂悤�ɂȂ�B
600�~�i4000���i6000�{4000�j�{7000���i3000�{7000�j�j��2��330
�@�i���Y�ƒ����Ƃ��ǂ̂悤�ɃE�G�C�g�t�����邩�A�Ƃ����������邪�����ł͏ȗ�����j
8.4.2.2. �킪���̈ړ]���i�Ő��̊T�v
8.4.2.2.a. �킪���̈ړ]���i�Ő��̍\��
8.4.2.2.b. �킪���̈ړ]���i�Ő��̊T�v
8.4.2.3. �ړ]���i�Ő��̓K�p�v��
8.4.2.3.a. ���O�֘A��
8.4.2.3.b. �Ɨ���Ɗԉ��i�̎Z����@�@�\�\��{�O�@
����2��1�������́u�I�����Y�̔̔����͍w���@���Ɍf������@�i�j�Ɍf������@�́A�C����n�܂łɌf������@��p���邱�Ƃ��ł��Ȃ��ꍇ�Ɍ���A�p���邱�Ƃ��ł���B�j�v�ƂȂ��Ă������A����23�N������́i�@�j�����폜����Ă���A�u��{�O�@�D��̌����v���Ȃ��Ȃ�u�w�ł��K�ȕ��@�x��p����ׂ��|�̌����v�ɕς�����B���@OECD�ړ]���i�K�C�h���C��(OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations)2010�N7��22����(�ŐV�ł�2017�N7��10����)�́u�ł��K���ȕ��@most appropriate method�v����(�č���best method rule�ɑ���)�����ꂽ�B
| �������D�����E���R�n������16�N4��14������11(�s�E)7����51��9��2395�Ŋ��p(�������E�W�����X�g1289��236��)�E������������18�N10��13������16(�s�R)17����54��4��875�Ŋ��p�E�Ō�����19�N4��10������19(�s�c)34�����p�A�s�c�c�Ɨ����i��y�@(CUP�@:comparable uncontrolled price method)��K�p��������B ���ؐӔC�Ɋւ����R���|�c�c�u�I�����Y�̔�������Ɋւ��ēƗ���Ɗԉ��i���Z�肷����@�ɂ́A�u�Ɨ����i�䏀�@�v�̑��ɁA�@���O�֘A����ɌW��I�����Y�̔��肪�A���̒I�����Y�����W�ɂȂ��҂ɑ��Ĕ̔��������i�i�Ĕ̔����i�j����ʏ�̗����̊z���T���������z�������ēƗ���Ɗԉ��i�Ƃ���u�Ĕ̔����i��@�v�i�{���K���Q���P�����j�A�A���O�֘A����ɌW��I�����Y�̔��肪�A���̒I�����Y�̍w���A�������ɂ��擾�̌����̊z�ɒʏ�̗����̊z�����Z���Čv�Z�������z�������ēƗ���Ɗԉ��i�Ƃ���u������@�v�i�{���K���Q���P���n�j�A�R�u���̑��̕��@�v�i�{���K���Q���P���j�j���F�߂��Ă���Ƃ���A�ېŒ����A�Ɨ����i�䏀�@�A�Ĕ̔����i��@�A������@�̂�����̕��@���̂�ׂ����ɂ��ẮA����̋K�肪�Ȃ��A�ېŒ��̔��f�Ɉς˂��Ă���Ƃ���ł���B�m���s�n �@�@�������A�{���ł́A��������A�Ɨ���Ɗԉ��i���Z�肷��ɂ��A�Ɨ����i�䏀�@��p��������A��L�̇@�Ȃ����B�̕��@�ɂ�邱�Ƃ��A���K�ł���A�D��Ă���Ƃ̎咣�A��������Ă��Ȃ�����A�퍐���A�{���e����ɌW��Ɨ���Ɗԉ��i���Z��ɂ��āA�Ɨ����i�䏀�@���̗p�������Ǝ��̂ɂ́A���ɁA�����Ȃ��B�v |
| ���{�����[�q�����E���n������20�N7��11������16(�s�E)152�����^1289��155�ňꕔ���p�A�ꕔ�p��(���ΗY��Y�E�W�����X�g1399��171��)�E��㍂������22�N1��27������20(�s�R)126���Ŏ�260������11370���p�m��c�c�d�œ��ʑ[�u�@66����4��2��1���n�̌�����@�̓K�p����B �ېŒ����ړ]���i�Ő���K�p����ɍۂ����O�����ړ]�̊W�R����F�肷��Ȃǂ̎��O�葱���H�͕K�v��(����)�B ����K�͂̊g��ɔ����Ēl�������͂������W�͎���Љ�ɂ�����o�����ɏƂ炵�Ĉ�ʓI�Ɏ�m��������̂ł���Ƃ���A�[�Ŏ҂̍��O�֘A�҂ɑ��锄����z�̑S�̂ɐ�߂銄������50���ɒB����Ȃǂ̎���̉��ɂ����ẮA����K�͂ɒ��ڂ��Ĕ�r�Ώێ���Ƃ̍ۂ����ׂ��ł���Ƃ��ꂽ����B |
| ���[���h�E�t�@�~���[�����E�����n������29�N4��11������21(�s�E)472���S�I7��76(�ѐD�N���E�W�����X�g1516��10�ŁA�����C��E�W�����X�g1516��44�ŁA����l�E�W�����X�g1536��118��)�c�c�f�B�Y�j�[�E�L�����N�^�[��p�����p�ꋳ�ނ��O���֘A��Ђ���d����ē��{�ŖK��̔����Ă����B�f�B�Y�j�[�E�L�����N�^�[�̃��C�����e�B�Ɋւ��鍷�ْ������s�\���ł���ېŏ�����������ꂽ����B |
8.4.2.3.c. �Ɨ���Ɗԉ��i�̎Z����@�A�\�\���̑��̕��@
8.4.2.3.c.�A. PS�@(���v�����@: profit split method)
8.4.2.3.c.�A.1. ��r���v�����@(comparable profit split method)(�d����39����12��8��1���C)
8.4.2.3.c.�A.2. ��^�x���v�����@(contribution profit split method)(�d����39����12��8��1����)
| �G�N�A�h���o�i�i�����E�����n������24�N4��27������21(�s�E)581����59��7��1937�Ő������p(�_�R�O�s�E�W�����X�g1445��8�ŁA�ѓc�T��E�W�����X�g1475��124��)�E������������25�N3��28������24(�s�R)229���Ŏ�263������12187�T�i���p�E�Ō�����27�N1��16���Ŏ�265������12587�s�m��c�c�Ŗ�����Y�́A�t�B���s���Y�o�i�i��A�����Ă����Ђ̎�����r�Ώێ���Ƃ��Ċ�{�O�@�̉��ꂩ��K�p���邱�Ƃ���������(�����͊�{�O�@�D��̌����ł�����)�B�������G�N�A�h�����{�̋K��(�Œ�A�o���i)�ɂ��K�ȍ��ْ������ł��Ȃ��Ɣ��f���A��^�x���v�����@��p�����B�ٔ������A��{�O�@��K�p�ł��Ȃ���ʂł��邱�Ƃ�F�߁A��^�x���v�����@�̓K�p��F�߂��B(��8.4.2.3.d.���ؐӔC) |
8.4.2.3.c.�A.3. �c�]���v�����@(residual profit split method)(�d����39����12��8��1���n)
| �{�c�Z���H�ƃ}�i�E�X���R�f�Ւn�掖���E�����n������26�N8��28������23(�s�E)164���Ŏ�264������12520�����ꕔ�F�e�E������������27�N5��13������26(�s�R)347���Ŏ�265������12659�T�i���p�m��S�I7��77(�n�ӏ[�E�W�����X�g1476��8�ŁA���v�����E�W�����X�g1485��10�ŁA���쒉�P�E���ېŖ�35��3��43�ŁA��{�j���E�W�����X�g1488��136�ŁA���������E�Ō�186��81��)�c�c�������{�@�l�̃u���W���֘A��Ђ��u���W���̎�����֎Ԏs��ɂ����ė��v���グ�Ă���͓̂��{�@�l�̖��`���Y�̍v�����傫������ł͂Ȃ��u���W���̃}�i�E�X���R�f�Ւn��ɂ�����Ő���̉��T���v�ɂ����̂ł���A�Ƃ��錴���̎咣���T�˔F�߂�ꂽ����B |
| �㑺�H�Ǝ����E(��1����)�����n������29�N11��24������25(�s�E)263����65��12��1665�Ŋ��p�m�����N��́u�����ōX����������������T�i�����v�͌�L�ł��낤�n(�������E�W�����X�g1530��131��)�E���������ߘa���N7��9������29(�s�R)382����65��12��1745�Ŋ��p�E(��2����)�����n���ߘa2�N2��28������27(�s�E)535���Ŏ�270������13386���p�m�� �@����(X��)�͂߂�����i�̐����E�̔����c�ޓ��{�@�l�ł���B��p�q��Ђ���A�Ђ�X�Ђ͂߂�����i�̃��C�Z���X�_���������AA�Ђ͎��Ђ��ۗL�����p�H��ł߂�����i�����A���ڂ܂��̓V���K�|�[���@�lC��(X�Ђ̎q���)����Ĕ�֘A�҂ɔ̔����AA�Ђ�X�Ђ�5���̃��C�Z���X�����x������(�}���[�V�A�q��Ђ���B�ЂƂ��ǂ��悤�̎�������Ă��邪�ȗ�)�BX�Ђ́A�q��Ђł͂Ȃ��؍��@�lK�ЂƂ��߂�����i�̃��C�Z���X�_���������Ă����B���{�̐Ŗ������͑d�œ��ʑ[�u�@�{�s��39����12��8���u�c�]���v�����@�Ɠ����̕��@�v�ɂ���ĎZ�肵�����i���Ɨ���Ɗԉ��i�ł���Ƃ����O��Ŗ@�l�ł̍X���������������B �@��1������R���|�@X-A�����X-K����u�Ƃł́C���̎���̑Ώۂ��閳�`���Y�����w����x�̂��̂Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B�vX-A�����X-K����u�ɌW����r����ƁC�c�c���̎���̑Ώۂ��閳�`���Y���̑Ή��̊z�ɉe�����y�ڂ����ق����݂���B�����āC���̉e������̓I�ɔc�����邱�Ƃ͋ɂ߂č���ł����āC������Ή��̊z�̍����ł���Ƃ͂����Ȃ�����C��������w���l�̏x�̉��ł��ꂽ���̂Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B�v �@�u�����O�֘A����ɂ��ẮC�����y�т��̍��O�֘A�҂��L����d�v�Ȗ��`���Y�����v�l���Ɋ�^���Ă��邱�Ƃ��炷��C���̓Ɨ���Ɗԉ��i�̎Z��ɂ́C��{�I���v��z��������Ŏc�]���v���d�v�Ȗ��`���Y�̉��l�ɉ����Ĕz������c�]���v�����@�Ɠ����̕��@��p����̂������I�ł���Ƃ������Ƃ��ł���B�v �@�i�T�i�R��������R���������p�����j �@��2�������|�@�u�{�����C�Z���X����y�і{���I�����Y�̔�����̂�����ɂ��Ă��C��{�O�@���͊�{�O�@�Ɠ����̕��@��p���Ă��̓Ɨ���Ɗԉ��i���Z�肷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��v�B �@�u�{�����O�֘A������̂��P�̒P�ʂƂ�����ŁC�c�]���v�����@�y�юc�]���v�����@�Ɠ����̕��@��p���Ă��̓Ɨ���Ɗԉ��i���Z�肷�邱�Ƃ́C�{�����O�֘A����̓Ɨ���Ɗԉ��i���Z�肷�邽�߂̍����I�ȕ��@�ł���ƔF�߂���B�m���s�n�@�����āC�{���ɂ����ẮC�c�]���v�����@�y�юc�]���v�����@�Ɠ����̕��@�ȊO�̖{�����O�֘A����̓Ɨ���Ɗԉ��i���Z�肷�邽�߂ɗp����ׂ��K�ȕ��@���������̓I�ȊW�R�������邱�Ƃ��������킹�鎖��͌�������Ȃ�����C�퍐���C�c�]���v�����@�y�юc�]���v�����@�Ɠ����̕��@��p���Ė{�����O�֘A����̓Ɨ���Ɗԉ��i���Z�肵�����Ƃ́C�K�@�ł���B�v |
| ���{�K�C�V�����E�����n���ߘa2�N11��26������28(�s�E)586���ꕔ�F�e�A�ꕔ���p�E���������ߘa4�N3��10���ߘa3(�s�R)25���T�i���p(�эK��u�c�]���v�v�Z�@�̗��v�����v���v�V�E������Watch�d�Ŗ@No.171�A��Ɏ��E���ېŖ�42��8��74�ŁE10��98�ŁA�Е�����E�W�����X�g1582��10��) �@���{�@�l���錴��(X��)�̓Z���~�b�N�X���f�B�[�[���ԗp�����q�����t�B���^�[�Ɋւ�����������̖��`���Y��L���Ă����B���B�ɂ�����f�B�[�[���Ԕr�K�X�K�������炷��ɓ����蓖�Y�����̎��{�͕s���ł��������߁AX�Ђ̊Ԑڎq��Ђ���|�[�����h�@�lB�Ђ̔���͔���ɂȂ����BB�Ђ̒��ߗ��v�����X�ЕۗL�̖��`���Y�ɗR������ƍl�����B�Ђ�X�Ђɑ��z�̎g�p�����x�����ׂ��ł���(���{�̍��Œ��̗���)�A���ߗ��v����ɉ��B�̋K���ɂ��ƍl�����B�Ђ���X�Ђɗ��v���ړ]����K�v�͂Ȃ�(X�Ђ̗���)�B�ٔ����͑��X�Ђ̎咣��F�߂��B �@�T�i�R���|�@�u�c�]���v�����@�́C�[�u�@�{�s�߂R�X���̂P�Q��W���P���ɒ�߂闘�v�����@�̈��ł���Ƃ���C�����̋K��ɂ��C���v�����@�́C�����Ώۗ��v���C���O�֘A����ɌW��I�����Y�̍w���C�����C�̔����̑��̍s�ׂ̂��߂ɖ@�l���͍��O�֘A�҂��x�o������p�̊z�C�g�p�����Œ莑�Y�̉��z���̑������̎҂������Ώۗ��v�̔����Ɋ�^�������x�𐄑�����ɑ����v���i�����v���j�ɉ����āC���Y�@�l�y�ѓ��Y���O�֘A�҂ɋA��������̂Ƃ�����@�ł���c�c�C�܂��C�����̋K�����̉�������̂Ƃ��Ē�߂�ꂽ�[�u�@�ʒB�U�U�̂S�i�S�j�|�Q�́C���v�����@�̓K�p�ɓ�����p���镪���v���ɂ��C�@�l���͍��O�֘A�҂��x�o�����l����̔�p�̊z�C�������{�̊z�ȂǁC�����̎҂����Y�����Ώۗ��v�̔����Ɋ�^�������x�𐄑�����ɂӂ��킵�����̂�p������̂Ƃ��C�����v������������ꍇ�ɂ́C���ꂼ��̗v���������Ώۗ��v�̔����Ɋ�^�������x�ɉ����č����I�Ɍv�Z������̂Ƃ��Ă���c�c�B�v |
8.4.2.3.c.�C. TNMM(����P�ʉc�Ɨ��v�@:transactional net margin method)(�d����39����12��8��2��)
| �������IHI(�ΐ쓇�d���d�H��)�����E�����n���ߘa5�N12��7���ߘa2(�s�E)372���F�e�E���������ߘa6�N12��11��(���m�F�B�m�肵���炵��)(PwC�u�ړ]���i�ٔ����ǂ݉��� ����Љ�Ɣ�r�\���̍čl�v2024.11.13�A��i�M���E�W�����X�g1605��10-11��) �@�����@�����i�������IHI�^�ΐ쓇�d���d�H�Ɓj�Ƃ��̍��O�֘A�҂ł���h�s�s�Ёi�^�C�@�l�j�Ƃ̊Ԃ̎ԗ��ߋ��@�i�^�[�{�`���[�W���j�ɌW�镔�i�A�o����A���`���Y����y�і���ɂ��āA�����̍��O�֘A����ɂ�茴�����x�������Ή��̊z���A�[�u�@�{�s�߂R�X���̂P�Q��W���Q������̎���P�ʉc�Ɨ��v�@�ɏ�������@�Ɠ����̕��@�ŎZ�肵���Ɨ���Ɗԉ��i�ɖ����Ȃ��Ƃ��āA���Y���O�֘A������Ɨ���Ɗԉ��i�ōs��ꂽ���̂Ƃ݂Ȃ��Čv�Z�����������z����ɁA�@�l�ŁA�������ʖ@�l�ŋy�ђn���@�l�ł̊e�X���������тɉߏ��\�����Z�ł̕��ی��菈���������B �@�������������������������������������������������������������������� �@���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����i���{�@�l�j�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �@�������������������������������������������������������������������� �@�����i�A�o��������`���Y���������y���킹�č��O�֘A����z�@ �@�������������������������������������������@�@�@�@�@�@�@������������ �@���@�@�@�@�@�h�s�s�Ёi�^�C�@�l�j�@�@�@�@�����\�\�\�\�\�\����֘A�҄� �@���������������������������������������������i�E���ލw�������������� �@���ꕔ�����i�E���i�̔̔��@���ԗ��ߋ��@�̔̔� �@�������������������@�@�@���������������������������� �@���@�@�֘A�ҁ@�@���@�@�@����֘A�ҁi���n���[�J�[�j�� �@�������������������@�@�@���������������������������� �@���_�P�i�{���Z����@�͎���P�ʉc�Ɨ��v�@�ɏ�������@�Ɠ����̕��@���j�c�c�ٔ����͂���̂ݔ��f�����B �@���_�Q�i�{���Z����@�͖{�����O�֘A����ɂ��x������ׂ��Ή��̊z���Z�肷�邽�߂̍ł��K�ȕ��@���j �@���_�R�i�{���Ē����́u�V���ɓ���ꂽ���v�ɏƂ炵��Ⴊ����ƔF�߂�ꂽ���߂Ɏ��{���ꂽ���̂��j �@���_�S�i�{���e�X���ʒm���̗��R�̋L�ڂ͗��R�t�L�Ƃ��Č�����Ƃ��낪�Ȃ����j �@���|�@�����F�e �@�u�@���f�g�g�݁v �@�u�[�u�@�U�U���̂S��Q���Q������́u�����̕��@�v�Ƃ́A�I�����Y�̔�������ȊO�̎����O��Ƃ�����̂ł��邩��A�[�u�@�{�s�߂R�X���̂P�Q��W���S������̎���P�ʉc�Ɨ��v�@�ɏ�������@�Ɠ����̕��@�Ƃ́A�I�����Y�̔�������ȊO�̎���ɂ����āA���Y������e�ɓK�����A����P�ʉc�Ɨ��v�@�̍l�������瘨�����Ȃ������I�ȕ��@���������̂Ɖ�����̂������ł���B�v �@�u�퍐�́A����P�ʉc�Ɨ��v�@�ɂ����ẮA���O�֘A�ҋy�є�r�Ώۖ@�l�́u���ꂼ�ꂪ�ʂ����@�\�╉�S���郊�X�N�v�����l���ۂ����d�v������邩��A����炪���ꖔ�͗ގ������r�Ώۖ@�l�̗��v�w�W����ɂ����Z����@�́A����P�ʉc�Ɨ��v�@�i�Q���j�ɏ�������@�Ɠ����̕��@�Ƃ�����|�咣����B �@�������A����P�ʉc�Ɨ��v�@�i�Q���j�́A���O�֘A����ɑΉ��������O�֘A�҂̔�֘A�҂ɑ������̑Ή�����Ɨ���Ɗԉ��i���Z�肷����̂ł��邩��A����P�ʉc�Ɨ��v�@�i�Q���j�ɏ�������@�Ɠ����̕��@�Ƃ����邩�ۂ��̌����ɂ����Ă��A���O�֘A����ɑΉ��������̑��݂��̏ۂ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�܂��A���O�֘A�ҋy�є�r�Ώۖ@�l�́u���ꂼ�ꂪ�ʂ����@�\�╉�S���郊�X�N�v�ɍ��ق��Ȃ����Ƃ́A���҂ɔ�r�\�������邱�Ƃ𗠕t���锻�f�v�f�̈�ɂƂǂ܂�A��L�S�i�S�j�A�̂Ƃ���A����P�ʉc�Ɨ��v�@�i�Q���j�͂����̍��قɂ��e�����r�I�ɂ������̂Ƃ�����B��������ƁA���O�֘A����ɑΉ����������痣��č��O�֘A�҂Ɣ�r�Ώۖ@�l�́u���ꂼ�ꂪ�ʂ����@�\�╉�S���郊�X�N�v����X�ɏd�v�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B �@���������āA�u���ꂼ�ꂪ�ʂ����@�\�╉�S���郊�X�N�v�����ꖔ�͗ގ������r�Ώۖ@�l�̗��v�w�W����ɂ����Z����@�ł���A����P�ʉc�Ɨ��v�@�i�Q���j�ɏ�������@�Ɠ����̕��@�ɊY������|�̔퍐�̎咣�́A�̗p���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�v �@�u�A����P�ʁv �@�u�����@�l�ƍ��O�֘A�҂Ƃ̊Ԃ̕����̎�������݂ɖ��ڂɌ��ѕt���Ă���A�ʂ̎�����Ƃɕ]������̂ł͓K���ɓƗ���Ɗԉ��i���Z�肷�邱�Ƃ��ł��Ȃ��悤�ȏꍇ�ɂ����āA�����̎������̂̍��O�֘A����Ƃ��Ď�舵���āA����ɑΉ����������i�������ēƗ���Ɗԉ��i���Z�肷����@�́A������e�ɓK�����A����P�ʉc�Ɨ��v�@�i�Q���j�̍l�������瘨�����Ȃ������I�ȕ��@�ł���v�B �@�u�{���A�o����A�{�����`���Y����y�і{������͑��݂ɖ��ڂɌ��ѕt���Ă���A�ʂ̎�����Ƃɕ]������̂ł͓K���ɓƗ���Ɗԉ��i���Z�肷�邱�Ƃ��ł��Ȃ��v�B �@�u�����́A����P�ʉc�Ɨ��v�@�i�Q���j�́A�Ĕ̔����i����K���Ȋz���T�����ēƗ���Ɗԉ��i���Z�肷��Ƃ����_�ōĔ̔����i��@�Ɠ����ł��邩��A����P�ʉc�Ɨ��v�@�i�Q���j�ɏ�������@�Ɠ����̕��@�ɂ����Ă��A���Y���Y�̍Ĕ̔�����y�эĔ̔����i�̑��݂��s���ł���Ǝ咣���A�܂��A�w���������Y�ɑ傫�ȉ��H�������ĕʌ̐��i�Ƃ��Ĕ̔��������ɂ́A����P�ʉc�Ɨ��v�@�i�Q���j�ɏ�������@�Ɠ����̕��@�͓K�p�ł��Ȃ��Ǝ咣����B�v �@�u���O�֘A����������̎������\������Ă��Ă��A���Y���O�֘A����ɑΉ��������y�т��̑Ή������݂���A�Ή��W�͖��������c�c����P�ʉc�Ɨ��v�@�ƍĔ̔����i��@�̗ގ����𗝗R�ɁA�{���Z����@������P�ʉc�Ɨ��v�@�i�Q���j�ɏ�������@�Ɠ����̕��@�ł͂Ȃ��Ƃ��錴���̎咣�́A�̗p���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�v �@�u�����́A�{�����O�֘A�҂͎ԗ��ߋ��@�̊����i�̈ꕔ�╔�i�������̊W��Ђɔ̔����Ă���A���̎�����i���܂{�����O�֘A�҂̔��㍂���N�_�Ƃ��ēƗ���Ɗԉ��i���Z�肷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ǝ咣����B�v �@�u����P�ʉc�Ɨ��v�@�i�Q���j�ɏ�������@�Ɠ����̕��@�ɂ����Ă��A�����Ƃ��āA��֘A�҂���Ƃ������łȂ���A���O�֘A����ɑΉ��������ł���Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B �@�����Ƃ��A���O�֘A����ɑΉ��������̂����A����̊W�ɂ���҂���Ƃ��������ꕔ�ɂƂǂ܂�̂ł���A���̑S�̂̎�����i�́A���R�s��ɂ����鉿�i�Ƙ���������̂ł͂Ȃ��B�c�c�{�����O�֘A����ɑΉ��������S�̂̎�����i�́A���R�s��ɂ����鉿�i�Ƙ���������̂ł͂Ȃ��Ƃ�����B �@����āA�{�����O�֘A�҂̔��㍂�Ɍ����̊W��ЂƂ̊Ԃ̎���̑Ή����܂܂�Ă���Ƃ��Ă��A���̂��Ƃ������āA�{���Z����@���A������e�ɓK�����A����P�ʉc�Ɨ��v�@�i�Q���j�̍l�������瘨�����Ȃ������I�ȕ��@�ł͂Ȃ��Ƃ܂ł͂����Ȃ��B�v �@�u�B���v�P�ʁv �@�u���O�֘A����y�є�֘A�w��������������ɑΉ��������̉��i�Ɋ�Â����Y���O�֘A����̓Ɨ������Ҋԉ��i���Z�肷����@�́A���O�֘A�҂̍w������ɂ����Ĕ�֘A�w���������߂銄�����������ꍇ�⍑�O�֘A����ɌW�鎑�Y�Ɣ�֘A�w������ɌW�鎑�Y������ގ��̎��Y�ł���ꍇ�ɂ́A�Q������̎Z�������֘A�w������ɌW�錴�������Z����Ƃ����Z����@�i�{���Z����@�j���̗p�������A������e�ɓK�����A����P�ʉc�Ɨ��v�@�̍l�������瘨�����Ȃ������I�ȕ��@�ł���v�B �@�u�{���Z����@�́A�{�����O�֘A����y�є�֘A�w��������������ɑΉ��������̉��i�Ɋ�Â��{�����O�֘A����̓Ɨ������Ҋԉ��i���Z�肷��Ƃ����_�ɂ����āA������e�ɓK�����A����P�ʉc�Ɨ��v�@�i�Q���j�̍l�������瘨�����Ȃ������I�ȕ��@�ł���Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ����̂́A���̂��Ƃ́A�{���e�X�������y�і{���e���ی��菈���̈�@������N������̂Ƃ͂����Ȃ��B�v �@�u�C��r�\���v �@�u�i�P�j���f��c�c���O�֘A�҂Ɣ�r�Ώۖ@�l�̍��ق��A�@���㍂�c�Ɨ��v���̑���ɏd�v�ȉe����^���Ȃ����A���͇A���Y���ق��^����e������菜�����߂ɑ������x���m�Ȓ������\�ł���A��r�Ώۖ@�l�̔��㍂�c�Ɨ��v������ɁA���O�֘A����̓Ɨ���Ɗԉ��i���Z�肷�邱�Ƃ��ł���v�B �@�u�i�Q�j���Ƃ̓��e�c�c�h�s�s�ЂƖ{����r�Ώۖ@�l�̎��Ƃ̓��e�͗ގ�����v�B �@�u�i�R�j���i�̓����c�c�h�s�s�Ђ������̔�����ԗ��ߋ��@�Ɩ{����r�Ώۖ@�l�������̔����鎩���ԕ��i�Ƃ̍��ق́A�h�s�s�ЂƖ{����r�Ώۖ@�l�̔��㍂�c�Ɨ��v���̑���ɏd�v�ȉe����^���Ȃ��v�B �@�u�i�S�j�����҂̐��s����@�\�c�c�h�s�s�Ђɂ��ԗ��ߋ��@�̐��������Ɩ{����r�Ώۖ@�l�ɂ�鎩���ԕ��i�̐��������Ƃ̍��ق́A�h�s�s�ЂƖ{����r�Ώۖ@�l�̔��㍂�c�Ɨ��v���̑���ɏd�v�ȉe����^���Ȃ��v�B �@�u�i�T�j�s��̏c�c�h�s�s�ЂƖ{����r�Ώۖ@�l�̎s��̏Ɋւ��鍷�ق́A�h�s�s�ЂƖ{����r�Ώۖ@�l�̔��㍂�c�Ɨ��v���̑���ɏd�v�ȉe����^������̂ł����āA���㍂�c�Ɨ��v���̑���ɗ^����e������菜�����߂̑������x���m�Ȓ����́A�\�ł͂Ȃ��v�B �@�u�i�U�j�o�c�̌������c�c�h�s�s�ЂƖ{����r�Ώۖ@�l�Ƃ̊Ԃ̌o�c�̌������Ɋւ��鍷�ق��A�h�s�s�ЂƖ{����r�Ώۖ@�l�̔��㍂�c�Ɨ��v���̑���ɏd�v�ȉe����^����悤�ȍ��قł���Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B�v �@�u�i�V�j�����ړ]�̊W�R���ɂ��āc�c�퍐�́A�����y�тh�s�s�Ђ��{�����O�֘A����ɉʂ����@�\���͂���A�h�s�s�Ђ̔��㍂�c�Ɨ��v���̍����Ɍ������v�����Ă�����x�͍����A�{�����O�֘A����ɂ����Č�������h�s�s�Ђɏ����ړ]�������Ă���W�R���������|�咣����B �@�������A�[�u�@�U�U���̂S��Q�������O�֘A����̓����ҁi�{���ł͌����Ƃh�s�s�Ёj���ʂ����@�\���̊��Ă����߂�̂́A�[�u�@�Ȃ����[�u�@�{�s�߂���߂�Ɨ���Ɗԉ��i���Z�肷�镡���̕��@�̒�����œK���@��I�����邽�߂ł���B�����́A����P�ʉc�Ɨ��v�@�i�Q���j�ɂ����č��O�֘A�҂Ɣ�r�Ώۖ@�l�̔�r�\������������ɓ�����A���O�֘A����̓����҂��ʂ����@�\�������Ă��邱�Ƃ����߂���̂ł͂Ȃ��B�܂��A���O�֘A����ɂ����ē����@�l���獑�O�֘A�҂ɏ����ړ]�������Ă��邩�ۂ��́A�[�u�@�Ȃ����[�u�@�{�s�߂���߂���@����Z�肳�ꂽ�Ɨ���Ɗԉ��i�ƍ��O�֘A����̑Ή����r���Ĕ���������̂ł��邩��A�Ɨ���Ɗԉ��i�̎Z��ɓ�����A�����ړ]�̊W�R�����l�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�v �@�u�i�W�j�܂Ƃ� �@�h�s�s�ЂƖ{����r�Ώۖ@�l�̍��ق̂����A�s��̏Ɋւ��鍷�ق́A���㍂�c�Ɨ��v���̑���ɏd�v�ȉe����^������̂ł����āA���Y���ق��^����e������菜�����߂̑������x���m�Ȓ������ł��Ȃ����̂ł��邩��A�{���Z����@�ɂ����ē��Y���ق̒��������ۂɂ���Ă��邩�ۂ��ɂ��Č�������܂ł��Ȃ��A�h�s�s�ЂƖ{����r�Ώۖ@�l�Ƃ̊Ԃɔ�r�\��������Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B�v |
8.4.2.3.c.�E. DCF�@(�f�B�X�J�E���g�E�L���b�V���E�t���[�@:Discount Cash Flow method)
COLUMN8-1 �ړ]���i�Ő��ƓƗ������ҊԊ[Arm's Length Standard]�@�\�\�ʎ���̉��i�����ƑS�̗̂��v������
���}���u�c�]���v�����@���߂��������̏����v���q�G�ҁw�d�Ŗ@�̔��W�x679��(�L��t�A2010)�G�n�ӗT�ׁu���`���Y��������̈ړ]���i�ېŁ\TNMM(����P�ʉc�Ɨ��v�@)�����̕K�v���v�W�����X�g1248��72�ŎQ�ƁB8.4.2.3.d. �Ɨ���Ɗԉ��i�̎Z����@�̑I���Ɋւ��闧�ؐӔC
�������u�ړ]���i�Ő��ɂ�����Ɨ���Ɗԉ��i�̗��\�\�ŋ߂̍ٔ����f�ނɂ��ā\�\�v�d�Ō���2009�N5����245�ŁA�O�����_�u�d�ŏ؋��@�̔��W�\�\�ؖ��ӔC�Ɋւ�����𒆐S�Ƃ��āv���q�G�ҁw�d�Ŗ@�̔��W�x463��(�L��t�A2010)���Q�ƁB| �A�h�r�V�X�e���Y�����E�����n������19�N12��7������17(�s�E)213����54��8��1652��(���ȏ�341�ł͋��炭��L)�������p�E������������20�N10��30������20(�s�R)20������������A�����F�e�A�m��A�S�I6��71 ���ƍĕґO�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�@���ƍĕҌ� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b �ڋq�\�\�\���{�@�l�\�\�A�����J�@�l�@�b�@�ڋq�\���\�A�C�������h�@�l�\�\�A�����J�@�l �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�@�@�@���{�@�l �@���ٔ��|�@�u�T�i�l�m���{�@�l�n�́A�{���e�Ɩ��ϑ��_��Ɋ�Â��A�@�����̂o�R���i�̔̔����i�y�ѐV�K�̂o�R���i�̏Љ�y�ѐ����̂��߂ɁA�����Ǝ҂�K�₵�Čڋq����U�����A�A�o�R���i�̃}�[�P�e�B���O�̔�p�S���A�}�[�P�e�B���O�������쐬���āA�}�[�P�e�B���O���s���A�B�{�����O�֘A�҂ɂ����{�ł̂o�R���i�̔̔����i�y�ѐ�`�L�����x�����A�C�����ƎҁA�f�B�[���[�y�уG���h���[�U�[�ɑ��o�R���i�̃g���[�j���O�R�[�X����A�D�ڋq�ɑ��T�|�[�g�T�[�r�X�����Ȃǂ̖s�ׂ��s���Ă������ƁA�{���e�Ɩ��ϑ��_���A�T�i�l�̕�V�́A���{�ɂ����鏃���㍂�̂P�D�T�p�[�Z���g���тɍT�i�l�̃T�[�r�X�����ۂɐ��������ڔ�A�Ԑڔ�y�ш�ʊǗ���z���z�̈�ɓ��������z�ƒ�߂��Ă������Ƃ��F�߂���B�m���s�n�@�@�܂��A�T�i�l�͍Ƀ��X�N�S�����A�ڋq����̍�������X�N�����S���Ă��Ȃ����Ƃ͑O���̂Ƃ���ł���B�v �@�u�{�����O�֘A����ɂ����čT�i�l���ʂ����@�\�ƁA�{����r�Ώێ���ɂ����Ė{����r�Ώۖ@�l���ʂ����@�\�Ƃ��r����ɁA��L�F�莖���̂Ƃ���A�{�����O�֘A����́A�{���e�Ɩ��ϑ��_��Ɋ�Â��A�{�����O�֘A�҂ɑ�����̗��s�Ƃ��āA�����Ǝғ��ɑ��Ĕ̔����i���̃T�[�r�X���s�����Ƃ���e�Ƃ�����̂ł����āA�@�I�ɂ��o�ϓI�����ɂ����Ă�����Ɖ����邱�Ƃ��ł���̂ɑ��A�{����r�Ώێ���́A�{����r�Ώۖ@�l���Ώې��i�ł���O���t�B�b�N�\�t�g���d����Ă����̔�����Ƃ����Ĕ̔�����𒆊j�Ƃ��A���̔̔����i�̂��߂Ɍڋq�T�|�[�g�����s�����̂ł����āA�T�i�l�Ɩ{����r�Ώۖ@�l�Ƃ����̉ʂ����@�\�ɂ����Ċʼn߂�����ق����邱�Ƃ͖��炩�ł���B�v �@�u��T�i�l�m���n�́A�{�����O�֘A������d���̔�����łȂ�����ł��邱�Ƃ�O��ɁA�o�R���i�̔̔��ɂ����čT�i�l�̉ʂ����Ă���@�\�y�ѕ��S���Ă��郊�X�N���A�̔��������̂�Ĕ̔�����ɂ�����Ĕ̔��҂̋@�\�y�у��X�N�Ɨގ����Ă���̂ŁA�{���Z����@�́A�Ĕ̔����i��@�ɏ�������@�Ɠ����̕��@�ɓ�����Ǝ咣���A�T�i�l�ƈقȂ�Ĕ̔��ҌŗL�̋@�\�́A��L�̔����i�̋@�\���珃���ȏ��i�̎��y�єz����z�A�d�����z�̎x���y�є̔�����̎�̓��̎���������Ƃɂ������A���̂悤�Ȏ���������Ƃ�ʂ��ď��i�̎�����i�┄�㑍���v���ɉe������悤�ȑ���ȗ��v���������邱�Ƃ͑z�肵��Ƃ��A���������āA�T�i�l�̗��v�����Z�肷��ɂ́A���m�ƃT�[�r�X��̔�����{����r�Ώێ���̗��v�����烂�m��̔��������̗��v�����T������K�v�͂Ȃ��Ƃ��Ă���B �@�@�������Ȃ���A�Ĕ̔��Ǝ҂��s���̔����i���̖̓��e���T�i�l�̒���̓��e�Ɨގ����Ă���Ƃ��Ă��A���悻��ʓI�ɉ��i�ݒ�ɂ�����邻��ȊO�̔�T�i�l�咣�̏�L�v�������P�Ȃ鎖��������ƂƂ��ĂقƂ�Ǎl������K�v���Ȃ����̂Ƃ͂�����̂ł����āi�{���ɂ����āA�l������K�v�����Ȃ����Ƃ𗠕t����ɑ�����̓I�ȏ؋��͂Ȃ��B�j�A�{������ɂ����čT�i�l�̉ʂ����@�\�Ɩ{����r�Ώۖ@�l�̉ʂ����@�\�Ƃ̊Ԃɂ͎̏ۂł��Ȃ����ق�������̂Ƃ��킴��Ȃ��B �@�@�܂��A��L�̂Ƃ����T�i�l�̓O���t�B�b�N�\�t�g�̔̔����s���Ă��Ȃ�����A���ׂ��萔���ɂ̓O���t�B�b�N�\�t�g�̔̔����v���܂܂�Ȃ����ƂɂȂ�̂ɑ��A�{����r�Ώۖ@�l�̑����㗘�v���ɂ̓O���t�B�b�N�\�t�g�̔̔����v���܂܂�����ƂɂȂ�B���Ȃ킿�A�T�i�l�͏�L�̖Ɍ����������v���擾���ׂ����ƂɂȂ�̂ɑ��A�{����r�Ώۖ@�l�͍Ĕ̔�����y�є̔����i���̖Ɍ����������v�i���̔��㑍���v�����A�{���Z����@�ɂ����ėp������u�ʏ�̗��v���v�i�d�œ��ʑ[�u�@�U�U���̂S��Q����P�����A������Q�����A�d�œ��ʑ[�u�@�{�s�߂R�X���̂P�Q��U���j�ł���B�j���擾���邱�ƂɂȂ���̂Ɖ������̂ł���A�{����r�Ώۖ@�l�̍s���̓��e���{�����O�֘A����ɂ����čT�i�l���s�����e�Ɨގ����Ă���Ƃ��Ă��A�{����r�Ώۖ@�l�́A���i�̍Ĕ̔��i�����E�����j���s���Ă���̂ł���A���̑����v�ɂ͐��i�̍Ĕ̔��̗��v���܂܂�邱�ƂɂȂ�B����ɑ��āA�{�����O�֘A�҂Ɠ���̊W�̂Ȃ������Ǝ҂��o�R���i���d����āA�̔����v�čĔ̔����A����ƕ��s���čT�i�l�����Z���[�i�����Ǝҁj�ɑ��Ĕ̔����i�����s�����Ƃɂ��{�����O�֘A�҂ɖ���Ă��邱�ƂɂȂ�ꍇ�ɂ����Ă��A�����Ǝ҂͍Ĕ̔����v�Ă���̂ł���A����A�T�i�l�ɂ͐��i���Ĕ̔����邱�Ƃɂ�闘�v�͂Ȃ����ƂɂȂ�̂ł��邩��A�{���Z����@�̂悤�ɁA�䂪���ɂ�����o�R���i�̔��㍂�ɖ{����r�Ώۖ@�l�̔��㑍���v�����悶�ē����闘�v�z�̒��ɂ́A�����Ǝ҂��{�����O�֘A�҂���o�R���i���d����ď����X���ɍĔ̔����Ď擾����̔����v���܂܂�Ă���W�R���������Ƃ����ׂ��ł���B�v �@�u�{�����O�֘A����ɂ����čT�i�l�����S���郊�X�N�ƁA�{����r�Ώێ���ɂ����Ė{����r�Ώۖ@�l�����S���郊�X�N�Ƃ��r�����ɁA�T�i�l�́A�{���e�Ɩ��ϑ��_���A�{�����O�֘A�҂���A���{�ɂ����鏃���㍂�̂P�D�T�p�[�Z���g���тɍT�i�l�̃T�[�r�X�����ۂɐ��������ڔ�A�Ԑڔ�y�ш�ʊǗ���z���z�̈�ɓ��������z�̕�V������̂Ƃ���A��V�z���K�v�o��̊z�����荞�ރ��X�N�S���Ă��Ȃ��̂ɑ��A�{����r�Ώۖ@�l�́A���̔��㍂�����v����_������Η��v���擾���邪�A�����Α�������̂ł����āA�{����r�Ώێ���͂��̃��X�N��z��i��܁j������ōs���Ă���̂ł���A�T�i�l�Ɩ{����r�Ώۖ@�l�Ƃ͂��̕��S���郊�X�N�̗L���ɂ����Ă���{�I�ȍ��ق�����A����͎̔��`�����̂��Ă����Ƃ��Ă��ς�肪�Ȃ��B�{����r�Ώێ���ɂ����āA���̕��S���X�N���̏ۂł�����y���ł��������Ƃɂ��ẮA�����F�߂�ɑ����I�m�ȏ؋��͂Ȃ��B�v �@���Ă̓A�h�r(�A�����J�n�����Њ�ƃO���[�v)�̓��{�@�l�����{�̌ڋq����ɔ̔��@�\��S���Ă������A���ƍĕ�(business reorganization)��A�̔��@�\���A�C�������h�@�l�Ɉړ]���A���{�@�l�͕⍲�I�Ȗ�����S�������ƂȂ����B���ƍĕҌ�A���{�@�l�̒S���@�\�����������߁A���{�@�l�ɋA�����鏊�����������A�Ƃ���[�Ŏґ��̎咣�����ق͔F�߂��B �@����͓��{�����łȂ��n�d�b�c���������ʂ̉ۑ�ł���A���ƍĕ҂ɂǂ��Ώ����Ă������A�Ƃ����`�ŋc�_����Ă���B �@�A�����J�ʼnېŒ����s�i��Ƃ���Xilinx v. Commissioner, 125 T.C. 37 (2005); reversed by 567 F.3d 482 (9th Cir., May 27, 2009), withdrawn by 592 F.3d 1017 (9th Cir., January 13, 2010); affirmed by 598 F.3d 1191 (9th Cir., March 22, 2010)�y��Veritas Software Corp. v. Commissioner, 133 T.C. No. 14 (Dec. 10, 2009)���m���Ă���B���g�M�ׁu�č��̃R�X�g�E�V�F�A�����O�_��ɌW��ړ]���i�i�ׂւ̍l�@�����U�C�����N�X���ċy�уx���^�X���āv�d�Ō���2010�N12��266-329�ŁG�_�R�O�s�u�U�C�����N�X�����č��A�M��9����T�i�ٔ��������v���������w�ړ]���i�Ő��̃t�����e�B�A�x308�ŁG���\��u���F���^�X�����č��d�ōٔ��������v���������w�ړ]���i�Ő��̃t�����e�B�A�x341�œ��Q�ƁB�ގ��_�_(�K��������)�ʼnېŒ������i����Ƃ���Altera Corporation and Subsidiaries v. Commissioner, 145 T.C. 91 (2015.7.27); reversed by 926 F.3d 1061 (9th Cir., 2019.6.7); rehearing denied by 941 F.3d 1200 (9th Cir., 2019.11.12); certiorari denied on (Supreme Court, 2020.6.22)������B �@�܂��A�ړ]���i�ł͂Ȃ����A�K�@�ȏ����ړ]�̗�Ƃ��ĕی��������O�֘A��ƂɎx�����Ƃ�����@������B�t�@�C�i�C�g�����E�����n������20�N11��27������2037��22��(���\��E�W�����X�g1400��173�ŁA���쒉�P�E���ېŖ�2010�N11����37��)�E������������22�N5��27������2115��35��(�m��)(��ȏ͔@�E�����2133��162��)�B |
�G�N�A�h���o�i�i�����E������������25�N3��28��(��8.4.2.3.c.�A.2.)
8.4.2.3.e. �]������Ȗ��`���Y����ɌW�鉿�i�����[�u(HTVI: Hard-To-Value Intangibles)
COLUMN8-2 �ړ]���i�Ő��ƓƗ������ҊԊ�A�\�\��b�T�O�̍čl�̕K�v��
���\��u�ړ]���i�Ő��̖@����̊�b�ɂ��āv���q�G=�������ҁw�d�Ŗ@�Ɩ��@�x311��(�L��t�A2018)�A��ȏ͔@�uBEPS: value creation��arm's length�Ƃ̈ٓ��A����value creation��̓�_�v�ő�W���[�i��27��35��(2017)8.4.2.4. �ړ]���i�Ő��K�p�̌���
8.4.2.4.a. �����ʂɂ����鏈��
8.4.2.4.b. �Ή��I����
�@�`���ŗ�20���@�������i�H�@�a���ŗ�40���d��200���o�Ё��������ԁ����r�Ё�����҂�1000
������p400�@�@�@�@�@�@�̔���p100
�@�@�@�@�@��
�@�@�@�@�@���@�@�������i800
�@�@�@�@�@�����������ԁ�����O�ҁ�����҂�1000
�@�o�E�r�ЊԂŁA�����Ԃ̉������i��750�ł���Ƃ��Ď�����Ȃ��ꂽ�Ƃ���B���̂܂܂Ȃ�A�o�Ђ̏�����150�A�r�Ђ̏�����150�ł��邱�ƂɂȂ�B
�@�����ŁA�a���͉������i���s���ɒ݂�グ���Ă���Ƃ��A�ړ]���i�Ő���K�p���ēƗ������Ҋԉ��i��710�ł���ׂ��ł���Ƃ���B�����āA�r�Ђ̏�����150�ł͂Ȃ�190�ł���ׂ��ł���A�Ƃ��čX������������B
�@�a���łr�Ђ�190�̏������A������Ƃ����������Ȃ��ꂽ�̂ŁA�`���ɂ����Ă��o�Ђւ̉ېłɍۂ��ĉ������i��710�ł������Ƃ��A�o�Ђ̏�����150�ł͂Ȃ�110�ł���ɉ߂��Ȃ��A�ƒ������Ă����Ȃ���A���z��40�̏����ɑ��ē�d�ېł��������Ă��܂��B
�@�`���Ƃa���ƂŁA�Z�肳���Ɨ������Ҋԉ��i���قȂ邱�Ƃ͂��肤��B�a���̉ېœ��ǂ�����ɓƗ������Ҋԉ��i��710�ł���ƍl��������Ƃ����āA�`���̉ېœ��ǂ��Ɨ������Ҋԉ��i��710�ł���ƍl�������˂Ȃ�Ȃ��A�Ƃ������̂ł͂Ȃ��B�`���̉ېœ��ǂ��^���ɎZ�肵�����ʓƗ������Ҋԉ��i��750�̂܂܂ł���ƍl����Ȃ�A�o�Ђ̏�����110�ł͂Ȃ�150�̂܂܂ł���A�Ƃ���F��Ɋ�Â����ېł��`���ɂ����鐳�����ېłł���B�܂��A�`���œƗ������Ҋԉ��i��750�̂܂܂ł���ƍl����ꂽ����Ƃ����āA�a���ɂ����ēƗ������Ҋԉ��i��710�ł���Ƃ��ĂȂ����X�������������Ɉ�@�ƂȂ���̂ł��Ȃ��B���ێЉ�ł͐�����������2�ȏ㑶�݂���A�Ƃ������Ƃ���������B
�@��������d�ېł���u����͔̂[�Ŏ҂ɂƂ��č��ł���B�[�Ŏ҂͂������킵�����Ƃ����ĉېł�Ƃ�悤�Ƃ��Ă���Ƃ͌���Ȃ��B�`���E�a���̏����ŗ��������ŁA�ǂ���ɂ��Ԏ����Ȃ��ꍇ�A�[�Ŏ҂Ƃ��Ă͂ǂ���ɔ[�ł��Ă������ł���B��d�ېł��������邱�Ƃ����邾���ł���B���đd�ŏ��9��2�����A�Ή��I�������s���ׂ��|���K�肷�邱�Ƃ�����B�iCf.�d�ŏ����{����@7��1���j
�@�����ŁA�K�v������Η������������铖���icompetitive authority�j�����c���āA�Ɨ������Ҋԉ��i�𗼍��ň�v������悤�ɂ��邱�Ƃ�����B��25�������c(MAP: mutual agreement procedure��8.5.4.�j�@���X��25��5������(arbitration)���B(cf.���Ē��َ葱���{�挈��)
| ������������8�N3��28������1574��57�ŕS�I4��71�c�c�����@�ɑΉ��I�����̋K�肪�����Ă������ł����Ă��A���đd�ŏ��Ɋ�Â��Ή��I�����̂��߂́i�g���^�́j�@�l�Ŋz���z�X�������i�n���ł��ҕt���܂ށj�͓K�@�ł���A�i�_�ސ쌧���Ԏs�ɂ��āj�n���ŏ���`�Ɉᔽ���邱�Ƃ��Ȃ��B |
8.4.2.5. ���O�m�F�葱(APA)(advance pricing arrangement)(MAP: mutual agreement procedure:�����c)
8.4.2.6. �ړ]���i�������Ɛ���ېœ�
8.4.2.6.a. ���_
8.4.2.6.b. ���ƊT������(�}�X�^�[�t�@�C��)
8.4.2.6.c. ���[�J���t�@�C���i�Ɨ���Ɗԉ��i���Z�肷�邽�߂ɕK�v�ƔF�߂��鏑��)�Ɛ���ېł���ѓ��ƎҒ���
| �ړ]���i�Ő��̓K�p�ɂ����萄��ې�(�d���@66����4��7��)���F�߂�ꂽ����Ƃ����G�X�R�����E�����n������23�N12��1������19(�s�E)149����60��1��94�Ő������p�S�I6��73(�{�ˋv�E�W�����X�g1442��8�ŁA��{�j���E�W�����X�g1462��124�ŁA���J�N�G�u�ړ]���i�Ő��Ɋ֘A���鐄��ېŋK��ɂ��Ă̈�l�@�v�ő�W���[�i��24��93-144��)�E������������25�N3��14������24(�s�R)19����60��1��149�ōT�i���p�B |
8.4.2.6.d. ���ʕ�(CbC���|�[�g)(Country-by-Country Report)
COLUMN8-3 ���ʕ�(CbC���|�[�g)�����̃C���p�N�g�\�\�Ŗ��K�o�i���X�̃p���_�C���V�t�g�̉\��
8.4.2.7. ���O�֘A�҂ɑ�����ې�
8.4.2.8. �O���@�l�̓�������ɌW��ړ]���i�ې�
8.4.3. �^�b�N�X�E�w�C�u�����Ő�(�O���q��Ѝ��Z�Ő��ECFC�Ő�: controlled foreign corporation/company)
8.4.3.1. �^�b�N�X�E�w�C�u�����Ő�(�O���q��Ѝ��Z�Ő��ECFC�Ő�)�Ƃ�
�^�b�N�X�w�C����(tax haven)�F�����ɑ���d�ŕ��S��0�����͋ɒ[�ɒႢ���E�n��B| �P�C�}���A�o�[�~���[�_�Ȃǂ��L���B�i�ŋ��V��tax heaven�ł͂Ȃ��̂Œ��Ӂj |
�@��@�����@�l�̊O���W��ЂɌW�鎟�Ɍf���銄���̂����ꂩ���S���̏\�ȏ��ł���ꍇ�ɂ����铖�Y�����@�l�m�C���n���n
�@��@�O���W��ЂƂ̊ԂɎ����x�z�W����������@�l�m�O�`�l�����n
�Q�@���̏��ɂ����āA���̊e���Ɍf����p��̈Ӌ`�́A���Y�e���ɒ�߂�Ƃ���ɂ��B
�@��@�O���W����@���Ɍf����O���@�l�������B
�@�@�C�@���Z�ҋy�ѓ����@�l�c�c�̊O���@�l�ɌW�鎟�Ɍf���銄���̂����ꂩ���S���̌\�����ꍇ�ɂ����铖�Y�O���@�l�m�i�P�j�i�Q�j�i�R�j���n
�@�@���@���Z�Җ��͓����@�l�Ƃ̊ԂɎ����x�z�W������O���@�l�m�n���n
�@��@����O���W����m�v����Ƀy�[�p�[�E�J���p�j�[�Bcash box corporation�n�@���Ɍf����O���W��Ђ������B
�@�@�C�@���̂�����ɂ��Y�����Ȃ��O���W���
�@�@�@�i�P�j�@���̎傽�鎖�Ƃ��s���ɕK�v�ƔF�߂��鎖�����A�X�܁A�H�ꂻ�̑��̌Œ�{�݂�L���Ă���O���W��Ёc�c
�@�@�@�i�Q�j�@���̖{�X���͎傽�鎖�����̏��݂��鍑���͒n���i�c�c�u�{�X���ݒn���v�Ƃ����B�j�ɂ����Ă��̎��Ƃ̊Ǘ��A�x�z�y�щ^�c������s�Ă���O���W��Ёc�c
�@�@�@�i�R�j�@�O���q��Ёc�c�̊������ۗ̕L���傽�鎖�ƂƂ���O���W��ЂŁA���̎������z�̂����ɐ�߂铖�Y�������ɌW���]���̔z�����̊z�̊������������������Ƃ��̑��̐��߂Œ�߂�v���ɊY���������
�@�@�@�i�S�j�@����q����i�O���e���Ɍf��������@�l�ɌW�鑼�̊O���W��ЂŁA�����ΏۊO���W��ЂɊY��������̂��̑��̐��߂Œ�߂���̂������B�j�̊������ۗ̕L���傽�鎖�ƂƂ���O���W��ЂŁA���̖{�X���ݒn����������Ǘ��x�z��Ёc�c�ɂ�Ă��̎��Ƃ̊Ǘ��A�x�z�y�щ^�c���s���Ă��邱�ƁA���Y�Ǘ��x�z��Ђ����̖{�X���ݒn���ōs�����Ƃ̐��s�㌇�����Ƃ̂ł��Ȃ��@�\���ʂ����Ă��邱�ƁA���̎������z�̂����ɐ�߂铖�Y�������ɌW���]���̔z�����̊z�y�ѓ��Y�������̏��n�ɌW��Ή��̊z�̊������������������Ƃ��̑��̐��߂Œ�߂�v���ɊY���������
�@�@�@�i�T�j�@���̖{�X���ݒn���ɂ���s���Y�ۗ̕L�A���̖{�X���ݒn���ɂ�����Ζ����̑��̓V�R�����̒T�z�A�J���Ⴕ���͍̎斔�͂��̖{�X���ݒn���̎Љ�{�̐����Ɋւ��鎖�Ƃ̐��s�㌇�����Ƃ̂ł��Ȃ��@�\���ʂ����Ă���O���W��ЂŁA���̖{�X���ݒn����������Ǘ��x�z��Ђɂ�Ă��̎��Ƃ̊Ǘ��A�x�z�y�щ^�c���s���Ă��邱�Ƃ��̑��̐��߂Œ�߂�v���ɊY��������́m���n���n
�@�@�j�@�d�łɊւ�����̌����Ɋւ��鍑�ۓI�Ȏ�g�ւ̋��͂��������s�\���ȍ����͒n��Ƃ��č�����b���w�肷�鍑���͒n��ɖ{�X���͎傽�鎖������L����O���W���
�@�O�@�ΏۊO���W����@���Ɍf����v���̂����ꂩ�ɊY�����Ȃ��O���W��Ёc�c�������B
�@�@�C�@�������Ⴕ���͍��ۗ̕L�A�H�Ə��L�����̑��̋Z�p�Ɋւ��錠���A���ʂ̋Z�p�ɂ�鐶�Y�����Ⴕ���͂����ɏ�������́c�c�Ⴕ���͒��쌠�c�c�̒��͑D���Ⴕ���͍q��@�̑ݕt�����傽�鎖�ƂƂ�������i���Ɍf������̂������B�j�łȂ����ƁB�m���Ɗ�˃z���R�����I�n��8.4.3.5.b.1.�n
�@�@�@�i�P�j�@�������ۗ̕L���傽�鎖�ƂƂ���O���W��Ђ̂������Y�O���W��Ђ����̖@�l�̎��Ɗ����̑����I�ȊǗ��y�ђ�����ʂ��Ă��̎��v���̌���Ɏ�����Ɩ��Ƃ��Đ��߂Œ�߂���́i�c�c�u�����Ɩ��v�m�˃f���\�[8.4.3.5.b.1.�n�Ƃ����B�j���s���ꍇ�ɂ����铖�Y���̖@�l�Ƃ��Đ��߂Œ�߂���̂̊������ۗ̕L���s�����̂Ƃ��Đ��߂Œ�߂���́m�i�Q�j�i�R�j���n
�@�@���@���̖{�X���ݒn���ɂ����Ă��̎傽�鎖���i�C�i�P�j�Ɍf����O���W��Ђɂ��Ă͓����Ɩ��Ɓc�c����B�n�ɂ����ē����B�j���s���ɕK�v�ƔF�߂��鎖�����A�X�܁A�H�ꂻ�̑��̌Œ�{�݂�L���Ă��邱�Ɓc�c���тɂ��̖{�X���ݒn���ɂ����Ă��̎��Ƃ̊Ǘ��A�x�z�y�щ^�c������s�Ă��邱�Ɓc�c�̂�����ɂ��Y�����邱�ƁB�m���̊�˃����^���E�I�t�B�X�E�X�y�[�Xln�A�Ǘ��x�z��ˈ���؍�8.4.3.5.b.3.�n
�@�@�n�@�e���ƔN�x�ɂ����Ă��̍s���傽�鎖�Ƃ����Ɍf���鎖�Ƃ̂�����ɊY�����邩�ɉ������ꂼ�ꎟ�ɒ�߂�ꍇ�ɊY�����邱�ƁB
�@�@�@�i�P�j�@�����ƁA��s�ƁA�M���ƁA���Z���i����ƁA�ی��ƁA���^�ƁA�q��^���Ɩ��͕��i���Ɓi�q��@�̑ݕt�����傽�鎖�ƂƂ�����̂Ɍ���B�j�@���̎��Ƃ���Ƃ��ē��Y�O���W��ЂɌW���m�֘A�ҁn�ȊO�̎҂Ƃ̊Ԃōs�Ă���ꍇ�Ƃ��Đ��߂Œ�߂�ꍇ�m��֘A�Ҋ�n
�@�@�@�i�Q�j�@�i�P�j�Ɍf���鎖�ƈȊO�̎��Ɓ@���̎��Ƃ���Ƃ��Ă����{�X���ݒn���c�c�ɂ����čs�Ă���ꍇ�Ƃ��Đ��߂Œ�߂�ꍇ�m���ݒn����n
�@�l�@�K�p�Ώۋ��z�@����O���W��Ж��͑ΏۊO���W��Ђ̊e���ƔN�x�̌��Z�Ɋ�Â������̋��z�ɂ��@�l�Ŗ@�y�т��̖@���ɂ��e���ƔN�x�̏����̋��z�̌v�Z�ɏ�������̂Ƃ��Đ��߂Œ�߂��ɂ��v�Z�������z�i�c�c�u��������z�v�Ƃ����B�j����b�Ƃ��āA���߂Œ�߂�Ƃ���ɂ��A���Y�e���ƔN�x�J�n�̓��O���N�ȓ��ɊJ�n�����e���ƔN�x�ɂ����Đ����������̋��z�m�ˑo�P�D�Dka�n�y�ѓ��Y��������z�ɌW��Ŋz�Ɋւ��钲�������������z�������B
�@�܁@�����x�z�W�@���Z�Җ��͓����@�l���O���@�l�̎c�]���Y�̂����ނˑS���𐿋����錠����L���Ă���ꍇ�ɂ����铖�Y���Z�Җ��͓����@�l�Ɠ��Y�O���@�l�Ƃ̊Ԃ̊W���̑��̐��߂Œ�߂�W�������B
�@�Z�@�����ΏۊO���W��Ё@��O���C����n�܂łɌf����v���̑S�ĂɊY������O���W��Ёi����O���W��ЂɊY��������̂������B�j�������B�m�����A3���ȉ����n
1992�N�����O�F�w�萧�x�i�u���b�N�E���X�g�����j�c�O���V��㎸��ɓ�����Ƃ̎w�E���B
1992�N������F25���ȉ���20���ȉ���20%�����i�g���K�[�ŗ��Ƃ����j(�y�[�p�[�E�J���p�j�[�ɂ��Ă�30��)md
�O���W��ЁF��������50��������{�̋��Z�ҁE�����@�l�S���Œ��ځE�ԐڂɗL���Ă������
�����@�l���O���W��Ђ�10���ȏ��ځE�ԐڂɗL���Ă���ꍇ�A���������ɉ��������Z�ې�������������B
100���q��Ђɂ��Ė��ƂȂ邱�Ƃ��������A100�������̏ꍇ�A�@�l�Ŗ@11���i���������҉ېŁj�i����12���Ɠ��l��4.5.1.1.�j�ƓK�p���ʂ��قȂ�B
�@�l�Ŗ@11���̏ꍇ�c�c�O���q��Ђ���r�Ђ�����̖��`�l�̗p�ł��邪�����e��Ђ���o�Ђ������I�ɋ��Ă���ꍇ�A�o�ЂɋA�����鏊���Ƃ����B���R�A���Y����̑S�z�����������ɊW�Ȃ��o�ЂɋA������B
�d��66����6�̏ꍇ�c�c�r�Ђɐ^�Ɏ��@��A�����鏊���ł����Ă��o�Ђ̎��������ɉ����Ăo�Ђ̉v���ɎZ�������B(�d��66����6�͂r�ЂɋA������Ƃ��鎄�@��̖@���W��۔F���悤�Ƃ�����̂ł͂Ȃ�)
������Ƃ̐^�����ȊC�O�i�o��{���ېł��W�Q���邱�ƂɂȂ�͍̂T���悤�Ƃ���K��B���O���ł͈�ʂɁApassive income�i�I�����j�݂̂ɉېł��Aactive income�i�\���I�����j�͓K�p���O�Ƃ���Ɛ��������B�ēƓ��ł͎���P��(income approach�܂���transaction approach)��passive/active������s���̂ɑ��A���{�@�͌����Ƃ��ĊO���@�l�P��(entity approach)��passive/active�̔�����s�Ȃ��Ă���(��8.4.3.6.)�B��������22������income approach����������(��8.4.3.7.)�B
20��������ɂ��āB
| ������Ѓ{�f�B���[�N�z�[���f�B���O�X�����E�����n���ߘa5�N1��27���ߘa2(�s�E)211�����p(�x���F2024�N9��5���d�Ŕ��ጤ�����) �@�����@���{�@�l�w��(����)�͐j�A���A����܁A�}�b�T�[�W�A�w���y�я_�������̎��Ó����c�ށB�w�Ђ͕���29�N3����(�{�����ƔN�x)�I�����Ɍ����O���[�v�V�Ђ̑S������ۗL���Ă���B�}���[�V�A�A�M�߃��u�A���̂a�n�c�x�@�v�n�q�j�@�h�m�r�t�q�`�m�b�d�@�b�n�D�C�k�s�c�i�`�Ёj�͕ی��Ƃ��c�ށB�`�Ђ̑S�������w�Ђ͕���28�N3�����ɕۗL���Ă����B�e���͂w�Б�\�ҁA�w�Ў�����A�`�Ў�����ł���B �@�w�Ђƌ����O���[�v�T�Ђ͕���25�N3��28������29���t�Ō���C��Еی�������Ёi�u�Ёj�Ƃ̊ԂŁA��ی��҂��w�Ћy�ь����O���[�v�T�Ђ̏]�ƈ��Ƃ��鏝�Q�ی��_�����������B�u�Ђ́A�����Q�ی��_����b�`�h�r�r�d�@�b�d�m�s�q�`�k�d�@�c�d�@�q�d�`�r�r�t�q�`�m�b�d�i�r�Ёj�ɏo�āi�ĕی��ɏo�����Ɓj���A�r�Ђ́A�������āi�ĕی������邱�Ɓj������ł`�Ђɏo�Ă��i�āX�ی��_��j�A�`�Ђ́A���Y�āX�ی��_�����Ă����B �@�w�Ђƌ����O���[�v�U�Ђ͕���26�N3��31���t�łu�ЂƂ̊ԂŔ�ی��҂��w�Ћy�ь����O���[�v�U�Ђ̏]�ƈ��Ƃ��鏝�Q�ی��_�����������B�u�Ђ́A�����Q�ی��_����r�Ђɏo�Ă��A�r�Ђ́A�������Ă�����ł`�Ђɏo�Ă��i�āX�ی��_��j�A�`�Ђ́A���Y�āX�ی��_�����Ă����B �@�w�Ђƌ����O���[�v�V�Ђ͕���27�N3��31���t�łu�ЂƂ̊ԂŁA��ی��҂��w�Ћy�ь����O���[�v�V�Ђ̏]�ƈ��Ƃ��鏝�Q�ی��_��i�ȉ��u�{�����Q�ی��_��v�Ƃ����B�j����������B�����O���[�v�V�Ђ̂��������O���[�v�R�Ђ́A�����t���ŁA�u�ЂƂ̊ԂŁA��ی��҂������O���[�v�R�Ђ̃Z���s�X�g�Ƃ��锅���ӔC�ی��_��i��ی��҂̃Z���s�X�g�̋Ɩ����s�ɋN�����đ�O�҂̐g�̂ɑ��Q��^���đ�O�҂����S�����ꍇ�ɔ�ی��҂������ׂ��@����̑��Q�����ӔC��⏞������́B�ȉ��u�{�������ӔC�ی��_��v�Ƃ����B�j����������B�u�Ђ́A�{�����Q�ی��_��y�і{�������ӔC�ی��_����r�Ђɂ��ꂼ��o�Ă��A�r�Ђ́A��������Ă�����ł`�Ђɂ��ꂼ��o�Ă��i�āX�ی��_��j�A�`�Ђ́A�����t���ŁA���Y�āX�ی��_����r�Ђ��炻�ꂼ���Ă����i�ȉ��A�`�Ђ��r�Ђ����Ă��������̍āX�ی��_��̂����A�{�������ӔC�ی��_��ɌW����̂��u�{�������ӔC�ی��āX�ی��_��v�Ƃ����B�j�B �@�`�Ђ́A����30�N2��2���A�{�������v�Z���i�`�Е���28�N3�����j�Ŕ�p�̊z�Ƃ��Čo�������{�������ӔC�ی��������ϗ��z���38���ăh����0�ăh���Ƃ��A���Q�ی��ɌW��ی��������̐ϗ��z��{�������v�Z���Ŕ�p�Ƃ��Čo�������z�Ɩ{�������ӔC�ی��������ϗ��z�Ƃ̍��v�z�ł����83���ăh����120���ăh���Ƃ�������i�{�������j�������B�{������������v�Z���ɂ��āA�i�x�������̑����j�Ƃ̋L�ڂ��i���������X�N�������̑����j�ƍĒ����i�{���Ē����j������ŁA����31�N4��23���A�{���Ē���������v�Z���ɂ��Ă`�Ђ̎������y�ъ��呍��ɂ�鏳�F���c���s���A�{���Ē���������v�Z�������u�A�����Z���ɒ�o�����B �@�w�Ђ�����29�N6��29���ɖL���Ŗ������ɒ�o�����{�����ƔN�x�̖@�l�ł̊m��\�����ɂ����āA�`�Ђ͂b�e�b�Ő��K�p���O�v�������|���L�ڂ����d�œ��ʑ[�u�@66����6��7���̏��ʁi�K�p���O�L�ڏ��ʁj���Y�t����Ă��Ȃ������B�L���Ŗ������́A�`�Е���28�N3�����ɂ�����d�œ��ʑ[�u�@�{�s��39����14��1��2���̐ŗ���20�������ł��邩��`�Ђ͓���O���q��Г��ɊY������Ƃ��A�`�Ђ̑d�œ��ʑ[�u�@66����6��1���̉ېőΏۋ��z1��3603��3131�~���w�Ђm�v���ɎZ������X�������������B �@���_�@�`�Ђ̐ŗ���20�������ł������O���q��Г��ɊY�����邩�ۂ��B �@�`�Ђ���p�Ƃ��Čo�������{�������ӔC�ی��������ϗ��z���u�ُ�댯�������ɗނ��鏀�����̊z�v�i�d�œ��ʑ[�u�@�{�s��39����14��2��1���j�j�ɊY�����邩�ۂ��B �@���|�@�u�L���v�e�B�u[captive]�Ƃ́A����̊�Ɩ��͊�ƃO���[�v�̃��X�N����I�Ɉ��邽�߂ɐݗ������ی��Ɩ����̎q��Ђ������B�L���v�e�B�u�̐ݗ��́A�C�O�̃L���v�e�B�u�@���x�������Ă��鍑��n��ōs����̂���ʓI�ł���B���{���܂ޑ����̍��ł́A�@�߂ɂ���Ƃ͎����̕ی���Ђŕی���t�ۂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ���Ă��邽�߁A�ʏ�A���n�̌���ی���Ђ�ʂ��ăL���v�e�B�u�ւ̍ĕی����s����B�L���v�e�B�u�́A�ی��ɂ�����ŏI�I�ȑ������S�̎�̂��A�ی���Ђł͂Ȃ����Ў��g�Ƃ��邱�Ƃ���������d�g�݂ł���B �@�L���v�e�B�u�̎�ނɂ́A���ЃL���v�e�B�v�i���Ђ̊��S�q��ЂƂ��Đݗ�����X�L�[���j�A�����^�L���v�e�B�u�i��O�҂��ݗ������L���v�e�B�u���ؗp����X�L�[���j��������B���̂������ЃL���v�e�B�u�́A���Ђ̊��S�q��Ђł��邱�Ƃ���A�o�c�̎��R�x�������A���{�@�l�ւ̎����җ�����r�I�e�Ղł��邱�ƁA���{�@�l�ւ̔z�����s���Ă����{�̐Ŗ@��͊C�O�q��Ђ���̔z���Ƃ��ĂX�T������ېłƂȂ�Ƃ��������b�g���������ŁA�y�ېō��Ɏ��ЃL���v�e�B�u��ݗ������ꍇ�A���{�̊O���q��Ѝ��Z�Ő��ɒ�G���A���ЃL���v�e�B�u�̏��������{�@�l�̉v���Ƃ݂Ȃ���鍇�Z�Ő��̑ΏۂƂ���Ă��܂����X�N�����铙�̃f�����b�g������B�v �@�u�`�Ђ́A�`��27�N3�����܂ł́A���Q�ی��_��ɌW��āX�ی��_��݂̂���Ă��Ă����Ƃ���A�`��28�N3��������́A���Q�ی��_��ɌW��āX�ی��_��ɉ����āA�{�������ӔC�ی��āX�ی��_��̎�Ă��J�n�������Ƃ���A�����ӔC�ی��ɌW��ی����̂����������ꍇ�ɂ��ی������x�������X�N�����ƂɂȂ����B�����āA�ی����̂����������ꍇ�̕ی����̎x���ɔ�����Ƃ����ی��������̐������ɏƂ炷�ƁA�`�ЂƂ��ẮA�{�������ӔC�ی��āX�ی��_��̎�Ă��J�n�������ƂŁA�����ӔC�ی���ΏۂƂ��ĕی��������̐ϗ��Ă����邩����������K�v��������̂ł���A���ہA�ؐl�Q���A�`�Ђ��{�������ӔC�ی��āX�ی��_�����Ă��邱�ƂɂȂ����ہA�ی����̂̔������X�N�ɂ��Ă`�ЂɃq�A�����O�����铙���āA�����ӔC�ی��ɕی���������ςݗ��Ă邩�ǂ��������������|�q�ׂĂ���i�ؐl�Q�@�V�A�W�Łj�B �@�����āA�c�c�A�{�������ӔC�ی��āX�ی��_��̎�Ă��J�n�������Ƃɔ����A�ی����̂���������\���������Ă̏�ŁA�����ӔC�ی��ɕی���������ςݗ��Ă邱�ƂƂ����Ƃ��Ă����������������̂ł͂Ȃ��Ƃ���A�c�c�A�����ӔC�ی��ɂ��ی���������ςݗ��Ă�|�̖{�������v�Z�����܂ޖ{���������\���쐬����C���ꂪ�����̎������ɂ����ď��F���ꂽ�Ƃ����̂ł���B �@������̉��ł́A�`�Ђɂ�����ی��������̐ϗ��Ăɂ��ẮA�`�Ђ��������Ă���āX�ی��_��̑ΏۂƂȂ鏝�Q�ی��y�є����ӔC�ی��̑o���ɂ��ĕی����������ςݗ��Ă��邱�ƂƂȂ����Ƃ݂�̂����R�ł���A�`��28�N3�����ɂ����āA�`��27�N3�����ȑO�Ɠ��l�ɏ��Q�ی��݂̂ɂ��ĕی����������ςݗ��Ă��Ă����Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B�v �@�u�{�������v�Z���́A�`�Ђɂ�����ی��������̐ϗ��𐳊m�ɔ��f�������̂ł���A�����̎咣����悤�Ɂu��L�v�ł���Ƃ͂����Ȃ�����A�������b�Ƃ��đ[�u�@�{�s�߂R�X���̂P�S��Q���ɂ��d�ŕ��S�������Z�肷��̂������ł���B �@�����A�{������������v�Z���y�і{���Ē���������v�Z���́A���Z�Ƃ��Ċm�肵�����̂������I���R�Ɋ�Â�������I�ɏC���������̂ł��邩��A�c�c�A�{���Ē���������v�Z�����`�Ђ̎������y�ъ��呍��ɂ�鏳�F���c���o����A���u�A�����Z���ɒ�o���ꂽ���Ƃ��l�����Ă��A�d�ŕ��S�����̎Z��̊�b�Ƃ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��i�{�������y�і{���Ē������l�e�q�r�mMalaysian Financial Reporting Standards�n�ɉ����Ă��ꂽ�Ƃ��Ă��A���̔��f�����E������̂ł͂Ȃ��B�j�B �@�����āA�{�������v�Z������b�Ƃ���ƁA�{�������ӔC�ی��������ϗ��z�́A�[�u�@�{�s�߂R�X���̂P�S��Q���P���j�ɋK�肷��u�ُ�댯�������ɗނ��鏀�����̊z�v�ɓ�����A����܂��đd�ŕ��S�������v�Z����ƁA�d�ŕ��S�����͂O���ƂȂ�A�P�O�O���̂Q�O�����ƂȂ邩��A�`�Ђ͑[�u�@�U�U���̂U��P���ɋK�肷�����O���q��Г��ɊY������B�v |
COLUMN8-4 �d�ŏ��ƃ^�b�N�X�E�w�C�������Ő�
| �O���N�\���������E�Ŕ�����21�N10��29�����W63��8��1881�ŕS�I7��74jy �����咣�@�V���K�|�[���q��Ђ̏����ɂ��ē��{���^�b�N�X�w�C�������Ő���K�p���ē��{�ʼnېł��邱�Ƃ́A���{�E�V���K�|�[���d�ŏ���PE�Ȃ���ΉېłȂ��̃��[���Ɉᔽ����B ���咣�@�V���K�|�[���@�l�ɑ���ېłł͂Ȃ����{�@�l�ɑ���ېłł��邩����ᔽ�ł͂Ȃ��B �n�ٔ��|�i���قł��ێ��j�@�u�N�ɑ��ĉېł�����̂��Ƃ����ϓ_���`���I�ɓK�p����_���́A�����d�ŏ��̐��E��e�Ղɋ����Ă��܂������ꂪ������̂ł����āc�A���̂܂܍̗p���邱�Ƃ͍���ł���B �@�����A�V���K�|�[���̊C�O�q��Ђ��A�e��Ђł�������@�l�ɑ��A�z�����̑��̕��@�ɂ���ĔC�ӂɗ��v�ړ]���s�����ꍇ�A�����@�l�Ɉړ]���ꂽ���v�ɑ��ẮA�䂪���ɂ����ĉېł�����邱�ƂɂȂ邪�A���ꂪ�����d�ŏ��Ɉᔽ������̂ł͂Ȃ����Ƃ͖��炩�ł���B�������Ƃ���ƁA�e��Ђł�������@�l�ƃV���K�|�[���̊C�O�q��ЂƂ̊W�A�V���K�|�[���ɂ����ĊC�O�q��Ђ��u���ꂽ�n�ʂ���ۂ̊������̑��̎���ɏƂ炵�A�C�O�q��Ђ�������@�l�ɑ��ė��v�ړ]���s����̂����R�ł���ɂ�������炸�A���̂悤�ȗ��v�ړ]���s���Ă��Ȃ��Ƃ݂���ꍇ�ɁA�����@�l�ɑ��A�{������ׂ����v�ړ]�����ۂɂ��������̂Ƃ݂Ȃ��A���̈ړ]���v�����z�ɑ��ĉېł����邱�Ƃ́A�o�ϓI�������̂Ȃ��s���R�ȏ�Ԃ��A�{������ׂ����R�ȏ�Ԃɖ߂��A����ׂ���ԂɊ�Â��ېł����Ă���̂ɂƂǂ܂�̂ł��邩��A���̂悤�Ȏ��Ԃ́A�����d�ŏ��Ɉᔽ���邱�Ƃ͂Ȃ����̂Ɖ������B�v �ō��ٔ��|�@�u�����d�ŏ��V���P���́A����̒��i�`���j�̊�Ƃ̗����ɑ��đ����̒��i�a���j���ېł��邽�߂ɂ́A���Y��Ƃ��a���ɂ����čP�v�I�{�݂�ʂ��Ď��Ƃ��s���Ă��邱�Ƃ��K�v�ł���Ƃ��i�����O�i�j�A���A�a���ɂ�铖�Y��Ƃɑ���ېł��\�ȏꍇ�ł����Ă��A���̑ΏۂY�P�v�I�{�݂ɋA�����闘���Ɍ��肷�邱�ƂƂ��Ă���i������i�j�B�����́A������u�P�v�I�{�݂Ȃ����ĉېłȂ��v�Ƃ������ۑd�Ŗ@��m�����Ă��錴�������߂Ċm�F�����|�̋K��Ƃ݂�ׂ��ł���Ƃ���A��Ƃ̗����Ƃ����ېŕ����ɒ��ڂ���K��̎d���ƂȂ��Ă��āA�ېőΏێ҂ɂ��Ă͒��ڐG���Ƃ��낪�Ȃ��B�������A������i���A�a���ɍP�v�I�{�݂�L����`���̊�Ƃɑ���ېłɂ��ċK�肵�����̂ł��邱�Ƃ͕����㖾�炩�ł���A����͓����O�i�����K��ł��邩��A�����O�i���A�܂��A�`���̊�Ƃɑ���ېłɂ��ċK�肵�����̂Ɖ�����̂����R�ł���B���Ȃ킿�A�����́A�`���̊�Ƃɑ��邢�����@�I��d�ې����֎~����ɂƂǂ܂���̂ł����āA�������a���ɑ��ċ֎~���͐������Ă���s�ׂ́A�a���̂`����Ƃɑ���ېŌ��̍s�g�Ɍ�������̂Ɖ�����̂������ł���B�v �u�[�u�@�U�U���̂U��P���́A�O���q��Ђ̗��ۏ����̂����̈��z������@�l�ł���e��Ђ̎��v�̊z�Ƃ݂Ȃ��ď������z�̌v�Z��v���̊z�ɎZ��������̂ł��邪�A���̋K��ɂ��ېł��A�����܂ʼn䂪���̓����@�l�ɑ���ېŌ��̍s�g�Ƃ��čs������̂ł���ȏ�A�����d�ŏ��V���P���ɂ��֎~���͐����̑ΏۂɊ܂܂�Ȃ����Ƃ́A��q�����Ƃ��납�疾�炩�ł���B�v �u�����d�ŏ��́A�o�ϋ��͊J���@�\�i�n�d�b�c�j�̃��f���d�ŏ��ɕ�������̂ł��邩��A�����Ɋւ��Ăn�d�b�c�̑d�ňψ���쐬�����R�����^���[�́A���@�Ɋւ���E�B�[�����i���a�T�U�N����P�U���j�R�Q���ɂ����u���߂̕⑫�I�Ȏ�i�v�Ƃ��āA�����d�ŏ��̉��߂ɍۂ��Ă��Q�Ƃ����ׂ������Ƃ������Ƃ��ł���v �����@�ō��ق͒n�قƓ������_�Ȃ���n�ق́u�{������ׂ����v�ړ]�v�Ƃ����\��������Ă���悤�Ɍ�����B���������Ƃɂ��A����21�N�����E�@�l�Ŗ@23����2�i�O���q��Дz���v���s�Z���j��������{�����͈Ӗ������ƍl������i���A�`���I�ɂ����Ε���21�N��̑d�ŏ��ᔽ�̉\���ɂ��Ă̓u�����N�j�B �@�Ȃ��O��I�v�ٔ����⑫�ӌ��́u�����d�ŏ��V���P���̋K��́A�e��̏����̂����u��Ƃ̗����v�i�䂪���̐Ő��ɏƂ炵�Ă����A�����ނˁu���Ə����v�ɑ������鏊�����������̂Ƃ����悤�B�j�ɑ���ېłɍۂ��Ă̒��Ԃł̉ېŌ��̒����Ɋւ���K��ł���A�����̎�ނ�����ƈقȂ�ꍇ�̉ېŌ��̒����ɂ��ẮA���������̎���ɉ����ē����d�ŏ�̑��̏����̋K�肪�D��I�ɓK�p�����ׂ����Ƃ������U���ɖ��肳��Ă���B������āA�Ⴆ�A�z�������ɑ���ېłɂ��Ă͓����d�ŏ��P�O���̋K��A���n�����ɑ���ېłɂ��Ă͓������P�R���̋K�蓙���A���ꂼ��ʂɒu����Ă���Ƃ���ł���B���̂悤�ȓ����d�ŏ��̋K��U�肩�炷��A�[�u�@�̋K�肪�����d�ŏ��Ɉᔽ���邩�ۂ��̖�����������ɍۂ��ẮA�����Ŗ��Ƃ���Ă��鏊���̎�ʂɑΉ���������d�ŏ��̊e���ƂɁA�[�u�@�̋K�肪�����d�ŏ��̒�߂Ɉᔽ���邩�ۂ����ʂɌ��������ׂ����ƂƂȂ낤�v�Əq�ׂĂ���B �@�l�����ł̑d��40����4�ɂ��ē��|�F�Ŕ�����21�N12��4������2068��34�� |
8.4.3.2. �^�b�N�X�E�w�C�������Ő��̐��x��|
COLUMN8-5 �ېŌJ���ׂ̖h�~�̂��߂̐��x���H
���{�@�l���O���Ɏq��Ђ�ݗ������ꍇ�A���Y�q��Ђ͂��̋��Z�n���ʼnېł���B�q��Ђ̐ň��㏊������e��Ђɔz�����������Ƃ��ł��邪�A�z������`���͂Ȃ��A�z������Ȃ�������{�̉ېőΏۂƂ͂Ȃ�Ȃ��B�q��Ђ��^�b�N�X�w�C�����ɐݗ�����A���{�ɔz������Ȃ��܂܂ł���ƁA�������w�ljېł���Ȃ��܂܊O���ɗ��ߍ��܂�邱�ƂƂȂ�B�������u����ƁA���{�@�l���O���Ǝ������ۂɊԂɃ^�b�N�X�w�C�����q��Ђ���݂����A���Y�q��Ђɏ����𗭂ߍ��ނ��Ƃ��\�ƂȂ�B�i���{�@�l���O���ڋq�̔��p�łȂ��A���{�@�l���^�b�N�X�w�C�����q��Ё��O���ڋq�̔̔��Ƃ��铙�B�j
�����A���{�@�l���O���Ɏx�X��ݗ������ꍇ�A�S���E�����ېłȂ̂ő������Ȃ��Ă����{�̉ېł��y�ԁB
��@���v�����N10���B�����@�l��40%�̐ŗ��ʼnېł�������A�O���@�l�͖��ŁB
| �����@�l(�܂��͂��̎x�X)��10000�𓊎� | �O���q��Ђ�ʂ���10000�𓊎� |
| 1�N��̐ň���̌������v10600 | 1�N��̐ň���̌������v11000 |
| 2�N��̐ň���̌������v11236 | 2�N��̐ň���̌������v12100 |
| 10�N��F10000�~1.0610��17908 �ň��㗘�v��7908 |
10�N��F10000�~1.110��25937 �ň��㗘�v��9562�i��15937�~0.6�j |
���{�̗��@�S���҂͖������ېŌJ���h�~����ے�B�d�ʼn��h�~�Ɛ����Bmc
8.4.3.3. �ΏۂƂȂ�O���@�l(�O���W���)
8.4.3.3.a. �������ۗL�
| �݂��ً�s�����E�����n���ߘa3�N3��16������31(�s�E)42��(���p)�E���������ߘa4�N3��10������1649��34�ŗߘa3(�s�R)96��(���������)�E�Ŕ��ߘa5�N11��6���ߘa4(�s�q)228�����W77��8��1933��(���̑�)ce(�ꍂ���i�u�^�b�N�X�E�w�C�u�����Ő��ɂ�����ېőΏۋ��z�Ɋւ���ϔC���߂̓K�p���ے肳�ꂽ�����v�V�E������Watch�d�Ŗ@No. 177 (2023.5.19)�A�{�{�\���q�u�^�b�N�X�E�w�C�u�����Ő��ɂ����鐿�������ĕۗL�������ۗL�����̔����v�V�E������Watch�d�Ŗ@No.184 (2024.2.26)�A�{�{�\���q�E�W�����X�g1597���d����5�N183-184�ŁA��ؗI�ƁE����鏑�W���[�i��HJ100197 (2024.5.31)�A���{�[��E�W�����X�g1610���d����6�N46-47�łق�����) �@�d�œ��ʑ[�u�@�{�s��39����16��1������2��1�����O���q��Ђ̎��ƔN�x�I�����̐��������ĕۗL�������̊����ɒ��ڂ��Ă���Ƃ���A�����́ASPC(special purpose company)���猴���ɔz�������闘�v�������̂�0���ł���Ǝ咣���A�퍐(��)��100���ł���Ǝ咣�����B �@���| �u�i�P�j�{���ł́A�O�L�����W���̉��ɂ����Ė{���K���K�p���邱�Ƃ��{���ϔC�K��̈ϔC�͈̔͂���E���邩�ۂ������ƂȂ�Ƃ���A���̓_�f����ɓ�����A�܂��A�{���K��̓��e���A��ʂɁA�{���ϔC�K��̎�|�ɓK�����邩�ۂ��ɂ���������B �@�{���ϔC�K��́A���@��͓���O���q��Г��ɋA�����鏊���Y����O���q��Г��ɌW������@�l�̉v���̊z�ɍ��Z���ĉېł�����e�̋K��ł���B����́A�����@�l���A�@�l�̏����ɑ���d�ł̕��S���Ȃ������͒������Ⴂ�����͒n��ɐݗ������q��Ђ𗘗p���Čo�ϊ������s���A���Y�q��Ђɏ����������邱�Ƃɂ���ĉ䂪���ɂ�����d�ł̕��S���������悤�Ȏ��Ԃ�h�~���A�ېŗv���̖��m����ېŎ��s�ʂɂ�������萫���m�ۂ��A�ŕ��S�̎����I�Ȍ�����}�邱�Ƃ�ړI�Ƃ�����̂Ɖ������B �@�܂��A�{���ϔC�K��́A�ېőΏۋ��z�ɂ��āA�����@�l�̗L�������O���q��Г��̒��ڋy�ъԐڕۗL�̊������̐��ɑΉ�������̂Ƃ��Ă��̊������̐������̓��e�����Ă��Čv�Z���ׂ����̂ƋK�肷��Ƃ���A����́A�������Ɋ�Â��邱�Ƃ��ł����]���̔z�����̊������������������傫�����Ă���������������@�ɂ��d�ʼn���ɑΏ����邱�Ƃ�ړI�Ƃ�����̂Ɖ������B �@�����āA�{���ϔC�K�肪�ېőΏۋ��z�̋�̓I�Ȍv�Z���@�ɂ����߂ɈϔC�����̂́A��L�̂悤�ȖړI����������ɓ�����A�ǂ̎��_����Ƃ��Ċ������̐������̓��e�����Ă����v�Z�����邩�ȂǂƂ������_���A�D��ċZ�p�I���זړI�Ȏ����ł��邽�߂ł���Ɖ������B���������āA��L�̓_�́A���t�̐��Z�p�I�ȍٗʂɈς˂��Ă���Ɖ�����̂������ł���B �@���̂悤�Ȏ�|�Ɋ�Â��ϔC���Đ݂���ꂽ�{���K��́A�K�p�Ώۋ��z�ɏ悸�ׂ����������ĕۗL�����������ɌW���������O���q��Г��̎��ƔN�x�I���̎��Ƃ�����̂ł���Ƃ���A�{���ϔC�K��ɂ����ĉېŗv���̖��m����ېŎ��s�ʂɂ�������萫�̊m�ۂ��d������Ă���A���ƔN�x�I���̎��Ƃ�����ߕ��͈�`�I�ɖ��m�ł��邱�Ɠ����l������A�ʋ�̓I�Ȏ���ɂ�����炸��L�̂悤�Ɋ����݂��邱�Ƃɂ͍�����������A���̂悤�ȓ��e���߂�{���K�肪�{���ϔC�K��̖ړI���Q������̂Ƃ������Ȃ��B �@��������ƁA�{���K��̓��e�́A��ʂɁA�{���ϔC�K��̎�|�ɓK��������̂Ƃ������Ƃ��ł���B �i�Q�j�ȏ��O��Ƃ��āA���ɁA�O�L�����W���̉��ɂ����Ė{���K���K�p���邱�Ƃ��{���ϔC�K��̈ϔC�͈̔͂���E���邩�ۂ��ɂ���������B �@�O�L�����W���̉��ɂ����Ė{���K���K�p�����ꍇ�ɂ́A�{���e�q��Ў��ƔN�x�ɂ�����{���e�q��Ђ̗��v�͖{���D��o���،��ɂ̂ݔz�����ꂽ�ɂ�������炸�A�{���D��o���،��������ƔN�x�̓r���ŏ��҂��ꂽ���߂ɖ{���ۗL�������������P�O�O���ƂȂ�A��㍐�l�ɑ��č��Z�ېł�����邱�ƂƂȂ�B �@�����Ƃ��A�O�q�̂Ƃ���A�ʋ�̓I�Ȏ���ɂ�����炸�����݂���{���K��̓��e�������I�ł���ȏ�A��L�̂悤�ȋA���������Ē����ɁA�O�L�����W���̉��ɂ����Ė{���K���K�p���邱�Ƃ��{���ϔC�K��̈ϔC�͈̔͂���E���邱�ƂƂ͂Ȃ�Ȃ��Ƃ���A����O���q��Г��̎��ƔN�x�̓r���ɂ��̊���\�����ϓ�����̂ɔ����A��]���̔z����������鎞�Ǝ��ƔN�x�I���̎��ƂŎ����������ɈႢ��������悤�Ȏ��Ԃ͓��R�ɑz�肳���Ƃ����ׂ��ł���B�܂��A�����@�l���O���q��Ђ�����]���̔z�����́A�����Ƃ��āA�����@�l�̏������z�̌v�Z��A�v���̊z�ɂ͎Z������Ȃ��ȏ�i�����Q�V�N�@����X���ɂ������O�̖@�l�Ŗ@�Q�R���̂Q��P�����j�A�{���ϔC�K��ɂ��A����O���q��Г��ɂ����ď�]���̔z���������ۂ���邱�Ƃɂ������@�l�����]���̔z�����ւ̉ېł��J�艄�ׂ��邱�ƂɑΏ����悤�Ƃ�����̂Ɖ����邱�Ƃ͂ł��Ȃ�����A�O�L�����W���̉��ɂ����ď�]���̔z�����ɌW��ʋ�̓I�ȏ���Ƃ��邱�ƂȂ��{���K���K�p���邱�Ƃɂ���āA�{���ϔC�K��ɂ����ė\�肳��Ă��Ȃ��悤�Ȏ��Ԃ�������Ƃ͂����Ȃ��B�����āA�O�L�����W���̉��ɂ����ẮA�{���e�q��Ђ̎��ƔN�x��{���D��o���،��̏��ғ��̑O���܂łƂ���Ȃǂ̕��@���̂�A�{���e�q��Ђ̓K�p�Ώۋ��z���O�~�ƂȂ�悤�ɂ���]�n���������ƍl�����邩��A�{���K���K�p���邱�Ƃɂ���Ĕ�㍐�l�ɉ�������Ȃ��s���v��������ȂǂƂ������Ȃ��B �@��������ƁA�O�L�����W���̉��ɂ����Ė{���K���K�p���邱�Ƃ��{���ϔC�K��̈ϔC�͈̔͂���E������̂ł͂Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���B�v �@�i���̗��v�ɂ��� �@�u���z�X��������ɍ��Œʑ��@�Q�R���P���̋K��ɂ�肳�ꂽ�X���̐����ɑ���X�������ׂ����R���Ȃ��|�̒ʒm�����́A��L���z�X�������ɂ���U�m�肵���Ŋz�ɂ��āA�X���̐����̗��R�܂��ĉ��߂Ē��������ꂽ��ŁA��L���z�X��������̐Ŋz�����z���ׂ����R�͂Ȃ��Ƃ��Ă���鏈���ł���i�����A�����S���j�B��������ƁA��L�ʒm�����́A��L���z�X�������Ƃ͕ʌɂ��ꂽ�V���ȏ����ł��邱�Ƃ����炩�ł���A��L���z�X�������ɋz������A���͂��̓��e�������I�ɕ�ۂ����Ƃ������Ƃ��ł��Ȃ��̂ł����āA��L�X���̐����������҂́A��L�ʒm�������������ꂽ�ꍇ�ɂ́A���z�X����������\�������邱�Ƃ��ł���ȏ�A��L�ʒm�����̎���������߂�i���̗��v��L����Ƃ����ׂ��ł���B �@�{���̂悤�ɏ�L���z�X��������ɏ�L�X���̐��������ꂽ�ꍇ�A����ɌW��Ŋz���\���Ŋz�������Ƃ��ł����Ă��A��L���z�X�������ɌW�����i�ׂɂ����āA��L���z�X�������̂�����L�X���̐����ɌW��Ŋz���镔���̎���������߂邱�Ƃ��ł�����̂́A���̂��Ƃ��璼���ɏ�L�ʒm�����̎���������߂�i���̗��v��ے肷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B �@���������āA���z�X��������ɍ��Œʑ��@�Q�R���P���̋K��ɂ��X���̐��������A�X�������ׂ����R���Ȃ��|�̒ʒm���������҂́A���Y�ʒm�����̎���������߂�i���̗��v��L����Ɖ�����̂������ł���B�v �@cf.�Ŕ��ߘa3�N6��24�����W75��7��3214�� �@�u�����Ŗ@�T�T���Ɋ�Â��\���̌�Ɉ�Y�������s��ꂽ�ꍇ�ɂ��������̑����l�ɂ�铯�@�R�Q���P���̋K��ɂ��X���̐����ɑ���X�������ׂ����R���Ȃ��|�̒ʒm�����Ɠ��Y�����l�ɑ��铯�@�R�T���R���P���̋K��ɂ�鑝�z�X���́c�c����������Y��Y�����ɂ��e�����l�̎擾���Y�̕ϓ��Ƃ��������œ��L�̌㔭�I���R����b�Ƃ��Ă��ꂽ���ꑊ���l�ɑ��鏈���ł���C��L���z�X���́C��U�m�肵�Ă����Ŋz�Y��Y�������s��ꂽ���Ƃ𗝗R�ɑ��z�����Ċm�肷�鏈���ł��邩��C���Y��Y�����ɔ����Ŋz�����z���ׂ����R�͂Ȃ��Ƃ�����L�ʒm�����̓��e�������I�ɕ�ۂ�����̂Ƃ������Ƃ��ł���B�����āC��L�X���̐���������Ă��邽�߁C���Y�����l�́C��L���z�X���̎���i�ׂɂ����āC��L�X���̐����ɌW��Ŋz���镔���̎���������߂邱�Ƃ��\�ł���Ɖ������B��������ƁC�{���ʒm�����ɂ��ẮC���̎���������߂闘�v�͂Ȃ��C�{���i���̂����{���ʒm�����̎���������߂镔���͕s�K�@�ł��邩��C�p�����ׂ��ł���B�v |
| �C���}����������Ў����E�����n���ߘa5�N3��16���ߘa2(�s�E)34��(���p)(�x�����i�E�W�����X�g1598��10��)�c�c�d�œ��ʑ[�u�@66����6��2��1���u�O���W��Ёv�u����W�Z�ҁv�̈Ӌ` |
8.4.3.3.b. �����x�z�
8.4.3.4. �O���W��Ђ̏��������Z���鋏�Z�ҁE�����@�l
8.4.3.5. ��ВP�ʂ̍��Z�ېł̑ΏۂƂȂ�O���W���
8.4.3.5.a. ����O���W���
8.4.3.5.b. �ΏۊO���W���
8.4.3.5.b.1. ���Ɗ
| �z���R�����I�n�������E�É��n������7�N11��9����42��12��3042�ŁE������������8�N6��19���Ŏ�216��619�ŁE�Ŕ�����9�N9��12���Ŏ�228��565�� ���_�@�u�����i�o�����܂ށB�j�Ⴕ���͍��ۗ̕L�v���u�傽�鎖�Ɓv�Ƃ��Ă������̑����B ���|�@��ʘ_�Ƃ��Ắc�u����O���q��Г��������̎��Ƃ��c�ޏꍇ�A���̂�����̎��Ƃ��傽�鎖�Ƃł��邩�̔���́A���̎��ƔN�x�ɂ������̓I�E�q�ϓI�Ȏ��Ɗ����̓��e���画�肷��ق��͂Ȃ��̂ł��邩��A���̎��Ɗ����̋q�ϓI���ʂƂ��ē���������z���͏������z�̏A�g�p�l�̐��A�Œ�{�݂̏��𑍍��I�Ɋ��Ă��Ĕ��肷��ׂ��v �u1989�N3�����̎����́c�c�ۗL�����ɌW����������̖w�ǁi���z�����y�ѓ����L���،����p�v�őS�̖̂�96�p�[�Z���g�j���߂Ă���v |
| �f���\�[�����E�Ŕ�����29�N10��24�����W71��8��1522�ŕS�I7��75kb(���ˋM�V�E�����@�G��154��3��557��)(�f���\�[�����ɂ��Ăł͂Ȃ�����ȏ͔@�uCFC�Ő�(�^�b�N�X�E�w�C�������Ő�)�̓K�p���O�v���ɂ��Ă̈�l�@�v�Ŗ��O��56��2��121-130��(2008.2)���Q�Ƃ��ꂽ��) ���{�@�lD�Ё\�\�\�V���K�|�[���q���S�Ё\�\�\�����n�摷���M1��M2��M3�Ёc �@S�Ђ̏������z��8�`9���͑���Ђ���̎��z������߂Ă����̂ŁA���{�̉ېŒ���S�Ђ́u�傽�鎖�Ɓv�������ۗL�Ƃł���Ǝ咣����(���Ƃ��ăz���R�����I�n������)�B�[�Ŏґ��́AS�Ђ̏]�ƈ����̐��Y�v�f�̑���������Ђ̒n�擝���Ɩ��ɏ]�����Ă���̂Łu�傽�鎖�Ɓv�͊����ۗL�Ƃł͂Ȃ��Ǝ咣�����B�����͓�����Ђ̓���(8.4.3.5.c.�A.)���@�O�ł������B �@��R�͔[�Ŏґ��̎咣��F�߂����A�T�i�R�ŋt�]�������������Ă����B�ō��قŋt�]�����B �@���|�@�u�n�擝���Ɩ��̒��̕������P�Ɩ��Ɋւ��锄�㍂�͎������z�̖�W�T���ɏ���Ă���C�������z�ł͕ۗL�����̎��z���̐�߂銄�����W�C�X���ł��������̂́C���̔z�������̒��ɂ͒n�擝���Ɩ��ɂ���Ĉ���O���[�v��БS�̂Ɍ��������ጸ�������ʐ��������v���������x���f����Ă������̂ł���C�{�����n�������ŋΖ�����]�ƈ��̑������n�擝���Ɩ��ɏ]�����C�`�ۗ̕L����L�`�Œ莑�Y�̑唼���n�擝���Ɩ��ɋ�����Ă����v�B�uS�Ђ̍s���Ă����n�擝���Ɩ��́C�����̋K�͂Ǝ��̂�L������̂ł���C���z���̏������z�ɐ�߂銄�����������Ƃ܂��Ă��C���Ɗ����Ƃ��đ傫�Ȕ�d���߂Ă����Ƃ������Ƃ��ł��C�mS�Ђ́n�e���ƔN�x�ɂ����ẮC�n�擝���Ɩ����[�u�@�U�U���̂U��R���y�тS���ɂ���S�Ђ̎傽�鎖�Ƃł������v�B |
8.4.3.5.b.2. ���̊
8.4.3.5.b.3. �Ǘ��x�z�
| ����؍ގ����E�����n������2�N9��19���s�W41��9��1497�ŁE������������3�N5��27���s�W42��5��727�ŕS�I4��70�c�c�O���q��Ђ����炻�̎��Ƃ��Ǘ��x�z���Ă��Ȃ��Ƃ��āA���̐e��Ђł�������@�l�ɂ��āA�^�b�N�X�E�w�C�u���ېŋK��̓K�p�����O�����ꍇ�ɓ���Ȃ��Ƃ��ꂽ����B |
8.4.3.5.b.4. ��֘A�Ҋ�E���ݒn���
| ���Y�����E�����n���ߘa4�N1��20���ߘa2(�s�E)86��(���p)�E���������ߘa4�N9��14���ߘa4(�s�R)36��(���������)�E�Ŕ��ߘa6�N7��18�����W78��3��1097�ŗߘa4(�s�q)373��(�j������)(���Ă̊T�v�����N��̃t�@�C���������Ă��܂���)(�Ҕ��}�E�W�����X�g1579��10-11�ŁA�ѓc�T��E�W�����X�g1582��121-124�ŁA�I���G�K�E�W�����X�g1585��10-11�ŁA�����S��E�Ō�231��82-86�ŁA���������Y�E�W�����X�g1610���d����6�N152-153��) �@�K�p���O�v���@�d�œ��ʑ[�u�@�i����28�N�@����15���ɂ������O�j68����90��3���F���Y����O���q��Г��̍s���傽�鎖�Ƃ������ƁC��s�ƁC�M���ƁC���Z���i����ƁC�ی��ƁC���^�Ɩ��͍q��^���Ƃ̂����ꂩ�ɊY������ꍇ�ɂ́C���̎��Ƃ���Ƃ��ē��Y����O���q��Г��ɌW�鏊��̊֘A�҈ȊO�̎҂Ƃ̊Ԃōs���Ă���ꍇ�ɊY�����邱�Ɓi��֘A�Ҋ�j �@�d�œ��ʑ[�u�@�{�s�߁i����28�N���ߑ�159���ɂ������O�j39����117��8��5���F�u�ی��Ɓ@���Y�e���ƔN�x�̎����ی����̍��v�z�̂����ɓ��Y�����ی����Ŋ֘A�҈ȊO�̎҂������������́i���Y�����ی������ĕی��ɌW����̂ł���ꍇ�ɂ́A�֘A�҈ȊO�̎҂��L���鎑�Y���͊֘A�҈ȊO�̎҂��������Q�����ӔC��ی��̖ړI�Ƃ���ی��ɌW������ی����Ɍ���B�j�̍��v�z�̐�߂銄�����S���̌\����ꍇ�v �@�����F���Y�i���{�@�l�j �@�`�ЁFNissan Global Reinsurance, Ltd������NGRE�B�o�~���[�_�@�l�B�����������������ԐڕۗL�B�傽�鎖�Ƃ͕ی��ƁB�{�X���ݒn���ɂ����鏊���ŕ��S����0���B �@�a�ЁFNR Finance Mexico, S.A. de C.V. SOFOM ER������NRFM�B���L�V�R�@�l�B�����������������ԐڕۗL�B�傽�鎖�Ƃ͋��Z�ƁB �@�b�ЁFAssurant Vida Mexico, S.A.������AVM�B���L�V�R�@�l�B�����Ƃ̎��{�W�Ȃ��B�傽�鎖�Ƃ͕ی��ƁB �@�a�Ђ́u�{���e�ڋq�v�i���Y�̎Ԃ������w���j�Ɓu�{���N���W�b�g�_��v�i�w�������̑ݕt�j��������Ă����B�a�Ђ͂b�ЂƂ̊ԂŁu�{������ی��_��v�i���҂̎��S�Ǝ��ƂɊւ���ی��_��B�ی����͖{���N���W�b�g���̊���c����0.096���j����������B �@�b�ЂƂ`�Ђ́u�{���ĕی��_��v�i�b�Ђ��{������ی��_��ɂ����Ĉ���S�ی����X�N��70�����`�Ђɑ��čĕی��ɕt�j����������B �@�`�Ђ̎����ی������z�͕ā�5��2521��4976�i�@�j�B��֘A�ҁi�b�Ђ������j�����̂��������ی����́�2��5318��3120�i�A�j�B�b�Ђ����̂��������ی����́�1149��3075�i�B�j�B�A/�@��50���B(�A�{�B)/�@��50���B �@�������������������������������������������������������������������� �@���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��㍐�l�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �@�������������������������������������������������������������������� �@�@�F�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�F �@�@�F�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�F�P�O�O���ԐڕۗL �@�@�F�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �@�@�F�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������������������������������ �@�@�F�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���i����O���q��Г��j�@�@�@�� �@�@�F�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�@�m�f�q�d�i�`�Ёj�@�@�@�� �@�@�F�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�@�o�[�~���[�_�@�l�@�@�@�� �@�@�F�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���{���ĕی��_��̕ی���Ё@�� �@�@�F�P�O�O���ԐڕۗL�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������������������������������ �@�@�F�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�@�� �@�@�F�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�{���ĕی��_��b�@�@�b�ĕی��� �@�@���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�@�b �@�������������������������@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������������������������������ �@���i�֘A�ҁj�@�@�@�@�@���@�{������ی��_��@���@�@�i��֘A�ҁj�@�@�@�@�@�� �@���@�m�q�e�l�i�a�Ёj�@�����\�\�\�\�\�\�\�\�����@�@�@�`�u�l�i�b�Ёj�@�@�@�� �@���@���L�V�R�@�l�@�@�@���\�\�\�\�\�\�\�\�\�����@�@���L�V�R�@�l�@�@�@�@�@�� �@���ڋq�ɍw��������Z�����@�@�@�ی����@�@�@�@���{������ی��_��̕ی���Є� �@�������������������������@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������������������������������ �@�@�@�@�@�@���@�� �@�{���N���W�b�@�b�ی��������z �@�@�b�g�_��b�@�b �@�@�@�@�@�@���@�b �@������������������������ �@���@�����ԍw���ҁ@�@�@�� �@���@�@�i�ڋq�j�@�@�@�@�� �@������������������������ �@���_�@�{���ĕی��_��ɌW������ی������A�{�����ʏ����ɂ����u�֘A�҈ȊO�̎҂��L���鎑�Y���͊֘A�҈ȊO�̎҂��������Q�����ӔC��ی��̖ړI�Ƃ���ی��ɌW������ی����v�ɊY�����邩�ۂ��B �@�T�i�R���|�@�u�{�����ʏ����́A�傽�鎖�Ƃ��ی��Ƃł������O���q��Г��̎����ی������ĕی��ɌW����̂ł���ꍇ�ɂ́A���Y�����ی������A�֘A�҈ȊO�̎҂��L���鎑�Y���͊֘A�҈ȊO�̎҂��������Q�����ӔC��ی��̖ړI�Ƃ���ی��ɌW������ی����ł���ꍇ�Ɍ���A��֘A�Ҋ�������̂Ƃ��Ă���B����́A�ی��ƂɌW���֘A�Ҋ�ɂ��ẮA����O���q��Г��Ƃ��̊֘A�҂Ƃ̎�����ĕی��̌`�Ŕ�֘A�҂���݂���ꍇ�̎戵�����s���m�ł���Ƃ̎w�E�����������Ƃ���A����O���q��Г��̑��ی��������ɐ�߂��֘A�҂���̕ی����������ߔ����ۂ��肷��ۂɁA�ی��_��ɂ���ĒS�ۂ����ی��댯�̉ߔ�����֘A�҂̍��Y���ɌW����̂��ۂ��Ƃ������f������邱�Ƃɂ��A���̏��݂��鍑���͒n��ōs�����Ƃɂ��o�ύ��������F�߂��Ȃ����Ɗ����ɂ��ĊO���q��Ѝ��Z�Ő��̐��E��h�~����Ƃ�����|�ɂ����̂Ɖ������B�����āA���̂悤�Ȏ�|�́A���Q�ی��Ɍ��炸�L���ی���ʂɑÓ�����Ƃ����ׂ��ł��邩��A�{�����ʏ����ɂ����u���Y�v��u���Q�����ӔC�v�́A�P�Ȃ�Ꭶ�ɂ����Ȃ��Ɖ������B �@��������ƁA�{�����ʏ����ɂ����u�֘A�҈ȊO�̎҂��L���鎑�Y�c��ی��̖ړI�Ƃ���ی��v�Ƃ́A��֘A�҂̎��Y���ɑ���ی��댯��S�ۂ���ی����������̂Ɖ�����̂������ł���B�v �@�u�{������ی��_��ɂ����ẮA�{���e�ڋq�̎��S����ی����̎��R�Ƃ���|��߂��Ă����A�m�q�e�l���{���e�ڋq����ی��������z�̋��K�����Ă`�u�l�Ɏx�������ƂƂ���Ă��邩��A�ی����̎����I���S�҂͖{���e�ڋq�ł���B��������ƁA�{������ی��_��́A�{���e�ڋq�����̐����A�g�̓��ɌW��ی��댯��S�ۂ��邱�Ƃ̑Ή��Ƃ��ĕی������x�����A�{���e�ڋq�̎��S���̎��R�����������ꍇ�ɕی������x������d�g�݂ƂȂ��Ă���̂ł��邩��A�{������ی��_��́A�{���e�ڋq�̐����A�g�̓��ɑ���ی��댯��S�ۂ���ی��ł���Ƃ����ׂ��ł���B�v �@�㍐�R���|�@�u(1)�@�{�s�߂R�X���̂P�P�V��W���T���́A�[�u�@�U�W���̂X�O��P���̋K��̓K�p�����O�����ꍇ�̗v���̈�ł����֘A�Ҋ���A��Ƃ��ĕی��Ƃ��s������O���q��Г��ɂ��ċ�̉�������̂ł���B�����āA�{�����ʏ����́A����O���q��Г����֘A�҂Ƃ̊Ԃ̕ی�����Ɋ֘A�҈ȊO�̎҂���݂������ꍇ�̎����ی����̎戵���m�ɂ��A��L�̎҂��`���I�ɉ�݂����邱�Ƃɂ���Ĕ�֘A�Ҋ���[�������A�����̓K�p�����O����邱�ƂƂȂ�̂�h����|�ɏo�����̂Ɖ������B �@���̂悤�Ȗ{�����ʏ����̎�|�ɉ����āA�ʏ�A�ی��ɉ�������҂́A�ی����̎x�����邱�Ƃɂ���Čo�ϓI�s���v�̕ۏ�A�U����邱�Ƃ�ړI�Ƃ��āA�ی����S���ĕی��_������������̂ƍl�����邱�Ƃ܂���ƁA�{�����ʏ����́A����O���q��Г����ی��҂Ƃ��čĕی�������s���ɍۂ��A���Y�ĕی�������֘A�҈ȊO�̎҂̎��Y���͑��Q�����ӔC�ɌW��o�ϓI�s���v��S�ۂ��悤�Ƃ�����̂ł���ꍇ�Ɍ���A���Y����O���q��Г������Y�ĕی�������瓾������ی����͊֘A�҈ȊO�̎҂������������̂Ƃ��Ĉ������ƂƂ������̂Ɖ������B �@���������āA�{�����ʏ����ɂ����u�֘A�҈ȊO�̎҂��L���鎑�Y���͊֘A�҈ȊO�̎҂��������Q�����ӔC��ی��̖ړI�Ƃ���ی��v�Ƃ́A�֘A�҈ȊO�̎҂̎��Y���͑��Q�����ӔC�ɌW��o�ϓI�s���v��S�ۂ���ی����������̂Ɖ����ׂ��ł���B �@(2)�@�����{���ɂ��Ă݂�ɁA�O�L�����W���ɂ��A�m�q�e�l�́A�{���N���W�b�g�_�����������{���e�ڋq������̕ی��_���������Ȃ��ꍇ�ɂ́A�{������ی��_��ɖ{���e�ڋq�����������A�{���e�ڋq����A�{���N���W�b�g���̎c���ɉ����Ē�߂���{������ی��_��̕ی����ɑ���������z�����ĕی������`�u�l�Ɏx�����Ă���A�܂��A�{������ی��_��ɂ����ẮA�m�q�e�l���D���v�҂Ɏw�肳��A���̎w��͎��������Ƃ��ł��Ȃ����ƂƂ����ƂƂ��ɁA�{���e�ڋq�̎��S�����͎��Ɠ��̕ی����̂��������ꍇ�ɂ́A���ꂼ��A����̌��x�z������Ƃ��āA�{���N���W�b�g���̖����Ҏc�����͌��z�������U�������ɑ�������ی����t���邱�ƂƂ���Ă����Ƃ����̂ł���B �@��L�̂悤�Ȗ{������ی��_��̎����ɏƂ点�A�{���ĕی��_��ɌW��ی��́A�{���m�f�q�d���ƔN�x�ɂ�����m�f�q�d�ɌW��֘A�҂ɓ�����m�q�e�l���L���鎑�Y�ł���{���N���W�b�g���ɌW��o�ϓI�s���v��S�ۂ�����̂ł���Ƃ������Ƃ��ł���B���������āA��L�ی��́A�{�����ʏ����ɂ����u�֘A�҈ȊO�̎҂��L���鎑�Y���͊֘A�҈ȊO�̎҂��������Q�����ӔC��ی��̖ړI�Ƃ���ی��v�ɂ͓�����Ȃ�����A�m�f�q�d�͖{���m�f�q�d���ƔN�x�ɂ����Ĕ�֘A�Ҋ�������A�[�u�@�U�W���̂X�O��P���̓K�p�����O����邱�ƂƂ͂Ȃ�Ȃ��B�v |
8.4.3.5.c. �o�ϊ�����ɌW����ʂȎ戵��
8.4.3.5.c.�A. ������Ђ̓���
8.4.3.5.c.�C. �q��@�̑ݕt�����傽�鎖�ƂƂ���O���W���
8.4.3.5.c.�E. �ی���Ђ̓���
COLUMN8-3 �������H����ƃ^�b�N�X�E�w�C�u�����Ő�
| �������H����(���{�d�Y�j�b�V������)�E�����n������21�N5��28������18(�s�E)322����59��1��30�Ő������p(�������W�����X�g1411��157��)�E������������23�N8��30������21(�s�R)236����59��1��1�ōT�i���p �@���{�@�l�̍��`�q��Ђ������x�X�Ő����������Ă����ꍇ�ɁA���`�q��Ђ̎傽�鎖�Ƃ͉����Ƃł͂Ȃ������Ƃł���(�܂���֘A�Ҋ�Ŕ��肳�ꂸ�c��֘A�Ҋ�Ȃ���`�q��Ђ͓K�p���O������ƍl�����Ă���)�A���`�Ő������ĂȂ��̂����ݒn��������Ȃ��B �@Cf.���{���`��������3��(�u������̈���̒��{�̓����Ƃ��A�����̒��{�̒n����ɂ����āA�������Y�A���v�y�ѓ����Ɋ֘A���鎖�Ɗ����Ɋւ��A���Y�����̒��{���͗����{�ȊO�̐��{�̓����Ƃɗ^������ҋ������s���łȂ��ҋ���^������B�v)�ᔽ�Ƃ����咣�͍T�i�R�Ő˂���ꂽ�B�O���N�\�����E�Ŕ�����21�N10��29�����W63��8��1881�ł̔��f�g�g�Ɉˋ��B cf.�ޗ�F�D��d�@�����E���n������23�N6��24������18(�s�E)191����59��1��100�Ŋ��p�E��㍂������24�N7��20������23(�s�R)107���Ŏ�262������12006�T�i���p cf.�ޗ�F���R�n������26�N7��16������24(�s�E)12����61��3��702�Ŋ��p�A�m��(�{�c���G�E�W�����X�g1501��128��)�B cf.�������H�Ŕ[�Ŏґ��咣��F�߂�����Ƃ��č��ŕs���R��������26�N8��26���ٌ��E�ٌ�����W75�W415�ōٌ�����(�@)��26��17���B |
8.4.3.5.d. ��ВP�ʂ̍��Z�ېł̓K�p�Ə�
COLUMN8-7 �ŗ���I���ł���O���@�l��
| �K�[���W�[������(���ۃW���p��)�E�Ŕ�����21�N12��3�����W63��10��2283��dg(�a�J��O�E�W�����X�g1402��110�ŁA�n�ӗT�ׁE�W�����X�g1409��203�ŁA�c���r�v�u�f�U�C�i�[�E���[�g�E�^�b�N�X�Ɋւ���l�@�\�X�C�X�Ő��𒆐S�Ɂ\�v�ő�_�p75��1��)(Bailiwick of Guernsey)(��2.2.2.�A8.3.2.1.) �p�����̃K�[���W�[���ł́A���̏������Ŕ[�Ŏ҂�0-30%�͈̔͂��ŗ���I�����Ƃ��ł���B�^�b�N�X�w�C�������Ő��̑Ώۂ͐ŗ�25���ȉ�(�����B�g���K�[�ŗ��Ƃ���)�̊O���q��Ђł���̂ŁA���{�̑��Q�ی���Ђ��x�z����K�[���W�[�����ݎq��Ђ����n��26���̐ŗ���I�����[�ł����B���ꂪ�@�l�łɓ����邩�̖��B�O���Ŋz�T���̓K�p�̉ۂ����킹�Ė��ƂȂ����B�����R�́A������(�O�L�u���͐��v�Q��)�������d�ʼn���T�[�r�X�̑Ή��ł���Ƃ������A�ō��ق͑d�Ő����m�肵��(�[�Ŏҏ��i)�B ���|�@�u�@���R�́A�O�L�̂Ƃ���A�{���O���ł́A���s���A�������Ȃ����������Ƒ�����Ȃ����̂ł���A���̎����̓^�b�N�X�E�w�C�u�����Ő��̓K�p�����������Ƃ����T�[�r�X�̒ɑ���Ή��Ƃ��Ă̐��i��L������̂ł����āA���������d�łɊY�����Ȃ��Ɣ��f�����B �@�m���ɁA�O�L�����W���ɂ��A�{���O���ł��ۂ����ɓ������āA�{���q��Ђɂ͂��̐ŗ����ɂ��čL���I���̗]�n���������Ƃ������Ƃ��ł���B�������A�I���̌��ʉۂ��ꂽ�{���O���ł́A�K�[���W�[�����̉ېŌ��Ɋ�Â��@�߂̒�߂���̗v���ɊY�����邷�ׂĂ̎҂ɉۂ������K���t�ł���Ƃ̐��i��L���邱�Ƃ�ے肷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�܂��A�O�L�����W���ɂ��A�{���O���ł��A���ʂ̋��t�ɑ��锽���t�Ƃ��ĉۂ��ꂽ���̂łȂ����Ƃ͖��炩�ł���B �@���������āA�{���O���ł����������d�łɊY�����Ȃ��Ƃ������Ƃ͍���ł���B�v |
8.4.3.6. �O���@�l�P�ʂ̍��Z�ېłɂ����č��Z������z
8.4.3.6.a. ��������z
8.4.3.6.b. �K�p�Ώۋ��z
8.4.3.6.c. �ېőΏۋ��z
| �o�P�D�D�����E�Ŕ�����19�N9��28�����W61��6��2486�ŕS�I7��29 ���_�@���Z�ΏۂƂȂ�u�ېőΏۗ��ۋ��z�v���v�Z����ߒ��ɂ����āA�^�b�N�X�w�C�����q��Ђ̉ߋ�7�N�ȓ������������T������Ƃ����K�肪����B �@�Ⴆ�A��1�N�x�̃^�b�N�X�w�C�����q��Ђ�100�̌����ł��������A��2�N�x�ɂ�����300�̗��v���o�����Ƃ����ꍇ�A��2�N�x�ɂ�����300�|100��200�݂̂��A���Z�ΏۂƂȂ�B �@�t�ɂ����ƁA���N��������������A����7�N�Ԃ̗��v�Ƒ��E���邱�ƂƂȂ�B �@���������N�̌��������N�̓��{�̐e��Ђ̑����ɎZ�����邱�Ƃ��֎~����K�肪�Ȃ�����A�Z���ł���̂ł͂Ȃ����Ƃ����咣���Ȃ��ꂽ�B ��R�@�ېœ��ǂ̏����ɕs������Ƃ��Ĕ[�Ŏҏ��i�B�i[���]�傽�鑈�_�Ƃ͈Ⴄ�ӏ��ɂ�錋�_�j ��R�E�ō����@�t�]�B�^�b�N�X�w�C�����q��Ђ̌���������@�l�̑����̊z�ɎZ�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B �l�@�@�K��Ԃ肩�炵�Ďq��Ђ̌������������Ɋ��傽����{�@�l�̑����ɎZ�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��͎̂d���Ȃ��B�J��^�̑��_�́A���ƂȂ��Ă��錇���������@��q��ЂɋA�����邩���傽����{�@�l�ɋA�����邩�A�ł������̂ł��낤�B |
8.4.3.7. �������Z�ې�
8.4.3.7.a. �������Z���鏊��
8.4.3.7.b. �O�����Z�q��Г��̓���
8.4.3.7.c. �������Z�ېł̓K�p�Ə�
8.4.3.8. ��d�ېł̒���kd
| �����R�[�f�B�A�������E�����n������26�N6��27������23(�s�E)370�����p�E������������27�N2��25������26(�s�R)278��61��8��1627�Ŋ��p(�g������E�Ō�35��4���ʊ�208��163��)�c�c�P�C�}���@�l���{�x�X�����{�ʼnېł���Ă��Ă��d�œ��ʑ[�u�@66����6�̓���O���q��Г��ɊY������B |
8.4.4. �ߏ����{�Ő�(thin capitalization)
8.4.4.1. �ߏ����{�Ő��Ƃ�
���ۓI�Ȑe�q��ЊW�̒ʏ�̏ꍇ�w���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�x��
�o��(�e���)�@�@�@�@�@�r��(�q���)
�@�@�@�@�@���������o��1000
�@�@�@�@�z��100������(�z���O���v150)
�r�Ђ̗��v�͂x���ʼnېł����B
�r�Ђ��o�Ђɔz�����x�����Ă����̔z���͂r�Ђ̔�p�ł͂Ȃ��̂ŁA�x���ł̉ېł͖Ƃ���Ȃ�(�r�Ђ̉ېŏ�����150-100=50�ɂȂ�Ȃ�)�B
�ߏ����{(Thin Capitalization)�̏ꍇ
�w���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�x��
�o��(�e���)�@�@�@�@�@�r��(�q���)
�@�@�@�@�@���������o��100
�@�@�@�@�@�z��10������(�z���O���v150)
�@�@�@�@�@���������ݕt900
�@�@�@�@�@���q90������
�e��Ђo�Ђ���q��Ђr�Ђւ̏o�������Ȃ�������ɑݕt�𑝂₷�B
�r�Ђ���o�Ђւ̎x�����́A�����̔z���ƁA���߂̗��q�A�Ƃ����@���\���ɂȂ�B
�r�Ђ̉ېŏ�������������(��:150-90=60)�B
�����@�F�r�Ђ����{�F���䗦���s���ɒႢ�ꍇ�A�x���͗��q��p�T���𐧌�����B
���{�@�ł͂P�F�R�������̔䗦�������ꍇ�A�����������ɌW�闘�q�x���ɂ��Ĕ�p�T����F�߂Ȃ��B�i��̗Ⴞ�ƁA���q�x���̔�p�T����30�܂ł����F�߂Ȃ��̂łr�̉ېŏ�����120�j
8.4.4.2. �ߏ����{�Ő��̍\��
�d��66����5�i���O�x�z���哙�ɌW�镉�̗��q���̉ېł̓���j�@�����@�l���A����4�N4��1���Ȍ�ɊJ�n����e���ƔN�x�ɂ����āA���Y�����@�l�ɌW�����O�x�z���哙���͎������^�ғ������̗��q�����x�����ꍇ�ɂ����āA���Y���ƔN�x�̓��Y�����@�l�ɌW�鍑�O�x�z���哙�y�ю������^�ғ��ɑ��镉�ɌW�����ϕ��c�������Y���ƔN�x�̓��Y�����@�l�ɌW�鍑�O�x�z���哙�����{�����̎O�{�ɑ���������z����Ƃ��́A���Y�����@�l�����Y���ƔN�x�ɂ����ē��Y���O�x�z���哙�y�ю������^�ғ��Ɏx�������̗��q���̊z�̂����A���̒����镔���ɑΉ�������̂Ƃ��Đ��߂Œ�߂�Ƃ���ɂ��v�Z�������z�́A���Y�����@�l�̓��Y���ƔN�x�̏����̋��z�̌v�Z��A�����̊z�ɎZ�����Ȃ��B�������A���Y�����@�l�̓��Y���ƔN�x�̑�����[��]�ɌW�镽�ϕ��c�������Y�����@�l�̎��Ȏ��{�̊z�̎O�{�ɑ���������z�ȉ��ƂȂ�ꍇ�́A���̌���łȂ��B�@[2���ȉ���]8.4.4.3. �ߏ����{�Ő��̓K�p�ɂ�����W�����҂̒�`
8.4.4.3.a. ���O�x�z���哙
8.4.4.3.b. �������^�ғ�
8.4.4.4. �ߏ����{�Ő��̓K�p�ɂ�������z�v���̒�`
8.4.4.4.a. ���ϕ��c��
8.4.4.4.b. ���O�x�z���哙�̎��{����
8.4.4.4.c. ���Ȏ��{�̊z
8.4.4.5. �ߏ����{�Ő��̓K�p�̊O��
8.4.5. �ߑ�x�����q�Ő�
8.4.5.1. �ߑ�x�����q�Ő��Ƃ�
8.4.5.2. �ߑ�x�����q�Ő��̍\��
�d��66����5��2�i�Ώۏ��x�����q���ɌW��ېł̓���j�@�@�l�̕�����\�ܔN�l������Ȍ�ɊJ�n����e���ƔN�x�ɂ����āA���Y�@�l�̓��Y���ƔN�x�̑Ώێx�����q���̊z�̍��v�z�i�ȉ����̍��A������Z���y�ё�O����ꍆ�ɂ����āu�Ώێx�����q�����v�z�v�Ƃ����B�j���瓖�Y���ƔN�x�̍T���Ώێ�旘�q�����v�z���T�������c�z�i�ȉ����̍��y�ё�O���ɂ����āu�Ώۏ��x�����q���̊z�v�Ƃ����B�j�����Y�@�l�̓��Y���ƔN�x�̒����������z�i���Y�Ώۏ��x�����q���̊z�Ɣ�r���邽�߂̊�Ƃ��ׂ������̋��z�Ƃ��Đ��߂Œ�߂���z�������B�j�̕S���̓�\�ɑ���������z����ꍇ�ɂ́A���Y�@�l�̓��Y���ƔN�x�̑Ώێx�����q�����v�z�̂������̒����镔���̋��z�ɑ���������z�́A���Y�@�l�̓��Y���ƔN�x�̏����̋��z�̌v�Z��A�����̊z�ɎZ�����Ȃ��B[2���ȉ���]8.4.5.3. �ߑ�x�����q�Ő��̓K�p�ɂ�������z�v���̒�`
8.4.5.3.a. �Ώێx�����q���̊z
8.4.5.3.b. �ΏۊO�x�����q���̊z
8.4.5.3.c. �T���Ώێ�旘�q�����v�z
8.4.5.3.d. �����������z
8.4.5.4. �ߑ�x�����q�Ő��̓K�p�̊O��
8.4.6. �d�ŋ���(tax competition)(���ȏ��ɂ͂Ȃ�)
��Ƃɏd���ŕ��S���ۂ��A��Ƃ͂��̍����瓦���Ă����B�Y�ƗU�v�̂��߂ɁA��Ƃɑ���ېł��y�����铮��������B�ŕ��S���������������d�ŋ����ƌĂԁB��ւ̋����irace to the bottom�j�̋���Bme�@�d�łɊւ��Ă��A�����ɂ��A���Ƃ͖��ʂȉېł��ł��Ȃ��Ȃ�A���ʂȍ����x�o���ł��Ȃ��Ȃ�B�i�ł̖�肾���łȂ��A�d�G�̗v���Ȃǂ�����Ȃ�j�@�Ƃ�킯�A���W�r�㍑���Ő��D���ŎY�ƗU�v���悤�Ƃ��邱�Ƃ��A��i���i�y�ѐ�i���̏W�܂�ł���n�d�b�c�j���Ƃ₩���������i�͂Ȃ��B�e���̐Ő��͊e���̔��f�Ō��߂�B
���d�ŋ�������������A���I(mobile)�Ȑ��Y�v�f�i���{�E�n���J���ғ��j�ɉېłł��Ȃ��Ȃ�B
�@�������v���Ȃ��Ȃ��ł͂Ȃ�����A�K�v�ȐŎ����A�s���Y�A���n���J���ҁA�����K���i����Ƃ����������̒Ⴂ���̂ɋ��߂�B�@���@�����Ȑŕ��S�̔z���Ƃ��������ړI���B���s�B��������������B
8.5. �d�Ŏ葱�@�̍��ۓI����
8.5.1. ��{�I���_
8.5.2. ���O�ɂ�����Ŗ������\�\�d�ŏ���ʂ���������
8.5.3. �O���ɂ�����d�ō��̎��s�E�ۑS�A�O���d�ō��̎��s�E�ۑS
| �V�h�z�[���f�B���O�J���p�j�[�����E�����n���ߘa4�N11��30���ߘa4(�s�E)124����70��4��499�Ŋ��p(���l�q�P�E�W�����X�g2024�N12�����\��)(�T�i�R�F���������ߘa5�N7��19���ߘa4(�s�R)341����70��4��481�Ŋ��p�m��)�c�c�؍��̍��Œ����؍��̍��őؔ[�ҁiA���B�����̌���\�ҁB�؍��E���{�E���`�ŊC�^�ƂɌg���B2016�N2��18���E�ŗL�ߊm��j�ɌW���[�ŋ`���҂Ƃ��Ďw�肵�������iCIDO Holding Company�B�P�C�}���@�l�j�ɂ��āA�Ŗ��s�����s�������Ɋ�Â������̂��߂̍��Y�̕ۑS�̋�������{�̍��Œ��ɗv�������i�u�{���ۑS�����v���v�j�B�������ŋǒ��́A�{���ۑS�����ΏۊO���d�łɂ��ĕۑS���������{���錈��i�u�{���ۑS�������{����v�j���s���A�������݂��ً�s�ɑ��ėL����O�ݕ��ʗa���̕��ߐ������������������A�������Ď�藧�Ă����K�𓌋��@���ǂɋ��������B �@���| �@���_2�F�{���ۑS�����ΏۊO���d�ł́A�䂪���ɂ����ĐŖ��s�����s�������̓K�p�̂���ېŊ��Ԃɉۂ����d�łł���Ƃ����邩�B �@�u�{���ۑS�����ΏۊO���d�ł́A�v�i�nj̈ӎ��ĂɌW��d�łɊY�����邩��A�����Q�U�N�P���P�����O�̉ېŊ��Ԃɉۂ����d�łł͂�����̂́A�䂪���ɂ����ĐŖ��s�����s�������̓K�p�̂���ېŊ��Ԃɉۂ����d�łł���v�B �@�u�����́A�Ŗ��s�����s�������Q�W���V�����k�y�����̋֎~�i���@�R�X��O�i�j�ɔ����Ĉጛ�����ł��邩��A�����������Ƃ��āA�����Q�U�N�P���P�����O�̉ېŊ��Ԃɉۂ����d�łł���{���ۑS�����ΏۊO���d�ł�Ŗ��s�����s�������̓K�p�̂���ېŊ��Ԃɉۂ����d�łł���Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��|���咣����B�v �@�Ŗ��s�����s�������Q�W���V�u���́A���鍑�ɂ��ĐŖ��s�����s��������͂����N�̗��N�̂P���P�����O�ɊJ�n����ېŊ��ԁi�ېŊ��Ԃ��Ȃ��ꍇ�ɂ͓������O�j�ɉۂ����d�łɂ��Ă��A�Ŗ��s�����s��������K�p����|���߂��K��ɂƂǂ܂�A���鍑�ɂ����ČY����̐ӔC�����Ă��Ȃ������s�ׂɂ��āA�k�y�I�ɓ����ɂ����ČY����̐ӔC��Njy���邱�Ƃ��ł���|���߂��K��ł͂Ȃ�����A�k�y�����̋֎~�ɐG�����̂ł͂Ȃ��B�v �@�u�����́A�v�i�nj̈ӎ��Ăɂ́A�ߋ��ɑi�ǂ���Ċ��Ɋm�蔻�����o�Ă���d�Ŏ��Ă͊܂܂�Ȃ�����A���ɖ{���m��O���������o�Ă���{���O���i�ǎ��ĂɌW��d�łł���{���ۑS�����ΏۊO���d�ł͗v�i�nj̈ӎ��ĂɌW��d�łɂ͊Y�����Ȃ��Ƃ��āA�Ŗ��s�����s�������Q�W���V���������Ƃ��āA�����Q�U�N�P���P�����O�̉ېŊ��Ԃɉۂ����d�łł���{���ۑS�����ΏۊO���d�ł�Ŗ��s�����s�������̓K�p�̂���ېŊ��Ԃɉۂ����d�łł���Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��|���咣����B�v �@�u�v�i�nj̈ӎ��Ă̌����ł���wintentional conduct which is liable to prosecution under the criminal laws of the applicant Party�x�Ƃ�����������́A�ߋ��ɌY���i�ǂ��Ċ��Ɋm�蔻�����o���d�Ŏ��Ă�v�i�nj̈ӎ��Ă��珜�O���ׂ������������������Ƃ͂ł��Ȃ����A�ߋ��ɌY���i�ǂ��Ċ��Ɋm�蔻�����o���d�Ŏ��Ă�v�i�nj̈ӎ��Ăł���Ɖ������Ƃ��Ă��A���̂悤�ȑd�Ŏ��Ăɂ��āA�ēx�A�Y����̐ӔC��Njy���邽�߂ɑi�ǂ��邱�Ƃ����e���邱�Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ�����A�����I�ɂ��A�ߋ��ɌY���i�ǂ��Ċ��Ɋm�蔻�����o���d�Ŏ��Ă�v�i�nj̈ӎ��Ă��珜�O���ׂ������͂Ȃ��B�������āA�����̉��߂ɂ��A�L�߂̊m�蔻�����o�Ă��炸�A�����A���߂ƂȂ�\�����Ȃ��Ƃ͂����Ȃ��d�Ŏ��ĂɌW��d�ō��������̑ΏۂƂ������ŁA�L�߂̊m�蔻�����o���d�Ŏ��ĂɌW��d�ō��������̑ΏۂƂ��邱�Ƃ��ł��Ȃ����ƂɂȂ�Ƃ���A������A���͕s�����ł���Ƃ��킴��Ȃ��B�v �@���_3�F�{���ۑS�����ΏۊO���d�ł̕s���݂𗝗R�Ƃ��āA�{���e�����͈�@�ƂȂ邩�B �@�u�i�P�j�����@�P�P���P�R���́A�����Ώێ҂́A�����@��̏����ɂ��Ă̕s���\���ċy�ёi���ɂ����āC���Y�����Ώێ҂ɌW�鋤���ΏۊO���d�ł̑��ۖ��͊z�����Y�����ΏۊO���d�łɊւ���@�߂ɏ]���Ă��邩�ǂ������咣���邱�Ƃ��ł��Ȃ��|���߂Ă���Ƃ���A�{���i���́A�����@��̏����ł���{���e�����ɂ��Ă̑i���ɊY�����邩��A�����́A�{���i���ɂ����āA�{���ۑS�����ΏۊO���d�ł̑��ۖ��͊z���{���ۑS�����ΏۊO���d�łɊւ���@�߂ɏ]���Ă��邩�ǂ������咣���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B �i�Q�j�����ŁA�Ŗ��s�����s�������Q�R���Q���́A���̏��Ɋ�Â��v�������̂����[�u�A���ɁA�����̕���Ɋ֘A���āA�����ΏۊO���d�ō��̑��ݎႵ���͊z���͂��̎��s�������Ɋւ��č̂�ꂽ�[�u�i�d�ō��̑��y�ѐŊz���m�肷����ʂ�L����ېŏ������̑��̑[�u�i�ȉ��u�ېŏ������v�Ƃ����B�j�͂���ɊY������c�c�B�j�ɂ��Ă̑��ׂ̎葱�́A�v�����̓K���ȋ@�ւɂ̂ݒ�N���邱�Ƃ��ł���|���߂Ă��邩��A�����́A�����̑[�u�ɂ��ĕs��������ꍇ�ɂ́A�v�����ł���؍��̓K���ȋ@�ւɑ��ׂ̎葱���N���ׂ��ł����āA�䂪���ɂ����āA�����̑[�u�ɂ��Ă̑��ׂ̎葱���N���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B �i�R�j���������W�K��̍\���ɏƂ炷�ƁA�v�����ł���؍��ɂ����āA�{���ۑS�����ΏۊO���d�ł̑��y�ѐŊz���m�肷��ېŏ�����������Ă���ꍇ�ɂ́A�䂪���̍ٔ����ɂ����āA�{���ۑS�����ΏۊO���d�ł̑��ۋy�ъz�ɂ��A���Y�ېŏ������Ɩ����������f�����邱�Ƃ͑z�肳��Ă��Ȃ��Ƃ����ׂ��ł��邩��A�{���i���ɂ����āA�{���ۑS�����ΏۊO���d�ł̕s���݂͖{���e�����̈�@������b�t���鎖��ɂ͂Ȃ�Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���B �@�����āA�{�������v�����ɂ́A�{���ؔ[�O���d�ŋy�т���ɂ��Ă̌����ɑ����[�ŋ`���ɂ��āA�؍��̍��Œ��ɂ��ېŏ�����������Ă���|�̋L�ڂ�����Ƃ���c�c�A���L�ڂ̓��e���������|�̓����Œ��̐錾�c�c���������ŁA���L�ڂ��q�ϓI�����ɔ����邱�Ƃ��������킹��I�m�ȏ؋��͂Ȃ�����A�؍��ɂ����āA�{���ۑS�����ΏۊO���d�ł̑��y�ѐŊz���m�肷��ېŏ������͂���Ă�����̂ƔF�߂���B �i�S�j���������āA�{���ۑS�����ΏۊO���d�ł̕s���݂𗝗R�Ƃ��āA�{���e��������@�ƂȂ邱�Ƃ͂Ȃ��B �i�T�j�Ȃ��A�����́A�{���e�������ɂ����āA�{���ۑS�����ΏۊO���d�ō��̉ېŗv�����������݂��Ă��Ȃ��ꍇ�ɂ́A�{���ۑS�����ΏۊO���d�ł�ۑS�����̑ΏۂƂ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ƃ̌�����O��Ƃ��āA�{���ۑS�����ΏۊO���d�ł�ۑS�����̑ΏۂƂ����{���e��������@�ȏ����ł���|���咣���Ă�����̂Ɖ�����邪�A������咣�́A�O�L�i�P�j����i�R�j�܂łɂ����Đ��������W�K��̍\���ɔ������Ǝ��̌����ł���Ƃ��킴����A�̗p���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�����Ƃ��ẮA�{���ۑS�����ΏۊO���d�ō��̑��y�ѐŊz�ɕs��������̂ł���A�v�����ł���؍��ɂ����āA�K���ȋ@�ւɑ��A�����̓_���m�肷����ʂ�L����ېŏ������ɂ��Ă̑��ׂ̎葱���N���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���B�v |