「ダイエットと健康」
発表者:石井沙奈枝(01DA018Y),古田麻美(01DA135W),森高(01DA158E)
1.仮説
現在、人々の中に「痩せている」=「美しい」という価値観がかなり深く浸透していると思う。メディアに登場するタレントや俳優やモデルなどの中で、人々の理想や憧れの的となっている人の多くは痩せ型であることからも、この価値観は大なり小なりメディアに影響されていると言えるのではないだろうか。特に体型を意識するのは男性よりも女性に多いと思うのだが、女性にとっては特に「痩せる」ということが外見的な美しさの重要な要素になっていると思う。
このような時代の流れの中で、身体の美しさを求めるアプローチの仕方が近年は変化していて、人々の身体に対する価値観も以前とは異なるものになっていると私たちは考える。美しさを求めるためにダイエットをする人は多いが、以前はダイエットと健康というものは別物であり、特にダイエットを強く意識する人にとって健康は二の次の話であったと思う。しかし最近ではダイエットの方法も次々と新しいものが生まれ、身体の美しさに対しても単に外見的な美しさだけでは本当に美しいとは言えず、からだの中身まで美しくあることで初めて本当の美を達成できるという「健康」に重点をおいた志向がうまれてきた。日常的によく耳にするようになった「血液サラサラ」、「血液ドロドロ」といったような言葉はからだの中身も美しくありたいと思わせる格好の表現であると思う。このようなことから現在はダイエットと健康は共に果たされるべきだという考えが一般的になってきたのではないかと思う。私たちはこの考えを仮説とし、実際にどのようにダイエットと健康が結びついているのか、ダイエットのあり方や意識はどのように変わってきたのか、メディアによって与えられてきた影響はいかなるものか等の点について調べていこうと思う。
![]() 2.ダイエットの歴史
2.ダイエットの歴史
![]() 中世
中世
大食は罪とされたが、過度の快楽を戒めるものであり、体形を責めるものではなかった。
ルネッサンス
体重を意識してダイエットをするようになったのはこの頃からである。ダイエットは、男性のものとされていた。男性は自分の意志で太ったりやせたりできるとされたが、女性は受動的で自分の身体をコントロールできないと考えられていた。
十九世紀(第一次世界大戦まで)
イタリア・ルネッサンスのダイエットは、イギリスを経て、アメリカに伝わった。近代に入って、食糧事情がよくなり、女性も自由に食べることができるようになり、体格もよくなり、女性のダイエットが生じた。アメリカ人は、食物の生産が豊かであったこともあり、非常に大食であった。そのため、消化不良、胃の重苦しさに悩み、それを解消するために、内と外の両面から消化を良くし、軽やかな身体を取り戻そうとした。女性は、できるだけ薄着をし、乗馬や水泳をして、活動的になっていった。
南北戦争の時期には、エクササイズが盛んになった。大食は肥満になるから悪とされ、スリムになるためのダイエットがあらわれた。消化剤や消化にいいとされた民間の薬草がそのままダイエットに使われた。また、この頃から節食も行われるようになり、ダイエットのために水分を取るか取らないかが問題になった。朝食を抜き、一日二食にするといったダイエット法がアメリカの女性の間で流行った。体操も盛んになり、自転車こぎ、ジョギング、体操、エクササイズ・マシンなどが取り入れられた。マッサージは、消化不良や神経衰弱の治療に行われていたが、九十年代からやせるために使われるようになる。やせるためのマシンも次々と開発された。そして、ダイエットの残りのフィールドは、心である。世紀末から神秘主義が盛んになるとともに、マインド・キュア(霊的治療法)への関心が高まった。薬、食事、マインドといった領域において、さまざまなダイエット法が出てくる。
1880年から1920年までの過渡期に、消化不良治療からつくられた過去のダイエット法とはちがう、断食、フレッチャーリズム、カロリー計算などが登場した。断食はダイエットの極端な形で、劇的で英雄的な表現を生む。ダイエットにヒロイズムが漂うようになった。フレッチャーリズムは、よくかんで食べるというものである。完全な咀嚼は、身体を純化し、軽くすると信じられていた。また、どの栄養素を取れば太るというわけではなく、全体のカロリーが多いと太ると考えられ、カロリー計算に合わせて食べるというダイエットがあらわれた。
第一次世界大戦は、ばらばらにはじまっていたダイエット運動を一気に加速させた。配給制度などが導入され、無駄遣い、贅沢は社会的にも批判され、太っていることは非国民とされた。ダイエットは道徳的にも支持されるようになった。それらに加え、広告宣伝技術の開花によって、肥満、消費は悪という社会的イメージのキャンペーンがくりかえされ、潜在的な強迫観念も刷り込まれていった。
1920年代
女性の社会進出は、食生活、ダイエットにも影響を与えた。女性にとって性的魅力が重要になり、スリムで若々しいことが理想となった。高度消費社会のはじまりの中でダイエットが産業になってきた。
1930年代
女性の理想像は、グラマーといわれ、成熟した大人の女の魅力が理想とされた。よりいっそうのダイエットと体形をつくるのコルセットなどの下着が必要になった。ダイエットが、身体だけでなく、心・魂の問題であることが強調されるようになった
1940年代
この頃からダイエットのためのグループ・セラピーが行われるようになった。ダイエットが力点を身体から心に移し、共同幻想にかかわることで、サイコセラピーやグループ・セラピー、カルトなどに近づいてくる転換期。
1950年代
美容整形が注目されはじめる。ダイエットとエステと美容整形が連携するようになる。身体は形成されるものとなり、自己表現となってくる。マリリン・モンローが時代のシンボル。女らしいシルエットが理想とされ、ダイエット・ブームが少し下火になったが、50年代末にダイエット・ブーム再来。
1960年代
モデルのトウィッギが一大ムーブメントとなり、若さとスレンダーを求め、女性は過激なダイエットを行うようになった。強力なやせ薬や美容整形の一般化など、人工的なものの支配が強まった。その反動で、ピッピー文化などでナチュラルな生活が目標とされ、身体を意識した健康志向が強まった。
1970年代
拒食症や過食症が社会問題になってくる。スリムで若い特徴は続き、60年代よりいくらかナチュラルなシルエットが理想になったが、体重は減りつづけた。ダイエット食品が大企業化し、ダイエットが一般生活そのものとなった。
1980〜1990年代
ダイエットやその逸脱は、精神の問題となり、一般的な社会問題になった。摂食障害の一般的知識が普及した。この頃のダイエットは、単に減量するのではなく、エクササイズをし、シェイプアップするといった特徴を持っていた。ダイエットが、精神、心、脳といった内部的なものを強調するようになり、客観的、科学的でなくてもいいことになり、誰でも参加できるようになった。そのようなことから有名人など素人がダイエット本を出すようになった。裏づけのない主観的な方法がまかり通るようになり、さまざまなダイエット法があらわれる状況がうまれた。
(参考文献 海野弘『ダイエットの歴史 みえないコルセット』1999年 新書館)
3.ダイエット産業について
近年、健康食品産業は拡大している。人々の健康に対する意識は高まっていて、さまざまな健康ブームが話題を読んでいる。健康食品産業の拡大については以下に列挙するような点が影響しているのではないかと考える。まず最近雑誌などに健康食品や健康に関する内容が頻繁に取り上げられるようになったこと、またダイエットを特集する記事の中に“からだの中身からきれいになろう”といった健康面の要素が盛り込まれるようになったこと、さらには2003年4月から医療費の自己負担率が2割から3割に上昇したことや、同年5月から健康増進法が施行されたことなどである。これらによって人々が今までよりも積極的に自身の健康維持について考えさせられる環境になってきたのではないかと思う。健康食品市場は現在1兆円以上の市場規模を持ち成長を続けているが、その背景には健康維持に関する食事の重要性について、国民の意識が高まっていることがあげられる。すなわち食事に対する意識の変化が健康食品産業の発展に影響していると考えられるので、ここでは健康食品産業=ダイエット産業と仮定して考えてみようと思う。
健康食品産業はなぜ発展したのか。その答えを見つける鍵は社会の変動という点にある。ここ数十年で社会は大きく変化してきている。産業が発展し各企業が利益を生むためにこぞって様々な効率化を図ろうとしたり、女性が家庭に簡単に入るのではなく積極的に社会に進出したりするようになった。(以下のグラフ参照)そんな中で加工食品や保存食品、冷凍食品、レトルト食品、インスタント食品などの手軽に作れるものがその便利さから人気になったが、この人気が食生活に変化をもたらし、肥満や生活習慣病の増加といった問題を生み出す大きな一要因になったのである。また同時にテレビの影響も大きいだろう。現在報道されている健康に関する情報を提供するテレビ番組の多くが、かなり詳しい科学的な説明を織り交ぜながら健康と食事に関する専門的な知識を人々に与えようとしている。このような状況の中で、以前よりもカテキンやポリフェノールなどの栄養成分に関する知識が人々に浸透しつつあると思う。このような環境の変化が大きな要因となり、人々の健康に対する意識が高まっていったのではないだろうか。
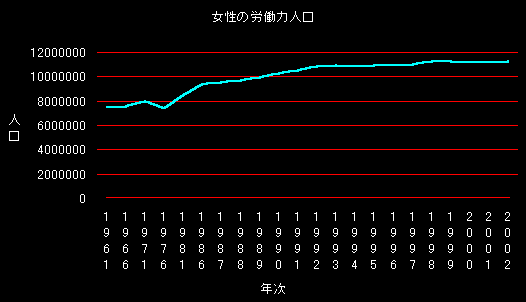
また人々が健康志向であることは商品の売上からも見て取れる。花王では、1999年に発売した料理油の「エコナ」や2003年に発売した「ヘルシア緑茶」が大ヒットし、ヘルスケア・健康食品市場への展開が成功している。「ヘルシア緑茶」はカルピスウォーター以来の飲料業界最大級のヒットと言われているが、このヒットの要因を花王は「現在のダイエットブームにある」としている。この言葉からも健康とダイエットが密接な関係を持っていることがわかる。
4.ダイエットに対する意識
2003年年末の読売新聞に以下のような記事が掲載されていた。
|
|
適正な体重の15―19歳の女性のうち、70%以上が、「自分は太っている」と感じていることが、厚生労働省の国民栄養調査で分かった。20歳代の女性も同じ傾向で、ともに五年前の調査に比べ10ポイント以上増えている。同省は「やせていることが美しいと思う女性がますます増えている」と分析している。 |
女性の「痩せていることが美しい」という認識に基づく、ダイエットへの関心はとどまる事を知らない。ここでは女性のダイエットに対する意識について探ってみたいと思う。先に述べられているように、ダイエット方法は以前の過激で偏りのあるダイエットから健康的なものへと変化してきている。特に、以前過激なダイエットを行っていた20~30代の女性は、過去の経験から健康的なダイエットへの志向が強い。その年代の女性が興味を持つダイエット方法として、「ウォーキングなどの有酸素運動や半身浴」「サプリメントなどの利用」が挙げられている(ロート製薬による10〜40代女性1,447人へのインターネット調査・02年11月)。これは過半数以上の人が「すぐに効果があっても健康を害するようなダイエットは避けたい」と考えているためで、特に30代では過去に無理なダイエットをして体調を崩したなどの経験があり、健康的なダイエットを支持する人は20代よりも10%以上多いという結果が出ている。さらに、一時流行した中国の痩せ薬など、ダイエット薬の安全性に対する不安の声も多い。そういった点からも、過激な薬に頼らないダイエット、摂取しても害のないサプリメントを利用し、「美しく痩せる」ダイエットの傾向に拍車がかかっているのではないだろうか。
また、こういった女性はどこからダイエットに関する情報を入手しているのか尋ねたところ、以下のような結果となった。
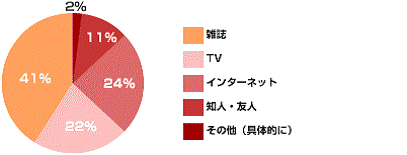
この図を見てわかるように、約6割の人が雑誌やテレビといった、頻繁にダイエット特集をする媒体を挙げている。インターネット上で行われた調査なのでインターネットを挙げる人も多いが、やはり匿名性が高く、雑誌等に比べると信頼性に欠けるところもあるため、知人・友人からというのと合わせて口コミとして参考にしているようだ。出版社やテレビ局にとっても販売部数や視聴率に結びつく企画であり、また読者や視聴者としても、実際に試して効果を検討する企画や効果的なダイエット方法紹介といった、さまざまな情報を入手できるという利点が挙げられる。また、ダイエット特集を定期的に組み、その都度話題のダイエット方法を紹介することで読者や視聴者の関心を維持しているとも考えられる。さらに、痩せた女性タレントやモデルを起用することで「ああいうスタイルになりたい」という女性の願望を肥大化させ、ダイエット特集への関心を高めるというサイクルを繰り返していることも行われている。人々の痩せたい願望を維持できるよう、メディアがダイエット・ブームを作り続けていくことが可能ならば、今後も女性の痩せたいという意識の流れは続くものだと考えられる。
3.結論
以上のことから、最近では「痩せている=美しい」という考えに加え、ダイエットと健康は共になされるべきだという考えが人々に浸透していることがわかった。そして、その背景にはダイエットの産業化とコマーシャリズム、メディアがあり、人々の理想の体形やダイエットに対する意識などに影響を与えてきた。
そもそも一般的なダイエットは、健康になるために痩せるといったところからはじまった。その起源からもダイエットと健康は切っても切り離せない関係にあるのだ。ところが、ダイエットが一人歩きしはじめ、美さを手に入れるためのダイエットに変わっていった。メディアの発達によって人々に共通した理想の体形が作り上げられ、高度消費社会によってダイエットは産業化し、消費されていった。そしてダイエットがエスカレートしていき、ときに死にいたるケースもあった。そんなことから、ダイエットを見直そうという考えが出てき、再び健康とダイエットが結び付いた。健康ブームとダイエットブームが結び付き、結果、相乗効果で市場はさらに拡大した。
現在、健康的に痩せるためのダイエット方法は、ダイエット本が出版されたり、女性雑誌に掲載されたり、健康番組で紹介されたり、どんどん生まれ続けている。昔のダイエット方法が焼き直されたものもあるが、最近では科学的根拠から、手軽に、健康的に痩せるダイエット方法が目立つ。高濃度カテキンを毎日摂取すると、一ヶ月で〇kgやせる、それはカテキンが脂肪を分解するからだといった専門家の科学的な説明が登場してくる。ダイエット方法が再び健康と結び付いたことによって、科学的根拠を押し出したものが増えてきた。科学的根拠を価値基準におく現代人にとって、科学的根拠のあるダイエット法は、最も説得力があり、信ずるべきものなのだ。
あるダイエット方法が生まれ、それを信じるものが生まれ、そのダイエット方法が布教されていく。信じるもの(信者)がいるから、さまざまなダイエット方法がどんどん生まれるのだ。そして、科学という現代の絶対的価値が加わり、ダイエットはさらなる広がりを見せている。健康とダイエットは、メディアよって人々の価値観が形成され、産業化し、消費される。それがいつも繰り返されつづけている。理想が簡単に手に入らないためであり、ブームは常に変化するからだ。そろそろ人々が健康や美しさについて自分で見つめなおす時期なのではないだろうか。