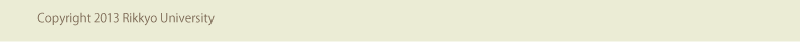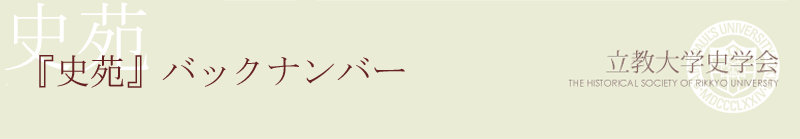
30-2/ 30-1/
29-2/ 29-1/
28-2/ 28-1/
27-2/ 27-1/
26-2/ 26-1/
25-2/ 25-1/ 24-2/ 24-1/ 23-2/ 23-1/ 22-2/ 22-1/ 21-2/ 21-1/
25-2/ 25-1/ 24-2/ 24-1/ 23-2/ 23-1/ 22-2/ 22-1/ 21-2/ 21-1/
| 第30巻 第2号(1970年3月刊) | |
| 論文 | |
| 別技 篤彦 | ラッフルズのスマトラ研究 ――第1部 ベンクレーンを中心として―― |
| 冨所 治 | ロウア・サウスの分離運動に関する一考察 ――陰謀説の再評価を中心として―― |
| 目録 | |
| 日本史研究室 | 立教大学図書館所蔵文書概要2 |
| ▲ | |
| 第30巻 第1号(1969年6月刊) | |
| 論文 | |
| 田畑 勉 | 宝暦・天明期における加賀藩財政の意義 |
| 奥村 哲 | 豊臣期前田政権の地方支配に関する考察 |
| 研究ノート | |
| 渡辺梨枝子 | 尾張鳴海における一酒造業の展開 ―「千代倉」東店家を中心として― |
| 目録 | |
| 日本史研究室 | 立教大学図書館所蔵文書概要 |
| ▲ | |
| 第29巻 第3号(1969年3月刊) | |
| 論文 | |
| 手塚 隆義 | 孫権の夷洲・亶洲遠征について |
| 遠矢 徹志 | 幕末におけるキリスト教再伝来について |
| 佐々木 克 | 「民・蔵分離問題」についての一考察 |
| 柴田 徳 | 転換期としての平安初期東国の一考察 |
| 高瀬 保 | 越中・小山出土の露卯の下駄 |
| ▲ | |
| 第29巻 第2号(1969年1月刊) | |
| 論文 | |
| 別技 篤彦 | ラッフルズの「ジャワ誌」にあらわれたジャワの風土と人口の記述について ――ラッフルズ研究 その三―― |
| 中田 栄一 | 利根川流域の集落に関する諸問題(その2) ――工業化と村落―― |
| 正井 泰夫 | 言語別・文字別にみた新宿における諸設営物の名前と看板広告 |
| 石川 栄吉 | メラネシアの村落構造 ――土地所有を中心に―― |
| 保柳 睦美 | 伊能忠敬と根気 |
| 昭和四十三年度立教大学史学会大会発表要旨 | |
| ▲ | |
| 第29巻 第1号(1968年10月刊) | |
| 論文 | |
| 井上 幸治 | フランス革命研究の反省 ――ルソー,ロベスピエールをめぐって―― |
| 若原 英明 | クロムウェル政権の財政問題 |
| 西川 進 | 1840年代のニュ−オ−リンズの地位とその役割 ――アメリカ産業革命期の市場構造をめぐって―― |
| 関水 斉 | 中西部穀物生産地帯の形成過程について −十九世紀中葉イリノイ州の場合− |
| ▲ | |
| 第28巻 第2号(1968年3月刊) | |
| 論文 | |
| 保柳 睦美 | 西域の歴史時代における自然の変動 |
| 石橋 秀雄 | 清初のアハ(aha)―特に天命期を中心として― |
| 書評 | |
| 石川 栄吉 | 宮本馨太郎・八幡一郎共著『日本の民具第四巻 周囲民族』 |
| 昭和四十二年度立教大学史学会大会研究発表要旨 | |
| ▲ | |
| 第28巻 第1号(1967年12月刊) | |
| 立教大学の創生 | |
| 海老沢有道 | 立教史学誕生;立教史学前史 |
| 大久保利謙 | 立教史学誕生;大正末期史学界の状況 |
| 森田 優三 | 史学創設と「史苑」刊行;震災前の池袋r. |
| 江戸川乱歩 | 史学創設と「史苑」刊行;大正末期の池袋r. |
| 松崎 一雄 | 史学創設と「史苑」刊行;大正十五年頃の池袋 |
| 佐藤 庸哉 | 史学創設と「史苑」刊行;昭和四年頃の池袋r. |
| 柴田 亮 | 史学創設と「史苑」刊行;「史苑」の創刊ごろの会計 |
| 手塚 隆義 | 立教史学の創生:昭和零年;嵐の前の静寂 |
| 大沢 洋三 | 立教史学の創生:昭和零年;昭和初期の学生 |
| 楜沢 竜吉 | 立教史学の創生:昭和零年;詩と史 |
| 海老沢有道 | 立教史学の創生:昭和零年;史学同好会の活動 |
| 遠矢 徹志 | 立教史学の創生:昭和零年;史学科学生時代 |
| 金田福太郎 | 立教史学の創生:昭和零年;恥かし昔ばなし |
| 田村 武敦 | 立教史学の創生:昭和零年;想い出の小箱 |
| 大木 一郎 | 立教史学の創生:昭和零年;史学科時代 |
| 十河 佑貞 | 立教史学の創生:昭和零年;研究室の思い出 |
| 暗い時代の学生と大学 | |
| 手塚 隆義 | 戦争と大学;戦争への道と大学 |
| 島田 芳子 | 戦争と大学;立教時代の島田雄次郎 |
| 田辺 広 | 学徒出陣と文学部休止;二か年半の立教 |
| 林 英夫 | 学徒出陣と文学部休止;友人たちと先生 |
| 高橋巳壽衛 | 学徒出陣と文学部休止;飯島大佐と資本論 |
| 宮本馨太郎 | 学徒出陣と文学部休止;戦中日記抄 |
| 伊東多三郎 | 学徒出陣と文学部休止;戦中の日記 |
| 手塚 隆義 | 学徒出陣と文学部休止;文学部は消える |
| 手塚 隆義 | 「史苑双書」と史学科再生;再生と「史苑双書」 |
| 海老沢有道 | 「史苑双書」と史学科再生;史学科復活運動 |
| 海老沢有道 | 「史苑双書」と史学科再生;史学科の再生 |
| よみがえる立教史学 | |
| 井上 幸治 | 混迷の中に道を求めて;戦後の史学界 |
| 小林 通雄 | 混迷の中に道を求めて;混乱期の学生 |
| 竹田 鉄三 | 混迷の中に道を求めて;神父のみた戦後の立教 |
| 山田 昭次 | 混迷の中に道を求めて;混迷の中の学生 |
| 野村 悦子 | 女子学生の登場;二番目の女子学生として |
| 宮川 澄 | アンポハンタイの叫び;この目でみた暴力 |
| 野口 尚 | アンポハンタイの叫び;警官隊に追われて |
| 久留間 忍 | アンポハンタイの叫び;この手で闘った安保 |
| 本多 耕治 | 戦後の学生生活;古文書に取りくんだ学生時代 |
| 奥村 哲 | 戦後の学生生活;古文書・民俗調査の回想 |
| 野村 忠弘 | 戦後の学生生活;地理巡検の思い出 |
| 清水 正巳 | 戦後の学生生活;ペリ-さんとボクの学生時代 |
| 松浦 高嶺 | 教師から学生へ;西洋史の学生たち |
| 別技 篤彦 | 教師から学生へ;現在の学生に望むこと |
| 清水 博 | 西洋史学専攻大学院の開設 |
| 中田 栄一 | 地理学専攻課程の成立 |
| 中川 成夫 | 史学科と博物館学講座 |
| 別技 篤彦 | アジア地域総合研究施設の設立 |
| 北島 正元 | 親からみた立教大学;娘の大学 |
| 稲田 正次 | 親からみた立教大学;娘の大学 |
| 立教大学史学会小史(編集部担当部分)・史苑総目録 | |
| ▲ | |
| 第27巻 第3号(1967年3月刊) | |
| 論文 | |
| 岡本 勇 | 弥生時代石製工具の意義 |
| 加藤 晋平 | 日本におけるルバロワ技法の問題 ―星野第三地点出土遺物の位置― |
| 大塚 和義 | 繩文時代の葬制 ―埋葬形態による分析― |
| 田畑 勉 | 幕末期における知多木綿生産者と価格形成について |
| 史料紹介 | |
| 山田 昭次 | 横浜連合生糸荷預所事件と自由民権派諸新聞の論調(三) |
| 昭和四十一年度立教大学史学会大会発表要旨 | |
| ▲ | |
| 第27巻 第2号(1966年12月刊) | |
| 論文 | |
| 村本 竹司 | アメリカ国民経済の形成について |
| 第十七回西洋史学会 | |
| 清水 博 | 日本西洋史学会第十七回大会を主催して |
| 松浦 高嶺 | イギリス史部会報告 |
| 米川 伸一 | イギリス史部会に参加して |
| 武本 竹生 | フランス史部会報告 |
| 遅塚 忠躬 | フランス史部会に参加して |
| 富田 虎男 | アメリカ史部会報告 |
| 井上 幸治 | 共同討議の開催にあたって |
| 共同討議 | |
| 武本 竹生 | はしがき |
| 江口 澄・小林 基男 関水 斉・山本 晃子 | 一 ヴルジョワ的発展について |
| 若原 英明 | 二 市民革命について |
| 村本 竹司 | 三 「国民経済」について |
| 関水 斉 | むすび |
| ▲ | |
| 第27巻 第1号(1966年6月刊) | |
| 論文 | |
| 手塚 隆義 | 南匈奴の「故胡」と「新降」とについて |
| 平井 尚志 | モンゴ−ルによるモンゴリアの考古学 ――現状とその問題点―― |
| 駒井 和愛 | 渤海中京顕徳府即遼陽説について(補) |
| 松浦 高嶺 | ピュ−リタニズムにかんする最近の諸解釈 |
| 史料紹介 | |
| 山田 昭次 | 横浜連合生糸荷預所事件と自由民権派諸新聞の論調(二) |
| ▲ | |
| 第26巻 第2・3号(1966年1月刊)史学科創設四十周年記念特集号 | |
| 論文 | |
| 駒井 和愛 | 渤海中京顕徳府即遼陽説について |
| 田中 克己 | 遷界令と五大商 |
| 和田 久徳 | 宋朝に知られたジャワ語の二三について |
| 石橋 秀雄 | 清代漢人官僚に関する一考察 ―特に漢人進士と督・撫との関係について― |
| 宇都木 章 | 墨子尚賢論の一側面 |
| 久保 靖彦 | 戊己校尉設置の目的について |
| 大久保利謙 | 中村敬宇の初期洋学思想と『西国立志編』の記述及び刊行について ―若干の新資料の紹介とその検討― |
| 海老沢有道 | 「天主実義」雑考 ―特に日本との関連において― |
| 宮本馨太郎 | 朝鮮における頭髪の輸出と加髢の禁 |
| 中川 成夫 | 伊豆宗光寺横穴群の調査 ―後期古墳群の研究(4)― |
| 別技 篤彦 | ポルトガル領時代のマラッカ(マラッカの研究その2) ―アジアにおけるヨーロッパ植民地の原型― |
| 中田 栄一 | 建具工業地域の特質とその地理的基底 |
| 昭和四十年度立教大学史学会大会研究発表要旨 | |
| ▲ | |
| 第26巻 第1号(1965年7月刊) | |
| 論文 | |
| 中川 成夫 | 奥州平泉中尊寺大長寿院の一考察 |
| 藤井 基旦 | 清教徒革命期における地方政治の一考察 ――州委員会を中心として―― |
| 田畑 勉 | 河川運輸による江戸地廻り経済の展開 ――享保・昭和期を分析の対象として―― |
| 史料紹介 | |
| 山田 昭次 | 横浜連合生糸荷預所事件と自由民権派諸新聞の論調(一) |
| ▲ | |
| 第25巻 第3号(1965年3月刊) | |
| 杉山 博 | 相模国高座郡渋谷庄について |
| 若原 英明 | イギリス革命の革命勢力(下) |
| 海老沢有道 | マノエル・アキマサと賀茂在昌 |
| 山田 昭次 | 「東京横浜毎日新聞」社説目録 |
| ▲ | |
| 第25巻 第2号(1964年11月刊) | |
| 論文 | |
| 手塚 隆義 | 日逐王比の独立と南匈奴の単于継承について |
| 小山 悳子 | キリシタンにおける罪意識 |
| 山田 昭次 呉屋治美 | 「東京横浜毎日新聞」社説目録(一) |
| 別技 篤彦 | 中近東の旅から |
| 昭和三十九年度立教大学史学会大会 | |
| 研究発表要旨 | |
| ▲ | |
| 第25巻 第1号(1964年5月刊) | |
| 論文 | |
| 村本 竹司 | 南北戦争前夜南部の分離運動について ――その一、奴隷制「南部」諸州の基礎構造―― |
| 昭和三八年度立教大学史学会大会 | |
| 共同論題「近代化の再検討」報告の発表にあたって | |
| 富田 虎男 | アメリカ独立革命の前提(一) |
| 若原 英明 | イギリス革命の再検討 |
| 武本 竹生 | ノルマンディにおける都市工業と農村工業 −一七八九年の陳情書の分析− |
| 山田 昭次 | 立憲改進党における対アジア意識と資本主義体制の構想 |
| ▲ | |
| 第24巻 第3号(1964年3月刊) | |
| 論文 | |
| 中田 栄一 | 九十九里平野における農村工業の展開 |
| 若原 英明 | イギリス革命の革命勢力(上) ――諸派の改革案の検討―― |
| 史料紹介 | |
| 山田 昭次 | 立志社関係史料 |
| 松浦 高嶺 | イギリス便り(第四信) |
| 立教大学史学会大会 | |
| 市井 三郎 | 歴史における法則と人間主体 ――歴史哲学の観点から――(公開講演要旨) |
| 研究発表要旨 | |
| ▲ | |
| 第24巻 第2号(1963年12月刊) | |
| 論文 | |
| 別技 篤彦 | ラーデン・アジェン・カルティニの思想における国土と民族 ――インドネシア民族運動史の序章―― |
| 中川 成夫 | 信濃川中流域の遺跡遺物 ――新潟県小千谷市内における考古学的調査―― |
| 研究ノート | |
| 高瀬 保 | 越中・中沖出土の露卯の下駄 |
| 資料紹介 | |
| 平井 宣子 | 池袋(東)貝塚について |
| 松浦助教授の欧州便り | |
| 米国史関係欧文雑誌論文目録 | |
| ▲ | |
| 第24巻 第1号(1963年7月刊) | |
| 論文 | |
| 海老沢有道 | 『ドチリナキリシタン』をめぐって |
| 久保 靖彦 | 後漢初頭の烏桓について ――御烏垣校尉に関する一考察―― |
| 中川 成夫 | 新潟県魚野川流域古墳群の調査 ―――後期古墳群の研究(3)―― |
| 宮本馨太郎 | 三宅島坪田の生活(聞書) |
| ノート | |
| 梅沢 純子 | 捕鯨に関する神事・芸能について |
| ▲ | |
| 第23巻 第2号(1963年3月刊) | |
| 論文 | |
| 別技 篤彦 | マラッカ――その成立と発展 ――十五世紀のイスラム王国時代を中心として―― |
| 手塚 隆義 | 親魏倭王考 |
| 中田 栄一 | 山村の変貌 |
| 立教大学史学会研究発表要旨 | |
| 目録 | |
| 海老沢有道 | 高橋五郎著訳書目録 |
| ▲ | |
| 第23巻 第1号(1962年9月刊) | |
| 論文 | |
| 松浦 高嶺 | 清教徒革命における宗教上の独立派 ――Independencyについての一考察―― |
| 独立革命史の史学史的再検討 | |
| 清水 博 | まえがき・結び |
| 市橋 靖子 | 一、独立革命 |
| 大原 祐子 | 二、連合の時代 |
| 西川 進 | 三、憲法の制定 |
| 富田 虎男 | 四、戦後のわが国におけるアメリカ史研究 |
| 清水 博・富田虎男 | 結び |
| 米国史関係欧文雑誌論文目録 | |
| ▲ | |
| 第22巻 第2号(1962年1月刊) | |
| 論文 | |
| 海老沢有道 | 明治反動期におけるキリスト教教育の一齣 ――立教学校文学会刊『八紘』紹介を兼ねて―― |
| 大久保利謙 | 五代友厚の欧行と彼の滞欧手記『廻国日記』について |
| 中川 成夫 | 島根県牧谷古墳群の調査 ――後期古墳群の研究(2)―― |
| 書評 | |
| 山田 昭次 | 林英夫著『近世農村工業史の基礎過程』 |
| 一九六一年度立教大学史学会大会研究発表要旨 | |
| ▲ | |
| 第22巻 第1号(1961年9月刊) | |
| 論文 | |
| 手塚 隆義 | 中国の虞と夷蛮の呉 |
| 別技 篤彦 | シンガポ−ル占拠に至るまでのラッフルズの地域選択の歴史 −一八一八−十九年における彼の行動を中心として− |
| 宮本馨太郎 | 露卯下駄の終焉 |
| 資料紹介 | |
| 平井 尚志 | 資料室新収イラン及びアナウ出土考古遺物解説 |
| 米国史関係欧文雑誌論文目録 | |
| ▲ | |
| 第21巻 第2号(1960年12月刊) | |
| 論文 | |
| 大久保利謙 | 文書から見た幕末明治初期の政治 ―明治文書学への試論― |
| 海老沢有道 | 阿部真造 ―維新前後における一知識人の足跡― |
| 中田 栄一 | 機業圏の地理的基底 ―関東地方における事例から― |
| 中川 成夫 | 新潟県頸城古墳郡の調査 ―後期古墳群の研究(1)― |
| 立教大学史学会大会公開講演要旨 | |
| 高橋幸八郎 | 封建制から資本制への移行 ―第十一回国際歴史学会議をめぐって― |
| ▲ | |
| 第21巻 第1号(1960年9月刊) | |
| 論文 | |
| 清水 博 | アメリカにおけるナショナリズムの成長 |
| 有賀 貞 | 革新主義運動の一考察 |
| 西川 進 | ファクトレッジ・システムから見たる旧南部の経済構造の一断面 |
| 研究ノート | |
| 冨所 治 | 分離運動研究の一前提 ――ダモンドの著作を中心に―― |
| 論文 | |
| 高橋 秀 | ロ−マ帝政期ビティニアにおける都市化について |
| 研究ノート | |
| 若原 英明 | イギリス革命における革命思想 |
| 米国史関係欧文雑誌論文目録 | |
| ▲ | |