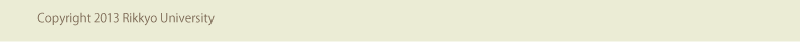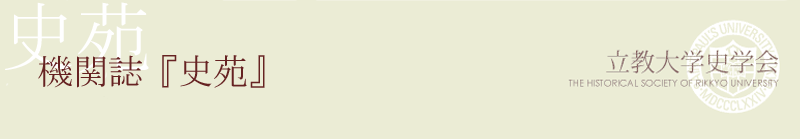
機関誌『史苑』とは
『史苑』とは、1928(昭和3)年より発行している歴史ある機関誌です。
現在は、年2度の発行を原則とし、論文、研究ノートほか様々なジャンルによって構成されております。
※なお、『史苑』の題字は、第2巻1号から「嵯峨天皇」の筆蹟に変わり、現在まで続いております。(『立教大学史学会小史』12頁)
※業務省力化のため、日常業務としてバックナンバー販売を取りやめておりますのでご了承ください。
E-mail /rshigakkai@rikkyo.ac.jp
『史苑』最新号
| 第85巻 第2号 (2025年3月)
講集団から見る日本文化の変化と再生産 | |
| 史苑の窓 | |
| 中森弘樹 | 「蒸発」は想像を喚起する――Les ?vapor?s du Japonをめぐって |
| 研究ノート | |
| 王子奇 | 近年新見のソグド語史料紹介と考察―文化受容と宗教信仰の視点から |
| 特集1 立教大学史学大会特集報告 講集団から見る日本文化の変化と再生産 | |
| 市田雅崇 | 趣旨説明 |
| 浅川泰宏 | コロナ禍の聖年―2020年〜2023年の調査から― |
| 乾賢太郎 | 京浜地区における海苔養殖と木曽御嶽講―生業と信仰に関連して― |
| 井上卓哉 | 俵札をめぐる信仰活動の一形態としての伊勢参詣―新潟県妻有地域に残された道中記から― |
| 笠井賢紀 | 栗東市の街道筋集落にみる左義長と伊勢講 |
| 高木大祐 | コメント 講研究の現在と現代への接続 |
| 特集2 | |
| 佐藤二葉、小澤実、大谷哲 | 歴史の現場に聞く!佐藤二葉『アンナ・コムネナ』・アニメ『ヴィンランド・サガ』・歴史考証 |
| 座談会 | |
| 荒井雅子、大西信行、小川幸司、佐藤雄基 | 歴史学と歴史教育の新たな協力を目指して(続)日本史と世界史をつなぐ |
| 書評 | |
| 庄嫣? | 向正樹『クビライと南の海域世界』大阪大学出版会、2024年 |
| 新刊紹介 | |
| 岡村茜 | 朝比奈新『荘園制的領域支配と中世村落』吉川弘文館、2024年 |
| 第85巻 第1号 (2025年1月)
グローバルヒストリーと中世ヨーロッパ(3) | |
| 史苑の窓 | |
| 寺尾美保 | 博物館の展示と研究 |
| 論文 | |
| 谷望 | 安政の改革における軍制改革?幕府海軍における塩飽水主の登用過程から? |
| 浦野聡、小岩直人、深津行徳、長谷川敬、イスマイル・ベイタク、オズデミル・コチャク | Two Approaches in a Preliminary Archaeological Survey of Polybotos (Dura Yeri ? Hac? Murat) prior to the Excavation |
| 特集1 グローバルヒストリーと中世ヨーロッパ(3)インド洋と世界システム論 | |
| 小澤実 | 序文 |
| フィリップ・ボジャール(佐藤彰一・村田光司訳) | 鉄器時代に想定される3つの世界システムから単一のアフロ・ユーラシア世界システムへ |
| フィリップ・ボジャール(佐藤彰一・村田光司訳) | 16世紀以前のユーラシア・アフリカ世界システムにおけるインド洋 |
| 特集2 中世初期ヨーロッパの出自神話 | |
| ヴァルター・ポール(飯尾圭司・加納修訳) | 中世初期ヨーロッパにおける「出自神話」の意義 |
| ヘルムート・ライミッツ(加納修訳) | 起源の窃取―中世初期フランク王国におけるローマの過去の摂取― |
| 加納修 | 訳者解説 |
| 特集3 梅原先生追悼特集 | |
| 丸山浩明 | 梅原弘光先生のご逝去を悼む |
| 大塚直樹 | 梅原弘光先生を偲んで |
| 弘末雅士 | 書評:梅原弘光『スペインはなぜフィリピンを占領したのか? 群島占領・植民地支配・住民の抵抗』(書籍工房早山、2023年) |
| ▲ | |
○『史苑』投稿規定へ
○『史苑』バックナンバーへ
○ 立教大学学術リポジトリ(立教Roots)へ