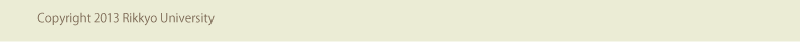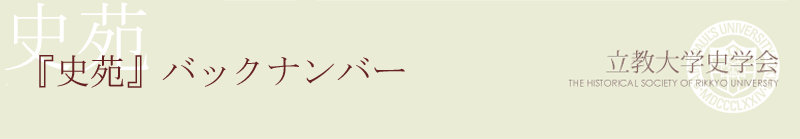
10-4/10-3/
10-2/10-1/
9-4/9-3/
9-2/9-1/
8-3・4/ 8-2/8-1/ 7-4/7-3/ 7-2/7-1/
6-6/6-5/ 6-4/6-3/ 6-2/6-1/ 5-6/5-5/ 5-4/5-3/ 5-2/5-1/
4-6/4-5/ 4-4/4-3/ 4-2/4-1/ 3-6/3-5/ 3-4/3-3/ 3-2/3-1/
2-6/2-5/ 2-4/2-3/ 2-2/2-1/ 1-6/1-5/ 1-4/1-3/ 1-2/1-1/
8-3・4/ 8-2/8-1/ 7-4/7-3/ 7-2/7-1/
6-6/6-5/ 6-4/6-3/ 6-2/6-1/ 5-6/5-5/ 5-4/5-3/ 5-2/5-1/
4-6/4-5/ 4-4/4-3/ 4-2/4-1/ 3-6/3-5/ 3-4/3-3/ 3-2/3-1/
2-6/2-5/ 2-4/2-3/ 2-2/2-1/ 1-6/1-5/ 1-4/1-3/ 1-2/1-1/
| 第10巻 第4巻 (1937年3月刊) | |
| 論文 | |
| 西岡虎之助 | 中世荘園に於ける土地配分形態 |
| 中西敬二郎 | 希伯来律法考 第三部 希伯来法典註解 |
| 杉本 俊夫 | 大井川忍び越に就いて |
| 講座 | |
| 小林 秀雄 | 史学研究法(Lehrbuch der historischen Methode)(三三) |
| ▲ | |
| 第10巻 第3号(1937年11月刊) | |
| 論文 | |
| 滝 善成 | 四円寺、法性・法成寺の研究 ――平安仏教の社会経済史的一考察―― |
| 祝 宮静 | 兵主神社神供漁場の「株」を繞る紛争の一例 |
| 古谷 郁郎 | カルヴィニズムの歴史的意義 特に「運命予定説」に就て |
| 呉 文 炳 | 大阪落城と千姫脱出の真相 |
| ▲ | |
| 第10巻 第2巻 (1936年7月刊) | |
| 論文 | |
| 原 随園 | 歴史学における時代区分 |
| 桜井 秀 | 室町時代と児童の生活 |
| 市村 次郎 | 荘子に就きて |
| 小林 秀雄 | フランス史学とジャン・ボ−ダン |
| 渡辺 轍 | 維新前後に於ける会津藩と越後との関係 |
| 藤本 了泰 | 中世末期浄土宗教団的発展の一考察 ――特に転宗に就て―― |
| 田代 秀徳 | 歴史主義の勃興と其哲学的意義 |
| 十河 佑貞 | ヘルデルの文化的民族主義 |
| 柴田 亮 | 寛文年間に於ける尾張藩の宗門改 |
| 駒井 和愛 | 先秦時代の馬面と其の始原 |
| 手塚 隆義 | 漢孝武帝の匈奴懐柔と賈誼の新書 |
| 海老沢有道 | 切支丹慈善事業の思想背景 ――十六世紀に於ける切支丹社会事業の一考察―― |
| 富田 美彦 | 平家納経雑攷 |
| 遠藤 武 | 「お太鼓結び」の起源に関する疑い |
| 劉 昌 宜 | 新羅郷歌の解読小考 |
| ▲ | |
| 第10巻 第1号(1936年2月刊) | |
| 論文 | |
| 山口 和雄 | 幕末の貿易額と諸外国の地位 |
| 海老沢有道 | 切支丹禁因の再吟味(二) |
| 中西敬二郎 | 希伯来律法考 第二部 希伯来法典彙纂 |
| 宮本馨太郎 | 足半草履に関する史料の補遺 |
| 講座 | |
| 小林 秀雄 | 史学研究法(Lehrbuch der historischen Methode)(三二) |
| ▲ | |
| 第9巻 第4巻 (1935年9月刊) | |
| 論文 | |
| 野々村戒三 | ヘブライ民族の社会思想 |
| 中西敬二郎 | 希伯来律法考(第一部) |
| 十河 佑貞 | ライン同盟を中心として観たるナポレオンとダンベルヒとの関係について(二) |
| 海老沢有道 | 切支丹禁因の再吟味 ――秀吉の場合を通して―― |
| 史料 | |
| 辻 善之助 | 異国日記目次稿・異国日記分類目録稿(二三) |
| ▲ | |
| 第9巻 第3号(1935年7月刊) | |
| 論文 | |
| 桜井 秀 | 風俗史と人生 |
| 田代 秀徳 | 近代に於ける歴史認識発展の一考察 |
| 十河 佑貞 | ライン同盟を中心として観たるナポレオンとダンベルヒとの関係について(一) |
| 講座 | |
| 小林 秀雄 | 史学研究法(Lehrbuch der historischen Methode)(三一) |
| ▲ | |
| 第9巻 第2巻 (1935年5月刊) | |
| 論文 | |
| 小林 秀雄 | マックス・ウェ−バ−の史観(其三・完) |
| 内田 秀雄 | 地人相関論史の一節 |
| 講座 | |
| 小林 秀雄 | 史学研究法(Lehrbuch der historischen Methode)(三〇) |
| ▲ | |
| 第9巻 第1号(1935年1月刊) | |
| 論文 | |
| 滝 善成 | 賑給・借貸制度に就いて ――日本社会政策史の一駒―― |
| 小林 秀雄 | マックス・ウェ−バ−の史観(其二) |
| 勝田 勝年 | ヘ−ゲル歴史観批判 |
| ▲ | |
| 第8巻 第3・4巻 1934年8月刊) | |
| 論文 | |
| 津田左右吉 | 日本思想形成の過程 |
| 李 相 佰 | 佰庶ゲツ考(二) |
| 講座 | |
| 小林 秀雄 | 史学研究法(Lehrbuch der historischen Methode)(二九) |
| 史料 | |
| 辻 善之助 | 異国日記(二二) |
| ▲ | |
| 第8巻 第2巻 (1933年7月刊) | |
| 論文 | |
| 清水 泰次 | 皇荘の起源とその発達 |
| 李 相 佰 | 佰庶ゲツ考(一) |
| 小林 秀雄 | マックス・ウェ−バ−の史観(其一) |
| 講座 | |
| 小林 秀雄 | 史学研究法(Lehrbuch der historischen Methode)(二八) |
| 史料 | |
| 辻 善之助 | 異国日記(二一) |
| ▲ | |
| 第8巻 第1号(1933年4月刊) | |
| 論文 | |
| 木村 定三 | 理学神道及び垂加神道の系統に就いて |
| 市村 次郎 | 続論語源流考(二) |
| 野々村戒三 | 能楽雑爼 |
| 勝田 勝年 | 歴史に於ける偶然性と必然性 |
| 岡田 太郎 | 民族学の人々(三) |
| ブランミッヒ 著 編集部 訳 | マルクス史観と独創的個人 |
| 講座 | |
| 小林 秀雄 | 史学研究法(Lehrbuch der historischen Methode)(二七) |
| 史料 | |
| 辻 善之助 | 異国日記(二〇) |
| ▲ | |
| 第7巻 第4巻 (1932年7月刊) | |
| 論文 | |
| 井野辺茂雄 | 明治維新の富国強兵 |
| 白鳥 清 | 古代日本の神判に就いて(迦具土神誕生神話の一考察) |
| 中西敬二郎 | 希伯来の一宗儀に就いて |
| 十河 佑貞 | 一七九七年に於けるライン左岸共和国運動に就いて |
| 駒井 和愛 | 唐代の胡禄について |
| 講座 | |
| 小林 秀雄 | 史学研究法(Lehrbuch der historischen Methode)(二六) |
| 史料 | |
| 辻 善之助 | 異国日記(十九) |
| ▲ | |
| 第7巻 第3号(1932年4月刊) | |
| 論文 | |
| 岡田 太郎 | 民族学の文献(完) |
| 市村 次郎 | 続論語源流考 |
| 大森金五郎 | 源頼朝征夷大将軍辞任説について |
| 細川 亀市 | 中世に於ける金剛寺の教団組織 |
| 勝田 勝年 | 歴史解釈の前提に関する一考察 |
| 講座 | |
| 小林 秀雄 | 史学研究法(Lehrbuch der historischen Methode)(二五) |
| 史料 | |
| 辻 善之助 | 異国日記(十八) |
| ▲ | |
| 第7巻 第2巻 (1932年1月刊) | |
| 論文 | |
| 津田左右吉 | 神とミコト |
| 滝 善成 | 段銭段米の研究 |
| トレルチ 著 編集部 訳 | マルクス弁証法(三) |
| 講座 | |
| 小林 秀雄 | 史学研究法(Lehrbuch der historischen Methode)(二四) |
| 史料 | |
| 辻 善之助 | 異国日記(十七) |
| ▲ | |
| 第7巻 第1号(1931年10月刊) | |
| 論文 | |
| 滝 善成 | 応仁乱前後に於ける寺院の経営維持に就いて |
| 編集部 | マルクス弁証法(二) |
| 遠矢 徹志 | ドルイドの研究 |
| 岡田 太郎 | 民族学の文献六 |
| ▲ | |
| 第6巻 第6巻 (1931年9月刊) | |
| 論文 | |
| 十河 佑貞 | フランス革命とドイツにおける反革命思想 ――主としてバークとゲンツとの思想的関係について―― |
| 手塚 隆義 | 葡萄漢土移入考 |
| 赤坂 新二 | 太平洋発見史 |
| ルナール,G著 編集部 訳 | 農業の起原 |
| 目録 | |
| 岡田 太郎 | 民族学の文献(五) |
| ▲ | |
| 第6巻 第5号(1931年8月刊) | |
| 論文 | |
| 津田左右吉 | 大化改新の研究(五) |
| 井上 芳郎 | 古代人の集団生活様式と世界観(二) |
| 岡田 太郎 | 民族学の人々(二) |
| 講座 | |
| 小林 秀雄 | 史学研究法(Lehrbuch der historischen Methode)(二三) |
| 史料 | |
| 辻 善之助 | 異国日記(十六) |
| ▲ | |
| 第6巻 第4巻 (1931年7月刊) | |
| 論文 | |
| 小林 秀雄 | 文化史発展の過程(六・完) |
| 楊 能 漸 | 古代ヘブライ民族の家族道徳について 孝道(二) |
| 井上 芳郎 | 古代人の集団生活様式と世界観 |
| 目録 | |
| 岡田 太郎 | 民族学の文献(四) |
| ▲ | |
| 第6巻 第3号(1931年6月刊) | |
| 論文 | |
| 小林 秀雄 | 文化史発展の過程(五) |
| 楊 能 漸 | 古代ヘブライ民族の家族道徳について 孝道 |
| 木村 定三 | 服部安休の神道説に就いて |
| 講座 | |
| 小林 秀雄 | 史学研究法(Lehrbuch der historischen Methode)(二二) |
| ▲ | |
| 第6巻 第2巻 (1931年5月刊) | |
| 論文 | |
| 小林 秀雄 | 文化史発展の過程(4) |
| 岡田 太郎 | 民族学の概念 |
| クロフォード著 編集部 訳 | 文明発祥の地 |
| 講座 | |
| 小林 秀雄 | 史学研究法(Lehrbuch der historischen Methode)(二一) |
| 史料 | |
| 辻 善之助 | 異国日記(十五) |
| ▲ | |
| 第6巻 第1号(1931年4月刊) | |
| 論文 | |
| 津田左右吉 | 大化改新の研究(四) |
| 小林 秀雄 | 文化史発展の過程(三) |
| トレルチ 著 編集部 訳 | マルクス弁証法(一) |
| 目録 | |
| 岡田 太郎 | 民族学の文献(三) |
| ▲ | |
| 第5巻 第6巻 (1931年3月刊) | |
| 論文 | |
| 野々村戒三 | 児童十字軍考 |
| 西岡虎之助 | 石川荘の成立と河内源氏の発展 |
| 津田左右吉 | 大化改新の研究(三) |
| 史料 | |
| 辻 善之助 | 異国日記(一四) |
| 目録 | |
| 岡田 太郎 | 民族学の文献(二) |
| ▲ | |
| 第5巻 第5号(1931年2月刊) | |
| 論文 | |
| 出石 誠彦 | 浦島の説話とその類例について |
| 小林 秀雄 | 文化史発展の過程(二) |
| 助川 貞三 | エトラスカ文化(完) |
| 講座 | |
| 小林 秀雄 | 史学研究法(Lehrbuch der historischen Methode)(二〇) |
| 目録 | |
| 岡田 太郎 | 民族学の文献(一) |
| ▲ | |
| 第5巻 第4巻 (1931年1月刊) | |
| 論文 | |
| 津田左右吉 | 大化改新の研究(二) |
| 十河 佑貞 | ウィルヘルム・フンボルトの歴史理念説に就いて |
| 岡田 太郎 | 民族学の人々(一) |
| 高田 春彦 | 歴史上から見た伝説とその取扱方について |
| 史料 | |
| 辻 善之助 | 異国日記(十三) |
| ▲ | |
| 第5巻 第3号(1930年12月刊) | |
| 論文 | |
| 津田左右吉 | 大化改新の研究(一) |
| 小林 秀雄 | 文化史発展の過程(一) |
| 祝 宮静 | 天平九年度穴師神税帳の数字的説明 |
| 講座 | |
| 小林 秀雄 | 史学研究法(Lehrbuch der historischen Methode)(十九) |
| ▲ | |
| 第5巻 第2巻 (1930年11月刊) | |
| 論文 | |
| 朝日 融渓 | 「自由」の歴史的変遷に就て |
| 柴田 亮 | 愛知県丹羽郡高木村小島三保次氏所蔵切支丹関係文書の解釈 |
| 市川 勇 | 西洋文明起源論 ―スムメル説― |
| ▲ | |
| 第5巻 第1号(1930年10月刊) | |
| 論文 | |
| 辻 善之助 | 近世仏教衰微之由来と民心の離反 |
| 井野辺茂雄 | 文政度幕府の蝦夷地経営中止に関する考察 |
| 伊藤 憲之 | 中世西欧羅巴の土地財産の変遷 |
| 講座 | |
| 小林 秀雄 | 史学研究法(Lehrbuch der historischen Methode)(十八) |
| ▲ | |
| 第4巻 第6巻 (1930年9月刊) | |
| 論文 | |
| 蘆田 伊人 | 樺太島の地図学史上に於ける或考察 |
| 山岸 徳平 | 太極蔵主と其の詩文 |
| 助川 貞三 | 社会学と史学との関係についての考察 |
| ロージェコフ著 平竹 伝三 訳 | ロシアのニコライ一世の時代(ロ−ジェコフ「ロシア最近史」第2章 ) |
| 講座 | |
| 小林 秀雄 | 史学研究法(Lehrbuch der historischen Methode)(十七) |
| ▲ | |
| 第4巻 第5号(1930年8月刊) | |
| 論文 | |
| 和田 英松 | 日本書紀に就いての考察 |
| 志田不動麿 | 委面の意義と邪馬台国在南方論の否定 |
| 助川 貞三 | エトラスカ文化(其一) |
| 講座 | |
| 小林 秀雄 | 史学研究法(Lehrbuch der historischen Methode)(十六) |
| 史料 | |
| 辻 善之助 | 異国日記(十二) |
| ▲ | |
| 第4巻 第4巻 (1930年7月刊) | |
| 論文 | |
| 市村サン次郎 | 論語源流考(五) |
| 秋山 謙蔵 | 為朝琉球入伝説再批判 |
| 中西敬二郎 | 亜米利加印度人の標式語(Sign Language)中に於ける原始宗教思想 |
| 楊 能 漸 | アッシリア婦女法典 |
| ▲ | |
| 第4巻 第3号(1930年6月刊) | |
| 論文 | |
| 楊 能 漸 | 古代ヘブライ民族の家族道徳について ――復讐―― |
| 丸山 林平 | 語部に関する研究 |
| 木村 定三 | 三度保科正之の勤王に就いて |
| 史料 | |
| 辻 善之助 | 異国日記(十一) |
| ▲ | |
| 第4巻 第2巻 (1930年5月刊) | |
| 論文 | |
| 中山久四郎 | 唐音語の研究と其実例五則 |
| 中山 太郎 | 古神道の事相に及せる支那思想 |
| 高田 春彦 | ヘレニスチック文化の歴史的特質 Julius kaerst ; Geschichte des Hellenismus 2 の一節 |
| 岡田 太郎 | 北米土人に於ける奴隷の却略とその交易 |
| 講座 | |
| 小林 秀雄 | 史学研究法(Lehrbuch der historischen Methode)(十五) |
| ▲ | |
| 第4巻 第1号(1930年4月刊) | |
| 論文 | |
| 渡辺 轍 | 下関償金の支払に就いて |
| 白鳥 清 | 古代日本の神判に就いて(其二) ―火を適用したる神判思想の反映― |
| 小林 健三 | 神宮式年遷宮の歴史的意義 |
| 岡田 太郎 | 中央亜米利加の奴隷制度 |
| 講座 | |
| 小林 秀雄 | 史学研究法(Lehrbuch der historischen Methode)(十四) |
| ▲ | |
| 第3巻 第6巻 (1930年3月刊) | |
| 論文 | |
| 小林 秀雄 | ランケに関する研究(四) |
| 十河 佑貞 | ゲンツの手記と「イエナ会戦秘史」の一節に就いて(完) |
| 高田 春彦 | カルル・ユリウス・ベロッホ(完) |
| 岡田 太郎 | 財産起源論に関する一考察(二) ――濠洲土人に於ける家族狩猟地制度について―― |
| 講座 | |
| 小林 秀雄 | 史学研究法(Lehrbuch der historischen Methode)(十三) |
| 史料 | |
| 辻 善之助 | 異国日記(十) |
| ▲ | |
| 第3巻 第5号(1930年2月刊) | |
| 論文 | |
| 白鳥 清 | 古代日本の神判に就いて(其一) |
| 中山 太郎 | 古田券地名考 |
| 高田 春彦 | カルル・ユリウス・ベロッホ(其一) |
| 朝日 融渓 | 文芸復興と思想の解放(承前) |
| 岡田 太郎 | 財産起源論に関する一考察(一) ――濠洲土人に於ける家族狩猟地制度について―― |
| 講座 | |
| 小林 秀雄 | 史学研究法(Lehrbuch der historischen Methode)(十二) |
| ▲ | |
| 第3巻 第4巻 (1930年1月刊) | |
| 論文 | |
| 出石 誠彦 | 支那の古文献に現はるる麒麟について |
| 鈴木拾五郎 | 万葉集の七夕説話(二・完) |
| 十河 佑貞 | ゲンツの手記と「イエナ会戦秘史」の一節に就いて(一) |
| 朝日 融渓 | 文芸復興と思想の解放 |
| 史料 | |
| 市村サン次郎 | 各項稿簿(六・完) |
| 辻 善之助 | 異国日記(九) |
| ▲ | |
| 第3巻 第3号(1929年12月刊) | |
| 論文 | |
| 鈴木拾五郎 | 万葉集の七夕説話(一) |
| 小林 秀雄 | ランケに関する研究(三) |
| 木村 定三 | 再び保科正之の勤王に就いて |
| 三上 義夫 | 日本数学史論(三) |
| 史料 | |
| 市村サン次郎 | 各項稿簿(五) |
| 講座 | |
| 小林 秀雄 | 史学研究法(Lehrbuch der historischen methode)(十一) |
| ▲ | |
| 第3巻 第2巻 (1929年11月刊) | |
| 論文 | |
| 西岡虎之助 | 池溝時代より堤防時代への展開(下) ――中古農業史の一節―― |
| 小林 秀雄 | ランケに関する研究(二) |
| 三上 義夫 | 日本数学史論(二) |
| 十河 佑貞 | 浪漫主義的国家学の史的発展(七・完) |
| 講座 | |
| 小林 秀雄 | 史学研究法(Lehrbuch der historischen methode)(十) |
| ▲ | |
| 第3巻 第1号(1929年10月刊) | |
| 論文 | |
| 井野辺茂雄 | 蝦夷地に於ける露人暴行の善後策 |
| 西岡虎之助 | 池溝時代より堤防時代への展開(上) ――中古農業史の一節―― |
| 三上 義夫 | 日本数学史論(一) |
| 講座 | |
| 小林 秀雄 | 史学研究法(Lehrbuch der historischen methode)(九) |
| ▲ | |
| 第2巻 第6巻 (1929年9月刊) | |
| 論文 | |
| 池内 宏 | 公孫氏の帯方郡設置と曹魏の楽浪帯方二郡 |
| 三浦 周行 | 黎明期の近世文化に於ける堺の地位 |
| 祝 宮静 | 我が国奴隷経済時代に於ける其の使役者との交渉に就て |
| 木村 定三 | 山崎闇齋の唯一神道研究期に就いて |
| 十河 佑貞 | 浪漫主義的国家学の史的発展(六) |
| 講座 | |
| 小林 秀雄 | 史学研究法(Lehrbuch der historischen methode)(八) |
| 史料 | |
| 辻 善之助 | 異国日記(八) |
| ▲ | |
| 第2巻 第5号(1929年8月刊) | |
| 論文 | |
| 飯島 忠夫 | 支那暦法の起源に関する伝説 |
| 辻 善之助 | 黒衣の宰相金地院祟伝(八) |
| 岡田 太郎 | 北米土人に於ける奴隷制度の経済的側面 |
| 楊 能 漸 | ヘブライ民族のレヴイル結婚 |
| 十河 佑貞 | 浪漫主義的国家学の史的発展(五) |
| 史料 | |
| 市村サン次郎 | 各項稿簿(四) |
| ▲ | |
| 第2巻 第4巻 (1929年7月刊) | |
| 論文 | |
| 津田左右吉 | 子代名代の部について(二) |
| 桜井 秀 | 平安季世の文化と人生(四) |
| 祝 宮静 | 律令時代の賤民制度の概説(三) |
| 十河 佑貞 | 浪漫主義的国家学の史的発展(四) |
| 講座 | |
| 小林 秀雄 | 史学研究法(Lehrbuch der historischen methode)(七) |
| 史料 | |
| 市村サン次郎 | 各項稿簿(三) |
| ▲ | |
| 第2巻 第3号(1929年6月刊) | |
| 論文 | |
| 津田左右吉 | 子代名代の部について(一) |
| 辻 善之助 | 黒衣の宰相金地院祟伝(七) |
| 祝 宮静 | 律令時代の賤民制度の概説(二) |
| 金 允 経 | 訓民正音発布の事情 |
| 講座 | |
| 小林 秀雄 | 史学研究法(Lehrbuch der historischen methode)(六) |
| 史料 | |
| 辻 善之助 | 異国日記(七) |
| ▲ | |
| 第2巻 第2巻 (1929年5月刊) | |
| 論文 | |
| 小林 秀雄 | ランケに関する研究(一) |
| 祝 宮静 | 律令時代の賤民制度の概説(一) |
| 木村 定三 | 松平正之公の勤王に就いて |
| 板沢 武雄 | 慶長の遣使支倉一行の跡を尋ねて |
| 十河 佑貞 | 浪漫主義的国家学の史的発展(三) |
| 赤坂 新二 | 中世欧羅巴の亜弗利加旅行家 |
| 岡田 太郎 | 新石器時代の穿顱術について(三) |
| 講座 | |
| 小林 秀雄 | 史学研究法(Lehrbuch der historischen methode)(五) |
| 史料 | |
| 辻 善之助 | 異国日記(六) |
| 市村サン次郎 | 各項稿簿(二) |
| ▲ | |
| 第2巻 第1号(1929年4月刊) | |
| 論文 | |
| 津田左右吉 | 歴史の矛盾性 |
| 芝 葛盛 | 長慶天皇の皇胤について |
| 竹岡 勝也 | 常世国思想の発達 |
| 木村 定三 | 会津藩に於ける陽明学説禁止について |
| グラフ | |
| 伊藤 憲之 | 中世欧羅巴の武士道 |
| 論文 | |
| 十河 佑貞 | 浪漫主義的国家学の史的発展(二) |
| 史料 | |
| 市村サン次郎 | 各項稿簿(一) |
| 講座 | |
| 小林 秀雄 | 史学研究法(Lehrbuch der historischen Methode)(四) |
| ▲ | |
| 第1巻 第6巻 (1929年3月刊) | |
| 論文 | |
| 辻 善之助 | 黒衣の宰相金地院祟伝(六) 附 異国日記解題 |
| 桜井 秀 | 平安季世の文化と人生(三) |
| 大森金五郎 | 上総介平広常の拠所及び其事蹟 |
| 三上 義夫 | 我国の科学史上に於ける廣川晴軒の地位 |
| 十河 佑貞 | 浪漫主義的国家学の史的発展(一) |
| 岡田 太郎 | 新石器時代の穿顱頭蓋について |
| 講座 | |
| 小林 秀雄 | 史学研究法(Lehrbuch der historischen Methode)(三) |
| ▲ | |
| 第1巻 第5号(1929年2月刊) | |
| 論文 | |
| 井野辺茂雄 | 和宮の御降嫁に関する研究 |
| 市村サン次郎 | 論語源流考(三) |
| 辻 善之助 | 黒衣の宰相金地院祟伝(五) 附 異国日記解題 |
| 桜井 秀 | 平安季世の文化と人生(二) |
| 金 允 経 | 「大唐平百済国碑」に就いて |
| 小木 鉄彦 | 日本国民性に就ての一考察(二) |
| 岡田 太郎 | ホ−マ−時代の奴隷制度(二) |
| ▲ | |
| 第1巻 第4巻 (1929年1月刊) | |
| 論文 | |
| 市村 次郎 | 論語源流考(二) |
| 辻 善之助 | 黒衣の宰相金地院祟伝(四) 附 異国日記解題 |
| 野々村戒三 | 米国独立宣言書の系統批判 |
| 飯田 豊 | 太平記「阿新殿の事」中の船戻伝説に就いて |
| 柴田 亮 | 美濃尾張の切支丹 |
| グラフ | |
| 赤坂 新二 | 古代希臘劇場 |
| 論文 | |
| 岡田 太郎 | ホ−マ−時代の奴隷制度 |
| 史料 | |
| 辻 善之助 | 異国日記(三) |
| ▲ | |
| 第1巻 第3号(1928年12月刊) | |
| 論文 | |
| 辻 善之助 | 黒衣の宰相金地院祟伝(三) 附 異国日記解題 |
| 桜井 秀 | 平安季世の文化と人生(一) |
| 金田平一郎 | 徳川時代に於ける訴訟上の和解(二) |
| グラフ | |
| 伊藤 憲之 | 中世欧羅巴に於ける庶民の生活 |
| 論文 | |
| 小林 秀雄 | 古文書学の建設者ジャン・マビヨンと其著デレ・ヂプロマチカ |
| 小木 鉄彦 | 日本国民性に就ての一考察 |
| 講座 | |
| 小林 秀雄 | 史学研究法(Lehrbuch der historischen Methode)(二) |
| ▲ | |
| 第1巻 第2巻 (1928年11月刊) | |
| 論文 | |
| 市村サン次郎 | 論語源流考 |
| 辻 善之助 | 黒衣の宰相金地院祟伝(二) 附 異国日記解題 |
| 芝 葛盛 | 元中東宮考 長慶天皇に関連せる問題の一 |
| 金田平一郎 | 徳川時代に於ける訴訟上の和解(一) |
| グラフ | |
| 岡田 太郎 | 民族学図絵 |
| 論文 | |
| 小林 健三 | 武家の勃興と其の信仰の様式に就て |
| 史料 | |
| 辻 善之助 | 異国日記(二) |
| ▲ | |
| 第1巻 第1号(1928年10月刊) | |
| 論文 | |
| 白鳥 庫吉 | 神代の国号考 |
| 辻 善之助 | 黒衣の宰相金地院祟伝(一) 附 異国日記解題 |
| 楊 能漸 | 天平税帳に見ゆる振入について |
| 菅 円吉 | カテキとエラスムスに関する一疑義 |
| グラフ | |
| 池田 俊彦 | 伊太利亜の旅 |
| 講座 | |
| 小林 秀雄 | 史学研究法(Lehrbuch der historischen Methode) |
| 史料 | |
| 辻 善之助 | 異国日記 |
| 書評 | |
| 小林 秀雄 | 原 随園氏近業「ギリシャ史研究」を読みて |
| ▲ | |