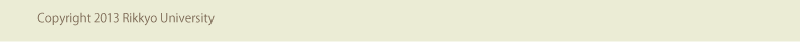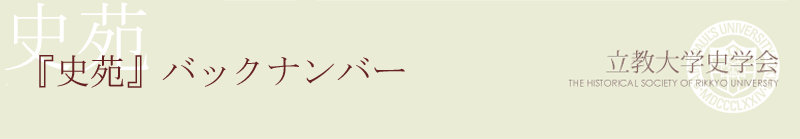
60-2/60-1/
59-2/59-1/
58-2/58-1/
57-2/57-1/
56-2/56-1/
55-2/55-1/ 54-2/54-1/ 53-2/53-1/ 52-2/52-1/ 51-2/51-1/
55-2/55-1/ 54-2/54-1/ 53-2/53-1/ 52-2/52-1/ 51-2/51-1/
| 第60巻 第2号 (2000年3月刊) | |
| 史苑の窓 | |
| 小井 高志 | フランス革命とセクシュアリテ |
| 論文 | |
| 盛本 昌広 | 豊臣政権の贈答儀礼と養生 |
| 荒野 泰典 | 近世東アジアの国際関係論と漂流民送還体制 |
| 申 東珪 | 付:一九九九年 韓日関係国際シンポジウム |
| 「朝鮮時代漂流民を通してみた韓日関係」参加記 | |
| 胎中 千鶴 | 日本統治期台湾の斎教に関する一視点 |
| 加藤 鉄三 | ジョン・ミユーアとシェラ・ネヴァダ山脈における国立公園の形成、1889 |
| 大塚 直樹 | 植民地期ベトナムの地域分化 -フランス土地政策との関連を中心として |
| 林 陽子 | 募集業者とクライアント−ジャワにおける労働者募集の展開、1870年代〜1950年代 |
| 研究ノート | |
| 川崎 晴朗 | 立教学校の発祥地についての一考察 -「詩人ロングフェローの息子の住居」について− |
| 史料紹介 | |
| 梶原 康久 | 炭鉱会社と戦犯調査−筑豊・貝島炭鉱を事例として (GHQ法務局福岡分局・貝島義之尋問録) |
| 書評 | |
| 青柳 かおり | 見市雅俊著 『ロンドン=炎が生んだ世界都市大火・ペスト・反カソリック』 |
| 川島 正樹 | ロナルド・シーガル著、富田虎男監訳 『ブラック・ディアスポラー世界の黒人がつくる歴史・社会・文化』 |
| 一九九九年度立教大学史学会研究会報告 | |
| 後藤均平先生の略歴と主要研究業績(訂正版) | |
| ▲ | |
| 第60巻 第1号 (1999年10月刊) | |
| 史苑の窓 | |
| 設樂 國廣 | コソボ問題とトルコ |
| 大橋 厚子 | 1820年代チアンジュール-レヘント統治地域の開拓 |
| -コーヒー生産 を目的としない開拓- | |
| 鈴木 恒之 | 一七世紀後半を中心とするパレンバン王国の胡椒交易 |
| 高津 茂 | 1946〜1948年当時のカオダイ教(1)-国教への夢- |
| 弘末 雅士 | ヨーロッパ人の調査活動と介在者の「食人」文化の創造 |
| 上田 信 | 被害者・遺族にとっての細菌戦訴訟 -中国浙江省義烏市崇山村の事例- |
| 梅原 弘光 | コロナダルの地域概念 -ミンナダオ島の一地名に関する考察- |
| 青木 康 | 有力ジェントリの条件 -十八世紀末イギリス・サフォーク州の一事例 |
| 研究ノート | |
| 関口 真理 | ブライアン・ホジソン伝を読む一九世紀ネパールの英国公使、そして寄留者- |
| 斉藤 伸義 | アジア太平洋戦争開戦決定過程における 「戦争終末」構想に与えた秋丸機関の影響 |
| 一九九九年度立教大学史学会大会・総会報告 | |
| ▲ | |
| 第59巻 第2号 (1999年3月刊)日本史特集号 | |
| 史苑の窓 | |
| 藤木 久志 | 山城停止令の伝承を訪ねて |
| 論文 | |
| 舘鼻 誠 | 由緒と相論 - 大和・大方家文書ノート |
| 平山 優 | 戦国・近世初期の被官・下人について -主家と被官・下人争論の検討を中心に |
| 矢島 有稀彦 | 牛込流江戸氏と牛込氏 |
| 青柳 かおり | ラティテューディナリアンと包括 -一七世紀後半のイングランド国教会と非国教徒- |
| 大塚 直樹 | 長野盆地における果樹園栽培の展開過程 -長野市長沼地区のリンゴ栽培を中心として- |
| 研究ノート | |
| 松田 松男 | 1990年代前半における 上海・浦東新区の開発について |
| 書評 | |
| 申 東珪 | 岸野久著『ザビエルと日本』 |
| 藤木久志先生の略歴と主要著作目録 | |
| 追悼後藤均平先生 | |
| 一九九八年度立教大学史学会研究会報告 | |
| ▲ | |
| 第59巻 第1号 (1998年10月刊) | |
| 史苑の窓 | |
| 上田 信 | 雲夢沢幻視 |
| 論文 | |
| 小西 正捷 | ガンディーによる村落工業の復興 -ことに抄紙技術の"改良"とハリジャンの投入をめぐって |
| 黒川 康 | ドイツ国民国家における連邦主義と民衆 -ライヒ改革(1928ー1930)とバイエルン |
| 関 恒樹 | フィリピン・ビサヤ地方の島嶼間移動を支える社会関係 -セブアノ漁民のライフ・ヒストリーの考察を中心に |
| 右谷 理佐 | 国際結婚からみる今日の日本農村社会と「家」の変化 |
| 研究ノート | |
| 市川 哲 | マレーシア華人の同郷会館の国際化 -中国・マレーシア関係の推移との関わりから |
| 加藤 鉄三 | 「新しい西部史」と環境史 |
| 追悼 森 弘之先生を偲ぶ | |
| 一九九八年度立教大学史学会大会・総会報告 | |
| ▲ | |
| 第58巻 第2号 (1998年3月刊)東洋史特集号 | |
| 史苑の窓 | |
| 後藤 均平 | 書誌二題 |
| 論文 | |
| 森 弘之 | 義浄と『聖大乗論』の間 |
| 胎中 千鶴 | 日本統治期台湾の仏教勢力-1921年南瀛仏教会成立まで- |
| 盛本 昌広 | 近世における小田氏関係史料収集の背景 |
| 阿諏訪 青美 | 室町期・奈良 福智院地蔵堂の再興と「勧進憑支」 |
| 史料紹介 | |
| 酒井 紀美 他 | 成簣堂文庫『(建武二年)興福寺大乗院奉行引付』 |
| 戴國煇先生の略歴と主要著作目録 | |
| フィールド・ノート | |
| 陳 梅 卿 | 詩山鳳山寺の進香 |
| 一九九七年度立教大学史学会研究会報告 | |
| ▲ | |
| 第58巻 第1号 (1997年10月刊)地理学特集号 | |
| 史苑の窓 | |
| 豊田 由貴夫 | 研究の道具としてのパソコン |
| 論文 | |
| 内藤 暁子 | ニュージーランド政府との「和解」の果てに -先住民族マオリ、タイヌイ・マオリ・トラスト・ボードのめざすもの- |
| 永井 博子 | フィリピンの農村における国内出稼ぎ労働者の実態 -アンティーケ 州シンボラ村の事例- |
| 上橋 菜穂子 | 地方のアポリジニの形成に関する一考察 -ミソニゲニューの事例を中心に- |
| 鈴木 慎一郎 | 帰還と解放 -ジャマイカのラスタファリアンにとっての救済- |
| 執行 一利 | 大規模農村開発と親族組織の変容 -スリランカの一農村社会の事例から- |
| 田中 禎昭 | 古代の「サト」 -『万葉集』を中心として- |
| 青柳真智子先生の略歴と主要著作目録 | |
| 別技篤彦先生追悼 | |
| 一九九七年度立教大学史学会六月大会報告 | |
| 活動報告 | |
| ▲ | |
| 第57巻 第2号 (1997年3月刊) | |
| 史苑の窓 | |
| 戴 國煇 | 西安事変六〇周年に思うこと |
| 論文 | |
| 松下 洋巳 | 前秦苻堅政権の性格について |
| 安達 宏昭 | 一九三〇年代日本のフィリピン鉄鉱資源進出 |
| 永井 均 | フィリピンと東京裁判 -代表検事の検察活動を中心として |
| 研究ノート | |
| 今野 春樹 | 近世大名墓の構造について -国立西洋美術館出土清水家墓所を中心 |
| 中村 茂生 | 「経歴書」にみる鈴木経勲 |
| 石川 真作 | ドイツにおけるトルコ系イスラーム団体 |
| 書評 | |
| 高柳 俊男 | 山田昭次著『金子文子ー自己・天皇制国家・朝鮮人』 |
| 小林 一岳 | 蔵持重裕著『日本中世村落社会史の研究』 |
| 右谷 理佐 | 和田正平編著『アフリカ女性の民族誌』 |
| 1996年度立教大学史学会秋季大会報告 | |
| ▲ | |
| 第57巻 第1号 (1996年10月刊) | |
| 史苑の窓 | |
| 鈴木 慎一郎 | 文化の語りの<正しさ>について |
| 論文 | |
| 石井 輝義 | 律令国家の喪葬-豪族の喪葬権の行方- |
| 近藤 いずみ | 漢代四川の富裕層における死後の世界観 |
| 高橋 裕子 | ポリス成立期のエレウシスとアッティカ |
| 岩田 晋典 | 浅川のささら-風流系獅子舞の象徴分析 |
| 研究ノート | |
| 菊地 真 | 遺跡立地にみる先史人類の土地利用について -縄文時代中期・下総台地東京湾岸地域の例- |
| 書評 | |
| 木野 淳子 | 大原祐子著『カナダ史への道』 |
| 百瀬 響 | 河野本道著『アイヌ史概説』 |
| 追悼 大久保利謙先生を偲ぶ | |
| 1996年度立教大学史学会大会報告 | |
| ▲ | |
| 第56巻 第2号 (1996年3月刊) | |
| 史苑の窓 | |
| 香原 志勢 | 歴史の底流に潜む生物学的なもの |
| 論文 | |
| 高橋 秀 | 欲望は理性に従うべし |
| 浦野 聡 | 後期ロ−マ帝国における負担munera免除特権をめぐって |
| 設樂 國廣 | オスマン帝国末期のユダヤ教徒問題 |
| 木村 靖二 | ドイツ歴史学の戦後五十年 -ナチズム論をめぐって- |
| 書評論文 | |
| 大浜 恵 | J・A・クルック 『ロ−マ帝国における法的弁護』 |
| 柴野 浩樹 | C・R・ホイッタカー『ロ−マ帝国のフロンティア』 |
| 特別講演 | |
| 和田 春樹 | 東北アジア戦争としての朝鮮戦争 |
| 書評 | |
| 村井 文彦 | 岸野久・村井早苗編『キリシタン史の新発見』 |
| 高橋秀先生の略歴と主要著作目録 | |
| 1995年度立教大学史学会大会要旨 | |
| ▲ | |
| 第56巻 第1号 (1995年10月刊) | |
| 史苑の窓 | |
| 林 英夫 | 天明期の「ボランティア」運動 |
| 論文 | |
| 赤野 孝次 | 福沢諭吉の朝鮮文明化論と「脱亜論」 |
| 西成 健 | 自由民権期の田中正造の「民力休養」論 |
| −三島県令時代の道路開削反対論を中心として | |
| 留場 端乃 | 日清戦争後の中江兆民 |
| 高柳 俊男 | 東京・枝川町の朝鮮人簡易住宅建設をめぐる一考察 |
| 石坂 浩一 | 在日朝鮮人をめぐる授業についての実践と反省 |
| 資料と解説 | |
| 長澤 秀 | 北炭と朝鮮人強制連行−数量的側面を中心に− |
| 書評 | |
| 小久保 諭 | 江東・在日朝鮮人の歴史を記録する会・編『東京のコリアン・タウン-枝 |
| 山田昭次先生の略歴と主要著作目録 | |
| 1995年度立教大学史学会大会報告 | |
| ▲ | |
| 第55巻 第2号 (1995年3月刊) | |
| 史苑の窓 | |
| 高橋 秀 | 史苑をたずねて |
| 論文 | |
| 山田 昭次 | 近代日本の朝鮮観-その研究課題と方法- |
| 中村 茂生 | 「南洋民族学」と松岡静雄 |
| 長野 雅史 | 日本占領期香港における人口疏散政策 |
| 小林 元裕 | 1920年代天津における日本人居留民 |
| 水井 万里子 | イングランド南西部地域のスタナリ-近世すず鉱業の利益集団- |
| 細井 岳登 | 境界の祭祀、鎮守の祭祀-三州岡崎城下投町菅生八幡宮をめぐって |
| 文献紹介 | |
| 永井 均 | 東京裁判の研究動向に関するノ−ト-二冊の著作の刊行によせて- |
| 研究会情報 | |
| 小磯 学 | 「インド考古学研究会」 |
| 活動報告 | |
| 野田 嶺志 | 日本歴史学協会について |
| ▲ | |
| 第55巻 第1号 (1994年10月刊) | |
| 史苑の窓 | |
| 松浦 高嶺 | バ−フォ−ド-過去と現在 |
| 論文 | |
| 西願 広望 | フランス革命と軍隊-1794年以降の軍人の意識の変容を中心に- |
| 桑名 晶子 | 中国華南における不落家の起原・形成 |
| 赤井 孝史 | 近世前期の失人と村 |
| 百瀬 響 | 北海道旧土人保護法の成立と変遷の概要 |
| 研究ノート | |
| 永井 均 | フィリピン資料館探訪-マニラ及びケリン・シティを中心に- |
| 後藤 均平 | 銷夏二題 |
| 海外だより | |
| 西川 杉子 | ロンドン便り |
| 研究会情報 | |
| 松本 麻里子 | ぜんまいの会 |
| 1994年度立教大学史学会大会報告 | |
| ▲ | |
| 第54巻 第2号 (1994年3月刊)西洋史特集号 | |
| 論文 | |
| 白井 洋子 | アメリカ革命とインディアン-デラウェア族・モラビア教徒・北西部- |
| 鵜月 裕典 | ジェディダイア・モ−スのインディアン改革計画 |
| 岩本 裕子 | 全米黒人女性協会と創設者達-メアリ・C・テレルを中心に- |
| 川島 正樹 | ガ−ヴィ−運動衰退期のマ−カス・ガ−ヴィ−(1925〜1940) |
| 竹本 友子 | W.E.B.デュボイスと日本 |
| 近藤 淳子 | ジョン・フォスタ−・ダレスの中国政策 |
| 小島 茂雄 | M.L.キングJr.とヴェトナム戦争-キングの晩年のラディカリズムをめ |
| 進藤久美子 | 変貌するフェミニズム-ソーシャリスト・フェミニズムの動向- |
| 研究ノート | |
| 竹中 興慈 | シカゴ黒人ゲト−の黒人教会 |
| 木野 淳子 | アッパ−カナダ植民地における「外国人問題」-アメリカ系移民の帰化 |
| 佐藤 円 | 北アメリカ先住民の人口推定 |
| 野村 文子 | ネイティブアメリカンとゴ−ストダンス-神話、民謡、そして宗教学- |
| 書評 | |
| 木畑 洋一 | 松浦高嶺 『イギリス現代史』 |
| 富田虎男先生の略歴・主要著作目録 | |
| 清水博先生追悼 | |
| ▲ | |
| 第54巻 第1号 (1993年12月刊) | |
| 史苑の窓 | |
| 戴 国煇 | ふたりの黄興 |
| 論文 | |
| 土居 邦彦 | 1930年代日本の花郎研究にみえる戦士機能論の批判的再考 |
| ユリアリンス | 中国の第3革命と日本-1916年山東省における反袁運動を中心に- |
| 上白石 実 | 筒井政憲-開港前後の幕臣の危機意識について- |
| 宋 志 勇 | 終戦前後における中国の対日政策 |
| 史料翻訳 | |
| 海南雑著を読む会 | 蔡廷蘭「海南雑著」とその試訳 |
| 後藤均平先生の略歴・主要著作目録 | |
| 書評 | |
| 田中 定仁 | 梅原弘光 「フィリピンの農村 その構造と変動」 |
| 荒野 泰典 | アジアのなかの日本史(全6巻)の編集を終えて |
| ▲ | |
| 第53巻 第2号 (1993年3月刊) | |
| 史苑の窓 | |
| 富田 虎男 | 「タンガロとジュジロ−」 |
| 研究論文 | |
| 酒井 順子 | 「女性選挙権協会全国連合」とイギリス労働党の選挙協力 |
| 学会動向 | |
| 近江 吉明 | フランスにおける最近の「封建制成立論争」 |
| 研究動向 | |
| 新谷 一伴 | 19世紀初頭イギリス政治史研究の一動向 |
| 書評・文献紹介 | |
| 小幡 壮 | 青柳まちこ著 『トンガの文化と社会』 |
| 矢ケ崎 玲 | 島田周平著 『地域科間対立の地域構造』 |
| 倉敷 伸子 | 小田部雄次著 『梨本宮伊都子妃日記』 |
| 追悼 | |
| 海老沢有道先生を偲ぶ | |
| 手塚隆義先生を偲ぶ | |
| ▲ | |
| 第53巻 第1号 (1992年7月刊)地理学特集号 | |
| 回顧と展望 | |
| 編集委員会 | 地理学専攻と「アジア地域綜合研究施設」-別技篤彦先生に聞く |
| 中田 栄一 | 野外実習の回顧 |
| 梅原 弘光 | 地域研究雑感 |
| 佐藤 俊 | 地理学研究室の断想 |
| 論文 | |
| 松田 松男 | 農用地利用増進事業をとおしてみた村づくりの実態-丹波・篠山町の |
| 富岡 政治 | 地域労働市場の形成過程に関する一考察-奥秩父山村集落の事例か |
| 小嶋 響 | 旭川アイヌの祖霊祭祀「イアレ」 |
| 研究ノート | |
| 青柳まちこ | フィ−ルドワ−クについて |
| 永井 博子 | フィリピン、アンティ−ケ州の市場 |
| 田中 定仁 | アキノ政権下における国家政策としてのココナツ産業 |
| 吉田 正紀 | 東スマトラのプランテ−ションとジャワ人移民 |
| 内藤 暁子 | マオリ・クィ−ン戴冠二五周年式典とマオリの現状 |
| 上橋菜穂子 | オ−ストラリア・アボリジニ−と学校教育 |
| 小西 正捷 | 日本における南アジア民族学 1984〜1990 |
| 小磯 学 | 西インド・クンタシ遺跡出土土器の分析 |
| 石川 真作 | トルコ共和国における「トルコ人」 |
| 山浦 清 | 新大陸への人類の拡散過程研究の諸前提 |
| 思い出 | |
| 島田 周平 | 新幹線通勤裏話 |
| 中島 章子 | ヘルメットで掬われて |
| 高橋 昭久 | 「立教地理」と私 |
| 藤本 茂樹 | 近況報告-能と海とねぶた祭り- |
| 中矢 史朗 | 酒と徹夜観測-西沢研究室での思い出- |
| 歩み | |
| 編集委員会 | 文学研究科地理学専攻関係年譜 |
| ▲ | |
| 第52巻 第2号 (1998年3月刊)東洋史特集号 | |
| 史苑の窓 | |
| 山浦 清 | サハリン・考古学・ペレストロイカ |
| 論文 | |
| 小林 隆夫 | 貴州の成立について |
| 林 正子 | 台南の劉永福-「奉旨剿滅倭寇」の黒旗 |
| 石坂 浩一 | 韓国学生農村活動の歴史的意味-1960年代初期への一考察- |
| 中生 勝美 | 漢族の民俗生殖観とイトコ婚 |
| 甲子 雅代 | 『コ−ラン』"光の章"における"光"と"闇"について |
| 松本麻里子 | 長吏「新組合」の結成と解体-近世後期の武蔵国を事例として- |
| 研究ノート | |
| 石橋 秀雄 | アイシンギョロ(Aisin Gioro)-愛新覺羅と愛親覺羅- |
| 石橋秀雄先生略歴・主要著作目録 | |
| 新刊紹介 | |
| 栗原 純 | 戴国煇著『台湾、いずこへ行く?!』 |
| 辻 まゆみ | 青柳まちこ他著『女と「遊び」の時代』 |
| ▲ | |
| 第52巻 第1号 (1991年8月刊) | |
| 史苑の窓 | |
| 粟屋憲太郎 | 今、戦争犯罪裁判を考える |
| 座談会 | |
| 地理学専攻院生有志 | フィ−ルド・ワ−クを語る |
| 論文 | |
| 稲葉 継陽 | 中世後期の宿有徳人の存在形態 |
| 君塚 直隆 | グラッドストンとスエズ運河 |
| 鈴木慎一郎 | ジャマイカの「アフリカ人」-ラスタファリ運動の展開について- |
| 研究ノート | |
| 疋田 康行 | シンガポ−ル・マレ−シア資料館探訪 |
| 報告 | |
| 日本史院生協議会 | 「即位の礼」・大嘗祭に関する立教大学史学科学生の意識調査 |
| 書評・紹介 | |
| 小嶋 響 | 船橋市教育委員会『船橋の天道念仏-第三次船橋市民俗芸能調査報 |
| ▲ | |
| 第51巻 第2号 (1991年3月刊) | |
| 史苑の窓 | |
| 荒野 泰典 | 一人ひとりの卒業式 |
| 論文 | |
| 荒 敬 | 占領期における非軍事化と武装解除 ―特に「占領軍の刀狩り」を中心として― |
| 富岡 政治 | 近世中津川村における生業と林野利用-土地利用からみた生活領域- |
| 書評と紹介 | |
| 西川 杉子 | 今井宏編『世界歴史大系 イギリス史2近世』 |
| 村井 早苗 | 立教女学院 『天皇制を考える』 短期大学公開講座 編 |
| 海外だより | |
| 大木 毅 | 留学の記 |
| 武田 朝子 | クウェ−トに留学して |
| 三上 幸治 | アテネ大学に留学して |
| ▲ | |
| 第51巻 第1号 (1991年1月刊) | |
| 史苑の窓 | |
| 石橋 秀雄 | 中国再訪-学会と考察の旅-余話 |
| 論文 | |
| 藤井 智鶴 | 三河ひるわ山山論の展開-私領山論の公儀越訴をめぐって- |
| 岩本 裕子 | 反リンチ運動家アイダ・B・ウェルズ |
| 研究ノート | |
| 原田 正記 | 織田権力の到達-天正十年「上様御札之儀」をめぐって- |
| 書評・紹介 | |
| 田中 定仁 | 上田敏明著『聞き書きフィリピン占領』 |
| 研究会情報 | |
| 林 正子 | 『盈虚集』の七年 |
| 「史苑」総目次(第1巻〜第50巻) | |
| ▲ | |