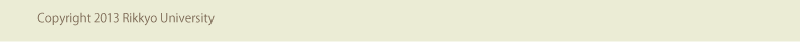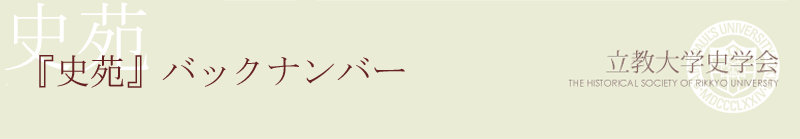
70-2/70-1/
69合併号/
68-2/68-1/
67-2/67-1/
66-2/66-1/
65-2/65-1/ 64-2/64-1/ 63-2/63-1/ 62-2/62-1/ 61-2/61-1/
65-2/65-1/ 64-2/64-1/ 63-2/63-1/ 62-2/62-1/ 61-2/61-1/
| 第70巻 第2号(2010年3月刊) | |
| 史苑の窓 | |
| 野中 健一 | 虹色のヘボ |
| 二〇〇九年度立教大学文学部史学科主催公開講演会 | |
| 荒野 泰典 | 島津氏の琉球出兵四〇〇年に考える―その実相と言説― |
| 報告 | |
| 上原 兼善 | 島津氏の琉球侵略―その原因・経緯・影響― |
| 豊見山 和行 | 敗者の戦略としての琉球外交 ―「唐・大和の御取合」を飼い慣らす― |
| 小峰 和明 | 〈薩琉軍記〉に見る島津氏の琉球出兵 ―日本人はどのように語り伝えてきたか― |
| コメント | |
| 紙屋 敦之 | 歴史学の立場から |
| 渡辺 憲司 | 文学の立場から |
| 渡辺 美季 | フロア発言のための覚書 |
| 目黒 将史 | 〈薩琉軍記〉について |
| 全体討論 | |
| 学会参加記 | |
| 田中 葉子 | 大会参加記 |
| 照沼 麻衣子 | 琉球/沖縄 日本/ヤマト :―緊張と弛緩の関係性― |
| 牟田 俊平 | 琉球出兵に対する新たな視点の発見 |
| 資料 | |
| 論文 | |
| 橋本 佐保 | 「よしの冊子」における寛政改革の考察 |
| 上間 創一郎 | 地域のエートスと組織化 ―沖縄的経営同族主義とその史的背景― |
| 山下 王世 | 現代トルコにおけるコジャテペモスクのデザイン変更 |
| 横島 公司 | 東京裁判の影 ―昭和天皇は何故裁かれなかったのか― |
| 書評 | |
| 朝比奈 新 | 蔵持重裕編『中世の紛争と地域社会』 |
| 香原 志勢 | 野中健一著『昆虫食先進国ニッポン』 |
| リレーエッセイ | |
| 桑山 裕佳子・ 田村 俊行 | 大学院ゼミナール紹介 |
| 小井 高志 | 私の大学院生時代 |
| ▲ | |
| 第70巻 第1号(2009年月12刊 東洋史特集号) | |
| 史苑の窓 | |
| 弘末 雅士 | ミステリアスな現地妻(ニャイ)―インドネシア民族意識の生の母?― |
| 論文 | |
| 設樂 國廣 | ヨーロッパ連合(EU)とトルコ共和国 |
| ヒュリヤー・タシュ (齊藤優子 訳) | 都市と周辺地域とのつながりにおけるアンカラ |
| 中林 広一 | 中国における食芋習俗とその展開 |
| 野口 久美子 | 北米ネイティブ・アメリカン史研究における理論の変遷と模索 |
| 研究ノート | |
| 荒野 泰典 | 近世中期における長崎貿易体制と抜荷(密貿易) ―海禁論の一例証として― |
| 書評 | |
| 仲丸 英起 | 山本信太郎著『イングランド宗教改革の社会史 ―ミッド・チューダー期の教区教会―』 |
| 近藤 祐介 | 長谷川優子著『中近世移行期における村の生存と土豪』 |
| エッセイ | |
| 上田 信 | 私の大学院生時代 |
| 朝比奈 新 | 大学院ゼミナール紹介 日本中世史・蔵持ゼミ |
| 設樂國廣先生の略歴と主要業績 | |
| 二〇〇八年度立教大学史学会大会・総会報告 | |
| ▲ | |
| 第69巻 合併号(2009年3月刊) | |
| 史苑の窓 | |
| 高林 陽展 | ロンドン大学ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドンの博士課程を終えて |
| 論文 | |
| 豊田 雅幸 | 中国の対日戦犯処理政策 ―厳罰主義から「寛大政策」へ― |
| 遠藤 ゆり子 | 生業からみた村落 ―近世前期における上野国緑埜郡三波川村の考察― |
| 倉橋 圭子 | 科挙エリートの再生産 ―統計的分析の試み― |
| 上間 創一郎 | 観光化と社会的統合 ―近現代日沖関係史の一視点― |
| 長谷川 裕子 | 紛争裁定にみる戦国大名権力の特質 ―分国法・裁判文書の検討を通じて― |
| 研究ノート | |
| 荒野 泰典 | 近世の日本において外国人犯罪者はどのように裁かれていたか? ―明治時代における領事裁判権の歴史的前提の素描― |
| 堀内 厚平 | 青方覚念関係相論の一考察 ―青方覚念と有河性心の相論について― |
| 矢島 初穂 | 水田からサトウキビ畑への転換に見られる人間と生き物との関係の変化 ―沖縄北部地区の事例を中心に― |
| 書評 | |
| 徳永 裕之 | 蔵持重裕著『声と顔の中世史 ―戦さと訴訟の場景より―』 |
| 中林 広一 | 胎中千鶴著『葬儀の植民地社会史 ―帝国日本と台湾の〈近代〉』 |
| 山本 信太郎 | 青柳かおり著『イングランド国教会包括と寛容の時代』 |
| リレーエッセイ | |
| 設樂 國廣 | 私の大学生時代 |
| 安田 千恵美 | 大学院ゼミナール紹介 日本近世史・荒野ゼミ |
| 二〇〇七年度立教大学史学会大会・総会報告 | |
| ▲ | |
| 第68巻 第2号(2008年3月刊) | |
| 史苑の窓 | |
| 設樂 國廣 | アンカラ概略史 |
| 論文 | |
| 森 仁志 | 「民族」の根拠に関する一考察 ―多民族社会ハワイにおけるエスニシティの名乗 りと名指しを事例として― |
| 長谷川 修一 | イエフによるヨラムとアハズヤ殺害主張の背景 ―歴史叙述的観点から― |
| 研究のノート | |
| 田中 彩貴 | 和田町における小型沿岸捕鯨の展開とその観光化 ―商業捕鯨モラトリアム以後の 動向を中心として― |
| 書評 | |
| 胎中 千鶴 | 上田信著『風水という名の環境学 気の流れる大地』 |
| 新刊紹介 | |
| 矢島 初穂 | 野中健一著『虫食む人々の暮らし』 |
| リレーエッセイ | |
| 野中 健一 | 私の大学院生時代 |
| 田中 彩貴 | 大学院ゼミナール紹介 |
| 論文 | |
| 高田勝 ・ 野中健一 | Indigenous Pigs Growing on Nora Land in Okinawa, Japan |
| 野中 健一 | Nora'- Land-space where a harmonious relationship exists between humans and nature |
| ▲ | |
| 第68巻 第1号(2007年11月刊) | |
| 史苑の窓 | |
| 小野沢 あかね | 「世間話」から歴史学へ |
| 論文 | |
| 茶谷 誠一 | 二・ 二六事件後の宮中勢力 |
| 加藤 鉄三 | シカのふるまい、ジリスの声 ―環境史における史料・認識・記述― |
| 加藤 拓 | 沖縄陸軍特攻における「生」への一考察 ―福岡・振武寮の問題を中心に― |
| 研究ノート | |
| 黒田 康弘 | 戦前日本における空襲への認識 |
| 書評 | |
| 豊田 雅幸 | 粟屋憲太郎『東京裁判への道』 |
| 近江 吉明 | 小井高志『リヨンのフランス革命―自由か平等か―』 |
| 2006年度立教大学史学会大会・総会報告 | |
| ▲ | |
| 第67巻 第2号(2007年3月刊) | |
| 史苑の窓 | |
| 豊田由貴夫 | 地名が変わる日 |
| 論文 | |
| 岩田 晋典 | アフロ・スリナム人女性の肖像 ―スリナム共和国の黒人ミス・コンテストが目指すもの― |
| 太田 久元 | 国際連盟脱退後における海軍の対外戦略構想―一九三三年を中心に― |
| 研究ノート | |
| 中村 茂生 | ブラジル日本人移民の学校教育をめぐって ―サンパウロ州バストスの「尋常小学校」(一九二九年から一九三三年まで)― |
| 大塚 直樹 | ベトナム土地法にみる農地使用権とその特徴 ―二〇〇三年土地法の改正点をめぐって― |
| ▲ | |
| 第67巻 第1号(2006年12月刊) 日本史特集号 | |
| 史苑の窓 | |
| 蔵持 重裕 | 人と土地の構図 |
| 論文 | |
| 田中 禎昭 | 「諸国校田」の成立 ―延喜民部省式班田手続き規定の歴史的意義 |
| 石井 輝義 | 律令陵墓制の特質について ―陵戸の考察を通じて― |
| 関口 功一 | 上毛野穎人について |
| 研究ノート | |
| 宮瀧 交二 | 日本古代民衆史研究と菅原道真「寒早十首」 |
| 新刊紹介 | |
| 大塚 直樹 | モナ・アハメド(文)、ダヤニタ・シン(写 真・序文)/関根光宏(訳) 『インド 第三の性を生きる―素顔のモナ・アハメド』 |
| 野田嶺志先生の略歴と主要業績 | |
| ▲ | |
| 第66巻 第2号(2006年3月刊) 西洋史特集号 | |
| 史苑の窓 | |
| 中田 潤 | 西洋史研究と地域社会 |
| 論文 | |
| 山中 秀人 | パラツキーの国家理念 −一九世紀ボヘミアのチェコネイション形成における思想− |
| 加藤 鉄三 | ミューアの夢の追求 ―シエラ南部の国立公園拡大運動、一九一五年〜一九四〇年 |
| 小西 公大 | 「トライブ」に関するヒストリオグラフィーのポリティクス ―ゴーヴィンドギリのバガット運動を事例として |
| 書評 | |
| 増山 智宏 | 藤木久志・蔵持重裕編『荘園と村を歩く II』 |
| 新刊紹介 | |
| 白坂 直子 | オズワルド・デ・リベロ著(梅原弘光訳) 『発展神話の仮面を剥ぐ―グローバル化は世界を豊かにするのか?−』 |
| 田中 葉子 | 貴志俊彦・荒野泰典・小風秀雅編 『「東アジア」の時代性』 |
| 史学会会員の研究・教育活動報告 | |
| 青木 道彦 | オクスフォード大学の市民講座に参加して |
| 黒川康先生の略歴と主要業績 | |
| ▲ | |
| 第66巻 第1号(年月刊) | |
| 史苑の窓 | |
| 桑田 和明 | 中世宗像氏と宗像社について |
| 論文 | |
| 安達 宏昭 | 「大東亜建設審議会」と「経済建設」構想の展開 ―「大東亜産業(鉱業、工業及電力)建設基本方策」を中心に― |
| 茶谷 誠一 | 関屋貞三郎の政治思想と政治活動 ―牧野グループ理解への一考― |
| 柳 芝娥 | 米軍の南朝鮮進駐と韓日米側の対応(一九四五年を中心に) |
| 中林 広一 | 中国におけるソバについて |
| 研究ノート | |
| 中尾 裕子 | 口裂け女は、妖怪か |
| 新刊紹介 | |
| 中川 岳夫 | Kurita, Kazuaki, Connections between the Nyakyusa and the Nkonde from the viewpoint of dance and trade: With Video data of dances |
| 史学会会員の研究・教育活動報告 | |
| 2005年度立教大学史学会大会・総会報告 | |
| ▲ | |
| 第65巻 第2号(2005年3月刊) 地理学特集号 | |
| 史苑の窓 | |
| 栗田 和明 | インド、シムラにて |
| 論文 | |
| 岩田 晋典 | スリナム奴隷解放記念日における黒人のエスニシティ ―文化団体ナックスの活動とその自己認識― |
| 市川 哲 | マレーシアにおける都市再開発と華人墓地 ―マラッカおよびクアラルンプールの華人墓地保存論争― |
| 宮内 洋平 | 定期市の社交・娯楽的機能の定量分析 ―タンザニア農村部・盛り場の考現学― |
| 黒田 康弘 | 大正デモクラシーから昭和ファシズムへ ―民主主義は民衆にどこまで浸透したか― |
| 野口久美子 | インディアン再組織法案審議に見るインディアン・アイデンティティの多様性 ―インディアン議会議事録の検討をてがかりに― |
| 研究ノート | |
| 八幡 綾 | 寺院への奉仕のもつ意味と「伝統」を継承するということ ―門前町ナートドワーラーの絵師集団の事例より― |
| 小松原秀信 | インド社会の邪視に関する諸研究レヴュー |
| 小西正捷先生の略歴と主要業績 | |
| ▲ | |
| 第65巻 第1号(2004年11月刊) | |
| 史苑の窓 | |
| 深津 行徳 | ハワイにて |
| 論文 | |
| 中村 哲子 | 中世在地途名の位置づけと変遷 ―中世前期から惣村の成立へ― |
| 及川 将基 | 日露領土交渉のなかの「是迄仕来」―条約文の解釈と領土観― |
| 安達 宏昭 | 「大東亜建設審議会」と「経済建設」構想 ―「大東亜経済建設基本方策」の形成をめぐって― |
| 設樂 國廣 | 第二次立憲体制期の政治動向 |
| 柴野 浩樹 | 元首政期のローマ軍制におけるプリンキパレスとインムネス |
| 大野 邦晴 | マラウィ共和国における公共交通の利用と運営 ―ゾンバのミニバスを事例として― |
| 書評 | |
| 久礼 克季 | 東南アジアにおける仲介者の「連続性」と「変化」 弘末雅士著『世界歴史選書 東南アジアの港市世界 ―地域社会形成と世界秩序』 |
| 大塚 直樹 | 栗田和明著『マラウィを知るための45章』 を読む |
| 2004年度立教大学史学会大会報告 | |
| ▲ | |
| 第64巻 第2号(2004年3月刊) 地理学特集号 | |
| 史苑の窓 | |
| 小西 正捷 | 追憶の建築群 |
| 論文 | |
| 関 恒樹 | 低地フィリピン社会における主体・エイジェンシー・アイデンティティ ―個に内在する力としてのドゥガンdunganの観念に注目して― |
| 永井 博子 | フィ リピン村落工業における開発の失敗 ―人類学的視点からの試論 |
| 白坂 直子 | スハルト政権期の観光開発 ―五ヵ年開発計画の分析を中心に― |
| 山本早 良紗 | スチとスブル―バリ島におけるケガレの実態的考察 |
| 松田 松男 | 最近のわが国における清酒流通の変容に関する一考察 |
| 酒井 順子 | シティーの日系金融コミュニティでのオーラル・ヒストリー調査 ジェンダー・クラス・エスニシティの交差点での「ナラティヴ」の分析と叙述 |
| 近江 吉明 | カボシャン蜂起勃発前夜の動き |
| 研究ノート | |
| 森川 真樹 | パキスタン国イスラマバードにおけるスラム・スクォッター地区開発の動向について |
| 書評 | |
| 大橋 里見 | 西川 杉子著『ヴァルド派の谷へ―近代ヨーロッパを行きぬいた異端者たち』 |
| 新刊案内 | |
| 田中 麻美 | 梅原 弘光(編)『グローバリゼーション下の東南アジアの社会変容と地域変化』 [科研報告書、英文] |
| 梅原 弘光先生の略歴と主要業績 | |
| 梅原 弘光 | 最終講義 フィリピン農村研究四〇年 |
| ▲ | |
| 第64巻 第1号(2003年11月刊) | |
| 史苑の窓 | |
| 黒川康 | ドイツ政党本部回遊の記 |
| 論文 | |
| 青柳かおり | イングランド国教会と便宜的国教徒防止法 |
| 八幡綾 | 西イ ンドの門前町、ナートドワーラーの絵師集団 |
| ―慣習的交換関係の変容― | |
| 増山智宏 | 中世修験道本山派形成過程の再検討 |
| 黒田基樹 | 十五・十六世紀徳政論序説 |
| 研究ノート | |
| 今野春樹 | 江戸極初期における下駄の変容 ―一六世紀末から一七世紀初頭において― |
| 川崎晴朗 | 築地外国人居留地の「予備地」 ―米国聖公会が入手するまで― |
| 書評 | |
| 遠藤ゆりこ | 藤井譲治著『幕藩領主の権力構造』 |
| 二〇〇三年度立教大学史学会大会報告 | |
| ▲ | |
| 第63巻 第2号(2003年3月刊) | |
| 史苑の窓 | |
| 上田 信 | 戦争と歴史家 |
| 論文 | |
| 鈴木 信昭 | 朝鮮粛宗三十四年描画入り『坤輿萬國全圖』攷 |
| 古川 麻紀 | 民国期中国の外米輸入とそれをめぐる諸問題 ―アジア交易論と中国― |
| 林 正子 | 民衆が見た植民地征服戦争・台湾 ―『風俗画報』と『点石斎画報』を中心に― |
| 胎中 千鶴 | 植民地台湾の死体と火葬をめぐる状況 |
| 研究ノート | |
| 陳 梅卿 | 代打者 ―台湾神父 涂敏正― |
| 石橋秀雄先生・戴國煇先生の略歴と主要著作目録 | |
| ▲ | |
| 第63巻 第1号(2002年11月刊) | |
| 史苑の窓 | |
| 栗田 和明 | 特定の地域と年代をはなれて |
| 論文 | |
| 岩本 洋光 | 太平洋戦争期における日本軍のラバウル占領統治 ―日本側の認識とその実態― |
| 遠藤 正之 | 十五〜十六世紀におけるチャム人の移住と活動に関する一考察 ―カンボジアの事例を中心として― |
| 大橋 里見 | 十八世紀イギリスにおける競売 |
| 研究ノート | |
| 安達 宏昭 | 高校における近現代史教育の試み |
| 聶 長順 | 森有礼の教育改革と儒教主義 ―森有礼と元田永孚・西村茂樹との交渉を通して― |
| 書評 | |
| 山本信太郎 | 近藤和彦編『長い十八世紀のイギリス その政治社会』 |
| 小西 正捷 | 麻田豊監訳・露口哲也訳注 N・A・チシュティー 『パンジャーブ生活文化誌―チシュティーの形見―』 |
| 二〇〇二年度立教大学史学会大会報告 | |
| 石橋秀雄先生・戴國�W先生追悼 東洋史特集号 | |
| ▲ | |
| 第62巻 第2号(2002年3月刊) | |
| 史苑の窓 | |
| 松下 洋巳 | 妻の直感―古代中国男性論試索― |
| 論文 | |
| 関 恒樹 | マリア・カカオと黄金の船 ―フィリピン・ビサヤ海域社会における口頭伝承の生成― |
| 森 仁志 | 伝統の創造とそのプロセス ―ハワイの食文化の事例から― |
| 研究ノート | |
| 阿諏訪 青美 | 東寺の借用状 |
| 細井 岳登 | 射和文庫における運営の基盤と財源 |
| 赤野 孝次 | 福沢諭吉像の研究史的変遷 |
| 松田 松男 | 高校地理B授業実践報告 ―「空間的視点」と「地域的視点」を柱として― |
| 友廣 純 | アウグスティヌスの説教をめぐって |
| 特別寄稿 | |
| 小関 昌男 | 大久保利謙先生をかこんで |
| 二〇〇一年度立教大学史学会秋季特別企画シンポジウム報告 | |
| ▲ | |
| 第62巻 第1号(2001年11月刊) | |
| 史苑の窓 | |
| 林 英夫 | 遠い日の出来事 ―軍事教員を殴打した事件― |
| 論文 | |
| 増田 昭子 | 南会津における祝儀・不祝儀の「野菜帳」 |
| 山本信 太郎 | 16 世紀ラドロウにおける都市と教区 ―イングランド宗教改革史研究の前提として― |
| 遠藤ゆ り子 | 執事の機能からみた戦国期地域権力 ―奥州大崎氏における執事氏家氏の事例をめぐって― |
| 市川 哲 | マ レーシアおよびシンガポールの華人社会の宗教的シンクレティズム再考 |
| 末永 信義 | ナチ占領期チェコにおけるゲルマン化構想(1939〜1941) |
| 小論 | |
| 山田 昭次 | 扶桑 社出版中学歴史教科書『新しい歴史教科書』の諸問題 ―とくにその日本国家への献身物語について― |
| シンポジウム報告 | |
| 西尾 寛治 | 近世 ムラユ港市国家と海民 |
| 重松 伸司 | 南イ ンド・バッキンガム運河史序説 ―海陸連結ルート・商品・交易― |
| 2001年度立教大学史学会大会・総会報告 | |
| ▲ | |
| 第61巻 第2号(2001年3月刊) | |
| 史苑の窓 | |
| 野田 嶺志 | 入鹿と女帝 |
| 論文 | |
| 西願 広望 | 総裁政府期から帝政末期までの仮病、公務員買収等による徴兵逃れ ―表面上の合法性を求める、しかし実は非合法な徴兵逃れ― |
| 水井 万里子 | 近世イギリスのすず産業 |
| ―すず先買制導入期(一五九五年〜一六〇七年)を中心に― | |
| 黒田 基樹 | 戦国大名権力と在地紛争 ―農村における立 山・立林― |
| 磯田 和秀 | 記憶の「生々しさ」について ―沖縄戦を想起するふたつの方法― |
| 研究ノート | |
| 川崎 晴朗 | 築地居留地に来た最初の宣教師 |
| 執行 一利 | 農村開発と村落社会の政治学 ―スリランカY村の共同墓地移転問題― |
| 二〇〇〇年度立教大学史学会秋季特別企画シ ンポジウム総合テーマ 海域ネットワークと地域世界 | |
| ▲ | |
| 第61巻 第1号(2000年11月刊) | |
| 史苑の窓 | |
| 青柳 まち子 | 国勢調査と人種・民族の分類 |
| 論文 | |
| 市川 哲 | 同郷会館の国際化と現地化 ―シンガポール及びマレーシアの福建会館を事例として― |
| 長谷川 裕子 | 戦国期畿内周辺における領主権力の動向とその性格 ―近江国坂田郡箕浦の今井氏を事例として― |
| 申 東珪 | オランダ人漂流民と朝鮮の西洋式兵器の開発 |
| 研究ノート | |
| 楚山 智大 | ローマ帝政前期、「使節制度」に関する近業 をめぐって ―ガブリエーレ・ツイ-テン『皇帝と元老院のへの使節』の紹介を中心に― |
| 荒野 泰典 | 東アジアの発見-「世界史の成立」と日本人 の対応 |
| 研究ノート | |
| 荒野 泰典 | 綱引きする「戦争責任」 ―オランダのある新聞記事をめぐって― |
| 書評 | |
| 鵜月 裕典 | 松村 赴・富田虎男編著『英米史辞典』 |
| 二〇〇〇年度立教大学史学会大会・総会報告 | |
| 活動報告 | |
| 野田 嶺志 | 日本歴史学協会・日本学術会議等について |
| ▲ | |