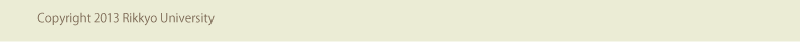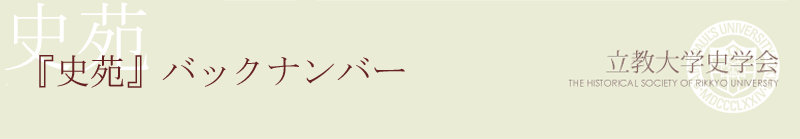
80-2/80-1/
79-2/79-1/
78-2/78-1/
77-2/77-1/
76-2/76-1/
75-2/75-1/ 74-2/74-1/ 73-2/73-1/ 72-2/72-1/ 71-2/71-1/
75-2/75-1/ 74-2/74-1/ 73-2/73-1/ 72-2/72-1/ 71-2/71-1/
| 第80巻 第2号(2020年3月) | |
| 史苑の窓 | |
| 四日市康博 | 声と色から読み解く歴史文書学 : イランのモンゴル帝国期命令文書から |
| 特集1 日本中世の「地下」社会 : 薗部寿樹の文書論と春田直紀の生業論から考える | |
| 佐藤雄基 | 趣旨説明 : 付・報告要旨 |
| 冨善一敏 | 薗部寿樹『日本中世村落文書の研究 : 村落定書と署判』から考えたこと : 近世(文書管理)史の側からみて |
| 朝比奈新・熱田順 | 書評・春田直紀『日本中世生業史論』 |
| 寺田浩明 | 生業の権利化の視点から |
| 特集2 グローバルヒストリーと中世ヨーロッパ(2)ドイツ語圏の視点 | |
| 小澤実 | 序 |
| ボルゴルテ・ミヒャエル 訳:井上周平 | ヨーロッパの一神教と中世における文化の一体性の問題 |
| ボルゴルテ・ミヒャエル 訳:井上周平 | 中世ヨーロッパ史とグローバルヒストリー : 諸々の経験と展望 |
| 小澤実・諫早庸一 | ウィーン発の中世グローバルヒストリー : ヨハネス・プライザー=カペラー博士連続講演会 |
| 小澤実 | 中世グローバルヒストリーの潮流 |
| 立教大学史学会大会特集報告 近代ヨーロッパにおけるナショナリズムとキリスト教 | |
| 井出匠 | 趣旨説明 |
| 大澤広晃 | 植民地主義・ナショナリズム・キリスト教 : 一九世紀末〜二〇世紀前半の南アフリカにおけるアフリカ人を中心に |
| 村田奈々子 | ギリシア・トルコ強制的住民交換と正教徒のアイデンティティ |
| 加藤久子 | コメント1 |
| 鶴見太郎 | コメント2 近代ヨーロッパにおけるナショナリズムとキリスト教 |
| 追悼 | |
| 中田潤 | 黒川先生との思い出 |
| 蔵持重裕 | 藤木久志先生ありがとうございました。 |
| 伊香俊哉 | 粟屋憲太郎先生の研究を振り返って |
| 書評 | |
| 小野寺拓也 | 山室信一・岡田暁生・小関隆・藤原辰史編『われわれはどんな「世界」を生きているのか : 来るべき人文学のために』 |
| 中村江里 | 後藤基行著『日本の精神科入院の歴史構造 : 社会防衛・治療・社会福祉』 |
| 仲丸英起 | 青木康著『歴史総合パートナーズ(2)議会を歴史する』 |
| 村田光司 | 高田英樹(編訳)『原典中世ヨーロッパ東方記』 |
| ▲ | |
| 第80巻 第1号(2020年2月) | |
| 史苑の窓 | |
| 栗田和明 | フィールドワークを深めるもの |
| 特集 グローバルヒストリーと中世ヨーロッパ(1)イギリスの視点 | |
| 小澤実 | 序 |
| キャサリン・ホームズ (訳 小澤実) | グローバルな中世:問題とテーマ |
| マレク・ヤンコヴィアク (訳 小澤実) | 奴隷のためのディルハム:9・10世紀のイスラーム世界と北ヨーロッパ間の奴隷交易 |
| チャールズ・バーネット (訳 阿部晃平・小澤実) | 12世紀ルネサンス |
| 小澤実 | 「グローバルな中世」から「中世のゾミア」へ:オックスフォードの中世グローバルヒストリー |
| 川戸貴史 | 海のゾミアとして倭寇をみる |
| 学生教員座談会 | |
| ジュンク堂書店池袋店特別企画 | 「立教大学文学部書店」から史学科の学びへ |
| 応答 | |
| 宮紀子 | 諫早庸一「書評 宮紀子『モンゴル時代の「知」の東西』」 |
| 書評 | |
| 梅原秀元 | エディス・シェファー著(山田美明 訳)『アスベルガー医師とナチス 発達障害の一つの起源』 |
| 見市雅俊 | 竹内真人 編『ブリティッシュ・ワールド−帝国紐帯の諸相』 |
| 青木康 | 君塚直隆 著『ヨーロッパ近代史』 |
| 新刊紹介 | |
| 赤松淳子 | 中田元子 著『乳母の文化史−19世紀イギリス会社に関する一考察』 |
| ▲ | |
| 第79巻 第2号(2019年5月) | |
| 史苑の窓 | |
| 佐藤雄基 | 日本中世史は何の役に立つのか |
| 立教大学史学会大会特集 13〜14世紀海域アジア・ユーラシア史特集 | |
| 四日市康博 | 緒言 |
| 高銀美 | 日本・高麗との交易事例からみた元の対外政策 |
| 徳留大輔 | 陶磁器から見た海域アジア ―13世紀から14世紀の事例をもとに |
| 諫早庸一 | 天文学から見たユーラシアの13世紀〜14世紀 ―文化の軸としてのナスィール・アッディーン・トゥースィー(1201〜1274年) |
| 桃木至朗 | 東南アジアから見たモンゴル帝国期海域アジア交流と13〜14世紀の分水嶺 |
| 四日市康博 | 総論に代えて モンゴル帝国=元朝の覇権から見た13〜14世紀の諸相 |
| 小特集 歴史学のアウトリーチ | |
| 牧田義也 | 歴史・記録・記憶 ―歴史実践と路上のアクチュアリティ |
| 大谷哲 | インターネット歴史学コンテンツと社会への発信 ―「せんだい歴史学カフェ」の活動より |
| 論文 | |
| 渡邉剛 | 黒板勝美とエスペラント ―歴史家における「言語」と「民族」の発見― |
| 公開講演会 | |
| アルバン・ゴティエ 井上みどり(訳) 小澤実(解説) | シャルルマーニュの食卓にて ―カロリング期ヨーロッパにおける飲食 |
| 書評 | |
| 諫早庸一 | 宮紀子『モンゴル時代の「知」の東西』 |
| ▲ | |
| 第79巻 第1号(2019年3月) | |
| 史苑の窓 | |
| 弘末雅士 | 「変な外人」が社会を動かす? |
| 公開講演会 | |
| 弘末雅士 | 東南アジア史研究を振り返る ―地域研究と交流史研究― |
| 論文 | |
| 久礼克季 | 台湾鄭氏とジャワ |
| 東條哲郎 | マレー半島ペラにおける華人錫鉱業とシンガポール ―世紀転換期における生産・流通を中心に |
| 工藤裕子 | スマランの華人運動 ―20世紀初頭の新組織と指導者層の分析から― |
| 坪井祐司 | 1930年代のマラヤのマレー・ナショナリズムからみたインドネシア |
| 菅原由美 | 東南アジアにおけるイスラームの展開とキターブ文献の成立 |
| 山口元樹 | アラブ地域の定期刊行物が構築するネットワークと東南アジアのムスリムの仲介者 ―カイロの雑誌『ファトフ』を事例として― |
| 書評 | |
| 相澤淳 | 太田久元著『戦間期の日本海軍と統帥権』 |
| 朝比奈新 | 遠藤ゆり子著『中近世の家と村落 ―フィールドワークからの視座―』 |
| 内田雅克 | A・コルバン、J-J・クルティーヌ、G・ヴィガレロ監修『男らしさの危機? ―20-21世紀』 |
| 川瀬貴也 | 小澤実編『近代日本の偽史伝説 ―歴史語りのインテレクチュアル・ヒストリー』 |
| 菊池雄太 | P・ドランジェ著(高橋理監訳)『ハンザ 12-17世紀』 |
| 弘末雅士先生の略歴と主要業績 | |
| ▲ | |
| 第78巻 第2号(2018年4月) | |
| 史苑の窓 | |
| 浦野聡 | 歴史学と人間科学 |
| 論文 | |
| 沼尻晃伸 | 戦後改革期〜一九五〇年代における都市住民の水利用と自治体 : 三島市(静岡県)を事例として |
| 公開講演会 | |
| 幸村誠 | 漫画でつなぐ、中世北欧と現代日本 |
| 研究ノート | |
| 我彦武範 | 足利義満執政前期における公家領安堵の特質 |
| 調査報告 | |
| 村田光司 | トロス司教座聖堂発掘報告(二〇一六) : 出土貨幣及び封鉛について |
| 書評 | |
| 牧田義也 | 平体由美・小野直子編『医療化するアメリカ : 身体管理の二〇世紀』(彩流社、二〇一七年三月) |
| 新刊紹介 | |
| 佐藤 雄基 | 黒岩康博『好古の瘴気 : 近代奈良の蒐集家と郷土研究』(慶応義塾大学出版会、二〇一七年) |
| 佐藤雄基 | 松田敬之『〈華族爵位〉請願人名辞典』(吉川弘文館、二〇一五年) |
| 深津行徳 | 関周一 編『日朝関係史』(吉川弘文館、二〇一七年) |
| ▲ | |
| 第78巻 第1号(2018年2月) | |
| 史苑の窓 | |
| 青木康 | 一八世紀イギリスの市議会の「出席簿」 |
| 公開講演会 | |
| 青木康 | 一八世紀イギリスの名望家支配と地域社会 : サフォーク州のジェントリ デイヴァーズ家の事例を通して |
| 論文 | |
| 青柳かおり | イングランド国教会とアン女王基金 |
| 大橋里見 | 一七八八年の「不況」とロンドン・ジェネラル・ホールの設立 : 展望と利害をめぐるとブリテン木綿産業の「攻防」 |
| 鹿野美枝 | イギリス下院における「インド予算」の登場 |
| 高林陽展 | 正気と狂気のあいだ : コルニー・ハッチ精神病院火災事件(一九〇三年)の表象をめぐって |
| 中込さやか | イングランドのミドルクラス向け女子教育と家庭科関連科目群 : マンチェスタ女子ハイ・スクールのカリキュラムと生徒層 一八九四-一九一四 |
| 仲丸英起 | ミッド・テューダー期イングランド下院議員の選出様態 : 選挙区移動の数量的分析 |
| 正木慶介 | フォックス晩餐会 : ホイッグ党の政治観 |
| 水井万里子 | イギリス東インド会社の地域産業救済 : コーンウォル産鉱物資源の中国輸出(一八世紀後半〜一九世紀初頭)をめぐって |
| 山根明大 | 『イングランド王国の繁栄』における経済思想 : 個人と国家の利潤動機という観点から |
| 山本信太郎 | エドワード六世治世初年のロンドンにおけるフランス国王フランソワ一世の葬儀 |
| 学会動向 | |
| 大和久悌一郎 | 修正主義以降の第一次大戦期イギリス社会史 |
| 書評 | |
| 桜井万里子 | 浦野聡編 『古代地中海の聖域と社会』 (勉誠出版、二〇一七) |
| 小林麻衣子 | 山根明大著 『コモンウェルスの政治思想史 : エリザベス一世期の政治的イングランド意識』 (立教大学出版会、二〇一七年) |
| 宝月理恵 | 高林陽展著 『精神医療、脱施設化の起源 : 英国の精神科医と専門職としての発展1890-1930』 (みすず書房、二〇一七年) |
| 小澤実 | 海老澤衷・近藤成一・甚野尚志編 『朝河貫一と日欧中世史研究』 (吉川弘文館、二〇一七年) |
| 渡邉 剛 | Yoshikawa, Lisa, Making History Matter : Kuroita Katsumi and the Construction of Imperial Japan (Harvard University Asia Center, 2017) |
| 青木康先生の略歴と主要業績 | |
| ▲ | |
| 第77巻 第2号(2017年3月) | |
| 史苑の窓 | |
| 松原宏之 | 人は「歴史する」、ゲームでもアニメでも |
| 研究ノート | |
| 七條めぐみ | アムステルダムの楽譜出版者エティエンヌ・ロジェ(1665/66―1722)再考 |
| 研究動向 | |
| 高橋裕子 | ギリシアにおける初期鉄器時代の遺跡(2)レフカンディ |
| 立教大学史学会大会特集報告 近世近代移行期の海域世界と国家 | |
| 弘末雅士 | 序 |
| 越村勲 | アドリア海の海賊ウスコクから見た近世の国家形成 |
| 鈴木英明 | インド洋西海域周辺諸社会における近世・近移行期とその矛盾――奴隷制・奴隷交易の展開に着目して―― |
| 木村直也 | 日朝関係の近代的変容と境界領域 ―明治維新期の対馬を中心に― |
| 荒野泰典 | コメント |
| 書評 | |
| 柿沼陽平 | 上田信『貨幣の条件 タカラガイの文明史』(筑摩選書) |
| 遠藤啓之 | 遠藤ゆり子著『戦国時代の南奥羽社会 ‐大崎・伊達・最上氏』 |
| 神野潔 | 亀田俊和著『ミネルヴァ日本評伝選 足利直義 ―下知、件の如し―』 |
| 亀田俊和 | 呉座勇一著『一揆の原理』『戦争の日本中世史』『応仁の乱』 |
| 新刊紹介 | |
| 大泉惟 | 阿部珠理編『アメリカ先住民を知るための62章』 |
| 戸村紀子 | 後藤雅知・吉田伸之編『古文書でよむ千葉市の今むかし』(崙書房出版) |
| 史料紹介 | |
| 居阪僚子、 村田光司、 仲田公輔 | コンスタンティノス7世ポルフュロゲネトス『帝国統治論』第9章に関する研究動向と日本語訳 |
| 論文 | |
| Yuki Kontani (紺谷由紀) | Castration as medical treatment ; the Miracles of St. Artemios and Paul of Aegina |
| ▲ | |
| 第77巻 第1号(2016年12月) | |
| 史苑の窓 | |
| 上田信 | 「クレオパトラの鼻」について |
| 論文 | |
| 高橋未來 | 制作過程から見る西南戦争錦絵―薩軍征討令と表象の変化― |
| 松元賢次郎 | 戦争責任を問うた教師たちー『戦争教育の記録運動』、その始まりと展開ー |
| 調査報告 | |
| 松崎哲也 | トロス司教座聖堂から出土した動物遺存体(二)―2015年度調査の概報 |
| 特集 外国史家が読み解く『近代日本のヒストリオグラフィー』 | |
| 小澤実 | 序 |
| 松沢裕作 | 『近代日本のヒストリオグラフィー』の意図と達成 |
| 菊地重仁 | 近代日本における/にとってのヨーロッパ中世研究―ドイツ歴史学界との関わりから― |
| 小山哲 | 「史学史」の線を引き直す―ヒストリオグラフィーにおける「近代」をどう捉えるか |
| 岸本美緒 | 近代東アジアの歴史叙述における「正史」 |
| 講演 | |
| 桃木至朗 | 新しい世界史叙述と歴史学入門を目指して〜阪大史学系の取り組みから〜 |
| 書評 | |
| 一ノ瀬佳也 | 坂本優一郎著『投資社会の勃興 財政金融革命の波及とイギリス』 |
| 鴨野洋一郎 | 斯波照雄・玉木俊明編『北海・バルト海の商業世界』(悠書館、二〇一五年) |
| 長谷川貴彦 | 青木康編『イギリス近世・近代史と議会制統治』 |
| 内田力 | 室井康成『首塚・胴塚・千人塚―日本人は敗者とどう向きあってきたのか』 |
| 阿部珠理 | 野口久美子著『カリフォルニア先住民の歴史 「見えざる民」から「連邦承認部族」へ 』 |
| ▲ | |
| 第76巻 第2号(2016年4月) | |
| 史苑の窓 | |
| 後藤 雅知 | 「あてんほう」考 |
| 論文 | |
| 林田 直樹 | 王位継承排除危機におけるイングランド・スコットランド同君連合 ―王位継承排除法案(Exclusion Bill)の審議過程の分析を通じて― |
| 学会動向 | |
| 高橋 裕子 | ギリシアの初期鉄器時代に関する調査および研究動向 2010〜2014年 |
| 調査報告 | |
| 浦野 聡 | トロス主教座聖堂発掘報告(2015) ―考古学・建築上の知見から― |
| 立教大学史学会大会特集報告 近代の構成原理 ―イギリス、アメリカ、日本における組織、倫理、専門知 | |
| 松原 宏之 | 序 |
| 長谷川貴彦 | 「底辺」からの産業革命 ―長い18世紀イングランドの中間団体と貧民 |
| 松原 宏之 | 医療、福祉、社会運動の領域で ―20世紀初頭ニューヨークの訪問看護婦たち |
| 宝月 理恵 | 規律、実践、習慣化 ―戦前・戦時期日本における《咀嚼する主体の主観性》をめぐる試論― |
| 高林 陽展 | 後期フーコーと近代史研究のこれから |
| 公開講演会 | |
| ディディエ・カーン 訳 小澤 実 | 中世・初期近代錬金術における変成と宗教 |
| 坂本 邦暢 | 愛は世界を動かす ―前近代宇宙論における神、知性、天球 |
| 書評 | |
| 室井 康成 | 清水克行著『耳鼻削ぎの日本史』 |
| 丸山 浩明 | 東栄一郎著(飯野正子監訳)『日系アメリカ移民 二つの帝国のはざまで ―忘れられた記憶 1868−1945』 |
| 山根 明大 | 小林麻衣子著『近世スコットランドの王権―ジェイムズ6世と「君主の鑑」』 |
| 大谷 哲 | ジョン・G・ゲイジャー編(志内一興訳)『古代世界の呪詛版と呪縛呪文』 |
| 新刊紹介 | |
| 河西 英通 | 山岡道男他著『朝河貫一資料集』 |
| 史料紹介 | |
| 向井 伸哉 斎藤 史朗 佐藤 雄基 | 朝河貫一とマルク・ブロックの往復書簡 ―戦間期における二人の比較史家― |
| ▲ | |
| 第76巻 第1号(2015年12月) | |
| 史苑の窓 | |
| 鵜月 裕典 | 研究生活を振り返って |
| 論文 | |
| 青木 康 | 議会改革運動創成期イギリスの都市自治体と下院議員選挙 ―1760年代末サマセット州ブリジウォータ市の事例― |
| 鹿野 美枝 | 小ピット政権期イギリスのインド政策 ―ヘンリ・ダンダスの影響力、1783-93年 |
| 野口久美子 | インディアン再組織法再考 ―部族主義の起源として― |
| 研究ノート | |
| 佐藤 円 | ポカホンタスによるスミスの助命論争 ―再考― |
| 木野 淳子 | 青年期のジョン・アレクサンダー・マクドナルド ―アッパーカナダの反乱をめぐる一考察 |
| 川島 正樹 | 「米兵は鬼畜ではなかった」のか ―沖縄戦をめぐる記憶の共有を目指して― |
| シンポジウム 宗教改革の伝播とトランス・ナショナルな衝撃 ―宗教改革500周年に向けて | |
| 加藤 喜之 | 序 |
| ケネス・G・アッポルド 訳 井上 周平 | 宗教改革のグローバルな理解にむけて |
| 踊 共二 | 日本の宗教改革史研究―過去・現在・未来 |
| 書評 | |
| 齊藤 邦明 | 沼尻晃伸著『村落からみた市街地形成 ―人と土地・水の関係史 尼崎1925-75年』 |
| 林 みどり | 弘末雅士編『人喰いの社会史 ―カンニバリズムの語りと異文化共存』 |
| ▲ | |
| 第75巻 第2号(2015年3月) | |
| 史苑の窓 | |
| 青木 康 | イギリス人の歴史好きと周年事業 |
| 論文 | |
| 鶴島博和 | ヨーロッパ形成期におけるイングランドと環海峡世界の「構造」と展開 |
| 研究ノート | |
| 松岡昌和 | 「昭南島」における漫画家松下紀久雄 ―「文化人」の南方認識の一事例 |
| グリザッド・ アコマトベコワ | 社会体制変化に伴う「観光」の変容 ポスト社会主義国キルギスにおける温泉施設利用者のライフヒストリー調査 |
| 立教大学史学会大会特集報告 ユーラシア東西における古文書学の現在 |
|
| 佐藤雄基 | 序 |
| 菊地重仁 | 初期中世ヨーロッパ政治史への「文書形式学的」アプローチ ―定型表現の形成・変遷とその意義について |
| 佐藤雄基 | 日本中世前期の文書様式とその機能 ―下文・奉書の成立を中心にして |
| 川西裕也 | 高麗の国家体制と公文書 |
| 四日市康博 | ユーラシア史的視点から見たイル=ハン朝公文書 ―イル=ハン朝公文書研究の序論として |
| 高橋一樹 | 総括コメントにかえて |
| 調査報告 | |
| 浦野 聡 | トロス司教座聖堂発掘報告(二〇一四) ―考古学・建築上の知見から |
| 村田 光司 | トロス司教座聖堂発掘報告(二〇一四) ―出土貨幣及び封緘について |
| 松崎 哲也 | トロス司教座聖堂から出土した動物遺存体 |
| 師尾 晶子 | トロス司教座聖堂出土碑文の概要(五) 二〇一四年度の発掘から |
| 奈良澤 由美 | トロス司教座聖堂出土の装飾石材について 二〇一三年度および二〇一四年度の発掘から |
| 公開講演会 | |
| ゲオルク・シュトラック (訳:菊地重仁) 解説:小澤実 | 教会「改革」から宗教「改革」へ ―盛期・後期中世における教皇権 |
| 大谷哲・井上周平 清水領・鈴木俊弘 | 第64回日本西洋史学会大会優秀ポスター賞受賞記念講演 |
| 書評 | |
| 大貫俊夫 | ジャイルズ・コンスタブル(高山博監訳) 『12世紀宗教改革 修道制の刷新と西洋中世社会』 |
| 田村俊行 | Catherine Lee, Policing prostitution, 1856-1886 |
| ▲ | |
| 第75巻 第1号(2015年1月) 日本中世史特集号 | |
| 史苑の窓 | |
| 蔵持重裕 | 中世初期の村のこと |
| 論文 | |
| 長塩智恵 | 院政期に於ける斎王選考の問題 |
| 朝比奈 新 | 中世伊勢神宮領にみられる多元的支配権の性格―大福寺・摩訶耶寺間本末訴訟を通してー |
| 徳永裕之 | 備中国上原郷の「半済」について |
| 窪田涼子 | 如法経信仰をめぐる財と村落─近江国蒲生郡を中心として |
| 増山智宏 | 中世後期における地方寺院の本末関係と在地領主 |
| 若林陵一 | 中世後期加賀国倉月荘・越中国般若野荘にみえる村と社会の枠組 |
| 遠藤ゆり子 | 戦国時代における田村領の「熊野山新宮年貢帳」と村落 |
| 深谷幸治 | 江戸時代前期の村落による大仙陵古墳利用とその環境 |
| 調査報告 | |
| クラウディア・テデスキ (訳、米倉立子) | トロス、ビザンティン聖堂の床モザイクにおける保存措置手法の報告 (二〇一三) |
| 書評 | |
| 蔵持重裕 | 上田信『シナ海域 蜃気楼王国の興亡』 |
| 青木 康 | 近藤和彦『イギリス史10講』 |
| 小林一岳 | 佐藤公実『中世イタリアの地域と国家』 |
| 鶴岡賀雄 | ヒロ・ヒライ、小澤実編 『知のミクロコスモス―中世・ルネサンスのインテレクチュアル・ヒストリー』 |
| 久礼克季 | 弘末雅士編『越境者の世界史―奴隷・移住者・混血者』 |
| 蔵持重裕先生の略歴と主要業績 | |
| ▲ | |
| 第74巻 第2号(2014年) | |
| 史苑の窓 | |
| 丸山浩明 | アマゾンと日本移民 |
| 研究ノート | |
| ドナシメント・アントニー | 第二次世界大戦前のブラジルにおける日本移民制限の動向 ―「レイス法案」をめぐる論争の多角的検討 |
| 野中健一、菅野祥一郎 | "山に逃げろ"となぜ言えた? ―東日本大震災直後の気仙小学校校長の状況判断と意思決定の背景を探る |
| 特集記事 | |
| 小澤実 | 序文 |
| 石野裕子 | 独立フィンランドにおける自国史の「創造」 |
| 藤波伸嘉 | ギリシア東方の歴史地理―オスマン正教徒の小アジア・カフカース表象 |
| 千葉功 | 歴史と政治―南北朝正閏問題を中心として |
| 石井規衛 | 比較史学史の可能性について |
| 調査報告 | |
| 浦野聡 | トロス司教座聖堂発掘報告(二〇一三)―考古学・建築上の知見から― |
| 村田光司 | トロス司教座聖堂発掘報告(二〇一三)―出土貨幣及び封緘について |
| 師尾晶子 | トロス司教座聖堂出土碑文の概要(四)二〇一三年度の発掘から |
| 公開講演会 | |
| H・ダレル・ラトキン(訳:菊地重仁) | ヨ―ロッパ史のなかの占星術 中世・ルネサンスから近代へ |
| 小澤実 | 解説 |
| ▲ | |
| 第74巻 第1号(2014年1月) | |
| 史苑の窓 | |
| 桜井万里子 | トゥキュディデスと史料 |
| 論文 | |
| 遠藤正之 | カンボジア・オランダ東インド会社間通商平和条約締結(1656〜1657年) ―カンボジア王権とオランダ東インド会社の交易独占の試みをめぐって |
| 大泉惟 | オーウェン・ラブジョイの職業教育論 ―雇用対策と民主主義 |
| 研究ノート | |
| 池田嘉郎 | 『社会運動史』覚書き |
| 書評 | |
| 朝比奈新 | 佐藤雄基著『日本中世初期の文書と訴訟』 |
| ▲ | |
| 第73巻 第2号(2013年3月) | |
| 史苑の窓 | |
| 小澤実 | 二宮隆洋さんのこと |
| 研究ノート | |
| 萩原史明 | 清海鎮大使張保皐と在唐新羅人居留地の関係について ―泗州漣水県を中心に― |
| 立教大学史学会大会 特集報告 近世・近代の地域社会 | |
| 後藤雅知 | 林産物の生産と輸送 ―近世房総の養老川水運を例に― |
| 小松賢司 | 藩領村役人にとっての城下町 |
| 大川啓 | 明治期の都市火災と地域社会 ―地方都市秋田を事例として― |
| 小野沢あかね | 講評 |
| 調査報告 | |
| 浦野聡・ 深津行徳 | トロス司教座聖堂発掘報告(2012)―建築上の所見を中心に |
| 田中咲子 | トロス司教座聖堂発掘報告(2012)―聖堂装飾(レリーフ、フレスコ)を中心に |
| 師尾晶子 | トロス司教座聖堂出土碑文の概要(3) 2012年度の発掘から |
| シンポジウム | |
| 小澤実 | 公開シンポジウム 「人知の営みを歴史に記す 中世・初期近代インテレクチュアル・ヒストリーの挑戦」報告記 |
| 論文 | |
| 大橋里見 | Auctioneers in Provincial Towns in England and Wales at the End of the Eighteenth Century |
| ▲ | |
| 第73巻 第1号(2013年1月刊) 荒野泰典教授退職記念号 | |
| 史苑の窓 | |
| 荒野泰典 | オランダ語講座のこと ─専門基礎言語と専門基礎(通称「蘭ゼミ」)の二〇年─ |
| 献辞 | |
| 上田信 | |
| 荒野泰典先生の略歴と主要業績 | |
| 荒野泰典先生最終講義 | |
| 荒野泰典 | 近世国際関係論と私 ─立教の二七年─ |
| 論文 | |
| 牟田俊平 | 一四世紀末から一六世紀初頭における琉朝関係の推移 |
| 及川将基 | 近世蝦夷漂着者とアイヌ・松前藩 −一七世紀〜一八世紀を中心に− |
| 安田千恵美 | 「女今川」成立考 ─女子用往来の写本と刊本─ |
| 橋本佐保 | 完成改革期における小普請組の制度改革 |
| 上白石実 | 明治維新期旅券制度の基礎的研究 |
| 書評 | |
| 及川将基 | 荒野泰典・石井正敏・村井章介編『日本の対外関係七 近代化する日本』 |
| 資料の窓 | |
| 荒野泰典 | 幕末維新期日米条約の原本調査 ─米国々立文書館での調査とその成果─ |
| 論文翻訳 | |
| ジョン・E・ウィルス jr.(訳:荒野泰典研究室オランダ語中級ゼミ) | |
| 一七世紀および一八世紀の中国・台湾・バタヴィアにおける東インド会社と中国人 | |
| ▲ | |
| 第72巻 第2号(2012年3月刊) | |
| 史苑の窓 | |
| 高尾千津子 | ユーラシア・ユダヤ史をめぐる断章 |
| 論文 | |
| 野口久美子 | インディアン再組織法の矛盾: トュールリヴァー先住民保留地における「家畜協会」設立の理念と現実 |
| 立教大学史学会大会報告 | |
| 末永雅洋 | イナゴの採集と調理活動 ―福島県中央部を事例として― |
| 田村俊行 | 一九世紀イギリスの売春統制 ―伝染病法の制定過程と「臣民の自由」 |
| 安田千恵美 | 近世女性を巡る書物と「女書」 |
| 特集 中世史研究の現状と課題 | |
| 朝比奈新 | 山城国禅定寺荘の領域画定と地域 |
| 五十嵐大介 | 一四世紀末〜一六世紀初頭エジプトにおける土地制度の展開 ―ワクフ(寄進)地の拡大とその影響― |
| 小澤実 | 紀元千年紀スカンディナヴィアにおける土地所有を巡る一考察 |
| 蔵持重裕 | 講評 |
| 調査報告 | |
| 浦野聡 | トロス司教座聖堂発掘報告(二〇一一) ―建築上の所見を中心に |
| 田中咲子 | トロス司教座聖堂発掘報告(二〇一一) ―聖堂装飾遺物を中心に |
| 師尾晶子 | トロス司教座聖堂出土碑文の概要(二) ―二〇一一年度の発掘から |
| 書評 | |
| 上田信 | 倉橋圭子著『中国伝統社会のエリートたち ―文化的再生産と階層社会のダイナミズム』 |
| 田中葉子 | 上白石実著『幕末の海防戦略 ―異国船を隔離せよ』 |
| 矢森小映子 | 荒野泰典・石井正敏・村井章介編『日本の対外関係六 近世的世界の成熟』 |
| ▲ | |
| 第巻72 第1号(2011年12月刊) 西洋史特集号 | |
| 史苑の窓 | |
| 沼尻晃伸 | 住宅政策と国家―その歴史的性格 |
| 論文 | |
| 菅原未宇 | イングランドにおけるグラマ・スクール設立の動向 −一一五〇〜一六六〇− |
| 青木康 | 一七五〇年代ベリ・セント・エドマンズ市の下院議員選挙 ベリの都市自治体を巡る補論 |
| 深沢克己 | 一八世紀フランスの知的エリートとフリーメイソン ―マルセイユの医師アシャールの内面的軌跡― |
| 近江吉明 | ベッレームにおける一七八九年の食糧蜂起 |
| 史料紹介 | |
| 高橋裕子 | ギリシアにおける初期鉄器時代の遺跡 アテネのアゴラ |
| 学会動向 | |
| 佐藤公美 | アンドレア・ガンベリーニ(佐藤公美 訳・解説) 「中世後期ロンバルディア農村地域における領主領民紛争 ―レッジョの事例から―」 |
| 書評 | |
| 林倬史 | 栗田和明『アジアで出会ったアフリカ人−タンザニア人交易人の移動とコミュニティ』 |
| 岩本裕子 | 青柳まちこ『国勢調査から考える人種・民族・国籍 ―オバマはなぜ「黒人」大統領と呼ばれるのか―』 |
| 水口幹記 | 荒野泰典・石井正敏・村井章介編『日本の対外関係1東アジアの世界の成立』 |
| 小井高志先生の略歴と主要業績 | |
| ▲ | |
| 第71巻 第2号(2011年3月刊) | |
| 史苑の窓 | |
| 山下王世 | トルコ共和国で活躍した外国人建築家 |
| 立教大学史学会大会報告 | |
| 木下純平 | 喫茶の伝播と変遷 ―イスタンブルを事例として― |
| 横島公司 | カイザー訴追問題を巡る民間側の認識 ―判事選任問題を手がかりに― |
| 辻本諭 | 王政復古期イングランドにおける軍隊の宿営問題 |
| 特集 現代史研究の課題と方法 | |
| 明田川融 | 沖縄基地問題と「密約」 |
| 鈴木勇一郎 | 戦時下のキリスト教学校 ―「青山学院昭和一八年事件」をめぐって― |
| 沼尻晃伸 | 水辺と生活から見た都市史研究の方法 |
| 荒野泰典 | 論評 |
| 論文 | |
| 浦野聡 | トロス司教座教会聖堂の発掘について |
| 研究ノート | |
| 深津行徳 | 都市と祭祀空間 −二〇一〇年度トロス遺跡聖堂遺構予備発掘調査報告− |
| 師尾晶子 | トロス教会聖堂出土碑文の概要 |
| 書評 | |
| 倉敷伸子 | 小野沢あかね著『近代日本社会と公娼制度 ―民衆史と国際関係史の視点から―』 |
| 名村優子 | 丸山浩明編著『ブラジル日本移民 百年の軌跡』 |
| ▲ | |
| 第71巻 第1号(2010年12月刊 粟屋憲太郎教授退職記念号) | |
| 史苑の窓 | |
| 小田部雄次 | 東京裁判研究、もう一つの流れ |
| 特集 粟屋憲太郎先生 立教大学退職記念講演 | |
| 粟屋憲太郎 | 粟屋健太郎先生の略歴と主要業績 |
| 弘末雅士 | 献辞 |
| 粟屋憲太郎 | 一研究者の回顧 |
| 粟屋憲太郎 | 連合国は東京裁判で何をさばき、何を裁かなかったか |
| ゼミの思い出 | |
| 宮崎章 | 一九七六年・粟屋ゼミのスタート |
| 中里則之 | 粟屋先生との二五年 |
| 吉次公介 | 一九九〇年代の粟屋ゼミ |
| エッセイ | |
| 小林元裕 | 中国の経済発展と歴史認識 |
| 論文 | |
| 柳芝娥 | 第二次大戦後における南朝鮮の国防計画 ―挑戦国軍準備隊の活動と米国の国防計画― |
| 黒田康弘 | 時流への抵抗と限界 ―ある高等小学校長の昭和― |
| 書評 | |
| 梅原弘光 | 永井均 著『フィリピンと対日戦犯裁判一九四五−一九五三年』 |
| ▲ | |