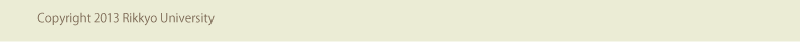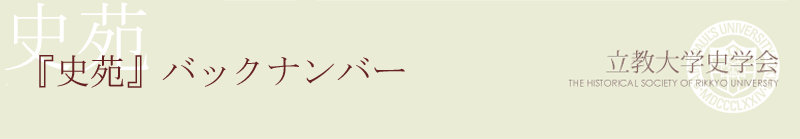
| 第85巻 第2号 (2025年3月)
講集団から見る日本文化の変化と再生産 | |
| 史苑の窓 | |
| 中森弘樹 | 「蒸発」は想像を喚起する――Les évaporés du Japonをめぐって |
| 研究ノート | |
| 王子奇 | 近年新見のソグド語史料紹介と考察―文化受容と宗教信仰の視点から |
| 特集1 立教大学史学大会特集報告 講集団から見る日本文化の変化と再生産 | |
| 市田雅崇 | 趣旨説明 |
| 浅川泰宏 | コロナ禍の聖年―2020年~2023年の調査から― |
| 乾賢太郎 | 京浜地区における海苔養殖と木曽御嶽講―生業と信仰に関連して― |
| 井上卓哉 | 俵札をめぐる信仰活動の一形態としての伊勢参詣―新潟県妻有地域に残された道中記から― |
| 笠井賢紀 | 栗東市の街道筋集落にみる左義長と伊勢講 |
| 高木大祐 | コメント 講研究の現在と現代への接続 |
| 特集2 | |
| 佐藤二葉、小澤実、大谷哲 | 歴史の現場に聞く!佐藤二葉『アンナ・コムネナ』・アニメ『ヴィンランド・サガ』・歴史考証 |
| 座談会 | |
| 荒井雅子、大西信行、小川幸司、佐藤雄基 | 歴史学と歴史教育の新たな協力を目指して(続)日本史と世界史をつなぐ |
| 書評 | |
| 庄嫣婷 | 向正樹『クビライと南の海域世界』大阪大学出版会、2024年 |
| 新刊紹介 | |
| 岡村茜 | 朝比奈新『荘園制的領域支配と中世村落』吉川弘文館、2024年 |
| 第85巻 第1号 (2025年1月)
グローバルヒストリーと中世ヨーロッパ(3) | |
| 史苑の窓 | |
| 寺尾美保 | 博物館の展示と研究 |
| 論文 | |
| 谷望 | 安政の改革における軍制改革−幕府海軍における塩飽水主の登用過程から− |
| 浦野聡、小岩直人、深津行徳、長谷川敬、イスマイル・ベイタク、オズデミル・コチャク | Two Approaches in a Preliminary Archaeological Survey of Polybotos (Dura Yeri – Hacı Murat) prior to the Excavation |
| 特集1 グローバルヒストリーと中世ヨーロッパ(3)インド洋と世界システム論 | |
| 小澤実 | 序文 |
| フィリップ・ボジャール(佐藤彰一・村田光司訳) | 鉄器時代に想定される3つの世界システムから単一のアフロ・ユーラシア世界システムへ |
| フィリップ・ボジャール(佐藤彰一・村田光司訳) | 16世紀以前のユーラシア・アフリカ世界システムにおけるインド洋 |
| 特集2 中世初期ヨーロッパの出自神話 | |
| ヴァルター・ポール(飯尾圭司・加納修訳) | 中世初期ヨーロッパにおける「出自神話」の意義 |
| ヘルムート・ライミッツ(加納修訳) | 起源の窃取―中世初期フランク王国におけるローマの過去の摂取― |
| 加納修 | 訳者解説 |
| 特集3 梅原先生追悼特集 | |
| 丸山浩明 | 梅原弘光先生のご逝去を悼む |
| 大塚直樹 | 梅原弘光先生を偲んで |
| 弘末雅士 | 書評:梅原弘光『スペインはなぜフィリピンを占領したのか? 群島占領・植民地支配・住民の抵抗』(書籍工房早山、2023年) |
| 第84巻 第2号 (2024年2月)
日本近世の生業・暮らしと文化的景観/戦争に向かう世界 | |
| 史苑の窓 | |
| 高林陽展 | 感情史という実験場 |
| 論文 | |
| 大西信行 | 胡惟庸・林賢事件についての歴史叙述-洪武年間の日明関係を理解するために |
| 青木康 | イギリス近代政党制の形成-ホイッグ党と 1780年代前半の政治危機- |
| 今井麻美梨 | アンテベラム期アメリカ合衆国における他者の痛みへの共感−L・M・チャイルドの『母親の本』にみる体罰論の変化と人道主義運動− |
| 特集1 立教大学史学大会特集報告 日本近世の生業・暮らしと文化的景観 | |
| 後藤雅知 | 趣旨説明 |
| 武井弘一 | 砺波平野の老農宮永正運の嘆き─近世の稲作をめぐる景観変容− |
| 桐生海正 | 近世山間村落の景観と生業−宝永噴火からの復興過程を中心に− |
| 東幸代 | 琵琶湖の暮らしと文化的景観 |
| 中尾俊介 | 神奈川宿青木町の生業と景観─町場と湊・山林の関係を中心に− |
| 多和田雅保 | コメント 所有の観点をふまえた生業論・景観論 |
| 特集2 朝河貫一生誕 150周年記念シンポジウム「戦争に向かう世界:1930年代と朝河貫一」 | |
| 佐藤雄基 | 趣旨説明 |
| 福田康夫 | 開会挨拶 |
| ダニエル・ボツマン 早川聖司 訳 | 基調講演 朝河貫一と日系アメリカ人-C・ヤナガとの関係を中心に |
| 陶波 | 1930年代のキリスト教ネットワークと日米関係 |
| 増井由紀美 | 1930年代のアメリカ美術と朝河貫一 |
| 討論 戦争に向かう日米関係と朝河貫一 | |
| 第84巻 第1号 (2024年1月)
古代地中海世界における人々の移動とネットワーク(2) | |
| 史苑の窓 | |
| 小澤実 | 2023年リーズ国際中世学会に参加して |
| 論文 | |
| 亀田俊和 | 佐藤進一の将軍権力二元論再論−東島誠からの批判への応答を中心として− |
| 山根明大 | 「マープレリト書簡」と16世紀末イングランドの主教制度を巡る論争 |
| 研究ノート | |
| 濱田浩一郎 | 鎌倉時代の夢について−『吾妻鏡』を題材にして− |
| 謝弘睿 | 明代の使節賜宴と宴使礼 |
| 特集 古代地中海世界における人々の移動とネットワーク(2)−Identity, Ethnicity, Acculturation− | |
| 青木真兵 | 新ポエニ語碑文から見る複数のポエニ文化とその利用 |
| 師尾晶子 | エーゲ海を往来したフェニキア人−シドンの商人の活動を中心に− |
| 史料紹介 | |
| 石井規衛 訳 | P.N. ミリュコーフ「ポクロフスキーの偉大さと没落(ソ連における学術史上の一エピソード)」 |
| 第83巻 第2号 (2023年3月)
世界史特集 | |
| 史苑の窓 | |
| 深津行徳 | |
| 特集1 立教大学史学大会特集報告 世界史における「学知」の政治的ダイナミクス | |
| 浦野聡 | 序 |
| 王尊龍 | 近世琉球における学知の構造転換−明・清皇帝への表文を手がかりに− |
| 大塚修 | ティムール朝における学芸保護と学知−イスカンダル・スルターンの『傑作集』を中心に− |
| 梅原秀元 | 科学的な精精神医学とナチ期の強制断種・「安楽死」 −エルンスト・リュディン(1874−1952)をめぐって− |
| 小森真樹 | 兵器化する科学主義−両論併記で「天地創造」を科学する博物館− |
| 岸本美緒 | 王報告・大塚報告へのコメント |
| 宇山智彦 | 梅原報告・小森報告へのコメント |
| 総合討論 | |
| 特集2 古代地中海世界における人々の移動とネットワーク(1)−Identity, Ethnicity, Acculturation− | |
| 佐藤育子 | 序 |
| 長谷川岳男 | 「移動」から見る古代ギリシア社会 |
| 佐藤育子 | 古代地中海世界におけるフェニキアの宗教の発展と変容 |
| 宮嵜麻子 | ローマ帝国形成期コルドゥバの「ローマ人」 |
| 書評 | |
| 大西信行 | 歴史学会編『歴史総合 世界と日本』(戎光祥出版、2022 年) |
| 第83巻 第1号 (2023年1月)
天草灘かくれキリシタンの世界 | |
| 史苑の窓 | |
| 小野沢あかね | 日本軍「慰安婦」問題と性売買 |
| 論文 | |
| デイビッド・ロフ 鶴島博和 訳註 | 交易地から市場都市へ−コングルトンのバラの起源− |
| 特集 天草灘かくれキリシタンの世界:松浦家文書から見た生業、交易、島嶼ネットワーク | |
| 小澤実 | 序 |
| 鶴島博和 | 天草灘とキリシタン−海からの視点− |
| 児島康子 | 幕府における寛政期と文化期の天草の位置付け |
| 中園成生 | 生月島かくれキリシタンの生業と信仰 |
| 木村直樹 | 長崎からみた天草−分断と連帯− |
| 中山圭 | 考古学、モノ資料の視点からみた潜伏キリシタン資料 |
| 座談会 | |
| 大西信行 竹田和夫 横井成行 佐藤雄基 | 歴史学と歴史教育の新たな協力を目指して 過去に学び、未来を考える |
| 書評 | |
| 大江満 | 藤本大士『医学とキリスト教−日本におけるアメリカ・プロの医療宣教』 |
| 第82巻 第2号 (2022年3月)
14世紀の危機 | |
| 史苑の窓 | |
| 市田雅崇 | 鵜はどこへ飛んで行く:鵜祭と変わりゆく伝統 |
| 論文 | |
| 李暁璐 王尊龍訳 | 宮内庁蔵『万国絵図屏風』人物図考 |
| 研究ノート | |
| 増渕美穂・石倉香鈴 | 「母親」たちはなぜ「座り込み」をしたのか:一九七八年の豊島園場外馬券売場反対運動 |
| 立教大学史学会大会特集報告 人権と向き合う現代世界:権力と人権をめぐる現代人類史・誌的省察のために | |
| 浦野聡 | 序 |
| 梶谷懐 | 中国社会と普遍的価値の困難性:監視社会と功利主義 |
| 小野仁美 | イスラーム家族法とフェミニズム:チュニジアの相続規定をめぐる多様な立場 |
| 飯尾唯紀 | ハンガリーのイリベラル政権と教会:学校教育への余波を中心に |
| 橋本栄莉 | 南スーダンの紛争後社会における混成的秩序:強制移動民の生活世界と「ものごとの国家的秩序」 |
| 司会: 上田信 松原宏之 | 総合討論 |
| 特集 14世紀の危機:研究の現在 | |
| 四日市康博 | 序 |
| 中塚武 | 樹木年輪古気候学の現状と課題:バレリー・トロエ『年輪で読む世界史』 |
| 宇野伸浩 | モンゴル帝国初期の気候変動:白石典之『モンゴル帝国の誕生』 |
| 西村陽子 | 中国史に関連する古気候研究の現状と課題:葛全勝等『中国歴朝気候変化』 |
| 長瀬篤音 | 中東史への気候史の導入とその反応:リチャード・W・ブレット『初期イスラーム期イランにおける綿花・気候・ラクダ』 |
| 諫早庸一 | ユーラシアから考える〈14世紀の危機〉 |
| 第82巻 第1号 (2022年3月)
アフリカの若者の身体/『明治が歴史になったとき』を読む | |
| 史苑の窓 | |
| 梅原秀元 | 二人のシュナイダー |
| 論文 | |
| 松原宏之 | 救貧問題と名望家の再編:ニューヨーク貧民化防止協会(一八一七−一八二三)の盛衰 |
| 研究ノート | |
| 髙橋裕子 | アルゴスのディラスにおけるミケーネ文化崩壊以降の埋葬と社会 |
| 特集 アフリカの若者の身体 | |
| 橋本栄莉 | 序 |
| 橋本栄莉 | 「本物の男」と「複写男」のあいだで:南スーダン紛争後社会における瘢痕とハイブリッドな「男らしさ」 |
| 村津蘭 | 悪霊との情交:西アフリカ、マミワタの憑依におけるペンテコステ・カリスマ系教会の役割 |
| 萩原卓也 | 身体をめぐるまなざしと感覚を基盤とした集団の形成と成形:自転車競技選手として生きるケニアの若者を事例に |
| 特集 『明治が歴史になったとき』を読む | |
| 佐藤雄基 | 『明治が歴史になったとき』の意図と達成:特集の序文として |
| 豊田雅幸 | 大学アーカイブズと大学アカデミズム:教員個人・学術研究を扱う難しさ |
| 寺尾美保 | 史料と史料をめぐる人的ネットワーク:島津家と大久保家の関係から |
| 前田亮介 | 「史学統一」の夢:戦前(一九二三−一九四五)の大久保利謙 |
| 書評 | |
| ヒライ ヒロ | 池上俊一『ヨーロッパ中世の想像界』(名古屋大学出版会、二〇二〇年) |
| 室井康成 | 谷口雄太『〈武家の王〉足利氏:戦国大名と足利的秩序』(吉川弘文館、二〇二一年) |
| 第81巻 第2号 (2021年3月)
今を映すもう一つの歴史記述:偽史・オカルト・歴史実践 | |
| 史苑の窓 | |
| 木村直也 | 新たな歴史研究の視点にふれながら |
| 研究ノート | |
| 佐藤雄基 | 鎌倉幕府政治史三段階論から鎌倉時代史二段階論へ:日本史探究・佐藤進一・公武関係 |
| 特集 今を映すもう一つの歴史記述:偽史・オカルト・歴史実践 | |
| 小澤実 | 序 |
| 室井康成 | 偽書もまた「史料」なりき。 馬部隆弘『椿井文書』に寄せて |
| 長谷川亮一 | 近現代日本における偽作史書とその受容を考えるために:藤原明氏の近業に接して |
| 樋浦郷子 | 「江戸しぐさ」の現代と未来−原田実氏著作を読んで− |
| 高林陽展 | 近現代における超自然信仰と不安のマーケット |
| 小澤実 | オカルト・学知・第三帝国:カーター『SS先史遺産研究所アーネンエルベ』の周辺 |
| 松原宏之 | 歴史学再生のために−歴史実践から考える− |
| 小澤実 | 歴史実践をさかなでに読む:偽史・オカルト・歴史実践 |
| 書評 | |
| 王尊龍 | 岩井茂樹 著『朝貢・海禁・互市−近世東アジアの貿易と秩序−』 |
| 井出匠 | 早坂眞理 著『近代ポーランドの固有性と普遍性−跛行するネイション形成−』 |
| 根占献一 | 桑木野幸司 著『ルネサンス庭園の精神史』 |
| 金澤周作 | 大石和欣 著『家のイングランド−変貌する社会と建築物の詩学』 |
| 藤野裕子 | 上田信 著『歴史総合パートナーズ①歴史を歴史家から取り戻せ!−史的な思考法』 |
| 大和久悌一郎 | 武田尚子 著『戦争と福祉』 |
| 赤嶺淳 | 小川真和子 著『海をめぐる対話 ハワイと日本』 |
| ▲ | |
| 第81巻 第1号(2020年12月)
ルネサンスにおけるテクスト・知識人・政治 | |
| 史苑の窓 | |
| 橋本栄莉 | 奇声が紡ぐ歴史、あるいは「狂人」が照らす真実 |
| 特集 ルネサンスにおけるテクスト・知識人・政治 | |
| 小澤実 | 序 |
| ハラルド・ミュラー (訳 纓田宗紀) | マリアかミネルヴァか ベネディクト派修道院におけるルネサンスの学識 |
| 皆川卓 | 西暦1500年前後の西南ドイツにおける人文主義者、政治と地域的アイデンティティ |
| ゲオルク・シュトラック (訳 渡邉裕一) | 修道士ロベール、イタリアの人文主義者たち、クレルモンの宗教会議(1095年) |
| イェシカ・ノヴァク (訳 阿部ひろみ) | ルネサンス期ロンバルディア地方の学識 「学芸」と政治の間で:ローランド・タレンティのケース |
| 村瀬天出夫 (訳 簗田航) | マ錬金術と終末論 ドイツのパラケルスス主義者 パウル・リンクとその救済史観 |
| 講演 | |
| ヨハネス・プライザー=カペラー (訳 小澤実) | 微生物からみた初期グローバリゼーション:2世紀から8世紀の疫病と帝国の絡み合い |
| 研究ノート | |
| 髙橋裕子 | 初期鉄器時代のミケーネ −埋葬資料の検討− |
| 青木康 | セント・オルバンズ・タバーン・グループとイギリス近代政党制の成立 |
| 史料紹介 | |
| 阿部晃平 | 『ソロモンの哲学書』(Liber de philosophia Salomonis) |
| 書評 | |
| 中川灯里 | 大塚修『普遍史の変貌』 |
| ▲ | |